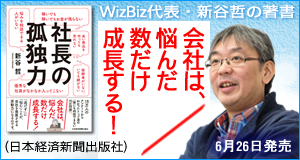2014年11月号より
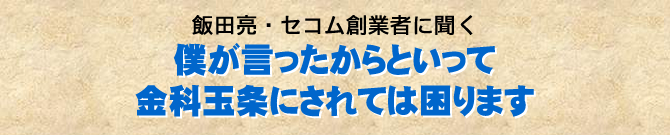

飯田亮・セコム創業者
いいだ・まこと 1933年東京・日本橋に生まれる。56年学習院大学政経学部を卒業し父親の経営する酒類問屋「岡永」入社。62年に日本初の警備会社、日本警備保障(現セコム)を創業し社長に就任。76年会長、97年から取締役最高顧問。
やりたいことをやってきた
―― セコムは警備会社からスタートして、いまではさまざまな分野に進出しています。ところがその結果、事業領域が多岐にわたりすぎて、何の会社か見えにくくなっている。いったいどういう基準で、進出する分野を決めているのですか。
飯田 セコムがどういう会社であったら、自分が満足できるか、あるいは社員などみんなが満足するにはどんな会社であったらいいのか。そういう考えに基づいて会社をつくってきました。だから好きなことだけ、自分の気に入ったことだけをやってきた50年です。
―― 50年前の創業時から、単なる警備会社で終わらないことを決めていたんですか。
飯田 そう。社会が必要とするものすべてをやるという考えでやってきました。
―― ということは、顧客のニーズに応えてきたら、いまの形になったということでしょうか。
飯田 お客さんの言うとおりやってきたらこうなったと言えればいいのだけれど、そう簡単なものではありません。仕事を続けているうちに、これはこういうやり方でやったらもっとうまくできることがわかったり、世の中に欠けているのはこれだ、ということに気づいてそれを埋めてきたようなものです。言い方を換えれば、そういうことができる会社を一生懸命につくってきた。
―― セコムに一貫しているのは自前主義ですね。システムの開発からサービスまで、すべて自分たちで手掛けています。セコム自身がアウトソーシングの会社なのに、自分たちの仕事はアウトソーシングしようとしないところが面白い。
飯田 アウトソーシングしたほうが効率的なところもあるかもしれません。でもそういうことより、自分たちが気に入った姿の会社にしたいと思うとアウトソーシングはできない。
―― でもセコムが成功すると、続々と追随する企業が現れました。その中には、アウトソーシングを活用するなどして、価格を武器に勝負してくる。脅威ではなかったですか。
飯田 脅威には感じました。そっちのほうが効率がいいから。でも自分の気に入った形で、気に入った風土で、仕事をしたいという考えが強かったから変えようがなかったですね。
―― 企業が成長する過程で、セコムは多くの会社を買収してきました。能美防災もセコム損害保険もそうです。このように多くのM&Aを行っていると、必然的に多くの案件が持ち込まれるでしょう。受ける受けないの線引きはどこにあるのでしょう。
飯田 持ち込まれる案件はそんなにあるもんじゃないですよ。ただ、自分の中に会社全体のデザインはそれなりに決まっているから。こういう会社が不足しているなあと思えば、そこで吸収合併しようとかそういう話になります。その場合、仮に時間がかかっても、粘り強く交渉していきます。おかげで能美防災なんかはとてもいい会社になりました。
―― それはセコムの子会社になったからですか。もともとトップ企業だった。
飯田 いえいえ、能美防災自体の素質がよかったんです。もともとシェアもトップでトラディショナルな、いい会社でした。それにさらに磨きがかかって、さらによくなった。あれだけの会社をつくるというのは大変なものだと思います。
―― 逆に失敗したことはありますか。
飯田 失敗例はアメリカのセキュリティ会社を買収したことですよ。結局うまくいかずに、アメリカ本土から撤退した。アメリカのセキュリティビジネスの経営形態は、日本とはまったく違います。小さな会社を買って、少し手を入れて株価を高めて高く売る。その数がまとまれば、結構な金額になる。そういうビジネスなんです。我々とは考えが違いますから、いまは全然手を出す気はないですね。
ただ、考え方としては、やる時は前のめりになってやる。それで失敗しても、仕方がない、また別のことをやればいいんです。
―― 飯田さんの目から見て、いまのセコムに、事業領域で足りないところはありますか。
飯田 少子高齢化に対するシステムですね。いまのセコムの体制に満足しているかというと、答えはノーです。もちろんこれまでも取り組んできましたが、もっと本気にならなくてはいけない分野だと思います。
いままでは、セキュリティの手法で対応しようとしてきました。だけどそれでは追いつかない。ですから、従来の延長線上ではない、新たなシステムをつくり上げなければなりません。普及させるためには、いまよりさらに人数をかけないで、コストももっと安くしていく必要があります。その意味では、当社の取り組みは、ちょっと遅い。
大企業病を防ぐ企業風土
 セコムがモデルになった『ザ・ガードマン』の出演者たちと。
セコムがモデルになった『ザ・ガードマン』の出演者たちと。―― 日本で初めて警備会社にスポットがあたったのが、1964年の東京オリンピックです。セコム(当時は日本警備保障)が会場警備を請け負ったことで、多くの人が知ることになりました。しかもその後、セコムをモデルにしたテレビドラマ『ザ・ガードマン』(65~71年、TBS)によって、警備業が産業として認知されるようになりました。
今年は東京オリンピックからちょうど50年の節目の年です。そして、6年後には東京で2度目のオリンピックが開催されます。50年前同様、セコムがさらにジャンプアップするきっかけになるんではないですか。
飯田 今度のオリンピックは50年前とは規模が全く違います。大会の規模も、企業の規模も、社員の質も違っている。ですから、まったく別なものとして取り組まなければなりません。どうすればいいか、いま経営幹部たちが一生懸命に考えているところです。むずかしいところもあるでしょうけれど、やりがいのある仕事だと思いますね。
―― セコムも誕生から52年です。守りに入ったり、大企業病に陥ってもおかしくない頃です。
飯田 まったくないと言ったら嘘になると思います。ただ、大企業病が奥深くまで浸透しているということはないと思います。
―― 陥らないための方策があるんですか。
飯田 具体的な方策というより、そうならない企業風土をつくることが重要です。創業以来、常に革新する企業カルチャーをつくろうと努力してきました。それが役に立っているのかもしれません。
―― ところで、最近、経営陣や社員に対して怒ったことはありますか。
飯田 全然ないですね。15年ほど前までは怒ってましたけどね。
最近、声がかすれてしまったんですが、医者は冗談で「飯田さん、怒らないから声帯が鍛えられない。それで声が出なくなったんですよ。だからたまには怒ったほうがいいですよ」と言われてます(笑)。
―― どういうことで怒りました?
飯田 細かいことですよ。大きな問題というのは、案外、きちんと対処できるものです。ところが、社員の取り扱いや、お客様の細かいクレームへの対応などは、いい加減になりやすい。例えば、地方の、しかも金額の小さなお客様の場合、時におろそかに扱うこともある。でもそういうことにこそ、企業は敏感にならなければいけません。ここまで細かいことにきちんと対応してきたからいまのセコムがある。だから、その対応がおかしい時など、よく怒っていました。
守ると組織が固くなる
―― 最近、怒らなくなったということは、そういうケースがなくなったということですか。
飯田 僕と同じように考える人が増えてきたということでしょう。
―― 創業者としてはうれしいことですね。
飯田 うれしいですよ。そういう人間を育てようと、創業の時からずっと努力してきましたから。
―― ということは、今後ともセコムには飯田さんの教えが受け継がれていくということですね。
飯田 この8年ほどかけて、僕の仕事を次の人たちに渡してきました。彼らは、創業の頃の考えをよく理解してくれています。
でもだからといって、僕の言ったことを金科玉条のようにとらえて欲しくはありません。セコムには「社会にとって正しいのか」や、「現状打破」といった基本的な考え方があります。それは大事にしてほしいですが、世の中は常に動いている。セコムもそれに対応していかなければなりません。
―― 将来、「これは創業者の教えだから守らなければならない」とは言ってほしくはないと。
飯田 言ってほしくはないですね。人間というのは非常に愚かなものだから、守るとなったら組織が固くなってしまうんです。そうではなく、常に柔らかく、環境に合わせて進化していかなければならないと考えています。
(聞き手=本誌編集長・関慎夫)