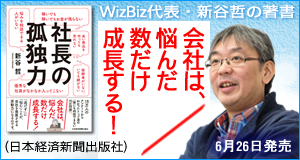2015年1月号より

NHK連続テレビ小説「マッサン」が好調だ。視聴率はここ数年で最も高い。このドラマをより面白くしているのが、堤真一演じる鴨居商店の大将、鴨居欣次郎の存在だ。モデルとなったのは、サントリーの創業者である鳥井信治郞。ドラマの中で鴨居は「やってみなはれ」を連発しているが、これは鳥井の口癖でもあり、サントリーのDNAでもある。米ビーム社の買収や、新浪剛史会長のスカウトなど、いまでもサントリーは世間を驚かせ続けている。これも「やってみなはれ」精神の発露である。
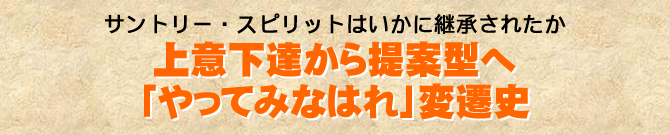
世界一に輝いた「山崎」
『ウイスキー・バイブル』という本がある。世界一のウイスキー評論家とされるジム・マレー氏が毎年出版しているウイスキーのガイド本で、その年に販売されたウイスキーをマレー氏が吟味し評価するものだ。
 世界一となった「山崎」
世界一となった「山崎」そのウイスキー・バイブルの2015年版で、サントリーが発売した「山崎シングルモルト・シェリーカスク2013」が世界最高のウイスキーとして評価された。日本のウイスキーが同書でトップに輝いたのはこれが初めて。国産ウイスキーとしては最高の栄誉を手にしたことになる。
受賞した山崎シェリーカスクは、大阪府にあるサントリー山崎工場で蒸留されたモルトウイスキーを、一度シェリー酒を貯留した樽で貯留したもの。マレー氏はこの「山崎」を、「言葉にできないほど」と最大級に評価、過去最高得点に並ぶ100点満点で97.5点をつけた。
「1990年代に日本を頻繁に訪れたが、その時に素晴らしい蒸留所だと思ったのは白州(サントリー)と余市(ニッカ)で、山崎はOKという評価だった。それがこの5~6年、ぐんぐんと追い上げ、いまや抜きん出てベストに輝いた。製造過程での品質管理や樽を選ぶ厳選された目などが、今回の結果に結びついた」(マレー氏)
山崎工場は、日本に初めて誕生したウイスキー醸造所だ。初代工場長は、現在NHK連続テレビ小説「マッサン」のモデルとなった竹鶴政孝。のちのニッカの創業者だ。同じドラマの登場人物、鴨居商店大将の鴨居欣次郎のモデルであるサントリー創業者の鳥井信治郎がスコットランドでウイスキー造りを学んだ竹鶴を招き、山崎工場を造らせた。
それまで日本で飲まれていたウイスキーは輸入品か、あるいは国産とは謳っていても、合成酒に色と香りをつけてウイスキーらしく味付けしたものばかりだった。山崎工場の完成によって、日本のウイスキー造りが始まった。1924年のことだった。
 世界一となった「山崎」を生んだサントリー山崎工場。
世界一となった「山崎」を生んだサントリー山崎工場。それから90年後に、山崎工場の名を冠したウイスキーが世界一に選ばれた。これはそのまま日本ウイスキーの成長の軌跡でもある。
信治郎がウイスキー造りを決意した時、サントリー(当時は寿屋)の社員はみな反対した。
というのも、ウイスキーは仕込みから出荷まで長い時間がかかる。その間、資金が眠り続ける。当時は「赤玉ポートワイン」の販売が好調だったが、その利益のほぼすべてをウイスキーに継ぎ込むことになる。しかも、そうやって造ったウイスキーが、果たして日本人に受け入れられるかどうかは未知数だった。抵抗するのは当然だ。
そういう時に信治郎が発したのが「やってみなはれ」という言葉だった。
これが信治郎の口癖だった。
「やってみなはれ、やらなわからしまへんで」
 創業者の鳥井信治郎
創業者の鳥井信治郎信治郎は創業社長らしい、天才型の経営者だった。時代の空気に敏感で、何が当たるか見極めることが得意だっただけでなく、自らムーブメントをつくることができた。赤玉ポートワインの販売に際しては広告を最大限活用、さらには日本初のヌードポスターをつくって酒販店に配布したほか、オペラ団を結成し、全国各地を巡回しPRを行っている。アイデアと実行力を兼ね備えていた。
周囲は大変だった。ウイスキー事業に続いて信治郎は買収によりビール事業にも手を出すが、当時の金庫番は「金繰りなんぞ考えんとパッと買うてしもて、わて一人、なんぼ往生したかわかれへん」と嘆いていたという。
信治郎はワインやウイスキー、ビールだけでなく、紅茶やジュース、さらには半練歯磨きにまで手を出した。それに対して社員が抵抗を示すと「やってみなはれ」の言葉が飛んでくる。そして、やるとなったら徹底的に任せてみる。
引き受けたほうも、なんとか期待に応えようと知恵を絞ってやってみると、何かしらの解決策がうまれてくる。結果的には自分が思っていたよりもうまくいくケースも多かった。それによってサントリーの社員は成長し、サントリーの業績も伸びていった。
「やってみなはれ大賞」
 操業間もない頃の山崎工場。
操業間もない頃の山崎工場。「やってみなはれ」という言葉が一般的に知られようになったのは、1969年に発行されたサントリー70年史によるところが大きい。この70年史は、文章と写真集の2冊からなる豪華本で、文章は、ともにサントリー宣伝部に勤めていた、直木賞作家の山口瞳と、芥川賞作家の開高健が執筆するという、なんとも贅沢なものだった。この70年史のタイトルが「やってみなはれ、みとくんなはれ」だった。これによって「やってみなはれ」は、サントリーの社風として一般的に認知されることになった。
そしてこの精神は、いまもサントリーに根付いている。ただし、信治郎の時代と現代とでは、大きな違いがひとつある。
「『やってみなはれ』は、未知の分野に挑戦する姿勢を表したものですが、創業者の時代は、上意下達でした。信治郎が決めて、社員を説得するために使われた。ところがいまは違います。下から提案されたものに対して、責任と権限を与えて任せる。社員の自主性を尊重する『やってみなはれ』になっているのです」(サントリー幹部社員)
つまり同じ言葉でも意味が大きく変わっている。そうなったのは2代目社長の佐治敬三の時代だった。
「佐治は、上意下達ではいかん、現場からいろんな提案が沸き立つように出てこなければならない、と考えていた。上はリスクを取ってやらせてみる。だから佐治はよく、『やってみなはれ、やらせてみなはれ』と言っていました」(同)
佐治敬三自身も、父・信治郎の時代に一度頓挫したビール事業へ再参入を決めるなど、リーダーシップを発揮して新規分野に挑戦する経営者だったが、同時に、サントリーがさらなる成長を果たすためにも、社員がいきいきと働く活気あふれる会社にすることが必要だと考えた。そこで「やってみなはれ」の方向転換を目指したのだ。
それが、いまに続くサントリーのDNAとなっている。
 2代社長の佐治敬三(中央)と3代社長の鳥井信一郎(右)、左は宮崎緑さん。
2代社長の佐治敬三(中央)と3代社長の鳥井信一郎(右)、左は宮崎緑さん。サントリーの経営のバトンは、創業者の信治郎から、次男の佐治敬三へ、敬三から、信治郎の長男・富太郎の長男である鳥井信一郎へ、信一郎から、敬三の長男の佐治信忠現会長、そしてローソンから招いた新浪剛史社長へと引き継がれている。そして「やってみなはれ」精神も、経営者が代わろうとも、そのまま引き継がれているという。
企業のDNAの継承は意外とむずかしい。創業者やその苦労を間近に見てきた人間がいる間はいいのだが、そうした人たちがいなくなると、途端に風化し始める。言葉として伝えていくのは簡単だが、中身が伴っていなければ、伝わっていないのと同様だ。
「やってみなはれ」は、前述のように未知の分野に挑戦する姿勢である。これはすなわちベンチャースピリットに他ならない。サントリーの企業規模が小さいうちは、チャレンジしなければ生き残ることさえむずかしかった。しかしいまやサントリーは売上高2兆円を超える巨大企業である。事業領域も酒類だけでなく食品や飲料、医薬・健康食品まで多岐にわたる。
こうなると、ベンチャースピリットを持ち続けるのは至難だ。何より新入社員は、大企業としてのサントリーを志望して入った人たちばかりだ。この社員に、創業期と同じようなチャレンジ精神を持てといっても無理がある。といって、それをほうっておけば、あっという間に大企業がはびこり、企業は衰退へと向かってしまう。
それを防ぐこと、すなわちいつの時代になっても「やってみなはれ」精神を貫くことが、サントリーの歴代経営者に課せられた責務だった。
佐治会長などは常日頃から、「『やってみなはれ』は薄めてはならない」と口を酸っぱくして言っており、人材の採用や教育、そして評価制度などにも挑戦意識を高める工夫がされている。たとえば人事評価の中には「挑戦するか・しないか」の項目があり、重視されている。
次稿では、「角ハイボール」や「ザ・プレミアム・モルツ」といった、サントリーのヒット商品を生む際に、「やってみなはれ」精神がどのように活かされたかを紹介している。
その登場人物をはじめとしたサントリー社員が口を揃えるのが、「仕事にも慣れてくると、知らぬうちにマンネリになる。それをそのままにしておくと、決まって、なんで挑戦しないんだ! と怒られる」ということだ。しかも失敗しても、同じ失敗でないかぎり、再挑戦のチャンスが与えられる。何度も何度も失敗しながら、懲りることなく新しいビジネスに挑戦し、事業を成功に導いた社員も珍しくない。
その結果として、サントリーでは「挑戦しないことは悪」という風土が出来上がった。
「仕事を現状の延長線上で考えていると、よく上司から『小さくまとまってるんじゃないよ』と言われます。こう言われることで、自分の中で守りに入っていることに気づかされます」(若手社員)
サントリーらしいと思うのは、社内表彰制度として「やってみなはれ大賞」があることだ。これは、社内から上がってきた提案を、「いままでにない発想かどうか」「どうチャレンジし、どう壁を乗り越えたか」などといった視点から評価し、表彰するというもの。この制度ひとつとっても、サントリーが「やってみなはれ」に対して誇りを持つと同時に、その維持に最大限の努力をしていることがよくわかる。
2つのサプライズ
ただし、「やってみなはれ」だからといって、何が何でも挑戦すればいいというわけではない。当然のことながら、提案が退けられることもある。
「通らなかった提案に共通するのは、考え方が甘かったり、一歩踏み込みが足りないケースが大半です。要するに、新しいことをやりたいなら、とことん考えろということです。そうした点を練り直したうえで、本人のどうしてもやりたいとの熱意が伝われば、上司としても応援したくなる。それがうまくいかない場合でも、本人が必死になって走り回っていると、意外なところから助っ人が現れるものなんです」(中堅社員)
2014年、サントリーには2つの大きな「やってみなはれ」があった。
1つは米蒸留酒最大手ビーム社の買収だ(買収後の社名はビームサントリー)。5月の買収終了後、佐治社長(当時)は次のように語っている。
「サントリーには創業以来、『やってみなはれ』という、新しい価値の創造に挑戦するチャレンジスピリットが、脈々と流れています。一方、ビーム社の200年を超える長い歴史にも、起業家精神と創造性、そして果敢な決断力が継承されてきた。両社の根幹をなす精神には、非常に共通している点があり、それもまた両社を結び付けた大きな要因です。今後、ビームサントリー社が、世界に向かって新たな可能性に挑戦する『やってみはなれ集団』として成長してくれるものと信じています」
 社長交代会見に臨んだ佐治信忠会長(左)と新浪剛史社長。
社長交代会見に臨んだ佐治信忠会長(左)と新浪剛史社長。続いて10月1日には、前ローソン会長の新浪剛史氏を社長に迎えるサプライズ人事があった。流通の最下流から最上流へ、180度の転身だった。
新浪社長のことを佐治会長は、「国際的な経営感覚、はつらつとした若さ、執念深さを持つ『やってみなはれ』な人だ」と評している。また新浪氏は佐治氏に会った時、「この人の『やってみなはれ』はすごいなと思った」という。「やってみなはれ」が2人を結びつけたともいえる。
2つの「やってみなはれ」は、果たしてどんな効果をもたらすのか。