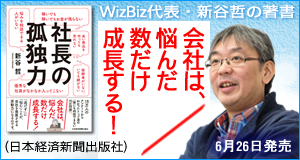2015年1月号より
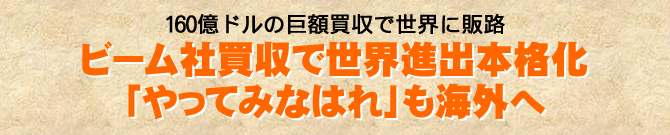
戦前に始まった米国進出
 買収合意で握手する佐治信忠・サントリー・ホールディングス社長(=右)とビーム社のマット・シャトックCEO。(2014年5月1日)
買収合意で握手する佐治信忠・サントリー・ホールディングス社長(=右)とビーム社のマット・シャトックCEO。(2014年5月1日)2014年5月、サントリーは米蒸留酒メーカー最大手のビーム社買収を完了した。
13年12月期のビームの売上高は約3200億円、同じくサントリーの蒸溜酒(スピリッツ)事業の売上高は約2800億円なので、蒸溜酒分野を単純合算すると約6000億円となる。サントリーは、20年に現在のほぼ倍に当たる4兆円企業を目指している。蒸留酒事業自体も一兆円とする計画で、今後もこの分野でのM&Aを実行していく考えだ。
一方、ビールについては国内を、スピリッツと飲料については世界市場をターゲットとしていき、20年の売上高に占める海外構成比を5割としていく。ちなみに、13年12月期の海外構成比は約25%にすぎない。
食品、流通、日用品は「3大国内産業」などと揶揄されるほど、グローバル化が遅れていた。だが、国内の少子高齢化や人口減などから、海外展開は待ったなしだ。サントリーホールディングス社長にローソン前社長の新浪剛史を招聘した理由のひとつも、グローバル化を推進するためだ。
しかし、サントリーが日本企業の中では早い時期から、グローバル化に着手していた企業だったことは、あまり知られていない。
1933年は米国でニューディール政策が始まった年として世界史と政治経済の教科書に必ず記されている。が、この年の12月に禁酒法が廃止されたことは子供の教科書には出てはいない。
寿屋(サントリー)創業者であり初代社長の鳥井信治郎は、禁酒法廃止からほぼ1カ月後に当たる34年1月に、山崎蒸溜所で造ったウイスキーの対米輸出を始めたのである。ホンダやソニー、ソフトバンクが誕生するずっと前の出来事だ。生糸をはじめとする絹製品でも、綿製品や手工芸品でもない。スコットランド以外では造ることは不可能とされた、モルト原酒を使った本格ウイスキーを、アメリカ市場に送り込んだのである。
当時、サントリーの国内ウイスキー事業は苦戦を強いられていた。一方、29年には世界恐慌が発生し、日本は不況のただ中、米国経済もどうなっていくのか予断を許さない情勢にあった。なのに、禁酒法廃止の間隙を突き、「やってみなはれ」でいきなりウイスキーの北米展開に踏み切ってしまう。創業経営者・信治郎がもつ経営の嗅覚に加え断固とした実行力とを示した事例でもあった。突然米市場に現れた日本のウイスキーに、あのアル・カポネも獄中で驚いたのではないか。
これはサントリーのウイスキー事業にとって、最初の本格的なグローバル展開だった(31年から満州や中国、東南アジアに出していたが)。
輸出は単発ではなく、継続される。なので、それなりに米市場に受け入れられたといえよう。山崎蒸留所で蒸溜が始まったのが24年年末なので、ほぼ9年が経過して良質なモルト原酒が熟成されていたのが、受け入れられた要因だったろう。ただし、日米関係が悪化し戦争へと向かうなかで、輸出は停止を余儀なくされていく。
戦後も、ビール事業に参入したのと同じ63年に、メキシコにウイスキー工場進出を果たす。主導したのは61年に第2代社長に就いた佐治敬三で、メキシコ工場(サントリー・デ・メヒコ)は、63年10月に完成した。ウイスキー対米戦略の第2弾だった。
当時まだ25歳だった折田一(後にサントリー常務)は、駐在する4人のうちのひとりとして着任する。羽田空港では、佐治敬三社長から「生きて日本の土を踏むと思うな」と檄を飛ばされる。
「日本のウイスキーを世界に広めるための一大プロジェクトであり、グローバル化は当時からの至上命題でした」と、97年頃に折田は「月刊経営塾」(現「月刊BOSS」)の取材で訪れた筆者に語った。
社長に就任して間もない佐治敬三にとってメキシコへの工場進出は、ビール参入と並び、大きな「やってみなはれ」、すなわちビッグチャレンジだった。
多すぎた「天使の分け前」
しかし、メキシコのウイスキー工場は失敗してしまう。原因は、工場が海抜2000メートルを超える高地にあったためだった。
ウイスキーはアルコール度数が高い酒だ。蒸溜したばかりの無色透明なニューポットのアルコール度数は65~70%に上る。これを樽詰めして長期熟成していくと、琥珀色のモルト原酒へと変容していく。
しかし、長期熟成の間、樽の中に眠るウイスキーは一部が蒸発する。蒸発分は“シェア・オブ・エンジェル(天使の分け前)”という美しい言葉で表現されるが、メキシコの高地には大酒飲みの天使がいた。
蓋を開けたら、予想以上にウイスキー原酒が消えていたのだ。
「なぜ、親父はあんなことをやったのか。僕なら、絶対にやらない」と、4代目社長の佐治信忠は笑いながら話してくれた。
当時はまだ、海外渡航に外貨の持ち出し制限があり調査も十分にはできなかったようだが、「やってみなはれ」の精神だけで進出したところに、やはり無理はあった。
 悪戦苦闘を強いられたサントリーのメキシコ工場。
悪戦苦闘を強いられたサントリーのメキシコ工場。メキシコ工場ではいま、熟成を必要としないリキュールの「ミドリ」を生産している。ミドリは、カクテル「メロンボール」などのベース酒で知られ、世界50カ国以上で販売されている。
このメキシコのウイスキー工場は「サントリー最大の失敗」ともいわれたが、80年代以降に本格化する海外展開で生かされていく。強引な工場進出ではなく、M&Aにより海外事業を推進する手法は、2014年のビーム社買収にもつながった。
最初のM&Aは1980年。ペプシコーラの在米ボトリング会社「ペプコム社」を買収するが、主導したのは佐治信忠だった。これは日本国内でサントリーがペプシコーラを販売(98年)するきっかけにもなる。その後のM&Aとしては、83年の仏ボルドーの名門シャトーであるシャトーラグランジュの買収をはじめ、近年ではニュージーランドのフルコア社、フランスのオランジーナ社、英国の老舗ブランド、ルコゼードとライビーナなどがある。「大型買収でサントリーは一気にグローバル化の進展を図っている」と佐治信忠は語っていた。
ウイスキーの北米を中心とする海外展開という点では、創業者による輸出が第1次攻撃、佐治敬三・第2代社長によるメキシコへの工場進出が第2次攻撃、佐治信忠によるビーム社買収に始まる第3次攻撃と、世代をまたいで実行されている。
もうひとつ、海外戦略で大きいのは中国ビール事業だ。きっかけは北京国際マラソンへのサントリーの協賛だった。83年の第3回大会の際、当時の王震国家副主席から佐治敬三に中国でビール事業をやってほしいという要請があり、敬三はその場で快諾したとされる。マラソンレースが終わるまでの2時間強のやり取りだった。
これにより、84年から江蘇省の連雲港市にあったビール工場を合弁として事業は始まる。東西冷戦終結以前であり、メキシコ工場同様に調査をしたわけではなく、始まりは人間関係にあった。サントリーにとって海外でのビール生産は初めてであり、中国にとっても初めてのビール産業での外資導入だった。
「10年間は筆舌に尽くしがたい苦労をした」(当時を知る関係者)そうだが、92年に単年度黒字化し、94年には累損を一掃する。この時点で、社内からは事業を売却して中国から撤退しようという意見もあったのを、「売却などとんでもない。中国の最大消費地である上海に出るべし」と断を下したのが第3代社長の鳥井信一郎だったとされる。
96年に上海に進出。99年には、それまで上海ナンバー1だったハイネケン系の「力波」を抜き去り、シェア1位となる。新商品「白」の大ヒット、問屋にテリトリーを設けた新しい流通政策、中国初の飛行船広告などが、短期間に首位となった勝因だった。いまでも上海シェアトップだが、2008年から事業は赤字に陥る。SABミラー(本社はロンドン)系の華潤雪花ビール(本社北京市)が、豊富な資力を背景に営業の大攻勢をかけてきたためだ。
上海の営業現場は、協賛金や販促費が飛び交う状態に陥る。
このためサントリーは、12年に中国大手の青島と提携すると発表。翌13年、それまで単独で展開してきた上海および江蘇省のビール事業を、青島との合弁2社(生産などの事業合弁、販売合弁)へと切り替えた。
ハイボールを全世界に
さて、スピリッツをもって海外へと舵を切っていくサントリー。既にビームサントリー(本社シカゴ)を設立させていて、「山崎」や「響」などのジャパニーズウイスキーを既存のビーム社の販路に乗せて世界で拡販させていく計画だ。だが、もうひとつの切り口として有効だと思えるのは、ハイボールではないか。08年から日本でヒットした、ウイスキーをソーダで割るハイボールを、欧米や新興国に広めていったなら、新しい市場を創造できる。
ウイスキーは本来は食後酒だが、ハイボールならば発泡性のビールと同じ食前酒・食中酒として飲んでもらえる。飲用シーンが大きく広がり、世界の食文化を変える可能性をもつ。海外でも高い評価を得ている「山崎」や「響」などの高級酒と、大衆的なハイボールとの2本柱での展開が予想される。これは日本のビール市場で、高級ビールの「ザ・プレミアム・モルツ」と、第3のビール「金麦」とでシェアを上げたのと同じ作戦だ。
さて、サントリーのDNAである「やってみなはれ」を、旧ビーム社の社員をはじめ関係していく外国人の社員たちに、どう敷衍していくかもポイントになろう。
サントリーには、海外で働く優秀な現地採用社員の日本本社への登用をはじめ、新たな人事システムの導入が求められていく。同時に、外部に向けて「やってみなはれ」の会社ということをグローバルにアピールしていく必要もある。
自動車や電機と比べ、酒類は文化的要素が強い。「やってみなはれ」をベースとするサントリーの企業文化を、グローバルに発信していく時が近づいている。(文中敬称略)
(経済ジャーナリスト・永井隆)