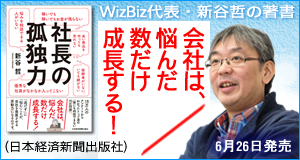2014年1月号より
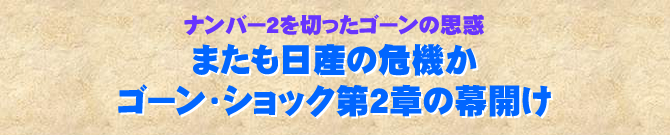
COOの電撃解任
11月1日、日産自動車で電撃的な解任劇が起こった。
本来、日産の2013年3月期中間決算の発表は11月5日に行われるはずだった。その予定を繰り上げ、1日に発表会見を行うという連絡が入ったのが前日のこと。通常ならCOOである志賀俊之氏が発表する予定だったが、急遽CEOであるカルロス・ゴーン社長自らが会見を行うことになった。当然これは「重大発表がある」ことを示すものだ。
 ナンバー2の志賀COOの電撃解任は衝撃を与えた。
ナンバー2の志賀COOの電撃解任は衝撃を与えた。会見に先立って報道陣に配られたニュースリリースには「役員体制の変更について」と記されていた。日産のナンバー2である志賀氏のCOO退任、最高意思決定機関であるエグゼクティブ・コミッティ(EC)のメンバー入れ替えが1日付で行われたのである。志賀氏解任の真意は何か、決算の数字はそっちのけで人事についての発言に注目が集まった。
もちろん、業績と人事が無関係であるはずはない。決算の数字は他の国内メーカーと比べて厳しいものになっていた。
日本メーカーを長らく苦しめていたのは、リーマン・ショック後に急激に進行した円高だった。いくら原価低減を進めても為替差損で消し飛んでしまう。トヨタですら単体決算の赤字を解消するのに5年を費やした。それがアベノミクス効果で年初から円安方向に進み、一時は1ドル=70円台まで進んだ為替は97~100円前後まで回復している。国内メーカー各社は1ドル=80円でも利益が出せる体質づくりを進めてきたおかげで、今年に入ってからの決算の数字は好調そのもの。為替差益の後押しもあって、この中間期の営業利益は、ホンダが前年同期比28.7%増の3564億円、トヨタに至っては同81%増の1兆2554億円まで数字を伸ばしている。
ところが、日産は1449億円の為替差益を得ながら、前年同期比7.8%減の2647億円にとどまった。営業利益率は6.3%から5.1%に悪化。中期経営計画「日産パワー88」では営業利益率8%を目標値に据えているだけに、大きな後退になったと言える。
今回の決算で、最大のトピックは、14年3月期の決算見通しを下方修正したことだろう。
日産の期初の通期見通しでは、為替レートを1ドル=95円としたうえで、営業利益7000億円を目標に掲げていた。営業利益率も6.3%と前期の5.4%を大きく上回るものだった。しかし、今回発表された見通しでは1ドル=97.9円で営業利益6000億円、営業利益率5.4%に修正された。国内メーカーの上方修正が相次ぐ中で、日産はひとり負けの様相を呈し、悪い意味で目立つ結果になってしまった。
もともと、今期の日産は上半期の苦戦が予想されていた。日産が他の国内メーカーに先駆けて注力していた新興国市場の停滞があったからだ。下半期の反攻を目論んでいただけに、想定以上の上半期のダメージが悔やまれる。
なかでも日産が期待していたのはブラジルだったが、12年から始まったメキシコからブラジルへの完成車の輸出制限により、メキシコ工場からの供給が制限されてしまっていた。14年初頭にブラジル工場が完成するまでは、売りたくても売れない状況がつづくことはわかっていたため、年が明けてからの反攻が期待されていた。しかし、レアルの通貨安の影響もあり、ダメージはより深刻なものになっている。
ロシアも生産計画が予定通り進んでおらず、インドも景気減速が著しい。頼みの中国市場も、尖閣問題以来の不振から、期待された伸びになっていないのが実情だ。新興国戦略に重きを置いてリーマン・ショックから回復してきただけに、市場拡大の見込みが甘すぎたのかもしれない。急拡大のツケが溜まってきているのではないか。
決算会見後、ある自動車記者は次のように漏らした。
「急拡大で兵站が伸びきってしまっている。どこかで見聞きしたような状況ですね」
販売台数を追って業績が急落したと言えば、リーマン・ショック前のトヨタがそうだった。世界一の座と販売台数1000万台を目指したトヨタは、利益を確保できる体質が伴わないまま拡大政策を続けた。リーマン・ショック前の04年、経営説明会に登場した当時の奥田碩会長は、拡大する生産・販売拠点に対し、「兵站が伸びきっている」とトヨタの弱点を語った。急拡大に追いつかない人材育成と、世界一は目の前という社員の驕りを戒めたものだった。奥田氏の不安は的中。世界一の販売台数を確保したその年にトヨタは上場以来初の赤字を記録することになってしまう。
環境が異なることから一概に当時のトヨタと日産を比較することはできないが、日産が中期経営計画「日産パワー88」で16年度までのグローバル市場占有率8%(750万台以上は必要と言われる)を掲げ、販売台数を追っている状況は同じだ。遠くを見すぎて足元をおろそかにすると、どんな結末になるのか、歴史が物語っている。
とはいえ、数字だけ見れば、日産はまだ営業利益率5%を誇る優良企業である。販売台数も下方修正したものの、過去最高の520万台を見込んでいる。何より純利益が3550億円確保できる見通しというのが大きい。赤字に転落してからでは再びリストラの嵐に飛び込むことになってしまうからだ。利益を出せているうちに、何らかの手を打つというのは正しい経営判断だと言えるだろう。そこはさすがゴーン氏だ。
ただ、問題はどんな手を打つか、である。
ルノーでも起こった解任劇
ゴーン氏は業績の下方修正と同時に、エグゼクティブ・コミッティの入れ替えという、いわば社内に対するショック療法という道を選んだ。
 次期社長候補の呼び声も高いアンディ・パーマー副社長。
次期社長候補の呼び声も高いアンディ・パーマー副社長。かつてゴーン氏の代名詞と言えば、「コミットメント経営」だった。必達目標を掲げ、それを達成できなければ責任を取るという、明快なスタイルで日産の改革を実行してきた。年度の業績目標という株主やステークホルダーに向けた目標値に対し、下方修正を行うことは裏切りに等しい。実は、この上半期の数字だけではない。前期の13年3月期決算でも、営業利益7000億円の見通しから下方修正、実績は5235億円の営業減益に終わった。
いつしか「必達目標」という言葉を使わなくなったゴーン氏だが、さすがに2年連続での下方修正では株主に対して申し訳立たない。
漏れ出てきた話によると、今回の決算見通しでは、下方修正をすべきか否か、意見が割れていたようだ。もともと後半に巻き返しの予定だっただけに、据え置くという意見が出ても不思議ではない。しかし、上半期の数字が悪すぎたために、志賀氏は下方修正をすべきとの意見だったとみられる。ゴーン氏は、下方修正を決断する代わりに、社員の意識を引き締める意味でも、懲罰人事は避けられなくなったようだ。
「通期の予想について、いろいろ議論しました。確かに痛みを伴います。当初の予測を達成できないと認めるのは難しかったのですが、下方修正を決めました」(ゴーン社長)
とはいえ、功労者で盟友でもある志賀氏に対し、懲罰人事という形にはしたくなかったのだろう。会見でのゴーン氏の言い分は次のようなものだった。
「今回の人事変更について、懲罰的だとは考えていません。現に志賀さんはこの場にいるでしょう? 懲罰ではありません。いまの体制でも、逆風の一部は吸収できる。しかし、拡大の取り組みに集中していくなかで問題が発生しているので体制を見直します。ECは平均年齢が高すぎる。ある時点で若返りを図らなくてはいけません。ただ若返りは徐々にやっていきたい。4月1日にも変更を発表します。将来的にも変更していく。しかしながら、業績が想定よりも低かったことで、実行を迅速化していきます」
志賀氏の退任、ECの入れ替えは、若返りの一環だとしたが、この人事で実質ナンバー2に就いたのは副社長の西川廣人氏である。志賀氏と西川氏は同学年であり、若返りとは言えない。また志賀氏とともにECから離れた副社長のコリン・ドッジ氏は、もともと年度末までに退任する意向を示していた。志賀氏の解任をカモフラージュするために、タイミングを合わせたとみるのが自然だろう。実質的にECをクビになったのは志賀氏だけだったのである。
実は13年8月29日、ゴーン氏がCEOを兼任している仏ルノーでもCOO解任劇が起こっていた。ルノーのナンバー2でCOOに就いていたのはカルロス・タバレス氏。ルノーの公式発表では「個人的プロジェクトの追求のため」としているが、真相はゴーン氏との感情的対立が原因だという。
タバレス氏と言えば、F1ファンの間では馴染みの名前でもある。現在チャンピオンチームのレッドブル・レーシングにエンジンを供給しているのがルノー。タバレス氏は大のモータースポーツファンであり、自身もテストドライバーからCOOに上り詰めた人物でもある。ルノーのF1活動に対する発言権もあり、タバレス氏の解任はルノーのモータースポーツ活動に少なからず影響を及ぼすと思われる。
そのタバレス氏解任のキッカケとなったのは、米ブルームバーグのインタビューだった。タバレス氏は「我が社では偉大なリーダーが君臨している。自動車産業に情熱を注ぐ者ならだれでも、ある時点でナンバー1を目指したくなるものだ」と語り、自らの権限拡大を求めていたという。
ゴーン氏は14年でルノーのCEOの任期が切れるが、再任されることも考えられる。仮にゴーン氏の引退が5年後ならば、タバレス氏は60歳を超えることになり、CEOを引き継ぐには遅すぎると考えていたようだ。他社でトップを目指すこともチラつかせていたようだが、この野心がゴーン氏の逆鱗に触れたらしい。ゴーン氏はルノーのCOO職を廃止し、職務は他の役員で分担させている。
効果的なショック療法
8月にこんなことが起こった直後の日産である。ゴーン氏は日産の人事にあたり、ルノーの前例が頭にないはずはない。野心的なCOOは自らの存在を脅かすと認識したはずだ。
タバレス氏と志賀氏は状況が異なるが、ルノーのCOO職を廃止しながら日産のCOO職を残すのは違和感があったのだろう。日産もルノーと同じく、志賀氏の職務を西川氏、アンディ・パーマー氏、トレバー・マン氏の3人の副社長に分担させた。
 実質的ナンバー2となった西川廣人副社長。
実質的ナンバー2となった西川廣人副社長。「組織体制は会社の戦略と目標に応じて適応していかなくてはいけません。COO職を設けたのは、私がルノーと日産の2社を経営することになった05年の時です。COOは、私がフルタイムで働いていた時には必要がなかった役職です。いまの日産は、05年の日産にくらべて、徐々に会社が大人になり、成熟し、経営層は重責を担うようになっています。いまの日産には、成熟したマネジメントが揃っている。ナンバー2として1人を置く必要はない。これからは複数のナンバー2にあたる人間を設けることが必要です。彼らが会社の責任の大部分を担う必要があります。ナンバー2(COO)が必要ないというのは、悪いサインではない。会社が大人になっているという証です。これはルノーもしかり日産も同様です」(ゴーン氏)
ものは言いようではあるが、ともかくナンバー2を置かず、権限を集中させないことを選んだのは間違いない。言い換えれば、ゴーンCEOに対する一極集中が進んだということだ。ちなみに、ゴーン氏は自身の責任と進退について次のように語っている。
「私次第ではなく、会社を持っている株主の方々次第だ」
株主が退任を迫れば、ゴーン氏は退かざるを得ないということらしいが、日産の株主を見てみよう。43.4%を持つ大株主は、言わずと知れたルノーである。ルノーの責任者はゴーン氏である。つまり、実質的にルノー以外のすべての株主が解任論をぶち上げるくらいでなければクビになることはない。すなわち、日産のCEOのヤメ時は、株主ルノーのCEOである自分が決めるということ。都合のいい話ではある。
それにしても日産は好調時を迎えると、なぜつまずくのか。未達に終わった中期経営計画「日産バリューアップ」の時もそうだった。トヨタが世界一を睨むなか、日産の販売は伸び悩んでいた。この時はリーマン・ショックでの危機感がバネとなって復活したが、何かしらの衝撃がなければ本気を出せない企業体質なのかもしれない。
ルノー、日産のCOO解任劇は、どこか来日当初のゴーン氏を思い出させる。
たとえ批判の声が上がろうとも、断固たる信念でミッションを遂行する「コストカッター」時代のゴーン氏である。当時の日本は、日本人にはないゴーン氏の圧倒的な改革力に畏れを抱いた。系列をぶっ壊し、鉄鋼業界の再編を招いた「ゴーン・ショック」は、日産社員にとって改革の本気度を認識させるに十分だった。ゴーン氏は再びゴーン・ショックで日産社員の目を覚まそうとしているのかもしれない。
電撃的な人事から始まったゴーン・ショックは成功するのか、日産の復活を検証したい。