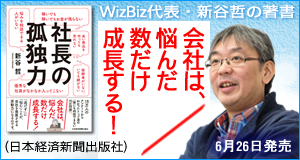2014年1月号より
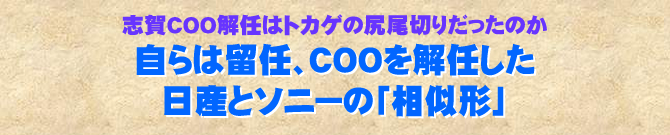
権限の一極集中
他稿にもあるので詳しくは触れないが、日産自動車は11月1日、中間決算を発表すると同時に、志賀俊之COOがCOO職を離れ副会長に就任すると同時に、コリン・ドッジ副社長兼CPO(チープ・パフォーマンス・オフィサー)がCPO職を離れると発表した。
志賀氏は2005年にCOOに就任。ルノーCEOを掛け持ちするゴーン氏をサポートしてきたが、ついにその座を解かれることになった。通常の人事であれば、後任のCOOを誰かが引き受けることになるが、今回、日産はCOO職を廃止、新たに西川廣人氏、アンディ・パーマー氏、トレバー・マン氏の3人が分担してCOO職を引き継ぐことになった。
この人事によって「ゴーンCEOの独裁色が強まった」と見るのが自然だろう。これまでは志賀氏がクッションの役割を果たしていたが、すべての業務が直接ゴーン氏とつながることになるからだ。
また、ゴーン氏は否定しているものの、今回、日産が通期営業利益見通しを、従来予想より1200億円下方修正しているため、志賀氏はその責任を取らされたとの見方は強い。
かつてゴーン氏は、日産リバイバルプランによる再建策を発表した時に、「これはコミットメントだ」と強調。達成できなかった時は退陣すると宣言した。この「コミットメント経営」は一種の流行語となり、日産を象徴する経営手法ともなった。
ところが今回、業績目標到達が不可能になった時にゴーン氏が選んだのは、自らの進退ではなく、COOの志賀氏の退任だった。「トカゲの尻尾切り」と言われてもしかたがない。
ゴーン氏にしてみれば、来期以降の業績回復によって、今回の人事の正当性を証明するしかない。逆に、ゴーン氏への「権力一極集中人事」が功を奏さなかった場合、ゴーン氏の威信は大きく傷つくことになる。
「ゴーンさんにしてみれば、瀕死の日産をここまで成長させたという自負もある。ただ、長期政権が続き、志賀さんのCOO任期も8年を超え、ややマンネリ化してきたことも事実。そこでゴーンさんは一種のショック療法として今回の人事を断行したのでは。決算発表の日程を前倒しし、出席しないはずのゴーンさんが壇上に立つ。これだけで社内には緊張が走ったでしょう。そしてCOO退任を発表する。そのインパクトは大きかったはずですよ。
問題はこれからです。結果が伴えば名人事となるけれど、うまくいかなかったら“ゴーンの限界”と言われることになる。実際、今回の日産と同じような人事をやっておきながら成果を出せず、最後は戦犯扱いされて会社を去った外国人経営者もいましたからね」
と語るのは、古くから財界を取材している年輩記者である。
この記者の言う、「会社を去った外国人経営者」とは、昨年、ソニーCEOを退任したハワード・ストリンガー氏のことである。
ストリンガー氏がソニーCEOに就任したのは2005年のことだった。
それ以前のソニーCEOは出井伸之氏。出井氏は1995年に社長に就任、2000年からは会長を務めていた。ソニートップとなった出井氏は、見た目のスマートさに加え、フランス映画の巨匠のルイ・マル監督と親交があるなど文化的な香りを漂わせていたこともあり、たちまち人気経営者となっていく。
ITバブルにも乗って業績も好調、株価も2000年に3万3900円の高値をつけた。出井氏はそれまでの歴代トップと違い、創業時の社名、東京通信工業時代を知らない第二世代の経営者だ。2000年頃までの出井氏の活躍を見ているかぎりでは、ソニーは無事、代替わりを果たした、と思われた。ところがITバブルの崩壊と同時にソニーにも暗雲が立ち込める。ブラウン管テレビにこだわり、液晶テレビに出遅れたこともあって業績は低迷、03年、業績の下方修正をきっかけにソニー株は急落する。世に言う「ソニー・ショック」である。
以来、出井氏の評価は一変、社内外から批判の声が出て、結局05年に安藤国威社長ともども退陣せざるを得なかった。代わって会長兼CEOに就任したのがストリンガー氏だった。
ソニーCEOの失敗
ソニーのトップには、他の電機メーカーのトップとは違う資質が求められる。というのも、ソニーはエレクトロニクス=ハードと、エンタテインメント=ソフトそれぞれの部門を持つ、世界で唯一の両輪経営を行っている。そのため、単にハードに明るいというだけでは通用しない。特にソフトについては、買収したアメリカのコロンビア映画(現ソニー・ピクチャーズエンタテインメント)で散々苦労したこともあり、これを御する能力を求められた。そこで白羽の矢が立ったのが、米三大ネットワーク、CBS社長を務めた経験があり、ソニーアメリカ会長だったストリンガー氏だった。ストリンガー氏はアメリカのエレキ事業を立て直した経験もあり、両輪経営を標榜するソニーのCEOにふさわしいように見えた。
当時、よく言われたのが「ストリンガーは第二のゴーンになれるか」ということだった。ゴーン氏はルノーから日産に派遣されたが、ルノーの前にはタイヤメーカー、ミシュランで実績を残している。2人に共通するのは他の業界を知っているプロの経営者であること。ゴーン氏の日産での成果が華々しかっただけに、ストリンガー氏にも同様の結果を期待した。
 2009年、ソニーのストリンガー会長(右から3人目)は中鉢社長(同4人目)を解任し、権限を自らに集中させた。
2009年、ソニーのストリンガー会長(右から3人目)は中鉢社長(同4人目)を解任し、権限を自らに集中させた。出足はまずまずだった。前述のように、当時のソニーの最大の泣き所が、液晶テレビの出遅れだった。しかしストリンガー体制になって初めて迎えたクリスマス商戦。ソニーの液晶テレビ「ブラビア」は瞬間風速ながらも「液晶のシャープ」の「アクオス」を上回りシェアトップにも立った。株価も半年近くで5割も上昇した。「第二のゴーン」が現実のものになるかもしれない。期待はさらに膨らんだ。
その後曲折はあったものの、08年3月期決算では過去最高益を計上、ストリンガー体制は盤石かと思えた。そこをリーマン・ショックが襲った。それによって明らかになったのは、ソニーの過去最高益は資産の切り売りによってもたらされたものであって、高収益体質になってはいないことだった。そのためリーマン・ショックで世界同時不況が起きると同時に、ソニーの業績は水面下に沈んだ。同時にストリンガー氏がゴーン氏の再来だと言う人はどこにもいなくなった。
05年のストリンガー体制発足時から、ソニートップはストリンガー会長兼CEO、中鉢良治社長兼COOのコンビだった。ストリンガー氏はひと月のうち1週間から2週間しか日本に滞在しない。またエレクトロニクスにも明るくない。そこで、日ごろのオペレーションやエレキ部門については中鉢氏に任せていた。
リーマン・ショック後、エレキ部門が大赤字となり、ソニー本体も赤字転落すると同時に、経営陣の責任を問う声が強まった。そこでストリンガー氏は思い切った人事を断行する。
09年4月1日付で、中鉢社長は副会長となり、ストリンガー氏が社長を兼務することになったのだ。さらに40~50代の執行役員4人を抜擢し、COOの役割を分担させた。中鉢社長を副会長に棚上げした理由についてストリンガー氏は、「余計なレイヤー(階層)はいらない」と語っている。中鉢氏がいたことが、自分と事業責任者との距離を遠ざけていた、中鉢氏こそ、エレキ不振の根源だと言わんばかりだった。
「でも実際のところは、ハワードのハード音痴がソニーのエレキがおかしくなった最大の理由です。AIBO(犬型ロボット)のようなソニーならではの商品も、利益が出ないために製造を中止するなど、製品に対してほとんど興味を持たなかった。そのためエンジニアの間では、いずれハワードはエレキ部門を売却するつもりじゃないか、との噂まで出たほどです」(ソニーの中堅エンジニア)
ストリンガー氏はソニー時代「ソニー・ユナイテッド」という言葉を口にした。また「サイロを壊す」という言葉も、経営方針発表会などで繰り返し使っている。
しかし内情は、エンジニアたちはエレキに理解のないCEOに不満を抱き、ストリンガー氏はヒット商品を生まない現場にいらだちを募らせるという状況で、ソニー・ユナイテッドとは口当たりのいいスローガンにすぎなかった。
そのため、中鉢社長を中抜きする人事も効果を発揮することなく、結局、ソニーは赤字を積み重ねていくのだが、中鉢氏がいなくなった分だけ、ストリンガー氏への批判は強まっていき、12年2月に開かれたソニー指名委員会で、ストリンガー氏の4月1日付でのCEO退任が決まった。ストリンガー氏は最後まで会長職にとどまりたいとの意向を示していたが、指名委員会は株主総会までの留任しか認めなかったため、6月に取締役会議長となり、13年5月、取締役も退任した。
結局、自分に権限を集中させ、レイヤーを少なくして経営にスピード感を持たせようとの目論見は実らなかった。
サポート役の必要性
今回、日産が発表した、志賀COOが副会長になり、その業務を3人の副社長が担当するというのは、09年のソニーの人事に瓜二つだ。強いて違いを挙げれば、ソニーの場合、四銃士はすべて日本人だったが、日産の三銃士は日本人1人に対して外国人2人というところだが、COOの処遇も、CEOに権限を集中させるやり方もまったく同じである。しかもゴーン氏はルノーCEOを兼務しているため、日本にいる時間も限られている。社長兼務後も、日本での勤務は限定的だったストリンガー氏と、これまた相似形だ。
もちろん企業の置かれている立場はソニーと日産ではまるで違う。ソニーは赤字転落がきっかけで人事を断行したが、日産は下方修正したとはいえ、営業利益率5%以上を誇る優良企業である。ただし、経営者の危機感という意味では同じなのかもしれない。ゴーン氏にしてみれば、いまのうちに手を打っておかなければ将来的に取り返しがつかなくなると感じたのかもしれない。
 今度の人事の成果でゴーン氏の評価は定まる。
今度の人事の成果でゴーン氏の評価は定まる。いち早く手を打ったのは、ゴーン氏ならではの慧眼と言えるのかもしれない。ただし、権限の集中が、必ずしもいい方向に働くとはかぎらない。志賀氏のような存在が、組織の上で果たす役割は意外と大きいからだ。
1999年にゴーン氏は来日。半年後に日産リバイバルプラン(NRP)を策定して聖域なき構造改革を行った結果、日産は劇的に立ち直った。これは、産業史に特筆されるほどの快挙である。この時ゴーン氏は、それまでのしがらみや慣習をことごとく破壊し、コスト削減と生産率向上と、社員のモチベーションアップを同時に成し遂げた。
しかし、従来の仕事のやり方を根本から否定するかのようなNRPにとまどう社員も多かった。そのとまどいが、ゴーン氏に対する恨み節に転じることもあった。
この時、バッファー役としてゴーン氏をサポートしたのがゴーン社長の前任者、塙義一氏だった。
塙氏は早いうちから日産のプリンスと目され、1996年に社長に就任した。当時の日産は、シェアは右肩下がりで低下、財務も毀損し、「明日をも知れない」という言葉が誇張でないほど惨憺たる状況だった。そのため社長になった塙氏の最大の仕事は、生き残るための提携先を見つけ出すことだった。
当初は独ダイムラーと提携を模索したが不調に終わり、最後に望みを託したのが仏ルノーだった。
幸いルノーとの提携交渉は上首尾に終わり、今日のルノー・日産連合が誕生する。言わば塙氏は、いまの日産の形をつくった立役者である。
ゴーン氏が赴任してからも2001年までの2年間は、塙氏が社長兼CEOだった。つまり最終責任者であるにもかかわらず、塙氏はゴーン氏のやりたいようにやらせた。その代わりになだめ役に回り、社内の不満を一手に引き受けた。塙氏の存在が一種のガス抜きとなったのだ。この功績はけっして小さくはない。
志賀氏の存在も同様だ。カミソリのように、触れれば切れるほど鋭いゴーン氏を志賀氏がソフトに包み込んでいたからこそ、ゴーン氏が誤解を恐れることなく経営手腕を発揮することができた。社員にしても、ゴーン氏に文句は言えないが、志賀氏に対してなら、具申することができる。志賀氏を通すことで、ゴーン氏と社員が多少なりとも意思疎通することが可能になっていた。
責任へのコミットメント
ところがこれからは違う。たとえは悪いが、抜身の刀を持ったまま、ゴーン氏は社内を練り歩くことになる。いままで鞘の役割を果たしてくれた女房役は自らの手で更迭してしまった。これがどんな結果を生むのか。意思決定が段違いに早まり、ゴーン氏の指示がダイレクトに末端まで届くのか、あるいはゴーン氏が雲上人になってしまうのか。こればかりは行く末を見守るほかはない。
 ストリンガー氏はエンジニアの反発を買った。
ストリンガー氏はエンジニアの反発を買った。少なくとも4年前に似たような人事を行ったソニーの場合、結果は吉とは出なかった。ソニーのエンジニアは、エンジニア出身の中鉢社長に対して、「自分たちの気持ちをわかってくれる人」という仲間意識を持っていた。それが更迭されたことで、エンジニアの気持ちは一気に萎えてしまった。そしてストリンガー氏には、しぼんでしまったエンジニアの士気を、再び燃え上がらせることはできなかった。
「ゴーンさんに必要なのは、NRPを行っていた時のように、自らの責任を明確にすることです。コミットメント経営で一世を風靡したゴーンさんですが、08年に『必達目標は社員を怖がらせ、不安にさせていると思った』と、その看板を下ろしています。確かに社員を必要以上に怖がらせる必要はないでしょうが、いま問われているのは、自らの責任をどうコミットメントしていくかということです。少なくとも、今度の人事を社員が“トカゲの尻尾切り”と考えているようでは、士気は上がりません」(前出の財界記者)
十数年前、日産自動車を蘇えらせたのは、ゴーン氏の不退転の決意だった。いま一度、その決意が必要なのかもしれない。