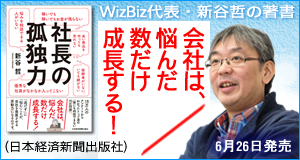2014年5月号より
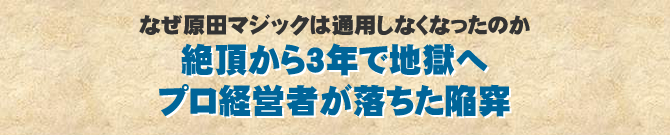
マック、KFCの不振鮮明
まずは下の表をご覧いただこう。表にある4社のうち、日本マクドナルドホールディングス(以下マクドナルド)と日本ケンタッキー・フライド・チキン(以下KFC)の業績が急降下していることが見て取れる。
次いで3社目のモスフードサービス(以下モスフード)に目を転じると、絶好調とは言えないまでも、かなり善戦、健闘した数字だ。そしてスターバックスコーヒージャパン(以下スターバックス)。昨年は、100円の「セブンカフェ」に代表される、コンビニの淹れたてコーヒーが席巻した年であり、普通に考えれば、スターバックスはマクドナルド、KFC、モスフード以上にコンビニコーヒーの影響が出そうなもの。
だが、実際には表の通りでスターバックスでは過去最高益を予想し、経常利益、純利益ではマクドナルドを抜いてしまう。スターバックスの店舗数が1000店強なのに対し、マクドナルドは順次減らしてきたとはいえ3100店と、なお3倍の規模があるだけに、マクドナルドとしては由々しき事態だ。
もちろん、同社は赤字に転落したわけではない。原田泳幸氏(14年3月末の株主総会後に代表権のない会長に就任予定)がアップル日本法人社長からマクドナルドに転じたのは2004年だが、その前の02年、03年は2期連続の最終赤字に喘いでいた。だからか、いまでもマクドナルドの古参幹部はこう振り返る。
 10年間、日本マクドナルドを率いた原田泳幸氏。
10年間、日本マクドナルドを率いた原田泳幸氏。「当時は3900店で全店売上高が4300億円。直近は3100店で5000億円です。つまり1店当たりの売上高は劇的に改善しているわけで、昔とは違います。赤字の頃は、内部の人間では為す術がなくなっていた。とはいえ上場会社だし、いつまでも赤字というわけにはいかない。それまでの一切を変える改革のリーダーシップが必要となり、原田の招聘となったわけです」
原田氏が着任するまで、マクドナルドの既存店売上高は7年連続でマイナスだった。それが、04年以降11年まで8期連続増収という離れ業を達成したことで、同氏自身、「自分は雇われ社長としては世界でも有数」との自負を公言した。
確かに、どん底から立て直しても数年の増収で止まっていたら、原田氏が特に注目されはしなかったかもしれない。それだけに、この2、3年なぜ“原田マジック”が通用しなくなったのかが気になる。前出のマクドナルド幹部の説明はこうだ。
「まず、東日本大震災後、消費者が夜間に出歩くことを控えるようになり、弁当や総菜を買って帰る中食や、家庭で調理する内食へのシフトが顕著になりました。特に中食にシフトした消費者を取り切れておらず、厳しさがあります。
同時に、我々も24時間営業店を順次、縮小しています。3100店のうち24時間営業店は1800店ぐらいありますが、さらに300店ほど減らしていく予定です。
当社の強みだった、テイクアウトでも客席での食事でもお待たせしない利便性、おもてなし、100円コーヒー、スマホクーポンなどのウェブマーケティングと、いろいろなものがどんどん(同業にも異業種にも)追随され、優位性のあったギャップが埋められてきてしまった」
もちろん、マクドナルドも手をこまねいていたわけではない。たとえば、同社が主力業態と位置づけてきたドライブスルー型店舗。通常の駅前立地店舗は、瞬間的な集客力は高いが、持続性には波がある。その点、ドライブスルー型店舗は一度認知されると、周辺の商圏に左右されない集客が見込めるという。そのため、同タイプの店は11年末時点で1330店だったのが12年末は1459店、13年末は1493店と、全店の半分弱までに迫ってきている。
その、ドライブスルー型シフトを可能にしたのが、原田氏が急速に進めてきた直営店からFC(フランチャイズ)店への切り替えだった。かつては直営店比率が7割近かったが、その比率は現在、そっくり逆転している。平均して1人のFCオーナーが十数店、場合によっては100店以上を経営し、マクドナルド本体は身軽になった分、コンピュータシステムやドライブスルー型店への投資などに振り向けていった。
米国の方式を忠実に

効率性を極める合理主義者の原田氏だけに、時にはFC店オーナーとは摩擦や軋轢もあったかもしれないが、それはFCビジネスを展開する企業にとって宿命でもある。特に、店舗数が桁違いに多いコンビニの場合はなおさらだ。FC運営の巧拙の差は各チェーンであるかもしれないが、直営からFCへのシフトを急いだこととマクドナルドの業績降下は、それほど強い要因とも思えない。
もう1つ、中途入社した幹部の流出なども業績不振の遠因と指摘する声がある。だが、これもドライな外資系企業で人の出入りが激しいのは普通のこと。原田氏が強いリーダーシップを発揮して求心力を高めれば高めるほど、一部の幹部にとっては遠心力となりうるだろう。
原田氏は過去、牛丼チェーンの値下げ合戦を引き合いに出し、「体力勝負の価格競争に意味なし」と語ってきた。一言で言えば、割安価格でまず客数を上げ、そこから付加価値商品に誘導していくというのが、いわば原田氏の成功方程式だった。もちろん、そこには季節要因から時間帯の要因まできめ細かいマーケティングの仮説があり、タイミングよくセットメニューやイベント、期間限定キャンペーンなどを絡ませてきた。
「従来の外食業界は、まず商品ありきで、ブランド力をライフスタイルイメージにしていく力が弱い」
原田氏はそうも考えてきた。店舗の内外装デザインのモダン化などもその1つだが、そのスマートさが、外部からは逆に危ういと映ることもある。同じカリスマ型でも、義理人情に厚かった藤田田時代のマクドナルドを知る元幹部は以前、こう語っていたものだ。
「マーケティング力に長けた原田さんだから、CMや商品訴求の仕方はうまくなった。店舗デザインもカッコよくなったし、一言で言えばアカ抜けた感じです。藤田さんの頃は、店の看板も英語表記でなくカタカナでしたからね。
ただ、原田さんは米国本社の言う通りのことをしている印象が否めず、日本のマクドナルドとしてのオリジナリティやクリエイティビティがあまり感じられません。昔は、店舗内のマシンも日本で独自仕様のものを開発していたんですけどね」
元幹部の言うことももっともだが、2期連続赤字に陥って原田氏が招聘された時点で、米国のマクドナルド方式が日本でも徹底されていくのは必然だった。
振り返ってみると、連続増収記録の最後となった11年は、すでに薄氷を踏む流れだった。同年11月の第2週時点までの売り上げ数字で推移すると、12月にどんなに頑張っても8年連続増収に赤信号が灯ることが確実だったからだ。原田氏はその数字を見た後、
「たとえ0.1%でも(年間既存店売上高の)プラスはプラス、マイナスはマイナス。後者に終わった場合、どれだけ世間の認識が違ってくるか。その怖さを知れ」と、社内に檄を飛ばしている。
同時に、特に東日本大震災以降、原田氏は「ライバルはコンビニ」と公言するようになった。コンビニとて業績格差が鮮明になり、勝ち組と言えるのは、セブン‐イレブン・ジャパン、ローソン、ファミリーマートの上位3社だが、震災以降、大手コンビニは女性やシニアの取り込みにも成功し、この3社はいまなお、最高益を更新し続けている。
前述したように、昨年はコンビニコーヒーが席巻した上、プレミアムチキンなどの投入が、マクドナルドやKFCに少なからず影響を与えたのは確実。コンビニの商品力が目に見えて向上していることが1つ。その上、マクドナルドが約3100店、KFCが約1200店で計4300店、対するコンビニ3社の合計店舗数は、すでに3万8000店近い。メッシュ細かく消費者を捉まえるという点では勝負にならない。コンビニは店内調理やイートイン店舗も増える一方だし、扱う商材も多彩で、ついで買いも誘いやすい。
原田氏も12年2月時の本誌の取材で「コンビニはいろいろな来店動機を創造しながらマーケットを作っているわけで、素晴らしいし見習わなくてはいけない」と脱帽していた。
ライバルと見立てたコンビニと勝負するには、やはりまずは商品力だが、その12年のハイライトは、夏に投入した「世界のご当地ハンバーガー」だった。フランスの「ル・グラン」、インドの「ゴールドマサラ」、オーストラリアの「オージーデリ」がそれで、マクドナルドではかなり大がかりな販促キャンペーンも行っている。
既存店売上高は同年4月以降マイナスが続いており、原田氏としてもこのご当地ハンバーガーに寄せる期待は大きかった。ところが、同氏が就任して以降、これだけハズレた商品も珍しいと思えるほど、消費者に受け入れられなかった。結果、既存店売上高をプラスに転じさせることができずに秋に突入、ついに連続増収記録がストップすることを覚悟せざる得なくなる。
このため、例年なら通期決算発表の2月に開示するその年の戦略を、12年11月1日に行った第3四半期決算発表で同時に公表した。当時の会見で原田氏はこう語っている。
「事業環境が変わり、すでに13年の戦略も決めていることから、このタイミングでの発表となりました。今年は世界のご当地バーガーを投入しましたが、これまでのようには伸びませんでした。率直に言えば、予見の精度が狂ったのです」
同氏は着任時からずっと、地域別、店舗別、曜日別、時間帯別まで、細かく各店舗の状況分析をし、次の一手を探ってきた。その“原田コンピュータ”の精度、確度が初めてずれてしまったことになる。
誤算続きで浮上できず
それ以降も原田氏の誤算は続く。やみくもな期間ないし季節限定メニューの投入はコストを増大させるだけとの反省に立ち、13年年初は静かな商戦でスタートしている。ところが、これも裏目に出た。前年の政権交代により、アベノミクス効果で日経平均株価がグングン上昇、資産効果もあって、消費者が財布の紐を少し緩めるようになった。
年初に特段、キャンペーンを展開しなかったマクドナルドは、13年1月の既存店売上高が前年同月比でマイナス17%まで拡大、続く2月もマイナス12%を記録した。この大幅な落ち込みを挽回するのは容易ではない。景気回復基調ムードの中で、この数字はいかにも手痛かった。
「お客さんは、やはり新しい価値やサプライズを求めています。キャンペーンの抑制と新商品投入の、バランスを取ることが大事だとわかったので、そこから猛烈に企画を立て始めました」(原田氏)
6月、サッカーの本田圭佑選手をイメージキャラクターに起用した、アグレッシブな印象の「BITE!」キャンペーンを打ち、原田氏自身も企画に深く関わった。「クォーターパウンダー ハバネロトマト/BLT」の2商品がそれで、特に「ハバネロトマト」は久々にスマッシュヒットとなる。
ここから、さらに話題作りを切らさない。7月に入ると、今度は期間限定で3種類の1000円バーガー、「クォーターパウンダー ジュエリー」を発表、この商品は特製の“化粧箱入り”というおまけもついた。ただし、販売個数には限りがあり、「あくまで話題作りで、勢いを見せるための仕掛け」(同)
ここで消費者の来店動機を盛り上げ、集客を増やし、売上高も上げる作戦だ。
足元では、13年5月、6月とわずかながらも既存店売上高がプラスに転じていただけに、期待も高まった。ただし、夏場に稼ぐはずなのは派手な一連のキャンペーン商品でなく、フローズンドリンクの新商品、「マックフロート」だった。
7月、8月の来店客数はそれぞれマイナス9.8%、9.3%で、既存店売上高も7月から再びマイナスに。その7月時点でインタビューした際、原田氏は「今回の『マックフロート』で客数を増やさないといけないが、まだ予定よりも客数が下回っているのが正直なところ」と、やや苦悩の色を見せていた。
また、景気回復過程で、消費者が総じてファストフードから少し離れているのではとの問いにも「そういうデータはないですね。アベノミクス効果で外食産業の消費構造がそんなに変わったとは思えません」としていた。
が、翌8月の中間決算発表では「ボーナスが増えたからマックに行く回数を増やすとは考えにくく、グレードを上げて、デパートのレストラン、さらに上のホテルのレストランにシフトしたような現象が起こっているかもしれない」と語り、発言の一貫性も欠いている。
 2013年8月末、サラ・カサノバ氏(右)にバトンタッチ。
2013年8月末、サラ・カサノバ氏(右)にバトンタッチ。そして8月27日、原田氏はサラ・カサノバ氏を帯同して記者会見し、事業会社の社長を譲ることになる。この時点では「私は退任ではなく、引き続きリーダーシップを発揮し、(カサノバ氏と)二人三脚経営になる」として、持ち株会社社長にとどまる意義を強調していたが、14年3月25日の株主総会をもって持ち株会社トップも譲ることは、米国のマクドナルド本社首脳との話し合いの中で規定路線だったのだろう。
その後、原田氏は日本経済新聞のインタビューで、
「経営者として1年も“浪人”する気はない。同業他社に行くことは道徳的に許されないだろう」と語っている。まだ、マクドナルドのトップにある人物としては軽率の感が拭えないが、逆に言えば、10年社長を務めてもまだ燃え尽きることのないファイターぶりと、赤字から8期連続増収をやり遂げた、“プロ経営者”としての矜持を示したかったのかもしれない。
(本誌編集委員・河野圭祐)