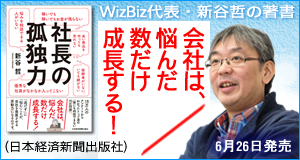2013年1月号より
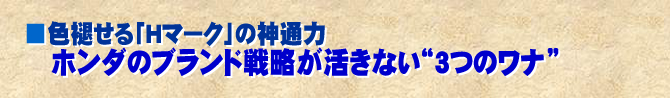
販売台数2位に躍進
 Hマークのブランド力を高めることができるのか。
Hマークのブランド力を高めることができるのか。ホンダの軽自動車販売が絶好調だ。昨年末に発売した、斬新なデザインと大型ミニバンを思わせる広大な室内空間を持つ軽自動車のミニバン「N BOX」は発売以来、常に受注残を抱えるほどの人気を博している。
2012年10月の販売台数は1万8200台と、トヨタを代表する人気モデル「プリウス」を抜き、同じくトヨタのコンパクトハイブリッドカー「アクア」に次ぐ販売台数2位に躍り出た。非ハイブリッドカーとしてはトップで、次点のスズキ「ワゴンR」に2000台以上の差をつけた。
11月には新たに軽セダンの「N-ONE」を発売した。軽セダンは地方で日常の足として使われるケースが多いため、低価格と低燃費を両立したモデルでなければ売れないというのが業界常識。N-ONEはライバルに比べて価格がずっと高く、燃費性能もとりわけ優れているというわけでもない。にもかかわらず、洒落たデザイン、質感の高い内装、乗り心地や走りの良さなどを武器に、発売前から大量の予約受注を獲得。月1万台以上の販売を目指している。
このように軽市場で破竹の勢いを見せるホンダの販売店はえびす顔かと思いきや、販売の最前線に立つ営業担当者の表情は決して明るくはない。東京近郊でトップセールスを連発している有力販売会社の首脳は、現場の実情を語る。
「たしかにN BOXは指名買いのお客様が多く、とてもよく売れていますし、N-ONEに対する反応もいい。一方でその割りを食っているのが、これまでコンパクトカーのベストセラーだった『フィット』。売れ行きはがっくりと落ちました」
コンパクトカーのフィットは、01年に登場した初代が大ヒットして以降、ホンダの国内営業の圧倒的な支柱となってきたモデルで、燃費性能に優れたハイブリッドカーも用意されるなど技術面も充実している。そのフィットの10月の販売台数は9300台。前年の4割程度しか売れなかったのだ。
「N BOXが発売されてからも、しばらくはフィットもよく売れていましたが、ショールームで両車を比較して、N BOXのほうがいいという方がだんだん増えてきました。秋になると、N-ONE発売の情報がお客様に伝わり、そっちにも食われた。結局フィットは、身内の軽自動車にやられた格好です」(前出の販売会社首脳)
実はホンダは、フィットを登場させた時も同じような経験をしている。当時、ホンダの稼ぎ頭となっていたのは、ミニバンブームの火付け役となった「オデッセイ」。オプション装備を含めた平均売価が300万円以上という決して安くない車が飛ぶように売れ、ホンダの財政を大いに潤わせた。が、コンパクトカーでありながら広い室内を持つフィットが登場すると、全くクラスの違う両モデルを見比べてフィットを選ぶ顧客が急増し、販売単価を落としてしまったのだ。
ホンダの国内販売は今や、全く売れなくなった3ナンバー車と、コンパクトカー主体の5ナンバーを合わせた台数よりも、軽自動車のほうが多いという有り様である。通常、自動車メーカーは1台あたりの単価を少しでも上げていきたいところなのだが、ホンダのこの10年はミニバンからコンパクトカーへ、コンパクトカーから軽へと、ステップダウンを続けてきている。
トヨタのブランド戦略
今日、日本の製造業にとっての大命題の一つに、付加価値の拡大がある。1ドル=80円前後という円高のなかで収益力を保つには、利益幅を広げていくことが必要不可欠なのは言うまでもない。
自動車業界でも収益力拡大への取り組みは、はるか昔からなされていた。これまでは同じ売価のものをより安く作るコストダウン側の取り組みを得意としてきた。しかしリーマン・ショック後の円高に翻弄されるなかでクローズアップされているのが、収益力拡大のもうひとつの要素である、価格引き上げだ。
 伊東社長は軽自動車の拡大を打ち出しているが…。
伊東社長は軽自動車の拡大を打ち出しているが…。日産自動車首脳は語る。
「ドイツは歴史的にマルク高、ユーロ高に苦しめられてきた。そのなかでドイツ車メーカーは、単に車を作るためのコストを下げるだけでなく、ドイツ製の車は余分にお金を払ってでも欲しいとユーザーに思わせるような製品作りに邁進してきた。ユーロが安くなった今、ドイツのメーカーはその果実を存分に享受している。我々も同じクラスのモデル同士でコストや商品力を競うだけでなく、そろそろ同じクラスのライバルより高い値段で買ってもらえるような車作りをモノにしていきたいとつくづく思う」
ユーザーに高い値段で買ってもらえる製品作りは、日本の自動車が伝統的に苦手としてきた分野だ。日本の自動車産業が急成長を遂げはじめたのは1980年代だが、当時の日本はいわば新興国で、為替レートや人件費などいろいろな点で先進国である欧米諸国に対して有利だったことを生かし、“良い物をより安く”の戦法で勢力を拡大してきた。
その戦法によって確立されたバリューフォーマネーというブランドイメージが、超円高時代を迎えて、日本メーカーを逆に苦しめているというのが今の状況だ。日本車は性能、耐久性、維持費など、計算高く考えた時に最良の選択肢の一つ。一方で、同じクラスの車と比較して、たとえば2割値段が高くてもぜひ買いたいという付加価値の高さを感じさせるような車を作れたというケースは非常に少ない。
付加価値拡大に最も力を入れてきたのはトヨタ自動車である。89年にアメリカで高級車チャネル「レクサス」を展開し、日本車は安物というイメージを覆すことに、ある程度成功した。その後、日本、欧州でもブランド化するなど、収益力の高い高級車分野の拡充に取り組んでいる。
しかし、そのレクサスとて、本当に高付加価値戦略を成功させられているとは言えない。2012年の夏、トヨタは前輪駆動型の高級車「レクサスES」の新型モデルをアメリカに投入した。価格は排気量3.5リットルのV6エンジンを搭載したもので3万6100ドル、トヨタお得意のハイブリッドモデルで3万8800ドル。ドイツの高級車メーカー、アウディのなかで車体の大きさが近く、装備も同レベルの「A6」に比べ、ものによっては1万ドル以上も安い値段で売られているのである。かつてアメリカで大人気となったフルサイズセダンの「レクサスLS」も、価格的にはメルセデス・ベンツ、BMWの同格モデルに比べてはるかに安い。
富士重工との共同開発モデルであるスポーツカー「86」のトヨタ側チーフエンジニアを務めた多田哲哉氏は、
「86はリーズナブルな価格のスポーツカーということを売りの一つにしていますが、全部が安い必要はない。お金をかければもっと走りが良くなる。丹精を込めて走りを磨いた400万円、500万円という価格帯の特別モデルがあってもいい」
と、高付加価値への挑戦に意欲を見せる。
トヨタは他にも「G's」と名付けた特別な車の販売にも力を入れている。コンパクトカー「ヴィッツ」、高級セダン「マークX」などいろいろな車に、ボディを補強したり高級なブレーキを装備するなど大規模な改修を加えたもので、車によっては普通のモデルに対して60万円ほど高い。そのぶん、性能も欧州メーカーの高付加価値モデルに近い。
「トヨタもこういう車を作れるんだということを世界のお客様に伝えたい。(豊田)章男社長は就任以来、ずっと“もっといい車を作ろうよ”と言い続けています。先進国メーカーの生命線である付加価値の拡大を実現するうえで、いい車を作り、それをユーザーに理解、共感してもらうのは一番大事なこと」
トヨタの車作りを長年手がけてきたベテランテストドライバーはこう語っていた。
本来ならば、最初からそういう車を作って、それを50万円、100万円高く売り、顧客が最初からトヨタ車にはそれだけの価値があると考えて買うというのが理想なのだが、現時点ではそうはなっていない。ブランドを育てていくには、10年単位の長い年月がかかるもの。それに継続して取り組んでいこうというのが、トヨタが先進国ビジネスにおいて取ろうとしている基本戦略なのである。
欧州は“惨状”が続く
オデッセイからフィットへ、フィットから軽自動車へと、販売価格がどんどん下がっているホンダとて、ブランドイメージの重要性を軽視しているわけではない。
もともとホンダは、他の日本車メーカーにはない、独特のブランドイメージを築いてきた。1960年代、まだ4輪車を市販していない時期にいきなりモータースポーツの最高峰であるF1に参戦して2年目に優勝。70年代、当時は技術力の面で優勢だった欧米メーカーさえ対応不能としたカリフォルニアの排出ガス規制「マスキー法」をクリア。日本勢の先陣を切って北米に工場進出。80年代にはF1でホンダエンジンが無敵の快進撃――といった数々のチャレンジと成功によって、ホンダは不可能を可能にするという、いわゆる“ホンダ神話”が生まれた。そのイメージは、事あるごとにホンダを成長させ、あるいは苦境から救うことに貢献してきた。
今日、ホンダが苦しんでいるのは、そのホンダ神話の象徴である「H」のマークの輝きが色褪せていくのを止められないことだ。
トヨタに対抗して2009年以降、ハイブリッドカーのラインナップを大幅に拡充したが、最大市場であるアメリカで大惨敗を喫し、今や韓国勢の現代自動車のハイブリッドカー1車種にも負けるという有り様。欧州では人気の高いディーゼルエンジンのラインナップが薄いことも災いして、「経営効率だけ考えれば撤退するしかないというくらいの惨状」(ホンダ幹部)である。
 ホンダの軽の原点。
ホンダの軽の原点。何より痛いのは、ホンダ神話の根幹をなしていた技術イメージの高さが崩れ始めていることだ。
あるライバルメーカーのASEAN現地法人首脳は、現地を訪問した人に「最近のホンダの動向がわからない。何もやっていないように見える」と語ったという。現実的に考えれば、研究開発費を年間5000億円も投じる企業が技術開発をやらないことなどあり得ないのはすぐにわかる。にもかかわらず、何もやっていないように見えてしまうのは、技術イメージが希薄になっていることの表れにほかならない。
実際のところ、ホンダの研究開発の実情はどうなっているのか。
12年11月、ホンダはまもなく投入する次世代型ハイブリッドシステムをはじめ、多数の新技術を発表した。それらの技術を盛り込んだ試作車に乗ったというジャーナリストは、次のような見方を示す。
「次世代ハイブリッドはこれまでのものよりずっと効率が高く、またそれ以外の新型エンジンの完成度も非常に良かったが、それらは他社との競争に負けないための、いわば必修科目のようなもの。ホンダの独自性が感じられたのはむしろ、簡単な機構で走りを格段に楽しくする新しい車両安定システムなどのデバイス。これは運転にあまり慣れていない女性新聞記者もミニサーキットを走って面白がるほどだった」
しかし、最も興味深かったのは技術そのものではなく、研究所の若手から中堅のスタッフのメンタリティの変化だったという。
「本田技術研究所は昔から、エンジニアにチヤホヤすることによって、モチベーションを上げてきたという風土があった。何があっても自分たちの技術は負けてないと、時には詭弁を弄してまで強弁するようなことも、つい最近まで多々あった。しかし、今回驚いたのは、そのエンジニアたちの間に少なからず危機感と問題意識が芽生えていたこと。それは技術力で勝つ・負けるということ以上に、いい車を作るには車のハードウェアだけでなく道路やドライビングをもっとよく知らなければならず、また、いいものを作ってもユーザーにどう共感してもらうかを考えなければホンダのブランドイメージの再興はない、という危機感です」
もともとホンダのクルマ作りの実力は、ホンダ神話が輝いていた頃と比べても、次元が違うほどに進化している。ホンダが国内で売り出したものの苦戦を強いられているSUV「CR-V」などは、価格は安めでありながら、静粛性、乗り心地の滑らかさなど、多くの点ですでに高級車レベルである。前出のジャーナリストは、「内外装のデザインセンスが絶望的にダサいことだけが課題でしょう」と苦笑する。
北米偏重の大きな代償
実は、この部分にホンダ再興のカギの一つが隠されている。それは、成功体験の呪縛だ。北米向け「アコード」やCR-Vなど、ホンダの主力車種のデザインが野暮ったいのは、ホンダにデザインの実力がないからではなく、アメリカ人の好みに合わせてあるからだ。「北米では、欧州車のようなデザインセンスを持たせた車は数が出ない」(トヨタ幹部)のだ。
ホンダにとって、北米は今も最大顧客である。その市場を失うようなリスクを冒すことは到底許されない。が、ホンダはその北米市場に目が行くあまり、北米向けだけでなく、他地域向けの車まで野暮ったいイメージになってしまっている。北米ビジネスを手がけている派閥の社内発言力が大きすぎるためだ。
軽自動車へのシフトもまた、成功体験の呪縛になりかねない可能性がある。「ホンダは何かがうまくいくと、そこに2匹目、3匹目のドジョウを求め、他のことをやらなくなりがちなところがある」(本田技術研究所幹部)からだ。実際、早くも日本国内では軽自動車一色のマーケティングになってしまっており、このままでは足元市場での評価は「軽のホンダ」になってしまいかねない。
過去の成功体験の呪縛を打ち破り、新しいことにチャレンジして社内を活気づける旗振り役となれるのは、社長である伊東孝紳氏だけだ。その伊東氏が自分の花道作りにいそしむのか、本田技術研究所のエンジニアたちに芽生えている“変革意識”をうまく誘導して新しいホンダ神話を作り、Hマークを再び高い価値を持つブランドとして輝かせることができるのか。その力量が今、問われている。
(ジャーナリスト・杉田 稔)