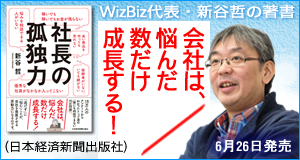2013年1月号より

怒涛の軽自動車投入計画
 「ホンダDNA」について説明する、浅木泰昭・本田技術研究所主任研究員。
「ホンダDNA」について説明する、浅木泰昭・本田技術研究所主任研究員。「HONDAがヘンだ!」と題し、特集でホンダらしさの検証をしたのがちょうど1年前。
看板車種の「フィット」以外、これといった大きな話題もなくなっていた同社が、軽自動車テコ入れを具体的に表明したのが2011年10月27日だった。この日、同年12月に開催される東京モーターショーに出品する、「N BOX」を初めて披露したからだ。同車は、一見すると他社のハイトワゴン系の軽と変わり映えしない印象だったが、当時、松本宣之・執行役員四輪事業本部第3事業統括(現在は常務執行役員)は、こう語っていた。
「スモールカーと軽を自前でやっているのはウチだけ。OEM(相手先ブランド車の供給)もしません。本日は、その決意表明でもあります。パッケージングとスポーティさの両立で先進性を見せていく。これからは我々も軽に本腰を入れ、“第2の創業”のつもりで、当社の原点である軽に挑みます」
 手前が「N BOX+」、奥が「N BOX」。いまや軽市場を牽引するクルマだ。
手前が「N BOX+」、奥が「N BOX」。いまや軽市場を牽引するクルマだ。こと国内市場においては、新車販売に占める軽のシェアは4割に迫り、完全に主戦場になった。少子化と超高齢社会、不況下での維持費安などの状況から考えても、軽は今後も主役であり続けそうだ。自動車メーカーにとっても、円高による国内生産の空洞化を補う手立てになる。
その軽市場を軽視していたホンダは、1年前までは完全に遅れをとっていた。新しくN BOXを1車種投入した程度で劣勢を挽回できるのか、懐疑的に見る向きのほうが多かったといってもいい。
あれから1年。結果は右の表の通りである。ホンダのこの驚異的な数字は、ちょうど10年前の02年、年間の新車販売台数で、フィットがトヨタ自動車の「カローラ」を抜き去った衝撃にも似ている。

N BOXはフィット譲りのセンタータンクレイアウト(ホンダの特許)によって広大な足元空間を実現したものの、「やっと軽自動車にもスライドドアを導入し、CVT(無段変速機)が搭載された。他社では従来から当たり前の装備でしたから」(東京都内のホンダカーズ販売店の営業マン)と、居住空間のアドバンテージ以外、当初は、それほど独創性ある商品とは認識されなかった。
にもかかわらず、N BOXは大ヒットになった。これが他社とは違う、“HONDA”というブランド力の差なのか、販売的に売り切る力がついたのか。12年夏に出した派生車で、さらに使い勝手で一ひねり加えた「N BOX+」の投入もヒットを底上げしたが、前出の松本氏の「第2の創業のつもりで軽に本腰を入れる」という言葉を受け止めるには、まだ物足りなさは残った。
ホンダの“変心度”が伝わってきたのは、同社の伊東孝紳社長が会見し、今後の車種展開を明らかにした、12年9月21日からだ。会見の場で、11月1日に発表することになる「N-ONE」を含め、なんと6車種もの新型軽自動車を15年までに投入すると宣言したからだ。
「フィット」の将来は?
すでに、軽のオープンスポーツカーを開発することは明らかにしているが、N BOXで広さを追求、N-ONEでかつての「N360」(45年前の1967年に登場)を現代版にリモデル、オープンスポーツも計画するとなると、残りで考えられるのは、ズバ抜けた燃費性能を誇る軽や、デザインの自由度が高くなるSUVタイプの軽あたりだが、それでもあと2車種ある。要は、Nシリーズのプラットフォームを最大限に共通化して活用し、軽のフルラインを早期に、しかもすべて自前で展開しようというわけだ。数年後のホンダは、「“小型車も手がける”軽メーカー」というポジションになっているかもしれない。
実際、最大の看板車であるフィットは、13年にフルモデルチェンジを控えたモデル末期ということも重なり、快走する軽市場とは裏腹に、販売は大きく失速している。同車の、過去10年の購入者という母数を考えれば、これからも一定の買い替え需要は見込めるだろうが、Nシリーズの軽が、走行性能、安全性能ともにフィットを凌駕するほどのレベルになったいま、フィットはフルモデルチェンジ後も、絶頂期の販売台数を果たして稼げるだろうか。

フィットのモデルチェンジについてはすでに、派生車種も2車種アナウンスされており、セダンタイプのほうは「シティ」という往年の名が日本でも復活し、小型SUVも用意するという。セダンやSUVの投入はあくまで海外が主体で、日本はおまけ程度なのだろう。Nシリーズ同様、フィットの新しいプラットフォームを最大限生かして、ワールドワイドに生産効率も収益性も高めようという狙いは見てとれる。
ホンダは過去も、大きな“変心”を見せてきた。1980年代半ばから後半、車高の低いクーペスタイルやハードトップ車でスポーティイメージを確立したが、バブル崩壊後の停滞時期を経て、90年代前半、ミニバンやSUV路線に大きく舵を切った。さらにその後、「オデッセイ」「ステップワゴン」「CR-V」といった90年代に売れた主力車種は、フィットの登場後から徐々に影が薄くなっていく。
代わりに、フィットのプラットフォームを用いた小型ミニバンの「フリード」がスマッシュヒットにはなったものの、再び停滞期を迎えていたのが、1年前までのホンダの姿で、そこで出した答えが、「軽シフト」へのアクセル全開だったわけだ。
N BOXに引き続き、N-ONEの開発責任者を務めた、本田技術研究所の浅木泰昭・四輪R&Dセンター主任研究員は、N-ONE発表会でこう語っている。
「N360の現代版といっても、つまらなければ“ゾンビカー”と呼ばれてしまう。このクルマは、Nシリーズの直系という意味を込めてN-ONEと名付けました。特に『ツアラー』(=ダウンサイジング過給のターボ搭載車種)は、1300cc以上のクルマの走行性能があり、エンジン音もとても静か。走行安定性も、フィットより長いホイールベースで高いレベルにある。合言葉は、フィットを超える軽を開発しようということでしたから」
ただし、浅木氏は囲み取材時には、「特に安全性能については、ここまで本当に軽に必要なのかという思いが、正直いまもある」と漏らしていた。
同氏が指摘する、安全性能てんこ盛りの一例が、軽自動車では初めての導入となった、「エマージェンシーストップシグナル」。走行中に急ブレーキと判断すると、ブレーキランプに加えて、ハザードランプも自動で高速点滅するというもの。が、華奢な骨格の軽だからこそ必要な技術ともいえ、将来、軽の「海外展開」を考えるなら、先送りしていてはいけない技術ともいえる。
一方、日本営業本部長を務める常務執行役員の峯川尚氏は、同じN-ONE発表会の場で、こうアピールした。
「N-ONEはホンダらしさに溢れ、クルマを持つ喜びをもう一度、消費者に感じてもらえるクルマ。本日の会場である六本木ヒルズ界隈でも、当たり前のようにN-ONEの姿が見られるはずです」
確かに、N-ONEの大きな売りの1つに、ボディとルーフの塗装色を分けるツートーンスタイルがあるが、これはスタイルも相まって「BMWミニ」を彷彿とさせ、デザイン上の演出の上手さは伝わってくる。ただ、先行予約も上々というのがホンダ側の発表だったが、商業的な成否は、今後数ヵ月を見なければわからない。
一方で、特に東京都心部のホンダカーズの営業マンによるN-ONEの評価は、次のようにイマイチ冴えなかった。
「N BOXのような広さがあるわけでもないし、要は技研(=ホンダ)側の、過去の復刻版という思いが強い、プロダクトアウトのクルマです。デザインも売りとはいっても、競合他社で80万円を切る軽がある中では弱いですね。
加えて、都心部はマンションなどの集合住宅が多いので、機械式駐車場が圧倒的です。なので、N-ONEの高さ(1610ミリ)では駐車場に入らないんですよ。同じ入らないなら、さらに背高で広いN BOXのほうが売りやすい。レトロカーなら、かつて日産が出した『Be-1』のような、イメージ作りを主眼としたクルマのほうが良かったのでは。正直、ウチではN-ONEの受注は、まだポツポツです」
駐車場事情は、首都圏郊外や地方に行けばまた大きく変わりそうだが、都心部では、売りづらいクルマというのが本音のようだ。
水面下で“地殻変動”?
ここまでは4輪事業を見てきたが、ホンダの事業展開のメリハリは、水面下でもっと進んでいると見る向きもある。たとえば航空ビジネス。トヨタ自動車も、かつてセゾングループだった朝日航洋というヘリコプター運航会社を持つが、ホンダも独自開発した、小型ジェットの量産化体制に入りつつある。
 2012年9月21日に今後の戦略説明で会見した、ホンダの伊東孝紳社長。
2012年9月21日に今後の戦略説明で会見した、ホンダの伊東孝紳社長。これに関連してか、ある航空関係者は、「地域航空について、ある専門家が講演した後、ホンダがその講演の原稿入手をしつこく要望したと聞いている」と言う。
この関係者は、ホンダは将来、地域航空のエアラインに資本参加したい意向も持っているのではないかと感じたという。
一方で、あるホンダOBの一人はこう語っていた。
「もちろん4輪や2輪の事業ではないけど、もう1年以上前から、ほかの事業では売却も含めた検討をいろいろしているらしい」
航空関連では積極的な動きが出ているが、他方で撤退・売却の事業を模索することも辞さないのだとすれば、根幹の4輪車事業で見せた今回の軽シフト以上に、ホンダという企業の全体像は、さらに変わっていくかもしれない。
(本誌編集長・河野圭祐)