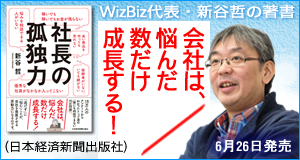製造業、サービスを問わず、企業には「◯△の生みの親」、「△◯の達人」と呼ばれる人がいる。
そうした、いわば「匠の技」の数々がこれまで日本経済の強さを支えてきたのだ。日本の競争力低下とともに、そこがいま揺らいでいるという指摘が多いからこそ、各界の匠にスポットを当ててみたいー。
2013年11月号より
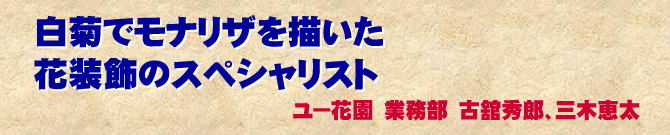
葬儀用装花で日本一
東京・世田谷区桜新町に本社を持つ花屋「ユー花園」。創業者の山田祐也会長が世田谷区下北沢に最初の店をかまえてから、すでに54年を数える老舗の花屋である。
店頭での生花販売だけではなく、葬儀用装花、ブライダル・ホテル用飾花なども手掛けている。
都内にある日航ホテル東京(お台場)、ザ・ペニンシュラ東京(日比谷)、コンラッド(東京)内に飾られている花は、すべてユー花園の手によるものだ。
しかしそれ以上に大きなボリュームを占めているのが葬儀用装花で、これを手がけることでユー花園は大きく成長した。
とはいえ最初は苦労の連続だった。葬儀社に花を提供しようと思っても、葬儀社ごとにつきあいのある花屋がいて、容易に入っていくことはできなかった。そこで創業者は、毎日のように斎場に出かけて行っては、葬儀社の人の祭壇づくりをだまって手伝っていた。そうやって顔見知りになったうえで、もう一度営業をかけることで、徐々に取引先を増やしていく。
後発だからこその工夫も欠かせなかった。従来の花屋は、斎場でジャンパーに長靴で仕事をしていた。水に濡れた花を扱うのだから当然といえば当然なのだが、ユー花園では社員にスーツとネクタイを義務付けている。葬儀社の人たちは必ずスーツ姿なのだから、花屋もスーツで仕事をするのが当然、との考えに基づくものだ。
仕事のやりかたも、従来の花屋は祭壇ができるとそこに花を運び込んで終わりだったものを、葬儀社の人と一緒に、祭壇の飾りつけから後片付けまでずっと一緒にするようにした。花のプロであるユー花園の社員が飾りつけをやったほうがきれいにできるのは当たり前。葬儀社が喜ぶだけでなく、遺族も参列者も喜ぶ。それがユー花園の仕事のやり方だった。
さらには、飾りつけにも工夫をこらし、いまでは当たり前になった青竹に生花を挿すなどの新趣向を次々と生み出していった。こうした努力によって、ユー花園を指名する葬儀社がどんどん増えていき、現在、葬儀用装花の分野において、ユー花園は日本一の売り上げを誇っている。
創意工夫は日本一になったいまでも日常的に行われている。ユー花園では、葬儀用の花の装飾においては、「元気だったあの人が微笑みかけてくれるようなステージプランニング」を心がけている。厳粛な儀式である葬儀会場を、時にはしめやかに、時には華やかに飾り上げる。ゴルフ好きだった人の葬儀には祭壇をグリーンのように装飾するなど、遺族の思いに応えるために多彩なプランニングを用意をしているのがユー花園の特徴で、少しでも故人、遺族に喜んでもらおうと、日々、新しい提案を行っている。
今年8月、東京・お台場のホテル日航東京で、ユー花園の葬儀用装花の内覧会が開かれた。この内覧会では、ユー花園が提案する新しい演出を見ることができたが、ひときわ目を引いたのが、白菊でつくられた「モナリザ」だった。
 祭壇用の装花をつくる古舘秀郎氏(左)と三木恵太氏。
祭壇用の装花をつくる古舘秀郎氏(左)と三木恵太氏。このモナリザをつくったのが、業務部第4課係長の古舘秀郎氏と、業務部第1課主任の三木恵太氏。古舘氏は入社13年目の32歳、三木氏は8年目の30歳だ。
2人ともユー花園に入る前は、それほど花と親しんでいたわけではない。しかし「デスクワークがいやで、現場で汗を流したい。体を動かしたかった」(三木氏)、「ものをつくることに興味があった」(古舘氏)ことから、入社以来、祭壇用装飾にたずさわり、2人とも、「生花祭壇検定S級フラワーデザイナー」の資格を持つ。
これは、ユー花園の社内検定なのだが、いちばん下のD級を取るのに3年間、以降、C、B、Aと上りつめていった最上級の資格がS級だ。
各自が、ほぼ毎日、1つの現場を担当するなど、多忙な毎日を送っている。2人とも「遺族の方に喜んでもらった時に、この仕事をやってよかったと思います」と口を揃えるが、その日々の仕事の中でも、「こうすればもっと喜んでもらえるのではないか」と考えているという。モナリザのアイデアも、そうした中から生まれてきた。
ユー花園では以前から、「文字祭壇」を提案してきた。これは2.7メートル四方(四畳半)の枠の中に、花で「愛」「響」など、故人を偲ぶのにいちばんふさわしい文字を表したもの。そして今度は人の顔を花で描こうというわけだ。
「モナリザを選んだのは、誰もがその顔を知っているため」(三木氏)というが、これまで生花によって人の顔を描くのは不可能と言われてきた。それにチャレンジしたのだ。
不可能を可能にした自信
ホテル日航東京での内覧会で2人は、招待客の目の前でモナリザを描いた。その様子はユーチューブでも見ることができるが、所要時間3時間半という大作だった。
当日を迎えるまでの前1週間、2人は練習を重ねた。
 8月に日航ホテル東京で行った白菊によるモナリザの実演。
8月に日航ホテル東京で行った白菊によるモナリザの実演。「最初の作品はどう見てもモナリザとは似ていなかった」(三木氏)
最初は、上から何センチ、左から何センチのところに目頭、というように、細かい位置を決めたうえで描き始めたがうまくいかない。結局、ポイントだけを決めておき、あとは現場で全体を見ながら微調整したほうがうまくいくことに気づいた。1本1本の花は、同じように見えて微妙に違う。その微妙な違いによって、全体の雰囲気も違ってくる。それを現場で最適な花を選びながら置いていく。言葉にするのは簡単だが、実際には相当な苦労があったはずだ。
なかでもむずかしかったのが、目と口だ。目の印象は強烈なため、ここが違うとまるで似ない。また、「謎の微笑」の異名を取ることからもわかるように、微笑む口元が、モナリザをモナリザたらしめている。
「視線の方向や左右の大きさなどに気を使いましたね」と言うのは、目を担当した古舘氏。一方、口を担当した三木氏は「最初は、口の形を決めておいて、それに合わせて花を置こうとしたのですがうまくいかない。そこで、最初に口の部分を花で埋めておいてから、ポイントの花を抜くようにしたところ、うまくいきました」と振り返る。
最初は似ても似つかなかったモナリザだが、練習を重ねるうちにだんだん形になっていき、最後にはカメラを向けると顔認証するまでになったという。「その時はうれしかったですね」(三木氏)
内覧会の会場でも、モナリザは好評を博した。生花によって人の顔を描くという試みは大成功に終わった。
「最初はできるかどうか半信半疑でしたから、できた時には本当にうれしかったですね」(古舘氏)
「不可能といわれたものがここまでできたわけですから、むずかしいことでもやればできるという自信を持つことができました」(三木氏)
2人が語るには、モナリザを描くからといって特別な技術が必要なわけではないと言う。いつも現場で行っていることの延長線上にモナリザはある。
葬儀用の装花は、通夜の当日の午前中に本社内の作業場でつくられる。午後にはそれをいったん分解してトラックで運搬、葬儀会場でもう一度組み立てるという手順を踏む。しかし現場では、すべて予定どおりにいくわけではない。遺族から「こうしてほしい」という要望が寄せられるなど、その場で対応が求められることも多い。
「遺族の方、葬儀社の方などの要望を聞きながら、少しでもきれいになるよう心掛けています。それには現場での臨機応変な対応が必要です」(古舘氏)
前述したように、ユー花園ではフラワーディレクターをD級からS級にランク分けしている。ランクが違えば、技術、スピードなどが違うのは当然だが、現場対応力も大きく差が開くという。
モナリザを描けたのも、花の個性を考えて、最適の1本を選び、より正確にきれいに飾る技術があってこそだった。
そして、さらに技術を高めていけば、故人の肖像を花でつくれるようになるだろう。愛する人を花の肖像で送ることが、当たり前になる時代が来るかもしれない。