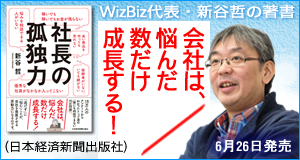2015年2月号より
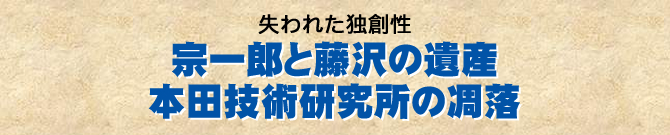
技術者の“聖域”
ホンダのモノづくりの特色のひとつに、研究開発部門の独立性の高さがある。通常、自動車メーカーは先端研究を行うラボは別として、社内に研究開発部門を持つのが一般的である。が、ホンダの場合はちょっと違う。研究開発を一手に引き受けている本田技術研究所は、ホンダの100%出資の子会社ではあるが、組織としては独立した別会社だ。
従業員数は研究員、間接部門を合わせて1万3000人という大所帯。社長や役員もホンダ本体とは別にいる。ホンダは2014年度、6450億円という巨額の研究開発費を投じる計画だ。研究所はその潤沢な資金を受け取り、商品であるクルマやバイク、将来技術、また生産技術の一部などを開発するのである。約5000万円という従業員1人あたりの人件費込み予算の数字は、世界の自動車メーカーのなかでもトップクラスの高さだ。
「本社の業績や意見に左右されることなく、エンジニアが自由な着想でものづくりができるように」――本田宗一郎と共にホンダ創業に大きな役割を果たした藤沢武夫のアイデアにもとづいて1960年に発足した本田技術研究所は、かつては本社の経営陣もおいそれと口出しできない、“技術者の聖域”と呼ばれるほどの独立性を有していた。
4代目社長の川本信彦が90年代、開発の効率化や市場のニーズのくみ取り力の強化をめざして本社と研究所をクロスオーバーさせるという改革を断行したのを境にやや弱まったとはいえ、今日でも他メーカーに比べると独立性は桁違いに高い。
その本田技術研究所が今、深刻なモノづくり力の低下に苦しんでいる。昨年登場させた新しいハイブリッドシステムやタカタのエアバッグなど、多くの分野で開発陣のボーンヘッドともいえる稚拙なリコールを連発してしまったことは記憶に新しいが、問題はそれだけではない。ホンダの業績を上向かせる一番の特効薬は、ヒット車種を生み出すことだが、04年に福井威夫が6代目社長に就任して以降、今日まで爆発的なヒットモデルをろくに出せていないのだ。
「リーマンショック前、アメリカで販売台数を伸ばしたため、世間ではホンダは成長していると受け取られていましたが、内情は厳しいものでした。販売が好調なモデルはどれも過去の遺産と言うべきものばかりで、ホンダが市場を開拓したと胸を張れるようなモデルは1台もなかったと言っていい。伊東(孝紳)さんが社長になってからも、状況はほとんど変わっていません。軽自動車のホンダになってしまいました」
本田技術研究所の中堅エンジニアは、開発力の低下を嘆く。
「それにもかかわらず、研究所内ではどのチームも自分たちがいかに失敗していないかということをアピールするのに必死。度重なるリコールも、何とか世間に騒がれないようにすれば“人の噂も七十五日”で、うまく軟着陸できる、くらいにしか思っていない。厳しい現実を直視せず、状況をどう解釈して宣伝すれば自分たちに都合がいいかということばかり論じている様子は、まるで敗色濃厚となった第2次大戦末期の大本営のようです」
戦略なき新車開発
研究所の士気は今、ホンダ創業以来と言ってもいいほどの危険水準にまで低下している。13年来のハイブリッドに関する連続リコールが一段落したことで、1年近く停滞していた新車投入を14年12月にようやく再開した。先陣を切ったのは、ハイブリッド専用セダンの「グレイス」である。
発表会で演説を打ったのは国内営業トップの峯川尚専務執行役員。「コンパクトセダンのベンチマークとなるようなクルマを目指して開発した。広い室内、上質な乗り心地、しなやかな走りを実現させた」と、誇らしげに語った。
が、このグレイス、正体をひもとくと、インドや東南アジアなどの新興国向けに作られた、いわゆるアジアンカー。ベースとなっているのはフィットだが、アジア市場で売るために極力低コストで作る必要があったため、車体の基本構造を大きく変えることができず、ずんぐりむっくりとした不格好なデザインになってしまった。
 ホンダを牽引した本田技術研究所(埼玉県和光市)
ホンダを牽引した本田技術研究所(埼玉県和光市)「クルマづくりを手がける人だったら誰でも、あんな付け焼刃みたいなモデルではなく、もっと乾坤一擲の素敵なクルマを作りたいと本音では思っている。お客様に“このクルマはデザインが素敵なんですよ”と詭弁を駆使して力説したところで、お客様がなるほどなどと思ってくれるわけがない。社内で上司が部下に、どうだ俺のクルマはかっこいいだろうと同意を強要するのとは、わけが違うんですから」(前出の研究所エンジニア)
15年1月に発売する高級車の「レジェンド」は新興国向けではないが、もっぱらアメリカ市場をターゲットにつくった「アキュラRLX」というモデルを右ハンドル化して持ってきたもので、日本では“ついでに売る”〟というイメージだ。
「アキュラは、13年にアメリカで新型を投入したものの、さっぱり売れずに大敗北を喫し、月200台くらいで推移している。14年の秋には鳴り物入りでハイブリッドモデルを追加しましたが、それも1カ月に数十台しか売れないというありさま。日本では月300台という目標を掲げています。アメリカをターゲットとしたクルマを日本でアメリカ以上に売るというのは、どだい無理な話だとは思うんですが、ちょっぴり売れるだけでもホンダにとっては御の字なのかもしれませんね」(レジェンドのメディア向け発表会に出席したジャーナリスト)
日本市場ではもともと、アメリカ向けのクルマは基本的に販売不振になる傾向が顕著だ。新興国向けのモデルもしかり。日産自動車のコンパクトカー「マーチ」は現行モデルで新興国モデルに切り替えたところ、販売が激減。三菱自動車は「ミラージュ」を超低燃費モデルとして売り出したが、こちらも販売不振になっている。
ホンダがアメリカモデルや新興国モデルを日本で売るという筋の悪い戦略を取らざるを得ないのは、福井、伊東の2代にわたって、自分たちが比較的得意とする市場や、成長性が高くて何をやっても成功する市場ばかりを重視してきた結果、日本で売れそうなモデルがグローバルラインナップからほとんど消えてしまったためだ。
「福井、伊東の両社長は、どちらも台数を増やし、自分の売名を図ることにしか興味がなかった。基本的にはアメリカ、中国、新興国さえよければ、あとはどうでもいいという戦略です。日本市場については、ひとえにフィットで台数を稼げているおかげで崩壊せずにすんでいるようなものです。さすがにそれではまずいということで、福井氏はハイブリッドカーの『インサイト』を送り出しましたが、これが空前の大失敗で、日米欧の3大市場でまったく売れませんでした。伊東氏に至っては、台数を稼げるなら軽自動車でもいいと、国内市場には興味もないという態度でしたよ」(元ホンダ幹部)
このような状況で、クルマづくりを手がける研究所の士気が維持できるわけがない。研究所では今、軽自動車のオープンカーとハイブリッドスーパースポーツの2種のスポーツカーを開発しているのだが、「エンジニアの多くは、しょせんホンダの体面を保つためにつくっているにすぎず、ホンダのブランドイメージを底上げするような骨太の戦略があるわけではないと見切ってしまっている」(元ホンダ関係者)というのが実情のようだ。
保守的な技術陣
そんな技術研究所に、あるとき伊東が檄を飛ばした。
「諸君の半分がいなければお金が浮いて、ホンダはもっと儲かるんだ」
もちろん伊東も本気で人員を半分にすればいいと思っているわけではないだろう。研究所の奮起を促すつもりで言ったことは明白だが、いくら何でも言葉が悪かった。研究所では、かえって厭戦気分が広がったという。
ホンダに詳しいある自動車ジャーナリストは、
「伊東氏がそんなことを言ったとすれば、それは人の心をあまりにも知らない、経営者としてはあるまじき台詞だと思います。が、一方で本田技術研究所のほうも、1万3000人も人員を抱え、潤沢な開発資金を受け取っているわりには商品でのアウトプットがあまりになさすぎるのも事実。つまり、どっちもどっち」
と語る。
「ここ20年ほどのホンダの商品展開を見ると、本当の意味でホンダらしさの源泉である革新的な価値があったのは、初代フィットくらいしかない。あとは、ホンダ自身は真価を理解していないようですが、軽自動車のライバルメーカーから賞賛されている『N-ONE』くらいでしょうか。94年に発売されたミニバンの『オデッセイ』は、ホンダらしさという点ではそうでもありませんでしたが、時流に乗って売れた。
でも、そういうモデルは数代モデルチェンジを重ねるうちに売れなくなる。欧州市場ではすでに存在感はゼロ、アメリカでは一見好調ですが、すでに個性的なブランドというイメージはなく、白物家電のような存在になっています。本田技術研究所は悔しいという気持ちがあるなら、商品で見せつけてくれないといけないのですが、そういう気概はかなり前から薄れている」(前述のジャーナリスト)
本田技術研究所は、かつては「シビック」で日本とアメリカの市場を席巻したかと思えば、お洒落な2ドアクーペの「プレリュード」で若者を取り込んだりと、まさに変幻自在のモノづくりをしていた。
また、今ではエンジンの熱効率を高めるうえで欠かせない技術となっている「可変バルブタイミング機構」を世界に先駆けて量産車に採用したり、エアバッグやアンチロックブレーキなどの安全装備を日本メーカーとしては真っ先に搭載するなど、先進性の面でも抜きん出ていた。さらにモータースポーツの世界でも最高峰レースであるF1で大活躍していたことはよく知られている。
研究所の八面六臂の活躍ぶりは“ホンダ神話”と評されるほどで、ホンダのブランドイメージを高めるのに一役買っていた。しかし、今の研究所には、そのような進取の機運はない。モノづくりは保守的となり、冒険を極度に恐れるようになってしまっている。
経営者から研究所のエンジニアに至るまで、ホンダマンが事あるごとに口にするセリフのひとつに「ホンダは失敗が許される会社」というものがある。創業者の本田宗一郎や、その薫陶を受けた世代がホンダの経営に関わっていた時代は、東証1部上場クラスの企業としては異例と言ってもいいほどに失敗が許される社風があった。本田宗一郎が「失敗は成功するための種の宝庫」「ダメなことがわかることは素晴らしいこと」などと言っていたためだ。
が、今日の研究所において、そうした風土は雲散霧消していると、本田技術研究所OBは語る。
「見かけ上は今も失敗しても許されるケースは多いんですが、昔とは明らかに違う。昔は失敗を総括したうえで許され、再チャレンジさせてもらえた。今は、失敗をうやむやにして責任を負わないで次のことをやるという感じです。誰も責任を取らず、失敗から学ぶこともない。失敗が成功のもとにならず、同じような失敗を延々繰り返すんですね」
流動性なき組織
なぜ失敗をうやむやにしてしまうような体質になってしまったのだろうか。
「研究所も大所帯になり、所内は無数のチームに細分化されています。そのチーム間で、出世のために激しい足の引っ張り合いが起きるんですよ。失敗を失敗として認めたら、たちまち攻撃の材料になってしまう。そうならないためには、見識やセンスに裏打ちされた“大岡裁き”のようなものが必要なんですが、それをなすべき上層部も世代交代を経て、今や足の引っ張り合いの中で出世してきた人たちが主体で、とてもそんなリーダーシップは期待できません。下のほうも、上に対してモノを申す勇気など持てない。そのような状況の中で、社内を殺伐とした雰囲気にしないためには、失敗はなかったことにするというのが一番なんです」(前出の研究所OB)
 本田宗一郎と藤沢武夫。本田技術研究所は両創業者思いが込められていた。
本田宗一郎と藤沢武夫。本田技術研究所は両創業者思いが込められていた。かつて“ホンダ神話”の立役者であった本田技術研究所は、今や大企業病に蝕まれて自立的な回復は見込めないような深みにはまってしまっているのだ。
その状況をホンダは自力で変えることができるのか。やるとすれば伊東、もしくは研究所の山本芳春社長が強力なリーダーシップを発揮する必要があるのだが、社内からは、
「山本さんは研究所の中ではクルマづくりの本流からは外れてきた人で、人柄はとてもいいのだが求心力が強いとは言い難い。伊東さんは若い頃からプリンスとして育てられた人で、腰巾着タイプの人を可愛がってしまう。伊東さんの次は、その腰巾着の誰かが社長になり、また腰巾着タイプを下につけるでしょう」(ホンダ幹部)
と、悲観的に見る声が多く聞こえてくる。
とはいえ、本田技術研究所が大企業病を克服して活力を取り戻さない限り、ホンダのモノづくりは停滞したままで、たまに出るまぐれ当たりを当てにせざるを得ない状況から抜け出せない。どうすれば今の流れを変えることができるのだろうか。
まずやらなければならないのは、研究所に染み付いたテリトリー意識を打ち破ることだろう。現状では四輪車、二輪車、発電機などの汎用機の3つの大きなカテゴリーの間でのエンジニアの交流が、事実上、まったくない。たとえば二輪車のエンジニアにとっては、四輪車の開発を手がけるなどあり得ないことなのだという。汎用機、四輪車のエンジニアもしかりである。この流動性のなさは、1万3000人もの人員を抱えながら、特定の部署に仕事が集中したときに簡単にボトルネックとなってしまい、アウトプットが遅れる原因となっている。
「実はカテゴリーの改革は、社内の抵抗が最も大きくなると思われるもののひとつなんです。ですが、それができれば自分の専門に必要以上に固執することがなくなり、さまざまな経験をして視野を広げることができるかもしれない。もともと研究所は栃木、北海道の鷹栖など、極端な田舎が主体で、研究員は自分の人生に広がりを持てない。仕事だけでもバリエーション豊かになれば、発想の硬直化や無意味な部署間の軋轢は減る可能性がありますね」(前出のホンダ幹部)
もちろんそれだけで本田技術研究所の大企業病が治るわけではない。失敗の許される風土を作り直してホンダらしさを取り戻すためには、研究所とホンダ本社の首脳が自らを省みつつ、ホンダは変わらなければならないというメッセージを全社に発する必要がある。その道のりは果てしなく遠い。(本文中敬称略)
(ジャーナリスト・杉田 稔)