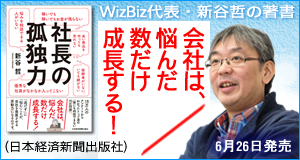2013年12月号より

5年前、米国に端を発したリーマン・ショックは、日本の電機業界を直撃した。ほとんどの企業が赤字に転落。前3月期の決算も芳しいものではなかった。しかしこの試練に直面して、企業は否応なく自己改革を断行せざるを得なくなった。その結果、業界地図は5年前とはまったく違う姿となった。横並びは影を潜め、得意分野を最大限に追求する姿勢へと変化したのだ。反撃の準備は整った。
5年の赤字総額4兆円
今年も10月1日から5日間、千葉市の幕張メッセで日本最大のエレクトロニクス見本市、CEATEC(シーテック)が開かれ、多くの電機メーカーや部品メーカーが、最先端の技術や製品を展示、会場は多くのエレクトロニクス関係者でにぎわった。
開幕当日には、多くの主要メーカー首脳も顔を見せたが、昨年までと比べると、なんとなく明るい表情をしているのが印象的だった。それは、日本の電機業界が置かれた状態と無縁ではない。
5年前の2008年10月に起きたリーマン・ショックは、世界の産業構造を激変させたが、日の丸電機メーカーに与えた影響も深刻だった。それを証明するのが、次の数字である。
08年度 ▲2兆1312億円
09年度 ▲943億円
10年度 3775億円
11年度 ▲1兆1394億円
12年度 ▲9757億円
5年間分すべて合算すると、3兆9641億円のマイナスとなる。
この数字は、本特集でも個別に取り上げている電機メーカー大手8社の、年度別最終損益の合計(黒字額から赤字額のを引いたもの)である。黒字になったのは10年度だけ。全メーカー合わせると、5年間で4兆円もの赤字を出したことになる。
日本の電機メーカーはこのまま没落してしまうのではないか。大手メーカーの中にも経営破綻するところが出るのではないか。昨年の今頃は、そうした論調の報道ばかりだった。
終戦から50年間、日本の電機メーカーは世界を牽引してきた。メイド・イン・ジャパンの家電製品は世界中で消費者の心を捉えていき、その結果としてアメリカではテレビメーカーが“絶滅”した。家電の日本一極集中状態がしばらく続いた。
1990年代半ばともなると、バブル経済の崩壊、円高の進行、そして韓国や台湾など新興国の台頭によって、徐々にその地位は低下していくが、それでも世界の中心は日本だった。
ブラウン管テレビに代わる薄型テレビの量産化にいち早く取り組んだのも日本メーカーだったし、DVDやそれに続くブルーレイといった記録メディアの規格も、日本メーカー主導でつくられていった。技術力にしても製造能力にしても、90年代までは日本優位が続いていた。
しかし90年代末から2000年代に入る頃になると、次第にほころびが目立つようになる。
かつては超優良企業と言われ、「石橋を叩いても渡らない」というほど堅実経営で知られた日立製作所が1999年3月期に創業以来初の赤字を計上したのはその象徴だった。
2001年度には松下電器産業(現パナソニック)が赤字となり、さらにはITバブル破裂の影響もあり、ソニー・ショックと呼ばれる株価暴落も起きる。世界の電機業界をリードしてきたビッグカンパニーの足元が、徐々におかしくなってきた。
日本企業がここまで追い込まれたのはAV機器におけるデジタル化の進展で、極端にいうと、電機メーカーはただのアッセンブルメーカーになってしまったためだ。デジタル部品を組み立てさえすれば、それなりの品質のデジタル家電ができてしまう。日本企業は新興国のメーカーに歯が立たなくなった。
それでもこれまでは生産拠点を海外に移転したり、AV以外の分野で補ったりしながら持ちこたえていた。苦しいながらも、市場全体は新興国の生活レベルの向上もあって確実に大きくなっている。ここを乗り切り、さらに生産性を上げることができれば、再び覇権を手にすることができるかもしれない。その思いで必死に耐えていた。
この一縷の望みを、完全に断ち切ったのが、リーマン・ショックだった。
リーマン・ショックによって、世界経済は一気にしぼんだ。同時にデジタル機器の価格は暴落、電子部品の市況も悪化した。それまで市場の膨張を前提にに生産計画を立て、設備投資を行ってきた企業は、一気にピンチに立たされた。
その結果が、冒頭に記した最終損益の合計である。
相次ぐテレビ撤退
中でも悲惨だったのがテレビメーカーで、パナソニック、ソニー、シャープ3社はいずれも巨額な赤字に転落、シャープにいたっては企業の存続さえ危ぶまれる事態となった。
かつてテレビは茶の間の中心にあった。時代は変わり、いまでは1室に1台が当たり前となったが、それでもテレビが家電の王様であることには違いない。だからこそ、多くのメーカーがテレビ事業を維持し続けたし、キヤノンのような“部外者”さえも、参入を目指したのだ。
しかしもはやテレビ事業は、そんな安易な気持ちで維持できるようなものではなくなった。各社とも、テレビ事業の大幅な見直しに着手せざるを得なくなった。日立はいち早く国内生産から撤退したし、東芝も最近海外生産への移行が明らかになった。
ほんの10年前までは、10社に迫る日本メーカーが国内でテレビを生産していたが、いまでは半減。しかもパナソニックやソニーでさえも、赤字が続く場合の撤退の可能性を否定しない。「テレビをつくってこそ電機メーカーは一人前」との常識は、まったく通用しない時代となった。価値観がまるで違ってしまった。
問題は、これをどう捉えるかだ。「電機業界の動向をずっと見ていると、リーマン・ショック直後はどう対応していいかわからず、リストラなど後ろ向きのことをやって、どうにかしてコストを抑えようとしていたものが、しばらくすると、これを企業が生まれ変わるためのひとつのきっかけにしようという動きが始まった」(IT業界ウォッチャー)
日本企業を批判する時によくつかわれる言葉が「横並び主義」だ。競合相手がつくっているから自分たちもつくる。テレビなどその代表例だった。しかしこの数年の電機業界の状況は、それを許さないほど厳しいものだった。だとしたら、いま一度自分たちの強みを確認し、それを最大限に活かしていく。同時に、不必要な事業は大胆に切り捨て、経営資源を強い事業に振り分けるしかない。否が応でも、そう考えざるを得なくなった。いわゆる「集中と選択」の徹底である。
電機メーカーの多くは、米ゼネラル・エレクトロニック(GE)にならって、1990年代から「集中と選択」を口にしていた。しかし現時点から振り返れば、それは極めて甘いものでしかなかった。事業構造を根本から覆すような変革は行ってこなかった。ところがここにきて、過去にない企業構造の変化が起き始めた。いちばんわかりやすいのがパナソニックだろう。
言うまでもなく、パナソニックは家電業界の覇者である。旧松下電工と旧三洋電機を本体に吸収したことにより、電化製品のみならず、配線や太陽電池にいたるまで、家の中の電気に関係するものは、ほとんどすべてを取り扱う会社となった。
ところがそのパナソニックが、「家電依存を改め、B2Bビジネスで成長していく」(津賀一宏社長)というのである。いままで消費者に向いていた企業が、企業を対象にしたビジネスに比重を置こうとしている。ある意味180度の方針転換だ。
 これから開発競争が激化するウェアラブル情報機器。日本企業の得意とするところだ。
これから開発競争が激化するウェアラブル情報機器。日本企業の得意とするところだ。パナソニックは5年後に創業100周年を迎える。その直前の大きな決断だった。悪く言えば、それだけ追い込まれているということであり、よく言えば、新しい可能性を見出したということだ。とにかく生き残り、さらなる成長を遂げるためにはなりふり構っていられないという必死さが見てとれる。
同じように、事業構造を大きく変えて、すでに成果を出しているのが日立である。
パナソニックが家電の覇者なら、日立は電機の覇者である。売り上げがいちばん大きいというだけでなく、重電、コンピュータ、通信、AV機器、白物家電と、およそすべてのジャンルの商品を手がけてきた。しかも昔から「自前主義」を貫いていたため、膨大な商品ラインナップをすべて自分たちでつくってきた会社だった。
ところがリーマン・ショックとほぼ同時期に、日立は自分たちの本業を定義し直し、それに基づき事業を選別していった。
すると、「イギリスで鉄道事業を受注」等々、大型案件を次々とモノにしていくようになる。本業に経営資源を絞り、全社挙げての取り組みが、功を奏したのだ。その結果、日立はリーマン・ショックの2年後にはV字回復を果たした。
復活の時は来た
残念ながら前3月期決算までは、依然として大赤字を垂れ流している企業もいくつかあった。しかしそうした企業であっても、体質は確実に改善されており、今期第1四半期決算では、いずれも黒字を計上している。間もなく発表される中間決算でも、好決算が相次ぐはずで、少なくとも最悪期は脱したといえる。重要なのは、これからどうやって成長路線に乗せていくか、である。
少なくとも外部環境は、日本の電機メーカーにとって悪くない。これは別に為替が円安に進んだとか、アベノミクス効果のことを言っているわけではない。いま世界が進もうとしている方向が、日本企業が得意とする分野と一致しているという意味である。
たとえば最近、話題になっているウェアラブル情報機器。これはポストスマホとも言うべきもので、メガネや時計のようにして身につけるものだ。この分野に関してはグーグルやサムスンが先行しているように見えるが、ソニーもすでに時計型スマホを出すなど、「かなり前から議論している」(平井一夫社長)
 CEATECで話題になった日産の自動操縦車。このクルマの中には電機メーカーの技術とノウハウが満載だ。
CEATECで話題になった日産の自動操縦車。このクルマの中には電機メーカーの技術とノウハウが満載だ。このような、技術を組み合わせ凝縮した商品というのは、日本企業がもっとも得意とするところだ。しかもこうした製品は素材の力を最大限活用しなければならず、日本にはすぐれた素材が揃っている。それらをきちんと組み合わせ、コーディネートする能力さえあれば、日本ほど、ウェアラブル製品をつくりやすい環境をもった国はほかにない。
あるいは冒頭に紹介したCEATECでも話題になっていた自動操縦車。ドライバーが何もしなくても、クルマが目的地にまで運んでくれるという優れものだ。
CEATECに出展していたのは、電機メーカーではなく、自動車メーカーの日産だが、クルマ自体は走る電気機器だ。その内部のほとんどを、電機メーカーに依存している。
また実際に自動操縦車が道路を走るには、街全体のインフラとして、自動操縦を可能にする情報システムを構築する必要がある。これなど、社会インフラや情報通信分野を手がける日の丸電機メーカーのもっとも得意とするところだ。
社会のIT化は、間違いなく、今以上に進んでいく。地球環境やエネルギー資源のことを考えれば、スマートハウス、スマートシティもどんどん増えてくる。これは誰にでも容易に想像がつく世界である。最初は先進国から始まって、やがては新興国にも及んでいく。ビジネスチャンスは無限といっていい。
つまり、電機メーカーの果たす社会的役割は、今後ますます重要になってくる。しかもハード単体ではなく、社会インフラを組み合わせた世界である。これこそ、日本企業の独壇場になってもおかしくない。
リーマン・ショックによって、電機メーカーの多くが危急存亡に陥った。しかしこれを奇貨として、他社にはない独自の強みを認識することができたのだ。そしてそれが活用できる社会がすぐそこに迫っている。日の丸電機が復権する条件は揃った。