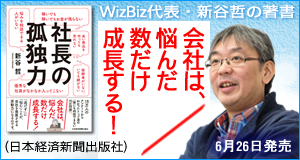2014年3月号より
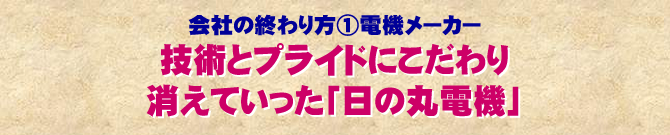
三洋電機の悲劇
年明け早々、パナソニックが子会社の三洋電機の社員を対象に、250人規模の早期退職を募集するとの記事がメディアを賑わした。見出しには「三洋電機 完全消滅へのカウントダウン始まる」とあった。
1947年に創業し(会社設立は49年)、一時は売上高2兆6000億円、全世界の従業員数10万人を誇った電機メーカーが名実ともに消えようとしているのだ。
三洋電機は松下幸之助の義弟(むめの夫人の弟)で、創業期から松下電器を支えてきた井植歳男が、戦後独立して設立した会社である。その意味で松下電器とは兄弟のような関係だった。事業領域は白物家電やAV機器など、完全に松下電器とかぶっていたが、高度成長期には、義兄弟会社同士、切磋琢磨することで、ともに成長していった。一時はデジカメメーカーとして世界一になったほか、太陽電池や二次電池では、松下を凌ぐ技術力を誇っていた。
しかし2004年の新潟県中越地震によって新潟県内の工場が被害を受け、特損を計上、これをきっかけに業績は年を追うごとに悪化していった。
 電機メーカーの再編はこれからも続く(写真は2013年のCEATEC会場)。
電機メーカーの再編はこれからも続く(写真は2013年のCEATEC会場)。いまから振り返れば、2000年代に入ってからの三洋電機は、日本の高度成長が終わったこともあり、ミニ松下として存続することはむずかしくなっていた。にもかかわらず、従来路線のままの企業存続を経営陣は指向し、またできると信じていた。その無理が会社の至るところに現れていた。
たとえば1980年代には同社製石油ファンヒーターによるCO2事故が起き、創業家の社長が引責辞任に追い込まれている。また90年代には太陽電池のデータ偽装が発覚、この時も社長が辞任した。
2000年代に入ると、三洋電機は中国の家電メーカー、ハイアールと提携、三洋がハイアール製品を日本国内で売り、ハイアールが三洋製品を中国で売ると発表した。当時の井植敏会長は、「三洋が国際的ブランドになるための第一歩」と胸を張っていたが、実際には、前途が描けなくなったがための苦肉の策でしかなかった。
05年秋には、業績悪化は誰の目にも明らかになり、大幅なリストラを行うとともにゴールドマンサックスや三井住友銀行などから3000億円の資本を受け入れざるを得なかった。これにより一時的に資金的余裕を得るがそれも長くは続かず、結局08年に、パナソニックがTOBによって三洋電機を買収することが決まり、最終的には10年にパナソニックの完全子会社となった。
パナソニックにしても義兄弟会社いう義理人情だけで買収を決意したわけではない。傘下に収めることで、エネルギー部門をもう一つの収益の柱にしたいとの思惑があった。当時の大坪文雄・パナソニック社長は、「三洋の得意なエネルギー部門は、AV、白物、産業用、住設に次ぐ5番目の柱となる」と、その意義を強調した。
ところが、実際には、買収した三洋は、金の卵を産むニワトリどころか、赤字を垂れ流すお荷物でしかなかった。
12年3月期、13年3月期の2年間で、パナソニックは1兆5000億円もの最終赤字を計上しているが、この中には、三洋電機ののれん代減損処理費2500億円も含まれている。買収時と比べ、三洋電機の企業価値が大きく減損したため、損失処理をしたというわけだ。
 2008年、三洋電機はパナソニックと提携、存続をはかったが……。
2008年、三洋電機はパナソニックと提携、存続をはかったが……。三洋電機の事業も、いまパナソニックに引き継がれているのはエネルギー部門などごく一部にすぎない。すでにすべての三洋ブランドはパナソニックに取って替わられただけでなく、白物家電部門は、かつて提携関係にあったハイアールに、わずか100億円という価格で売却されている。携帯電話事業は京セラに、半導体事業も米国の会社に売却された。
エネルギー部門でも車載用を除くニッケル水素電池が古河グループに売却されるなど、買収当時とは大きく陣容は変わっている。
すでに、現在パナソニックに残っている三洋社員は2000人ほど。その1割強を間もなく削減する。さらには大阪・守口市にある三洋電機旧本社は、守口市との間で売却話が進む。すでにブランドはなく、もう少し時間がたてば社員も旧本社も消えてしまう。三洋という会社の痕跡さえ残らないかもしれない。
パナソニックの完全子会社になってから5年もたっていないにもかかわらず、である。
ビクターはどこへ行った
さて、ここまで三洋電機の末路をたどってきたが、本稿は三洋電機だけを論じるものではない。
戦後の日本経済を支えたのは、まずは繊維であり、その後は電機と自動車だ。繊維はいち早く構造不況業種となったが、電機と自動車はバブル経済が破裂するまでは「貿易立国ニッポン」の象徴であり続けた。それが1990年代に入って明暗が分かれる。自動車業界は紆余曲折あり、資本の移動などもありながらも、トヨタ自動車を筆頭に11社体制がいまなお維持されている。
ところが電機業界は、もともと母数の大きさの違いはあるが、数多くの歴史のある企業が姿を消した。三洋電機はその中のひとつにすぎない。
三洋と同じくパナソニックと縁の深いところでは、日本ビクターも消えていった企業のひとつである。
日本ビクターはもともと米ビクターの日本法人として戦前に設立されたが、戦後、米国親会社が身売りしたことなどもあり、日本法人の業績は低迷していた。そこに救いの手を差し伸べたのが松下幸之助だった。いまではほとんど見ることはなくなったが、ビクターのトレードマークといえば、蓄音機に耳を傾けている「ビクター犬」だが、幸之助はこのビクター犬のマーク欲しさにビクター救済を決断したとも言われている。こうして日本ビクター株式の50%以上を松下電器が持つことになり、その関係は60年近く変わらなかった。
ビクターは白物部門を持たないが、AV機器においては完全に松下と競合する。しかし三洋電機同様、日本経済が右肩上がりの時は問題がなかった。松下とビクターは親子でありながら、競い合いながらともに伸びていった。
1970年代に、ビクターは家庭用ビデオ、VHSを開発する。VHSはソニーのベータ方式との競争に完全勝利し、ビデオのデファクトスタンダードとなる。この勝利によって、ビクターは大きく売り上げを伸ばしただけでなく、その特許料収入が毎年100億円単位で入ってくるなど、70年代から80年代にかけ、ビクターは超優良企業となった。
ところが90年代に入ると、さしもの「VHS神風」も弱まってきた。本来であれば、VHSで稼いだ資金を元手に次なる経営の柱を育てればよかったのだが、ビクターは「VHSの次はVHS」と、VHSのさらなる進化を目指した。S-VHSで高画質を実現するくらいならまだしも、ハイビジョン放送に対応してW-VHSなる規格を発表するなど、VHSにこだわりすぎた。世の中は、CDの発売以降、テープからディスクへと、大きく舵を切っていった。その流れにビクターは乗ろうともしなかった。成功体験が失敗要因になる典型的パターンだ。
90年代半ば以降、ビクターの業績は急速に悪化していく。松下電器も社長を送り込むなど、立て直しに本腰を入れるが、VHSを開発したという“自信と誇り”が松下なにするものぞという社風を生み、親会社の介入を容易に許さなかった。そのため、90年代後半には、ビクターの処遇が大きな経営課題としてのぼるようになる。
シナジー効果はほとんどない。しかも赤字企業で前途が見えない。しかし松下電器にとって、幸之助が買収を決めたビクターを、現経営陣の判断で売却するなどできることではなかった。結局、松下電器がビクターとの関係を見直すのは、幸之助の導入した事業部制を見直した中村邦夫社長の登場を待たなければならなかった。
07年、日本ビクターはケンウッドと資本提携、ついに松下電器の子会社でなくなった。さらに翌08年10月1日、ビクターはケンウッドと経営統合し、JVCケンウッドが誕生する。奇しくもこの日は、松下電器がパナソニックへと社名変更した日でもある。こうして長年続いた、松下とビクターの関係に終止符が打たれることとなった。
ビクターとケンウッドの経営統合には、当初、壮大なる目標があった。
「いつの間にか日本の電機メーカーは競争力を失った。これを復活させる責務が我々にはある。最初はケンウッドとビクターの2社から始めるが、もっと仲間を増やしていき、日の丸電機の象徴のような会社にしたい」と統合会社の社長に就任した河原春郎氏は語っていた。
ところが、この構想は画餅に終わる。統合直前のリーマン・ショックもあって、日本の電機メーカーはさらに苦境に追い込まれる。JVCケンウッドも自らが生き残るのに必死で、中堅メーカーの受け皿になることなどとてもできなかった。統合当時、ビクターとケンウッド合わせて8000億円あった売り上げは、いまでは3000億円程度。かつてビクターはVHSだけでなく、テレビ市場でもそれなりの存在感を保っていたが、いまではそれらの製品は残っていない。民生品で残っているのはカーナビと、廉価版のカムコーダー(ビデオカメラ)ぐらいなもので、あとは業務用無線などB2Bが主体となっている。ビクターという旧社名を聞くこともほとんどなくなった。会社としては残っているものの、VHSで天下を取った、栄光のビクターはすでにない。
 2002年、会社清算を発表するアイワ首脳陣。
2002年、会社清算を発表するアイワ首脳陣。ソニーの子会社だったアイワも、消えた1社だ。アイワもソニーと同じく、戦後すぐに誕生した音響メーカーだった。1969年にソニーと資本提携。無骨ながら堅牢なデザイン、品質の割には廉価ということもあり、市場では存在感を示していた。
85年のプラザ合意後に進んだ円高に対処するため、日本の電機メーカーの中ではいち早く海外に製造拠点を移設。これが奏功し90年代初めには、円高対応に成功した企業として評価も高かった。また、テレビとビデオが一体化したテレビデオを真っ先に市場に投入するなど、ニッチながらユニークな商品が消費者に受け入れられ、業績も好調だった。
誤算は、急速なデジタル化の進行だった。これは、どの電機メーカーも直面した問題だが、アイワは研究開発型企業ではなく、生産合理化によって市場に食い込んできた企業である。社内にデジタルがわかる技術者はおらず、デジタル化の波に完全に乗り遅れてしまった。しかも価格競争力が最大の武器だったが、韓国・台湾メーカーの台頭とともに競争力を失っていった。
結局、親会社のソニーは、2002年にアイワを吸収合併。企業としてのアイワは消滅する。当初、ソニーはアイワを第2ブランドにすることで商標の存続を図ろうとしたがそれもかなわず、いまでは、ブランドを含め跡形も残っていない。
それでも、以上見てきたような、電機メーカーの中でも比較的規模のある会社の場合は、その終焉を含めて人々の記憶に残っているだけでも幸せと言うべきなのかもしれない。
この20年の間に、人知れず消えていった電機メーカーやブランドは数多くある。
ブランドへのこだわり
かつて日本のオーディオメーカーは、会社の規模は小さくても、世界中にファンを持っていた。また、ユニークな製品づくりでファンを獲得してきたメーカーもあった。
山水電気もそうした会社の1社だった。「サンスイ」ブランドは、オーディオファンの間でも人気が高かった。ところが、CDの登場から始まったデジタル化によって業績は悪化していく。生き残りのために外国資本を受け入れ、1991年には香港企業に買収された。しかしそれでも業績は好転せず、2000年代に入ると、ほとんど営業活動を行っていないにもかかわらず上場だけは維持し、株価だけが数円~数十円の間を行き来する不思議な存在となっていた。しかし2012年、民事再生法を申請し倒産した。外国資本に買収された時は、日本ブランドの海外移転として話題になったが、その倒産劇はほとんど注目されることもなかった。静かすぎる幕引きだった。
このほかにも、赤井電機やナカミチも海外企業に買収されている。両社はまだ存在し、いまなお音響機器を販売しているが、赤井はオーディオよりも浄水器販売が主力となるなど、昔の面影は残っていない。
このほかにも、数多くの電機メーカーが、この20年の間に姿を消した。そして今後も、この流れは変わらないだろう。一昨年、シャープの存続が危ぶまれたように、大企業でもいつ危機に陥らないとは限らない。
共通するのは、自らのブランドと技術力に対する過信であり、一時は世界を支配したという驕りである。だからこそ、デジタル化が進んでも、円高が進み新興国メーカーが台頭しても、自らの優位性を疑わなかった。いずれ環境が好転すれば再び成長路線に戻れると甘い見通しを持ち続け、決断を遅らせることになった。
たとえば三洋電機なら、かつてデジカメのOEM供給で世界をリードしたように、自らのブランドにこだわらない路線を選ぶこともできたはずだ。しかしその決断はできなかった。ビクターでも、プライドを捨て、親会社の松下との一体化を進めるなどの選択肢もあった。
タラレバを言っても意味がないかもしれない。しかし、間違いなくもっといい形で生き残る選択肢はあったはずだ。すべての電機メーカーが他山の石とすべきところである。