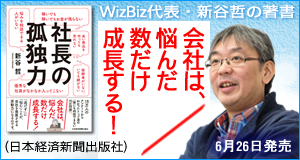2013年12月号より
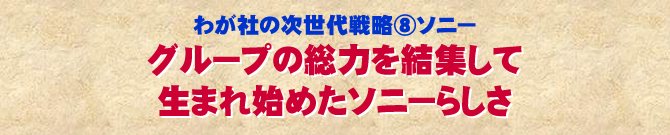
ソニーの社長兼CEOに平井一夫氏が就任して早くも1年半が経過した。
就任にあたり、平井社長はひとつのコミットメントを発表した。それは、ソニーの本業であるエレクトロニクス事業の復活であり、それをはっきりした形で示すために、2013年3月期でのエレクトロニクス事業の黒字化を明言した。
しかし結果は1344億円の営業赤字。前年の1702億円よりは改善しているとはいうものの、まだまだ巨額の赤字が残っている。公約は破られた。その責任を取って、平井社長以下全役員は、役員賞与を返上してけじめをつけざるを得なかった。
それだけに、今期は何が何でも黒字転換しなければならないが、幸いにもこれまでのところ、目標が達成できそうな趨勢だ。8月に発表した第1四半期決算では、エレクトロニクス事業の営業損益は、前年の131億円の赤字から134億円の黒字へと大きく改善した。これまで、エレキ部門最大の赤字要因だったテレビ事業も、前年の66億円の赤字が52億円の黒字へと黒字化を果たした。テレビ事業の黒字化は、10年度第1四半期決算以来12四半期ぶりのことだ。
平井社長によれば、第2四半期以降についても、「これまでのところ、予定どおりに進んでいる」。
ただしソニーの場合、単に黒字を出しただけでは誰も納得しないところがある。ソニーは創業以来、商品やサービスを通じて世の中を動かしてきた。決算数字よりも、むしろ商品によってソニーの復活を実感したいというファンは多い。平井社長はこれについても自信ありげだ。
「昨年来、会社をこうしたい、特にエレクトロニクスをこう持っていきたいという話をしているが、ここにきてそうした商品を市場に投入することができてきた。手ごたえを感じている」
次頁からの平井社長のインタビューにも出てくるが、昨年発売され、話題になったカメラに、ソニーの「RX1」がある。話題のミラーレス1眼ではない。部類としてはコンパクトカメラの仲間と言えるだろう。ズーム機能もついていない。それでいて実勢価格は25万円と超高価なカメラだ。こんな価格設定では売れるはずがないと思いがちだが、実際には人気を集めている。最大の特徴は、色再現性の素晴らしさ。昔のカメラのフィルムに当たるイメージセンサーを、従来のものよりはるかに大きい35ミリフィルムサイズにまで大きくすることで、画質を向上させたのだ。
ソニーはイメージセンサーにおいて、絶対の自信を持っている。その威信をかけてつくったカメラが、真のカメラ好きから高く評価された。購入した人からは、「こういうソニーらしいカメラを待っていた」という声も寄せられている。
もうひとつ、平井社長がソニーらしい商品として胸を張るのが、スマホの「エクスペリアZ」およびその後継の「Z1」だ。Z1はドコモの「スリートップ」にも入っているが、その最大の特徴はカメラ機能にある。ソニーがデジカメで培った最先端技術を、スマホの中に詰め込んだのがZシリーズだ。
デジカメやウォークマンは、スマホがその機能を兼ね備えるため、スマホ普及とともに販売台数が減少している。そういう状況ならば、スマホにデジカメの最先端技術を供与するのは、デジカメ部門の人間が抵抗するはずだ。「せめて1年前の技術を搭載してほしい」。こういう要請がデジカメ部門から出ることは容易に想像がつく。
ところがソニーのスマホには、最先端のデジカメ技術が提供されている。
平井社長は就任以来、「ワンソニー」という言葉を好んで使っている。ソニーグループがひとつになり、総力を結集してソニーらしい商品、サービスを提供していこうという意味が、そこには込められている。エクスペリアZシリーズは、まさにワンソニーを体現する商品と言えるだろう。
残念ながら、まだ今の状況では、ソニーが復活を果たしたと言うことはできない。しかし少しずつながら、その兆しが出てきていることは間違いない。
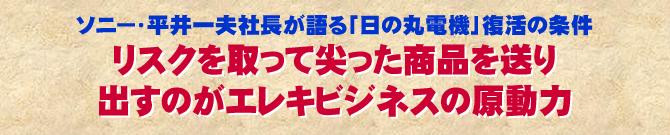
スマホは世界3位を確実に
〔ソニーの平井一夫社長は、10月11日、本誌などのインタビューに応じた。インタビューは、最初、平井社長による状況報告から始まった〕
 平井一夫氏がソニーの社長に就任してから1年半がたった。
平井一夫氏がソニーの社長に就任してから1年半がたった。平井 昨年4月に社長に就任して以来、自分の使命はソニーを変革すること、特にエレクトロニクス事業を再生させ、エンターテイメント事業と金融事業をさらに成長させることであり、この3事業をソニーグループのコアのビジネスとして積極的に関わっていくことだと思っている。(昨年、株主から上場を提案された)エンターテインメント事業については、ソニーグループにとっては戦略上必要不可欠なビジネスと考えているので、今後も100%保有していく。
エレクトロニクスビジネスの、コアビジネスはモバイルビジネス(スマホ等)、ゲームおよびネットワークサービス、デジタルイメージング(デジカメ等)だが、これから年末に向け、あるいは来年に向けいろんな商品を発表していく。モバイルではソニーの総合力を結集したエクスぺリアZおよびその後継のZ1、デジタルイメージングでは昨年大ヒットしたRX1と後継のRX1R、あるいは新しいスタイルのレンズ型カメラも発表した。ゲームではプレイステーション4の発売が控えている。加えてテレビ事業では4Kを中心にいろんな展開をしている。
昨年来、会社をこうしたい、特にエレクトロニクスをこう持って行きたいという話をしているが、ここにきてそうした商品を市場に投入することができてきた。手応えを感じている。ただし、エレキを取り巻く事業環境というのは、まだまだ厳しいし、解決すべき課題もあるので、マネジメントチームとしては、引き続き、気を引き締めていく。
―― エレクトロニクス再生の牽引役のひとつがモバイル分野だが、世界のスマホ市場でどういうポジションを目指していくのか。競争が激化する中、何が勝敗を分けるのか。
平井 モバイル市場におけるポジションということでは、ナンバー3ポジションには確実に入っていかなければならない。すでにナンバー3になっているところもけっこうあるので、そこでは、それを守っていく。あるいはナンバー2を目指す。
差異化ということについては、ひとつはハードウエアとしての魅力があるかということ。これに関してはエクスぺリアのシリーズ、とくにZ、Z1は、デザインや持った時の感触において、非常に高い評価をいただいている。デザイン力は昔からソニーのお家芸。これは徹底追求してきたし、これからもしていく。さらに「ワンソニー」として、ソニーの様々な事業部が持っている技術を投入していく。エクスぺリアでいえば、デジタルイメージングの技術に注目して投入した結果、撮像・撮影の部分が最大の差異化になっている。今後ともソニーグループが持つ最新の技術を投入し、商品に組み込んでいくのがソニーらしいスマートフォンの戦い方だと思う。
―― スマホに関して、米国市場、中国市場をどうやって開拓していくのか。
平井 スマホのいちばんのプライオリティは日本でのシェアを確実に守る、あるいはさらに伸ばしていくことにある。次にヨーロッパ。ヨーロッパ市場においてもソニーのシェアは高いので、これをさらに上げていくことが最重要課題だと考えている。そのため日本、ヨーロッパにはかなりの経営資源を投入している。逆に、米国、中国の市場に入っていくとなると、かなりの経営資源を投入してマーケティングからオペレーションまでやらなければならない。これを全部一度にやるのは現実的ではない。段階を踏んでひとつずつ確実にやっていく。
エレキとエンタの融合
―― グローバルなテレビ市場において、ソニーはどのようなポジションを目指すのか。
平井 世界各地でシェア何位を目指すと言うより、いまどういうステージにあるか話したほうがいいと思う。副社長になってコンシューマーエレクトロニクスの責任者になったのが3年前のこと。そこでテレビビジネスを見ることになったが、その時は、まずは出血を止めなければならなかったため、シェアは追わないと言った。赤字を減らすために、モデル数を絞り出荷台数も絞り込むなどして、マーケットシェアを意図的に落とした。しかしその一方で、ディフェンスもあればオフェンスもある。オフェンスとしては商品の強化をやってきた。その結果、4Kなどいいものが出てきたという認識だ。だからいまは、マーケットシェアを取っていくんだというスタンスで、世界で同じようにビジネスをしている。
 ソニー製スマホ、「エクスペリア」はソニー再生の原動力
ソニー製スマホ、「エクスペリア」はソニー再生の原動力―― 4Kが本格的普及期に入るのはいつ頃か。そのためにはコンテンツが必要なのか、あるいは価格が下がらなければならないのか。
平井 価格もですが、お客さんのいちばんの関心は、映像はきれいだけど何を見るんですかというもの。ソニーの4Kテレビは、アップコン機能(現行放送をより高精細に映す機能)がついていて高い評価を受けているが、やはり、総務省の次世代放送推進フォーラムで、4K放送をどう立ち上げるかが重要になってくる。
2020年に東京オリンピックがあるが、その前にも、来年はソチ冬季五輪とサッカーのブラジルW杯があり、3年後にはリオ五輪と、スポーツイベントがあるのだから、そこで4Kコンテンツを提供できるよう、ソニーとしてはハードもコンテンツも両面から、意見を述べさせていただく。
―― エレクトロニクスとエンターテインメントの融合の状況は。
平井 最近の例でいちばん手応えのあるのが、アメリカでスタートした4Kのサービスだ。4Kの場合、テレビは買ったもののコンテンツをどうするという話をよく聞く。その点、ソニーには、ソニー・ピクチャーズエンタテインメントがある。彼らに4Kの映画コンテンツをつくってもらい、映画が10本入っているハードディスクボックスを提供するサービスを始めている。このボックスを購入すれば、すぐに4Kの映画を観ることができる。9月1日にはダウンロードサービスも開始した。
他社ができないこうしたサービスをソニーができるのは、スタジオを持っているから。これがエレクトロニクスとエンターテインメントの融合の直近の例だと思う。
―― 日本におけるサービス開始の時期は。
平井 アメリカでダウンロードサービスを始めたばかりだが、4Kのコンテンツなので、ダウンロードに時間がかかる。これをどういうように提供するのがいいのかトライアルしている段階だ。たとえばヒットタイトルは先にダウンロードしておいて、見たい場合、キーだけダウンロードする。そうすれば、すぐに映画を再生できる。このようにいろんなアイデアがあるが、アメリカでトライアルして、お客さんの反応をいただき、それを踏まえて日本やヨーロッパで展開する時はグレードアップしたサービスを提供していこうと考えている。
エレキの黒字化は予定どおり
―― (ソニーの株主の)サードポイントから、エンターテインメント部門を上場すべきとの提案があったが、ソニーは100%保有し続けるとの結論を出した。その一方で、エレクトロニクス、エンターテインメントと並ぶコアビジネスである金融部門、ソニーファイナンス株は60%しか持っていない。なぜ完全子会社にしないのか。
平井 金融部門にいろんな見方があるのは承知しているが、いまの段階で発表するものは何もない。
同じコア事業でありながら、なぜ金融は6割にとどめているのかという話をよく聞くが、金融ビジネスというのは様々な規制があるために、仮に100%保有していても、60%保有と同じぐらいしかコントロールが及ばない。
 CEATECでは世界最大の有機EL4Kテレビも出品した。
CEATECでは世界最大の有機EL4Kテレビも出品した。それに比べてエンターテインメント部門は、少数株主の方々が入ってくると経営スピードが格段に落ちてしまう。もしくはワンソニーという観点からいうと、少数株主に対してはいい判断かもしれないが、ワンソニーとして違う方向に向かってしまう可能性がある。
具体的に言うと、先ほど4Kのボックスの話をしたが、あれは音源や映画コンテンツについて100%コントロールできるから、大号令をかけてグループで一気にできた。少数株主がいた場合、もしコンテンツをもっといい条件でほしいというところがあって、自社でボックスをつくるより、他社に提供したほうが株主にとってメリットがあるとしたら、他社にライセンスせざるを得ないかもしれない。でもそれではエンターテインメントがエレクトロニクスビジネスを支えることにはならない。ワンソニーを実現するためには、100%保有している必要がある。
―― エレクトロニクス部門の健全化の進捗状況はどうか。
平井 エレクトロニクスビジネスの黒字化については、現在のところ、当初の計画どおり行っている。
―― 事業環境は厳しいというが、どういう状況か。
平井 よく、円安に振れるといいと言うが、ソニーの場合、対ユーロに関しては確かにプラスαある。しかし対ドルでは、円安によってマイナスになる場合もある。またあまり注目されていないがソニーの中で新興国ビジネスの比率が上がっている中で、新興国通貨のバランスがちょっと崩れてきていて、そこが利益に影響してくる。
ソニーらしさが戻ってきた
―― そのような環境下で、ソニーとして何を目指していくのか。
平井 環境が悪いからと言って、手をこまねいていていいということではない。構造改革については、昨年社長に就任して以来、様々なことをやっているし、コスト削減についても各事業部で優先的にやっている。厳しい環境だからこそ、お客さんにこれってソニーらしい商品だよね、これって面白いねという商品を開発して市場に出していく。
―― 就任時に、ソニーを改革すると言ったが、1年半たって、その改革はどこまで進んだのか。
平井 改革については、これでいいいうものではなく、常にやっていかなければならない。最近は、ソニーらしい商品だねと言われることが増えてきたが、もっとソニーらしい商品、面白い商品を、各事業部がタイムリーに出してほしいし、もっとスピードアップできると思っている。
―― リーマン・ショック以降、日本の電機業界はソニーも含め大打撃を受けたが、復活できるのか。
平井 エレクトロニクスビジネスというのは、いかにお客さんに面白い、楽しいと言ってもらえる商品を市場に送り出すことかだと思う。これは、クリエイティビティとかイマジネーション、もしくはイノベーションという領域に入ってくる。そうしたものがソニーだけではなく、いままでの日本のエレキビジネスを支えてきた大きな原動力だと思っている。
そういったモノづくりのスピリット、考え方を推し進めていくと、リスクを取らないといけない。もしかしたらこの商品は売れないかもしれないという場合でも、果敢にリスクを取っていく。賛否両論あるような商品、それこそ、尖った商品を研究して開発しマーケティングしていく。こういうスピリットというのは必要だと思うし。それがあれば、日本のエレキビジネスは、価格競争に巻き込まれてコストで勝ち負けという軸とは違う軸のモノづくりができるのではないかと思っている。
(※)この記事は2013年10月19日のインタビューを再構成したものです。