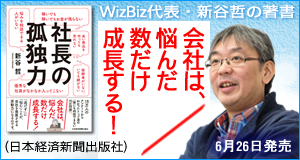2013年8月号より
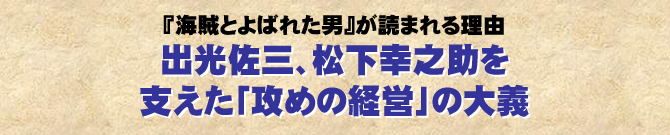
100万部超えの出光佐三本
今年の本屋大賞に選ばれた『海賊とよばれた男』(上・下巻、百田尚樹著、講談社)は上下巻合わせた発行部数が100万部を超えたというのが、しばらく前にニュースになった。
過去の本屋大賞受賞作はそのどれもがベストセラーになっていることを考えれば不思議はないのだが、同書が実話を元にした経済小説であることを考えると、100万部というのは「異常」な数字だといっていい。
『海賊とよばれた男』の主人公は、国岡商店店主の国岡鐡造で、彼の生涯を追いかける構成となっている。そのモデルは出光興産の出光佐三。石油業界の革命児にして風雲児である。
著者の百田氏がこの本を書いたきっかけは、知人に日章丸事件を教えてもらい、それを調べるうちにこんなすごい男がいるのかと興味を持ったことだった。
日章丸事件とは、1953年、イランが石油の国有化を宣言した直後、出光が自社タンカーの日章丸によってイランから石油を直接買い付けた事件である。イランの石油は、それまでイギリス資本が独占していた。国有化後もイギリスは、自らの所有権を主張し、もし無断で石油を運び出そうとした場合、船舶を拿捕すると脅しをかけていた。そうした状況下、日章丸は極秘にイランに行き、石油を買い付けて日本に持ち帰った。これが日英間の外交問題にまで発展したが、結局、出光の輸入は認められた。
 100万部のベストセラーになった『海賊とよばれた男』のモデルの出光佐三。
100万部のベストセラーになった『海賊とよばれた男』のモデルの出光佐三。このように、佐三は常識破りの経営を、その生涯において何度となく繰り返している。石油連盟が自主協定を結び生産調整をした時は、連盟を脱退して増産するなども、それを象徴するエピソードだ。とにかく攻めに攻めた生涯だった。
その一方で佐三は、社員を愛してやまない経営者でもあった。
少し前まで出光興産は、日本型経営の象徴でもあった。社員は解雇しない。労働組合はつくらせない。定年なし。勤務管理も行わない。佐三にしてみれば社員は家族と同じ。家族であるなら首を切ることはあり得ないし、定年をもうける必要もない、という考えに基づくものだ。またこの考えを徹底するために、上場せず、株式はすべて出光家が所有していた。
さすがにいまでは定年もあればタイムカードも導入されているし、2006年には上場を果たしている。しかし、いまなお労働組合はないし、いまに至るまで社員を解雇したことはない。社員は家族であり、家族はなんとしてでも守るという佐三の教えは、いまなお出光興産の背骨となっている。
この、「守るものがある」ことが、出光佐三を時として無謀なチャレンジに駆り立てたのだ。
敗戦当時、出光には内外に1000人の社員がいた。そのうち800人以上が満州など国外にいて、その全員が順次引き揚げてくる。しかし石油はGHQが全量管理しているため仕事はない。それでも佐三は1人も解雇することなく、石油以外の仕事で糊口を凌ぎ、誰もやらないような汚れ仕事も引き受けた。それもすべて社員を守るためである。
同時に佐三は、出光の利益よりも日本の利益を優先させた。出光のためにはならなくても、それが日本のためだと思えばためらうことはなかった。前述の石油連盟を脱退しての増産も、それが国民のためになると信じたからだ。そのためには権力に対して公然と歯向かうこともあったし業界内で軋轢を生むこともあった。しかし佐三にしてみれば、大義の前には軋轢などまるで意味のないことだった。
この大義こそが、攻める経営において絶対必要な条件となる。
大義なき攻勢は一時は大きな成功を収めるかもしれないが、やがて破綻する。企業が攻めに出る時は、当然、困難が付きまとう。社員一人ひとりに多大な負荷がかかることになる。自分の仕事が世の中のためになっているという思いがあればこそ、それに耐えることができる。しかし単に利益を追求するといった大義なき繁栄は長続きしない。ブラック企業が問題になるのも、そこに大義がないからだ。
共存共栄の幸之助
その意味で、近代日本をつくってきた企業、そして経営者には、みな大義があった。大義がわかりにくいのであれば、ロマンと置き換えてもいい。経営者の熱い思いが社員だけでなくステークホルダーに伝わったからこそ、数多くの神話企業が誕生したのだ。
 「共存共栄」が松下幸之助の大義だった。
「共存共栄」が松下幸之助の大義だった。松下電器(現パナソニック)の創業者・松下幸之助の場合なら、「水道哲学」と「共存共栄」がそれにあたる。家電製品を水道のように廉価であまねく行き渡らせたい。そして松下電器と、松下製品を発売する店と、消費者が、すべて栄えるようにしたい。この思いが、松下電器を世界的家電メーカーに発展させたのは言うまでもない。
「不況またよし」というのも、幸之助の言葉である。大半の経営者は、不況の時にはただ頭を下げて嵐が通り過ぎるのを待つ。しかし幸之助はそうでなかった。事業見直しのいいきっかけとしたのだ。イケイケドンドンで利益が出ている時には、小さな瑕疵は見逃されてしまう。それがやがては経営の足を引っ張ることもよくある話だ。不況時は、そのような積もり積もった澱を掃除する最大のチャンスだと考えた。同時に、次の攻めのための準備を進めておく。
実際、幸之助存命中の松下電器は、危機を迎え、それを乗り越えるたびに大きくなっていった。ありふれた言葉だが、「ピンチこそチャンス」を体現した企業が松下電器だった。
有名な「熱海会談」(1964年)のあと、幸之助は営業本部長代行に就任した。自ら営業の第一線に立ち、疲弊した販売店に貢献したいとの思いからだった。ただ、それだけで販売店の業績が向上するわけがない。
熱海会談の翌65年。松下電器は春から夏にかけて、テレビ、ステレオ、掃除機、洗濯機、炊飯器、冷蔵庫など、新商品を一気に市場に投入した。そのいずれもが大ヒットし、販売店の業績は一気に好転する。このように、勝負と思ったら一気に攻勢をかけることができるのも、製造現場が幸之助と「共存共栄」の理念を共有していたからだ。販売店の側も、これを意気に感じ、従来にも増して販促活動を行った。これによって松下と販売店の絆は一層、強まることになった。
その幸之助に真っ向から勝負を挑んだのが、ダイエー創業者の中内功だった。
流通革命の旗手だった中内は、「価格決定権はメーカーではなく消費者にある」というのが持論だった。中内の「安売り哲学」である。
中内にしてみれば、消費者に人気のある松下製品をできるだけ安く売りたい。しかし「共存共栄」を旨とし、販売店の利益を重視する松下にしてみれば、ダイエーの廉価販売は許しがたいものであり、ダイエーへの出荷を停止した。
それでも中内はさまざまなルートを使って松下製品を仕入れていたが、それを防ぐために松下は製品に隠し番号をつけて仕入れルートを突き止めようとした。松下・ダイエーの陣の一幕だ。この戦い、中内が攻め、幸之助が守っている。しかも消費者は中内の大義を支持した。これは日本の流通史上の一大エポックである。
この一件のあと、幸之助は中内を京都にある真々庵に招き「覇道ではなく王道を歩め」と諭したが、哲学と哲学のぶつかりあいなのだから折り合うことはなかったという。
もっとも中内の場合、1990年代に入ると事業拡大欲がどんどん肥大し、プロ野球チームやリクルートなど、本業とは関係ないものまで買収した。しかし、そこには流通革命の哲学など微塵もなかった。社員は、そんな中内を批判的に見ながらも、カリスマに対して何も言えない状態だった。社員に支持されない攻めの経営などうまくいくはずもなく、その後のダイエーは転落へと向かっていった。
自由競争への熱い思い
戦後経営者の中では松下幸之助と並んで人気が高いのがホンダの創業者・本田宗一郎だ。
戦後の経営者の中で、宗一郎ほど攻め続けた経営者は類を見ない。
1959年、スーパーカブがヒットしていたとはいえ、二輪メーカーとしてようやく経営が安定し始めた段階でマン島TTレースに出場、2年後には優勝を果たす。当時の情勢で日本のバイクメーカーが世界最大の二輪車レースに出場するのは無謀以外の何物ではなかった。62年には通産省の反対を押し切って四輪車参入を表明、翌年には販売にこぎつけている。
 自由競争を愛した本田宗一郎。
自由競争を愛した本田宗一郎。当時、通産省は「特振法」を制定しようとしていた。これは自動車や鉄鋼などの特定産業について、国際競争力を高めるため行政指導によって企業の統廃合を進めようというものだった。同時に新規参入は認めない。それが通産省の方針だった。
以前から四輪車参入を狙っていた宗一郎は、この方針に激怒、計画を前倒しして四輪市場に参入した。
もちろんこの背景には、その機を逃したら二度と四輪車をつくれなくなるという企業経営者としての怒りもあったが、同時に、「自由な競争こそが技術を向上させ、経済を活性化させる」との、宗一郎の終生変わらぬ思いがあった。そしてこの思いは、やはり全社員が共有していたものだった。
だからこそマン島レース参戦の時も、四輪車製造の時も、社員は宗一郎とともに寝食を忘れて没頭した。時には宗一郎にスパナを投げられたりもしたが、それさえも力になった。ホンダの攻めの経営は、こうした全社の一体感があったればこそだった。
ホンダと並ぶ「神話企業」のソニーも同様だった。
ソニー神話は井深大という天才技術者の夢をなんとか実現したいという思いを社員全員が持つことからスタートした。その筆頭が、井深とともにソニーをつくり、「アメリカでももっとも有名な日本人」との異名を取った盛田昭夫だった。盛田自身も大阪大学工学部出身のエンジニアであるにもかかわらず、井深に出会った時から、井深の夢をサポートする役回りを自ら引き受ける。井深がいままで世の中に存在しなかった新しい商品を開発し、それを盛田が世界で売りまくった。この二人三脚なくしてソニー神話は生まれなかった。
日本初のトランジスタラジオ、テープレコーダー、トリニトロンテレビ等々、このコンビによって新たなる市場が次々と誕生した。
特筆すべきなのは、ソニーが最初から世界を目指したことである。これは後発ゆえの選択ということもできるのだが、この決断がソニーを世界的メーカーへと押し上げることになった。
ソニー黎明期の有名な話として、盛田がアメリカでトランジスタラジオの売り込みに行った際、OEMなら10万台購入するという提案を断わったというエピソードがある。「ソニーブランドなど誰も知らない」と言う交渉相手に対し盛田は「50年後には(交渉相手より)有名になってみせる」と啖呵を切って破談にした。一時の利益より、ソニーブランドを売ることで将来の利益を取ったのだった。
1963年には、盛田自ら家族とともにアメリカに移住。米国販売の指揮をとった。この当時、メーカーのトップが自ら米国に住むなど考えられなかった時代である。しかも盛田は英語もそれほど堪能ではなかった。その盛田が米国に渡る。ソニーは世界で勝負することの、これほどまでに明快な見せ方はなかった。この時からソニーは世界的ブランドへの第一歩を踏み出した。
アメリカとの友情
 アメリカの真の友人になった盛田昭夫。
アメリカの真の友人になった盛田昭夫。盛田はアメリカのメディアにも積極的に登場した。講演なども、求められれば可能な限り引き受けた。自分が有名になることが、ソニーブランドの知名度アップにつながる。盛田はそう考えたのだが、これも当時の日本の経営者としては極めてレアケースだった。
しかしこうした努力を続けていたおかげで盛田の顔と名前は全米で知られるようになり、人的ネットワークも広がった。のちに家庭用VTRが著作権侵害だと問題になった時にも、盛田は「VTRはタイムシフトマシーンだ」と訴え、認められる。その背景には、多くの盛田ファンの後押しがあった。これも、未知の世界にトップ自ら打って出た盛田の決断がもたらしたものだ。
この決断がなければ、ソニーは米国で市民権を得ることはできず、コロンビア映画を買収することもなかったはずだ。
盛田がアメリカで受け入れられたのは、ソニーのセールスマンであると同時に、自由主義先進国アメリカに対する敬意を常に持ち続けていたことだ。愛知県の老舗造り酒屋の15代目当主という立場だからこそだろう、盛田はアメリカの自由を愛すると同時に、アメリカのよき友人であろうとした。
米国民はそれを感じたからこそ、時に盛田がアメリカに「ノー」を突き付けても、盛田の愛情によるものだと素直に受け入れることができたのだ。
単に積極的な攻めの経営を行うだけでは評価はされない。そこに関係者に対する思いやりと自らの事業に対する信念があって初めて、経営者は評価される。だからこそ、出光佐三、松下幸之助、本田宗一郎、盛田昭夫は没後何年たっても評価が高く、その人生を描いた本がベストセラーになるのだ。