



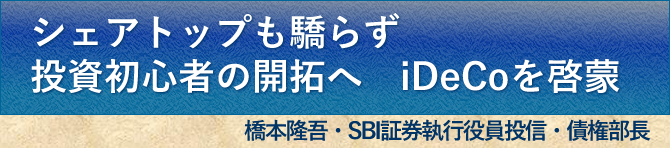
SBI証券のiDeCo口座の加入者は5月末現在で18万口座を超え、シェアトップに立っている。運用指図者(新たに掛金を拠出することが出来ず、口座資産の運用指図しか出来ない人)の約3万口座を加えても、業界シェアは20%を超えており、iDeCoを始めるにあたって、もっとも選ばれている金融機関だ。

橋本隆吾・SBI証券執行役員投信・債権部長
SBI証券の加入者は、他の金融機関に比べ、投資に対するリテラシーが高い。iDeCoでの運用も積極的に投資信託を選び、効率的に運用益を得ようとしているのが特徴だ。SBI証券執行役員投信・債権部長の橋本隆吾氏は次のように話す。
「iDeCo口座を開いているお客様のうち、3分の2弱は、SBI証券の総合口座を開いていただいています。iDeCoでの投信保有率は、加入者の方で76.3%。実に4分の3が投資信託を持っています。弊社のお客様は節税プラス運用を考えておられる方が多いと言えます」
国民年金基金の調査で、昨年3月末の時点で商品選択割合が預貯金38.6%、保険が26%を占めていたことを考えると、SBI証券の加入者は、投信選択率が高いことがわかる。運用目的の顧客が多い理由は、SBI証券の売りの1つであるファンドの品揃えだ。
「この1~3月で弊社のお客様が買われたランキングをみると、1位のひふみ年金が日本株中心のアクティブファンドで、4位の8資産バランスというバランスファンドを除けば、株のアクティブファンドか、株のインデックスファンドが上位に入っています。特長のあるパフォーマンスのいいアクティブの株のファンドが上位に来ていることで、弊社では長期投資での株のファンドが支持されています。アンケートの調査結果を調べると、個人向け国債と株のインデックスファンドの相関が非常に高かった。お客様は自分で判断されてポートフォリオを作っておられる。我々はそういうお客様の属性に合わせて、株のインデックスファンドやアクティブファンドを他社さんに比べて充実させているところが特徴かなと思います」
しかし、資産運用に長けた顧客だけを相手にしていては、新規の口座は増えない。初心者、あるいは若い世代の開拓が今後の経営方針にもなっているという。
「もともとSBI証券は株のトレーディングが収益の柱ですが、その次の柱として貯蓄から資産形成を考えた時に、積み立てが一丁目一番地と位置づけています。株に比べれば収益性は低いですが、確実に預かり資産は増えていますし、ゆくゆくは株などの優良顧客になっていただきたい。資産形成層を取り込んでいくのは非常に重要です」
昨年の法改正でiDeCoの対象者が増えると、すぐに対応に乗り出した。動画解説やオンラインセミナーなど、ネット証券ならではの迅速さで対応策を取ってきた。
「法改正のあたりから、すぐに専門家のフィナンシャルプランナー(FP)の解説動画もアップしました。フィデューシャリー・デューティー(受託者責任、投資信託や保険など金融商品の開発、販売、運用、管理について、真に顧客のために行動する金融機関の役割や責任全般を指す)の観点やお客様へのサービスということで、iDeCo、iDeCo&つみたてNISAといったテーマでリアルのセミナーを開いてFPから活用法について説明をいただいたり、運用会社さんを招いて運用の話やパネルディスカッションをしたりと、力を入れています。
また、シミュレーター型のロボットアドバイザーも導入して、質問に答えていくと、このあたりのファンドはどうでしょうと提案をしてくれます。自分でなかなか商品を探せないという方には人気です。逆に自分で探したいという方には、スクリーニング機能、コストやパフォーマンスで選べるように対応しています。リテラシーの高いお客様や、ネット証券ナンバーワンの企業として支持していただけるお客様は多いですが、まだまだ初心者向けコンテンツが弱い面もあります。しかし、急にブームで伸びるというものでもないですから、制度をしっかり説明して、投資教育、投資啓蒙として地道にやっていくしかない。経営方針として、しっかりやっていきます」
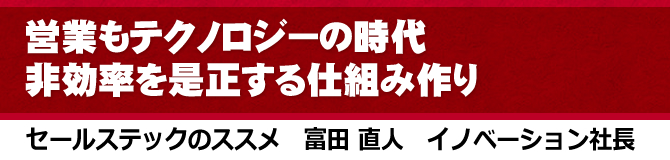
見込み顧客獲得から育成、顧客獲得後のフォローアップまで、B2B営業に関する非効率をセールステックで変革するビジネスを展開しているのがイノベーションだ。営業の仕事を「本来すべきである創造性の高いもの」に変えることをコンセプトにしており、中堅・中小企業を中心に注目が高まっている。イノベーション社長の富田直人氏にセールステックについて話を聞いた。
── セールステック(Sales Tech)はまだ聞きなれない言葉ですが、現在とひと昔前の営業の違いについて、どう捉えていますか。
時代によって、大きく3つくらいに分けて変化をお話ししたほうがわかりやすいと思います。

「将来、顧客が求めている情報の価値や内容は変わる」と富田社長。
とみだ・なおと 1965年生まれ。静岡県出身。87年横浜国立大学工学部電子工学科卒業後、リクルート(現リクルートホールディングス)入社。2000年退社後、イノベーションを設立。社長に就任。16年12月マザーズ市場へ上場。
1つは、営業マンが全部1人でやる時代。マーケティング部門もなく、行き先も自分で決めて、説明して、見込み客を管理して、見込みのありそうなところにクロージングし、受注し、納品する。商品にもよりますが、既存顧客もフォローしていく。最初から最後までを1人でやる。しかし、新規営業と既存顧客営業は求められる資質が違います。例えば狩りが得意な人もいれば、寄り添うとか守りが得意な人もいます。最初から最後まで1人の人間がやるのは、人材のミスマッチも含めて、非効率ですごくたくさんの課題があります。
2つ目は、見込み客を獲得するとか営業の行き先をマーケティング部あるいは販売促進部が担当して、その先は営業マンが担当し、既存顧客は別の人が担当するなど分業が進んだのが2つ目の時代です。そのなかでインターネットが登場しています。しかし、資質の違いはクリアできても、これでは見込み客を獲得するにも人件費や担当間の引き継ぎの手間といったコストがかかり、ニーズのないところに営業に行くこともあって、まだ非効率です。
そして3つ目がこれからどんどん普及していくもので、いわゆるインターネットを活用、ツールを活用して効率的に営業していくスタイルです。例えば当社が運営しているような見込み客獲得サイトや、リードジェネレーション(不特定多数ではなく、自社の製品・サービスに関心を示す個人や企業の個人情報を獲得すること)のためのWEB広告やツールも出てきています。また、営業マンがいなくても動画を活用して説明を行ったり、商談もスカイプのような訪問しなくてもよいツールを使ったり、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)を活用して行動履歴を残し、効果的に営業をします。WEBでもボットを使ったコミュニケーションシステムを使うなど、効率化が進む時代になってきています。
── かつて営業マンと言えば、企業が人海戦術を使って物量で顧客を獲得していくイメージがありました。
ガッツがあって、たくさん行動すればするほど成果が上がるわけですから、それは売れると思います。しかしながら、そういう売り方を長い間、続けられる営業マンが何割いるか。残業が無限にできて、募集すればすぐに採用ができる時代であれば、それでもよかったかもしれません。人手不足で、働き方改革で残業抑制とか、量で仕事をすることができなくなったなかで、仕組みでモノを売るということが求められているのだと思います。
── 確かに離職率が90%超という営業会社もめずらしくありませんでした。
そういう会社もまだあると思います。逆にその会社は営業が強い場合が多いです。なぜなら、そのような組織はなかなか作るのが難しいからです。でも、大きな時代の流れはテクノロジーを活用した営業へと変わってきていますので、もともと営業が強かった会社が、強みを活かしつつ効率的な仕組みを作り上げれば、さらに強い会社になっていくと思います。
── 採用が難しくなってきたなか、離職率をいかに下げるかが企業の課題になっているのも事実です。
採用は営業職だけでなく、全領域で難しくなっています。エンジニアなどは特に難しいと言われていますし、デジタル系のマーケティングはそもそもやっている人数が少ないので、引っ張りだこの状態です。従業員が働きやすい、働き甲斐のある会社を作っていくことが大事になっています。
── セールステックという言葉自体を打ち出している会社はまだ少なく、まだ浸透しているとは言い難い気がしますが。
まだ少ないと思います。検索したとしても、日本では限られた数社しか出てこないでしょう。我々はSales Tech Lab.(セールテック・ラボ)という研究開発機関を作りまして、将来に向け、どうやって営業をテクノロジーで変えていけるのかという研究を進めています。欧米ではこの領域にスタートアップが多く参入していて、資金調達を行っているベンチャーも少なくありません。日本でも同様で、一気通貫でシステムを提供するベンダーは少ないですが、部分的な個別のサービスを提供する企業は出てきています。
── 日本では、営業と言うとまだ個人単位での仕事だという印象が強く、どうすれば効率化が進むのか、わからないという経営者も多いのではないですか。
そんなに難しく考える必要はありません。いまのセールスのプロセスをふり返っていただいて、見込み客を獲得するというフェーズ、見込み客を育成するフェーズ、クロージングとサポートのフェーズと、流れの中での非効率を、どうテクノロジーで変えていくかというだけです。
テクノロジーとは言えませんが、エクセルを使って顧客情報を管理し、電話をするというのもセールステックの領域でしょう。当社のような資料比較サイトを活用して効果的に見込み客を獲るというのも、マーケティングや広告のような位置づけですが、セールステックの領域だと思います。
獲得した見込み客をしっかり管理するという意味では、SFAやCRMもその領域ですし、マーケティングオートメーション(マーケティングにおいて、個別な見込み顧客とのコミュニケーションを自動化するために開発されたツール)もその分野の1つです。カスタマーサポートの分野でも、よくある質問であれば、ボットを使って自動的にチャットで返すツールを導入している企業も増えています。
ただ、現状では、それぞれが1つずつのサービスで、なかなか統合できないのが課題となっています。また、使う側のリテラシーにも課題があります。
── せっかくセールステックを活用しようにも、それを使いこなせない企業が多いということですか。
中堅や中小企業では、そもそものITリテラシーが高くなかったり、マーケティング部門の数や質もまだまだこれからという企業が多く、ツールは導入したけれども使いこなせない場合も多いです。本当の意味で投資対効果を上げていくためには、ツールを提供する側も使う側も、サポートを含めて課題は多いです。
── 使いこなすための人材も必要だと。
PCが使えるというレベルではなく、デジタルマーケティングリテラシーとでも言うのか、ツールを使いこなせる能力もあるでしょうね。
とは言っても、営業マンはお客様と対峙しますから、基本的にお客様の立場に立って考えられる力は、時代が変わっても必要だと思います。そしてお客様に対して、環境がこう変わればこうなると、仮説をお客様にぶつける力は求められます。これは機械にはできないことですし、どんなにAIが進んだとしても、その3つの力を持つ人は、さらに上に行けるのではないかと思います。
── コンサルタントに近い業務に変わっていく感じですね。
いまはユーザーが自由に検索して調べることができますし、営業マンに聞くまでもなく調べられることが多くなっています。ネットで検索できる内容は営業に求めないという時代も近づいているかもしれません。いまの40代、50代と、10代、20代では、情報を得るためのリテラシーがまったく違います。20年後、30年後を見据えた時に、顧客が求めている情報の価値や内容は変わってくるでしょう。営業はコンサルティングとか、お客様に寄り添う形での課題解決に取り組むようなスキルが求められると思います。お客様の課題を聞いて適切なコミュニケーションをして提案する。営業のあり方で、すごく差がつく時代になっていくでしょう。
── イノベーションの事業としては、どのような取り組みをしているのですか。
我々はB2B、法人営業に特化した事業を行っています。いまは「ITトレンド」、「BIZトレンド」という、ある領域に特化した資料請求、見込み客獲得サイトを運営しています。またリードナーチャリング(見込み客育成)のところでは「リストファインダー」というマーケティングオートメーションのツールを提供しています。これがいまB2B企業で最も数が出ているツールと言われていますが、それでも累計実績で1000アカウントしかありません。日本のB2Bの営業をしている会社数からみれば、導入率はまだまだこれからです。これらは今後も進めていくつもりです。
一方で、様々なテクノロジーを駆使したサービス開発も進めています。一例を挙げると、現在は見込み客を獲得して営業が行くという流れが前提になっていますが、そうではない営業の仕方も存在します。例えばWEBサイトでのお客様の行動履歴を見ながら、この行動はこういう商品を検討しているのだろうとレコメンドしていくことによって、購入に結び付けることができます。簡単な質問ならチャットで答え、説明なら動画を見せる。WEBコミュニケーションの自動化はさらに進んでいきますので、人がいなくても売れる仕組みはできると思います。作業的な仕事はどんどん機械に置き換え、営業マンは人にしかできないクリエイティビティの高い仕事にフォーカスしていく。こんな時代が来るでしょう。
── B2Bでもサイトの行動履歴からわかるものがありますか。
おもしろい事例があります。既存顧客がすぐに他社に取られたり、取り返したりを繰り返すコンペティティブな業界があるのですが、例えば料金表や特許のページを何度も同じ会社の人が見ている場合があります。それはだいたい乗り換えの検討をしているんですね。営業マンが行ってみると「やっぱり」ということがあったんです。これはセールステックというよりも我々のサービスを使ってわかったことなのですが、こうした部分をもっと誰でも使えるように突き詰めれば、より効率化が進んで効果が出やすいと思います。
営業マンの採用が難しくなっているなかで、セールステックは社会的にも求められている領域ですので、スピード感を持ってサービスを提供することをしていかなければいけない、早いタイミングでサービスを作っていかなければいけないという危機感を持って事業を進めています。
(聞き手=本誌編集長・児玉智浩)
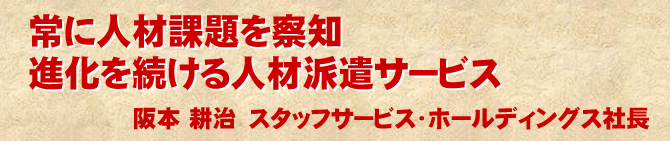
今年は、13年に改正された労働契約法、15年に改正された労働者派遣法、この2つの法律への対応が始まることから、人材派遣の「2018年問題」に直面した年だ。人材派遣業の各企業は事業のあり方が大きく変わろうとしている。そんななか、業界大手のスタッフサービスHDは社長交代、リクルートでグローバルでの人材ビジネスを経験してきた阪本耕治氏が社長に就いた。その阪本氏に法改正への対応と、今後の人材派遣業について話を聞いた。

スタッフサービスの戦略について語る阪本社長。
―― 派遣業は法改正の影響を大きく受けています。
派遣業だけでなく、派遣先の対応も変化が出てきています。
アメリカと日本の人材派遣のあり方は、比べてみるとまったくニーズが違っています。アメリカでは正社員であっても、今日辞めるという話になれば、今日で退職なんですよね。お互いの合意に基づく契約なので、即日に関係が切れるという意味では、非常に流動性が高い。対して日本は、よほどの環境がないかぎり、人を減らすのは難しい状況ですから、一定の、何かあった時のための変動人材層というのが常に存在する必要がある。したがって、通常時にはふつうに働いてもらう層ですから、派遣の仕事の期間が長いわけです。アメリカは正社員でも切れてしまうので、すぐに正社員として採用する。ですから派遣期間は必要な時だけですから短くなります。
日本は長期になりがちななかで、法改正で同じ事業所で働ける期間が3年までとなりました。日本企業の正社員の流動化がまったく進まないなかで入ってきたルールに、どう対応するか派遣先も派遣元も対応が難しくなっています。企業さんからすれば、3年間働いて、自社の働き方やノウハウとか理解しているわけですから、続けて働いてほしい。我々も働いていただけるのであれば、そのほうがいい。
―― 3年間派遣された人材を、企業は正社員として雇用するところも多いのではないですか。
企業が直接雇用を選択するケースは増えています。いわゆるブルーカラーと言われる軽作業領域は、直接雇用に繋がる可能性が高くない領域なのですが、その領域でも昨年あたりから正社員にするケースが多くなっています。その背景としては、人手不足を本当に深刻に受け止めていることが1つ。また労働人口の今後の推移を見ると、一定数社員を抱えておかないと、もう採れなくなるという恐怖感が企業の後押しをしていることも1つあります。もう1つは、企業が直接契約している契約社員にも5年働けば無期契約にする労働契約法のルールが適用されますので、そのプロセスに乗っかる形で派遣さんも受け入れやすくなっている部分があると思います。
―― 派遣社員をどんどん正社員にされてしまうと、人材派遣会社が派遣する人材がいなくなりませんか。
派遣会社のDNAとしては、働く人の役に立ちたいという面が強いんですよ。そういうチャンスがあれば後押ししてあげたい。ビジネス的な面から言っても、そこを支援してくれないような派遣会社は選ばれないと思います。あそこは正社員にしてくれそうなのに邪魔する会社だなんて言われてしまうと、マイナスのインパクトが出てくる可能性があります。むしろそれを活かして、徹頭徹尾、派遣さんのために役に立つ会社であることをブラさないことが、ビジネスを長く続けていくためにも重要だと思っています。
―― 派遣社員のなかには、正社員としてフルタイム働けないという人もいます。
働き方の多様化と言えば、もはや言葉が陳腐化されていますが、たしかに無限定でフルタイム働ける人の労働人口は増えていません。でも一定の条件、時間に制限があるとか、場所、職種に制限があってフルタイムでは働けない方を雇用していくことで、労働人口は増やすことができます。その一定の制限がある方を受け入れていく企業が増えていますので、派遣会社はまさにその橋渡しをしているところです。そういう方を派遣を通じて、お客様である企業に体験していただき、労働力として認知していただければ、それぞれの企業で制度を作って直接雇用していただければいい。正社員を望まない人は決して多くはないですし、それが当たり前になれば、派遣会社は別のニーズを探すだけの話です。
―― 派遣会社の使い方が変わってくると。
まずはそれぞれの企業が正社員をどう活用する制度なのか、がありきです。そのなかで発生してくるニーズ、課題について、派遣会社を使ってどう解決するかというアプローチになります。正社員の活用の仕方の違いによって、派遣の活用も変わってきます。
おもしろいのは、アメリカでも欧州でも日本でも、求められているニーズは異なっているのに、派遣社員はどの国も労働人口の2~2.5%なんです。イギリスだけ少し多いのですが、他の国は常にこの数字です。どんな制度のもとでも、一定の人材課題があって、ここのニーズが約2%発生している。派遣から正社員への雇用が増えても、あまり不安に感じないのは、その時はその時で、新しい人材課題があるからだと思います。だからこそ大事なのは、お客様と向き合っている社員や派遣さんと向き合っている社員が、何を困っているのか、何を希望しているのか、きちんと聞きつづけることで、会社がうまくニーズに応えられる変化を繰り返すことだと思います。
―― リーマン・ショックを前後した景気後退で、人材業の淘汰・再編が進みました。スタッフサービスもリクルートに買われたわけですが、リクルートスタッフィングと統合されるわけでもなく、子会社同士の統合はあったものの、それぞれ存続しています。ライバル関係が続いているわけですが、棲み分けなどはされているのですか。
リクルートは、実はアメリカでも3社買収しています。それらの会社もバックオフィスは統合しましたが、ブランドとしては併存しています。基本方針としては、買収しながら成長しつつ、各ブランド、文化は残す。健全な競争相手として併存することが基本方針です。これはビジネス的にも意味があって、リクルートとしてのシェアで見るのか、スタッフサービス(SS)、リクルートスタッフィング(RS)それぞれのシェアでみるのかによって変わる。リクルート50%シェアと聞けば、ポートフォリオを広げようかと思われる。でも、SS30%、RS20%となっていると、分散感が出て、響きも違ってきます。お客様にしてみれば、自分で選んだという気持ちになります。結果としてリクルートグループだとしても、2つのブランドを持っているほうが、より多くのマッチングを生み出せると思っています。フロント側で言えば、棲み分けはまったくしていなくて、単純に健全な競争相手でいましょうというだけです。
―― リクルートホールディングスから両社に対して、グループ戦略としての指示はないんですか。
ありません。もっと言えば、切磋琢磨しなさいとも言われません。全体で成長しなさいという目標が来るくらいです。派遣会社としては、1件でも多く仕事を探している人と、求人さんを繋ぐことが仕事の本質です。つまりこれが社会課題の解決だと思うんですよね。いかにここを最大化していくのか。その時に我々としても健全に成長し、利益を出していくのか、ということが課題なだけですから、2社でやろうがくっつこうが、派遣事業全体として考えればいい話です。
―― 買収した08年当時は、業界首位をリクルートが買ったとして話題になりました。
棲み分けはしていないものの、それぞれに得意な領域がありまして、RSは大都市圏、東名阪の大きなエリアを中心に事務職の派遣が強いです。お客様も大手企業が多いというのが彼らのマーケット。我々は全国にオフィスがあって、地方展開もかなり進んでいます。事務職だけでなく、エンジニアや介護、医療、軽作業といった仕事も幅広く事業部を持って取り組んでいます。大都市圏プラス事務職のRSと、地方を含めた日本全国で多様な働き方ラインを持っているのがSS、この差ですね。逆に言えば、地方では我々が大きなプレーヤーとして各地方で最大のマッチングを作り出しているのに対し、彼らは首都圏にフォーカスしているぶん、我々が追いかけている立場。
―― 実際の営業の現場では競争ですよね。
最後はよりよい提案をお客様と派遣さんにできたほうが勝ちですので、よりよいサービスを提供するという意味において競っていますし、我々も彼らに学ぼうと。会社の規模で言えば我々のほうが大きくても、東京というマーケットでは彼らのほうが大きいわけですから。競合がいるというのは、我々が強くなっていく意味でも非常に大事です。同じグループにいれば、コミュニケーションもしやすいですしね。ひと言も口をきかないということはないので(笑)。
―― 10年経ちましたから、スタッフサービスをリクルートグループと知らない人も多いかもしれません。
もともと派遣業界でリクルートのブランドの強さがあったかというと、どうでしょう。リクルートはかつてリクルート事件もあったので、リクルートという名前でビジネスをすることに抑制感がありました、だからじゃらんやゼクシィ、ホットペッパーといった雑誌ブランドをメインにやってきました。ある時期から禊も済んで、リクルートのブランドも使いながらやっていこうと。でも派遣事業でみた時に、リクルートの名前がどの程度集客力を持っているのか。スタッフサービスの社名や「オー人事」と比べた時に、まだまだスタッフサービスの持っている力は強いので、逆にそれを今後も活かすべきです。買収された会社ではありますが、自分たちのブランドが残って、そこでがんばっているというのは従業員の誇りではあると思いますし、そう簡単に名前を変えるのではなく、いまの名前といまのブランドを使いながら、いけるところまで行く。
―― その「オー人事、オー人事」の認知度は絶大ですね。昨年流れたCMは懐かしさを感じた人も多いと思います。
昨年、初CMから20周年だったんですよ。買収あり、リーマン・ショックありで、最近は流していなかったのですが、強いブランドは活かして、知っていただいて、もっともっとマッチングを増やしたい。ちょうど20周年の節目ですから、人手不足からくる成長という意味でも、じゃあやろうと。

「オー人事」のCM復活は大きな話題に。YouTubeでも再生回数は数十万回に達する。
―― 反響は大きかった?
ものすごく語られるシーンが増えましたね。お客様のところでも言われますし、働いている方からも観ましたと。あの「オー人事、オー人事」は、派遣事業のアイコンのような部分もあるので、派遣業界全体がポジティブな意味で注目を集めることができます。派遣業界にとってポジティブだと、同業他社さんからの賛辞もありましたね(笑)。
派遣社員は、みなさん真面目に働いていますし、現場の社員も一生懸命に派遣さんと向き合って仕事をしていますが、何か労働問題が出てくると、必ず冠がついてきて、イメージのいい業界ではない。やっぱり、いいイメージになっていく努力をしなければいけないし、あのようなCMが派遣という働き方にポジティブなイメージを残せるのであれば、うれしいですね。
―― 今後の戦略についてはいかがですか。
最近は「総合化」をキーワードにしていまして、これだけ多様なニーズ、働き方をしたいという人が増えているなか、どうやって働く場に持ってこられるのかが、1つのチャレンジなわけです。単純に派遣だけでは十分にお応えできない部分がありますので、人材紹介のように、正社員になりたいという要望があればお手伝いします。ニーズがあるならやってみよう。もともと、派遣業は未経験の方はお手伝いできないんです。企業さんからのニーズは、これをできる人を派遣してください、ですから。4年くらい前から、「ミラエール」という未経験の方を常用の派遣社員として派遣するサービスを始めました。未経験の方に一定のトレーニングをして、お客様のところに行っていただく。まだ白地の多い人ですから、お客様にも育てていただきながらお役に立つ。これが非常に評判がいいんです。
また、我々はエンジニアリングなどの領域をいくつか持っていますので、お客様に対して幅広く提案できる、お客様のニーズに対してワンストップでサポートできるような形にしていく。事業部における総合化の推進です。このやり方を進めていけば、そうそう負けることなく、展開できると思います。
―― 新社長ということで、尊敬する経営者はやはり江副さんですか?
「自ら機会を作り出し 機会によって自らを変えよ」、この言葉は強烈に残っていますね。この会社は待っていたら仕事が来ない会社なんだ、自分で取りにいく会社なんだということは強烈に感じました。直接の薫陶を得たわけではないですが、あの一言にのこされたインパクトはとても大きいし、あの一言でリクルートという会社のカルチャーを位置づけたというのは、やっぱり経営者としてすごいと思います。
(聞き手=本誌編集長・児玉智浩)
2018年6月に創業40周年を迎えたステーキハウス「ブロンコビリー」。東海地方を中心に現在は関東、関西にも店舗を増やし、125店舗(2018年3月現在)まで拡大している。07年にジャスダック、12年に東証1部に上場し、注目を集めたのが外食産業では特筆すべき経常利益率の数字だった。05年に経常利益率17.2%を達成すると、その後も外食不況のなか15%前後の数字をキープ。今期の1~3月の第1四半期も14.4%と高い収益性を誇っている。
いかにして高収益体質を作り上げたのか、ブロンコビリー会長の竹市靖公氏に話を聞いた。
── 今日は5月にオープンしたばかりの「ブロンコビリー新小岩店」でのインタビューになりましたが、出足は好調のようですね。
去年、張り切って出店数を増やしたら、最初は来るけれども、なかなか客足が続かないという店舗がいくつかありました。人口が少ない地域は立地もあって、出店しやすいけれども、続かない。改めて家賃や採算を見直して、今年は15店舗の出店が決まっていますが、今年出した店ははじめから利益が出る店ばかり。とても親孝行な店です。いつも失敗しながら学んで手を打つ。失敗はイヤですけど勉強になりますね。無理をせず、ゆっくりとやっています。
── 経常利益率が10%を超え、それを維持するというのは外食産業では異色の数字です。
自分で決めたんですよ。2001年に狂牛病(BSE)の問題で潰れそうになった時に、赤字に転落してマイナス8%。ふつうはゼロを目指すのですが、私は経常利益率20%を目指すと言った。

高収益体質を生んだ「3つのこだわり」について語る竹市会長。
竹市靖公 ブロンコビリー会長
たけいち・やすひろ 1943年生まれ。愛知県出身。69年喫茶店を創業。78年ステーキハウス「ブロンコ」を創業。83年株式会社ブロンコ(現ブロンコビリー)を設立、社長に就任。13年社長を息子の克弘氏に譲り、会長に就任。
その前に、コンサルタントについて外食産業で起こった低価格競争に立ち向かう戦略を立て、客単価を1700円から970円まで下げて客数を増やし、店舗を急拡大させていました。力もないのに5年で40店舗出したところでBSEに当たってしまった。売上53億円の時に38億円の借金を抱えてしまいました。そこで経常利益率20%を目指そうと。40年間やってきて、私の一番の自慢は、BSEで赤字に転落した2001年に社員が1人も辞めなかったことなんです。賢いやつほど、先が見えるから逃げていきますが、みんな付いてきてくれた。それが何よりうれしくて、みんながよくなることを優先しようと思いました。
企業理念にもある通り、一番大事なことは「全従業員の永続的、物心両面の幸福」です。利益を出すことによって内部留保が厚くなれば、何かの時に従業員を守ることができます。株主には配当をきちんと出して、株価が上がれば喜んでもらえる。利益の数字に対しては執念を持って、厳しくやっています。
── 利益を重視しながら、社員教育にもお金を使っていますね。
弊社は12月決算なのですが、05年は8月まで利益率が20%を超えていました。ただ、みんなに苦労をかけたので、途中で給料も上げてボーナスも上げたんです。自分は過去にアメリカに行き、たいへん感動してこの商売を始めたものですから、その原点を見てもらおうと従業員にはアメリカにも行ってもらっています。日本では味わえないものを感じてもらって、店長クラスはほとんどアメリカに行った経験があります。もちろん、アルバイトもパートの方にも行ってもらう。いまでも教育関係には3億円以上使っています。
開店にあたって他所から人を集めることはできるし、実際仕事もできるのかもしれませんが、企業としての考え方、根っこの部分が違うので、バラバラになってしまいます。できるだけ会社の考え方を伝え、それを共有できる人たちでやっていきたい。いま社員が530人くらいいますが、9割は生え抜きです。店長をやってもらう際には、男性女性、国籍、年齢など関係なく、その資格がある人に店長をやってもらう。興味深いのは、どうしても店長から降格してしまうことがあるのですが、ほとんど辞めない。もう一度挑戦して、再び店長になるというケースが非常に多いことですね。
── 高収益体質に変革させるにあたって、どのような取り組みを進めたのですか。
低価格にBSEで潰れそうになったので、もう一度、自分たちを見直して、価格競争に入らない世界で商売をやろうと。ブロンコビリーには3つのこだわりがあって、「炭焼き」のステーキに「サラダバー」、「大かまど」で炊いたご飯です。
ご飯はもともと炊く機械が56台あったのですが、全部やめてかまどにしました。お米も魚沼産、なかでも津南町という標高200メートルの地域で、雪解け水で作られたお米です。またサラダバーも20種類を用意して、年に5回、サラダのメニューを変えています。昼も夕方もできるだけ新鮮な野菜を出す。そして炭で焼くというのは、結構、めんどうくさいし熱い。燃費も高いし温度が絶えず変化して難しいんです。でも、焼き鳥でも炭で焼いたものが美味しいでしょう。この3つにこだわって、お客様に提供する。
価格競争になってしまうと商売がしんどくなりますから、他所では出せないものを1つずつこだわっていくようにしています。

自慢のサラダバーの魅力について語る。
お米も津南まで行き、作っている人ややっていることを見て、肉も牛の顔、食べている餌を産地まで見に行って、それを仕入れています。
後々本を読んだら、価格競争を避けたことで、ブルーオーシャンになっていたんです。例えば牛丼業界は20円30円の安さを競って体力を奪い合っていたでしょう。私たちは、自分が得意なこと、好きなこと、評価されることに特化して、不得意なことはやらない。ありがたいことにお客様は他の店を越えてブロンコビリーに来ていただけている。
── そういった積み重ねが40周年に繋がったと。
はじめはぜんぜん流行らなかったですよ(笑)。ステーキ屋を始める前に喫茶店をしていたのですが、確かに流行ってお金も少し残しましたけど、喫茶店では働いている人に高い給料を払えないんです。当時、外食産業は水商売だと言われたこともありました。アメリカでは大学にもホテル・レストラン科があって、人気で入れないくらいです。でも日本では低くみられている。それを変えていくには、価値のあるものを提供しながら、従業員を幸せにしていかなくてはならない。喫茶店の売り上げでは限られているので、ステーキを素人ながら始めたわけです。
初めは1日4000円しか売れませんでしたけど、価値観を一緒にして目標を一緒にするために企業理念を作って、毎日、「東海地方屈指の外食産業を目指します」と言っていました。店は夜12時までだったのですが、月に1回、それから夜明けまでミーティングをして、何のために外食をやるのか、話し合っていましたね。40年経って、途中でいろんな大変なこともありましたけど(笑)。
── 13年には息子さんの克弘氏に社長を譲り、会長として経営に関わってきましたね。5年経って、事業承継はいかがですか。
いま私は取締役会長ですが、先々、できればあと1年かそこらの間に会長は下りて引退しようかなと。前に行く時はみんなが押してくれたら前に出て、退く時は自分で退こうと。なぜ桜が人気あるかと言うと、散るからいい。月も満月から欠ける。そろそろ潮時かな。いま取締役に同じ苗字が3人いて、私と嫁さんが引退すれば会社のなかに竹市は息子の1人だけ。できればその次は、同じ苗字の人が1人もいなくなる会社にしようと。そうすればみんなの会社になります。
―― 実際、克弘氏の社長ぶりについてはいかがですか。
私より頭がいいし、一生懸命やっています。でも少しだけ、本人も意識していますが、野性の勘みたいなものは私のほうがあるんです。ちょっと風向きが変わったかな、と感じられるかどうかは、私が失敗の数が多いからわかるのでしょう。社長は違うやり方でやればいいし、会社には優秀な人材もいますので、相談しながらやっていけばいい。本当はちょっと失敗するといいんだけど、上場しているといろいろ言われますからね(笑)。

写真上/炭火焼もこだわりの1つ。 写真下/店内のビジョンにはサラダバーの補充状況などが映し出される。
── 株主の反応も気になりますね。
そうですね。でも、業績がよくなると株主が減るんです。1万2000人いたのが8000人になる。少し前に最高値になったのですが、みんな儲かっている。おもしろいのは、ブロンコビリーは下がってもまた上がるだろうと、株価が下がればみんな買い始めて株主が増える。見ている角度が違うのでしょう。でも私は売るわけにはいかないし(笑)。
個人的には、これまでの40年はおもしろかったですね。自分は1段ロケット、2段目にまたがんばってもらえればいい。外食は浮き沈みが激しいので、米国でも豪州でも、いいものが見つかればすぐに行って、いい材料を買わなければいけない。ほかよりも常に一歩先を行くようにする。世界中を回って肉を探し、ポテトはいまハンガリーから入れていますし、スパゲティはトルコです。ほかよりも努力をして、価格競争に入らない世界で、きちんと人も育てる。そしてお客様を大事にして、会社が続いていけばいいかなと。
── 3代目は考えていないんですか。
一番優秀であればそれでもいいですが、従業員みんなのためになればいいのであって、こだわりはありません。新入社員も100人ほど入ってきているし、会社は私のものではない。でも婿養子なら優秀な人を選べるかな(笑)。
── 最後に、50周年に向けての思いなどはありますか。
私は考えてないね(笑)。こういう仕事だから、決して楽なものではないけれど、できれば従業員の子供が大きくなった時に潰れない会社を作ろうと、企業理念に「永続的」という言葉を入れました。その時に業界でトップクラスでなければ会社はもたない。会社ってそのままなら潰れるようにできている。みんなにとってよくなるように、がんばり続けなければならないんです。
(聞き手=本誌編集長・児玉智浩)


加留部 淳 豊田通商社長
かるべ・じゅん 1953年7月1日生まれ。神奈川県出身。76年横浜国立大学工学部電気工学科卒。同年豊田通商に入社。99年物流部長、2004年取締役入り。06年執行役員、08年常務執行役員、11年6月末より現職。学生時代はバスケットボール部に所属。座右の銘は着眼大局、着手小局。
〔昨年、豊田通商が近畿大学と提携して卵から育てるマグロの“完全養殖”事業に参入(養殖事業そのものは2010年に業務提携)するというニュースが大きな話題になった。11年に同社の社長に就いた加留部淳氏は、就任後初めての出張が近大水産研究所で、同研究所の宮下盛所長と意気投合。今後は豊通と近大のタッグで完全養殖マグロの生産を順次拡大し、海外へも輸出していく計画だ〕
もともと当社は人材育成には力を入れ、いろいろな研修プログラムを用意していますが、その中に若い社員の事業創造チャレンジのプログラムがあるんです。自分たちでまず研究し、社内外の先輩や識者の意見も聞いて新事業案を作らせるものですが、その過程で「ぜひ、近大さんの販売や養殖のお手伝いをしたい」と提案してきた社員がいましてね。
面白い事業プログラムだったので、当時の経営陣が「やってみろよ」と。で、動き始めて実際に予算もつけ、近大さんにもお話をしに行ってというのがスタートでした。こういう社内提案制度は、起業家精神の醸成にすごく必要だと思います。もう1つ、マグロの漁獲量が減る一方で、需要は日本や東南アジアを中心に増えているわけですから、商社のビジネスとして意義がある。会社としてもやる意味があるし、若い社員を育てる点でも有効、その2つの観点から全面的にバックアップしています。
もちろん、ほかの商社でも水産系ビジネスには力を入れています。その中で、我々は違う土俵で戦うケースもありますし、どうしても同じ土俵の時は、真っ向勝負だと当社の企業体力では勝てないわけですから、戦い方を考えないといけない。そこは全社員と共有しています。そういう意味でも、他社が手がけていないマグロの完全養殖事業は非常に面白いビジネスですね。

近大とマグロの完全養殖事業で提携。左端が宮下盛・近大水産研究所長、右から2人目が加留部社長(2014年7月の会見)。
〔近大とのタッグは話題性が大きかったが、豊通という会社全体として見れば1事業の域は出ていない。これに対し、加留部氏が12年末に決断した買収案件は全社横断的な規模だ。当時の為替レートで同社では過去最大となる、2340億円を投じて買収したフランスの商社、CFAO(セーファーオー)がそれ。CFAOは、30年には中国を上回る巨大市場になると目されるアフリカ市場で強固な事業基盤を持ち、とりわけフランス語圏の多いアフリカ西側地域で圧倒的な商権を持っている〕
過去最大の投資ですから、我々もものすごく慎重に考えましたし、私も実際に現場を見に行きましたが、先方も傘下の自動車販売会社の修理工場とか、結構オープンに見せてくれましてね。当社とはDNAが合いそうだなと。
もう1つ、彼らは自動車関連事業以外もたとえば医薬関係、あるいはオランダのハイネケンと一緒に合弁工場を手がけるほか、BICブランドのボールペンなど、プラスチック成型品の生産なども手がけていて当社と親和性が高かったのです。
海外に商社という業態はあまりないですが、彼らは自分たちのことをはっきり「商社だ」と言いますから。ですから豊通がやっている事業はすぐに理解してもらえましたし、右から左のトレーディングだけでなく、彼らは工場を持ってモノづくりまで踏み込んでいるので、(トヨタグループの豊通と)お互いの理解はすごく早かったですね。
唯一、気になったのは若手社員の意識でした。若い社員が果たしてアフリカの地でビジネスをやってくれるのかどうか。そこで数人の若手に聞いてみたところ「この買収案件はいいし、アフリカは将来、伸びる市場だからやりましょうよ」と。そういう声に最後、後押しをしてもらえたようなところもあるんです。“一人称”という言葉を当社ではよく使うんですが、一人称、つまり当事者意識をもってやっていく気持ちがあるかどうかが大事ですから。

独自戦略を掲げる加留部氏。
〔前述したように、CFAOは歴史的にアフリカ西海岸エリアの市場を得意とし、豊通は東海岸に強みを持っていたため、エリア補完も綺麗に成立した〕
地域的、事業的な割り振りで言えば、自動車関係はお互いの強みなのでしっかりやっていこうと。アフリカ西海岸で当社が細々とやっていたテリトリーは全部、CFAOに渡しています。物流の共通化なども進めて、お互いの事業効率を高めてきていますし、トヨタ車の販売や物流もCFAOと一緒にやっています。
当社としてはマルチブランドを扱うつもりはあまりなくて、トヨタと日野自動車、スバル(=富士重工)の商品を扱うわけですが、CFAOはマルチブランドなので、たとえば今年、アフリカでフォルクスワーゲンとのビジネスも決めました。
当社はケニアでトヨタ車を扱っていますが、CFAOはケニアにVW車を持ってくるわけです。CFAOは豊通の子会社なのにと一瞬、矛盾するような印象を持たれるかもしれません。我々はトヨタ車で現地シェアナンバー1を取りたいけれども、彼らもVW車でナンバー2を取ればいい。そういう組み合わせみたいなものができてくると思うんです。
いずれにしても、自動車関係のビジネスはお互いに共通しているので、この分野はオーガニックな成長で伸ばしていけるでしょう。一方、医薬品関係はいま、彼らもどんどん伸ばしていて、我々も日本の製薬メーカーを紹介したりといったサポートをしています。
〔豊通がCFAOを買収したことで、新たな効果も表れてきている。たとえば、前述したCFAOが合弁で手がけるハイネケンの工場運営会社。豊通の傘下に入る前は、CFAOの株主が収益はすべて配当で還元してほしいと要請していたため、新しい投資ができなかったのだが、豊通が入ったことでロングタームで事業を見るようになってくれたのだ〕
私もハイネケンの合弁会社社長に会って話をしました。先方も理解してくれて、生産国もコンゴだけだったのを別の国でも展開しようという話に発展しましたしね。さらに、フランス大手スーパーのカルフール。CFAOがカルフールとの合弁でコートジボアールで店舗を出しますけど、これも私がカルフールの社長とお会いし、アフリカ8カ国で展開することを決めました。
日系メーカーとではこんな事例もあります。ヤマハ発動機のオートバイを生産する合弁会社をCFAOがナイジェリアで作るのですが、彼らもヤマハとのお付き合いは従前からあったものの、それほど深かったわけではありません。
一方で、我々は日本でも(ヤマハと)いろいろなビジネスをやらせていただいているので、この合弁話を提案したら了承してくださり、出資比率も50%ずつでOKしてくれたんです。CFAOは豊通の資本が入っている会社だからと、全幅の信頼を置いていただけた。普通は、日本のメーカーが現地へ出るのに50%ずつというのはあまりなく、イニシアチブは日本のメーカー側が取るものだからです。
そういうCFAOとの協業ロードマップは10年スパンで立てていまして、私もCFAOの首脳もお互いに行き来しています。フェース・トゥー・フェースで、年に4回ぐらいは顔を合わせているでしょうか。それ以外にも毎月、テレビ電話での会議も1時間半ぐらいかけて実施し、いまの経営課題や将来の絵図などをお互い共有化するようにしています。
〔豊通には、TRY1という経営ビジョンがある。これは収益比率として自動車と非自動車の割合を均等にしていき、さらに20年にはライフ&コミュニティ、アース&リソース、モビリティの3分野の収益比率を1対1対1にするというものだ。CFAOをテコにしたアフリカビジネスの拡大も、TRY1計画達成に寄与する部分は大きいだろう〕
いまでもCFAOは1億ユーロぐらいの純利益を上げていますから、それだけでも我々は彼らのプロフィットを(連結決算で)取り込むことができますし、プラス、将来的な絵図という意味でも、お互いにステップ・バイ・ステップで各事業を伸ばしていくことで、TRY1の実現にすごく貢献するはずです。
〔総合商社といえば近年、資源ビジネスで荒稼ぎしてきたイメージが強かったが、資源価格の市況に大きく左右されるリスクがあることは、住友商事や丸紅が資源価格の大幅な下落などで多額の減損を強いられたことでも明らか。とはいえ、こうしたリスクテイクは、総合商社にとってはいわばレーゾンデートルでもあり、投資するしないの判断は難しい〕
資源といってもいろいろあると思います。いまさら石炭や鉄鉱石の採掘ビジネスにお金をガンガンつぎこんでもダメ。また、シェールガスやシェールオイルも私が社長になった頃に他社がみんなやり出して、社内でも「やりたい」という声が多かったのは事実です。でも、よく調べてみたら、当社はすでに周回遅れ、しかも1周でなく2周も3周も遅れている。「これでは高値掴みしてしまう可能性があるし、投資金額も大きいのでやめておきなさい」と、社内でかなり明確に言いました。
ですから、我々はもっとニッチで別な土俵で勝負していこうと。たとえば、チリで開発しているヨード。これはイソジンのうがい薬、レントゲンを撮る時の造影剤でも使うんですが、ヨード産地は日本、米国、チリと世界で3カ国しかありません。当社はその全部の産地で開発拠点を持っているので、将来的には取り扱いシェアを15%まで高めたいと考えています。
ほかにも、アルゼンチンではこれからの自動車ビジネスに直結する、リチウム関連の鉱山事業を昨年から始めましたし、豊通らしさというんでしょうか、ニッチキラーでもいいからウチらしさが出て、かつ上位の商社とも十分に戦えるビジネス分野でやっていこう、というのが当社の基本ポリシーです。
〔目下、前述したTRY1達成に向けて歩を進める豊通だが、現在の非自動車ビジネス拡大の基盤を整えたともいえるのが、06年に旧トーメンと合併したこと。トーメンが持っていた化学品や食料といった主力事業分野を得たことで、総合商社としての幅が各段に広がったのだ〕
実際、事業ポートフォリオが広がって、合併は結果として大正解でした。エネルギーや電力関係のビジネスはいま、一部を除いてすごくうまくいっているんですが、こうしたジャンルは豊通のままだったら絶対に出てきていないビジネスですね。
豊通はもともとが自動車関連ビジネスメインでしたから、農耕民族なんです。畑を耕して種をまいて、雑草をとって肥料や水をやってと。それが狩猟民族(=トーメン)と見事に化学反応したという感じ。狩猟民族の人も農耕民族から学んでもらえたし、お互いの良さを認め合ってすごくいい合併だったと思います。
〔加留部氏は横浜国立大学工学部出身だが、就職活動では「とにかく商売がやりたくてしかたがなかった」と述懐するように、入社試験は商社しか受けなかったという〕
私は1976年の入社ですが、当時は就職が全般的に厳しくなり始めた頃で、「商社冬の時代」になりかけていた難しい時期。各商社とも採用人数を絞り、狭き門になっていました。それでも私はとにかく商社に行きたくて、最初に内定をくれたのが豊通だったんです。商社としては規模は小さいけれど、その分、若手にも仕事を任せてくれるんじゃないかと。トヨタグループだから財務基盤もしっかりしていましたしね。
〔豊通入社後は3年目に米国駐在となり、米国でのビジネスで5年間揉まれて逞しくなった後に帰国。国内で6年過ごして結婚後、再び渡米して9年間駐在した。こうした国際経験豊富な加留部氏だけに、昨年からは入社7年目までの社員を対象に、駐在でも長期の研修でも語学留学でもいいから、とにかく一度、海外へ出ることを奨励している。
ただし、加留部氏はほかの商社との戦いにおいては、純利益で何位といった相対的な物差しでなく、あくまで豊通としてどうなのかという基準で考えると強調する〕
2年か3年前、社員みんなにメールを打った時に触れましたが、何大商社とか何位であるとかは、私はまったく関心がないんです。自分たちが目指す方向に向かえているかが大事ですから。たとえば敵失があって他社の順位が下がったとします。仮に順位を純利益で測ったとして、「他社が失敗してウチが5位になったところで君たちは嬉しいか? 私は嬉しくないよ」と。
社員向けのメッセージメールは年に8回か9回出していますが、ある時、新入社員から「何位を目指しますか?」という質問を受けた時も同じことを言いました。各社ごと、事業ポートフォリオがかなり違いますし、順位は関係ない。自分たちのビジネスがどうなのか、常にそこを自問自答し検証することが正しい道だと考えます。
(構成=本誌編集委員・河野圭祐)
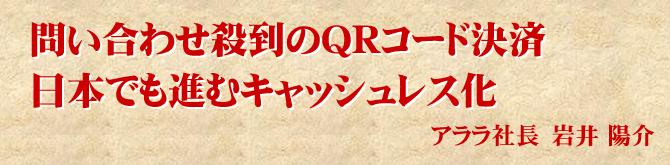
中国では当たり前のように見られるようになったQRコード決済。日本ではまだまだ現金での支払いが主流のなか、QRコードを開発したデンソーウェーブとアララが高セキュリティを実現した決済方法を提案した。
今年3月に行われた「リテールテックJAPAN2018」で、デンソーウェーブのブースに登場し、注目を集めたのがQRコードRを活用したキャッシュレス決済技術だった。これは電子マネーなどのソリューション事業を手掛けるアララの決済技術と、デンソーウェーブが開発したセキュリティ機能を高めたQRコードの技術をもとに共同で開発するもので、本格的に導入されればスマートフォンを使った決済の幅が大きく広がることになるという。アララ社長の岩井陽介氏は次のように話す。

QRコード決済について解説するアララ社長の岩井氏(右)と取締役の竹ヶ鼻氏。
「これまで日本では、磁気カードやSuica、楽天EdyなどのICチップを使った電子マネー決済が主流でした。ところが世界的にスマートフォンが主流になり、QRコードを読み取ることで決済ができるようになっています。Felica(フェリカ)チップを使わず、低コストでキャッシュレスのシステムができることで、中国などで非常に伸びてきています。中国ではAlipay(アリペイ)とWeChat Pay(ウイチャットペイ)の2つに集約され、お店は初期の導入費がかからないため、小さなお店でもQRコード決済が伸びてきています」
今回、展示されたものは、POSで金額を打ち込むと、レジのサブ画面にQRコードが表示され、それをユーザが自分のスマホで読み取り、タップすることで決済が終了するというものだ。ただし、中国などで使われているQRコードとはセキュリティ面などで大きく異なる仕様となっている。
「今回、提供させていただいたのは、デンソーウェーブ社が独自開発した『フレームQRR』やセキュリティ機能を持つ『SQRCR』を活用したもので、有効期限付きのワンタイムQRコードにすることでより安全性を高めています」(岩井氏)
従来のQRコードは、デンソーウェーブが1994年に発表し、仕様を公開、誰でも作成でき、誰でも使える環境になっている。そのため中国では、偽のQRコードを利用したなりすましや詐欺事件など、悪用されるケースも発生した。アララ取締役の竹ヶ鼻重喜氏は決済のセキュリティについて次のように話す。
「中国ではお店に貼られたQRコードをユーザが読み込み、金額を打ち込んで決済ボタンをタップし、決済完了の画面を店員に見せることで支払いを済ませるスタイルを取り入れている店舗があります。ところが、お店に貼っているQRコードの上に偽物のQRコードを貼られ、ユーザがスキャンをしたら別の個人の口座に送金されるという事件が実際に起きました。
フレームQRは、デンソーウェーブの専用デコードエンジンでなければ読むことができません。さらに通常のQRコードはアプリ内のエンジンが解析するのですが、フレームQRではいったん通信をしてサーバーでデコードをし、それをスマホに戻しています。つまりサーバーにログが残るのでいつ誰がどこでデコードをしたのか、きちんと発行したQRコードなのか、サーバー上でチェックできる仕組みになっています。また『SQRC』もサーバー通信しますが、これはふつうのQRコードリーダーで読めば『A』という表示しかされませんが、専用のリーダーで読めば裏側の『B』という情報も読めるものです。偽造をしようにも表面の『A』しか読めないため、改竄ができない仕組みになっています」

デンソーウェーブとアララが共同開発したQRコードリーダー「Q」のダウンロードはこちらから。
サーバーと通信することで、お店側とユーザ側がともに確定することができ、電子レシートが発行され、履歴も残るという。ユーザがタップして送金した情報が、その場でレジにも届き確認できるのが理想だ。
日本ではカードにしろスマホアプリにしろ、Suicaや楽天Edyをはじめ、Felicaチップを採用した電子マネーが一般的だ。しかしQRコード決済を前提にした決済方法も増えてきている。NTTドコモの「d払い」はスマホに表示されたバーコード(QRコード)を見せて店側に読み取らせる形、Origami Payはレジ側のQRコードをユーザが読み取って決済する形を採用した。楽天ペイ、LINEペイなども実店舗での決済はバーコードあるいはQRコードを使っており(d払いと同じ方式)、仮想通貨のビットコインでもビックカメラなどで買い物をする際はQRコードを使った決済(Origami Payと同じ方式)が採用されている。
「内閣府の『未来投資戦略2017』では27年6月までにキャッシュレス決済比率を4割程度に増やす発表がされるなど、日本自体がキャッシュレスを進める動きになっています。キャッシュレス化が進めば店舗のオペレーションも簡略化され、便利な世の中になるはずです」(竹ヶ鼻氏)
「我々の提供するハウス電子マネーサービスに繋げることもできますし、クレジットカード、デビットカード、口座引き落としなど、複数の手段に対応することを想定しています。外国人観光客も増え、お店も様々なペイメントに対応しなければならないなか、QRコードを使うことで煩雑さを減らせるソリューションを提供していきたいですね」(岩井氏)
QRコード決済で、日本にもキャッシュレス化の波が一気に押し寄せることになるかもしれない。

レジ横の画面に表示された「フレームQRR(R)」を読み込む。 ユーザが支払い確定のタップをすることで決済完了。
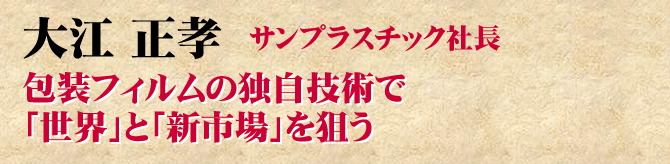

大江 正孝 サンプラスチック社長
おおえ・まさたか 1982年10月31日生まれ。千葉工業大学プロジェクトマネジメント学科卒業後、プラスチックフィルムメーカーに入社。入社3年で総務経理担当取締役就任。2014年、事業承継のためサンプラスチック株式会社を創業。日本国内トップシェアのPVCシュリンクフィルムで新市場を開拓し、世界一のフィルムメーカーを目指す。
── サンプラスチックの事業について教えてください。
「シュリンクフィルム」の製造を主力としています。あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、実は身近な製品です。商品を覆ったフィルムに熱を加えて収縮(=シュリンク)させ、商品がぴったりと包まれるという技術で、ペットボトルのラベルや化粧品の箱などにかけられているフィルム包装としておなじみです。そのほか当社では、帯電防止フィルムと導電フィルム(静電気を逃がす機能を持ち、精密機器や電子部品を静電気障害から保護するフィルム)などを製造しています。
── たしかに多くの商品がフィルムでくるまれています。薬事法や食品衛生法はフィルム包装を義務付けているのですか。
義務はないのですが、特に日本では広く普及しています。シュリンクフィルムは、工業用途を中心に、絶縁体として、または半導体の被膜として活用されてきました。しかし、ある事件を契機として、生活空間に拡大していきました。
それが「グリコ・森永事件」(1984?85年)です。一連の事件の中で、毒物が混入した食品が全国のスーパーにばらまかれ、消費者にとっては、一時は店舗で食品を購入することが恐ろしくなるほどのショックを与えました。事件を受けて食品の安全性を高めるため、容器に未開封を示すシールを貼る、開封されたことが一目でわかる構造の容器を採用するなどの対策がとられます。シュリンクフィルムを含むフィルム包装もそのひとつだったというわけです。現在では、商品の保護だけでなく、マンガ本、電池、雑貨などのあらゆるパッケージに使われています。
── 包装材は品質とコストのバランスも難しそうです。御社の商品の強みは。
シュリンクフィルムには多様な素材が使用されます。そのなかで当社では「PVC」(ポリ塩化ビニル)に絞って扱っています。PVCは生産コストが安く、購入ロットも少なくて済む。ほかの素材ではフィルムを糊で接着する手間やコストが発生しますが、PVCは熱でよく縮むため加工も簡単で、工場など大掛かりな設備を使えない個人でもフィルムをかけることができます。使い勝手のよい優秀な素材です。
PVCは、いわゆる「ダイオキシン問題(90年代~)が社会問題化したことが一因となり、他素材への代替が進みました。現在は高温焼却によりダイオキシンを発生させない処理の仕組みができていますが、シュリンクフィルム市場全体におけるPVCの存在感は大きいとは言えません。市場規模は約2000億円、そのうちPVCは4億円ほど。当社はPVCで約60%のシェアを持つトップ企業ですが、PVCを扱う企業はほかに4社しかない。業界全体で市場を拡大していく努力が必要です。
── なぜ、PVCのなかでトップシェアをとれたのでしょうか。
開発力ではないでしょうか。PVCに限らずですが、プラスチックへの規制は年々強まっており、使用できない添加剤が毎年増え続けている状況です。たとえば、最近ではフィルムを軟化させる可塑剤の「フタル酸」が、環境ホルモンとの関連性を疑われ「ROHS」(ヨーロッパの輸入規制の一種。日本企業の自社基準値にも影響を与える)の対象になりました。そうした規制の更新のなかで、コストや加工性を損なわずにフィルムを作り続けるには、技術力とアイデアが必要です。
また、私はPVCという素材に愛着があるのです(笑)。サンプラスチックは2014年創業ですが、事業承継によるものでした。私は前身となる会社に新卒で入社してから、設備も職人もPVC一筋といえる環境でビジネスをしてきました。いまもこの素材にこだわりながら事業に打ち込んでいるところなんです。
── 今後のサンプラスチックの展望について、また、シュリンクフィルム業界の将来をどう見ていますか。
「世界展開」「新分野開拓」を狙います。
先日、ベトナム、ミャンマーなどのアジア地域を視察しました。シュリンクフィルムは世界中にありますが、日本のフィルムのクオリティは格別です。袋型で包む構造や品質追究の姿勢は日本ならでは。ですが、それだけで世界で勝てるものではないでしょう。海外には使い捨ての包装にコストをかけ品質を求める価値観はない。むしろ欧米ではエコの意識からも、プラスチック包装は嫌われる傾向です。さらに中国には安価で大量に製造できる圧倒的な体力がある。我々は新しい付加価値を生み出すことで対抗する以外ありません。
ではどうするか。シュリンクフィルムは前述のようにフィルムを熱で縮ませるという特殊かつシンプルな技術。さらに添加剤の配合でさまざまな機能をもたせることもできますから、包装以外の新しい分野に活用を広げられると考えています。
たとえば、異素材やプリントを貼り付ける利用方法。ゴム手袋やレインコートなどに鮮やかな模様を印刷したPVCを接着させれば、デザインに貢献します。抗菌素材を混合すればコーティング効果を高めることもできる。蛍光塗料や蓄光剤を混合した暗闇で光るフィルムは利用価値があるのではないか。導電性をもたせられれば、ウェアラブル端末に活用できるかもしれない。まだまだ可能性はあるはずです。
目標はPVCの市場を現在の倍にすること。競合他社とも力を合わせ、業界を再起したい。トップシェアを持つ当社が、その流れをつくっていきます。