





かつての工場、倉庫街のイメージとは風景が一変し、整然とした街並みにモダンな高層ビル群が屹立する東京・江東区豊洲。アスクルの本社は、同エリア内の豊洲キュービックガーデンにある。このビルに本社移転したのは、2011年の東日本大震災後のことで、それまでは01年から10年強、隣り駅の辰巳にあった。辰巳のオフィスは倉庫を改造したものだったが、「震災時は、幸い怪我人は出ませんでしたが、東京とは思えないくらいの被災の仕方で、みんな怖い思いをしたので新しく安全な場所を探そうと」(アスクルの岩田彰一郎社長)。

アスクルの岩田彰一郎社長は、オープンな“共同執務スペース”で執務。
現在の豊洲の高層ビルは免震構造で、安全性の担保はまったく問題がなかった。辰巳のオフィスは広いフロアの上部に長いブリッジが架けられ、オフィス全体が見渡せるようになっていたが、現在のオフィスも、岩田氏のアイデアでいろいろな工夫が施されている。象徴的で出色なのが。岩田氏の社長室はなく、六角形をした囲いの中で、岩田氏や他の役員、秘書スタッフが執務し、椅子から振り向けばいつでもミーティングに入れる、極めてオープンなものだ(右にある写真)。
また、アスクルのオフィスは2フロアにまたがっているのだが、岩田氏は“内階段”を作ることにこだわった。同氏曰く、「ビルに内階段を作ると結構、コスト高になるのですが、できるだけコストセーブして螺旋階段を通し、自由に行き来できるようにしたのです」
同氏がそこまで考えた理由は、大きなビルに移転してもオープンなコミュニケーションを徹底することだった。上下2フロアはエレベーターでの行き来でなく、いわばアスクルという大きな家に集うような、風通し感を大事にしたかったのだろう。
同社のオフィス空間は、特に無機質で退屈な大企業のオフィスを見た後であれば、誰でも驚きを覚えるほどだ。また、来客の通路の導線には間伐材を使って温もりも演出している。さらに、社内の技術系社員たちが集まるワークスペースは“エンジニアの森”と呼び、個々人のデスクの周囲を緑と木でお洒落に囲い込むといった工夫もある。
こうした空間デザインの考案がもともと好きだったという岩田氏は、マーケティングの才覚に長けた、アイデアマンとして知られてきた。まず、その軌跡を辿ってみよう。
大阪教育大附属高校を経て慶應義塾大学商学部に進学した岩田氏は、元ダイエー副社長の中内潤氏や、サントリーホールディングス会長の佐治信忠氏らも学んだ村田昭治ゼミに入り、1年先輩にエーザイの内藤晴夫社長らがいる。時代背景的には、岩田氏の1、2年生時は大学紛争真っ只中で、慶應大学でもたびたびキャンパスが封鎖されていた。一方で、同氏は「シルバーキャノンボール」というテニスクラブに入り、交友も広げて大学生活をそれなりに謳歌していたようだ。
やがて就活のシーズンを迎え、ゼミでも広告系を学んでいた岩田氏だけに、「就職は電通に行きたいです」と前述の村田氏に相談したところ、「マーケティングをやりたかったら広告会社ではなく、メーカーに行ってマーケティングを一から勉強したほうがいい」とアドバイスされたという。その結果、1973年にライオンに入社。当時のライオンは花王を激しく追い上げる勢いがあり、テレビCMも華やかで、実戦でマーケティングを学ぶ企業としてはうってつけだった。
ところが最初の配属は大阪支店。当初は小さな卸会社やスーパーを担当したのだが、3年半ぐらい経った頃に転機が訪れた。東京のライオン本社からマーケティング本部長が来て案内役を担った際、マーケティング志望だということを熱く訴えたのだ。念願叶って25歳の時に本社に戻されてマーケティングの仕事に従事。後に岩田氏が手がけたヒット商品の代表例が、シャンプーの「フリー&フリー」である。
「女性は洗浄力でなくてヘアメイクをシャンプーに求めているのだから、そういう商品を作ろうと。当時、女性誌の『JJ』などがよく読まれていた頃で、流行っていた髪型も全部ビデオでチェックをし、ライオンの研究所を含めて100回ぐらいプレゼンしましたね。結果、商品がヒットして社内で表彰もしていただき、ライオンでは初めてフランス人のデザイナーを起用させてもらったりと、かなり自由に仕事をすることができました」
ちなみに、岩田氏より4歳年少で同じライオンに勤めていたのが、後に日本コカ・コーラ社長を経て、現在、資生堂社長を務めている魚谷雅彦氏だ。魚谷氏は当時、米国の大学に留学中だったが、社内報で岩田氏の活躍を知り、以来今日に至るまで親交が続いている。ひょっとすれば魚谷氏と一緒に仕事をするチャンスもあったかもしれなかったが、岩田氏はライオン入社13年、35歳にして転職という大きな決断をした。
転職先は、事務用品やオフィス家具を扱うプラス(63年11月創業)。慶應大学で1年後輩にあたり、交友が深かったプラス創業家の副社長、今泉公二氏(当時。現・社長)から足かけ3年にわたって再三、「一緒に、世界で通用する文房具を作ろう」と熱心に口説かれていたのだ。まさに三顧の礼で、これには岩田氏も心を動かされた。
今泉氏も岩田氏に負けず劣らずのアイデアマンで、たとえばかつて、プラスのヒット商品となった「チームデミ」という文房具キットは、今泉氏が手がけたものだった。岩田氏がプラスに転じた後、文房具だけでなく、日用品やキッチン用品へ商品アイテムの領域を広げる議論も起こったが、そこまでの許可はまだ取れず、ベーシックでかつユニークな、新基礎文具というジャンルにチャレンジしていった。カッターナイフの「ツリーズ」、あるいは消しゴムの「エアイン」などがそれだ。

社内は遠くまで見渡せる開放的なスペースになっている。
通常の商品でも、たとえばお洒落で新しさもあるファイルを、浜野商品研究所のメンバーたちと生み出していったのだが、市場調査段階では人気があったものの、いざマーケットに投入してみるとまったく売れない。その理由を突き詰めていった結果、文房具業界で圧倒的な力を持っていた、コクヨの存在にぶち当たった。文房具の販売店側にしてみれば、同じジャンルの商品であればコクヨ製のほうを優先的に販売するのはいわば自明の理。この壁をどうにかして突破する手立てを考えたことが、アスクルのプロジェクトの原形になったのだ。
プラス社内にアスクル事業部が発足したのは93年3月で、25年前のことである(97年にプラスから分離、独立)。親会社の一事業部からスタートし、後に分離、独立していった小売業の事例に、西友から派生した良品計画、西武百貨店から一旦は独立したロフトなどがあるが、アスクルの場合は、立ちはだかったコクヨの存在が大きかったわけだ。
「マーケッターの1人として、お客様が手に取ってダメだというのは諦めがつきますが、お客様の目にも手にも触れないで商品が死んでいくのは、やはりいてもたってもいられないわけです。ならば、ダイレクトにお客様に売りにいこうと。我々のお客様は法人マーケットが75%ぐらいでしたから、そこにターゲットを絞る。中小の法人ではみんな、お昼休みなどに女性社員が文房具や備品などを買い回るというのが昔の購買習慣でしたので、ここにサービスをしようというのがアスクルのコンセプトです」(岩田氏)
ビジネスモデルのコンセプトを詰めるのに2年ほどを要したが、顧客は文房具の販売店ではなく最終消費者だと定め、無駄なものは排除して効率的なバリューチェーンにすることを決めた。
だがカタログ通販にした過程で、顧客の要望もあってプラス以外の商品も幅広く扱うようになり、同時に価格面でも顧客の希望に合うリーズナブルな値付けにしていったことで、プラスから分離、独立する必要性に迫られたのだ。独立時のメンバーは、わずか4人だった。そして独立後、パブリックな企業になるという観点から、2000年にまずジャスダック市場に上場し、04年には東証1部に指定替えした。
アスクル事業は、初年度が売り上げ2億円、以降、6億円、19億円、53億円と倍々ゲームで業績を伸ばした。ただし、株式公開後には市場の洗礼を浴びることにもなった。上場したのは2000年11月だったが、売り上げ見通しの800億円を750億円に下方修正した途端、4営業日連続でストップ安になったことも。岩田氏は、「上場した後の市場の厳しさ、怖さを身をもって体験しました」と述懐する。ちなみに、アマゾンが日本に上陸したのも、奇しくも同じ2000年11月だった。
その後、リーマンショックが起こる08年までは再び右肩上がりの成長軌道を描いたのだが、大企業の顧客も含めて、取引企業が一斉に大がかりなコストセーブに走ったため、岩田氏も初めて成長が止まる経験をした。そこから再度、成長軌道に乗せるべく努力していた矢先、冒頭で触れた東日本大震災に見舞われたのだ。ヤフーとの資本業務提携に至ったのは、翌12年のことである。
「オフィス・デポさんに対して、実は92年ぐらいから米国で調査をずっと定期的にやってきて、いずれは大きなライバルになるなと。で、仮想ライバルをオフィス・デポに置いて準備をしていました。
その後は仮想ライバルをオフィス・デポさんからアマゾンさんに置き、どう戦っていけばいいんだろうと考えてきました。これからはEコマースでアマゾンの時代が来ると。その時にカタログビジネスは必ず飲み込まれてなくなる。となると、B2BとかB2Cの境も徐々に消えていく。生き残るには、次に大きなビジネスモデルのチェンジをしなければいけないし、併せて物流の投資も必要。かなり突っ込んだ議論をしたのです」
出した結論がヤフーとの資本提携(現在のヤフーによるアスクルの持ち株は41.6%)で、アマゾンと戦っていくための軍資金、330億円を調達し、筆頭株主もプラスからヤフーに替わった。ヤフーはヤフーでちょうど社長交代して、爆速で攻めると評判だった宮坂学社長が登板して意気投合、満を持して立ち上げたB2C事業がロハコである。
「ロハコ事業が大きく伸びたところで、今度は火災事故(17年2月の埼玉県三芳町の大型物流センターの火災)。ここで大きく一回転び、まさにいま、態勢を立て直してアマゾンを追っかけていくところです。この5年間でEコマースのノウハウをかなり蓄積し、そのノウハウがB2Bのほう(=アスクル)にかなり移植できました。たとえば、AI(人工知能)を使ったリコメンデーション機能がサイトで表示できるようになったとか、ロハコ事業のノウハウはかなり、アスクルの事業にも活かされてきています」
前述の火災事故が縁となり、昨年7月にはセブン&アイ・ホールディングスとの業務提携を発表、同年11月末から生鮮宅配のIYフレッシュの事業もスタートした。
今期(18年5月期)以降は、収益も再び成長軌道に乗るだろうが、怒涛の攻めのアマゾンを筆頭にEC市場の争奪戦は熾烈さを増す。マーケティングのプロでもある、岩田氏の次の一手はいかに――。
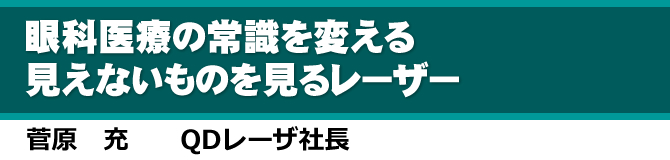

菅原 充 QDレーザ社長
すがわら・みつる 1958年生まれ。新潟県出身。82年東京大学工学部物理工学科卒業、84年同修士課程修了。95年東京大学工学博士を取得。84年富士通入社。富士通研究所 フォト・エレクトロニクス研究所フォト・ノベルテクノロジ研究部長、ナノテクノロジー研究センター センター長代理等を歴任し、2006年、富士通のベンチャー支援制度により、QDレーザを設立、社長に就任。
2016年の「CEATEC JAPAN 2016」で最高賞にあたる経済産業大臣賞を獲得したのがQDレーザ。網膜に直接映像を映し出す「網膜走査型レーザアイウェア」で注目を集めている。
このアイウェアで驚くのは、メガネやコンタクトレンズを使っても十分な視力矯正ができないロービジョン(全盲ではない視覚障害者)の人でも鮮明にモノを見ることができる可能性があること。ロービジョンと一語で言っても、症状は多様で、緑内障や白内障をはじめ、強度近視など幅広い。これらの患者の多くが、このアイウェアを使えば目の前の景色が見えるようになるという。すでに発売目前の段階に入っている「網膜走査型レーザアイウェア」について、QDレーザ社長の菅原充氏に話を聞いた。
── シーテックで経済産業大臣賞を獲得して以降、メディアに登場する機会も増えていますが、改めて「網膜走査型レーザアイウェア」について、解説していただけますか。
網膜に画像を書きこむというテクノロジーで、アイウェア「RETISSA(レティッサ)」と網膜に直接投影する新技術「ビジリウムテクノロジー」を商標登録しています。このアイウェアをロービジョンの方々に届けるプロジェクトを始めています。
PCやスマートフォン、カメラからのデジタル情報を、網膜にそのまま書き込むことができる。そのデジタル情報をRGBの三原色の光に変換して、それを点描画していく形です。プロジェクター自体をアイウェアの中に持ってきて、網膜をスクリーンとして映し出す。アイウェアの中心にカメラが付いていて、その映像をそのまま見ることができたり、あるいはスマートフォンの動画を観たりすることもできます。
レーザー光が瞳孔に照射されて、網膜をスクリーンとして直接画像を届ける。基本的に我々がモノを見る時は、目のレンズ全体を使って見る。そのレンズが曇っていたり、ピントが合わなくなると画像がきちんと見えないわけですが、細いレーザー光を使うので、曇っていようがピント作用があろうがなかろうが、目の調節作用によらずに鮮明な画像を見ることができます。
2年ほど前に日本の病院で視力試験をやってみたのですが、35人被験者がいて、裸眼視力は0.0いくつから、1.5くらいまで幅広く試してもらいました。すると、網膜に書き込んだ時の視力は、裸眼の視力がよい人も悪い人も、平均して0.5前後になります。つまり、目のレンズ調節機能に関係なく同じ視力になったわけです。
私は、これを医療運用しようとしています。目の病気にはいろいろあって、屈折異常や混濁とか網膜症とかありますが、特に前眼部の曇りや屈折にかかわらず画像を書きこむことができるので、そこがおかしくなった人たちの視力を上げることができます。これはハンディでウェアラブルなものですから、日常的にメガネとしてかけて使うことができます。
専門的な話になりますが、眼底検査のSLOや断層撮影のOTCと同じレーザーテクノロジーですから、将来的にすべての装置をコンバインして、1つの装置にすることも可能です。アイウェアをかければ、目のどこに病変があって、どのように視機能を妨げているかがわかるようになります。そこまでたどり着ければゴールだと思います。
── 角膜に異常があったり、白内障でも光さえ通せれば、目が見えるようになるわけですね。
全盲だと難しいのですが、レーザー光が通せれば見ることは可能です。ロービジョンの方は、世界中で2億4600万人くらいいると言われていて、日本では145万人と言われています。特に日本は、高齢化が続いていることもあって、増えていくと予想されます。目の病気は高齢になるほど増えていき、元には戻りません。目の病気があると、QOLが下がって、気持ちが落ち込んだり、事故が増えたり危険なことがたくさんあります。レティッサなら前眼部をバイパスして画像を認識いただけます。持ち運びもしやすいですので、美術館に行って絵を見たり、会議で人の表情を見ながら会話することができるわけです。
いま欧州と米国と日本で医療機器認証を取ろうとしていて、臨床試験を受けることになっています。網膜に直接レーザーを届けることで、病変と視機能を同時に測ることができ、病変の早期発見や見え方と病変の相関を明らかにすることができるでしょう。SLOやOTCのデータが統合されていくと、AIで解析して、どんな生活をすればどんな病気が起こるかまでわかってきます。アイウェアをかけるだけで、将来の失明を救うこともできると思っています。
── レーザーを使った視力回復の発想はどこから生まれたんですか。
もともと私はレーザーを通信やインターコネクトなどいろんな分野で展開してきました。レーザーでディスプレイに映すというのは、ずっと研究されてきていたんですね。網膜に画像を書きこむという技術は、それ自体は30年くらい前に発想があって、特許も取っていました。2013年に試しに作って発表してみると、視覚障害者の方から試させてほしいと連絡をいただきました。盲学校に持っていくと、これを使えば見えるという人が結構いたのです。事業として可能性があると思ったのは14年になってからですね。

網膜走査型レーザアイウェアの「RETISSA」。メガネの内側に機構を付けることで、外観をより自然なものにした。
── 富士通時代から、レーザーの可能性をいろいろ研究されていたわけですね。
特に量子ドットレーザーという通信向けのレーザーを基礎からやっていまして、広いバックグラウンドは持っていました。QDレーザ自体は、通信向け、光インターコネクト向けの新しいレーザーを事業化するために始めた会社ですが、ディスプレイやセンシング、メディカルと、いろんな分野にレーザーを応用できる基盤技術を持っていることに気が付いて、広げてきたところです。
18年の7月から、レティッサの試験販売を数百台から1000台の規模で行います。民生機器として売るんですが、治験が終わって医療機器の認証が取れた段階で、19年度から本格的に販売していきます。いまより安く、高性能、小型にしていくというプロセスで開発を進めていますので、東京五輪の頃には、世の中に知られて広まりはじめていると思います。
── 価格はどれくらいを?
10万円くらいでできます。実は、これは半導体レーザーの技術なので、もともと我々が持っているものです。メガネに半導体とスマホの技術があればできてしまいます。数千台レベルでもその価格は可能で、もっと安くできる。あとは作り方とパートナーシップですね。
── 先ほど私もレティッサを付けさせてもらいましたが、健康な目でもかけられることで、様々な可能性を感じます。
2~3年後には、プロジェクターの機構がメガネに埋め込まれるまで小さくなります。つまり、ふつうのメガネにIT機能が付くところまでいくでしょう。数年先になると思いますが、スマートフォンと連動して、スマホの情報が、そのまま見たい時に見られるようになる。このアイウェアのいいところは、レーザーが瞳孔を通らないと見えないので、見たくない時には見なくてすむわけです。メールを見たい時だけ、少し上を向くと、メールが読める。もうそういう時代に来つつあります。
── いいことずくめの話でしたが、QDレーザにとって、今後の課題はなんでしょうか。
アイウェアについては、小型低電力化が課題ですね。いまはフル充電でも2時間強しかもたない。最初の頃のスマートフォンもそうだったと思いますが、小さくしても電池がもたなければ辛いです。それを倍にしようと、次のモデルの開発を進めているところです。
レーザーは80年代に光通信を作り、CDやDVDの光記録を作り、インターネット社会を作ってきました。それがレーザーの第1世代だとすると、いまは第2世代が始まっています。新しい分野を自分たちで開拓していかなくてはいけません。とっかかりが医療機器やメガネですが、レーザーの広がりはそんなものだけではない。我々の力で、新しい世界が作れればいいと思います。
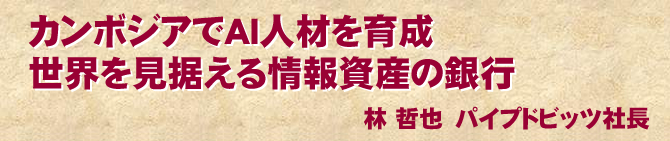

林哲也 パイプドビッツ社長
はやし・てつや 1973年生まれ。東京都出身。97年青山学院大学大学院修了後、SAPジャパン入社。2006年デジタルフォレスト入社。10年パイプドビッツ入社。13年取締役CTOを経て、15年代表取締役に就任。
いまやインターネットは企業の業務に欠かせないものになり、企業活動におけるデジタルデータの取り扱いが爆発的に増えている。これらのデータを利活用し、企業の業務に必要なアプリケーションを自由に構築できるプラットフォーム「スパイラル」を提供しているのがパイプドビッツだ。導入アカウントは3459件に達し、さらにAIやIoTの新技術分野にも手を広げる。社長の林哲也氏にAI戦略を聞いた。
── パイプドビッツと言えば、中小企業向けのクラウドサービスというイメージが強かったですが、2015年9月に持株会社化に移行し、体制もかなり変わってきましたね。
確かに10年くらいまでは中小企業向けのSaaSという位置づけでサービスを提供してきましたが、現在は決まった既製品ではなく、簡易オーダーメイドのような形でシステムを作れるようにしまして、PaaS(Platform as a Service)へと製品の位置づけをシフトしてきました。オーダーメイドで提供できるようになったことにより、より大きなお客様のシステム案件ができるようになっています。データ量も昔は5000~1万レコードがボリュームゾーンでしたが、現在では100万~1000万レコードと、大きなお客様の資産をお預かりする形にビジネスが変化してきました。
近年は金融業界がFinTechを進めるようになって、銀行等のシステムの領域にベンチャー企業が踏み込めるようになっています。いままで大手のSIerでしか扱っていなかった大企業のシステムに我々のシステムも入っていけるようになり、それに伴ってデータのボリュームも増えてきた感じですね。
── IoTやAI(人工知能)といった新技術の開発についても積極的ですね。
我々は「情報資産の銀行」を事業コンセプトに、お客様からデータをお預かりしています。その情報資産をどう活用できるか。様々なサービスを提供していくなかで、AIの領域もつくっていく必要があると思っています。AIの領域では2つ考えていきたいと思っていまして、1つがお預かりしたデータの活用。例えば不動産のお客様なら、この沿線のこの駅の徒歩何分でこの間取りの部屋であれば、賃料はいくらくらいが適切なのかをAIで算定する。多くの不動産屋では、経験と勘にもとづいて賃料を予測していると思いますが、AIを使って妥当なものを導くことができるようになれば、オーナーさんが自分で調べたり、オペレーションのコストを削減したりといったことができます。
もう1点は、弊社はPaaSということで、WEBアプリケーションをいかに生産性が高く、安全につくっていくか。アプリケーションの開発をしていくなかで、セキュリティ上のリスクや効率は、プログラミングの知識や経験が大きいですが、ここにAIを活用することで、知識の少ない人でもより安全に開発の生産性を高められるようにしていきたいですね。
── 興味深いのは、カンボジアでAI開発、AI人材の育成に取り組み始めたことです。ベトナムやミャンマーという企業が多いなかで、なぜカンボジアだったのでしょうか。
私はもともと外資系企業からデジタルフォレストというASPの会社にいたんですが、その会社がNTTデータに買収されたことで、パイプドビッツに入りました。1つは世界に出ていきたい、グローバルで開発していきたいという思いがあったからです。しかしながら、いまでは日本で開発者を集めることが難しい。特に良質なエンジニアを採用することがたいへん厳しくなっています。そこで3~4年ほど前から外部のオフショア会社を使い始めました。自分たちでグローバルなオフショアを使うにしても、日本の開発者たちがそれを使いこなせなければ意味がないですから、まずは外部のオフショアリソースを使い始めたわけです。そこはベトナムでした。2~3年やっていくうちに、これならいけると手応えがありましたので、外部ではなく、自分たちでオフショアリソースを持とうと考えました。
中国は、いい人材は日本よりも高いくらいの賃金になっていますし、ベトナムも競争が激しい。ポストベトナムとして挙げられるのがミャンマーですが、すでに大手ベンダーさんが進出していまして、人材競争に巻き込まれる恐れがあります。
実は、デジタルフォレストの創業社長だった猪塚武さんがカンボジアの高原リゾートに「キリロム工科大学」を設立していまして、観光学園都市の開発をしていたんです。そこで猪塚さんにカンボジアはどうかと相談しました。
カンボジアは内戦等で教育はどうなのかというイメージを持たれると思いますが、猪塚さんが知能テストや数学のテストで成績が良い子を選んでITの教育をし、人材として活用できるようにしています。実際、視察に行くと、日本の新卒で優秀な子たちと同じくらいの感じです。ITの能力的にもオフショアでもいけると思いまして、カンボジアに設立しました。
カンボジアのいいところは、外資100%で会社を作ることができ、法律自体は日本が支援していることもあって、似ているところもあります。外資にとっては会社が作りやすい環境があります。ただ、人口がベトナムやミャンマーより少ないこともあって、のちの市場として見ると小さいですので、出ていく企業が少ないのかもしれません。
── 人材は育っている印象はありますか。
昨年の6月からですから、まだまだこれからですね。技術者と言っても2つのレイヤーがあって、1つはAIそのものを作る人。この人材は中国や米国で取り合いになっています。もう1つは、彼らが作ったAIをどう活用できるのか、活用の仕方を考えて作る技術者です。OSを作るのと、OSの上で動くアプリケーションを作ること。この2つのレイヤーのうち、我々は後者の人材を育てています。
── カンボジアでの関心は高いのでしょうか。
インターネットでフェイスブック等をよく見ていますから、知識や学習の意欲は高いです。彼らはAIやブロックチェーンをやれば、グローバルで活躍できてお金持ちになれるんじゃないかという夢を持っていますので、勉強したいと思っているんですね。まだ進出している企業は少ないですから、ポテンシャルのあるいい子を採用できると思います。
── パイプドビッツにとって、AIに関する需要はどのように捉えていますか。
AIもパターン認識だと考えていまして、大きなデータのなかからどういうパターンが導き出されるのか。特に弊社の場合はマーケティング分野でサービスを使われることが多いですので、いろんなパラメーターをもとにAIで分類できるような形にする。ただ、我々もAIとはいえ、機会学習エンジンと言ったりして、確率統計の理論の延長線上にあると考えています。まずはデータを集めて、最適な対応策、リターンを出すというところにフォーカスしています。いままではパラメーターを調整するのもエンジニアが入らないとできなかったわけですが、エンジニアがいなくても自動的に最適なモデルを選び出すような、そういったものを考えています。
── ターゲットとなる企業規模はどれくらいを考えていますか。
企業規模と言うよりは、データのボリュームがどれくらいかですね。
── 小売業はPOSレジもありますし、活用できそうですね。
POSだけでなく、WEBチャネルもありますしね。オムニチャネルのなかで、様々なデータをミックスしたうえで、そのお客様に響くオファーができます。小売りだけでなく、不動産や金融も需要があると思います。そのなかではマーケティング業務は我々の強い分野です。
── 今後はクラウドサービスの「スパイラル」とAIが結びついていくと思いますが、どういった展開を考えていますか。
将来的には、採用や採用後の活躍などに紐づいたデータや、そのようなアプリケーションも作れます。弊社でも個人の業績管理システムを運用していますので、こうしたところも提供できればいいですね。
── 人事用のHRテック(Human Resource X Technology)にも進出すると。
従来の多くの会社が採用や面接をしても、その時のデータがフィードバックされていません。どういう人が退職しやすいとか、経験と勘でやってきたところはAIに置き換えやすい。ただ、現状ではお客様の要望でシステムを組み上げるカスタマイズサービスの形になりますので、専門のHRテックサービスと比較すると、コスト競争力で厳しいです。「スパイラル」を使っているお客様であれば追加で導入しやすいですので、提案の余地はあると思っていますが、商品というよりはまず自社でやってみようと考えています。
ほかにもIoTは情報を集めるためのインターフェースですし、ブロックチェーンもデータベースとして活用できますので、この辺りは積極的にやっていきます。そのためにもアジア圏を第1ステップとして、世界に広げていきたいですね。
(聞き手=本誌編集長・児玉智浩)


加留部 淳 豊田通商社長
かるべ・じゅん 1953年7月1日生まれ。神奈川県出身。76年横浜国立大学工学部電気工学科卒。同年豊田通商に入社。99年物流部長、2004年取締役入り。06年執行役員、08年常務執行役員、11年6月末より現職。学生時代はバスケットボール部に所属。座右の銘は着眼大局、着手小局。
〔昨年、豊田通商が近畿大学と提携して卵から育てるマグロの“完全養殖”事業に参入(養殖事業そのものは2010年に業務提携)するというニュースが大きな話題になった。11年に同社の社長に就いた加留部淳氏は、就任後初めての出張が近大水産研究所で、同研究所の宮下盛所長と意気投合。今後は豊通と近大のタッグで完全養殖マグロの生産を順次拡大し、海外へも輸出していく計画だ〕
もともと当社は人材育成には力を入れ、いろいろな研修プログラムを用意していますが、その中に若い社員の事業創造チャレンジのプログラムがあるんです。自分たちでまず研究し、社内外の先輩や識者の意見も聞いて新事業案を作らせるものですが、その過程で「ぜひ、近大さんの販売や養殖のお手伝いをしたい」と提案してきた社員がいましてね。
面白い事業プログラムだったので、当時の経営陣が「やってみろよ」と。で、動き始めて実際に予算もつけ、近大さんにもお話をしに行ってというのがスタートでした。こういう社内提案制度は、起業家精神の醸成にすごく必要だと思います。もう1つ、マグロの漁獲量が減る一方で、需要は日本や東南アジアを中心に増えているわけですから、商社のビジネスとして意義がある。会社としてもやる意味があるし、若い社員を育てる点でも有効、その2つの観点から全面的にバックアップしています。
もちろん、ほかの商社でも水産系ビジネスには力を入れています。その中で、我々は違う土俵で戦うケースもありますし、どうしても同じ土俵の時は、真っ向勝負だと当社の企業体力では勝てないわけですから、戦い方を考えないといけない。そこは全社員と共有しています。そういう意味でも、他社が手がけていないマグロの完全養殖事業は非常に面白いビジネスですね。

近大とマグロの完全養殖事業で提携。左端が宮下盛・近大水産研究所長、右から2人目が加留部社長(2014年7月の会見)。
〔近大とのタッグは話題性が大きかったが、豊通という会社全体として見れば1事業の域は出ていない。これに対し、加留部氏が12年末に決断した買収案件は全社横断的な規模だ。当時の為替レートで同社では過去最大となる、2340億円を投じて買収したフランスの商社、CFAO(セーファーオー)がそれ。CFAOは、30年には中国を上回る巨大市場になると目されるアフリカ市場で強固な事業基盤を持ち、とりわけフランス語圏の多いアフリカ西側地域で圧倒的な商権を持っている〕
過去最大の投資ですから、我々もものすごく慎重に考えましたし、私も実際に現場を見に行きましたが、先方も傘下の自動車販売会社の修理工場とか、結構オープンに見せてくれましてね。当社とはDNAが合いそうだなと。
もう1つ、彼らは自動車関連事業以外もたとえば医薬関係、あるいはオランダのハイネケンと一緒に合弁工場を手がけるほか、BICブランドのボールペンなど、プラスチック成型品の生産なども手がけていて当社と親和性が高かったのです。
海外に商社という業態はあまりないですが、彼らは自分たちのことをはっきり「商社だ」と言いますから。ですから豊通がやっている事業はすぐに理解してもらえましたし、右から左のトレーディングだけでなく、彼らは工場を持ってモノづくりまで踏み込んでいるので、(トヨタグループの豊通と)お互いの理解はすごく早かったですね。
唯一、気になったのは若手社員の意識でした。若い社員が果たしてアフリカの地でビジネスをやってくれるのかどうか。そこで数人の若手に聞いてみたところ「この買収案件はいいし、アフリカは将来、伸びる市場だからやりましょうよ」と。そういう声に最後、後押しをしてもらえたようなところもあるんです。“一人称”という言葉を当社ではよく使うんですが、一人称、つまり当事者意識をもってやっていく気持ちがあるかどうかが大事ですから。

独自戦略を掲げる加留部氏。
〔前述したように、CFAOは歴史的にアフリカ西海岸エリアの市場を得意とし、豊通は東海岸に強みを持っていたため、エリア補完も綺麗に成立した〕
地域的、事業的な割り振りで言えば、自動車関係はお互いの強みなのでしっかりやっていこうと。アフリカ西海岸で当社が細々とやっていたテリトリーは全部、CFAOに渡しています。物流の共通化なども進めて、お互いの事業効率を高めてきていますし、トヨタ車の販売や物流もCFAOと一緒にやっています。
当社としてはマルチブランドを扱うつもりはあまりなくて、トヨタと日野自動車、スバル(=富士重工)の商品を扱うわけですが、CFAOはマルチブランドなので、たとえば今年、アフリカでフォルクスワーゲンとのビジネスも決めました。
当社はケニアでトヨタ車を扱っていますが、CFAOはケニアにVW車を持ってくるわけです。CFAOは豊通の子会社なのにと一瞬、矛盾するような印象を持たれるかもしれません。我々はトヨタ車で現地シェアナンバー1を取りたいけれども、彼らもVW車でナンバー2を取ればいい。そういう組み合わせみたいなものができてくると思うんです。
いずれにしても、自動車関係のビジネスはお互いに共通しているので、この分野はオーガニックな成長で伸ばしていけるでしょう。一方、医薬品関係はいま、彼らもどんどん伸ばしていて、我々も日本の製薬メーカーを紹介したりといったサポートをしています。
〔豊通がCFAOを買収したことで、新たな効果も表れてきている。たとえば、前述したCFAOが合弁で手がけるハイネケンの工場運営会社。豊通の傘下に入る前は、CFAOの株主が収益はすべて配当で還元してほしいと要請していたため、新しい投資ができなかったのだが、豊通が入ったことでロングタームで事業を見るようになってくれたのだ〕
私もハイネケンの合弁会社社長に会って話をしました。先方も理解してくれて、生産国もコンゴだけだったのを別の国でも展開しようという話に発展しましたしね。さらに、フランス大手スーパーのカルフール。CFAOがカルフールとの合弁でコートジボアールで店舗を出しますけど、これも私がカルフールの社長とお会いし、アフリカ8カ国で展開することを決めました。
日系メーカーとではこんな事例もあります。ヤマハ発動機のオートバイを生産する合弁会社をCFAOがナイジェリアで作るのですが、彼らもヤマハとのお付き合いは従前からあったものの、それほど深かったわけではありません。
一方で、我々は日本でも(ヤマハと)いろいろなビジネスをやらせていただいているので、この合弁話を提案したら了承してくださり、出資比率も50%ずつでOKしてくれたんです。CFAOは豊通の資本が入っている会社だからと、全幅の信頼を置いていただけた。普通は、日本のメーカーが現地へ出るのに50%ずつというのはあまりなく、イニシアチブは日本のメーカー側が取るものだからです。
そういうCFAOとの協業ロードマップは10年スパンで立てていまして、私もCFAOの首脳もお互いに行き来しています。フェース・トゥー・フェースで、年に4回ぐらいは顔を合わせているでしょうか。それ以外にも毎月、テレビ電話での会議も1時間半ぐらいかけて実施し、いまの経営課題や将来の絵図などをお互い共有化するようにしています。
〔豊通には、TRY1という経営ビジョンがある。これは収益比率として自動車と非自動車の割合を均等にしていき、さらに20年にはライフ&コミュニティ、アース&リソース、モビリティの3分野の収益比率を1対1対1にするというものだ。CFAOをテコにしたアフリカビジネスの拡大も、TRY1計画達成に寄与する部分は大きいだろう〕
いまでもCFAOは1億ユーロぐらいの純利益を上げていますから、それだけでも我々は彼らのプロフィットを(連結決算で)取り込むことができますし、プラス、将来的な絵図という意味でも、お互いにステップ・バイ・ステップで各事業を伸ばしていくことで、TRY1の実現にすごく貢献するはずです。
〔総合商社といえば近年、資源ビジネスで荒稼ぎしてきたイメージが強かったが、資源価格の市況に大きく左右されるリスクがあることは、住友商事や丸紅が資源価格の大幅な下落などで多額の減損を強いられたことでも明らか。とはいえ、こうしたリスクテイクは、総合商社にとってはいわばレーゾンデートルでもあり、投資するしないの判断は難しい〕
資源といってもいろいろあると思います。いまさら石炭や鉄鉱石の採掘ビジネスにお金をガンガンつぎこんでもダメ。また、シェールガスやシェールオイルも私が社長になった頃に他社がみんなやり出して、社内でも「やりたい」という声が多かったのは事実です。でも、よく調べてみたら、当社はすでに周回遅れ、しかも1周でなく2周も3周も遅れている。「これでは高値掴みしてしまう可能性があるし、投資金額も大きいのでやめておきなさい」と、社内でかなり明確に言いました。
ですから、我々はもっとニッチで別な土俵で勝負していこうと。たとえば、チリで開発しているヨード。これはイソジンのうがい薬、レントゲンを撮る時の造影剤でも使うんですが、ヨード産地は日本、米国、チリと世界で3カ国しかありません。当社はその全部の産地で開発拠点を持っているので、将来的には取り扱いシェアを15%まで高めたいと考えています。
ほかにも、アルゼンチンではこれからの自動車ビジネスに直結する、リチウム関連の鉱山事業を昨年から始めましたし、豊通らしさというんでしょうか、ニッチキラーでもいいからウチらしさが出て、かつ上位の商社とも十分に戦えるビジネス分野でやっていこう、というのが当社の基本ポリシーです。
〔目下、前述したTRY1達成に向けて歩を進める豊通だが、現在の非自動車ビジネス拡大の基盤を整えたともいえるのが、06年に旧トーメンと合併したこと。トーメンが持っていた化学品や食料といった主力事業分野を得たことで、総合商社としての幅が各段に広がったのだ〕
実際、事業ポートフォリオが広がって、合併は結果として大正解でした。エネルギーや電力関係のビジネスはいま、一部を除いてすごくうまくいっているんですが、こうしたジャンルは豊通のままだったら絶対に出てきていないビジネスですね。
豊通はもともとが自動車関連ビジネスメインでしたから、農耕民族なんです。畑を耕して種をまいて、雑草をとって肥料や水をやってと。それが狩猟民族(=トーメン)と見事に化学反応したという感じ。狩猟民族の人も農耕民族から学んでもらえたし、お互いの良さを認め合ってすごくいい合併だったと思います。
〔加留部氏は横浜国立大学工学部出身だが、就職活動では「とにかく商売がやりたくてしかたがなかった」と述懐するように、入社試験は商社しか受けなかったという〕
私は1976年の入社ですが、当時は就職が全般的に厳しくなり始めた頃で、「商社冬の時代」になりかけていた難しい時期。各商社とも採用人数を絞り、狭き門になっていました。それでも私はとにかく商社に行きたくて、最初に内定をくれたのが豊通だったんです。商社としては規模は小さいけれど、その分、若手にも仕事を任せてくれるんじゃないかと。トヨタグループだから財務基盤もしっかりしていましたしね。
〔豊通入社後は3年目に米国駐在となり、米国でのビジネスで5年間揉まれて逞しくなった後に帰国。国内で6年過ごして結婚後、再び渡米して9年間駐在した。こうした国際経験豊富な加留部氏だけに、昨年からは入社7年目までの社員を対象に、駐在でも長期の研修でも語学留学でもいいから、とにかく一度、海外へ出ることを奨励している。
ただし、加留部氏はほかの商社との戦いにおいては、純利益で何位といった相対的な物差しでなく、あくまで豊通としてどうなのかという基準で考えると強調する〕
2年か3年前、社員みんなにメールを打った時に触れましたが、何大商社とか何位であるとかは、私はまったく関心がないんです。自分たちが目指す方向に向かえているかが大事ですから。たとえば敵失があって他社の順位が下がったとします。仮に順位を純利益で測ったとして、「他社が失敗してウチが5位になったところで君たちは嬉しいか? 私は嬉しくないよ」と。
社員向けのメッセージメールは年に8回か9回出していますが、ある時、新入社員から「何位を目指しますか?」という質問を受けた時も同じことを言いました。各社ごと、事業ポートフォリオがかなり違いますし、順位は関係ない。自分たちのビジネスがどうなのか、常にそこを自問自答し検証することが正しい道だと考えます。
(構成=本誌編集委員・河野圭祐)
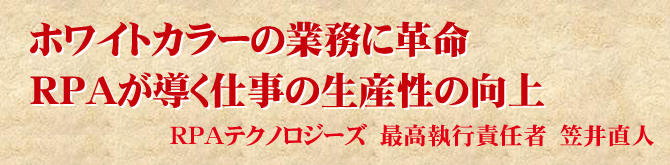
「人手不足」と言われ、少子化で労働人口の急激な減少が危惧される日本。そんななか、間接部門での生産性向上が期待されるのがRPAだ。RPAは日本の救世主となり得るのか、RPAテクノロジーズの笠井直人COOに話を聞いた。
RPAと聞いて、何かをイメージできる人はまだ少ないのではないだろうか。
RPAは、日本の少子高齢化による労働人口の減少を解決し、日本人の働き方を大きく変えることが期待されるロボット技術のこと。
しかしロボットとは言っても、メカニカルで大きな産業用ロボットやソフトバンクのペッパー君のようなコミュニケーションロボットとは異なる。ホワイトカラー向けの業務を自動化できるPC内で活躍するソフトウェアロボットと考えるとわかりやすい。しかし、単なるソフトウェアではないのがRPAだ。
「RPAは、効率化のためのソフトウェアではありません。人の手作業を記憶する簡単なツールだから、導入すればよいと思われがちですが、そうではありません。ロボットを入れることによって、オペレーション自体を変化に強くしていくことが最終的なゴールです。コスト削減を目指すのではなく、労働人口が減ることに対してオペレーションを強くする。ここを目指さなければ、導入しても意味がない」

RPAテクノロジーズ最高執行責任者の笠井直人氏
こう語るのはRPAテクノロジーズ最高執行責任者の笠井直人氏。RPAテクノロジーズは2008年にRPAへの取り組みを進め、10年にロボットサービスの「BizRobo!」(ビズロボ)の提供を開始した国内では先駆者的な企業だ。このビズロボが、単なるシステムやソフトウェアと決定的に異なるのは、導入した企業にとって、「労働者を雇用した」のと同じ意味を持つことだ。
「我々が定義しているロボットは、1つは代行できるということ。人の作業が代行できなければ人の代わりにはなれません。2つめは能力。人と比べてミスを連発したりスピードが遅いなら意味がありません。ここまでは自動化というソフトウェアのアプローチでもできるところですが、3つめの変化に強いことがロボットです。
システムを改修する時に時間がかかっては困ります。人が作業の変化に対応できるように、RPAもその作業の変化に対応できる。この3つを為していなければいけない。
よく言われますが、RPAは夢のテクノロジーではありません。人の機能で言えば手足だと思ってください。ですから音声認識や複雑な処理をするものではない。システム間の繋ぎや新しいテクノロジーとの繋ぎの部分で、人が行う単調なルーティンワークに対し、人に代わって柔軟に連携できるものです。
ビズロボは作業を記録するというアプローチになりますので、プログラミングが必要ないぶん、導入のスピードが速く、既存のシステムがそのままで使えます。人と同じレイヤーで作業をさせますから、業務を変える必要もありません。そのなかで圧倒的な処理能力がありますから、業務によっては人が10時間かかっていた作業が5分で終わるといった事例もあります」
具体的な事例を見ていくと、わかりやすい。日本生命が導入したRPAは、「日生ロボ美」と名付けられるほど社員のなかに溶け込んでいる。日生は16の業務に6台のロボットを活用しているが、その1つのロボ美ちゃんの担当業務が、顧客の住所変更だという。導入前は、電話で聞き取った情報を社員が手作業で1件ずつPCで入力し、それを紙で印刷して別の社員がダブルチェックをしていたという。人が約5分かけて行っていたこの作業を、ロボ美さんは1件あたり約30秒で終える。10倍の速さとともに、入力ミスも起きない。人間の代わりにロボットが事務作業を行うことで、日生では6台の導入で20人以上ぶんの仕事をしているのだという。
「例えば親会社と子会社のシステムが繋がっていれば、日本生命様の事例である、住所変更はスムーズにシステムに反映されるのですが、現在はシステムがツギハギになってしまっている場合が多く、個社対応をしていることが多いです。その間を繋ぐのに人の手作業ができて、ルーティンワークになっている場合があります。それをロボットにすることで、人の時間を救っていく。社員はもっとクリエイティブな仕事ができるはずなのに、コピペのために使われていたわけです。そこを解放するのが大事です。エネルギーを解放すれば、新たな企画が生まれますし、オペレーションをさらに改善できるかもしれません」
ビズロボの導入事例は幅広く、全国で200社、2万ロボットが稼働している。PC上で行われるルール化した作業であれば、すべてビズロボが対応できるという。もちろんコスト削減にも繋がるのだが、笠井氏はその意図での活用は勧めないと話す。
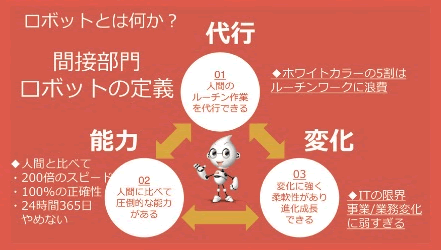
「実際、コスト削減としての期待値は高いし、それで注目されている面もあります。日本の場合、経営は経営、現場は現場とそれぞれ動いていることが多く、コスト目的でRPAを始めると、現場からの反発が生まれます。とある企業では、ロボットは社員を楽にするためのもの、ロボットも社員もしくは派遣スタッフの1人としてマネジメントをしなくてはいけないというスタンスで非常に成功しています。業務整理もロボットにやらせる仕事も現場でマネジメントしている。いままでは、オペレーションは与えられるものというイメージでした。それがひっくり返って現場から上がって来ないと、労働人口減少には対応できなくなるのかなと思います」
RPAが労働人口減少の救世主になる日も近いのかもしれない。
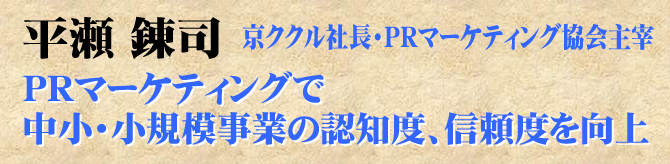

平瀬 錬司 京ククル社長・PRマーケティング協会主宰
ひらせ・れんじ 大阪大学で理論物理学を学んだ後、広告系ベンチャーに入社。マーケティングとセールスを学び独立後、2011年京ククルを設立。代表取締役に就任。10を超える業種で法人立ち上げに参画。「知名度」と「信頼度」が成否に大きく関わる、と痛感し、どうすればメディアに取り上げられるかを研究。17年9月にPRマーケティング協会を設立。
── 昨年、PRマーケティング協会を設立したそうですが、もともとは異なる業種をされていたとか。
会社としては6年目になりますが、最初は介護の資格学校を関西で始めました。現在は初任者研修という名称になりましたが、当時はヘルパー2級という資格が取れるスクールです。政府の緊急人材育成支援事業(基金訓練)で、生徒の受講料を労働局が負担するという制度を使って、京都、滋賀、三重、東京、埼玉等で資格スクールをやっていました。
ただ、介護の人材育成は、それだけでは事業として厳しいものがあります。そこで、卒業生の人材紹介を始め、さらに下流の紹介後の定着支援まで行っています。介護業界では、業界全体の平均在籍期間2年強と、3年以内にほとんど辞めてしまうような状況ですから、定着させることが大きな課題になっています。
これに加えて、採用活動も介護業界の課題になっています。単純な折込チラシや人材サービスを使っての採用活動には限界があります。そこで広報活動を通して、採用活動もしていきましょうと、数年前から手掛けるようになりました。例えば地元紙で対談を組んだりして、施設のブランディングと採用を同時に行えるようにしたわけです。ここで蓄積してきた広報活動のノウハウを活かそうと別法人として始めたのがPRマーケティング協会です。
── この協会ではどのような活動をしているのですか。
法人化したのは17年9月ですので、まだまだこれからの事業なのですが、現在は1回10名以内で、月5回、月間40~50名に対してPRマーケッター育成の講座を開いています。1講座10時間、全6回で60時間です。
── 受講生はどのような層の人たちなんですか。
2つあって、1つは新規事業を探していらっしゃる中小企業の経営者、もう1つはサラリーマンの副業が解禁されたので、これから起業したい、副業をしたいと考えている方ですね。
もともとは採用活動の1つとしてメディアとうまく付き合っていきましょうと何年もやってきたなかで、どうすればメディアの方に取材をしたいと思わせるような情報を届けることができるかというノウハウがわかってきました。ただ、単なるPR・広報業務ではなく、あくまでマーケティングとしてのPRですから、採用であれば質と量、他業界であれば売上利益をいかに伸ばすかです。それをお教えするのですが、ただノウハウを教えるだけではなく、それを新規事業としませんか、という話をしています。
新規事業を作ることが目的でノウハウをお伝えしますから、いわば本部とフランチャイズのような関係だと考えています。出し惜しみなく開示しますので、コンサルタントの方はおそらく簡単にコピーできると思いますが、私としては事業として取り組む方と一緒にやっていきたいというのが正直なところです。
いま日本には、中小企業や個人事業主、いわゆる「社長」と呼ばれる人が500万人くらいいます。しかし、おそらくその99%くらいの方はメディアとの付き合い方をご存知ないのではないでしょうか。よく講座内でも話すことですが、メディア露出で何を得るかというと、知名度と信頼度です。実はこの2つこそが中小企業、個人事業主にないものです。だから苦労をされている経営者が多い。
各会社さんには、いい商品、いいサービスを持っていても、知名度、信頼度がないので辛い戦いを強いられています。必死に営業したり、広告費用を使ったり、いろんな努力をしているのですが、メディア露出を戦略的に行うことが、コストも抑えられるやり方だと話しています。これを500万人いる中小スモールビジネスのオーナーに話ができれば、日本のビジネスのあり方も変えていけるのではないかと思っています。
── 最近はPR会社からメディアへの売り込みは増えていますが、どのような差別化を図っているのですか。
大手のPR会社さんと我々のやっていることは、まったく違います。マーケットも違いますし、内容も違います。我々は、家族で経営しているような街のパン屋さんや、従業員数10人未満の介護施設もクライアントです。あくまでもマーケティングのなかでメディアとどう付き合うかという考え方です。出たい出方で、出たいメディアに、出たいタイミングで定常的に出る。これをどうやって作っていくかを考えています。
どういう切り口で見せれば、メディアの方に興味を持っていただけるか、いくつかのテンプレートをつくって、ジャーナリズム魂をくすぐる形にする。センスがなくてもメディアから取材をしたいと思われる形はつくれるわけです。いろんなマーケティング、ブランディングの手法のなかで、メディアの方に親和性があるものだけを引っ張ってきて、テンプレートで落とし込む。思った以上に取材に来ていただけるという経験値があるので、そのノウハウを業務マニュアルレベルに落とし込んでいます。
── 協会としてはまだできて間もないわけですが、今後の展望はどのように考えていますか。
まずは協会認定のPRマーケッターを1000人育成していきたい。メディアを使ったマーケティングをお手伝いする人間を多く輩出していけば、500万人の経営者の強力なパートナーになれるんじゃないか。少子高齢化で明るいニュースがないなかで、中小企業を盛り上げていければいいと思っています。