




いつの間にか、新聞や雑誌で「FinTech」の文字を見ない日がなくなっ た。ひと言で言えば金融とIT 技術の融合ということだが、ネット証券の時 代から、両者は融合していたはず。ではいまなぜブームになっているのか。FinTechによって何が変わろうとしているのか。既存の金融業は生き残る ことができるのか。我々の生活は豊かになるのか。ブームが去った後に何 が起きるのか。その全貌を明らかにする。
FinTech(フィンテック)――いまではこの言葉自体は誰でも知っている。しかしそれが社会に及ぼす影響について、いったいどれほどの人が知っているだろうか。
フィンテックとは、Finance とTechnologyの造語。すなわち金融とITが融合することで、これまでにない価値を提供しようというものだ。
「ムーアの法則」とは、インテル創業者のゴードン・ムーアが予言した、「半導体の集積度は18~24カ月で倍になる」というもの。半導体の性能が、指数関数的に向上することを意味している。最初に唱えたのは1965年だったが、以来50年たったいまでも、ムーアの法則は成立する。IOTやAIの急速な発展も、その延長線上にある。少し前までは不可能だったことが、いまではどんどんできるようになり、AIは囲碁で人間を負かすまでになった。
フィンテックも同じこと。ITの急速な発展と、スマホの普及によって、新しい付加価値を持つサービスがどんどん誕生している。片手に収まる携帯電話で銀行振り込みや買い物の決済が行えるなど、少し前までは夢物語だったが、いまでは誰もが当たり前に受け止めている。この恩恵は先進国だけでなく発展途上国でも享受できる。アフリカで銀行口座を持っていない人でも、スマホを使って送金ができる時代となったのだ。フィンテックは社会インフラが未整備という壁を、いとも簡単に乗り越えた。同時にIT技術者たちの自由な発想と好奇心が、硬直的な金融システムの限界を打ち破ったとも言えるだろう。

フィンテックやAI、IOTなど一連のイノベーションは、農業革命、産業革命、IT革命に続く第4の経済革命と位置付けることができる。それほどにまで大きな変化の波が押し寄せているのだ。
フィンテックの特徴は、前述のように地域の壁や貧富の壁を破るところにある。従来の金融システムでは先進国と発展途上国、富裕層と貧困層とでは受けるサービスに大きな違いがあった。ところがフィンテックによって、高度なサービスの利便性が大きく向上した結果、誰でも同じようなサービスを受けることができる。
一例を挙げよう。これまでフィナンシャルアドバイザーに資産管理を相談できるのは富裕層に限られていたが、ロボアドバイザーという自動資産管理サービスなら、だれもが極めて安いコストで利用できる。このような例はいくらでもある。
こうして書くと、フィンテックにはいいとこだらけのように思えてくる。どんなに大きな波が押し寄せようとも、それによっていままでできないことが可能になり、新たな付加価値を持ったサービスを利用できるなら、歓迎するべきだろう。しかし大きな変化には、必ず陰がある。
「これまでの革命は、経済を大きく成長させ、人々を豊かにした。ところが今度は、経済が大きくなるように働くというよりは人々の生活にゆとりをつくる方向に働く」と指摘するのは、フィンテック問題に詳しい安田育生・ピナクル会長兼社長だ。
たとえば、フィンテックのひとつであるクラウド会計ソフトを使えば、帳簿をつける作業から解放される。しかしその一方で、企業の会計部門や税理士などの仕事を奪うことにもつながる。フィンテックでは、このような事例が数多く発生するため、大きな混乱を招くことが予想される。
中でも大きな影響を受けるのが、金融機関だ。これまで送金や決済、融資といった業務は銀行など金融機関の独占事業だった。ところが前述のように、金融機関を介さない、決済や送金が現実に広まり始めた。「これまでは銀行しか選択肢がない時代が長く続いた。フィンテックにより銀行以外の選択肢ができ、金融のあり方が大きく変わる」(安田氏)新たな選択肢を提供するのは、スタートアップ企業とも呼ばれるITベンチャー。別稿でも紹介しているが、「銀行のライバルは銀行」という時代から、「銀行のライバルはグーグルやフェイスブック」という時代が到来したのだ。
ある予測によると、銀行の従来業務の4分の1は、フィンテックに取って替わるとの予測もある。スタートアップ企業が、銀行業務を削り取ろうとしている。
加えて、ブロックチェーンの登場が、さらなる大変革を加速する。ブロックチェーンは、仮想通貨「ビットコイン」の中核技術だ。日本ではビットコインの交換所を運営していたマウントゴックスが不正を行ったことで傷を負ったが、世界の舞台では、その手数料の安さもあって、利用者がどんどん増えている。
従来の銀行のビジネスは台帳が基本となっている。この台帳が改竄されないよう、銀行は多額のコストをかけてデータ管理を行っている。ところがブロックチェーンは、台帳の代わりに世界中のコンピュータが相互承認をすることで、正当性を保証するものだ。その思想は、従来の銀行とは対極にある。
フィンテックによって銀行業務の一部が削り取られ、ブロックチェーンがそれを加速する。このままでは銀行は、存在意義を問われることになりかねない。
そこで、ここ1、2年、メガバンクはフィンテック対策に本腰を入れ始めた。従来の自前主義を捨て、オープンイノベーションにより、銀行では絶対に発想できない新しいサービスを取り入れようとしている。
金融機関を監督する金融庁も、昨年初めてフィンテックという言葉を行政方針の中で使い、サポート体制を本格化させている。
銀行や金融庁は、本来、非常に保守的な組織だ。特に日本の官庁は前例のない新しいものに対しては否定から入ることが多い。ところがフィンテックに対してだけは、従来にない積極的な取り組みを示している。これは、フィンテックの衝撃の強さの裏返しで、いま手を打たなければ、日本の金融システムが世界に取り残されるとの危機感が背景にある。
日本でも世界でも、フィンテック投資は大きく伸びている。金融の大きな波が、世の中を飲み込もうとしているようだ。

「最近のFinTechベンチャーは小粒だ」――。経産省のFinTech研究会でマネックスグループ社長の松本大氏がこう発言した。ブームとも言えるフィンテック企業のスタートアップに対し、警鐘を鳴らした形だ。その発言の真意はどこにあるのか、日本のフィンテックの現状と飛躍するための条件について松本氏が語った。
フィンテックはたいへん可能性がある産業だと思いますが、いちアプリケーションで終わってしまうのかどうか、これが重要なテーマだと思います。
どういうことかと言えば、いまのフィンテックは銀行とかかわっているケースが多いと思いますが、フィンテック企業が銀行をやっているという例はありません。いまのフィンテックは、銀行等の金融機関のいちアプリケーションになっています。
オンライン証券も一種のフィンテックだと思いますが、我々においては東証があり、ほふり(証券保管振替機構)があり、どの証券会社で買っても、同じ株が同じ値段で買え、ほふりに預けられるので安全。根幹の部分は公的な機関により供給されていますから、ユーザーは安心してどの証券会社からでも株の売買ができます。だから我々は野村證券等の大手証券会社と戦うことができた。ユーザーは手数料の部分や情報、使いやすさ等で選べばよかったわけです。サービスさえ持ち込めば、大企業と同じ土俵で戦えました。
フィンテックがこのままアプリ屋さんで終わるのか、銀行のサービスを揺さぶるような新サービスを作っていけるのか、が今後の課題です。
もうひとつ私が言っているのが、銀行、あるいは金融庁や経産省が、このフィンテックブームで優秀な人材がいる時に、ベンチャー企業をアプリ屋さんで終わらせておくつもりなのか、ということです。

「フィンテック企業が活躍できるフィールドを」と松本氏。
従来の銀行のサービスのこの部分までは銀行免許を取らなくてもフィンテック企業がやっていいよという形で、活躍できるフィールドをもう少し国、銀行が広くしていけば、もっと大きくなれる。フィンテック企業側の問題だけでなく、国と銀行がどれだけスペースを作ってあげるかにもよると思います。
ただ、銀行は国でもあります。何かあれば公的資金を使って助けてきた。これからもそれは明らかです。ですから銀行に真っ向から対立する勢力ができるのを国が助けるのは考えにくい。フィンテック企業が銀行を倒そうなんて日本では無理でしょう。一方で、銀行側も自分たちだけで思いつくアイデアや技術に限界を感じています。フィンテック企業にはさまざまなおもしろいアイデアがあるので、アプリ屋さんとしてこき使うのではなく、共存共栄していく道を考えていくべきでしょう。現状では、共存共栄というよりも、アイデアコンテストをやってあげるよといったアプリ屋さんとしての扱いに終わっています。国もフィンテックを推すのであれば、共存共栄の方向に行くように行政的に導いたほうがよい。フィンテックにより、広く金融機関のサービスがよくなるし、日本経済もよくなり、みんなにとってよい方向に行くことが望ましい。
というのも、フィンテック企業はそんなに儲かっていないんです。銀行はマイナス金利といってもメガバンク1行で1兆円の利益が出るほど儲かっています。たとえば決済のような儲かる部分は銀行が握り、フィンテック企業もがんばってはいるけれども、具体的には儲かっていない。銀行業務のなかで利益が出る部分を、銀行免許を持っていない企業でも要件を満たせばやってもいいと国が線を引き直せば、そこにもっとフィンテック企業が入り、アイデアが出てきて栄える。ところが、金融庁は銀行法を変えて、銀行がもっとなんでもできるようにする方向に行ってしまっている。逆なんです。
これまで国が育てようとして育った産業はありません。国が放っておいたバイクやカメラは世界一になり、国が守り抜いてきた金融や通信は世界で通用しない。金融庁や経産省が手を出すのではなく、銀行以外のプレイヤーができる範囲を広くすれば、なんのサポートをしなくても勝手に事業家が入ってきておもしろいことを始めると思います。
ただ、フィンテック企業の人は、こういうことを言わない。フィンテック企業は銀行と仲良くしなければいけないし、金融庁とも仲良くしなければいけないので、言えないんですよ、おそらく。だから、傍らにいる私たちが代わりに言う。私が「フィンテックが小粒だ」と言っているのは、フィンテック企業がダメだと言っているのではなく、いまのやり方のままだったら限界がありますよ、という意味です。
オンライン証券が既存の大手証券会社と戦えたのは、スペースが提供されていたからです。いまのフィンテック企業にSBIの北尾吉孝さんや松井証券の松井道夫さん、私のような荒い人間がいないという可能性もありますが、それ以上にスペースがあったことが大きい。
かつて証券会社を変更する際は、株券を預けてある証券会社から返してもらって、それを持って新しい証券会社にいかなければいけませんでした。セールスと顔を合わせて引き留めを振り切らなければならず、証券会社の乗り換えは非常にハードルが高かったのです。
それを野村證券さんが大きな心で名義書き換えの簡素化を認めてくれた。手数料の自由化があり、株券の電子化も視野に入っていたわけで、いろんな意味でスペースができることがわかっていました。私自身、手数料の自由化がなければマネックスを創業していません。99年10月1日から自由に手数料を決められると法律が変わり、それなら営業部隊を抱えず、インターネットでコストを下げれば安い手数料を提供できると私も始めたし、他の人も入ってきた。
戦えるスペースを与えよ
シンガポールでは、政府のなかにチーフ・フィンテック・オフィサー、いわゆるフィンテック大臣を作り、特区を作りました。フィンテックで2020年までにGDPを12%上げようと言っています。シンガポールが国内経済でそんなに大きくできるわけがない。つまり外から12%ぶんの経済をフィンテック経済として持ってきてしまう。特区を作るという発想はまさにそうで、規制を考えるのではなく、まずスペースを作ってしまおうと。そこに世界中から優秀な人材が集まってくる。
ある国はフィンテックでGDPを2ケタ伸ばそうとしているのに、日本は逆のことをやっている。いち国民として見た時に、銀行業界、あるいは国に対する怒り、フィンテック企業への応援と愛を込めて「小粒」という表現になったわけです。政治家や金融庁は、新しい成長戦略が欲しいのであれば、優秀でおもしろいアイデアを活用すべきで、そのためのスペースを作るべきです。お金をあげることではなく、補助することでもありません。活躍できる場所があれば、勝手に優秀な人間が来て伸びていく。お金もかからないし、難しく考える必要もない。そういう発想を政府が持てれば、変わると思います。

オンライン証券は株取引を変えた。(写真は東京証券取引所)
「棒ほど願って針ほど叶う」とウチのおふくろが言っていましたけど、大きく願って、それでも実現はほんの少ししかできないんです。マネックスだって、野村證券を超えたい、郵便局に代わる国民的金融インフラになると創業時から言ってきて、せいぜいこんなものです。フィンテック企業は、やはり根こそぎ変えてやるんだという考えで発信し、行政にぶつかっていき、そういう考えをメディアの人と話をして世論を作っていくことをやらないといけない。
もしかしたら、やった本人は潰されるかもしれません。だけど誰かがやって変えていかないと、小さいパイのなかで一番を争うようなことになってしまいます。もっとパイを大きくするようにしてほしい。
フィンテックに限りませんが、最近、ベンチャー企業が増えてきて、それについてはいい傾向だと思います。でも、みんないい成績を取ってやろうと思っている。オンライン証券は、失敗するかもしれないけどやらざるを得ない、失敗してもやり抜く、ドン・キホーテと言われても戦いに行くと言われたものです。もともと起業はドロップアウトの道でしたから、やるしかなかった。
いまのベンチャー企業の人はすごく優秀になって数も増えて、平均点はすごく高い。我々の時よりもいまの起業家のほうが、レベルが高いと思います。でも、みんなふつうに勝とうと思っている。先ほどの話で言えば、自分は金融庁に潰されても、ここは言わざるを得ないとか、そういう感じが少ない。これでは少なくともコミュニティは大きくなりません。フィンテックでなくても、日本のベンチャー企業はアプリケーション屋さんが多い。アメリカのITベンチャーは基礎技術から始めたうえでアプリケーションレイヤーもやっています。そういった意味でも日本は小粒なんです。
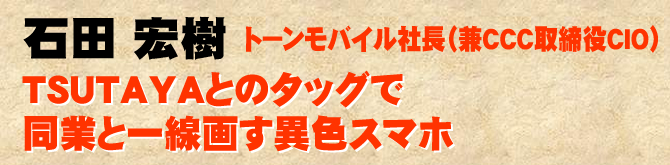

トーンモバイル社長(兼CCC取締役CIO) 石田宏樹
いしだ・あつき 1972年佐賀県生まれ、福岡県育ち。98年慶應義塾大学総合政策学部卒。在学中に有限会社リセットを設立し、取締役に就任。その後、三菱電機よりISP(インターネット・サービス・プロバイダー)立ち上げの依頼を受け、ドリーム・トレイン・インターネット(DTI)設立に参画。99年に最高戦略責任者に就く。2000年フリービット・ドットコム(現・フリービット)を設立、07年東証マザーズに上場。同年DTIを買収。13年freebit mobileのブランドを掲げてスマートフォン分野に参入。15年2月カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と資本・業務提携。同年3月CCCと合弁のトーンモバイルを設立して社長。CCCの取締役CIOも兼務。
今後も右肩上がりが確実視される、格安SIM&スマホ市場。ただし、あまたあるMVNO(仮想移動体通信事業者)同士の戦いは、生き残りを賭けて熾烈さを増している。当然、そこでは個性や差別化が一層求められるわけだが、異彩を放つ存在といえるのが、CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)とフリービットの合弁によるトーンモバイル。同社の石田宏樹社長に差別化ポイントを中心に聞いた。
〔トーンモバイルは、もともと格安スマホ事業も展開していたフリービット(インターネット・サービス・プロバイダーの草分けの1社で2000年に設立、07年に東証マザーズ上場)が昨年3月にCCCと合弁を組んでスタートした企業。石田宏樹氏はフリービットの創業社長(現・会長)でもあるほか、CCCのCIOも務めている。まずは、CCCとのタッグの経緯などから振り返ってもらうと――〕
いまMVNOのブームが起こっていますけど、20年ほど前にもインターネット接続業者のブームがありました。その市場にフリービットとして参入し、市場が広がった後、参入企業が集約されるという戦いを見てきていることが、とても貴重な経験になっています。MVNOは継続課金サービスのビジネスとしてすごく魅力的ですが、同時に継続的にコストがかかるサービスですので、その部分をいかに技術的にコストセーブするかとか、あるいは特許なども含めてフリービット時代にノウハウを積み上げていきました。
そのようにフリービットは技術中心の会社ですが、スマホ事業をさらに拡大するためには、フランチャイズ(以下FC)のビジネスモデルが必要だったのです。そして、私が戦略を作るうえで目標にしてきたのがCCC、つまりTSUTAYAの戦略でした。そう思っていたところ、(CCC創業者の)増田宗昭さんのほうからお声がけをいただき、我々が持っている技術とCCCが持っている生活提案力やFC展開力、加えて増田さんの商人精神がマッチングすることでステップアップが可能になりました。
増田さんのすごいところは、大阪商人のスピリットを持ちつつ、売らんかなの供給者論理ではなく、常に消費者目線があること。カッコいいライフスタイル提案に長けていて、そことフリービットの技術力をどう融合化、パッケージ化していくか。そこがこの1年で一番、重要なポイントでした。
CCCとフリービットって、意外と企業理念が近いんです。実際に議論の過程ではたくさん摩擦も起きましたが、一旦お互いに理念まで立ち戻って話し合うと、結果的にはコンセンサスが取れるんです。
〔もともと、CCC側も14年12月にCCCモバイルを設立し、同年に中古パソコンやスマホの販売、買い取りを手がけるイオシスと資本提携するなど、フリービットとの合弁を発表する前から独自の動きは見せていた。当初から、これまでの複雑怪奇なスマホの料金体系をシンプルにし、いたずらに機種も増やさずにユーザー・オリエンテッドなスマホに仕上げるというコンセプトも公表、その理念の部分で石田氏と意気投合できたというわけだ〕
増田さんはリアルのビジネス世界が得意で、私は学者肌なのでIT系の未来情報や技術を持っている。その間をどう最短距離にして新しいビジネスとして組み上げていくか。その部分でのディスカッションはすごく面白いですね。
一番のキモはシンプルなこと。とにかく消費者にわかりやすくしていかないといけないというのが増田さんの最重要な考えで、事業者の論理を一番嫌います。「MVNOだからこうだとかは事業者側の論理で、お客様には何の関係もない」と。お客様に対して何がメリットなのかを、いかにシンプルにして提案、提供していくか。増田さんは「お客様に伝わらなければ存在していないのと一緒だぞ」とも言われます。売ろう売ろうとしたら、お客様はかえって買ってくれないことをよくわかっているからです。
あとは「スマホの手触りはセクシーでないといけない」と。手で持った瞬間にそう感じるようにしないといけないということで、たとえば(昨年11月に発表、発売した)「m15」という我々のスマホは、裏面を少しザラザラした感触にしています。これは心地いい感触と同時に、スマホを落としにくくする面でも効果を出しているのです。しかもザラザラ感を出すことで、重量の軽さ感も出せることがわかりました。
〔トーンモバイルの座標軸は、端末は1機種、料金体系も月額1000円(税抜き)のみというシンプルさにあるが、ほかのMVNOはスマホに挿すSIMカードのみか、国内外のメーカーから調達した端末とSIMカードのセットで販売しているのに対し、トーンモバイルでは端末も自社製で、いわゆる垂直統合モデルを展開している。同業ではFREETELブランドのプラスワン・マーケティングも同様だが、プラスワンのほうは料金体系も機種も多岐にわたっており、シンプルでわかりやすい点はトーンモバイルのほうが上だ。
また、トーンのm15の端末では、端末が入っている化粧箱の上に置くだけで、スマホに生じた不具合などを発見し、自動的に修復する「置くだけサポート」や遠隔サポート、スマホ紛失時にパソコンからスマホのアラームを鳴らしたりロックをかけたりデータも削除可能。また、歩数や消費カロリーを計測できるライフログ機能、親だけが知っているパスコードを入力しないとアプリがダウンロードできないようにするインストール制限など、主としてシニアやスマホ初心者、子供向けに手厚い商品設計になっている。スマホの買い替え需要の奪い合いはすでにレッドオーシャンだが、トーンが核にしているターゲットはまだ、ブルーオーシャンといっていい〕

トーンモバイルの石田宏樹社長の名刺には“デジタルアーキテクト”の肩書も刷りこまれている。
もともとハードウエアのロードマップを向こう3年分ぐらい持っていて、我々は端末も自社開発しています(ただし生産は海外に委託)が一番難しいのは、(グーグルの)アンドロイドOSをどこまでいじれるのかということです。アンドロイドはいろいろな制限が厳しくなってきていますので、その中でどこまで我々の独自性が担保できるか。それでいて、ちゃんとグーグルから認証も取らないといけないというラインを、ハードウエアやミドルウエアのチームでずっと展開してきました。いかに早くAPI(アプリケーション・プログラム・インターフェイス)を作ってお客様に役立つものを作れるかが鍵ですね。
サービス面で言えば、MVNOは扱い端末数が増えてくると、サポートするのにコールセンターがもたなくなってくるので、端末まで自分たちでコントロールしていないと、どこで問題が起こっているのかがしっかり把握できません。
お客様にしてみると、「これはメーカーに聞いてください」「これはキャリアに聞いたほうがいいですね」とたらい回しにされてしまう。これも、フリービットでインターネットプロバイダー事業を展開してきた経験でよくわかっていたことです。メールがつながらない時にパソコン自体が悪いのか、Wi‐Fiルーターの問題なのか、あるいは半導体チップが悪いのかわからない。そこを全部解決できるように端末も自社で開発し、遠隔のサポートまでサービスに付けているのです。
料金のシンプルさについては、これまではライトユーザーがヘビーユーザーの分も負担するような料金構造がまかり通ってきましたが、1000円支払う対価はライトユーザーもヘビーユーザーも等しく公平でないといけない(トーンではパケットは使い放題。ただし動画視聴などを快適にしたい場合は1GB300円で高速チケットオプションがある。通話はトーン端末同士は無料)。
〔今年2月末以降、トーンモバイルは攻勢に出た。1つは、俳優の坂口健太郎氏を起用したテレビCMの開始。もう1つが、2月末時点で14カ所にとどまっていたTSUTAYA店舗での自社スマホの販売を、2017年3月までに全国のTSUTAYA、200店舗へ拡大(TSUTAYAはトータルでは約1500店ある)すること。ただ、TSUTAYAの主力顧客層のイメージは若年層。スマホの操作や情報に詳しく、端末もハイスペックなものを求める人が多いのがこの層だが、シニアや子供をターゲット層にしていてズレはないのだろうか〕
まず、TSUTAYAは個店ごとに全然、クラスターが違います。年齢クラスターのデータベースが個店ごとにありますので、どこのお店で売ればいいかというのも、ここ1年間の中で見えてきました。たとえば、都会のすごくお金持ちの多いエリアでどんなにトーンの端末の訴求をしても、まったく響きません。我々は、家族とお子様が安心安全にスマホが使えるという点を担っていくわけですし、売り方もこれまでに14店舗で販売したデータでいろいろとわかってきています。

化粧箱の上に端末を置くだけで不具合を検知、修正してくれる。
端末も1機種にしているのは、選択肢が増えれば増えるほど、お客様が選ぶのに煩雑で選ぶ苦痛があるからです。
かつて、スティーブ・ジョブズがアップル社に戻った時、それまで36種類あった商品ラインナップをノート、デスクトップ、エントリー、プロと4種類に整理していますが、当社も1機種にこだわっているのは、選択の苦痛をなくしたいから。当社のスマホ1台でお子様も使えるし、高齢者もファミリーも使える、もちろんITのプロである私も心地よく使える端末を、どう完成度高く実現するかが勝負なのです。
そもそも、イノベーションによる貢献度の物差しは、時間の使い方が変わったかどうかだと思っています。情報革命のいま、時間消費型商品と時間節約型商品がごっちゃになっているので、よくわからなくなっているんですね。たとえばかつては松下電器が、作業効率の高いナショナルブランドの掃除機や洗濯機などで主婦の空き時間を絞り出し、その絞り出した時間を、今度はパナソニックというブランドで、オーディオやテレビの世界に誘っていました。時間節約をシンプルさで達成していき、よりよい時間消費ができるようにしたい、というのが我々のすごく重要な考え方です。
その点、CCCとの提携はものすごく大きくて、CCCが持っているTポイントカードなどを通じたデータベースを、お客様のためにどうやって役立てていくか。結果として、それをさらに時間節約にどう寄せていくかはすごく大事です。集積データをビジネスにするというのではなく、データによって、人の時間軸にいかに早く貢献できるかにこだわっています。


加留部 淳 豊田通商社長
かるべ・じゅん 1953年7月1日生まれ。神奈川県出身。76年横浜国立大学工学部電気工学科卒。同年豊田通商に入社。99年物流部長、2004年取締役入り。06年執行役員、08年常務執行役員、11年6月末より現職。学生時代はバスケットボール部に所属。座右の銘は着眼大局、着手小局。
〔昨年、豊田通商が近畿大学と提携して卵から育てるマグロの“完全養殖”事業に参入(養殖事業そのものは2010年に業務提携)するというニュースが大きな話題になった。11年に同社の社長に就いた加留部淳氏は、就任後初めての出張が近大水産研究所で、同研究所の宮下盛所長と意気投合。今後は豊通と近大のタッグで完全養殖マグロの生産を順次拡大し、海外へも輸出していく計画だ〕
もともと当社は人材育成には力を入れ、いろいろな研修プログラムを用意していますが、その中に若い社員の事業創造チャレンジのプログラムがあるんです。自分たちでまず研究し、社内外の先輩や識者の意見も聞いて新事業案を作らせるものですが、その過程で「ぜひ、近大さんの販売や養殖のお手伝いをしたい」と提案してきた社員がいましてね。
面白い事業プログラムだったので、当時の経営陣が「やってみろよ」と。で、動き始めて実際に予算もつけ、近大さんにもお話をしに行ってというのがスタートでした。こういう社内提案制度は、起業家精神の醸成にすごく必要だと思います。もう1つ、マグロの漁獲量が減る一方で、需要は日本や東南アジアを中心に増えているわけですから、商社のビジネスとして意義がある。会社としてもやる意味があるし、若い社員を育てる点でも有効、その2つの観点から全面的にバックアップしています。
もちろん、ほかの商社でも水産系ビジネスには力を入れています。その中で、我々は違う土俵で戦うケースもありますし、どうしても同じ土俵の時は、真っ向勝負だと当社の企業体力では勝てないわけですから、戦い方を考えないといけない。そこは全社員と共有しています。そういう意味でも、他社が手がけていないマグロの完全養殖事業は非常に面白いビジネスですね。

近大とマグロの完全養殖事業で提携。左端が宮下盛・近大水産研究所長、右から2人目が加留部社長(2014年7月の会見)。
〔近大とのタッグは話題性が大きかったが、豊通という会社全体として見れば1事業の域は出ていない。これに対し、加留部氏が12年末に決断した買収案件は全社横断的な規模だ。当時の為替レートで同社では過去最大となる、2340億円を投じて買収したフランスの商社、CFAO(セーファーオー)がそれ。CFAOは、30年には中国を上回る巨大市場になると目されるアフリカ市場で強固な事業基盤を持ち、とりわけフランス語圏の多いアフリカ西側地域で圧倒的な商権を持っている〕
過去最大の投資ですから、我々もものすごく慎重に考えましたし、私も実際に現場を見に行きましたが、先方も傘下の自動車販売会社の修理工場とか、結構オープンに見せてくれましてね。当社とはDNAが合いそうだなと。
もう1つ、彼らは自動車関連事業以外もたとえば医薬関係、あるいはオランダのハイネケンと一緒に合弁工場を手がけるほか、BICブランドのボールペンなど、プラスチック成型品の生産なども手がけていて当社と親和性が高かったのです。
海外に商社という業態はあまりないですが、彼らは自分たちのことをはっきり「商社だ」と言いますから。ですから豊通がやっている事業はすぐに理解してもらえましたし、右から左のトレーディングだけでなく、彼らは工場を持ってモノづくりまで踏み込んでいるので、(トヨタグループの豊通と)お互いの理解はすごく早かったですね。
唯一、気になったのは若手社員の意識でした。若い社員が果たしてアフリカの地でビジネスをやってくれるのかどうか。そこで数人の若手に聞いてみたところ「この買収案件はいいし、アフリカは将来、伸びる市場だからやりましょうよ」と。そういう声に最後、後押しをしてもらえたようなところもあるんです。“一人称”という言葉を当社ではよく使うんですが、一人称、つまり当事者意識をもってやっていく気持ちがあるかどうかが大事ですから。

独自戦略を掲げる加留部氏。
〔前述したように、CFAOは歴史的にアフリカ西海岸エリアの市場を得意とし、豊通は東海岸に強みを持っていたため、エリア補完も綺麗に成立した〕
地域的、事業的な割り振りで言えば、自動車関係はお互いの強みなのでしっかりやっていこうと。アフリカ西海岸で当社が細々とやっていたテリトリーは全部、CFAOに渡しています。物流の共通化なども進めて、お互いの事業効率を高めてきていますし、トヨタ車の販売や物流もCFAOと一緒にやっています。
当社としてはマルチブランドを扱うつもりはあまりなくて、トヨタと日野自動車、スバル(=富士重工)の商品を扱うわけですが、CFAOはマルチブランドなので、たとえば今年、アフリカでフォルクスワーゲンとのビジネスも決めました。
当社はケニアでトヨタ車を扱っていますが、CFAOはケニアにVW車を持ってくるわけです。CFAOは豊通の子会社なのにと一瞬、矛盾するような印象を持たれるかもしれません。我々はトヨタ車で現地シェアナンバー1を取りたいけれども、彼らもVW車でナンバー2を取ればいい。そういう組み合わせみたいなものができてくると思うんです。
いずれにしても、自動車関係のビジネスはお互いに共通しているので、この分野はオーガニックな成長で伸ばしていけるでしょう。一方、医薬品関係はいま、彼らもどんどん伸ばしていて、我々も日本の製薬メーカーを紹介したりといったサポートをしています。
〔豊通がCFAOを買収したことで、新たな効果も表れてきている。たとえば、前述したCFAOが合弁で手がけるハイネケンの工場運営会社。豊通の傘下に入る前は、CFAOの株主が収益はすべて配当で還元してほしいと要請していたため、新しい投資ができなかったのだが、豊通が入ったことでロングタームで事業を見るようになってくれたのだ〕
私もハイネケンの合弁会社社長に会って話をしました。先方も理解してくれて、生産国もコンゴだけだったのを別の国でも展開しようという話に発展しましたしね。さらに、フランス大手スーパーのカルフール。CFAOがカルフールとの合弁でコートジボアールで店舗を出しますけど、これも私がカルフールの社長とお会いし、アフリカ8カ国で展開することを決めました。
日系メーカーとではこんな事例もあります。ヤマハ発動機のオートバイを生産する合弁会社をCFAOがナイジェリアで作るのですが、彼らもヤマハとのお付き合いは従前からあったものの、それほど深かったわけではありません。
一方で、我々は日本でも(ヤマハと)いろいろなビジネスをやらせていただいているので、この合弁話を提案したら了承してくださり、出資比率も50%ずつでOKしてくれたんです。CFAOは豊通の資本が入っている会社だからと、全幅の信頼を置いていただけた。普通は、日本のメーカーが現地へ出るのに50%ずつというのはあまりなく、イニシアチブは日本のメーカー側が取るものだからです。
そういうCFAOとの協業ロードマップは10年スパンで立てていまして、私もCFAOの首脳もお互いに行き来しています。フェース・トゥー・フェースで、年に4回ぐらいは顔を合わせているでしょうか。それ以外にも毎月、テレビ電話での会議も1時間半ぐらいかけて実施し、いまの経営課題や将来の絵図などをお互い共有化するようにしています。
〔豊通には、TRY1という経営ビジョンがある。これは収益比率として自動車と非自動車の割合を均等にしていき、さらに20年にはライフ&コミュニティ、アース&リソース、モビリティの3分野の収益比率を1対1対1にするというものだ。CFAOをテコにしたアフリカビジネスの拡大も、TRY1計画達成に寄与する部分は大きいだろう〕
いまでもCFAOは1億ユーロぐらいの純利益を上げていますから、それだけでも我々は彼らのプロフィットを(連結決算で)取り込むことができますし、プラス、将来的な絵図という意味でも、お互いにステップ・バイ・ステップで各事業を伸ばしていくことで、TRY1の実現にすごく貢献するはずです。
〔総合商社といえば近年、資源ビジネスで荒稼ぎしてきたイメージが強かったが、資源価格の市況に大きく左右されるリスクがあることは、住友商事や丸紅が資源価格の大幅な下落などで多額の減損を強いられたことでも明らか。とはいえ、こうしたリスクテイクは、総合商社にとってはいわばレーゾンデートルでもあり、投資するしないの判断は難しい〕
資源といってもいろいろあると思います。いまさら石炭や鉄鉱石の採掘ビジネスにお金をガンガンつぎこんでもダメ。また、シェールガスやシェールオイルも私が社長になった頃に他社がみんなやり出して、社内でも「やりたい」という声が多かったのは事実です。でも、よく調べてみたら、当社はすでに周回遅れ、しかも1周でなく2周も3周も遅れている。「これでは高値掴みしてしまう可能性があるし、投資金額も大きいのでやめておきなさい」と、社内でかなり明確に言いました。
ですから、我々はもっとニッチで別な土俵で勝負していこうと。たとえば、チリで開発しているヨード。これはイソジンのうがい薬、レントゲンを撮る時の造影剤でも使うんですが、ヨード産地は日本、米国、チリと世界で3カ国しかありません。当社はその全部の産地で開発拠点を持っているので、将来的には取り扱いシェアを15%まで高めたいと考えています。
ほかにも、アルゼンチンではこれからの自動車ビジネスに直結する、リチウム関連の鉱山事業を昨年から始めましたし、豊通らしさというんでしょうか、ニッチキラーでもいいからウチらしさが出て、かつ上位の商社とも十分に戦えるビジネス分野でやっていこう、というのが当社の基本ポリシーです。
〔目下、前述したTRY1達成に向けて歩を進める豊通だが、現在の非自動車ビジネス拡大の基盤を整えたともいえるのが、06年に旧トーメンと合併したこと。トーメンが持っていた化学品や食料といった主力事業分野を得たことで、総合商社としての幅が各段に広がったのだ〕
実際、事業ポートフォリオが広がって、合併は結果として大正解でした。エネルギーや電力関係のビジネスはいま、一部を除いてすごくうまくいっているんですが、こうしたジャンルは豊通のままだったら絶対に出てきていないビジネスですね。
豊通はもともとが自動車関連ビジネスメインでしたから、農耕民族なんです。畑を耕して種をまいて、雑草をとって肥料や水をやってと。それが狩猟民族(=トーメン)と見事に化学反応したという感じ。狩猟民族の人も農耕民族から学んでもらえたし、お互いの良さを認め合ってすごくいい合併だったと思います。
〔加留部氏は横浜国立大学工学部出身だが、就職活動では「とにかく商売がやりたくてしかたがなかった」と述懐するように、入社試験は商社しか受けなかったという〕
私は1976年の入社ですが、当時は就職が全般的に厳しくなり始めた頃で、「商社冬の時代」になりかけていた難しい時期。各商社とも採用人数を絞り、狭き門になっていました。それでも私はとにかく商社に行きたくて、最初に内定をくれたのが豊通だったんです。商社としては規模は小さいけれど、その分、若手にも仕事を任せてくれるんじゃないかと。トヨタグループだから財務基盤もしっかりしていましたしね。
〔豊通入社後は3年目に米国駐在となり、米国でのビジネスで5年間揉まれて逞しくなった後に帰国。国内で6年過ごして結婚後、再び渡米して9年間駐在した。こうした国際経験豊富な加留部氏だけに、昨年からは入社7年目までの社員を対象に、駐在でも長期の研修でも語学留学でもいいから、とにかく一度、海外へ出ることを奨励している。
ただし、加留部氏はほかの商社との戦いにおいては、純利益で何位といった相対的な物差しでなく、あくまで豊通としてどうなのかという基準で考えると強調する〕
2年か3年前、社員みんなにメールを打った時に触れましたが、何大商社とか何位であるとかは、私はまったく関心がないんです。自分たちが目指す方向に向かえているかが大事ですから。たとえば敵失があって他社の順位が下がったとします。仮に順位を純利益で測ったとして、「他社が失敗してウチが5位になったところで君たちは嬉しいか? 私は嬉しくないよ」と。
社員向けのメッセージメールは年に8回か9回出していますが、ある時、新入社員から「何位を目指しますか?」という質問を受けた時も同じことを言いました。各社ごと、事業ポートフォリオがかなり違いますし、順位は関係ない。自分たちのビジネスがどうなのか、常にそこを自問自答し検証することが正しい道だと考えます。
(構成=本誌編集委員・河野圭祐)
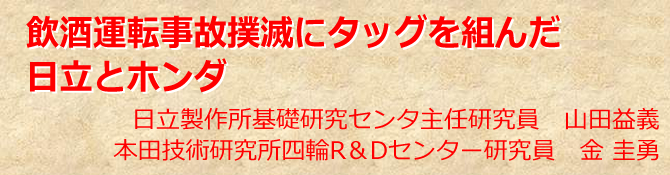
2007年に飲酒運転の厳罰化が施行されて以降、死亡事故は減少してきている。
しかし、現在まだ飲酒運転による重大事故のニュースは後を絶たない。
そんな現状に一石を投じるべく、日立とホンダが飲んだら運転できないシステムを開発した。
2016年3月24日、日立製作所とホンダが、スマートキー対応のポータブル呼気アルコール検知器の試作に成功したことを発表した。これは簡単に言えば、クルマのキーと検知器を連動させ、アルコールを検知した場合はエンジンがかからないようにするシステムが、より小型に、かつ精度が高くなって登場したというもの。

発表する日立の山田益義主任研究員。
米国ではすでに、アルコール検知器とクルマのエンジンを連動させた「アルコール・インターロック」を導入するための技術開発がNHTSA(米国運輸省道路交通安全局)主導で始まっているが、アルコール検知器のサイズが大きく、車内に備え付けたものになっていた。日立が2009年から開発してきた検知器もクルマに備え付ける前提のもので、ドライバーは車内に乗り込まなければ呼気の計測ができない不便さがあった。今回発表された検知器は携帯サイズで車外に持ち出すことができ、いつでも、どこでも、素早く検査を行うことができるようになる。

ホンダの金圭勇研究員。
日立とホンダが組んだ背景には飲酒運転事故撲滅というテーマがある。本田技術研究所四輪R&Dセンター研究員の金圭勇氏はこう語る。
「ホンダのグローバル安全スローガン『Safety for Everyone』には、クルマやバイクに乗っている人だけでなく、道を使う誰もが安全でいられる事故に遭わない社会をつくりたいという思いが込められています。飲酒運転事故の現状を見ると、死亡事故に占める飲酒運転の割合は、米国や欧州の約30%に比べて日本は約6%と低いものの、マスコミに取り上げられるような重大事故が頻発しています。世界でアルコール・インターロックの装着が法制化される流れのなか、ホンダは米国で行われているアルコール・インターロック技術開発プロジェクトに参画してきました。そこで日立さんの呼気検出の技術論文に着目し、ホンダ側から共同開発の話を持ちかけました」
日立はもともと計測技術分野には強く、1970年代から医療分野等で実績を積み上げてきた歴史を持つ。90年代には環境分野にも進出し、環境汚染物質の測定や自動車排ガス測定等のガス分析を手掛けてきた。それらの測定技術の延長に誕生したのが09年から着手した呼気センサーの技術だった。日立とホンダがアルコール検知のセンサーの共同開発をスタートさせたのが12年。3年越しの成果が日の目を見た形だ。

手の平サイズのアルコール検知器。
なぜホンダが呼気センサーにこだわったのかといえば、現在市販されているポータブル呼気アルコール検知器では、吹き込まれた気体が人間の呼気であるのかどうかを判別できず、呼気とアルコール検知を同時で行うことができなかったことが挙げられる。アルコール・インターロックを前提にするならば、ドライバーの呼気で解除できなければ意味がない。エアスプレー等で解除させてはいけないのだ。
日立製作所基礎研究センタ主任研究員の山田益義氏はその技術について次のように語っている。
「酸化物絶縁体を電極で挟んだセンサー上に呼気が吹きかけられると、呼気中の水蒸気が絶縁体に吸着して検出電極に電流が流れる現象を利用し、クシ形構造として電極を長く、電極間距離を狭くして高感度かつ小型化に成功しました」

検知した状態ではクルマのエンジンがかからない。
しかし、課題はまだまだ多い。ドライバー以外の飲酒をしていない人の呼気を使ってエンジンをかけることは可能だ。また、普及には法制度の後押し等が不可欠であり、検知器のコスト負担を誰がするのかといった運用面の課題もある。技術は出来上がっても、それを受け入れる社会的な機運が高まらなければ搭載されない可能性もあるだけに、安全への啓蒙も進めなければならない。
「ホンダは、交通事故に関するあらゆるリスクの排除を目指しています。将来的には、運転中に意識を失ったり体調が急変することがないように、座っただけで健康状態もチェックできるようなところまで実現したい。アルコール検知はまだスタートの段階だと考えています」(安斉秀彦・本田技術研究所四輪R&Dセンター主任研究員)
交通事故撲滅を目指す技術者の追求はとどまることがない。

アルコールを検知すると赤いランプが点灯。
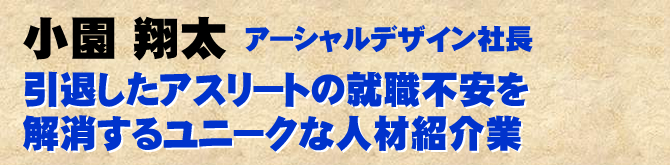

小園翔太 アーシャルデザイン社長
こぞの・しょうた 小さい頃からプロテニスプレーヤーを目指したが、ケガもあり断念。大学卒業後、人材紹介会社で20代専門人材紹介を行いトップセールスマンとなる。2014年、アスリートの就職を支援するためアーシャルデザインを設立、社長に就任した。28歳。
―― アーシャルデザインは、体育会系人材に特化した、人材紹介業です。どうしてこのような会社をつくろうと思ったのですか。
私自身、プロテニスプレーヤーを目指していましたが、ケガをしたこともあり、断念せざるを得ませんでした。でも学生時代も、アルバイトでテニスを教えていたため、プロと触れ合う機会も多かった。そこで彼らの引退後の実情を知りました。
彼らは小さい頃からテニスだけをやってきたため、引退したら進むべき道がない。そのため、ニートやフリーターになっている人たちがたくさんいた。これを何とかしなければ、子供たちがテニスプレーヤーになろうなんて思うはずがない。彼らを支援する仕事はできないものか、と漠然と考えていました。
その後、ジェイックという会社に勤めることになったのですが、この会社は、フリーターを対象に研修を行い、社会人の基礎を教えたうえで中小企業とのマッチングをするビジネスを行っていました。
アスリートを対象に、同様のビジネスを行うことはできないだろうか。そう考えて、当初は会社の中の新規事業として提案したのですが、うまくいかない。それで起業を決意しました。
―― 何もないところからのスタートです。どうやってアスリートや、紹介する企業を集めたのですか。
企業については、前職でつくったネットワークがありましたから、それほど心配はしていませんでした。問題はアスリートです。飛び込みで大学の体育会に行って営業活動しても、うまくいかないことは目に見えている。そんな時、先輩の紹介で、エイチアイエデュケーションの小林一光社長と出会いました。小林さんは元プルデンシャル生命の伝説的な営業マンで、エイチアイエデュケーションでアスリートに対する研修事業を行うなどアスリートのネットワークを持っていて、約100の大学体育会と密接な関係にある。そこで、エイチアイエデュケーションと提携し、ネットワークを利用させてもらうことにしたのです。
会社設立は2014年10月。実質的な活動はまだ1年ですが、新卒だけでも50人ほどのアスリートを企業に採用してもらっています。
今後は地方学生に対して、もっと積極的に関与していきたいと考えています。体育会系の学生は、アルバイトができないため、就職活動のために何度も上京することが困難です。ですから、その地域でのマッチングを増やしていきたいと考えています。
―― アスリートならではの特徴とはなんでしょう。
なんと言ってもストレス耐性が強いことです。アスリートとして、大変なプレッシャーと戦ってきた。これは仕事においても活かすことができます。またアスリートは、日々、PDCAを繰り返しています。自分のスキルを上げるために、計画を立て、練習、チェックし、改善する。これが身についている。これはアスリートの大きな強みです。
―― 逆に弱点は。
目標が定まらないと動かないことですね。アスリートとして、常に目標を立て、それに向けて努力することが習性となっている。それだけに、明確なゴールがイメージできないと、なかなかやる気が起きません。でもこれは、目標さえ決まれば、全力を尽くすことを意味しています。ですから採用した企業の側には、社員に対して明確な目標を設定することが求められます。
もうひとつ、アスリートならではの弱点に、自己否定が挙げられます。幼い頃からスポーツしかやってこなかった人の中には、自分からスポーツを取ったら何も残らないと思っている人が多い。自分自身に自信が持てないのです。そういう人に限って、自分の努力の過程に気がつかない。先ほど言ったように、PDCAを繰り返してきたことは、ビジネスの世界でも十分通用する。ですから当社では、研修を通じて、スポーツでやってきたことは仕事にも通用することを教え込むことにしています。
―― 実際に採用した会社からの評価はどうですか。
非常に高いです。そのため、採用は当社にしか頼まない、といってくれるところもありますし、一度利用した会社は、ほぼ例外なく次の採用でも利用してくれています。それだけ、以前に採用した人材の評価が高いということだと思います。
当社の場合、紹介先は中小企業が中心です。それには理由があって、中小企業のほうが、アスリートとの相性がいいからです。アスリートの場合、どんな仕事をするより、誰と仕事するかを重視する傾向にあります。どうせ働くなら、意気に感じて仕事をしたい。その意味で経営者との距離が近い中小企業との親和性は高い。それが入社後のミスマッチの少なさにつながっているのです。
―― 今後も目標は何ですか。
「アスリートエージェント」でありたいと思っています。アスリートが就職を考えた時、あるいは就職に困った時、真っ先に当社を思い浮かべる存在となりたいと考えています。
それと、セカンドキャリアという言葉もなくしたいですね。アスリートが引退したあとに新しい人生が始まるわけではありません。引退後も含めての人生です。その心配がなくなれば、アスリートは思う存分、競技に打ち込むことができる。そういう環境ができれば、日本のスポーツのさらなる振興につながると信じています。