




ドコモのシェアが下げ止まらない。番号持ち運び制度(MNP)では草刈り場となり、大量の顧客が流出する始末。そこで昨年には「禁断」とまで言われたソニーとサムスンの「2トップ戦略」を断行、秋にはソフトバンクに遅れること5年、auに遅れること2年でiPhoneの販売にも踏み切った。しかし事態はなかなか好転しない。いまなおドコモはMNPの赤字が続いている。そこでドコモはついに「通話料金定額制」という、事実上の通話料金の値下げに踏み切った。シェアトップ企業が率先して値下げ戦略に打って出るのは極めて異例のこと。果たしてこれで、ドコモは復活することができるのか。
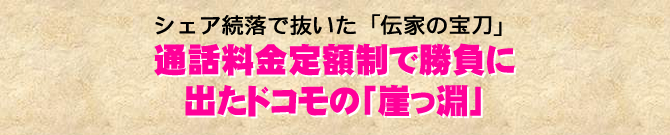
「国内初であり、時代を先取りするプランだ」
NTTドコモの加藤薫社長は、4月10日に記者会見を開き、6月1日から新しい料金体系を導入すると発表した。

4月10日、新しい料金プランを発表する加藤薫・NTTドコモ社長。
新しい料金体系の目玉は2つある。
1つは「カケホーダイ」で、毎月定額(スマホで2700円、従来機で2200円)を払えば、自社はもちろん他社の携帯電話へも、固定電話へも、すべての通話がかけ放題になる。現在でもドコモ同士なら、月額667円で通話料金は無料になるが、その対象を国内すべての電話に拡大したものだ。試算によると、毎日2分ほどドコモ以外と通話している人にとってはお得となるプランだ。
PHSのウィルコムではすでに通話完全定額制を導入しているが、大手3社の中で導入するのはドコモが初めてとなる。
もう1つが「パケあえる」で、家族内の合計データ通信料を、複数の回線で分け合えるというもの。家族4人で「シェアパック10」というプランに入ると、月額1万円で家族4人で合計10ギガのデータ通信が可能となる。これは従来の契約に比べ、4割近い割引となる。しかも、長期契約者の場合、家族で最大2000円の割引を受けることができる。こうしたパケットを家族で分け合えるサービスも、いままで日本にはなかった。加藤社長が「日本初」と胸を張るのもわかろうというもの。
このドコモの新料金プランは驚きをもって迎えられた。
ドコモのイメージの1つに、「料金が高い」というものがある。実際にはスマホなどにおいては、ドコモ、au(KDDI)、ソフトバンクの3社はほぼ横並びなのだが、8年前、ソフトバンクが携帯に参入するまでは、基本料も含め、料金が高止まりしていたこと、その中でドコモが圧倒的シェアを取っていたこともあって、「ドコモは高い」というイメージが醸成されていった。
今度の料金プランはそれに挑んだものだ。特に通話料金定額制は、後述するが、他社では導入するのがむずかしい施策である。それを前面に打ち出したところに、ドコモの本気度が見て取れる。
この新料金プランが、KDDI、ソフトバンクに与えた衝撃はけっして小さくなかった。
ソフトバンクの場合、この1月に新料金プランを発表しており、4月末からの開始を予定していた。ところがドコモの発表を受け、新料金プランの導入を中止せざるをえなかった。5月初めに決算会見に臨んだ孫正義・ソフトバンク社長は、ドコモの定額制について触れ、「ドコモに見劣りしない」新料金プランを策定中であることを明らかにしたが、その時期については明言を避けた。
またKDDIも、ソフトバンクの決算発表の翌日、夏物商品の発表会を開いたが、檀上に立った田中孝司・KDDI社長のプレゼンテーションでは、端末やネットワーク、新サービスなどについての説明はあったものの、料金については何の説明もなく、田中社長は、「別の機会に」というにとどまった。
KDDI、ソフトバンクとも、ドコモの定額制のインパクトがどのくらいのものなのか測りかねている状況で、6月以降のユーザーの動きを見たうえで、対抗策を練ることになりそうだ。
振り返ってみれば、ドコモは常に携帯業界の巨人であり、横綱だった。iモードなどで革命を起こしたり、LTEをいち早く導入するなど、業界の牽引役でもあった。こと料金に関しては、頭をつけて戦うのはいつもauやソフトバンクであり、ドコモはそれを受けて立つ立場にあった。
ところが今回は違う。日本初の通話料金定額制(=通話無料)を、ドコモが真っ先に導入したのだ。世界的に見れば、通話定額制は世の流れとなっている。日本国内でも、同じ会社同士の通話はすでに無料になっているし、ウィルコムやイー・モバイルなどは条件付きながら定額制を導入している。ところがメジャー3社に関していえば、いつまでたっても定額制に踏み切らなかった。ドコモはそこに踏み込んだ。
3社のうち、ドコモが一番乗りしたのは、同社が環境的に恵まれていたからだ。携帯電話から他社に電話をかければ、相手が携帯であれ固定であれ、そこに接続料が発生する。そのコストがあるため、これまで他社に対する通話料を無料にすることができなかった。
ところがドコモユーザーの場合、携帯シェアトップのため、そもそも、他社携帯にかけることが少ない。しかも固定電話にかける場合、相手はほとんどNTTの固定電話となる。接続料を払っても、それはNTT東か西の収入となる。つまりNTTグループ全体で考えたら“行って来い”だ。ところが、auからNTTの固定電話に電話すれば、KDDIはNTTに接続料を支払わなければならない。この違いは大きい。
ソフトバンクの孫社長は、ドコモの定額制について「ドコモさんはずるいですよね」と語っていたが、それはこうした理由によるものだ。
明治以来、日本の通信を一手に担い、全国隅々まで電話線を引いたNTTグループ。他社に比べ通信インフラという点では、圧倒的有利にある。それを最大限活用したのが今度の定額制なのだが、ある意味、国民共有の財産を利用して、自分たちだけ恩恵を受けるというやり方は、いささかえげつない。
それでもこのような料金体系を導入しなければならなかったところに、いまのドコモの苦しみがある。それほどまでに追い込まれているのだ。そんなドコモにとって、通話料金定額制は、伝家の宝刀を抜いたと言えば聞こえはいいが、次頁の石川温氏のコメントにもあるように、ドコモにしてみれば、最後の手段ということができるのだ。
日本に携帯電話(移動体通信)が誕生したのは1985年のこと。提供したのはもちろんNTT。自動車電話からのスタートだったが、ショルダーフォンなどを経て、携帯はどんどん軽くなっていく。92年には移動体通信部門がNTTから分離・独立、現在のドコモが誕生した(当初の社名はNTT移動通信網)。
それから今日にいたるまでの最大の成功体験といえば、なんといっても「iモード」だ。99年にスタートしたiモードは、空前のヒットとなり、ドコモのシェアアップに大いに貢献した。
iモードによって、携帯とインターネットが結びついた。しかもiモードにコンテンツ提供するプロバイダにとっても、その料金徴収をドコモが代行してくれるため、利用者にとってもプロバイダにとっても使いやすいシステムだった。そしてドコモには多大な手数料が入ってくる。この成功によって、ドコモはNTTグループの利益の7割を稼ぐ稼ぎ頭となり、その地位は盤石のものとなった。
ところが2006年にボーダフォンを買収してソフトバンクが参入したことで、業界地図が大きく動き始める。同年秋に番号持ち運び制度(MNP)が開始される。当初は3番手のソフトバンクが草刈り場となるかと思われたが、同社は価格戦略を打ち出し、契約者数純増トップを独走、シェアを伸ばしていく。さらにソフトバンクが08年にiPhoneを発売したことで、勢いはさらに加速、ドコモばかりかauも、シェアを落としていった。そして11年にはauもiPhoneを発売。この時以降、ドコモの独り負けが常態化した。

昨年秋にiPhone発売に踏み切ったが、流出は止まらなかった。
その代表的な指標がMNPの実績だ。昨年1年間でドコモは、MNPによって143万件の契約を失った。昨年秋にiPhoneを発売しはじめてから流出のスピードがにぶったとはいうものの、今年3月まで、62カ月連続でMNPはマイナスとなっている。これは、ソフトバンクがiPhoneを発売してからの期間とほぼ一致する。
ドコモも、市場全体の伸びにともなって契約者数は伸びているのだが、前頁のグラフを見てもわかるように、シェアは右肩下がりで落ちていった。
業績も同様だ。前3月期、KDDIとソフトバンクは揃って最高益を記録した。ところがドコモだけは減益決算だった。しかも営業利益は3期連続、最終利益にいたっては5期連続の減益である。
その結果、ドコモは利益面に関しては、営業利益で1兆円を超えたソフトバンクの後塵を拝することとなった。
ソフトバンクの携帯参入する前(06年3月期)の営業利益はわずか622億円。その前年度までは4期連続で赤字を垂れ流していた。ドコモの06年3月期の営業利益といえば、8326億円。ソフトバンクと10倍以上の差があった。
孫・ソフトバンク社長は当時を振り返って「10年以内でドコモを抜くと言っても誰も信じてくれなかった」と語っているが、比較すること自体が無謀だった。それがわずか8年での逆転劇である。ソフトバンクの躍進も驚異的だが、同時に、かつては営業利益が1兆1000億円を超えていたドコモが、ずるずると利益を落としてきて逆転されたという構図だ。
ドコモの低迷を、iPhoneに乗り遅れたためだとするのはたやすい。しかしドコモには、ソフトバンクより早くiPhoneを発売するチャンスがあった。ところがiモードの成功体験と、ドコモと一体化していた端末メーカーやコンテンツプロバイダとのしがらみが、それを許さなかった。そして何より、スマホがここまで急速に普及することを予見できなかったことが、最大の敗因だ。
もちろん、ドコモの中にもスマホの将来性に着目していた社員はいるだろう。しかし組織として、スマホに社運をかけることができなかった。
その背景について説明するのは、孫社長の次の言葉がもっとも適切かもしれない。
「お金持ちの家に、銀のスプーンをくわえて生まれ、努力しなくともエリートとして上流階級として育ち、リスクを取らなくても無理をしなくてもいい立場と、生まれながらにハングリーで、負けじ魂を持ち、どんな困難があっても成長するという企業の違いだ。もっている財産が違うのではない。思いが違うのだ」
よく「ゆでガエル症候群」というが、ドコモはまさにその状態にあった。そして気づいてみたら、MNPで独り負けし、利益でソフトバンクに逆転されていた。
そこでようやく、ドコモの尻に火がついた。その結果として出てきたのが、他社が真似することがむずかしい通話料金の定額制だった。これまで横綱相撲を取っていたドコモが、初めて積極的に仕掛けてきた施策だ。
これが想定どおりの成果をあげれば、ドコモのシェア低下に歯止めがかかる可能性は高い。しかし問題はそこからだ。
auもソフトバンクも、定額制については様子見の状況だ。もし、これがうまくいけば、収益を圧迫することになっても、両社は同様のサービスを行うことは間違いない。その時、ドコモはすぐに二の矢を放たなければならない。定額制がうまくいかなかった時も同様だ。顧客流出に歯止めがかからないなら、早急に次の手を打つ必要がある。
果たしてドコモに、それができるかどうか。
ドコモの加藤社長は2年前、社長に就任する際、スローガンとして「スピード&チャレンジ」を掲げていた。ライバルに比べ対応が遅く、リスクを追わない企業体質にあることを自覚したうえでのことだった。
新料金プランや、別稿で触れているM&A戦略など、従来のドコモにはないアグレッシブな姿勢は確かに見えてきた。それをいかに持続させ、さらに加速できるかどうかに、ガリバーの未来がかかっている。
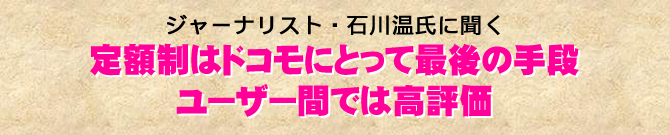
NTTドコモは通話料金定額制を導入することで、ついに最後の引き金を引いたことになる。
ドコモのシェアは、ここ10年間、ほぼ一貫して下がり続けている。1年前には「ツートップ戦略」を打ち出し、秋にはiPhoneの発売に踏み切った。ドコモ低迷の最大の要因はiPhoneを販売していないことだと思われていたにもかかわらず、いざ販売したところで、劇的な効果は得られなかった。
そこで最後の手段として、料金に手をつけたということだ。シェアが下がっているとはいえ、いまなおトップシェアを維持しており、2位以下とは大きな差がある。そのトップ企業が率先して値下げをするというのは、普通あり得ないことだ。
それだけドコモは本気ということでもあり、逆に言えば絶対に失敗できない戦術だといえる。
幸いなことに、いまのところユーザーの評価は高いようだ。
今度の定額制ですぐれているのは、ドコモの強みを活かした制度になっていることだ。
ドコモの強みといえば、昔から利用している加入者が多いこと。今度の定額制は、そうした長期契約者がきちんとメリットを享受できるようになっている。
さらに言えば、家族間のパケットシェア制度を導入することで、iPhone登場後、auやソフトバンクへ流れてしまっていた子供たちを呼び戻すことができるかもしれない。
すぐに効果が出ることはないかもしれないが、次のiPhoneが発売されるタイミングなどで、効果を発揮する可能性は大きい。
これまでドコモは、他社の攻勢に対抗する形で新たなプランを出してきた。それが今回は自ら攻めに出た。そこがいままでのドコモの戦略とまったく異なる。

ジャーナリスト・石川温氏
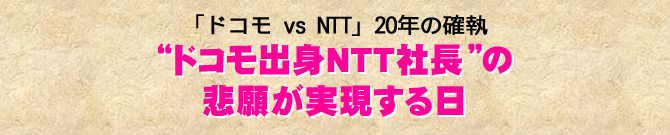
前稿でも触れたが、NTTドコモがNTTから分離・独立したのはいまから22年前の1992年のこと。初代社長は大星公二氏。以降、立川敬二氏、中村維夫氏、山田隆持氏、そして現在の加藤薫氏まで、計5人が社長を務めている。
大星氏と立川氏が6年間、続く2人は4年間、それぞれ社長の椅子に座っている。そして加藤氏は、現在でちょうど2年。前任2人に従えば、折り返し点ということになる。
しかしこの5人以外にもう1人。新聞紙面では社長に就任した人物がいる。立川社長時代に副社長を務めていた津田志郎氏がその人で、立川氏が任期を終えようとしていた2004年4月上旬、「次期社長に津田氏が内定」の見出しが新聞各紙を飾った。しかも複数紙が報じたことで、この人事は間違いないものと思われた。
「でも実際に社長に就任したのは、同じ副社長でも津田氏ではなく中村氏でした。津田氏の昇格に、NTTの和田紀夫氏が強く反対し、逆転人事となったのです」(当時のドコモをよく知る全国紙記者)
わざわざ古い話を持ち出したのは、ちょうどこの頃から、ドコモと6割の株を持つ親会社・NTTの関係に変化が起こり始めたからだ。

自由闊達な社風を取り戻せるのか(ドコモ本社の入るビル)。
初代社長の大星氏も、元はNTTの社長候補の1人だった。しかし現実は、当時は海のモノとも山のモノともわからない携帯電話事業への転出だった。これに大星氏は発奮する。その思いは同時期にドコモに常務として移った立川氏も同じだった。この2人の「NTTを見返してやる」との強い思いが、NTT何するものぞとの気概につながり、自主独立の社風を生んだ。
99年にサービスを開始したiモード開発に際しても、社外から多種多彩な人材を登用したことが、史上まれに見るヒットにつながった。官僚的な組織では、けっしてあのようなサービスは生まれなかっただろうし、生まれたところで、使い勝手の悪いものになっていたに違いない。
98年、大星氏が立川氏にバトンタッチする直前に漏らした「NTTの冠はいらない」という言葉が、当時のドコモの経営陣、社員の気持ちを何より雄弁に物語っている。
ところが皮肉なことに、iモードの大ヒットが、ドコモの自由度を奪っていく。
iモード以降、ドコモの業績は急速に拡大する。その結果、NTTの連結売上高のうち、利益の8割をドコモが稼ぐようになる。ドコモは金の卵を生むニワトリに化けた。
ニワトリが自由に動き回れる環境があったから、金の卵を生めたのだが、親会社のNTTにしてみれば受け止め方は違う。何しろ利益の大半をドコモが稼ぐのである。これをコントロール下に置きたいと考えるのは自然の流れだろう。
これはNTTに限った話ではない。たとえばプレイステーションが大ヒットし、ゲーム機事業が利益の大半を稼ぐようになっていた1990年代のソニーがそうだった。ソニーのゲーム事業は、ソニーとソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)の、2つの上場企業の折半出資会社として誕生した。しかしその事業が大きくなると、ソニーはゲーム部門の暴走を恐れ、SMEを100%子会社化することで、ゲーム部門をコントロール下に置いた。
NTTにしても同じことである。しかしドコモにしてみればたまったものではない。勝手に切り離しておいて、儲けが出た途端介入してくるのか、ということになる。大星、立川両氏は、ドコモ独立王国を守ろうと必死に抵抗した。
「NTTは97年に持ち株会社となり、その下に東西会社やドコモ、NTTコミュニケーションズなどがぶら下がる形となりました。その時以降、NTT本社は各事業会社に会長を置かないことを原則としています。ところが、大星さんは社長を退いたあと、4年間にわたり会長を務めています」(前出の全国紙記者)
影響力を発揮したいNTTと、自主独立を貫きたいドコモの攻めぎ合いである。
そのパワーバランスを崩したのが、次稿で詳しく触れているドコモの海外投資の失敗である。2兆円近くをM&Aに注ぎ込み、半分以上を失った。この損失のおかげでNTTの2002年3月期決算は8000億円もの赤字に転落している。
NTTにしてみれば、ドコモの自由にさせておいたら何をやらかすかわからない、という気持ちを一層強くする一件だった。それが、冒頭で記した、NTTによる「次期社長拒絶事件」へとつながっていく。
立川氏が強く推した津田氏は、立川氏と同じ技術屋で、ドコモが独立する前の1990年から携帯事業に携わってきた。いわばドコモ生え抜きであり、ドコモの自主独立路線を守るにはうってつけの人物だった。逆の見方をすれば、NTTにとっては津田氏の昇格だけは避けたかったということだ。
逆転人事で社長に就任した中村氏は、NTTの本流の1つである労務部を歩き、98年に取締役経理部長としてドコモに舞い降りている。当時、NTT社長だった和田氏もやはり労務畑出身で中村氏の5年先輩であり、気心も知れている。どちらを選ぶかは自明の理だった。
この2004年の人事をきっかけに、ドコモに対するNTTの管理が強まっていく。たとえば立川氏以降の3社長は、NTTの方針どおり、社長退任後会長職には就かず、相談役に退いている。
そして時をほぼ同じくして、ドコモのシェアの低下が始まっていくのは果たして偶然なのだろうか。
ドコモの現役社員が打ち明ける。
「NTTの子会社のわけですから、その方針に従うことは致し方ないと思っています。社長人事だって同様です。でもひとつ納得できないのは、NTTの歴代社長がみな携帯電話事業に明るくないことです。一時期より比率が下がったとはいえ、それでも7割の利益をドコモが稼いでいる。だったら、ドコモ社長がNTT社長になっても、何らおかしなことはない」
この言葉にあるように、ドコモの役員・社員の悲願とも言えるのが、NTT社長にドコモ出身者が就任することだ。
繰り返しになるが、持ち株会社NTTの下には、ドコモのほかに、地域会社の東と西、長距離のNTTコミュニケーションズ、ソフト会社のNTTデータなどがぶら下がっている。こうした形体の企業グループの場合、持ち株会社の社長を選ぶ際には、もっとも業績のいい子会社の長が最有力候補となる。NTTの場合ならドコモである。
3年前には、当時の山田・ドコモ社長が次期NTT社長の最有力候補と目されたこともあった。しかしこの年、東日本大震災が発生。それも影響してか、2期4年を迎えた三浦惺社長が1年留任。これによって山田・NTT社長の目はついえた。
しかしチャンスはこれからもある。
NTT現社長の鵜浦博夫氏と、加藤・ドコモ社長はともに12年に就任している。両社ともに4年ごとの社長交代が一般的のため、2年後に揃ってバトンタッチとなる可能性は強い。ただしNTTで副社長まで務めた山田氏と違い、加藤氏がNTT社長に就く可能性は極めて小さい。
しかし悲願を将来につなぐためにも、じり貧にあるドコモの業績を立て直すことが加藤社長には求められている。長期低落傾向にあるシェアを上向きに転じさせ、減益から増益へと流れを変えさせることができたら、ドコモ社長がNTT社長への登竜門となることは十分考えられる。
そのためにも前稿で触れたドコモの新料金プランは、何が何でも成功させなければならない。通話料金定額制度は、ドコモにとっても背水だが、その成否に、ドコモ社員の悲願の成就がかかっている。

大星公二(1992-1998) 初代社長。1932年生まれ。東京大学法学部を卒業し、日本電信電話(NTT)入社。企画畑を歩み、NTTでは常務にまで昇格。92年NTTドコモ移動通信網(NTTドコモ)に転じ初代社長に就任。98年から4年間、会長を務める。iモードの最初の発想は大星氏から生まれた。

立川敬二(1998-2004) 2代社長。1939年生まれ。東京大学工学部を卒業し日本電信電話入社。マサチューセッツ工科大学でMBAを取得。NTTアメリカCEOを経て92年からドコモ常務、98年から社長。立川社長時代の99年にiモードがスタート。以降ドコモは急成長を遂げた。

中村維夫(2004-2008) 3代社長。1944年生まれ。東京大学法学部を卒業し日本電信電話入社。労務畑を歩み、宣伝部長や労働部長を経て取締役経理部長としてドコモ入り。2004年、「津田社長」をNTTが拒否したことで社長の椅子が回ってきた。在任中、「ドコモ2.0」を推し進めるが、不発に終わった。

山田隆持(2008-2012) 4代社長。1948年生まれ。大阪大学工学部を卒業し日本電信電話入社。取締役設備部長、常務、副社長を経て2007年に副社長としてドコモに転じ、翌年社長に就任。在任中、iPhone発売のチャンスがあったが見送った。一時NTT社長有力候補だったが、実現しなかった。

加藤 薫(2012-) 5代社長。名古屋工業大学大学院工業研究家を修了し日本電信電話入社。94年にNTT関西移動通信網に転じ、同社常務、ドコモ常務経営企画部長を経て2012年に社長に就任した。昨年、「ツートップ戦略」を断行、秋にはiPhoneを発売。この6月から通話料金定額制に踏み切る。
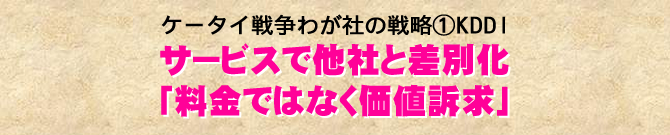
auを展開するKDDIは、5月8日、夏向け商品の発表会を開いた。しかしこの日、田中孝司社長がいちばん時間を割いたのは、新商品でもネットワークでもなく、「auウォレット」という新サービスだった。
これは、auユーザーだけが利用できるプリペイド型電子マネーで、全世界のマスターカード加盟店約3810万店で利用できるだけでなく、チャージや利用するたびにポイントが貯まる。しかも支払いは月々の通信料金と合算できるという、「早く申し込まないと損」(田中社長)なサービスだ。
クレジットカードを持つには審査が必要なため、所有者が限られる。一方の電子マネーは最近では提携によって多くの店舗で使われるようになってきたとはいえ、利用場所が限られることは否めない。その点、auウォレットは、両者の欠点をカバーする機能を持っている。

auウォレットを発表する田中孝司・KDDI社長。
この会見で田中社長が何度か繰り返したのは、「料金ではなく価値を追求していきたい」ということだった。
これは明らかにNTTドコモの音声通話定額制を意識してのことだ。一昨年のiPhone発売以来、MNPではドコモから大量の顧客を奪って圧勝し、前3月期決算でも過去最高益を記録したKDDIにしてみれば、敢えてドコモと同じ土俵で勝負することはないという判断なのだろう。
それにしても、iPhone発売前と発売後では、KDDIはまるで違う会社のように見える。発売前は、加入者も伸び悩み、売上高も2期連続で減収になったばかりか、通信障害も相次ぎ、携帯3社の中の落ちこぼれとなっていた。
ところがiPhone発売によってすべてが変わった。これ以降、前述のように、ドコモからauへの民族大移動が起こったのだ。
iPhoneの商品力によるところも大きいが、同時に、KDDIが進めてきた固定回線とスマホのセット販売という、事実上KDDIにしかできない販促手段がずばりと当たった。また、定額でアプリが使い放題になる「スマートパス」も大きな吸引力となった。
しかもLTEがスタートすると同時に、auはいち早くプラチナバンドと呼ばれる800MHz帯でのサービスを開始することで、他社との差別化を図った。ソフトバンクがCMでつながりやすさナンバーワンを謳っているが、ことLTEに関しては、auの評価がいちばん高くなっている。
つまりiPhone発売後は、それまでの不振が嘘のように、すべての施策がうまく回り始めた。「料金から価値の追求」も、その流れの中から出てきたものだ。
ただその一方で、新しい料金プランについても準備を進めている。現在は、6月1日から始まるドコモの定額制がどのような結果になるかを見守っている状況で、それを受けて、おそらくはドコモ以上のプランを出すことになるはずだ。
問題はこの勢いがどこまで続くか。2年前までの不振企業が、あっという間に好調企業に生まれ変わったということは、その逆も十分にあり得るということだ。
だからこそauは、サービスで他社と差別化することで、ユーザーの囲い込みに躍起になっている。
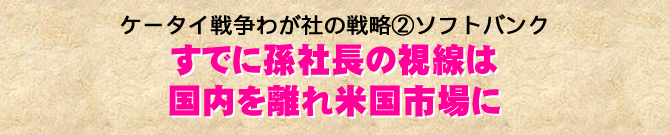
特集の冒頭でも触れたように、ソフトバンクの前3月期決算は、営業利益が1兆円を超えた。
「営業利益1兆円を超えた日本企業は、過去にNTTとトヨタだけ。NTTは118年、トヨタは65年かかったが、ソフトバンクは創業33年で到達した」
孫正義・ソフトバンク社長は決算発表の席上、こう語って胸を張った。

利益1兆円を発表するソフトバンクの孫正義社長。
前期の利益1兆円のうち2000億円については、ガンホーとウィルコムの子会社化に伴う一時的な利益であり、いわば水増しされた1兆円と言っても過言ではないが、孫社長は、今期は「営業活動だけで1兆円を達成する」と語るなど、勢いは止まりそうにない。
しかも今期からは、昨年買収した米携帯3位のスプリントの業績が、まるまるソフトバンクの業績に乗っかってくる。スプリントは、今期第1四半期こそ利益が出たものの、契約者の流出が続いている。いまのままでは業績に寄与するどころか足を引っ張ることになりかねないが、孫社長は「日本国内では、固定電話の日本テレコム(現ソフトバンクテレコム)、携帯のボーダフォン(現ソフトバンクモバイル)、PHSのウィルコムの3社の経営を引き受け、いずれも再建に成功した。その経験をアメリカでも活かす」と自信満々だ。
まずは設備投資によって通信品質を上げ、年末あたりから戦略的料金によって契約者増を目指していくという。しかも孫社長は、スプリントを買収したばかりであるにもかかわらず、米4位のTモバイルUSの買収も目論んでいる。実現するには、米連邦通信委員会の承認が必要となるが、もし認められれば、ソフトバンクはいきなり、ホライゾン、AT&Tを凌いで全米1位の契約者数を獲得することになる。
しかも、ソフトバンクが30%以上を出資する中国のアリババがニューヨーク市場に上場することが決定。孫社長は「株は持ち続ける」としているが、アリババの含み益は間違いなくソフトバンクの資金調達に有利に働くはずで、2兆円とも言われるTモバイルの買収資金にもこれでメドがついたことになる。
このように、ソフトバンクの視界に、すでにドコモはない。日本の小さな市場ではなく世界で勝負する会社に成長したのだ。
ただし、それが日本市場においてはソフトバンクの弱点となるかもしれない。
孫社長の長所でも欠点でもあるのだが、とにかく飽きっぽい。新しことを始めると、それまでのことにはまるで関心がなくなってしまう。つまり米国に本腰を入れれば入れるほど、日本はないがしろになる。そしてすでにその兆候は現れている。
ソフトバンクの携帯事業が伸び始めたのは、ホワイトプランなど、他社より価格競争で優位に立ったことがきっかけだった。当時、孫社長は「他社が安い料金を出したら、24時間以内にそれより安い料金を提示する」と語っていたほど、価格に執着をみせていた。
ところが、今回、ドコモが定額料金を出してきたにもかかわらず、孫社長は「出す以上はドコモに見劣りするつもりはない」と語っているものの、対抗策を出すのは、ドコモの経過を見てからのことになりそうだ。以前の孫社長にはあり得ない行動だ。孫社長の日本市場への無関心こそが、ソフトバンクのアキレス腱となりそうだ。
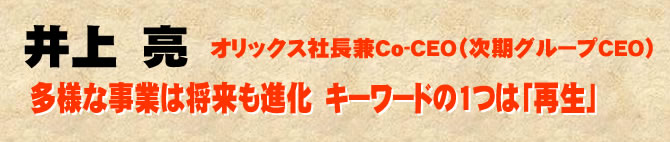

井上 亮
オリックス社長兼Co-CEO(次期グループCEO)
いのうえ・まこと 1952年10月2日生まれ。東京都出身。75年中央大学法学部卒。同年オリックス入社。2003年投資銀行本部副本部長、05年執行役でプロジェクト開発本部長、06年常務執行役兼業務改革室管掌、08年海外事業統括本部長、09年グローバル事業本部長、10年取締役執行役副社長で投資銀行本部統括。11年1月社長兼グループCOOとなり、14年1月グループCo-CEOに就任。この6月24日、グループCEOに就く予定。
来る6月24日の株主総会後の取締役会を経て、オリックス社長兼Co-CEOからグループCEOに就く井上亮氏。多様な事業を展開してきたオリックスを、さらにどう進化させていくのか。その戦略などを聞いた。
―― 井上さんは今年1月からCo-CEOとなり、半年の助走期間を経て6月24日からグループCEOに就くことになりました。
井上 COOの頃は、(現CEOの宮内義彦会長とは)頻度高く話し合わなくても、執行責任者でしたからやれていました。でも、Co-CEOになるとほとんど毎日、意見のすり合わせというか、宮内の方針を確認しながら進めないとまずいなということで、ずいぶん距離感が近くなっていましたね。一度、投融資委員会の会議に宮内が出られないことがあって、次の日に「井上君、なんでこの投資案件を了承したんだ」と言われ、「いや、これこれこういう条件をつけましたから」「うん、だったらいい」といったやりとりがあって、宮内とは必ず確認していました。
―― 前期(2014年3月期)決算の好調さ(純利益で1867億円)を継続し、今期は過去最高益(純利益で2100億円)を見込んでいます。前期の総括と、好業績の中に見えてきた課題はありますか。
井上 リース業から始めて、ここまで多角化というか多岐にわたった事業を(宮内氏という)1人の力でよく広げたなという感慨が1つ。あとは、昔なら国内が好景気の時は海外がダメだったり、船舶ビジネスがダメな時に不動産が良かったりと補完し合う事業構造でしたが、いまは6つのセグメント(法人金融サービス、メンテナンスリース、不動産、事業投資、リテール、海外)すべてで収益を出していますからね。ただ、5年経ったらオリックスはまた、全然違う業態に進化している可能性もあります。
―― 宮内さんも以前、「5年後に当社の会社案内を全面改訂しているくらいでちょうどいい」と言われてました。
井上 そういう進化の過程でキーになるのはやはり人材です。たとえばリースビジネスをやっていた人間がエクイティファイナンスをやり、エクイティをやっていた人間が今度は不動産の証券化をやり、証券化をやっていた人間が水族館の経営をやりという具合に、それぞれの分野で専門性を持たないといけない。そのためにはまだ人材が足りないし、育成の強化も大事だと思っています。
―― これだけ事業が幅広い中で、生え抜きと中途採用、あるいはヘッドハントする社員の比率はどのくらいなのでしょう。
井上 半々ぐらいでしょうか。ただし、同じ中途入社でも20代で入った人、30代や40代で入った人とでは違いますからね。40代で入ってきた人たちは、ごく狭い領域のスキルを求めて採用しますから、それはそれでいいんですけど、問題はその人がほかの部門に移った時、たぶん苦労することですね。一方で、新入社員はとにかくOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)でガンガン仕事をさせますから、違う苦労はあると思いますけど、いろいろなスキルが身についていく面白さは感じてくれるでしょう。
―― いま、オリックスが注力しているメガソーラーを含む再生エネルギー分野は、必然的に中途採用が多くなると思います。実際に、東京電力を辞めた人も入社しているようですが。
井上 この事業では、技術系とか専門性を求めるところではヘッドハントもしていますからね。電気系の知見のある人や地熱発電に詳しい人などが、意外と来てくれるんですよ。なんでオリックスがそんなことやるの? でも面白いから行ってみようという方が結構、いらっしゃるんです。

オリックスは今年、節目の50年を迎えた。
我々としては、太陽光発電のメガソーラービジネスも、いわば金融サービスの広がりの中にある事業と考えています。金融は、お金を融資するだけでなく、借りるのも金融だし、ポートフォリオを築いて証券化を展開するのも金融です。水族館の経営だってPFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ。公共施設の建設、維持・管理、運営を民間事業者が担って無理・無駄・ムラなく経営)から始まってますからね。ゴルフ場経営も、最初のきっかけはお取引先が破綻してしまい、当社で肩代わりしたのが出発点。経営していくうちに、ほかにも安く手に入るゴルフ場があるから買い増していった結果、いまでは41カ所のゴルフ場運営に携わっています。
―― メガソーラーのビジネスだけでなく、オリックスの事業は「再生」というのが1つのキーワードになっている気がします。
井上 その通り。当社は独立系ですからしがらみが意外と少ないですし、事業再生のお手伝いをし、最終的には再生して元の事業主に戻すのが基本です。ただ、再生後に「もう要らない」ということであれば、付加価値をつけた上で第三者に売却するといった出口戦略を取ることもありますね。
―― 一方で、主力の金融サービスではロベコ(オランダの資産運用会社)買収で2500億円、さらに米国のハートフォード生命保険買収で900億円と、かなり攻勢をかけている印象です。
井上 当社はケチですから高い買い物はしない(笑)。それが基本方針です。財閥系でもないしメガバンクがバックにある会社でもありませんから、いったん(M&Aの)エントリープライスを間違えて高値掴みしたら、その後の苦労が大変なものになってしまいます。また苦労するにしても、エントリープライスが低ければ経営のやり方次第で生き残ることができますから。
―― ハートフォードのほうはいずれ、グループのオリックス生命保険と一緒にしてということになると思いますが、ロベコのほうはたとえば、国内の金融サービス事業とのシナジーは考えていますか。
井上 ロベコ・ジャパンみたいな会社を作れば、日本でのアセットマネジメントビジネスも可能です。もちろん、アセットマネジメント分野には、すでに野村證券さんをはじめとした大手がいますからどこまで食い込めるかわかりませんが、日本でもやる価値はあると思っています。
―― オリックス銀行の旧社名はオリックス信託銀行でしたが、ロベコ・ジャパンは信託銀行のイメージに近くなるのでしょうか。
井上 いや、ちょっと違いますね。やっぱり資産運用会社としての位置づけで、まず日本円でのビジネスを考えています。もともと、お取引のある日本の投資家はロベコのファンドにはかなりお金を入れていただいてますし。その資金は運用上、これまでは必ず円を海外通貨に換えていましたけど、円でもお取引ができますよということになれば、サービスの幅が広がりますから。
―― 保有していた大京の優先株を普通株に転換して、議決権で64%を持つ連結子会社にしました。シナジー向上は見込めそうですか。
井上 マンション管理の受託ビジネスは基本、アセットマネジメントと一緒ですし、大京には電気技師関連の人材もたくさんいますから。これまではいわば、大京の自前のマンションだけの技術者じゃないですか。それを、さらにオリックスグループ全体に広げれば効果が出てきますよね。たとえば、電気技師の方にメガソーラービジネスのほうを見てもらうこともできるのです。
―― 不動産も、最近はマンション開発より管理などのストック重視になってきています。
井上 ケースバイケースで、メリハリをつけてやればいいと思っています。さきほど言いましたように、(マンション用地の仕入れで)エントリープライスが高いと身動きが取れなくなるのは一緒ですから。逆に言えば、安い時に土地を仕入れればどうにでもできる。そういうメリハリさえつければ、どんな事業でも収益性は確保できると思います。
―― 逆に、資産の入れ替えというか、売却していくケースも出てくると。
井上 たとえば今回、ハートフォードの買収で資産が膨らみますけど、一方的に資産を膨らませていく気は全然ないんです。資産の中身を入れ替えながら優良資産に変えていく。長く保有していれば、やっぱり売り時というのがあるじゃないですか。それを失するとプライスが下がってしまうので、いい時に売ることが大事。で、また景気が悪くなったら出物が出てくるかもしれませんし。
―― マネックス証券もオリックスが大株主でしたが、手堅い地銀の静岡銀行に売却しましたね。
井上 証券、特にネット証券は競合が激しくて収益性はきついし、マーケットに依存せざるを得ません。マーケットに依存する投資は、できるだけ限定的にしたいですから。
―― 海外の重点エリアや重点分野はどうでしょう。
井上 国ごとに景気は違うので、たとえば中国はダメでも中東がいいとか、常に目を広げて、安く買えて将来性のある事業や企業かどうか、さらに純投資なのか戦略投資なのかを見極めていく。で、後者の場合はどういう形でならオリックスとのシナジーを発揮できるのか、前者の場合はパートナーの能力、業界のポテンシャルを見て投資して、たとえば5年と決めたうえで5年後の出口戦略を考えながら投資していくと。
―― 外国人持ち株比率がいま6割強と高いですが、国内でもこれだけ多様に事業展開しているオリックスを、海外の投資家たちはどんな業種と捉えているのでしょうか。
井上 海外IRに行くと大変ですよ、1時間説明してもなかなか理解してもらえないケースもありますから(笑)。やっぱり6つの事業セグメントを1時間で説明するのは無理がありますよね。最近は、それぞれのセグメントで注目してほしいところをメインに説明していますが、ホールセール(法人向け事業)とリテール(消費者向け事業)という2カテゴリーの分類だけにして、あとは何も説明しないほうが逆にいいかもしれません(笑)。
―― 当面は、6つのジャンルの深掘りだと思いますが、これから可能性のある領域や地域はどう考えていますか。
井上 エリア的に言うと、これから見ないといけないのはアフリカですね。それからラテンアメリカがまだできていない。当社は商社と競合する気はありませんから、(商社のように)資源関連事業は手がけませんが、食料や農業関連も含めて、アフリカやラテンアメリカでも、かなり広範囲な分野でビジネスができるのではと考えています。
もう1つ、ベンチャー投資もやりたいんですが、我々にはまだこの分野での目利きがないんですね。昔、アリババやフェイスブックといった企業が誕生した頃、当社にも投資の引き合いはあったんです。でも、土地勘がないから結局、やりませんでした。もちろん、ベンチャーキャピタルの投資はこれまでもずっとやってますけど、もっと能動的に、新興企業の技術や将来性を分析して、ここだったら10年後にここまで成長する可能性があるから投資してみようという、そんな案件をものにしてみたいですね。分析力と将来性の目利き、オーナー経営者と親しくなって信頼に足るリレーションシップを作るとか、これから当社でも頑張りたいと思います。
―― オリックスはある意味、資源分野を除いた商社の業態に似ている感じですね。商社という業態は海外にはないので、海外投資家から見るとわかりにくいですから。
井上 確かに、資源を除いた部分ではほとんど商社とオーバーラップしてますね。食料や農業分野は当社ではまだそんなにやっていませんが、それ以外はかなりダブっているんじゃないでしょうか。
―― 最後に、足元の決算を踏まえた今後の展望を。
井上 ロベコ、ハートフォードの買収に大京の子会社化、メガソーラーにプラス風力や地熱発電もやっていますし、それらをうまく安定収益に結びつけていく間に、必ず新しいビジネスの話が出てきますから、それを模索していこうかなと。あとはUSA(米国)ですね。
―― オリックスの米国法人社長に今年、元あおぞら銀行社長のプリンス氏を起用しました。
井上 これまでオリックスUSAのメインの収入は、フィクスインカム=手数料収入だったんですが、いまはフィクスインカムで収益を維持するのはかなりハードルが高くなっていますので、そうなると、プライベートエクイティを含めたファンドやアセットマネジメント事業が主力になってきます。彼(=プリンス氏)はもともとそういうキャリアとネットワークを持っていますので、ちょうどいいのかなと。プラス、ロベコを買収したことで欧米の収益バランスも取れるようになるでしょう。
(聞き手・本誌編集委員・河野圭祐)
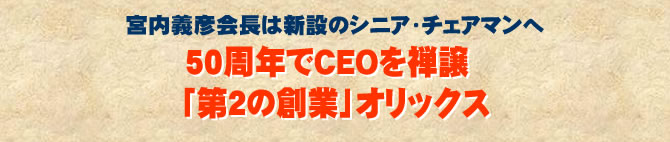
去る4月17日、オリックスは創業50年の節目を迎えた。今日までの主な歴史は左頁の表をご覧いただくとして、この50年、同社とともに歩んできたのが宮内義彦会長兼グループCEO(78)である。
同氏は、もともとは日綿実業(現在の双日)に勤めていた商社マンだが、米国で浸透していたリース業が日本でも根付くと判断した日綿から指示を受け、提携先リース会社への研修で渡米したのが始まりだった。そして、オリエント・リース(現・オリックス)の設立準備会社が立ち上げられ、メンバーは13人、宮内氏が最年少でもあった。
創業期の1964年から67年までは日綿の福井慶三社長が社長を兼務し、67年から80年まではメインバンクの三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行)出身の乾恒雄氏が社長を務めている。宮内氏が登板したのは80年、45歳の時だったが、75年時点で「次期社長」を告げられていたというから、宮内氏がいかに早くから頭角を現し、異能ぶりが評価されていたかがわかる。
こうして、80年12月から2000年まで社長、その後も会長、引き続きグループCEOとして陣頭指揮してきた。トップ在任は33年半に及ぶ。宮内氏が「これだけトップを務めると、オリックスのシンボルのような形になったのも、長いがゆえにやむを得ないところもある。いわば自分の会社のような意識で今日に至っているわけで、この意識は、いい悪いは別にして、おそらく変わらないんだろうなと思います」と述懐するのも無理からぬところだ。

オリックスグループCEOは宮内義彦会長(右)から井上亮社長へ(5月8日、東京・千代田区のパレスホテルで行われた会見で)。
その宮内氏が去る5月8日、ついに後継者にバトンタッチするとして記者会見を行った。まず冒頭の挨拶で、同氏は次のように述べている。
「ここ何年か、いい形で承継したいと思ってきました。元気な間にこれと思う方に引き継ぎ、私は少し違った立場からアドバイスをさせていただくと。私は会社設立時から関わってきましたから、取締役や執行役でいつづけることの意味が見えてこない。役員から外れても同じことだし、会社にまだ片足をかけるような必要はなかろうと思いました。
今後は、シニア・チェアマンという非常にわかりにくい称号になります。執行役からも取締役からも外れてアドバイスをするという新しい立場で、シニア・チェアマンとしてどれだけ会社に貢献できるかを試みる時期に入ります」
自身も「非常にわかりにくい」と語ったシニア・チェアマンとは、確かに聞き慣れない肩書だ。ほかの大企業では、功績を上げたトップが後進に道を譲る際は、名誉会長、あるいは最高顧問や特別顧問といったポストが用意され、宮内氏のように創業前から携わった場合はファウンダーといった呼称も考えられる。
選んだポストがそのいずれでもないところが、宮内氏の異能経営者たるゆえんかもしれない。シニア・チェアマンにした狙いや思いはどこにあるのだろうか。
「たとえば執行部がやっていることに関わって、いわば院政みたいなことになるのかと言えば、そうではありません。それに、もし院政をするのだったらいま辞める必要はまったくないと思っていますから。さきほど言いましたように、これまでとはまったく別の形で会社に貢献したいなと。それをこれから模索するということです。
そういう意味では、シニア・チェアマンというのはある種、前人未到のポジションです。お名前は出せませんが、私の尊敬する方に相談をしましたら、その方が『誰にもわからない名前が一番いい。シニア・チェアマンがいいぞ』と。最初はそんな変な肩書とも思いましたが、重ねて勧めていただいたものですから。
確かに、チェアマンというのはJリーグでも使われている呼称ですし、シニアのほうも、比較するのは大変失礼ながら、リー・クアンユーさん(シンガポールの元首相)が引退された時“シニア・ミニスター”という名称を付けておられます。
CEOを長くやっていて、できないことがいくつかありました。会社というのは毎日、目の前に大きな課題があるもので当然、そこに全力です。逆に言えば、本当は重要なことでもいまやらなくていいことは疎かになりがちだったのです。そういう面を私が担っていくことで、新しい執行部の負担を少しでも減らせればいいし、シニア・チェアマンの立場を利用しまして、会社を大きく包み込むような形で貢献できればというのが、いまの心境です」
宮内氏言うやれなかったこととは大きく2つあるという。1つが、長期の戦略をじっくりと時間をかけて考え、練り上げること。もう1つが次世代の人材育成。同氏の後を継いで、6月の株主総会後にグループCEOという頂点に立つ、井上亮・社長兼Co-CEO(61)の次の世代、つまり現在50歳前後の幹部たちの育成だ。この世代の幹部となると、本当の実力や人となりをまだ把握し切れておらず、いまから数年かけて次世代を担う人材を絞り込んでいく考えのようだ。
業容やネットワークから言って海外出張が頻繁にあった多忙な宮内氏は、いつも渡航前に秘書に封書を渡し、「万一、飛行機が墜落するようなことがあれば開封せよ」と指示してきた。それほど眼前のビジネスに追われてきたのが実情。長期戦略や後継候補の育成と聞くと、それこそ新グループCEOとなる井上氏の権限にも映るが、そこは執行役や取締役も外れることで、宮内氏が語ったように「会社を大きく包み込むような存在」になるのだろう。
一方、3年前の11年1月に社長兼COOに抜擢された井上氏は「正直、あと3年ぐらいは宮内がCEOを継続し、その3年後あたりにもし私がCo-CEOで残っていればCEOの覚悟をしなければいけないのかな」と考えていたという。Co-CEOという共同CEO職に就いたのはまだ今年1月だけに、3年後あたりかと井上氏が考えるのも道理だが、オリックスにとって今年は創業50年の節目の年であるうえ、39年間を共にしてきた部下だけに、宮内氏は井上氏を知り尽くしている。CEOの“試用期間”は当初から半年でいいと考えていたのだろう。


球団オーナーを務めるオリックス・バファローズも今年は好調。
―― 創業50年の節目の今年、オリックスの歴史はそのまま宮内さんの歴史でもあるので、まずはその感慨を。
宮内 私は昨日のことも思い出すのが面倒なほうで(笑)、どちらかと言えば“前傾姿勢”が強い人間ですから、過去のことはあまり思い出さないんですけど、スタート時は13人しかいない会社だったのが、大企業の1社に数えられるまでになったんだな、という思いはありますね。
―― ここまで多様な事業を展開する企業になると想像していましたか。
宮内 少なくとも初めの3年間はリース業という狭い範囲に没頭していました。5年後ぐらいから、急に同業の新設会社がたくさん出てきて競争が始まったわけですね。で、競争が始まってみると、案外とリースマーケットは小さいではないかと。それで、5年後ぐらいからこれは隣の領域へも行くべきだという考えが出てきたのです。
―― 最近は、メガソーラーを含めた再生エネルギー分野に積極的です。
宮内 たまたま(原発事故などで)エネルギー問題から脚光を浴び、どうもこの分野はまだ、本当の専門家がいないわけですね。ならば我々も一緒じゃないかいうことで参入していったのですが、私自身、数年前まではそういうビジネスを本格化させるとは、夢にも思っていませんでした。
―― 6年前のリーマン・ショック前と後とでは、事業内容が様変わりしてきた印象です。
宮内 方向性としては、すでにリーマン・ショック前からこちらへ行きたいなという話はしていたんです。実際に“じわっ”ぐらいは動いたんですけど、リーマン・ショックが起きて、これは事業構造の転換を急がなければと。結果的に禍転じて福、みたいな感じです。
リーマン・ショック前に米国へ行った時に「これは絶対に住宅バブルだな」と思いました。私どもの米国法人は債権の売買などもやっていましたが、現地法人のトップと話をして、手がけていた住宅案件は全部売ってしまった。だからオリックスには何の影響もありませんでした。ただ、リーマン・ショックで瞬く間に負の連鎖が伝播し、日本の金融市場も崩れていくというのは想像してなかったですね。
―― 「あの頃は当社も溺れかけた」と言われてましたが。
宮内 自分の会社がそんな大変になるはずがなかったんですけどね。リーマン・ショック直前まで、収益も上がってきて非常にいい状況で、私も年だからこれは楽隠居できるのかなと思ってたんですよ(笑)。そしたらそれどころじゃないと。リーマン・ショックでドーンとやられた後は復旧作業でしたけど、それが済んで、今度は新しいビジネスを構築していくという段階に来たと思いますので、少し落ち着いて長い目で仕事ができるのかなと。
―― 常に変化していくことがオリックスの特徴であるとすれば、将来のオリックス像を語るのはあまり意味がありませんか。
宮内 たとえば、航空会社だったら機材を100機持っていて、3年先には150機にもっていきたいというような話をすると思うんです。そういう意味では、我々は若干、“カメレオン”的な性格がありますからね。当社のように明確には事業を言えない会社、言える会社といろいろあるでしょう。ただ、金融をベースにフレキシブルに動いていくというのが基本です。
―― かつて、メーカーを買収して失敗したのも教訓になっていますか。
宮内 ええ、全然違うということがわかりましたからね。電機関連の会社でしたが、ハイテク技術を持つ会社でもなく、国内はすべてクローズして海外に行ったらよかったのかもしれませんが、そうこうしているうちに買ってもいいという会社が出てきましたので。やっぱり隣の領域でないと。
―― DNAでしょうか、宮内さんの2人の子息(誠氏と修氏)とも、サラリーマンを経ていまは起業家です。
宮内 起業するのはいいんだけど、事業として成り立っているかどうかが問題でしてね。ただ、アドバイスもせずにほったらかしなので、何をやっているのか時々聞かないとわからないぐらいですが(笑)。
―― さて、新グループCEOに就く井上亮社長の体制での課題ですが。
宮内 当社もいまは巡航速度に入って、目の前に大きな課題を抱えているわけではないんですね。こういう時こそ少し長い目で見た戦略立案、長い目で見た人材育成をやっておかないと。
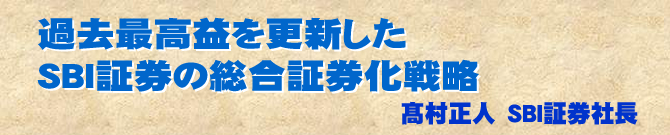

髙村正人 SBI証券社長
たかむら・まさと 1969年2月生まれ。92年慶應義塾大学法学部卒業後、三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行。2005年イー・トレード証券(現SBI証券)入社。07年取締役執行役員、12年常務を経て、13年社長に就任。
2013年度、証券各社は久しぶりとも言える好決算が相次いだ。なかでもネット証券は過去最高の数字が相次ぎ、アベノミクスの恩恵を大いに受けた業界だと言える。そのネット証券でシェアトップのSBI証券は、好決算を背景に、対面や法人部門の強化をさらに進めている。ネット証券の枠にとどまらないSBIの戦略とは――。
〔昨年は好況に沸いた証券業界。決算発表では各社とも大幅な利益の上積みを果たした。半面、HFT(ハイ・フリークエンシー・トレーディング)等、ミリ秒単位で売買注文を出す超高速高頻度取引が幅を利かせるようになり、個人投資家が積極的に商いができない状況に陥ってしまっている〕
全体的な流れで言えば、去年の年末までが絶頂期でした。株式の売買譲渡益や配当にかかる税金の軽減税率が昨年末で終わり、駆け込みで売り急いだりということもありましたので株価も年末がピーク(1万6320円22銭)。年明け以降、株価は下げトレンドでなおかつ膠着状態に入ってしまっています。
一方で、HFTと言われるような超高速取引が目立つようになってきました。実質的な取引所の売買代金は1日に1兆6000億円前後となっていますが、個人投資家の方に話を聞くと、感覚的にはその半分くらいだそうです。アルゴリズムを使った超高速取引が増えると、マニュアルでしか取引できない個人投資家は非常に不利になりますから、怖くて手を出しにくい状況になっています。これらが背景となって、取引のボリュームが3月、4月と減ってきています。
我々としては、個人投資家が安心して参加できるような取引環境を提供していかなければいけないと、取引所には個人投資家サイドの要望を出したり、提言をさせていただいているところです。
〔とはいえ、昨年の大幅な株価の上昇は個人投資家に大きな利益をもたらしている。株取引からは距離を置く個人投資家が増えているが、資産運用に対しては積極的な姿勢を崩していないという〕
私どもが源泉徴収を行う特定口座のお客様だけでも、昨年は7000億円のキャピタルゲインを上げられています。その意味では、手元のキャッシュポジションはすごく高い。短期で売買されている方は、いまでこそ手控えていても、流動性が増大してくるのを待っているという状況です。決して悲観的になっているわけではありません。
加えて、今年からNISA(日本版ISA)が始まりましたので、こちらの口座を開設されたお客様は、積み立て型の投資信託を始められる方が多い。現在、投信の積み立ての23%ほどはNISAでのお客様です。たった3カ月でこれだけの数字になっています。これはNISAの中長期で保有して資産形成を助けるというコンセプトが機能しているということでしょう。NISAで株を買われる方も、配当利回りのいいものを中心に長期保有するというお客様がほとんどです。着実に裾野は広がってきたという印象を持っています。
〔NISA口座については、銀行、大手対面証券会社をはじめ、様々な金融機関で口座獲得競争が繰り広げられてきたが、ここにきて利便性の面からもネット証券に分があるように思われる〕
我々はそれほどコストをかけていませんが、銀行や対面証券がかなり大々的にプロモーションをしてくれたおかげで、NISAの認知度そのものは非常に高まっています。3月末までに、私どもに口座を開設いただいたのが41万口座くらい。来年からは取引口座を変えることが可能になりますので、おいおい100万という数字も目指し得る。全金融機関で10%のシェアを獲ろうという高い目標を掲げています。
対面の証券会社さんの場合、NISAを使ってどうするのか、実は営業の現場とボリューム的に噛み合わないんですね。シニアの方はある程度、すでに資産を形成されている方ですから、志向も異なります。それこそ億円単位で投資をされる方たちですから、年100万円という枠では、合わない。対面証券はシニア層が7~8割で、若年層が7~8割のネット証券とは世代がまったく逆になります。NISAは将来の資産形成ということでお使いになる。実際の利用率も、SBI証券が4割なのに対し、対面証券は2割くらいと聞きますから、使い勝手などは我々のほうに分があると思います。
〔そうは言っても、大口の投資をする個人投資家は、どの証券会社にとっても魅力。SBI証券が他のネット証券と異なるのは、こうした層を取り込むべく、対面部門も持っている点だ〕
対面で営業マンのアドバイスを受けながら金融商品を購入する層は、それなりのロットで買い付けをされます。そういう志向性のお客様には、「マネープラザ」のコンサルティングを紹介してご提案させていただいている。直接やり取りして買い付けをするお客様は、ネットの売買とはボリュームが違いますから、一定のアドバイスを求めて、多少コストは高くてもアドバイス料と割り切っています。マネープラザ以外にも、IFA(金融商品仲介業)約200社と提携してネットワークを広げているところです。
〔IFAは、もともと会計士や税理士などが、自分のクライアント向けに金融商品を紹介するという形態が多かった。ところが最近では新しい形のIFAが増えつつあるという〕
弊社のIFAでは、会計士、税理士のある程度の規模を持った事務所さんが半分、ファイナンシャルプランナー、保険代理店さんがそれぞれ2割弱です。残りはというと、証券会社のOBの方々、いわゆるプロの仲介業者が増えてきています。

年末「株価は1万7000円」と語る髙村社長。
野村さんをはじめ出身会社は多種多様ですが、証券会社を退職されたあと、何人かで会社をつくったりして、お付き合いのあるお客様の金融商品取引の窓口になっています。証券会社に長く勤めていると、お客様は長年お付き合いした営業マンと離れたくないという要望があるようです。生計を支えるというよりも、ボランティア的な要素も含めて、私どもの仲介業者という肩書でお客様と繋がっていくというパターンができています。こうした方々のIFAはコンプライアンス等含めて熟知されていますので、我々としても安心して任せることができます。
ネット証券ではなかなかリーチできないような、投信で何億円も買うようなお客様に対して、プロの仲介業者の方々がリーチしていく。いまではマネープラザの15%ほどを占めるようになってきています。
〔IFAは楽天証券が力を入れている事業でもある。その差別化はどう図っていくのか〕
確かに楽天証券さんとは事業モデルは似たところがあって、特にIFAでは競合しています。私どもにあって、楽天さんにはない、例えば新規上場株の取り扱いなどを有効活用していくなど、差別化を意識しながら事業展開を進めています。
〔SBIにあって他のネット証券にないものと言えば、法人業務への強いアプローチだろう。新規上場の主幹事も一昨年が5社、昨年は6社と確実に実績を積んできている。それはネット証券の枠を超えた、総合証券へのこだわりと言える〕
主幹事の本数だけ見ると、新規上場ができる証券会社として認知されてきているのではないか。またIPOの引き受けの社数ではここ何年か業界トップになっています。ここは法人業務ですから、多少のコストはかかっても、プレミアム商品の仕入れ部隊と考えれば、ものすごく機能している。お客様に魅力的な商品供給ができているという意味では、私どもが頭一つ抜きん出ているところと言えるでしょう。
主幹事も、いまいただいている引き合いからすると、遠からず2桁の社数を達成できると思います。グループのなかにインベストメントがあることも大きいですね。実際に投資をしているかどうかにかかわらず、ベンチャー企業とのネットワークは強固なものがありますし、北尾(吉孝氏・SBIホールディングス代表)が意識したグループシナジーという意味では、すごく効いている部分だと思います。
年末に向けては上昇トレンド
〔前期は営業収益742億9800万円、営業利益327億9900万円、純利益180億6900万円と、過去最高の決算となった。株価が伸び悩んでいるとはいえ、昨年、せっかく戻ってきた個人投資家たちを手放すわけにはいかない。好業績に胡坐をかくことなく次の仕掛けが求められている〕
おかげさまで、創業以来の最高益でした。何がいままでと違うかというと、とにかくお客様が儲かった。我々証券会社にとって、これがいちばん大きいことです。株式市場で儲かったお客様が、次なるリスクマネーという形で資金の回転も上がりました。お客様が利益を実感することで、投信、債券、FX等の他のプロダクツに波及していく効果が生まれ、新しいお客様を呼び込む呼び水になります。
私どもとしては、マーケットが低迷しているから、商いが薄いからといって、指をくわえているわけにはいきません。去年からリサーチの部署を強化しまして、投資に直結するような情報をお届けする投資調査室のメンバーを拡充しました。一昨年と比べものにならないくらい、お客様の目に触れるコンテンツは積極的に投入しています。
例えば動画のコンテンツは飛躍的に増えていますし、静止画であっても投資情報に関するコンテンツは増やしている最中です。これは日本株と外国株にまたがって強化していきます。
また、ユーザー側から見た取引チャネルがすごく多様化して、パソコンですべてを完結するお客様の比率は年々下がってきています。モバイル、特にスマホ周りのチャネルに関しては、年初から積極的にアップデートを図っていまして、お客様の利便性を高めることを徹底的に追求してきました。ここは投資を惜しまずやっていきます。
〔金融商品が多様化したとはいえ、やはり証券会社は株取引が活発になってこそ利益が生まれる。年末に向けての株価はどうか。予想を聞いてみた〕
1万7000円くらい。堅実ですけど(笑)。消費税率10%という懸案もありますし、その意味ではきちんとデフレから脱却して、インフレへという道筋を確認しながら、局面によっては金融緩和もあると思います。法人税減税など、将来に繋がるポジティブな材料には事欠かない。年内は出し惜しみすることはないでしょう。
現段階では、今期の見通しを保守的な数字で出されている企業が多いですが、やはり企業業績はいい。10%ほどの増益で、仮に株価が1万7000円とすると、PERは15倍くらいですから、ぜんぜん高くないリーズナブルな水準です。地政学リスク等はありますが、年末に向けてトレンドは期待していいと思います。
(構成=本誌・児玉智浩)

あまたあるバターの中で、カルピスの「特撰バター」(以下カルピスバターと呼ぶ)は、いわばプレミアムバターとして人気が高い。このバターの箱を開けると商品のしおりが入っており、「トップシェフたちの絶賛の声」が載っている。一流料理店のシェフやパティシエにとって、カルピスバターはなくてはならない存在なのだ。その声の一例を挙げると「修業時代から40年以上使っていますが、このバターはとても水分が少なくて伸びがよく、調理の作業効率にも優れた製品。スポンジや焼き菓子に使うととても風味がよく、お客様に大変喜ばれています」。
カルピスバターの大きな特徴は(1)クリーミーなコク(2)口溶けの良さ(3)あっさりした味わいに集約される。
カルピスでは51年前の1963年からバターの販売を開始し、当初はレストランやホテル、洋菓子店向けなど“プロ仕様”のバターとして販売してきた。この逸品が、広く一般家庭向けにも販売されるようになったのは、それから18年が経過した81年のことで、そのためかつて“幻のバター”とも称されていたほど。消費者の手に入らない時期が長かったこともあるが、カルピスバターはそもそもが希少価値だった。
なぜなら、飲料のカルピス30本余に必要な生乳で、やっとカルピスバター1箱分(450グラム)を作ることができるからだ。一般のバターは200グラムのパッケージで300円から400円の価格帯に収まるが、カルピスバター450グラムは税込みで1500円ほどする。そのため、ハレの日などにちょっと美味しい料理やお菓子作りをしたいという女性に高い支持を得ているのだ。ちなみに、450グラム、いわゆる“ポンドバター”として流通しているのは、業務用が主力だったためである。

カルピスバターの魅力を語る川西氏(左)と小峰氏。
カルピスバターと普通のバターとを比べてみると、後者が黄色がかった色合いなのに対し、カルピスバターはかなり白い。この理由について、同社の川西伸幸・乳品事業部長はこう説明する。
「国産バターは、85%ぐらいが北海道産の生乳から生産されているのですが、当社では工場が岡山と群馬にあって、北海道産でない生乳を使っています。北海道の乳牛は青草を食べていることが多く、草に含まれる成分の影響で、やや黄色っぽくなる。
当社では、本州の工場近隣地域の生乳が使われており、本州の乳牛は干し草のほかに、とうもろこし・麦・大豆などをブレンドした飼料を食べていることが多いので、北海道産のバターに比べて白い色をしているわけです」
カルピスバターができるまでの工程をざっと見てみよう。まず、生乳を遠心分離機で脱脂乳と脂肪分に分離する。前者が飲料のカルピスの原料となり、後者のクリームがバターの原料へと分かれる。その後、風味を損なわないよう、高温短時間殺菌がなされ、エージングと言われる熟成の工程に移る。
「そのエージングでは、タンクでじっくり丸1日冷却して寝かせます、そうすることでなめらかさが増すからです。通常のバターですと、量産が前提ですから寝かせる時間はもっと短いでしょう」(乳品事業部乳製品・乳性原料グループリーダーの小峰順一氏)
つまり、あくまで飲料のカルピス製造が主で、バターはその副産物的な位置づけであったため、カルピス製造過程で、クリームのほうはしばらく置いておくことが、結果的にカルピスバターの独特な風味につながっているのだという。また、普通のバターの製造工程では、撹拌してできた脂肪粒を水洗いするところを、バターミルクで洗うことによって、よりミルク感もアップしている。
「カルピスバターは、どちらかと言えば繊細な、素材そのものの味を殺さない、奥ゆかしい風味かなと思っています」(川西氏)
女性には総じて認知度の高いカルピスバターだが、小峰氏によると「調査結果では、老若男女トータルでの認知度はまだ3割ぐらい。百貨店や専門店、食品スーパーなどの販路面で見てもカバー率は7割ぐらいと、まだマーケットでののびしろは大きい」と言う。
それゆえか、「幻のバターに始まって、知る人ぞ知るで認知度も上がってはきましたが、さらにファンを増やすべく、パッケージも一新して、もう少し店頭で目立つようなデザインに変えようという検討を始めたところです。もともと、バターは販売ボリュームの7割ぐらいを業務用で占める世界なので、ややマーケティングがしにくい面はありましたが、時期を見ながら攻勢に打って出たい」と川西氏。

商品バリエーションも広がってきたカルピスバターは女性の支持が抜群だ。
プレミアムバターと称されるジャンルのマーケットサイズは、業務用を除く市販用で年間13億円弱とまだ小さい。他社の製品で言えば、国産なら瓶入りの「小岩井純良バター」、輸入品ならフランスの「エシレバター」が有名だが、13億円の市販市場で、カルピスバターは4億円ほど。
「まずはお試しいただくのが重要で、食べていただければカルピスバターのリピート率は相当、高いものになりますので、今後は買いやすい容量や商品バリエーション(ギフトセットなどでは50グラム入りの小型商品としてソフトタイプや発酵バター、ガーリックやシナモン&シュガーバージョンもある)の拡大も検討課題です。特に発酵バターは、より風味豊かなバターとして人気が出てきている商材ですから」
アサヒが飲料業界で3位に躍り出たのはカルピスを子会社化できた点が大きく、カルピスにとってもシナジーが期待できるだろう。たとえば、アサヒが運営するビール園にカルピスバターを置けば、アピールできる上についで買いも誘える。
また、カルピスバターなら欧米に打って出ても、現地の有力バターと伍することができるかもしれない。ただこの点は、
「国内市場でまだ、消費者の皆様に(カルピスバターを)伝え切った感がありませんので、しばらくは国内中心にやっていきたいと思います」(川西氏)とした上で、小峰氏もこう補足する。
「フランスでも飼料の関係で、比較的色が白いバターです。ただ、本州産のこだわりの生乳ではあっても、カルピスバターのような、繊細で微妙な味わいを海外にも広げていくことができるかどうか。それは将来的な夢です」
2020年の東京五輪の際、ホテルの食事で供されるパンにカルピスバターが添えられれば、訪日外国人にも美味しさを実感してもらえるし、そこから口コミで海外市場に広がっていくこともあるだろう。海外では発酵バターが主力であり、前述したようにカルピスバターには発酵タイプもある。
カルピスバターの真骨頂はコクがあるのにしつこくなく、あっさりしたテイストを両立させている点にあり、そこが日本人に好まれる最大の理由である。
和食が世界的に注目されるいまは、日本で絶賛されるバターを世界に広めるチャンスかもしれない。
(河)
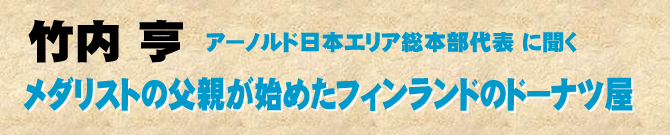

アーノルド日本エリア総本部代表 竹内 亨
たけうち・とおる 1962年生まれ。長野県出身。生家は冠婚葬祭業を営んでおり、東京商科専門学校を卒業後、家業を継ぐ。現在は株式会社大竹社長として、冠婚葬祭業のほか、福祉介護、居酒屋、学習塾など手広く事業を行っている。フィンランドのアーノルド本社と掛け合い、昨年東京・吉祥寺にアーノルドドーナツの1号店を開店した。
―― 竹内さんはフィンランド生まれのドーナツ店、アーノルドの日本エリア総本部の代表ですが、アーノルドを日本に持ってくることができたのは、今年のソチ五輪ジャンプ団体銅メダリストの長男・竹内択選手の存在があったからだそうですね。
竹内 ええ。私は長野県で冠婚葬祭業や居酒屋、学習塾などを経営しています。それがアーノルドを始めることになったのは、択が中学卒業後、2003年にフィンランドの高校に留学したことがきっかけです。
留学を希望したのは、地元の飯山市がジャンプ競技の強化のために、一時招いていたフィンランド人のコーチに教わるためです。択は単身で、日本人の誰もいない町で高校に通いながらジャンプを学ぶ生活を送っていました。私には弱音は吐きませんでしたが、誰も知る人のいない、言葉も通じない異国での暮らしは、さぞつらかったと思います。そんな択の数少ない楽しみが、トレーニングが終わったあと、小遣いで買ったアーノルドのドーナツを食べることだったそうです。
―― アーノルドのファンになったわけですね。
竹内 その話を択から聞いて、これは日本でもビジネスになるのではと考えました。択は、日本のドーナツにはない食感だというし、女房もフィンランドに行った際に食べておいしかったと言っていましたからね。
―― 竹内さんは食べなかったんですか。
竹内 2010年に、私はアーノルド本社を訪ね、日本での展開を直談判しています。でもその時はまだ一度も食べたことがなかった。訪問後、初めて食べたのですが、とてもおいしかった。もしおいしくなかったらどうしようかという気持ちもほんの少しありましたから、正直ほっとしました。
―― 食べる前に、よく自分でやろうと考えましたね。日本ではミスタードーナツが大量に出店しているし、10年頃にはアメリカ生まれのクリスピー・クリーム・ドーナツも進出し、人気となっていました。勝算はあったのですか。
竹内 食べていただければわかりますが、アーノルドの最大の特徴は生地にあります。他のドーナツにはない、モチモチとした食感で、塩が入っていてあまり甘くないため、甘党でない人にも好まれます。さらには卵と牛乳を使っていないので、アレルギーを持つお子さんにも食べさせることができる。だったらやってみる価値はあると考えたのです。加えて、息子が世話になったフィンランドと日本の懸け橋になりたいとの思いも強く持っていました。
―― 日本での展開を打診した時の本社の受け止め方はいかがでしたか。
竹内 フィンランドは大変な親日国です。ですから本当に日本でアーノルドを出店してくれるならうれしいとは言っていましたが、その半面、どこまで本気なのか疑っている感じもありました。
帰国後はメールで交渉を続けたのですが、なかなか真意が伝わらない。向こうが要求するロイヤルティは高すぎる。暗礁に乗り上げてしまいました。そこで本社に対して、我々にはお金がないから招待はできないが、ぜひ日本に来て日本のマーケットの魅力に触れてほしいと訴えたのです。飛行機代や宿泊代は出せないけれど、最大限のもてなしをすると。そうしたところ、11年9月に、社長と副社長が来日。私は成田空港まで迎えに行き、渋谷や青山、六本木などを案内。そのうえで私の知り合いのコンサルタントのオフィスで再交渉に臨みました。でもやはりうまくいかない。
私の要望は、ロイヤルティをもっと下げてほしいことに加え、ドーナツのサイズを日本人用に小さくしたいということなどでした。フィンランドで売っているアーノルドドーナツは、日本で売られているものの1.5倍ほどもあり、日本人には大きすぎる。このダウンサイズを申し入れたのです。ところが本社の回答は、ロイヤルティもサイズ変更もノー。結局、この時もまとまりませんでした。
―― なかなか前に進みませんね。どうやって乗り切ったんですか。それとも相手の言いなりになった?
竹内 彼らが帰ったあと、再びメールやスカイプで交渉を続けましたが、はかばかしくない。ところが、ある日突然、「お前は友達だ。サイズは日本人向けに変えてもかまわない。ロイヤルティも、いくらまでなら払えるのか」と言ってきた。それで交渉が一気に動き始めました。
ひとつには、交渉を重ねることでこちらの本気度が伝わり、信頼関係が構築できたということがあったと思います。そしておそらくは、択の活躍のおかげもあったのでしょう。
フィンランドはジャンプ王国です。それだけにジャンプ選手に対しては最大限の敬意を示します。択は2010年のバンクーバー五輪に出場したほか、ワールドカップでも表彰台に上がるなど活躍していて、本社の人たちも択のファンになってくれたようです。それが交渉で有利に働いたのではないかと思っています。
―― 息子さまさまですね。そこからはとんとん拍子ですか。
竹内 12年4月にフィンランドに行き、日本における事業契約に調印しました。この時には社員3人も連れて行き、ドーナツ製造の研修も受けています。そして1年後の13年5月、東京・吉祥寺に1号店をオープンして今日にいたります。
―― なぜ、吉祥寺だったのですか。
竹内 都心に近いところでは家賃が高すぎる。その点、吉祥寺は、都心ほど高くはないし、訪れる人も多い。公園があって池があるところがなんとなくフィンランドに似ているし、北欧関連のショップも多くある。しかも住んでいる人、商売をしている人も優しいし人情味がある。それで吉祥寺に決めました。
―― サイズを変更したのはわかったのですが、それ以外はフィンランドに出しているのと一緒ですか。
竹内 変えています。フィンランドのアーノルドは、生地は甘くないものの、その上に乗っているジャムなどのグレージングはとても甘い。そこで日本ではたとえばリンゴジャムに長野のリンゴを使うなど、あまり甘くない素材を使っています。またフィンランドはメニューが1年中ほとんど同じですが、できるだけ季節ごとに違う商品を提供したいと考えています。
―― 1年間やってみて手応えはどうですか。そして今後の展開は。
竹内 リピーターも増えてきましたし、週末にネットを見たと言って遠くからおいでになる方もいます。子供がアレルギーでいままでドーナツは諦めていたというお客さんにも喜んでいただいています。これまでのところ、だいたい予定どおりに進んでいるのではないでしょうか。
いまは吉祥寺のお店と、百貨店などの催事に出店し、より多くの人たちに味わってもらおうとしてます。いずれはFC展開や通販などで、できるだけ多くの方にアーノルドドーナツを味わってほしい。
択は4年後の平昌冬季五輪を目指すと言っています。その時までには、日本の誰もが知るドーナツ店になっていたいですね。