




ファストフードの雄として外食業界に君臨していた日本マクドナルド。新商品を発売すれば常に話題になった。ところが、最近、マクドナルドの明るい話を聞かない。注目を集めるのは原田泳幸氏の退任や、既存店売上高の大幅な低下など、ネガティブなものばかり。つい最近まで勝ち組企業の最右翼に位置していたマクドナルドは、なぜあっという間に転落してしまったのか。
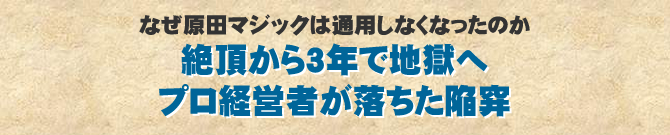
日本マクドナルドの苦戦が続いている。日本マクドナルドホールディングス(HD)の前12月決算によると、売上高は前年比11.6%減の2604億円、営業利益にいたっては、同53.5%減の115億円だった。減益は2年連続だが、2012年12月期の減益幅は2.2%に過ぎなかった。それが前期に大きく落ち込むことになった。
昨年は、すべての施策に対して消費者がノーを突きつけたような結果となった。はっきり現れたのが既存店売上高で、前期はその前年より6.2%減っている。今期に入っても状況は改善しておらず、1月こそ既存店売上高は前年比3.4%増だったが、2月は8.7%減だった。
ほんの3年前まで、日本マクドナルドが打つ手はすべて大当たりした。
まず07年にプレミアムローストコーヒーの発売を開始。それまでのコーヒーよりワンランク上の味が受け入れられ、大ヒットした。毎朝、マクドナルドでコーヒーを買い求める客が列をなしたのも記憶に新しい。
パティを4枚入れたメガマック、いまでは定番メニューとなったクォーターパウンダー、さらにはテキサスバーガーのビッグアメリカシリーズなど、高価格商品を発売するや大人気となった。
また、09年のワールドベースボールクラシック(WBC)時には、クォータパウンダーにWBC出場選手のクリアファイルをつけたところ、クリアファイル目当てでマクドナルドに通う客が続出した。

いつの間にか原田社長の打つ手が客の心に届かなくなった。
HD会長の原田泳幸氏が日本マクドナルド社長に就任したのは2004年。前職がアップル日本法人の社長だったことから、「マックからマックへ」と大きな話題となった。
お菓子メーカー(RJRナビスコ)からコンピュータメーカー(IBM)に転じ、IBMを復活させたルイス・ガースナー氏のように、欧米では異業種間のトップの異動は珍しいことではないが、日本では極めて稀なこと。1つの会社、1つの業種で仕事を極め、トップに立つ道こそ、経営者の王道であり、それはいまも変わらない。
ところが原田氏は「プロ経営者」と名乗り、異業種へと乗り込んだ。
当時のマクドナルドは創業者・藤田田が突き進んだ低価格路線の破綻により、2期連続赤字に苦しんでいた。2期連続減益のいまよりはるかに状況は深刻だ。
原田氏は就任初年度、いきなり結果を出す。03年度73億円の最終赤字だったものが、04年度には36億円の黒字を計上したのだ。その後2年間は、狂牛病の影響で売り上げは伸び悩むが、06年度からは再浮上、7年連続既存店売上高プラスという金字塔を打ち立てた。その前の7年間、マクドナルドの既存店売上高がマイナスだったことを考えると、これは奇跡と言っていい。
原田氏の考え方はきわめてシンプルだ。
「売り上げは客数×客単価。客数は来店頻度と顧客数で決まるから、これを上げるためにどうするか。そして客単価をどうやって上げるか」
それを突き詰めた結果が、100円マックによって来店客数を増やしたうえで、前述のような高価格商品を導入、客単価をアップさせるという戦略だった。
マクドナルドの業績を立て直したことで、原田氏の評価は急上昇した。その前のアップル時代でも再建に成功していたため、再建請負人としての名を欲しいままにしたのだ。11年には朝日新聞出版から『勝ち続ける経営』という本まで出している。まさにプロ経営者としての絶頂にあった。
しかしそれが長くは続かなかったことは冒頭に記したとおりである。3年前の東日本大震災に原因を求めることもできるかもしれないし、コンビニエンスストアの進化が影響したかもしれない。それは確かにそのとおりなのだろうが、それよりも、原田氏の日本マクドナルド社長としての賞味期限が切れたと考えたほうがわかりやすい。
どんなに優れた経営者にも、賞味期限は存在する。どんなにすぐれたビジネスモデルを構築しても、やがては陳腐化するし環境も変わる。それに合わせて企業も変わっていかなければならないが、残念ながら個人の能力には限界がある。特に年齢を重ねれば重ねるほど柔軟性はなくなり、変化対応はむずかしくなる。
それに気づかず、晩節を汚した経営者がいかに多いことか。
前述のIBMのガースナー氏にしても、その在任期間は9年でしかない。裏を返せば、9年で退任したからこそ、いまでもガースナー氏は名経営者として名を残していると言っていい。

最近では伸び悩んでいる日産自動車のゴーン社長。
日本企業におけるもっとも有名なプロ経営者といえば、カルロス・ゴーン・日産自動車社長にとどめをさす。
タイヤメーカーのミシュランで実績を残し、ルノーの上級副社長に就いていたゴーン氏は、1999年、経営不振によりルノーの子会社となった日産の社長に就任した。
ゴーン氏はすぐに日産リバイバルプラン(NRP)策定、外様社長の強みをいかして、日産の旧弊やしがらみを片っぱしから切っていった。それによって鉄鋼業界の再編が起きるほど大胆なものだった。
その結果、日産は大復活を遂げ、再建を果たしたゴーン氏の名声は高まった。その勢いを駆ってゴーン氏は、06年、親会社ルノーのトップにまで昇りつめた。ゴーン神話の完成である。
しかし最近の日産やルノーの状況は、ゴーン神話に陰りが出ていることを裏づける。
昨年11月1日、ゴーン氏は会見を開き、COOの志賀俊之氏が退任することを発表した。日産は14年3月期中間決算で、7.8%の営業減益を計上した。トヨタ自動車やホンダなど、自動車メーカーの多くが円安の恩恵を受け利益を伸ばしているのに、日産だけが蚊帳の外だった。志賀氏は、その詰め腹を切らされるかたちで退任した。
ゴーン氏はNRP、それに続く「日産180」で、日本中に「コミットメント経営」という言葉を流行らせた。高い目標を掲げ、目標が達成できない場合、進退を含めた責任を取る、というものだ。
コミットメント経営は、最初は大きな成果を上げた。それまでの日産は、目標未達に対してトップが責任を取ることのない会社だった。それが社内の規律を緩めていた。ゴーン氏はコミットメントにより不退転の決意を示すことで、社員の士気を高めることに成功した。
しかしそれも長くは続かなかった。コミットメント経営を続けることで、社員は次第に疲弊し、やがてゴーン氏は、自らコミットメント経営との決別を宣言することになる。
それでも、経営破綻寸前だった日産を、ルノーと合わせて世界トップ5の自動車会社にまで育て上げたゴーン氏の手腕は評価してもしきれない。しかし、日産の社長に就任してから、今年で15年がたつ。スズキの鈴木修氏を除けば、自動車業界でもっとも長い政権になった。赴任した当初のような、トップと社員の緊張感を維持することはもはやむずかしい。志賀COOの解任は、その緊張関係をもう一度つくろうという荒療治なのかもしれないが、もしうまくいかなかった場合、ゴーン氏の進退にもかかわってくる。ゴーン氏の賞味期限が切れたかどうか、まもなくはっきりする。

スマホ時代を読み違えた任天堂の岩田社長。
もう1人、賞味期限が切れかかっているのが、任天堂の岩田聡社長だ。
岩田氏もまた、任天堂プロパーではない。HAL研究所というゲーム開発会社のプログラマーだったが、同社の経営が悪化したために社長に就任。見事再建を果たした。
その手腕を、任天堂中興の祖の山内溥が見込んでスカウト、02年に43歳の若さで社長に就任した。
デビューは華々しかった。就任2年後の04年に発売した携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」は空前の大ヒット。続いて据え置き型の「Wii」も全世界でブームを起こした。
岩田社長の戦略は明確だった。
1983年に発売した「ファミリーコンピュータ」以降、新しいゲーム機が出るたびに高機能化し、それに伴い、ゲーム上級者以外には手が出ないものになっていた。そこで岩田氏は、「ゲームを大衆の手に取り戻す」とばかりに、老若男女誰でも楽しめるゲームづくりを目指した。それがDSの2つの画面であり、Wiiの振り回すことのできるコントローラーだった。その狙いはずばりと当たった。
しかしそれによって拡大したライトゲーマーは、携帯電話ゲームやスマホゲームが普及すると、あっという間に移っていった。岩田社長はいまでも、スマホによってユーザーを奪われたわけではないと強弁しているが、それが事実でないことは、誰の目にも明らかだ。
その結果、09年3月に1兆8368億円あった売上高は、前3月期6354億円と3分の1にまで落ち込んだ。08年度5000億円を超えていた営業利益も、3年後には赤字に転落した。株価も、07年には7万3200円の高値をつけたが、ここ2年ほど1万円前後をうろついている。
その逆に、徹底して高機能を追求し続けたソニーのプレイステーションは、ヘビーゲーマーに支えられ、収益を伸ばしている。いまや完全にゲーム業界におけるポジションは逆転した。岩田社長は成功体験が大きかったこともあり、時代の変化を捉えることができなかった。スマホが本格的に普及し始めた10年までが、岩田社長の賞味期限だった。
日本マクドナルドの原田社長に話を戻せば、減収減益とはいえ、利益の出ている状況で、サラ・カサノバ氏に椅子を譲ったのは賢明な判断だったかもしれない。原田氏はマクドナルドの業績がいい時から「次のステージがある」といい続けてきたし、社長交代発表後に応じた日経新聞のインタビューでも、次のキャリアの可能性を語っている。傷を負わずに社長交代にこぎつけられたのは本人にとっても幸いだった。
原田氏が日本マクドナルド社長に就任した当時と違って、日本企業でも他社、他業界から社長を招くケースが増えている。最近でも武田薬品が外国人社長をスカウト、資生堂も日本コカ・コーラ元社長を新社長に据えることを発表している。プロ経営者の時代がやってきたと言えるかもしれない。
だからこそ賞味期限についてもっと真剣に考える必要があるだろう。社長としてスカウトされるぐらいだから、優秀な人材であることは間違いない。新天地でのプランももっているはずだ。しかし、それによって短期的に利益を上げることができたとしても、そうそう長続きするものではない。日本マクドナルドの絶頂からの転落は、そのことを雄弁に物語っている。
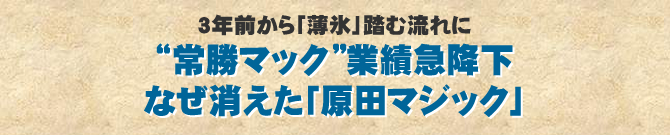
まずは下の表をご覧いただこう。表にある4社のうち、日本マクドナルドホールディングス(以下マクドナルド)と日本ケンタッキー・フライド・チキン(以下KFC)の業績が急降下していることが見て取れる。
次いで3社目のモスフードサービス(以下モスフード)に目を転じると、絶好調とは言えないまでも、かなり善戦、健闘した数字だ。そしてスターバックスコーヒージャパン(以下スターバックス)。昨年は、100円の「セブンカフェ」に代表される、コンビニの淹れたてコーヒーが席巻した年であり、普通に考えれば、スターバックスはマクドナルド、KFC、モスフード以上にコンビニコーヒーの影響が出そうなもの。
だが、実際には表の通りでスターバックスでは過去最高益を予想し、経常利益、純利益ではマクドナルドを抜いてしまう。スターバックスの店舗数が1000店強なのに対し、マクドナルドは順次減らしてきたとはいえ3100店と、なお3倍の規模があるだけに、マクドナルドとしては由々しき事態だ。
もちろん、同社は赤字に転落したわけではない。原田泳幸氏(14年3月末の株主総会後に代表権のない会長に就任予定)がアップル日本法人社長からマクドナルドに転じたのは2004年だが、その前の02年、03年は2期連続の最終赤字に喘いでいた。だからか、いまでもマクドナルドの古参幹部はこう振り返る。

10年間、日本マクドナルドを率いた原田泳幸氏。
「当時は3900店で全店売上高が4300億円。直近は3100店で5000億円です。つまり1店当たりの売上高は劇的に改善しているわけで、昔とは違います。赤字の頃は、内部の人間では為す術がなくなっていた。とはいえ上場会社だし、いつまでも赤字というわけにはいかない。それまでの一切を変える改革のリーダーシップが必要となり、原田の招聘となったわけです」
原田氏が着任するまで、マクドナルドの既存店売上高は7年連続でマイナスだった。それが、04年以降11年まで8期連続増収という離れ業を達成したことで、同氏自身、「自分は雇われ社長としては世界でも有数」との自負を公言した。
確かに、どん底から立て直しても数年の増収で止まっていたら、原田氏が特に注目されはしなかったかもしれない。それだけに、この2、3年なぜ“原田マジック”が通用しなくなったのかが気になる。前出のマクドナルド幹部の説明はこうだ。
「まず、東日本大震災後、消費者が夜間に出歩くことを控えるようになり、弁当や総菜を買って帰る中食や、家庭で調理する内食へのシフトが顕著になりました。特に中食にシフトした消費者を取り切れておらず、厳しさがあります。
同時に、我々も24時間営業店を順次、縮小しています。3100店のうち24時間営業店は1800店ぐらいありますが、さらに300店ほど減らしていく予定です。
当社の強みだった、テイクアウトでも客席での食事でもお待たせしない利便性、おもてなし、100円コーヒー、スマホクーポンなどのウェブマーケティングと、いろいろなものがどんどん(同業にも異業種にも)追随され、優位性のあったギャップが埋められてきてしまった」
もちろん、マクドナルドも手をこまねいていたわけではない。たとえば、同社が主力業態と位置づけてきたドライブスルー型店舗。通常の駅前立地店舗は、瞬間的な集客力は高いが、持続性には波がある。その点、ドライブスルー型店舗は一度認知されると、周辺の商圏に左右されない集客が見込めるという。そのため、同タイプの店は11年末時点で1330店だったのが12年末は1459店、13年末は1493店と、全店の半分弱までに迫ってきている。
その、ドライブスルー型シフトを可能にしたのが、原田氏が急速に進めてきた直営店からFC(フランチャイズ)店への切り替えだった。かつては直営店比率が7割近かったが、その比率は現在、そっくり逆転している。平均して1人のFCオーナーが十数店、場合によっては100店以上を経営し、マクドナルド本体は身軽になった分、コンピュータシステムやドライブスルー型店への投資などに振り向けていった。
効率性を極める合理主義者の原田氏だけに、時にはFC店オーナーとは摩擦や軋轢もあったかもしれないが、それはFCビジネスを展開する企業にとって宿命でもある。特に、店舗数が桁違いに多いコンビニの場合はなおさらだ。FC運営の巧拙の差は各チェーンであるかもしれないが、直営からFCへのシフトを急いだこととマクドナルドの業績降下は、それほど強い要因とも思えない。
もう1つ、中途入社した幹部の流出なども業績不振の遠因と指摘する声がある。だが、これもドライな外資系企業で人の出入りが激しいのは普通のこと。原田氏が強いリーダーシップを発揮して求心力を高めれば高めるほど、一部の幹部にとっては遠心力となりうるだろう。
原田氏は過去、牛丼チェーンの値下げ合戦を引き合いに出し、「体力勝負の価格競争に意味なし」と語ってきた。一言で言えば、割安価格でまず客数を上げ、そこから付加価値商品に誘導していくというのが、いわば原田氏の成功方程式だった。もちろん、そこには季節要因から時間帯の要因まできめ細かいマーケティングの仮説があり、タイミングよくセットメニューやイベント、期間限定キャンペーンなどを絡ませてきた。
「従来の外食業界は、まず商品ありきで、ブランド力をライフスタイルイメージにしていく力が弱い」
原田氏はそうも考えてきた。店舗の内外装デザインのモダン化などもその1つだが、そのスマートさが、外部からは逆に危ういと映ることもある。同じカリスマ型でも、義理人情に厚かった藤田田時代のマクドナルドを知る元幹部は以前、こう語っていたものだ。
「マーケティング力に長けた原田さんだから、CMや商品訴求の仕方はうまくなった。店舗デザインもカッコよくなったし、一言で言えばアカ抜けた感じです。藤田さんの頃は、店の看板も英語表記でなくカタカナでしたからね。
ただ、原田さんは米国本社の言う通りのことをしている印象が否めず、日本のマクドナルドとしてのオリジナリティやクリエイティビティがあまり感じられません。昔は、店舗内のマシンも日本で独自仕様のものを開発していたんですけどね」
元幹部の言うことももっともだが、2期連続赤字に陥って原田氏が招聘された時点で、米国のマクドナルド方式が日本でも徹底されていくのは必然だった。
振り返ってみると、連続増収記録の最後となった11年は、すでに薄氷を踏む流れだった。同年11月の第2週時点までの売り上げ数字で推移すると、12月にどんなに頑張っても8年連続増収に赤信号が灯ることが確実だったからだ。原田氏はその数字を見た後、
「たとえ0.1%でも(年間既存店売上高の)プラスはプラス、マイナスはマイナス。後者に終わった場合、どれだけ世間の認識が違ってくるか。その怖さを知れ」と、社内に檄を飛ばしている。
同時に、特に東日本大震災以降、原田氏は「ライバルはコンビニ」と公言するようになった。コンビニとて業績格差が鮮明になり、勝ち組と言えるのは、セブン‐イレブン・ジャパン、ローソン、ファミリーマートの上位3社だが、震災以降、大手コンビニは女性やシニアの取り込みにも成功し、この3社はいまなお、最高益を更新し続けている。
前述したように、昨年はコンビニコーヒーが席巻した上、プレミアムチキンなどの投入が、マクドナルドやKFCに少なからず影響を与えたのは確実。コンビニの商品力が目に見えて向上していることが1つ。その上、マクドナルドが約3100店、KFCが約1200店で計4300店、対するコンビニ3社の合計店舗数は、すでに3万8000店近い。メッシュ細かく消費者を捉まえるという点では勝負にならない。コンビニは店内調理やイートイン店舗も増える一方だし、扱う商材も多彩で、ついで買いも誘いやすい。
原田氏も12年2月時の本誌の取材で「コンビニはいろいろな来店動機を創造しながらマーケットを作っているわけで、素晴らしいし見習わなくてはいけない」と脱帽していた。
ライバルと見立てたコンビニと勝負するには、やはりまずは商品力だが、その12年のハイライトは、夏に投入した「世界のご当地ハンバーガー」だった。フランスの「ル・グラン」、インドの「ゴールドマサラ」、オーストラリアの「オージーデリ」がそれで、マクドナルドではかなり大がかりな販促キャンペーンも行っている。
既存店売上高は同年4月以降マイナスが続いており、原田氏としてもこのご当地ハンバーガーに寄せる期待は大きかった。ところが、同氏が就任して以降、これだけハズレた商品も珍しいと思えるほど、消費者に受け入れられなかった。結果、既存店売上高をプラスに転じさせることができずに秋に突入、ついに連続増収記録がストップすることを覚悟せざる得なくなる。
このため、例年なら通期決算発表の2月に開示するその年の戦略を、12年11月1日に行った第3四半期決算発表で同時に公表した。当時の会見で原田氏はこう語っている。
「事業環境が変わり、すでに13年の戦略も決めていることから、このタイミングでの発表となりました。今年は世界のご当地バーガーを投入しましたが、これまでのようには伸びませんでした。率直に言えば、予見の精度が狂ったのです」
同氏は着任時からずっと、地域別、店舗別、曜日別、時間帯別まで、細かく各店舗の状況分析をし、次の一手を探ってきた。その“原田コンピュータ”の精度、確度が初めてずれてしまったことになる。

それ以降も原田氏の誤算は続く。やみくもな期間ないし季節限定メニューの投入はコストを増大させるだけとの反省に立ち、13年年初は静かな商戦でスタートしている。ところが、これも裏目に出た。前年の政権交代により、アベノミクス効果で日経平均株価がグングン上昇、資産効果もあって、消費者が財布の紐を少し緩めるようになった。
年初に特段、キャンペーンを展開しなかったマクドナルドは、13年1月の既存店売上高が前年同月比でマイナス17%まで拡大、続く2月もマイナス12%を記録した。この大幅な落ち込みを挽回するのは容易ではない。景気回復基調ムードの中で、この数字はいかにも手痛かった。
「お客さんは、やはり新しい価値やサプライズを求めています。キャンペーンの抑制と新商品投入の、バランスを取ることが大事だとわかったので、そこから猛烈に企画を立て始めました」(原田氏)
6月、サッカーの本田圭佑選手をイメージキャラクターに起用した、アグレッシブな印象の「BITE!」キャンペーンを打ち、原田氏自身も企画に深く関わった。「クォーターパウンダー ハバネロトマト/BLT」の2商品がそれで、特に「ハバネロトマト」は久々にスマッシュヒットとなる。
ここから、さらに話題作りを切らさない。7月に入ると、今度は期間限定で3種類の1000円バーガー、「クォーターパウンダー ジュエリー」を発表、この商品は特製の“化粧箱入り”というおまけもついた。ただし、販売個数には限りがあり、「あくまで話題作りで、勢いを見せるための仕掛け」(同)
ここで消費者の来店動機を盛り上げ、集客を増やし、売上高も上げる作戦だ。
足元では、13年5月、6月とわずかながらも既存店売上高がプラスに転じていただけに、期待も高まった。ただし、夏場に稼ぐはずなのは派手な一連のキャンペーン商品でなく、フローズンドリンクの新商品、「マックフロート」だった。
7月、8月の来店客数はそれぞれマイナス9.8%、9.3%で、既存店売上高も7月から再びマイナスに。その7月時点でインタビューした際、原田氏は「今回の『マックフロート』で客数を増やさないといけないが、まだ予定よりも客数が下回っているのが正直なところ」と、やや苦悩の色を見せていた。
また、景気回復過程で、消費者が総じてファストフードから少し離れているのではとの問いにも「そういうデータはないですね。アベノミクス効果で外食産業の消費構造がそんなに変わったとは思えません」としていた。
が、翌8月の中間決算発表では「ボーナスが増えたからマックに行く回数を増やすとは考えにくく、グレードを上げて、デパートのレストラン、さらに上のホテルのレストランにシフトしたような現象が起こっているかもしれない」と語り、発言の一貫性も欠いている。

2013年8月末、サラ・カサノバ氏(右)にバトンタッチ。
そして8月27日、原田氏はサラ・カサノバ氏を帯同して記者会見し、事業会社の社長を譲ることになる。この時点では「私は退任ではなく、引き続きリーダーシップを発揮し、(カサノバ氏と)二人三脚経営になる」として、持ち株会社社長にとどまる意義を強調していたが、14年3月25日の株主総会をもって持ち株会社トップも譲ることは、米国のマクドナルド本社首脳との話し合いの中で規定路線だったのだろう。
その後、原田氏は日本経済新聞のインタビューで、
「経営者として1年も“浪人”する気はない。同業他社に行くことは道徳的に許されないだろう」と語っている。まだ、マクドナルドのトップにある人物としては軽率の感が拭えないが、逆に言えば、10年社長を務めてもまだ燃え尽きることのないファイターぶりと、赤字から8期連続増収をやり遂げた、“プロ経営者”としての矜持を示したかったのかもしれない。
(本誌編集委員・河野圭祐)
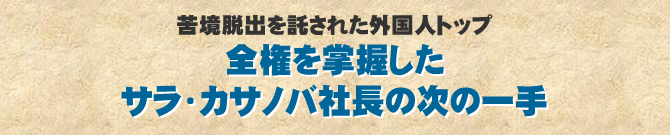
日本マクドナルドで社長交代会見が行われたのは、昨年8月27日のこと。同社は12月期決算なので、半期決算の発表を終えた矢先のことだった。原田泳幸社長に代わってトップに就任したのがサラ・カサノバ氏で、当時、64歳だった原田氏より16歳若返る人事となった。カサノバ氏はカナダ出身で、カナダのマックマスター大学大学院の経営修士課程を修了、マクドナルドカナダに1991年に入社している。
以後、マクドナルドロシアなどでマーケティングを担い、実績を積んできた。日本では、原田氏がマクドナルドに招へいされた2004年から5年間、執行役員マーケティング本部長兼事業推進本部長として原田氏の〝右腕〟を務めている。在職中、「えびフィレオ」「メガマック」「クォーターパウンダー」などのヒット商品を送り出し、昨夏に日本にカムバックするまでは、マレーシア・シンガポールエリアの責任者だった。
前述した91年以降から昨年までの22年間、カサノバ氏の「籍」は一貫してマクドナルドカナダだったが昨年、日本マクドナルド社長に着任するにあたっては、そのマクドナルドカナダを“退職”しており、いわば退路を断っての登板である。交代会見時、カサノバ氏は「これから全国の店舗を精力的に回りたい」として、その後、メディアに登場することはほとんどなくなった。
フランチャイズ(FC)オーナーとのコミュニケーションを重ね、これまでの状況を分析し、再びメディアの前に姿を現したのが昨年12月25日のクリスマス。東京都内にある、テストキッチンを備えたマクドナルドの総合研究施設において、年明けに投入する新商品ラインナップ紹介と試食会を行ったのがそれだ。

サラ・カサノバ社長は「復活」へのキーワード(上記)を掲げたが…。
陽気で明るいカサノバ氏はサービス精神も旺盛で、会見前、マクドナルドのクルーに交じって、トレイに載せた試食品を自らサーブするパフォーマンスも見せている。その後、同氏が発表したのが「アメリカンヴィンテージシリーズ」で、「米国の伝統的な良さを日本のお客様にお伝えするのは、マクドナルドでしかできないこと」と語り、日本では初お目見えのサイドメニュー「クラシックフライチーズ」やチキンパティ商品の展開など、目新しさも強調していた。
カサノバ氏にしてみれば、年初から“ロケットスタート”を切りたいという思いだっただろうが、会場内では、新商品に対して感嘆の声はそれほど聞かれなかった。もちろん、味覚や好き嫌いは性別や年齢も含めて個人差がある。とりあえずは、1月の既存店売上高や来店客数の結果を見るほかない。
そして2月6日、上場している日本マクドナルドホールディングスの通期決算発表が行われた。13年12月期の数字については、8月末に交代したのだからカサノバ氏の責任範囲は限定的。同氏の助走期間も考慮すれば、真価が問われるのは年明けからの数字である。だが、決算発表時点では1月の数字はまだ未集計とのことで、カサノバ氏の方針や考え方を披露するにとどまった。
前述のアメリカンヴィンテージシリーズに手応えを感じているとしたカサノバ氏は続けて、「マクドナルドのビジネスの中心はキッズとファミリー。なので、当社の店内で子供がエネルギーを発散できるキッズ向けプレイランド設備を増やしたいし、デリバリー(宅配)にも力を入れていきたい」と語った。
だが、「前体制とどこが変わったのか見えにくい」と問われ、「戦略の転換ではなく、改めてマクドナルドの強みを強化したい」と返すのみで、新商品同様、戦略にも目新しさに欠ける印象は否めなかった。
そして数日後、1月の数字が明らかになる。
1月の実績は前年同月比で、既存店売上高が3.4%伸び、客単価も9.2%上がったものの、来店客数は5.3%減少した。この数字が物語るのは、マクドナルドのコアなファンはある程度捉まえることに成功しているが、浮動票に近い客層の足が遠のいていることを窺わせる。
さらに、去る3月10日に発表となった2月の実績。ここでも客単価は新商品投入効果が持続して5.0%増だったが、来店客数は下げ幅が13.1%まで拡大し、既存店売上高も8.7%の大幅減少となった。もちろん、2月は2週連続で週末にかけて記録的な大雪に見舞われ、その点は割り引いて見なければいけない。ただ同じ外食企業でも、大手牛丼チェーンは鍋メニューで2月の増収を確保。こちらは大雪による厳しい寒さがプラスに働いた形だが、そうした天候要因を除いても、マクドナルドはいまだ“底這い”状態から脱していないといっていい。
決算発表時、カサノバ氏は「もはや規模拡大は諦めたのか」と問われた際、「ゴールはビジネスを拡大していくこと。いまは消費者とのコンタクトポイントをどう増やすかに注力しており、それは当然、店舗数やデリバリーにも関係してくる」と回答していた。だが、マクドナルドの宅配ビジネスは想定していたよりも進展が遅れている。
また、ターゲット層として明確に掲げた「キッズとファミリー」も世界のマクドナルドを俯瞰すれば最大公約数の客層なのかもしれないが、日本は高齢社会という点で世界の先頭を走っており、今後もシニア層以上のボリュームが激増していく。
さらに、老いも若きも単身世帯はこの先、ますます増えていく見込みで、カサノバ氏が照準とする主力顧客層とはズレを感じてしまう。既存のファミリーを集客する点も、一流レストランからファミリーレストランまで激しい顧客争奪で知恵の絞り合いになっており、マクドナルドはよほど強烈な来店動機を示せない限り、家族単位で客を呼び込むのはなかなか厳しい。むしろ、全体的な趨勢から言えば“個食”へのアプローチ強化のほうが、業績回復の早道になる可能性がある。
そして、最も肝心なのが商品力。前述のアメリカンヴィンテージシリーズは、本拠地の米国のみならず、世界各国で一定のファンはつかめるのだろう。
ただ、平均年齢がぐんぐん上がっている日本人の平均像に照らせば、カサノバ氏がとりわけ好評だとした、クラシックフライチーズ(マックフライポテトに温めたチーズソースと粒子状にしたベーコンフレーバートッピング)は、ややヘビーなテイストかもしれない。
前述したように、カサノバ氏の“緒戦”は黒星スタートとなったが、2月19日には持ち株会社の日本マクドナルドHD社長も同氏が兼務することを発表しただけに、本当の正念場は3月末の株主総会後、つまり第2四半期以降にやってくる。
マクドナルド社内ではまだ、カサノバ氏がトップダウン型、ボトムアップ型のどちらの経営者なのか測りかねているようだが、全権を掌握した後、果たしてどんな打ち手を見せるのか――。
(河)
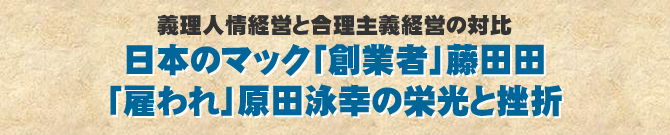
日本マクドナルドには2人のカリスマがいる。初代カリスマは、創業者として30年以上トップに君臨し、カリスマ経営者として畏怖された藤田田だ。2人目が先日、社長を退任することを発表した原田泳幸。米国マクドナルド本社の、いわば「代理人」として、藤田が創った日本マクドナルドを改革し、米国マクドナルド本社の“一支社”に組み込んできた。
藤田が独創性に優れた創業型経営者なら、原田は米国本社の戦略を踏襲する番頭・官僚型タイプの経営者であり、経営者としての資質は全く異なる。
晩年の藤田は業績悪化に苦しんだが、それを救ったのが原田だった。しかしここにきて原田もまた、業績悪化に苦しんだ。果たして歴史は繰り返したのか――。
(文中敬称略)
☆……☆……☆

日本マクドナルドの経営は、原田泳幸氏(左)からサラ・カサノバ氏(右)に引き継がれたが……。
日本マクドナルドホールディングス(以下HD)は今年2月、サラ・カサノバ(48)が社長兼CEOに就く人事を発表した。原田泳幸(65)はHDと日本マクドナルド(以下マクドナルド)の会長にとどまるが代表権は返上。
原田は2004年5月に社長に就任すると、米国本社の管理下で米国本社の戦略、命令を忠実に実行した。それによって8年連続で既存店売上高の増収を実現し、「原田マジック」と言われたものの、12年13年と、一転して2期連続の大幅な営業減益に陥り、結果、社長退任に追い込まれた。
原田は当面、カサノバをフォローして、カサノバが自由に経営できる環境を整えるために動くと思われるが、その後はマクドナルドを去ることになるだろう。だが、社長が原田からカサノバに交代したからといって、マクドナルドが本当に復活するかどうかは未知数だ。
カサノバは、「商品メニューの見直し」「家族客重視の原点回帰」「宅配事業の拡大」などの施策に力を入れることで、再成長を目指す方針だ。しかし、それだけでマクドナルドが復調するとはとても思えない。
原田もカサノバも、そして米国マクドナルド本社も、日本市場の構造的な変化を本当に理解しているようには見えないからだ。
原田時代、マクドナルドはスクラップ&ビルドを進め、中途半端な規模の店舗をフランチャィズ(FC)化して本体と切り離し、経営効率を高めた。
その一方、超一等立地を取ることに全力を傾けた。超一等立地に大型店を構え、1店舗の売上高の極大化を図ることで収益を上げてきたのだ。ところが、全国3000店舗を超すマクドナルドには、出店する超一等立地が不足し、新たな店舗展開が困難になってきている。
このような立地不足に加え、ハンバーガーの消費構造が大きく変わってきている。ハンバーガービジネスを支えてきた団塊の世代がリタイアし、少子高齢化、人口減少社会へ突入する中で、マクドナルドを牽引する主要顧客が見当たらなくなってきたのだ。
その上、競争環境も大きく変わってきた。コーヒーチェーンのスターバックスが台頭、マクドナルドの顧客流出が常態化した。一方、マクドナルドの商品価格が割高になったため、顧客がモスフードなどのライバルチェーン店に行く頻度が増し、底流で“マクドナルド離れ”現象が広まっている。
もう1つ、コンビニエンスストアの隆盛にも影響を受けているが、そのコンビニも、全国で5万店が限度などと言われていたものの、ここ1~2年で6万店に迫る勢いで増えている。
こうした激戦下でコンビニが生き残るためには、マクドナルドやケンタッキー・フライド・チキン(以下KFC)などのファストフードや外食チェーンから客を奪うよりほかない。まさに業態を超えたサバイバルゲームである。
マクドナルド創業者の藤田田は、1971年に米国マクドナルド本社の創業者レイ・クロック(故人)と「日本マクドナルド」を設立した。この際、藤田は交渉を有利に進め、株式は50対50の折半出資とし、米国本社からアドバイスは受けるが命令は拒む、という方針で臨んだ。

日本マクドナルドの経営は、原田泳幸氏(左)からサラ・カサノバ氏(右)に引き継がれたが……。
その結果、藤田が経営権・人事権を握り、食材の輸入調達などでは自分で設立した「藤田商店」を使うという、従来では考えられないほどの好条件を勝ち取った。こうして71年7月、東京・銀座三越の一角に第1号店が誕生した。
筆者は藤田とはいささか縁がある。「週刊サンケイ」(廃刊)の記者を1年ほどやってフリーになった80年代後半、学研が出していたビジネス雑誌「活性」(月刊。その後廃刊)という雑誌で、藤田が在籍した旧制松江高校の名簿を元に、藤田の同級生に電話して、藤田の青春時代を取材した。
高校から大学時代にかけて藤田が何をしていたのか6~7人に聞いて回り、彼らの写真入りでコメントを載せたのだが、藤田はこの「活性」を大切に持っていた。
その縁で、社史「日本マクドナルド20年のあゆみ」を出す時、私が巻末の「藤田田伝」を書くことになった。藤田からの依頼だった。
91年の春頃、藤田と新宿住友ビルで会った。
藤田はその時、自分が起業家になるいきさつなどを2時間ほど話した。筆者はその内容を、「凡眼には見えない、心眼を開け、好機は常に眼前にあり 藤田田物語」として、400字40枚ほどの文章にまとめた。
藤田は父親の遺志もあって東大法学部に進学、外交官の道を目指すが、大学時代にGHQ(連合国軍最高司令部)の通訳のアルバイトをして、高額のアルバイト料をもらっているうちに人生観が変わった。
一方、兵隊の中で金貸しをして羽振りの良いユダヤ人と知り合い、ユダヤ人の人生観や金儲けに開眼した。藤田はこの時の体験を、72年に『ユダヤの商法―世界経済を動かす』という本にまとめた。これが大ベストセラーとなり、「東大出の異色のアントレプレナー(起業家)」「銀座のユダヤ商人」などと呼ばれ、一躍著名人になった。
藤田が、その時筆者に一番伝えたかったのは、東大法学部4年生の50年から、旧住友銀行(現・三井住友銀行)新橋支店で、月々5万円の定期預金を始めたことだ。
当時の5万円は大金で、日雇い労働者の賃金が、「二個四」(ニコヨン、100円札2、10円札4)で、手取り240円。25日間働いても「240円×25日=6000円」しかならない時代だった。その時代に藤田はアクセサリーなどを輸入販売する「藤田商店」をスタート。5万円の貯金を始めることで、独立開業のリスクに備えたのだ。
藤田はこの時、筆者に漢数字(算用数字併用)でタテに書かれた古い預金通帳(銀行の受領印あり)を見せてくれた。藤田は5万円の定期預金額を10万円、15万円と上げて、その時点で40年間続けてきたと言った。貯金は複利で回り、91年4月時点で「24億1157万6544円」(この数字も藤田が手を入れた)に達した。藤田は人生が「仕事×時間=巨大な力」ということを、定期預金を通して証明した。
藤田が米国マクドナルド本社創業者のレイ・クロックに信頼され、日本マクドナルドの経営権を任されたのは、その人物の魅力にあった。藤田はマクドナルドの経営でPOSシステム(販売時点情報管理)の開発、GIS(地理情報システム)の開発、パルスフライヤー(熱効率85%、ガス代が従来の半分)、テリヤキバーガーなど日本発のイノベーションを起こし、米国本社に導入させた。
結果、藤田は米国本社の役員に抜擢される。
米国トイザらス本部と合弁で立ち上げた日本トイザらスが、92年1月に奈良県橿原市に第2号店を開店する少し前も、藤田にインタビューした。その時、彼は豪快に笑いながら、こう言った。
「ハンバーガーが売れないもので、トイザらスにおもちゃを買いに来たお客様に、ハンバーガーを買ってもらう作戦だ」

不振のマックに対し、堅調な販売を続けるモスバーガー。
藤田時代の業績のピークは99年12月期で、売上高3285億円、営業利益307億円を記録した。これは過去最高の営業利益で、10年間の原田時代にも破られていないが、藤田はこの時代、店舗数の拡大に固執していた。
それは、藤田が国内でのハンバーガービジネスの限界に気づき、店舗をネットでつなぎ、店舗とネットを一体にして、現在の楽天やアマゾンのようなビジネスを考えていたからではないかと思う。
藤田は現在のソフトバンク社長の孫正義が米国に行く時、
「これからはコンピュータの時代だ。コンピュータをやりなさい!」とアドバイスした。時代の流れや先行きを見る目は確かで、ハンバーガー屋にとどめておくのは惜しい逸材だった。
藤田を挫折させたのは2000年代に入って勃発した狂牛病騒動だった。対前年で20%近くも売り上げが減少するという、顧客の“マクドナルド離れ”が起きたのだ。そこで、平日半額セール(130円のハンバーガーを65円)などを実施し、客離れを食い止めたが、この頃から値下げ、値上げなどを繰り返して戦略がふらつき始めた。
また、マクドナルドのビジネスは、牛肉などの原材料を大量に輸入する関係で、業績の半分はドル/円相場に左右された。円高なら好調で、円安なら不調というわけだ。このため藤田は晩年、為替相場に熱中した。
2001年7月にジャスダックに上場するが、その翌年の02年12月期、マクドナルドは創業以来、29年ぶりに初の赤字に転落した。
この時期、米国マクドナルド本社では藤田とパイプの太いジャック・グリーンバーグ会長兼CEOが経営不振の責任を問われ、退任している。

マック同様、業績悪化に苦しむケンタッキー・フライド・チキン。
新経営陣は、この時を待っていたかのように、藤田に価格政策の失敗や赤字転落の責任を取らせるため、「藤田外し」の圧力を強めた。この時期、藤田が健康体であれば圧力をかわすこともできたはずだが、心臓に持病を持ち、02年3月には会長兼CEOに就き、翌03年3月には会長兼CEOも退任させられた。あるいは、藤田自身が退任を望んだのかもしれない。
それから1年後の04年4月、藤田は心不全で死去した。享年78。藤田は491億円という、歴代6位の巨額な遺産を遺した。これは、マクドナルドの経営者として30年以上かかって遺したものが大半だと思われる。
日本マクドナルド創業者の藤田は、「桜が散るように静かに死にたい」と言い、その通りに逝った。
一方、原田は藤田の死去1カ月後の04年5月、日本マクドナルドの社長に就いた。原田は日本のアップルコンピュータ社長兼米国アップルコンピュータ副社長を務め、マーケティングに精通していた。
とはいえ、米国マクドナルド本社が原田に白羽の矢を立てたのは、合理主義者で効率を最優先し、日本的な義理人情といった浪花節的な世界とは無縁の、意志の強いところが買われたと思われる。
米国マクドナルド本社が、「代理人」として原田に託した最大のミッションが、藤田が30年以上に亘って構築してきた「日本マクドナルド文化」の、いわば破壊、一掃であった。
米国本社は、世界の中で米国に次いで売上高の大きい日本マクドナルドが、利益率の低さにあえいでいることに業を煮やしていた。
それが「ディスカウントの多発」にあることを踏まえ、原田に従来のマクドナルド文化を破壊し、日本マクドナルドが米国本社の命令に服従することを約束させたといえる。
原田は、社長に就任すると取締役会などを英語で全部進行し、藤田派の幹部の一掃を図った。
「同じバスに乗るのかどうか」と迫ったという。ある藤田派の幹部は、「突然英語でしゃべられ、英語以外しゃべってはダメだと言われた。何を話しているのか全く分からず、これでは辞めるより仕方ないと思った」と振り返る。
原田は自分の体制について来れない幹部を次々にクビにした。この時代、現場を知り尽くしたマーケティングや店舗運営業務などに通じたプロが10~20人規模で転職し、マクドナルドのノウハウが流出した。
原田は米国本社と連携を深め、世界のマクドナルドでヒットした「ワンダラー商品」(100円マック)、プレミアムローストコーヒーの「マックカフェ」の導入などを進めた。
戦線が伸びきった藤田の後に登板し、スクラップ&ビルドの推進、中途半端な規模の店のFC化、直営店のFC化を推進。07年末時点でFC比率が28%だったのを、13年末には68%まで急激に進めた。08年以降、店舗関連の売却益は累計で150億円を突破した。FC化の推進も、米国本社の意向を進めたものだった。
マスコミは、既存店を8期連続プラスに導いたことから、「原田マジック」などと称賛したが、原田の頂点は11年12月期までであった。翌年から、2期連続で業績は悪化するのだが、前述したように、米国本社も原田も、日本市場の構造変化を十分に理解していない。
原田の周囲には、MBA(経営学修士)を取得した優秀な幹部がたくさんいたが、現場を知り抜いた幹部が流出し、さらにその人材が、コンビニコーヒーの開発などで「逆襲」に出てきている。
原田の最大の弱点は、外食産業やファストフードビジネスというより、米国本社の意向通りの務めを果たしていれば成功できる、と考えていた節があったことではないか。
藤田と原田の最大の違いは、藤田がマクドナルドの創業者でカリスマであるのに対し、原田はカリスマ型とはいえやはり“雇われ”だったことだ。
原田はいずれ、多額の慰労金を得てマクドナルドを去るだろうが、それでも、藤田の491億円もの遺産に比べればはるかに少ないだろう。この差はそのまま、創業者と雇われ社長の差と見るべきか。
「原田が徹底的な効率化を進めたマクドナルドは、あと2~3年はぺんぺん草も生えないのではないか」
業界関係者の間ではそんな声も聞かれる。後事を託されたカサノバの前途は高く、険しい。
(経済ジャーナリスト・中村芳平)
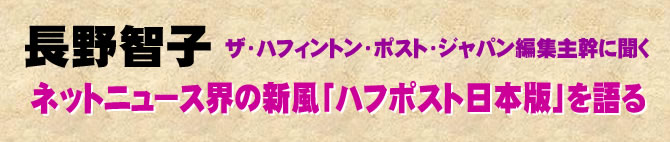

長野智子
ザ・ハフィントン・ポスト・ジャパン編集主幹
ながの・ともこ 米国ニュージャージー州出身。1985年上智大学外国語学部英語学科卒。同年フジテレビジョンアナウンス部に入社。90年フリーに。99年ニューヨーク大学大学院卒。2000年にテレビ朝日系「ザ・スクープ」キャスター、11年から「報道ステーションSUNDAY」のメインキャスターを務める。『踏みにじられた未来 御殿場事件、親と子の10年闘争』(幻冬舎)など著書多数。
テレビ朝日の「報道ステーションSUNDAY」メインキャスターの長野智子氏が去る1月、ザ・ハフィントン・ポスト日本版の編集主幹に就任した。ハフィントンポストは米国のリベラル系インターネットメディアで、創業編集長(現在は米国本社代表)のアリアナ・ハフィントン氏が2005年5月に開設。第一線で活躍中の、様々な著名コラムニストや識者が執筆するブログ、および自社の編集者による取材、執筆などで構成され、ジャンルも政治経済から社会、文化、ライフスタイル、そしてエンタメまで幅広い。
日本版は昨年5月、ハフィントンポストを買収した米国AOL(アメリカ・オンライン)と朝日新聞社との合弁事業としてスタートし、新たなステージに向けて今回、長野氏の起用となった。同氏は過去、月刊BOSSでも03年から6年間、経営者との連載対談で聞き手を務めていただいたのだが、ネットニュースメディアではどんな取り組みを見せてくれるのか、その抱負などを聞いた。
―― まず、改めて就任の経緯から聞かせてください。
長野 昨年12月半ばぐらいに、朝日新聞社さんからお話をいただきました。お話を伺って面白そうだなと思い、ぜひ、やってみたいと。その理由の一つは、私がテレビの報道番組に携わって14年になるのですが、報道の軸足は、どうしても身近でドメスティックな話題にならざるを得ないんですね。
その点、ハフィントンポスト(以下ハフポスト)は世界各国で展開していますし、ネットメディアということで何か新しいことにも挑戦できるでしょう。そういう点に惹かれてお受けしました。メールでの連絡が多いので、ここ(東京都千代田区外神田にあるハフポスト日本版編集部)に来るのは週に1回程度ですが、移動中も含めて、ハフポストの記事を朝から晩まで、無我夢中で読んでいます。
―― ネットニュースメディアはあまた存在しますが、長野さんのネットニュースとの接し方は、これまでどんなものでしたか。
長野 一人の読者として、ツイッターやフェイスブックでフォローしていましたし、ネットニュース全般にわたってかなりチェックしています。ハフポストに関しては、自由な言論空間という点に特徴があって、たとえば日本でも「BLOGOS」(提言型ニュースサイト)などがありますが、ハフポストはまた違う存在として見ていました。米国を軸に広く世界に扉を開けて、何かトライしようとしているのかなというイメージもあり、海外のニュースを翻訳ですぐに読めることからフォローしてましたね。
―― ハフポストの差別化として、読者参加型の、双方向コミュニケーションをかなり意識されているかと思いますが。
長野 そうですね、そもそもハフポストの成り立ちとして、ブロガーの人たちもたくさんいますし、読者の方からもコメントが寄せられて、言論空間がものすごく盛り上がってきました。ただ、日本は米国とはまた違うカルチャーじゃないですか。たとえば、自分の信念を鮮明にすることって、日本ではある種、マイナスになるようなところもありますし、自分が思っていること、考えていることを、率直にぶつけてどんどん表現していくような点でも、米国とはだいぶ差があります。
そんなカルチャーの中で、日本もやっとネットメディアが盛り上がってきて、自己主張を積極的にする人が少しずつ増えてきた段階だと思うので、言論空間として盛り上がっていくという点ではまだまだ先になるでしょう。もちろん、ハフポスト日本版にもすごくいいコメントがたくさん集まってきていることは確かなんですが、米国に比べればやっぱり、まだ数も少ないです。
ただ、記事のクオリティは高いですし今回、私がハフポスト日本版に入ったことで、日本におけるブランドイメージを強化することが役目なのだと思っています。たとえばフロントページ。メインになる「スプラッシュ」と言われる一番大きな記事を考えたり、新たに著名ブロガーを発掘して書いていただいたりとか。そうやって、ハフポスト日本版ってどんなサイトなんだろうという関心を、もっと多くの方に持っていただく。いまはそういう段階なのかなと思います。
そして、ブランディングをさらに強化した上で、たとえば米国と日本、それぞれで寄せられたコメントを日米間で交換するとか、米国の記事に対して日本の読者がコメントしたことを翻訳し、米国の読者がその日本の読者のコメントを読んで反応してくれたりとか。さらに、各国のハフポスト同士の双方向性を強めるとか、次のステージでやってみたい構想はたくさんあります。
―― 日本版の場合は、ターゲット層はどんなイメージですか。
長野 昨年5月に立ち上げた時は、団塊ジュニアをターゲットに定めています。この層は、ボリュームが多いのにサイレントというか、一番本音が聞こえてこない世代ともいえますから。
でも、10年もすればこのボリュームゾーンがオピニオンの中心になりますし、彼ら彼女らが何を考え、どういう意見を持っていて、社会をどうしていきたいのかを記事で発信し、その反響の輪を広げられるような形にしていきたいですね。プラス、団塊ジュニアのコアターゲット以外にも、ニュースが大好きな世代といえる、50歳以上の層にも浸透してほしい、という思いで動き始めたところです。

ハフィントンポスト日本版の松浦茂樹編集長(左)と二人三脚でブランド強化に挑む長野智子氏。
―― 紙とネットの違いはありますが、たとえばニューズウイーク日本版に関して思うのは、米国版の翻訳記事などを含めて、米国本社からのしばりや制約と、日本版の自由度のバランスはどうだろうかということです。ハフポストの場合はどうでしょうか。
長野 私が一番感じたのは、フォーマットというか、たとえばフロントページの作り方、見せ方にしてもそうですが、もっと日本人が見やすいように変えたらいいのではということでした。一例を挙げれば、スマートフォンでアクセスする時にコメントが書きづらいとか、逆にフェイスブックページのほうがコメントが書きやすいといったことがあるでしょう。
米国ではラップトップのデバイスからネットニュースにアクセスする人が多いのですが、日本人はスマートフォンを使うシーンがすごく多い。そうすると、使っているデバイスによってコメントの量も変わってきてしまう。そうした点は改善の余地ありですね。米国のほうからも、「もっとこういうふうにしてほしい」という、直接の要望はありますが、個別の記事に関してどうこうというのはないです。
―― 読者参加型というのとはちょっと違うと思いますが、同じネットニュースメディアという点では過去、韓国発祥で日本版も出したオーマイニュースがあります。オーマイニュースの特徴は、市民記者、市民ジャーナリズムという点にあって、日本版の合弁相手であった、ソフトバンクの孫正義社長も“市民ライター”として投稿したことがありました。でも結局日本では根付かず、サイトクローズに至っています。
長野 米国と日本とで違いがあるように、韓国と日本の違いというのもあるじゃないですか。ニュースを自分のこととして受け止めている人たちが記者になり、その人たちが発信して、あわよくばそれを権力層にも届けるというオーマイニュースのコンセプトは、ハフポストと似ている面もありますし、広く門戸を開いたオープンなニュースサイトはみんなそうでしょう。
ただ方法論として、ハフポストではプロの記者、プロのエディターが取材をしてますし、日本版のクレディビリティ、つまり信頼性という点でも、朝日新聞社という大手メディアがパートナーになっています。プラス米国もそうですが、ハフポストの大きな売りの一つが、著名な方から、何かの分野でものすごく詳しい専門を持っている方まで、幅広い方が書いてくださっているブログにあります。私自身、ハフポストってなんて贅沢な読み物なんだろうと思いますし、閲覧する上での登録などもまったくありませんから。
もちろん、読者がクリックして記事をどんどん読み進んでいく過程で、どうお金を得ていく仕組みを作っていくのかとか、ページビューをさらに増やしていき、安定的なスポンサーについていただくことも必要で、そこもこれからですね。
―― サイトの見せ方もそうですが、これからの重点課題はどう考えていますか。
長野 やっぱり、ハフポスト日本版がどんな主張をして、どういったニュースに特に力を入れていくかという、ブランドイメージをもっと明確に作り上げることでしょう。ただ、これも簡単ではなくて、米国のハフポストってものすごくエッジが利いていて、すごくリベラルですけど、それをそのまま日本でやって成功するのかといえば、文化背景も違うので難しいですよね。そこは、すごく慎重に見極めながらやらなければいけないと思っています。
米国のようにエッジの利いたことをどんどんやっていくというより、むしろ、たとえば政治家以外の方も含めて、いろいろな意見、主張をお持ちの方々に、東日本大震災についてのブログを豪華メンバーで揃えていくとか、地道に定点観測していくことも強みにしたいし、またなると思っています。そういうものを少しずつ、仕込んでいきたいですね。
あとはこの2月末、新しく韓国版のハフポストコリアもローンチしました。いま、日韓関係が政治的にすごく難しい局面ですけど、先日私も韓国に行きまして、米国のアリアナ・ハフィントン代表、それに現地の女性の編集主幹と3人で会談する機会をいただきましたし、ハフポストというメディアでも、日韓関係改善に向けて何か新しい仕掛けができないか、いろいろ議論していきたいと思います。
もう一つ、ホットイシューというか、原発問題から靖国参拝、アベノミクスや沖縄の基地問題、あるいは憲法や集団的自衛権まで、ハフポストではこんなに意見交換がなされているという、そうしたイメージを作ることに注力すべきだと思います。そして、言論が一番盛り上がるイシューに対し、ハフポストの存在イメージを慎重に、かつ丁寧に作っていくことが大事ですね。
(聞き手・本誌編集委員・河野圭祐)
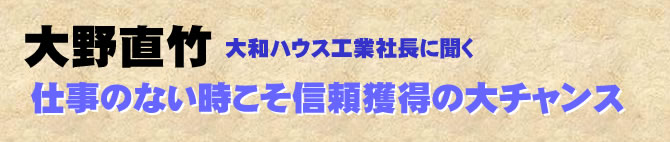

大野直竹
大和ハウス工業社長
おおの・なおたけ 1948年愛知県出身。71年慶応大学法学部を卒業し大和ハウス工業入社。以後一貫して営業畑を歩き、静岡建築営業所長、新潟支店長、東京本店特建事業部長、横浜支店長を歴任し、2000年に取締役就任。常務、専務、副社長営業本部長を経て、11年4月社長に就任した。
―― 4月1日に消費税率が5%から8%へと上がります。住宅は高額商品の最たるものですから、その影響は大きいのではないかと思いますが、4月以降についてどのように見ていますか。
大野 4月に8%となり、このままいけば、来年10月には10%となるわけですが、消費増税そのものをそれほど気にしているわけではありません。むしろ多少の逆風であればチャンスと捉えることもできますし、これまでやれなかったことを実行するいい機会になるかもしれません。でも一番気になるのは世の中の動きです。仮に社会全体がしぼんでしまってはどうしようもありません。一企業のやれることには限界があります。ですから、安倍首相もよくおっしゃってますが、景気の中折れがないよう、そこは政治によってきちんとした舵取りをしてほしいと思います。
―― 消費増税と時を同じくして大和ハウスでは、昨年から2015年度を最終年度とする第4次中期経営計画が始まっています。これによると今期2兆5500億円の売上高を、2兆8000億円に、1500億円の営業利益を1700億円に、800億円の最終利益を1000億円に引き上げようというものです(今期数字はいずれも見込み)。
大野 昨年秋にこの中計を発表した時には、ずいぶん保守的だとアナリストから言われました。みなさん、売上高3兆円という数字が出てくると思っていたようです。でも、消費増税のように、実際にやってみなければわからないところもありますから、その分、固めに見ています。
―― 大和ハウスは現在、建設関連産業で唯一の2兆円企業で、他を引き離しています。それでもまだ進軍ラッパは止まらず、3兆円が現実のものとなろうとしています。
大野 これまで売り上げを積み重ねてここまできましたが、各部門を見るとけっしてトップではありません。戸建住宅もトップではないですし、賃貸住宅でもそうです。マンション事業もトップではありません。あくまで総合体としてトップに立っているにすぎません。
ですから、もう一工夫してトップになる。もしくはトップに近いポジションになりたいというのが正直な気持ちです。でも、ここで注意しなければならないのは、内容が伴っていなければならないということです。
戸数だけを追い求めると、どこにでも建てればいいということになりかねない。でも我々はそういう商売のやり方はとりません。例えば賃貸住宅を建てるなら、その物件が満室になるようにフォローをしていく。戸数の目標ありきで、建てたあと、誰も住まないようなものは引き受けない、みんなが建てたい、みんなが住みたい家を建てるのが、大和ハウスのやり方です。
―― とはいえ、営業には目標数字があるわけですから、とりあえず目標をクリアしたいという欲求に負けてしまうこともあるでしょう。
大野 そうならないように、内部にチェックする部門を持っています。営業が持ってきた案件を、そこでいったん審査する。この審査を通らないことには、建設を引き受けることができないようになっています。
厳しく審査するのは当然ですが、それと同時に、そのままではあまり人気が出そうにない場合などは、最初からエアコンを設置するなどの提案も行っています。そのように、建設の仕方を工夫することで、住みたい家にしていくわけです。こうした議論を徹底的に行っています。
―― 公共投資や復興需要もあり、建設業界は活況を呈しています。さらに、ここに東京五輪特需が加わります。しかしその一方で、人手不足で人件費は上がり続け、円安によって建築資材も上がっています。その影響はかなり大きいのではないですか。
大野 いまでさえ人手が足りません。これに五輪特需が加わったらどうなるのか、ちょっと想像できないところがあります。ですから同業の中には、受注や売り上げは増えるけれど、利益は出ない、とおっしゃっているところもあるようです。状況は我々も同じです。ですからいま、モノづくり全体の見直しを図っています。プレハブ化をいま以上に進める。そのために集中生産、平準化、生産・調達品種の絞り込みを行っていきますし、物流ネットワークを構築することで配送コストも削減します。
こうした工夫によって、住宅系事業で100億円のコストを削減しようと考えています。

中計終了時には、売上高3兆円も見えてくる。
―― 中計の発表会見では、住宅部門以外の、商業施設や事業施設の展開について時間を割いて説明していました。中でも物流センターの開発・建設は、最近の物流拠点開発ブームもあって、期待できる分野ですね。
大野 いまさまざまな業界の業務形態が変わってきています。コンビニエンスストアへの物流なら、当日配送は当然ですが、商品管理が徹底され、より新鮮でおいしい状態でお店に届ける機能がより重要になってきます。そのために、従来は工場があって、そこから物流センターへ運び、各店舗へ、というものだったのに対し、最近では、物流センターそのものが工場機能の一部を持つケースも出てきています。またEビジネスなどは、物流のインフラがあって初めて可能なビジネスです。このように、これまで以上にいろんな機能を持つ物流施設が必要になってきています。
―― 事業用物件の場合、大和ハウスが施主から依頼を受けて建設するよりも、大和ハウスが企画・建設したものをテナントに貸し出すケースのほうが多いそうですね。
大野 最初の頃のお客様というのは、この土地に物流倉庫を建てたい、というケースが大半でした。ところが、そのうち、このエリアに物流拠点が欲しい。機能はこれだけ必要だ。ただし、自社で物件を所有することはできないので、賃貸の形で使用できないかという要望が増えてきました。そこで当社で土地を探し、土地のオーナーに提案し、倉庫を建てていたのですが、今度は土地のオーナーからも、土地は貸すけれど建物は大和ハウスの所有にしてという要望が出てくる。時には、土地も当社が所有する。いまでは物流施設を我々がつくって所有し、それをテナントにお貸しするケースが7割にまで達しています。
―― いま首都圏周辺では物流拠点建設ラッシュです。それだけに他の建設会社との競争も厳しいでしょうが、その中でも大和ハウスの強みとはなんですか。
大野 我々の強みは、テナントとの付き合いが古いということです。先ほど言ったように、最近の受注はオーダー型が中心です。テナントが場所や機能などの要望を出し、我々はそれに応えるわけですが、そのためには両者の深い信頼関係が必要です。信頼があるから機能に関して細かい注文も出てくる。我々はその注文に応じる。その代わり、長期的に借りていただく。そういう関係が構築できているのです。
もう一つは、土地を探す力があることです。というのも、我々は商業施設の立地をずっとフォローしているからです。仕事があろうがなかろうが、ずっとフォローしている。その土地がいまどういう状況にあるのか、オーナーの意向はどうなのか、常に把握しています。土地の売買情報もいち早く入ってくるため、必要なら土地を手当てすることができる。これは当社の強みです。
―― 仕事とは関係なくフォローをし続けるということですか。
大野 オーナーやその土地について知っているというだけではダメなんです。そこでいかに親しくして信頼されるかが勝負です。そしてこれは、お金の関係がない時こそ重要です。私がよく言うのは、仕事が出てからオーナーのところにかけつけてはダメだということです。仕事のない時に、どういうふうに通うかによって信頼関係を築くことができる。
仮に一つの仕事を運よく取ることができたとしても、それで仕事を終わりにしてはいけません。そのあとも、ずっと付き合いを続けていくことが必要です。
我々にはスーパーゼネコンさんのような歴史はありません。そんな会社が商売をしていくには、お客様一人ひとりから、あの会社は信頼できる、あの会社はいい、そう思ってもらえるかにかかっています。そこが我々の生命線です。
―― それは事業用施設についてだけではないわけですね。
大野 もちろんそうです。事業用施設も戸建住宅も賃貸住宅も全部一緒です。大和ハウスは1955年に、歴史も暖簾もお金もないところからスタートして、一歩一歩積み重ねて今日まで来ました。昔は「ヤマトハウス」なんて言われたりもしていました。それが今日まで来ることができたのは、先輩たちが、お客様や取引先様との信頼関係をずっと作ってきてくれたからです。
その先達に教わったことをこれからも大切にしていきたいし、さらには次の世代に伝えていく。それが我々の役目です。
―― となると社員教育が重要になってきますね。
大野 根気よく、根気よく、意識づけをしていかなければなりません。石橋信夫創業者、樋口武男会長など、先輩が築いてきた大和ハウスの伝統を、いかに下の人間に教えていくか。それによって、大和ハウスが順調に伸びていけるのか、伸びたのは一瞬だけの会社で終わってしまうのかは、この部分にかかっています。
そのためには日常業務を通じた教育が重要です。もちろん研修も必要ですが、やはり、日々の仕事を通して学んでいく。先ほど言った、仕事のない時にも通うことなど、最初はその意味が分からない社員もいるかもしれません。だけど、遠回りに見えるかもしれないけれど、それこそが近道です。簡単な近道はどこの世界にもありません。こうしたことを業務を通して学んでいくわけです。
―― とはいえ、大和ハウスはいまや2兆5000億円を売り上げる巨大企業です。社員の中には業界ナンバーワン企業という誇りというか驕りを持つ人も出てくるんじゃないですか。
大野 そんな社員がいたとしたら大和ハウスの危機ですね。でもその心配はあまりしていません。というのも、いくら規模が大きくなっても、当社は住宅メーカーだからです。
家を建てるお客様にとって、その家の価格が高い、安いというのは関係ありません。そのお客様にとっては、人生で最大の買い物になるわけです。自分の夢なんです。その夢を我々は預かっている。その重い気持ちを受け止めなければなりません。ですから、高い安い、大きい小さいということで、対応に差をつけたりすることはありえません。どんなお客様でも、全力で対応する。そして建てたあとでもフォローする。
この住宅メーカーとしての心を、社員全員が持っています。
すべての事業がその延長線上にあります。賃貸住宅も、その物件を建てるオーナーにしてみれば、非常に大きな事業です。ですから全力でそのお手伝いをする。建物を建てるだけでなく、空室を埋める努力もする。工場でも倉庫でも同じです。経営者にとってみれば、みなさん大きな決断をして建てるわけです。その重い気持ちを大切にすることが重要です。
いくら会社が大きくなっても、その気持ちに変わりはありません。将来的には、恐らく住宅部門の売上比率は小さくなっていくでしょう。でも大和ハウスは住宅メーカーですし、社名からハウスの名前がなくなることはありえません。
―― ところで、中堅ゼネコンのフジタを買収してほぼ1年がたちました。フジタの買収は、海外事業を強化するという目的があったと思いますが、合併の成果は出始めていますか。
大野 フジタと大和ハウスとでは、会社として生き方が違っていたことは事実です。ですから、我々の文化の中からいいところを学んでほしいですし、その逆に我々もまた、フジタの優れたところを学んでいきたいと思っています。特に海外事業については、学ぶべきものは非常に多いと感じています。
重要なのは、フジタの社員一人ひとりが、何を変えなければいけないのか感じてもらうことです。我々が押し付けるのではなく、自ら感じて変わってほしい。ですから、いまのところ社長を送り込むことも考えていませんし、ゆっくり、慌てずにやっていこうと思います。
―― 大和ハウスは2008年に小田急建設(現・大和小田急建設)の筆頭株主となり、一昨年6月には東京電力から老人ホーム経営の東電ライフサポート(現・大和ハウスライフサポート)を買収、そしてフジタです。その後もマンション大手のコスモスイニシアを買収していますし、中計にも500億円のM&Aが盛り込まれています。どういう基準でM&Aを考えているのですか。
大野 ひと言で言うと、我々は、お客様が生まれた時から亡くなる時まで、すべてのシーンでお付き合いしていきたいと考えています。つまり川上から川下までです。そう考えていくと、足りないところはたくさんある。これまでにも、多くの企業と提携しながら、足りない部分を強化していきましたが、自分たちでやったほうが効率がいいものに関しては、M&Aという手法で、その部分を埋めていこうと考えています。
ただし、これは樋口会長からもよく言われていることですが、儲かるからやるのではない。世の中のために、役に立つことをやる。その視点でM&Aを考えています。ですから、我々の事業と関係がない会社を、単に儲かりそうだからという理由で買収することはありえません。
すべてのことに言えるのですが、あまり得か損かということは気にしないほうがいい。そうではなく、何が世の中のためになるのか。まずはそれを考える。その結果として、お客様に大和ハウスを認めていただければ、それが最終的に当社の得となる。ですので、その時その時で一喜一憂するのではなく、常にお客様の役に立つことを考える。それができれば、中期経営計画も予定どおりにいくはずです。
(聞き手=本誌編集長・関 慎夫)
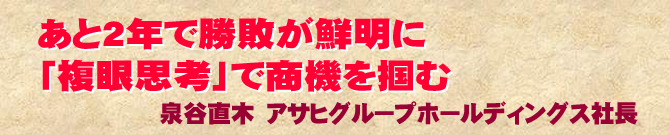

泉谷 直木 アサヒグループホールディングス社長
いずみや・なおき 1948年8月9日生まれ。京都府出身。72年京都産業大学法学部卒。同年アサヒビールに入社。86年広報企画課長、95年広報部長、96年経営企画部長、98年経営戦略部長、2001年首都圏本部副本部長兼東京支社長。03年取締役入りし、06年常務酒類本部長、07年マーケティング本部長も兼務、09年専務、10年3月社長に。11年7月に持ち株会社のアサヒグループHDに移行して社長を務め、14年3月末からはCEOも兼務予定。
国内偏重、「スーパードライ」頼みに映りがちなアサヒグループホールディングスだが、飲料事業も3位、海外展開も強化中と着実に歩を進めている。同社の泉谷直木社長に、今後のアサヒグループの展開や勝ち残り策を聞いた。
〔ビール大手上位3社の明暗が分かれてきた。2013年12月期決算を見ると、サントリーホールディングスとアサヒグループホールディングス(以下アサヒGHD)の2社が経常利益で過去最高となったからだ。サントリーHDの今期の売上予想は、トップのキリンホールディングスにほぼ並び、経常利益では首位に立つ見込み。
一方のアサヒGHDは売り上げこそキリンHD、サントリーHD比で約5000億円のビハインドとなる見通しなものの、経常利益では今期、キリンHDを抜きそうで、売上高経常利益率ではトップに立つ。そして、泉谷直木・アサヒGHD社長は、かつてのようなビールシェア争奪の攻防とは、もう景色が様変わりしたことを強調する〕
もちろん他社との競合はあるわけですけど、各社各様で事業構造も利益構造もかなり変わってきています。キリンHDさんでは海外展開や医薬事業にも力を入れ、サントリーHDさんは洋酒事業をグローバルに伸ばそうとされている。ですから、我々自身がどういう方向に事業を進めていくのかが大事で、あまり横を見ていると(方向性を)間違うかもしれません。しっかりと自分たちの目標を定めて、その方向に向けてどうステップを進めていくかが重要だと思っています。
〔いまや、アサヒGHDとキリンHDの株価を比較すると2倍の差がつき(3月上旬時点)、アサヒGHDが先を走っている。両社の株価が拮抗していた時期からすれば隔世の感があるといっていい〕
株価は期待値ですから、期待に応えられなかったらウチだって株価は下がりますよ。株価を上げることが目的ではないですけど、企業価値を上げる上で、きちんとROE(株主資本利益率)やEPS(1株当たり利益)を上げる努力をし、さらに最適な資本政策を組みながら、よりスピードを加速させていく。こうしたことをトータルで組み立てていく経営が必要なんです。
昔はビールの箱数(=ケース数。1ケースは大瓶換算で20本)が何箱か、ビールのシェアがどのくらいかに経営の大きなポイントがありましたが、いまは変化係数(前述のROEやEPS等)がたくさんありますし、シェアも大事ですが企業価値がどう、飲料事業や海外の成長率はどう、そしてトータルでの成長構造はどうなっているのかを、全部包含して経営しなければいけませんから。
〔他社のトピックで言えば、サントリーHDが米国洋酒大手のジムビーム社を、約1兆6500億円の巨資を投じて買収することが話題になったが、一昨年末までは、「ジムビーム」を日本で扱っていたのはアサヒビールで、代わりにサントリー酒類が取り扱っていた「ジャックダニエル」の販売権がアサヒに移っている〕
サントリーHDさんの立場で言えば、あちらの強みはウイスキーですから、その強みで打って出ていくのは正解だと思いますし、すごいご決断でしたが、勝算あってのことでしょうから我々があまりコメントすることではないですね。我々も洋酒戦略をどうするのかという課題はありますが、まずはビール事業があって、洋酒事業はそこに付随していく。サントリーHDさんはその逆でしょう。各社でコアコンピタンスが違いますから、他社との比較をしてもあまり意味がないですね。
〔アサヒGHDはキリンHDやサントリーHDと比べて、海外売上高の比率はまだ10%強で国内依存度が高い。それはそれで引き続き課題ではあるが、一方で、マザーカントリーで存在感が強くない企業が海外で勝負して勝てるはずがない。
その点、アサヒビールの看板商品の「スーパードライ」は、ビールの銘柄別販売ランキングで2位の「一番搾り」(キリンビール)とはケタ違いのボリュームを持ち、唯一1億ケースを超えている。ただし、その「スーパードライ」とて、ピーク時の2000年には、現在の倍近い1億9000万ケースもあった〕
確かに、他社分も含めてビールの販売箱数は総じて減ってきました。ですから、箱数の絶対量だけで見れば、日本市場はすでに世界の中で10番目ぐらいに落ちています。でも、それを金額ベースに置き換えるとまだ2番目。そういう観点で考えると、いまでも世界2位の市場ですし、日本のマーケットは減るからという理由だけで海外へ出ても成功しないですね。世界のビールメーカーでグローバルプレーヤーに数えられる企業は、我々が考えている以上に「スーパードライ」の動向に関心を持っていますし、それだけのプレゼンスがあれば、海外でのチャンスは今後、まだまだ膨らむと思います。
中でもアジア市場がターゲットで、将来的に事業構成比の2割は海外へ持っていき、なおかつ海外で利益が取れる事業構造にしていかないといけない。まずは海外比率15%が目標で、20%を目指す頃には、さらにアジア市場を拡大するのか、あるいは米国や欧州の市場を強化していくのかを決めていくことになるでしょう。
〔今年は、右肩上がりのプレミアムビール市場がヒートアップしている。この分野で首位を走るのは「ザ・プレミアム・モルツ」擁するサントリー酒類だが、アサヒビールでも、ギフト商品だった「スーパードライ プレミアム」の通年商品化を開始。キリンビールも「一番搾り」で参戦予定で、サッポロビールも「ヱビス」の拡販に挑む〕
プレミアムジャンルは我々が参入したことで、直近で2900万箱ぐらいあるこの市場をどう増やすかに尽きます。昨年、このジャンルは前年比で7~8%伸びていて、今年は14~15%ぐらい伸びるでしょう。そうなれば、2900万箱がいずれ4000万箱、あるいは5000万箱になっていく。そこまで市場が大きくなったら(シェアを)ガバっと取ればいい。
まずは、プレミアム市場をさらに大きくすることです。かつて「スーパードライ」を取り巻く市場がそうでした。他社が一斉に“ドライ商品”をぶつけてきましたからね。そして市場が一気に膨らみました。でも、その中で品質が勝るところが最後は勝つわけで、結果、我々が勝ってきたわけです。単に「スーパードライ」が売れたという体験だけではなく、なぜ売れたのかという点を知る経験もできました。

去る2月24日、インドフードとの合弁事業の会見に臨んだ泉谷直木・アサヒGHD社長
〔一方、飲料事業はカルピス買収で3位の座を確たるものにした。首位のコカ・コーラ、2位のサントリー食品インターナショナルの背中は遠いものの、アサヒ飲料も確実にステージを上げている。また国内だけでなく、海外もインドネシアでのインドフードとの合弁事業など着実に歩を進めている〕
ビールも飲料もそうですけど、ナンバーワンブランドか2位ブランドあたりまでしか店頭に置かれなくなる。要するに、それ以下の雑多なブランドは店頭から消えますから、一挙に業績の格差がついてしまうでしょう。その点、カルピスは乳性飲料ジャンルでは6割以上のシェアを持つ、まさにナンバーワンブランドです。加えて、「三ツ矢サイダー」、缶コーヒーの「ワンダ」、「十六茶」もそれなりの数字で推移していますからね。
特保の「十六茶」も出しました。これは健康志向の反映もありますが、経営側から見ると、従来品よりも商品単価を上げられますから粗利が変わってくるわけです。特保商品が入ってくることで、ボリュームは前年比で2~3%増ですけど、金額ベースではもっと伸びてくるはず。そういう期待もしています。
業界3位というポジションも大事ですが、飲料分野はこれだけ商品カテゴリーが増えてしまうと、各カテゴリーで強いブランドをいくつ持っているかということが大事です。(消費税増税で)向こう2年で、各業界とも企業間の業績格差が開くでしょう。そして16年以降はどういう戦いになるかというと、今度はその2年間を生き抜いた、強い企業同士の戦いになるわけです。その時、一番肝心なのがブランド力。この先2年は苦しいけど、苦しい中でも投資しながらブランドを強くしていかねばなりません。
プラス、国内での強さは維持していかないといけませんが、国内一辺倒では、10年先を考えたらやっていけない。やはり、どこかで国内と海外のバランスを取っていかないと。それを15年までにどこまで進め、16年からの次の中期経営計画でどこまでできるか。そこが勝負になってきます。
〔かつてはビールオンリーだった市場に発泡酒が登場し、さらにその後、新ジャンルと称されるビールがぐんぐん占有率を高めてきたのが現在の姿で、嗜好の多様化や、少子高齢化、若年層のビール離れなど、ビールメーカーにとって需要の先細りは避けられないと指摘されて久しい。だが、そうした近視眼的な思考から複眼思考に転換できれば、まだまだビジネスの種は転がっていると泉谷氏は説く〕
社内でよく言っている例をいくつか挙げましょう。いま、だいたい主婦の6割近くが働いているので、朝晩の2時間ぐらいはものすごく密度が濃い時間なわけです。朝、子供を起こして弁当を作り、自分も身支度をして保育園に連れていき、会社に行く。帰りは保育園に子供を迎えに行き、家で晩御飯を作る、さらに洗濯や掃除もする。
となると、家事や化粧時間などを最大限、効率化しなければいけません。たとえば洗剤。洗剤の品質が良くなって、昔の半分の時間で洗濯が済むようになった。だから、少々価格が高い洗剤でも売れるのです。
掃除機も「ルンバ」が登場したことで、炊事しながら「ルンバ」が部屋の掃除をしてくれる。そうやって人の生活をよく見ていくと、物事を遠目に見たり何となくデータで見たり、あるいは平均値でばかり見ていては気が付かないものが見えてくるんです。平均値の上にも下にも人がいるわけで、我々もお客さんを見る時にメッシュ細かく見ることによって、新たなニーズは必ずつかめるようになるはず。あとは、潜在需要をどう掘り起こすことができるか、その会社の感度の問題ですよ。
〔この4月、資生堂の新社長に元日本コカ・コーラ会長だった魚谷雅彦氏が就任する。魚谷氏は飲料業界で「マーケティングの達人」として知られ、泉谷氏も尊敬する経営者の1人だという。アサヒGHDもグループ会社でサプリメントや化粧品を手がけているだけに、魚谷氏がどんな手腕を見せるのか注目しているはずだ〕
いま、女性の化粧時間をどう短縮するかがものすごく大事なテーマで、手早く化粧できる商品がとても流行っているんですね。(アサヒのグループ会社でも手がけている)「オールインワンジェル」といった商品がそれです。物事をそういう生活時間の効率化で切って見ると、従来とは違う時間密度があって、すごく付加価値のある商品が求められている。そういう事例はたくさんありますよ。
たとえば世の中では高齢社会が加速しますという話ですけど、1人1人に置き換えてみると、それは「個人の長寿化」なんですね。その個人の長寿化に、我々がどう対応していけるかが大事で、世の中の平均値の話だけを見ているのでは見誤ると思います。
もう1つ事例を挙げれば、地方の大きな家だとトイレが離れているじゃないですか。高齢者は夜中にトイレに行くのも大変です。そこで、配管工事をしなくてもホース2本で簡易トイレが部屋の中に作れる時代です。価格は高いですけど価値があり、需要もある。「量で考えたらそんなもの1000万台出ないでしょう」という話になるわけですけど、1000万台売るのは従来の10万円ぐらいのトイレ機器。でも、50万円の付加価値製品を200万台売れば一緒です。いわば粗利ミックスで、そういう市場の見方をしていかないと。
〔ビジネスの新たなオポチュニティを掴むためにも、泉谷氏は社員に「もっとタウンウォッチングをせよ」と訴えている。アサヒGHD本社のある浅草エリア(東京都墨田区吾妻橋)は、円安効果もあって外国人観光客が増えているが、6年後の東京五輪の頃はさらに賑わうのは確実。その五輪商戦についてもオポチュニティは多いという〕

営業だけでなく広範な事業を経験してきた泉谷氏。
今後2年か3年で、海外で「スーパードライ」を1000万箱売って、その先はさらに倍に伸ばす。五輪開催時には訪日した海外の人たちに、日本で本場の「スーパードライ」を飲んでいただき、そこで満足感を持ってもらい、帰国してからもまたお飲みいただくような連鎖を作るとか。五輪をただ待っているのではなく、五輪の前にビジョンを作ってみんなで面白がってやることが大事。それがオポチュニティなのです。
日本人はすぐに、「私は運がない」とか「ついてない」とぼやきますが、海外の人たちは英語でチャンスとは言いません。みんなオポチュニティと言う。日本語で言う「機会」を、自分でどうチャンスに作り替えるかなんです。
〔ビール・飲料業界は、自動車や電機業界のように自社ブランドで世界を席巻していくことが難しい。各国の気候や民族性によって、飲み物の嗜好が大きく異なってくるからだ。勢い、現地企業と合弁でゼロからコツコツとスタートするか、M&Aで一気にブランドを手に入れるかのどちらかになる〕
飲料ビジネスで言えば、勝てる要素はブランド、ディストリビューション、それにその地域の食文化に合った商品の開発です。進出国で、上位5社のシェアが5割までなら自社ブランドで食い込める余地はありますが、これが8割取られていたらとても勝てません。だからブランドを持っている会社を買収しないといけないわけです。
当社は、たとえば92年当時は、売り上げが1兆円弱なのに、借金が1兆3000億円ありましたが、その後、10年間でトータル1兆円をコツコツ返してきました。そのおかげで、いまでは4000億円ぐらいまでの投資ならすぐにでもできますし、1兆円借りてでも思い切ってやるということも、いまは信用があるから可能です。その財務基盤をベースに、海外展開は進出国や地域の状況に応じて、柔軟にやっていきますよ。
(構成=本誌編集委員・河野圭祐)


日本リバース院長 今野 清志
こんの・きよし 中央大学法学部を卒業し、大学病院で核医学などに携わったあと、中国で経絡療法を学ぶ。帰国後、整体を始める。10年ほどたってから視力回復に効果がある「目の美容室」を開業。現在は東京・茅場町で視力回復、難聴改善専門の整体を行っている。昨年12月に自由国民社より『目は1分でよくなる』を発刊、これまでに5万部を超えるベストセラーとなっている。
―― 今野さんは大学卒業後、整体院を開き、いまでは「目の美容室」として、眼病の人たちの症状の改善に取り組んでいるそうですが、どういう経緯で今日に至ったのですか。
今野 私は若い頃。柔道をしていたこともあり、人間の身体について強い興味を持っていました。大学を卒業後は、ある大学病院で、核医学の手伝いをしていたのですが、そこでは、疑問に思うことばかりでした。
それまでの私は、科学は万能だと思い込み、西洋医学でどんな患者さんも治すことができると思っていました。ところがそうではなかった。病院に来ても治すことのできない患者はいくらでもいました。そのことを、酒の席などで医者に言うと、「無理なものは無理」という言葉が返ってきます。なんのための医学なのか、という疑問が私の中に生まれました。
そんな時、ある中医学の先生に出会い、施術してもらうことになりました。経絡療法というもので、不覚にもイビキをかいて眠ってしまったのです。その時、私はこれだ、と思いました。
その施術によって、私はとても楽になった。薬などでは、こうはなりません。そこで、中医学を学ぶことを決意しました。
―― 普通の整体とは違うのですか。
今野 私の学んだのは、経絡療法です。人間の身体に通っている経絡を刺激することで、健康を取り戻そうというものです。
そのために私は中国に渡り、先生に付いて徹底的に勉強し、帰国してから整体院を始めました。とはいえ、中医学は奥が深いですから、定期的に中国に行っては、勉強を繰り返すという時期がしばらく続きます。
―― それがどうして、「目の美容院」にたどりついたのですか。
今野 中医学には目の施術もあるのですが、最初の頃は、自分の専門外だと考えてやっていませんでした。でもある時、網膜色素変性症で、白杖で歩かざるを得ないほど視力の低下した人に出会ったのです。
私は医者の知り合いも多いですから、まずはいくつかの大学病院を紹介しました。それでも一向によくならない。それどころが、5万円もするメガネを買わされた。それで頭に来て、私が目の周りをタッピング(軽く叩いて刺激を与える)したところ、ほとんど見えなかった方が、壁にかけてある時計が見えると言ったのです。
これは大きな可能性がある。そう思った私は、その人を連れて中国に渡りました。そこで施術したところ、するたびに見えるようになっていく。5回の施術で、視力が0.5にまで回復したのです。そこで私は、目について猛勉強し、「目の美容室」を始めました。
―― 日本リバースのホームページを見ると、緑内障や白内障、近視・乱視の方まで、施術を受けることでよく見えるようになった、という利用者の声が掲載されています。でも緑内障などは、いまでも根源的な治療法がなく、特効薬もできていません。それが整体でよくなるものなのですか。
今野 私は「目の美容室」を始める前に、10年近く、人間の身体についての勉強を続けていました。その経験が活きたと思っています。
というのも、西洋医学では、目の病気や目の不調は、目そのものに問題があると考えます。でも本当は、目が悪いのは体のどこかが悪いからなのです。
中医学では、目は肝臓に支配されていると考えます。目が悪くなるのは、血流不足、酸素不足、栄養不足である場合が多い。ですから、目そのものよりも、体の血流をよくしてあげる。それによって眼病や視力が改善するなど、大きな効果を生むのです。
―― 恐らく眼科医にしてみれば受け入れられない考え方ですね。
今野 大学病院の眼科に通ったけれど一向によくならず、うちに来た方もいます。施術をしたところ、よく見えるようになった。その方は、その後、大学病院に「ここでは治らなかったけれど整体で治った」と文句を言いにいったそうです。若い先生はとまどっていたそうですが、続いて対応した教授は、そういうこともあるんでしょうね、と納得していたそうです。
いまの医学は、専門化が進む一方です。自分の担当のことは詳しいけれど、ほかのパーツのことはわからない。ましてや全身のことなど興味もない。でもそれはおかしい。全身があってパーツがあるというのが中医学の考え方です。体におかしいところがあると、それがいちばん弱いところに出る。ですから、パーツを治すのではなく、身体を治すことが必要なのです。
―― 近視も緑内障も、原因は一緒なのですか。
今野 ええ。先ほど言ったように、血流不足、酸素不足、栄養不足です。ですので、「目の美容院」では、3歳の子供から99歳のお年寄りまで、施術はまったく一緒です。望診(顔色や舌の色、体つきなどを目で見る診断法)の後、経絡を触診し、整体やアイトレーナーを使ったタッピングなどの施術を行います。人によっては1回の施術で効果が現れる方もいらっしゃいますし、平均で10回程度施術をすれば、ほぼ全員の方に効果があります。
―― ここでやっている施術を、『目は1分でよくなる』という本で紹介していますね。
今野 昨年12月に自由国民社から発売して、すでに5万部を超えました。本を出した理由は、これまで申し上げたことと同じです。目が悪いのは、身体に問題がある。そのことをより多くの人に知っていただきたかった。身体の調子を整えれば目もよくなる。それはけっしてむずかしいことではなく、日常生活の中でもちょっとした運動で改善するのです。もちろん本格的な施術と同じ効果にはなりませんが、呼吸法などで血流を改善することはできますし、それだけでも、効果は現れます。
―― それだけ売れると、来院する人もずいぶんと増えたのではないですか。
今野 問い合わせも多いですし、いらっしゃる方も増えました。でも、地方の方からは、自分の住んでいる地区に、同じような施術をする人はいないのか、とよく聞かれます。そこで最近では、整体師の方などプロを対象に、DVDなどを通じて施術を教えることを始めました。私の培ったノウハウをオープンに提供して、より多くの悩まれている方の役に立ちたいとの考えからです。
―― 今後は、どのような活動をしていく考えですか。
今野 「目の美容室」以外にも、「耳の美容室」をやっています。難聴は、腎臓や小腸の働きが悪いことによって起きるというのが、中医学の考え方です。ですから目と同様、身体の調子を整えることで、改善する。そういう方が当院にはたくさんいらっしゃいます。
それと同じように、鼻の不調、口の不調で悩まれている人がいる。耳鼻科や歯科に行ってもよくならないけど、やはり体のどこかがおかしいから現象として鼻や口に現れる。
そういうことを、より多くの人に知っていただきたい。そして日常生活を少し工夫することで、そうした不調を改善することができるのです。健康法とは、身近なところにあるんですよ。