




「終活」という言葉が流行っている。自分の人生を自分らしく終わらせたいと多くの人が思っているからだ。人生と同じように企業にも寿命はある。だとしたら個人と同じように企業も終活を考えてしかるべきだ。どうやったらステークホルダーが幸せになれるかどうか。幸いなことに日本経済にようやく曙光が差してきた。バブル崩壊から約四半世紀。待ちに待った時代の到来だ。景気がよければ終活の選択肢も増える。経営者が、企業の行く末を真剣に考える時代がやってきた。
「ようやく景気がよくなってきた。これまでは生き残ることに汲々としてきたけれど、将来に向けたチャレンジができる環境が整ってきた。でもだからこそ、いまこの段階で、自分たちの強みは何かを含め、長期的視点に立って、ステークホルダーに取って何が最善なのか考える必要があると思います。必要ならば、企業形態を見直すこともやぶさかではない。そういうことを考えるチャンスがいまなのです」
と真剣に語るのは、東証1部上場企業の経営者だ。
東証株価の最高値は、1989年末の大納会での3万8900円だった。翌90年以降、株価は下がり続け、20年後の2009年3月には7054円の最安値を記録している。最近でこそ株価は多少持ち直してきているとはいえ、いまでもなお、最高値の半分にも満たない。それがこの四半世紀の日本の経済の姿である。
経済が低迷すれば、当然のことながら企業収益も悪化する。バブル崩壊からこれまでの間に、いったいどれだけの企業が傷つき、市場から退出を命じられたことだろう。その中には、一時は日本経済を支えたほどの名門企業や巨大企業も含まれていた。この25年間で戦後の企業神話はすっかり覆ってしまった。
神話を覆した企業の代表とも言えるのが、10年に会社更生法を申請して倒産した日本航空だった。

日本株式会社そのものだった日本航空も倒産した。
かつて日本航空の個人筆頭株主だった糸山英太郎氏(新日本観光会長)は、日本航空株を買う理由について次のように語っていた。
「日本航空や三菱重工は日本株式会社そのものです。これらの会社がつぶれる時は、日本がつぶれる時。だから国策としても絶対につぶすことはしない。だから安心して株を買えばいい」
いまとなっては、その言葉はむなしく響くのだが、糸山氏と同じように、国策会社は何が何でも政府が守ると信じていた投資家は多かった。しかし民主党政権だったこともあってか、政府はあっさりと日本航空を見放した。「国策会社はつぶれない」という神話は、この瞬間、崩壊した。
日本航空倒産より十数年前に消えた神話が、「銀行はつぶれない」というものだった。戦後長らく大蔵省の庇護のもと、護送船団方式でわが世の春を謳歌していた金融機関には、真の意味でのリスク管理は存在しなかった。いざとなったらお上に助けてもらえばいいと考えていたためだ。だからバブル景気に溺れ、不良債権を抱えたのも当然のことだった。1998年には都銀の一角である北海道拓殖銀行が経営破綻。99年にはともに産業金融を担ってきた日本長期信用銀行と日本債券信用銀行が破綻。それぞれ一時国有化されたあと、長銀は外資に、日債銀は国内企業グループに売却された。
銀行でもつぶされる。この事実を目の当たりにして初めて、銀行経営者は生き残りに必死になり始める。それによって銀行業界に大きな地殻変動が起き、3大メガバンクに集約されていった。神話崩壊が今日の銀行業界図を描く引き金になったのだ。
2007年の鐘紡の解散も衝撃的だった。鐘紡は戦前、そして戦後のしばらく、日本最大の会社だった。国と行動を共にするかたちで朝鮮半島や満州にも進出、アジア各地に工場を建設した。
敗戦によって多くの工場を失うが、それでも多角化を図ることで鐘紡は日本を代表する企業であり続け、経営者は日本産業界の重鎮そのものだった。日本航空が御巣鷹山で墜落事故を起こしたあと、経営再建のために鐘紡の伊藤淳二会長が会長として送り込まれた一事は、経済界における鐘紡の存在感を示すものだ。
しかし名門企業のプライドゆえか、いつの間にか業績は悪化しているにもかかわらず、一流企業としてのメンツを粉飾決算によって保とうとしたものの、結局はそれがばれて、最後は解散に追い込まれた。
いまでは鐘紡の名は、花王に買収された化粧品部門に残るのみだが、そのカネボウ化粧品も、昨年、白斑事件を起こした。鐘紡の呪縛はいまなお続いている。

戦後の流通業をリードしたダイエーも、いまはイオン傘下になっている。
鐘紡が戦前からの名門企業なら、日本の大量消費時代をリードしたのが戦後の申し子とも言えるダイエーだった。
カリスマ創業者、中内功氏率いるダイエーは、中内氏の衰えることを知らない事業欲に突き動かされ、本業とは関係ない企業をも次から次へと傘下に収めていった。「売り上げはすべてを癒す」――これが中内氏の基本的な考えだった。
しかしそれが通用したのは1980年代まで。バブル崩壊後のダイエーはその負の遺産に苦しみ続けた。結局2004年、産業再生機構の支援を仰ぐ。しかしその後も業績は改善せず、昨年、イオン傘下として出直すことになった。
このほか、2度の不祥事を起こした雪印や、証券取引法違反容疑によってオーナーが逮捕された西武鉄道グループなど、誰もが名前を知っている企業がその姿を消したり、上場廃止になって銀行管理になるなど、従来とは違う姿になってどうにかその命脈を保っている。
企業は社会的な存在なだけに、経営破綻すると、さまざまなところに影響が出る。いちばんわかりやすいのは従業員である。かつて山一證券が経営破綻した時に、その幕を引いた社長が会見で「社員は悪くありませんから」と涙ながらに絶叫していたが、会社がなくなれば、当然社員は全員解雇される。若ければまだつぶしもきくが、ある程度、年齢がいった場合、再就職もむずかしい。会社がつぶれていちばん迷惑するのが社員である。
取引先や金融機関も多大な迷惑を受ける。会社が破綻した場合、支払いもできないし融資の返済もむずかしい。また株主の被害も甚大だ。倒産すれば株券の価値はゼロになる。上場企業の場合、何万人もの一般投資家が被害を受ける。投資家の自己責任とはいえ、多くの人の恨みを買うことになるのは間違いない。
企業の倒産は、ステークホルダーたちに多大なる迷惑をかけてきた。倒産は悪、多くの経営者がそう考え、会社の存続こそが善と刷り込まれている。しかし果たしてその考えは絶対的正義なのだろうか。
暗黒の四半世紀が過ぎ、アベノミクスによって、日本経済に薄明かりが差し始めた。ほとんどすべての経済指標が上向きに転じている。
倒産件数も減っている。東京商工リサーチの調べによると、昨年の倒産件数は1万855件、負債総額は2兆7823億円だった。前年比では、件数で10.5%、金額で27.4%の大幅減である。これもアベノミクス効果といっていい。ここまで経営環境の悪化に嘆いてきた経営者にしてみれば、待ちに待った瞬間である。
しかし、少し待ってもらいたい。環境がよくなったと笑っているようでは、いずれ環境が悪化した時に泣くことになる。
景気が少々上向いたところで、その事業の将来性や、それぞれの会社の持つ強みや弱みはそうそう変わるものではない。自分の会社を客観的に見て、将来に不安があるのなら、その事業形態を見直す大きなチャンスだと言うことができる。
このたび経団連会長会社となることが決まった東レ。この会社の中興の祖である前田勝之助氏は、「会社の業績が悪いからといって、安易に社員を削減するようでは経営者失格だ。だからといって、東レが人員削減をしたことがないわけではない。人を減らすなら、景気のいい時にやるべきで、それなら、就職先も見つけやすい」と語っていた。
その言にならえば、経済が好転しているいまこそ、存続も含め、ステークホルダーにとって何が最善かを考えるべきだ。
本稿の前半で取り上げた企業に共通するのは、時代の流れに抗いながらも何とかして存続しようともがいたものの、最後は刀折れ矢尽きてしまった。経済が低迷するなかで無理に無理を重ねたために、結果的に多くのステークホルダーに迷惑をかけることになった。このような経営破綻は最悪だ。もっと早く決断をしていれば、状況はまったく変わっていただろう。
極端な話、事業体が健全で、黒字もしくは収支とんとんな状態なら、買い手はいくらでもある。ましてや、景気が回復し、企業の投資意欲に火がついた状態ならなおさらだ。いっそのこと事業の一部、あるいは全事業を売却したほうが、社員も取引先もハッピーになるかもしれない。
企業を廃業するにしても、経済環境がよければ資産評価も高くなるため、取引先や金融機関にかける迷惑も、不況時に比べればはるかに小さい。職を失ってしまう社員にしても、経済が拡大している時期なら、まだ対処のしようがある。
恐らく、アベノミクス効果と東京オリンピック効果によって、2020年までは景気は緩やかながらも拡大していくはずだ。その間に、企業経営者は自分の会社の行く末を見極め、決断を下すべきだ。
これは大企業に限った話ではない。中小企業こそ、真剣にこの問題を考える必要がある。
仮に会社が存続できなかったとしても、ステークホルダーに対し最大限報いる終わり方ができたのなら、経営者はむしろ胸を張るべきだ。その好機が巡ってきた。
日本株式会社そのものだった日本航空も倒産した。
戦後の流通業をリードしたダイエーも、いまはイオン傘下になっている。

年明け早々、パナソニックが子会社の三洋電機の社員を対象に、250人規模の早期退職を募集するとの記事がメディアを賑わした。見出しには「三洋電機 完全消滅へのカウントダウン始まる」とあった。
1947年に創業し(会社設立は49年)、一時は売上高2兆6000億円、全世界の従業員数10万人を誇った電機メーカーが名実ともに消えようとしているのだ。
三洋電機は松下幸之助の義弟(むめの夫人の弟)で、創業期から松下電器を支えてきた井植歳男が、戦後独立して設立した会社である。その意味で松下電器とは兄弟のような関係だった。事業領域は白物家電やAV機器など、完全に松下電器とかぶっていたが、高度成長期には、義兄弟会社同士、切磋琢磨することで、ともに成長していった。一時はデジカメメーカーとして世界一になったほか、太陽電池や二次電池では、松下を凌ぐ技術力を誇っていた。
しかし2004年の新潟県中越地震によって新潟県内の工場が被害を受け、特損を計上、これをきっかけに業績は年を追うごとに悪化していった。

電機メーカーの再編はこれからも続く(写真は2013年のCEATEC会場)。
いまから振り返れば、2000年代に入ってからの三洋電機は、日本の高度成長が終わったこともあり、ミニ松下として存続することはむずかしくなっていた。にもかかわらず、従来路線のままの企業存続を経営陣は指向し、またできると信じていた。その無理が会社の至るところに現れていた。
たとえば1980年代には同社製石油ファンヒーターによるCO2事故が起き、創業家の社長が引責辞任に追い込まれている。また90年代には太陽電池のデータ偽装が発覚、この時も社長が辞任した。
2000年代に入ると、三洋電機は中国の家電メーカー、ハイアールと提携、三洋がハイアール製品を日本国内で売り、ハイアールが三洋製品を中国で売ると発表した。当時の井植敏会長は、「三洋が国際的ブランドになるための第一歩」と胸を張っていたが、実際には、前途が描けなくなったがための苦肉の策でしかなかった。
05年秋には、業績悪化は誰の目にも明らかになり、大幅なリストラを行うとともにゴールドマンサックスや三井住友銀行などから3000億円の資本を受け入れざるを得なかった。これにより一時的に資金的余裕を得るがそれも長くは続かず、結局08年に、パナソニックがTOBによって三洋電機を買収することが決まり、最終的には10年にパナソニックの完全子会社となった。
パナソニックにしても義兄弟会社いう義理人情だけで買収を決意したわけではない。傘下に収めることで、エネルギー部門をもう一つの収益の柱にしたいとの思惑があった。当時の大坪文雄・パナソニック社長は、「三洋の得意なエネルギー部門は、AV、白物、産業用、住設に次ぐ5番目の柱となる」と、その意義を強調した。
ところが、実際には、買収した三洋は、金の卵を産むニワトリどころか、赤字を垂れ流すお荷物でしかなかった。
12年3月期、13年3月期の2年間で、パナソニックは1兆5000億円もの最終赤字を計上しているが、この中には、三洋電機ののれん代減損処理費2500億円も含まれている。買収時と比べ、三洋電機の企業価値が大きく減損したため、損失処理をしたというわけだ。

2008年、三洋電機はパナソニックと提携、存続をはかったが……。
三洋電機の事業も、いまパナソニックに引き継がれているのはエネルギー部門などごく一部にすぎない。すでにすべての三洋ブランドはパナソニックに取って替わられただけでなく、白物家電部門は、かつて提携関係にあったハイアールに、わずか100億円という価格で売却されている。携帯電話事業は京セラに、半導体事業も米国の会社に売却された。
エネルギー部門でも車載用を除くニッケル水素電池が古河グループに売却されるなど、買収当時とは大きく陣容は変わっている。
すでに、現在パナソニックに残っている三洋社員は2000人ほど。その1割強を間もなく削減する。さらには大阪・守口市にある三洋電機旧本社は、守口市との間で売却話が進む。すでにブランドはなく、もう少し時間がたてば社員も旧本社も消えてしまう。三洋という会社の痕跡さえ残らないかもしれない。
パナソニックの完全子会社になってから5年もたっていないにもかかわらず、である。
さて、ここまで三洋電機の末路をたどってきたが、本稿は三洋電機だけを論じるものではない。
戦後の日本経済を支えたのは、まずは繊維であり、その後は電機と自動車だ。繊維はいち早く構造不況業種となったが、電機と自動車はバブル経済が破裂するまでは「貿易立国ニッポン」の象徴であり続けた。それが1990年代に入って明暗が分かれる。自動車業界は紆余曲折あり、資本の移動などもありながらも、トヨタ自動車を筆頭に11社体制がいまなお維持されている。
ところが電機業界は、もともと母数の大きさの違いはあるが、数多くの歴史のある企業が姿を消した。三洋電機はその中のひとつにすぎない。
三洋と同じくパナソニックと縁の深いところでは、日本ビクターも消えていった企業のひとつである。
日本ビクターはもともと米ビクターの日本法人として戦前に設立されたが、戦後、米国親会社が身売りしたことなどもあり、日本法人の業績は低迷していた。そこに救いの手を差し伸べたのが松下幸之助だった。いまではほとんど見ることはなくなったが、ビクターのトレードマークといえば、蓄音機に耳を傾けている「ビクター犬」だが、幸之助はこのビクター犬のマーク欲しさにビクター救済を決断したとも言われている。こうして日本ビクター株式の50%以上を松下電器が持つことになり、その関係は60年近く変わらなかった。
ビクターは白物部門を持たないが、AV機器においては完全に松下と競合する。しかし三洋電機同様、日本経済が右肩上がりの時は問題がなかった。松下とビクターは親子でありながら、競い合いながらともに伸びていった。
1970年代に、ビクターは家庭用ビデオ、VHSを開発する。VHSはソニーのベータ方式との競争に完全勝利し、ビデオのデファクトスタンダードとなる。この勝利によって、ビクターは大きく売り上げを伸ばしただけでなく、その特許料収入が毎年100億円単位で入ってくるなど、70年代から80年代にかけ、ビクターは超優良企業となった。
ところが90年代に入ると、さしもの「VHS神風」も弱まってきた。本来であれば、VHSで稼いだ資金を元手に次なる経営の柱を育てればよかったのだが、ビクターは「VHSの次はVHS」と、VHSのさらなる進化を目指した。S-VHSで高画質を実現するくらいならまだしも、ハイビジョン放送に対応してW-VHSなる規格を発表するなど、VHSにこだわりすぎた。世の中は、CDの発売以降、テープからディスクへと、大きく舵を切っていった。その流れにビクターは乗ろうともしなかった。成功体験が失敗要因になる典型的パターンだ。
90年代半ば以降、ビクターの業績は急速に悪化していく。松下電器も社長を送り込むなど、立て直しに本腰を入れるが、VHSを開発したという“自信と誇り”が松下なにするものぞという社風を生み、親会社の介入を容易に許さなかった。そのため、90年代後半には、ビクターの処遇が大きな経営課題としてのぼるようになる。
シナジー効果はほとんどない。しかも赤字企業で前途が見えない。しかし松下電器にとって、幸之助が買収を決めたビクターを、現経営陣の判断で売却するなどできることではなかった。結局、松下電器がビクターとの関係を見直すのは、幸之助の導入した事業部制を見直した中村邦夫社長の登場を待たなければならなかった。
07年、日本ビクターはケンウッドと資本提携、ついに松下電器の子会社でなくなった。さらに翌08年10月1日、ビクターはケンウッドと経営統合し、JVCケンウッドが誕生する。奇しくもこの日は、松下電器がパナソニックへと社名変更した日でもある。こうして長年続いた、松下とビクターの関係に終止符が打たれることとなった。
ビクターとケンウッドの経営統合には、当初、壮大なる目標があった。
「いつの間にか日本の電機メーカーは競争力を失った。これを復活させる責務が我々にはある。最初はケンウッドとビクターの2社から始めるが、もっと仲間を増やしていき、日の丸電機の象徴のような会社にしたい」と統合会社の社長に就任した河原春郎氏は語っていた。
ところが、この構想は画餅に終わる。統合直前のリーマン・ショックもあって、日本の電機メーカーはさらに苦境に追い込まれる。JVCケンウッドも自らが生き残るのに必死で、中堅メーカーの受け皿になることなどとてもできなかった。統合当時、ビクターとケンウッド合わせて8000億円あった売り上げは、いまでは3000億円程度。かつてビクターはVHSだけでなく、テレビ市場でもそれなりの存在感を保っていたが、いまではそれらの製品は残っていない。民生品で残っているのはカーナビと、廉価版のカムコーダー(ビデオカメラ)ぐらいなもので、あとは業務用無線などB2Bが主体となっている。ビクターという旧社名を聞くこともほとんどなくなった。会社としては残っているものの、VHSで天下を取った、栄光のビクターはすでにない。

2002年、会社清算を発表するアイワ首脳陣。
ソニーの子会社だったアイワも、消えた1社だ。アイワもソニーと同じく、戦後すぐに誕生した音響メーカーだった。1969年にソニーと資本提携。無骨ながら堅牢なデザイン、品質の割には廉価ということもあり、市場では存在感を示していた。
85年のプラザ合意後に進んだ円高に対処するため、日本の電機メーカーの中ではいち早く海外に製造拠点を移設。これが奏功し90年代初めには、円高対応に成功した企業として評価も高かった。また、テレビとビデオが一体化したテレビデオを真っ先に市場に投入するなど、ニッチながらユニークな商品が消費者に受け入れられ、業績も好調だった。
誤算は、急速なデジタル化の進行だった。これは、どの電機メーカーも直面した問題だが、アイワは研究開発型企業ではなく、生産合理化によって市場に食い込んできた企業である。社内にデジタルがわかる技術者はおらず、デジタル化の波に完全に乗り遅れてしまった。しかも価格競争力が最大の武器だったが、韓国・台湾メーカーの台頭とともに競争力を失っていった。
結局、親会社のソニーは、2002年にアイワを吸収合併。企業としてのアイワは消滅する。当初、ソニーはアイワを第2ブランドにすることで商標の存続を図ろうとしたがそれもかなわず、いまでは、ブランドを含め跡形も残っていない。
それでも、以上見てきたような、電機メーカーの中でも比較的規模のある会社の場合は、その終焉を含めて人々の記憶に残っているだけでも幸せと言うべきなのかもしれない。
この20年の間に、人知れず消えていった電機メーカーやブランドは数多くある。
かつて日本のオーディオメーカーは、会社の規模は小さくても、世界中にファンを持っていた。また、ユニークな製品づくりでファンを獲得してきたメーカーもあった。
山水電気もそうした会社の1社だった。「サンスイ」ブランドは、オーディオファンの間でも人気が高かった。ところが、CDの登場から始まったデジタル化によって業績は悪化していく。生き残りのために外国資本を受け入れ、1991年には香港企業に買収された。しかしそれでも業績は好転せず、2000年代に入ると、ほとんど営業活動を行っていないにもかかわらず上場だけは維持し、株価だけが数円~数十円の間を行き来する不思議な存在となっていた。しかし2012年、民事再生法を申請し倒産した。外国資本に買収された時は、日本ブランドの海外移転として話題になったが、その倒産劇はほとんど注目されることもなかった。静かすぎる幕引きだった。
このほかにも、赤井電機やナカミチも海外企業に買収されている。両社はまだ存在し、いまなお音響機器を販売しているが、赤井はオーディオよりも浄水器販売が主力となるなど、昔の面影は残っていない。
このほかにも、数多くの電機メーカーが、この20年の間に姿を消した。そして今後も、この流れは変わらないだろう。一昨年、シャープの存続が危ぶまれたように、大企業でもいつ危機に陥らないとは限らない。
共通するのは、自らのブランドと技術力に対する過信であり、一時は世界を支配したという驕りである。だからこそ、デジタル化が進んでも、円高が進み新興国メーカーが台頭しても、自らの優位性を疑わなかった。いずれ環境が好転すれば再び成長路線に戻れると甘い見通しを持ち続け、決断を遅らせることになった。
たとえば三洋電機なら、かつてデジカメのOEM供給で世界をリードしたように、自らのブランドにこだわらない路線を選ぶこともできたはずだ。しかしその決断はできなかった。ビクターでも、プライドを捨て、親会社の松下との一体化を進めるなどの選択肢もあった。
タラレバを言っても意味がないかもしれない。しかし、間違いなくもっといい形で生き残る選択肢はあったはずだ。すべての電機メーカーが他山の石とすべきところである。
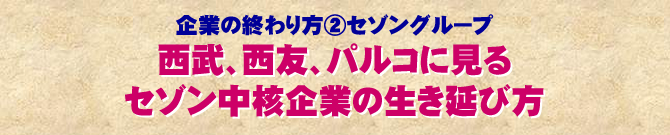
「詳細はまだ未定ですが、2月末に行うことになる予定です」
語るのは、セゾン文化財団幹部。行う予定とは、2013年11月25日に86歳で他界した、セゾングループ総帥だった堤清二氏のお別れの会のこと。生前、同文化財団で理事長を務めていた清二氏だが、お別れの会はセゾングループの中核会社だった企業との「合同の会」になりそうだ。かつては同じグループだった企業群のトップや幹部が、資本関係を離れてから一堂に会する機会は、これが最初で最後かもしれない。
元を辿ると、西武グループを築いた堤康次郎は、清二氏の義弟にあたる義明氏のほうに本業の鉄道事業を継承させ、併せてグループ資産の多くを義明氏が受け継いだ。逆に清二氏はスタートから、引き継いだ流通企業拡大のために多額の借金を余儀なくされたといえる。一方で、小説家の辻井喬と経営者としての堤清二という2つの顔を持ち、消費に「感性」といった文化的側面を持ち込んだという点で、清二氏は不世出の事業家といっていい。

西武百貨店を核に多様な流通集団を形成したセゾングループ。
時計を巻き戻してみよう。ちょうど30年前の1984年、セゾングループは絶頂期を迎えていた。前年の83年には百貨店の店舗別売上高で西武百貨店池袋本店が初めて日本一の座に就き、その余勢を駆って84年、清二氏の悲願でもあった銀座エリアへの出店、すなわち有楽町西武が誕生している。さらに翌85年には、西武流通グループからセゾングループへと呼称も変更した。
セゾンはフランス語で季節を意味するが、この頃までがセゾングループにとって“盛夏”だったといえる。それ以後のバブル期は、セゾンの感性路線云々というよりも、よく言えば総合生活産業、悪く言えば、清二氏に潜在的な破滅願望があったとしか思えないほどの膨張路線に舵を切っている。
その最たるものが、88年に2800億円もの巨費を投じて買収した、インターコンチネンタルホテルチェーンだった。そのほか、共同出資でジャガージャパンを設立したほか、西武自動車販売がフランスのシトロエン、プジョー、スウェーデンのサーブなどの輸入販売元になるなど、自動車販売にも傾倒している。
この時期、清二氏にはすでに“秋風”が忍び寄り始めていたのかもしれない。
その後、バブル崩壊によって91年頃から足掛け10年にわたって、セゾングループは“厳冬期”を過ごすことになる。過酷なリストラの果てが、住宅や商業施設、リゾート開発などの不動産業を手がけた、西洋環境開発の2001年の清算である。前後して、セゾングループの中核企業はほかの企業の傘下に入っていくことになり、いまも独立系として存続しているのは、クレディセゾンと良品計画ぐらいしかない。

堤 清二氏
そこで、ここからは中核企業のうち西武百貨店、西友、パルコを順に見ていこう。
まず西武百貨店だ。西友やパルコが株式上場していたのに対し、長男格の西武百貨店は未上場企業で、もともと財務内容がわかりにくかった。一時期、医療機器架空売り上げ事件が発覚するなど、特に外商部門はでたらめな経理操作も露呈した。さらに、バブル崩壊で債務危機に陥った前述の西洋環境開発の負債が西武百貨店に重くのしかかる。
それでなくても西武百貨店自身が債務過多で財務体質が脆弱だったことに加え、97年以降毎年、百貨店業界全体が前年の売上高を下回るようになり、西武百貨店の経営は追い詰められていった。それゆえ、堤清二氏と西武百貨店首脳がメインバンクを巻き込んで対峙し、清二氏はけじめをつけるため、100億円の私財拠出を強いられもしている。
西武百貨店の再編は2段階を踏んでいる。西洋環境開発が清算される前年、やはり膨張経営の果てに破綻したそごうの再建請負人に、西武百貨店の大リストラを指揮した和田繁明氏が就任、その後、03年に百貨店業界初の持ち株会社、ミレニアムリテイリングの傘下にそごう、西武百貨店が入る。
一方で、百貨店業界では大丸と松坂屋の統合(=Jフロントリテイリング)、三越と伊勢丹の統合(=三越伊勢丹ホールディングス)と再編が相次ぎ、結果的には破談になったが、髙島屋とH2Oリテイリング(傘下に阪急百貨店と阪神百貨店)も統合交渉を行ったほど。

堤 義明氏
こうなると、そごう・西武百貨店連合の存在感は後退してしまう。ルーツから言えば西武鉄道の傘下に入ることも選択肢の1つではあったが、その西武鉄道が04年秋、有価証券報告書虚偽記載事件を起こし、同社は上場廃止となる。06年に西武ホールディングスが発足するまで、こちらもコクド、西武鉄道、プリンスホテルの3社の資本再編の渦中となり、ミレニアムリテイリングを引き受けるどころではなくなった。
そして05年の年末、同年に持ち株会社を発足させたばかりのセブン&アイ・ホールディングスがミレニアムリテイリングを買収すると電撃発表。翌年、ミレニアムリテイリングはセブン&アイHDの完全子会社となった。
そごうや西武百貨店がセブン&アイ傘下となって幸せだったのかどうかは、まだわからない。
というのは、百貨店という業態自体が急速に退潮していったことが1つ。もう1つは、巨大流通企業となったセブン&アイHDのバイイングパワーによって、そごうや西武百貨店にもプライベートブランドの「セブンプレミアム」を導入、百貨店の生命線である衣料品売り場にもPB商品を導入したものの、劇的な成果を上げるまでには至っていないからだ。
そごう・西武百貨店を占う意味ではむしろ、これからが注目といえるだろう。理由は昨年末、セブン&アイHDが、米国の高級衣料品ブランド「バーニーズ・ニューヨーク」を手がけるバーニーズジャパン、さらにセレクト雑貨ブランドの「フランフラン」を手がけるバルスに、それぞれ49.9%、49%を出資すると発表したからだ。
バーニーズのほうは百貨店業との、フランフランは西武百貨店グループでやはりセブン&アイHD傘下になった雑貨専門店のロフトとの、それぞれシナジー効果を上げるのが狙いだろうからだ。
次男格の西友はどうだろう。西武百貨店における西洋環境開発同様、西友にもグループの負債がずしりとのしかかった。グループノンバンクの東京シティファイナンス、さらに前述のインターコンチネンタルホテルは西友の管轄。西友は上場していたものの、財務基盤の弱さは西武百貨店と似たようなもの。インターコンチネンタルホテルの持ち株放出はもちろん、優良子会社のファミリーマートを伊藤忠商事に売却し、元は西友の一事業部だった良品計画の株も手放さざるを得なくなった。
西友のルーツは西武ストアーで、その後西友ストアー、西友へと社名を変えていったが、上場してグループを牽引しているのは自分たちだという意識や自負も強かったのだろう、西武百貨店とはある種、近親憎悪に近い感情を抱いていた時期もあった。
実際、たとえば錦糸町西武など、西武を冠した店舗の中味が実は大型の西友だったというケースがいくつか見られ、消費者が混同したりもした。その後、大型店の名称は「LIVIN」に統一されはしたが、マーケティングの迷走は否定できなかった。そして2000年、10%に満たない持ち株ながら一度は住友商事が筆頭株主に躍り出る。が、翌01年には早くも米国のウォルマートと資本提携を発表、02年からウォルマートが筆頭株主になっている。
EDLP(エブリデイ・ロー・プライス)の元祖といえるウォルマート流の注入は、西友に壮絶なコスト低減を迫った。結果、04年には1600人の希望退職を募り、05年に完全子会社化。さらにTOB(株式公開買い付け)で上場廃止となったほか、09年からは株式会社を廃止して「合同会社」に変わっている。
西友の場合も、身売り先がウォルマートで正しかったのか否か、まだ答えは出せない。ウォルマート流を徹底するには西友のスケールでは足りず、ウォルマートがダイエー獲りに動いたこともあったが不調に終わり、バイイングパワーという点でイオン、セブン&アイHDの2強に遠く及ばない。この2強が、バーチャルとリアルをシームレスにつなぐオムニ(あらゆる)チャネルを宣言できるのは、コンビニや金融など、グループの店舗インフラやサービスを総動員できるからだ。
西友の場合、クレジットカードこそウォルマートカードを発行しているものの、店名をウォルマートにするでもなく、規模的にもマーケティング的にも中途半端な印象は否めない。業界4位のサークルKサンクスを持つユニーグループでも厳しい状況だけに、西友、というよりウォルマートは、日本市場にこのまま踏みとどまるのかどうか、どこかの段階で判断を迫られるのではないか。そうでなければ大型のM&Aで規模を拡大するしかないが、前述の2強があまりに大きくなり、切れるカードはそんなに多くないのが実情だ。
ここまで西武百貨店、西友と見てきたが、ここから取り上げるパルコの場合は少し異質だ。会社を揺るがすほどの負の遺産を背負いこんだわけでもなく、業態も商業ディベロッパーで、平たく言えば売れ筋のショップを入れ替える専門店ビル企業だからだ。70年代後半から80年代前半、セゾングループが感性路線でピークを迎えた頃、グループの代名詞が渋谷のパルコだった。
が、時代の変遷やバブル崩壊後のグループの疲弊も重なり、パルコに往年の輝きがなくなっていく。むしろ、専門店ビルとして伸張したのは、JR東日本グループの駅ビル専門店ビル、ルミネである。パルコもまた、グループが瓦解して資本関係を解消していく過程で新たな株主を迎える必要性に迫られた。
そこで筆頭株主になったのが森トラストだった。同社にすれば専門店ビルの運営ノウハウを吸収する狙いもあったのだろうが、パルコ経営陣が、大株主の森トラストを無視した増資という暴挙に出たほか、イオンも株を買い増すなど、ここ2年ほどは混乱が続いてきた。継続保有に意義を見出せなくなった森トラストは持ち株をJフロントリテイリングに売却、その後、同社の子会社として今日に至っている。
Jフロントリテイリングは、百貨店の中では早い段階で場所貸し業的な立場を鮮明にし、売れ筋ショップを入れることに注力してきただけに、パルコを自陣営に取り込んだのは理解できる。傘下の大丸や松坂屋も、本店や準本店級の大型店を除けば“パルコ化”が進むのかもしれない。ただしパルコのみならず、衣料品や雑貨を主力とする業態は、ファストファッションやネット通販の浸透で厳しい戦いが続くのは必至。店舗の「ショーウインドー化」も、家電量販店の話だけではない。
5年半ほど前、堤清二氏は辻井喬名で、東大大学院教授の上野千鶴子氏と対談形式の本を上梓している。内容は、セゾンの築城から落城までの検証だが、その中で辻井氏は「経営者という役柄は自分の性にあんまり合っていないなと、自分では感じていました。それでいていろいろ投資してきたことは自分で矛盾していたと思います」と吐露している。当時、この共著について本誌のインタビューで上野氏もこう語っていた。「バブル崩壊後、多くの経営者が後退戦を余儀なくされましたが、セゾンの場合、つんのめり方にも“個性”が出たという印象があります」
瓦解してしまったセゾングループだが、堤清二氏が生み、育てた企業が“とんがっていた”ことだけは語り継がれていくだろう。
(本誌編集委員・河野圭祐)
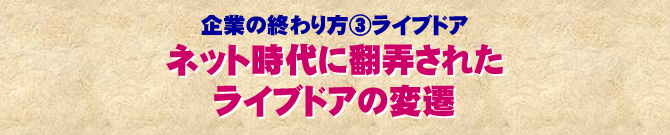
ライブドアと聞いて、最初に連想されるものは何か。おそらく、元ライブドア社長の堀江貴文氏の顔ではないだろうか。
堀江氏がライブドアの社長を退任したのは、もう8年も前のことだ。それでもなお堀江氏の印象が強いのは、その登場から散り方まで、ライブドア=堀江氏が社会に与えたインパクトが強烈だったからだろう。
ここではその堀江氏ではなく、ライブドアそのものにスポットを当ててみたい。その名はあまりに興味深い運命を辿っている。

ライブドア時代の堀江貴文氏。(2004年撮影)
もともと、株式会社ライブドアを立ち上げたのは、前刀禎明氏。ソニー出身で、ライブドア社長退任後も米アップルで携帯音楽プレーヤー「iPod mini(アイポッドミニ)」を仕掛けるなど、事業家として活躍している人物だ。
前刀氏がライブドアを創業したのが1999年のこと。まだ電話代もプロバイダー料金も従量制だったインターネット黎明期に、接続料無料のISP(インターネットサービスプロバイダー)をスタートさせ、従来にはなかったサービスとして高い注目を集めた。運営収入は広告で賄い、電話料金だけでネットに接続できるというビジネスモデルは、画期的だったと言えるだろう。ネットの普及と相俟って、会員数も急速に伸びていった。
2000年代になると「無料プロバイダー」を標榜するサービスを展開するライバル企業も出てきた。しかしライブドアも会員数を順調に増やし、01年5月には100万人を突破。無料ISPとしては最大手、有料プロバイダーを含めても7位と、大手プロバイダーの仲間入りを果たしている。
だが、経営としては安定軌道に乗れなかった。その理由の1つとして挙げられるのが、孫正義社長率いるソフトバンクのヤフーBBの大攻勢だった。ブロードバンドという言葉とともに、回線はISDNからADSLにシフトしていく。この波にライブドアは対抗できなかった。02年10月、ライブドアは民事再生手続き開始を申請。負債総額は約16億円だった。この時、事業を引き継いだのが、堀江貴文氏のオン・ザ・エッヂだった。
ちなみに、同時期に無料プロバイダー「ZERO」としてサービス展開していたゼロも経営不振に陥っている。ISP事業は04年にGMOインターネットに売却、会社そのものはスカイマークエアラインズ(現スカイマーク)に吸収された。厳密には、ゼロ創業者の西久保愼一氏がスカイマークに出資し、同社の社長に就任することで、ゼロの損失を解消させるために吸収したとも言える。これも一つの企業の終末としては興味深いドラマだろう。
さて、ライブドアの事業を引き継いだ堀江氏は、当初、無料ISP事業をコンテンツの1つと考えていた。ライブドアはあくまでサービスのブランド名だった。堀江氏は03年4月、オン・ザ・エッヂをエッジに社名変更している。この頃の堀江氏は、積極的にM&Aに手を伸ばしていた。ITバブル崩壊から2~3年というのは、「ビジネスをやめたい」と考えるベンチャー経営者が多かったからだ。ITバブル以降の急激な変化に耐えられず、高コスト体質のネットベンチャーが増えていた。安いコストで買収し、自社のインフラに乗せて固定費を減らし、グループシナジーを高めるという堀江氏の戦略は理にかなっていた。
堀江氏はエッジへの社名変更の際、「最初から大きくやろうとするから失敗するんですよ。ひとつひとつは小さくても、手堅く仕掛けることで、着実に収益に結びつく」とメディアによく語っていた。いま振り返ると、何とも不思議な気分になる。
しかし、堀江氏は再び社名変更に踏み切る。エッジへの変更から1年も経たない04年2月、ライブドアに社名変更したのだった。
エッジはもともと、オン・ザ・エッヂ時代からデータセンターに強みを持ち、「DATAHOUSE」というサービスを軸にしていた。これをポータルサイト「ライブドア」を軸にしたポータルサイト事業に本腰を入れるために社名変更に至った。これによりライブドアブログ、ライブドア掲示板など、メディア事業にも注力。同社のサービス名にはすべて「ライブドア」が付くようになっていく。
社名変更早々の2月、証券会社から近鉄球団買収の話が持ちかけられた。これは具体的な話ではなく、近鉄球団の窮状を示したものだ。買ってくれるところがあれば売ってもいいという状況だったのだろう。
日本プロ野球の04年シーズンは激動の1年だった。近鉄は当初、相手はともかく売却の意思があったと思われる。そこに1リーグ化を画策する球団が現われ、近鉄は売却ではなくオリックス球団との統合で話が進められていた。そこに割って入ったのがライブドアだった。
6月30日、ライブドアは記者会見を開き、近鉄に対して、買収の意思があることを伝えたと発表した。ポータルサイト事業に注力しようという時、プロ野球ほど認知が高まるコンテンツはない。堀江氏ら経営陣は、何としてでも参入を果たしたかった。しかし、黒いTシャツ姿で会見に現われた堀江氏の姿は、奇異の目で見られた。タラレバではあるが、もしこの時にスーツにネクタイ姿で会見に臨んでいたら、球界参入の可能性が少しは高まっていたかもしれない。近鉄はオリックスとの合併を選び、売却の意思がないことをライブドアに伝える。そこでライブドアは近鉄消滅によって空いた1枠に新規球団として参入する希望があることを8月に表明した。
結局、三木谷浩史社長の楽天に敗れ、球界参入はならなかったものの、この件でライブドアは爆発的に知名度を上げることができた。社名変更から1年で、名を知らぬ者はないほどの宣伝効果をあげ、ライブドアブログの利用者も爆発的に増えて、一躍時代の寵児となった。
05年、勢いに乗ったライブドアは、さらにM&Aを加速させる。3月にはニッポン放送の株式をの49.8%を取得、株式を巡る激しい戦いを通して、TOB、ホワイトナイトといった経済用語を社会に浸透させた。しかし同時に、ライブドアはヒールとしてのレッテルを貼られるようになってしまう。
この年、初代ライブドアから譲渡された無料プロバイダーのサービスを終了したが、中古車のジャック・ホールディングス、通販のセシールなどを買収。業容はどんどん拡大していった。敗れはしたが堀江氏は9月の衆議院選挙で立候補(広島6区)するなど、調子に乗っていた時期とも言えなくはない。必要以上に目立ちすぎると、目をつけられてしまうものだ。
06年1月16日、証券取引法違反容疑でライブドア本社と堀江氏の自宅等に家宅捜索が入った。ライブドア事件の始まりだった。24日には平松庚三氏がライブドア社長になる。取締役ではない異例の社長就任だった。堀江氏がライブドアという社名で社長だった時期はわずか2年しかなかったのである。
その後の堀江氏は、懲役2年6カ月の実刑を受け、2013年11月10日刑期を満了した。

宇野康秀USEN社長(左)が個人で95億円出資したことも。右は当時の平松庚三社長(2006年)
堀江氏が去ったライブドアは、凋落の一途を辿った。ポータルサイトの広告収入も7割落ち、06年4月の上場廃止後は、子会社の売却を次々と進め、解体されていった。07年4月、ライブドアは持ち株会社化され、ライブドアホールディングスに社名変更された。傘下には事業会社として新たにライブドアが設立された(3代目)。そのライブドアHDは08年8月にLHDに社名変更し、グループの再編、解体を担った。
主な子会社の動向を見ると、ライブドアグループの中核事業だったライブドア証券は06年、かざかフィナンシャルグループの100%子会社になり、07年にはかざか証券に商号変更している。オンライントレード事業は09年にオリックス証券に売却され、そのオリックス証券も10年5月にマネックス証券と合併している。かざか証券の対面部門は現在も存続し、内藤証券の100%子会社になった。
中古車のライブドアオートは売却後、事業は継続されているものの、4度も商号を変え、親会社も転々と入れ替わっている。現在の社名はカーチスホールディングス。筆頭株主はKABホールディングスとなっている。通販のセシールは09年7月にフジテレビがTOBをかけ、完全子会社化。現在はディノス・セシールとして経営統合されているが、サービスとしてのセシールブランドは残された。
株主も変動し、06年3月、フジテレビが持っていたライブドア株12.75%(約95億円)をUSEN社長だった宇野康秀氏が個人で取得。USENとは業務提携したが、大きな成果は得られなかった。宇野氏はその後、07年8月にモルガン・スタンレー証券にライブドアHD株を売却している。
また堀江氏自身が持っていた株も、ライブドアHDから損害賠償請求を起こされた際の和解として、09年12月にLHDに引き渡されている。

森川亮LINE社長。ライブドアの名でサービスを展開している。
10年5月、3代目ライブドアの全株式を韓国資本のNHN Japan(現LINE)が取得した。これに伴い、LHDは11年8月に会社の清算決議を行ったが、まだ訴訟が残っていたことから、いまも解散できずにいる。
3代目ライブドアは、12年に株式会社データホテルと社名変更された。ポータルサイト等のコンテンツ事業はNHN Japanに移管され、現在もポータルサイトとして“ライブドア”の名称が使われ続けている。ライブドアブログも健在。コンテンツ事業を除くデータセンター、ISPサービスなどのインフラ事業がデータホテルで運営されている形だ。奇しくもオン・ザ・エッヂ時代のインフラ事業のサービス名が継承されているのが興味深い。
NHN Japanは13年4月にLINEと社名変更。無料ISPでネット社会の扉を開いたライブドアは、企業としては消滅したものの、無料通話アプリの会社でその名前が受け継がれている。
(本誌・児玉智浩)
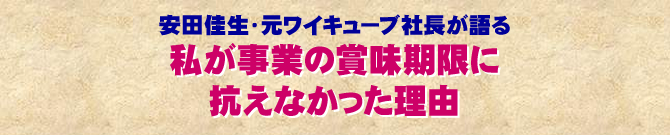

安田佳生 元ワイキューブ社長
やすだ・よしお 1965年大阪府堺市生まれ。18歳で渡米、オレゴン州立大学卒業後、88年リクルート入社。90年ワイキューブを設立、代表取締役に就任。採用コンサルティング事業を展開するも、2011年3月に経営破綻。現在は“境目研究家”として執筆活動等を行っている。著書は『千円札は拾うな。』(06年)、『採用の超プロが教える できる人できない人』(03年、いずれもサンマーク出版)『私、社長ではなくなりました。』(12年、プレジデント社)、『疑問論 なぜ今日も会社に向かってしまうのか?』(13年、ぼくら社)等多数。
2011年3月30日、経営難を理由に民事再生法の適用を申請し、経営破綻したワイキューブ。中小企業向けの新卒採用コンサルティング企業として名を馳せたが、20年で企業活動に終止符を打った。元ワイキューブ社長の安田佳生氏は発行部数30万部を突破した『千円札は拾うな』など、ベストセラー作家でもある。その安田氏に企業の終わりについて語ってもらった。
企業が永続することが正しい、というのが一般的な人の意見でしょう。でも私はそういうふうには思っていません。事業には必ず賞味期限があるからです。
以前、不二家でコスト削減のために賞味期限切れの牛乳を使うという不祥事が起きました。かつて不二家には、日本全国に美味しい洋菓子を届けるというミッションがあったからこそ規模が拡大できたと思いますが、いまや日本全国いたるところに洋菓子店があるなかで、その役割は終えてしまっていたわけです。無理に存続しようと思うとコストを下げて利益を出さなくてはならなくなるので、前述のような不祥事が生まれてくるわけです。企業を存続させようと思えば、新たな別の事業、別のミッションに転換していかなくてはいけません。
富士フイルムのように、うまく事業を転換していくという例はありますが、本来、会社というのは一つの事業を行うために人を集めています。事業がまったく変わってしまうのであれば、人も変わらなくてはいけない。大手企業がものすごいリストラをやっているでしょう。これはやらざるを得ないんです。いままでと仕事の中身が違うわけですからね。
もし私に社員を総入れ替えする覚悟があれば、ワイキューブを潰さずに続けられたと思います。でも、そんなことをする意味がわからなかったし、社員を含めて会社だと思っていましたから、できなかった。そこを割り切れる人でないと、ビジネスモデルを変えて会社を継続させていくのは難しいのではないでしょうか。
私が社長として20年間経営した間に、何度も潰れそうになりました。表立って発表しているのは2、3回ですが、潰れそうになかった時期のほうが短い。
私たちは知名度を上げるのがすごく上手かった。社内にビリヤード場をつくるなど、メディアに取り上げられるような仕掛けをしていました。これにより、2000年代前半は売り上げも伸び、新卒採用の需要もあって、新入社員でも、いきなり新規で1500万円くらいの仕事を取ってくることが普通に行われていたのです。この時、私はとにかく社員の給料を社長並みに高くしたいと思っていた。売れていることもあって、商品をさらによくしていくとか、改善していくほうに力を入れず、社員の平均給与を750万円まで上げましたが、そこで力尽きた。
直接的には、リーマン・ショックがキッカケでした。売り上げが2年で3分の1にまで落ちたんです。もうどうしようもない。でも実は、その前から緩やかに売り上げは落ちていたのです。すでに新卒採用のコンサルで成長できる時代ではなかった。仮にリーマン・ショックがなかったとしても、存続できていたのかはわかりません。最終的には、自分のつくった新卒採用のコンサルティングというビジネスモデルが終わりを迎えていたのです。
いまや小さい会社でも新卒採用を行うようになり、採用には社長が前面に出るといったノウハウも、当たり前のことになってきました。私たちが声をかけたことによって、5000社くらいは新卒採用を行ってくれたと思います。ワイキューブという会社の当初のミッションは終わっていた。
経営破綻の前、ビジネスモデルの限界を感じていた私たちは、ワイキューブの強みは採用だけでなく、中小企業に新しい価値を提供することだと、企業のブランディングにビジネスを切り替えようとしたわけですが、採用をコンサルするために集めた人材と、ブランディングをコンサルするために集めた人材はやはり違う。彼らは、採用はできたけども、ブランディングはできなかった。
新卒で優秀な人材を採ることについて、会社のビジネスモデルまで踏み込んで、組織をどう変えていくのか、ビジネスモデルをどう変化させていくのか、そのためにどういう人材を採るのか、というコンサルをしていれば、ワイキューブは潰れなかったと思います。残念ながら、我々はそのレベルのコンサルではなかったということですね。いずれ破綻する運命だったのでしょう。
余談ですが、いまだからこそ、正直にネタばらしをすると、当時、ワイキューブの社員は優秀な人が多いと、よく中小企業の社長に言われました。実は、中小企業の社長から見て、優秀そうに見えるヤツを集めていたんです。
目の前にワイキューブの1年目の社員が来る。社長は自分のところの社員と比べて、なぜコイツは社会に出て1、2年目でこんなに立派なんだろうと思う。ウチにも欲しいということになったら、「新卒採用をやるしかないですよ」ともっていける。いらないと思っていても、潜在的に欲しかったものが目の前に現れると、やはり欲しいと気づくわけです。中小企業の社長から見て、コイツはできそうだと思えるタイプはだいたい想像がつくでしょう。
ワイキューブは終わりを迎えましたが、採用自体がなくなるわけではなく、新卒採用をやりたいという中小企業のニーズはまだあります。社員もいましたし、採用でしかやっていけない人もいる。また採用を頼まれているお客さんもいました。これは残さねばならないと思いました。事業譲渡という形で、カケハシソリューションズという会社に残すことができ、これらがきちんと残ってくれたことで、私的には悔いはありません。自分で会社をつくって、やりたかったことは全部やりつくした感があるので、もういいですね(笑)。
現代は、会社の規模が大きくなるということが、安定とは正反対のものになっています。電機業界は家電が売れないとリストラばかりしていますが、仮に全社員を残してまったく違うことをやろうとしても、それだけの人員が賄えるマーケットをゼロから作るのは無理です。人数が多ければ多いほど、融通の利かない組織になる。仮に5人くらいなら、まったく別のことを始めるのも可能ですが、100人、200人の規模になれば、もう無理でしょう。安定という意味では、いまは小さなことが大事になっています。
だから中小企業は変化しやすいはずなのですが、現実的には中小企業の経営者ほど頭が固く、固執してしまう。小回りが利くはずなのに、何十年も同じ仕事を同じやり方でやって、ちょっとずつ売り上げが下がっていく。
多くの経営者は、他の人がやっているのをマネしているだけで、自分の売り方や独自の商品を考えている人は少ない。
企業を存続させるには、大胆なビジネスモデルの転換、もしくは事業のやり方に対する絶え間ないイノベーションが必要です。それができなければ企業の寿命は終わりを迎えるということでしょう。(談)
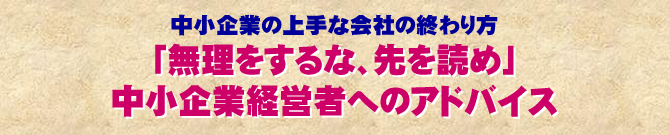
残念ながら、どんなものにも寿命はある。人間でもしかり、会社でも同様だ。
一時、「会社寿命30年説」という言葉がよく使われた。成長期10年、成熟期10年を経て最後の10年は衰退期に向かうというものだ。これは、企業経営者の年齢とも関係してくる。30代で起業した場合、若いだけにどんな無理もきく。40代に入り成熟期を迎えるが、徐々に経営者自身が保守的になってくる。創業から30年がたつと経営者も60歳。すでに老境に入りつつあり、新しいチャレンジはむずかしい。同時に会社も衰退に向かう、というわけだ。
この30年の寿命を乗り越えて発展し続けるには、不断の努力と時代の恩恵、そして創業者の意思を引き継ぐ継承者がいなければむずかしい。
特に中小・零細企業の場合、企業体力はないうえに、会社の存続自体が経営者自身の双肩にかかっている場合が多いため、これを継続するには大企業以上の努力と幸運が必要になってくる。
すべての企業が、その幸運にあやかるのはむずかしい。そうであるならば、最悪の事態を想定して、上手な企業の終わらせ方を考えるのも、経営者の責務である。
経営者の最大の使命は、企業を存続させ発展させていくことだ。それだけに大半の中小企業経営者は頑張りすぎてしまう。しかしそれが結果的に最悪の結末を招くことも多い。
たとえば、これまできちんと利益を出していた会社が赤字に陥ったとする。ほとんどすべての経営者は、なんとかして苦境を乗り切ろうと努力する。特に高度経済成長時代を知っている経営者なら、いずれ景気はよくなる。それまでの辛抱だと、自己資金をつぎ込みながらも、状況が回復するのを待つというのがよくあるパターンだった。
しかしながら、バブル経済が破裂してからのこの四半世紀は、そんな過去の常識が通用しない時代になった。むしろ「頑張りすぎる」ことの弊害が目立つようになったのだ。
黒字だった会社が赤字に転落した直後なら、債務超過になっていることもなく、資金的蓄積も多少なりともある。もしこの段階で会社を清算してしまえば、社員には退職金を払うこともできるし、再就職の斡旋も可能となる。
何より経営者自身が、多少のたくわえを持って引退することができるため、豊かな老後を暮らせるし、やる気があるなら、再チャレンジすることもできる。
ところが「頑張りすぎる」と資金を調達するため、金融機関から借り入れることになる。当然、金融機関は担保を求めるため、経営者は個人資産を差し出さなければならない。それで業績がよくなればいいが、最悪の場合、あがくだけあがいて倒産という末路を迎えることになる。こうなると悲劇である。金融機関は担保権を行使するため、経営者は倒産と同時に無一文になり、住むところさえ奪われてしまう。そこまでせっぱつまった状況では、会社にキャッシュがあるはずもなく、社員に対して退職金も払うこともできずに解雇することになる。経営者も社員もみな不幸になる結末だ。
このような不幸を避けるためには、もっと早い段階で見切りをつける必要がある。そうすれば、経営者も社員も不幸にならないような形で会社を終わらせることができる。
ひと口に会社を終わらせるといっても、いくつものやり方があるが、中小企業の場合、
(1)M&A
(2)分割
(3)民事再生法
(4)清算
(5)破産
が主なケースである。
M&Aは、企業をまるごと他社に買ってもらおうというものだ。経営者は売却資金を手に入れることができるし、従業員を守ることができる。ある意味、いちばんベストな会社の終わらせ方と言えるだろう。

中小企業の経営を数多く見てきた本郷孔洋理事長。
ただし、『会社整理・清算・売却・合併・分割マニュアル』という書籍の監修を務めている辻・本郷税理士法人理事長の本郷孔洋氏(公認会計士)によると「中小企業の中でM&Aの対象になるような企業はほんの一部でしかない。大半の企業は、売りたくても売れないのが実情です」というほど現状は厳しい。もっとも、考え方を変えれば、買い手がつくように、会社の強みを発揮できる企業であるべく、常日頃から努力しておくことが必要になってくる。
個人の場合でも、絶対的なスキルを持っていれば再就職はむずかしくない。それと同じことである。
また、会社まるごとを売ることができなくても、一部の事業部門だけを譲渡するケースもある。
(2)分割は、第二会社方式と言われるもので、現在ある債務は現在の会社に残したまま、新会社を設立し、事業を新会社に譲渡するというものだ。新会社は利益の一部を旧会社に支払い、旧会社はそれを返済に充てる。また旧会社は債権者に対し債務の減免を求めていくというものだ。
(3)の民事再生法は法的整理だが、雇用が確保できると同時に、経営者も存続できるのが最大の特徴だ。ただし債権者集会で承認されることが前提となるため、しっかりとした再建計画が必要だ。
(4)、(5)は、本当の意味での会社の終末である。どちらの場合でも、組織も社員も残らない。
(4)清算は、債務超過に陥ってない企業の終わり方。単純に資産から負債を引いて、残った資産は株主に還元する。
(5)破産は債務超過の会社の終わらせ方。経営者自身が会社の連帯保証人になっていた場合、経営者個人も破産しなければならないケースが多く、できれば避けたい会社の終わらせ方だ。
ただし現在、年間に13万件ほど、中小企業が倒産しているが、圧倒的に多いのが、破産によるものだ。
「経営者というのは、みなヘトヘトになるまで頑張ってしまうものです。ピカピカの企業の終わり方を選ぶことなど、ほとんどないといっていい。そして最後になると、やめたくてもやめられない状況になってくる。
会社をたたんだところで、残るのは借金だけ。再就職しようにも、経営者というのは経営以外のことはあまりできないので、就職先をみつけるのもむずかしい。だから必死になって頑張っている。それが多くの中小企業の実態ではないですか」(前出・本郷理事長)
現実は厳しい。だからこそ、自分の事業を客観的に見ることが、経営者には求められる。
「中には、先を見据えて上手に会社を終わらせた経営者もいますよ。徐々に社員を減らしていって、最後はフェードアウトするように会社を清算した。資産を残すことにも成功し、幸せな老後を送っています」(本郷理事長)
では、どうやったら、客観的な判断を下すことができるようになるのだろうか。中小企業経営者にとっては、それが最大の問題だ。
「中小企業の場合、バランスシートや損益計算書に基づいて判断してもあまり意味はない。それよりもキャッシュだけで考えたほうがよほどわかりやすい。いくらお金が入って、いくら出ていったのか。資産のうちどれだけ現金化することができるのか。それと、景気のいい時期に、年金代わりになるような資産を持っておくべきです。これに手をつけなければならないようなら、その段階で会社を整理することを考える。こうしておけば、会社がなくなったあとでも、なんとか生活することはできますから」
高度成長の終焉とともに、日本人の働き方は大きく変わった。同様に、経営者の会社に対する考え方も変えるべきなのかもしれない。
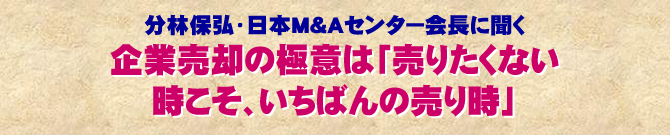
「企業の将来が見通せない」「後継者がいない」など、中小企業経営者の悩みは深い。こうした悩みの解決策のひとつが、M&Aだ。自分の会社を身売りすることで、事業を継続することができ、従業員を守ることができるのだから、会社の終わらせ方として大いに検討する価値がある。そこで、中小企業のM&A仲介を手がける、日本M&Aセンターの分林保弘会長に、M&Aの現状と、上手な活用法を聞いた。
―― ここ数年、国内でもM&A件数が伸び続けています。日本M&Aセンターの扱う案件も増えているのではないですか。
分林 増えていますね。毎日、20~30件もM&Aの相談が寄せられますし、当社が仲介した件数も、毎年20%以上も伸びています。
―― なぜ、ここに来て件数が増えているのでしょうか。
分林 最大の原因は後継者不足です。当社を設立したのは1991年ですが、その頃から、少子化傾向がはっきりしてきました。当時すでに出生率は1.4まで低下していました。男はその半分ですから0.7。ということは、中小・零細企業の場合、経営者の男児が全員その会社を引き継ぐとしても、3割の会社では後継者がいないことになる。しかも実際に継ぐのはいいところその半分程度でしょうから、子供が継いでくれるのは35%に過ぎません。つまり65%の企業で後継者不足になる。
そう推測して、中小企業のM&Aを扱うこの会社を立ち上げたわけです。
実際、数年前、帝国データバンクが40万社を対象に調査したところ、やはり3分の2の会社に後継者がいないという結果が出ています。われわれの予想通りになっています。
しかもここにきて、団塊世代が65歳を超えるなど高齢化してきている。そろそろリタイアを考える時期です。ところが後継者がいない。そこで、従業員を守るためにも、買収してくれるところがあれば売りたいと考えている経営者が増えています。
―― 事業承継は、中小・零細企業経営者にとっての最大の経営課題ですからね。
分林 それに加えて、将来性に疑問を持つ経営者も増えてきました。というのも企業の再編が進んでいるからです。
その理由もやはり少子化です。すでに日本は人口減少時代に突入していますが、減少スピードは加速していきます。2060年には現在より3割も減少するとみられています。しかも15~64歳までの生産人口年齢の減り方はもっと激しく、4割減ると予測されています。進学や結婚、家を買ったりクルマを買ったりする、最大の消費者層が4割も少なくなるわけです。これがそのまま企業の売り上げに直結した場合、どんな企業だって損益分岐点を下回ってしまう。
それを見越して、企業の再編が進んでいます。たとえば、薬品卸など、少し前までは日本全国に350社もありました。それがいまでは集約が進み、わずか4社で8割のシェアを持つまでになりました。食品卸も、これまで50社近くを買収してきた国分と、商社系卸に集約されています。

分林保弘・日本M&Aセンター会長。同社では年間200件以上のM&Aを成立させている。
わかりやすいのは家電販売店です。かつては松下電器のナショナルショップだけで2万点近くあった。各メーカー系列を合わせれば3万店以上あったでしょう。ところが家電量販店の台頭で、街の電器屋さんの多くが淘汰されました。でもいまでは量販店でも淘汰が進んでいる。10年前の最大手はコジマでした。いまはヤマダ電機が断トツとなり、コジマは10年前は12位にすぎなかったビックカメラの傘下に入ることで命脈を保っている。しかも、いま家電量販店は5社に集約されていますが、今後、さらに集約される可能性が強い。そういう時代です。
私の知り合いの家電量販店の社長は、そういう状況に嫌気がさし、電器店から宝飾店に衣替えしました。先日会ったところ、宝飾店は粗利がいいし値引きもしなくてすむ。本当に決断をしてよかったと言っていました。
これは電器店だけの話ではありません。ナショナルブランドを扱うかぎり、常に価格競争が起きてしまいます。いままでは小売店同士の競争だったのが、いまではアマゾンなどのネット販売も増えている。競争は厳しくなる一方です。ドラッグストアも調剤薬局も靴屋もスーパーも百貨店もみな同じです。ですから、中小・零細企業が独力で生き残るのは非常に厳しい時代になっています。
―― 小売業はそうかもしれませんが、製造業などは少し違うのではないですか。独自技術を持っていれば、小さくても存在感を示すことができるのでは。
分林 おっしゃるとおりです。大企業というのは、最低でも年商10億円以上の売り上げがあり、将来的に100億円以上になるマーケットしか狙ってこない。そこで、市場は小さくともウチしかつくれない、あるいは独自の強みがある、というポジションを確保できれば、生き残ることは可能です。
問題は、そのような強みを持つ企業がどれだけあるかということです。現実には、そんな企業はほんの一部にすぎません。
少し前までは、大企業の下請けとして生きる道もあったでしょう。しかしいまは、何の保証にもなりません。というのも製造業の海外移転が進んでいるからです。たとえば、かつて自動車メーカーが海外に工場を建設する時は、下請けの部品会社にも海外進出を要請していました。その代わり、そこで生産したものは、責任を持って引き受ける。こうやって大手メーカーと下請けが一緒に海外に進出できた。
いまは違います。海外に工場を新設する時でも、部品会社に対して「出たいのなら出てもいいですよ」としか言わない。あくまでも、自らの責任で決断しろと。しかも、保証はしない。現地の部品メーカーでもっといい条件で取引するところがあったら、いつでも切り替えるというわけです。それが現実です。
―― 中小・零細企業の経営者にとっては非常に厳しい時代になったわけですね。
分林 だからこそ経営者は、先を読む力が求められます。日本経済がどうなるか。自分の業界がこれからどのように変化していくか。それを見極めて、独力で生き残るのがむずかしいと思ったら、M&Aなどの手段を考えなければなりません。
実際、優れた経営者は真剣にそのことを考えていますし、積極的にM&Aを活用しようとしています。
―― 具体的な例を教えてもらえますか。
分林 インドネシアに工場を持つある自動車部品メーカーでは300~400人の従業員を雇用していました。しかも東南アジア進出を本格化している自動車メーカーから、さらに工場を拡大するよう要請されていました。会社には社長の子供たちも在職しており、将来性も、後継者も悩む必要はない会社です。
でもここの社長は、会社を売ることを選択しました。というのも、会社が大きくなりすぎたと考えたためです。しかも自動車メーカーの要請に応えようとすると、資金的にも対応できない。しかも子供たちは、会社をゼロから立ち上げた自分のようなしたたかさも持っていない。果たしてこの会社を継ぐことができるだろうか。こう考えた結果、会社を売ることにしたのです。
―― 確かに会社を子供に継がせたがために、会社がおかしくなったというのはよく聞く話です。
分林 よく言うのは、「継ぐ不幸」「継がせる不幸」です。親の後を継いだばかりに、みなが不幸になってしまう。たとえば、40歳で親の会社を継いで45歳で倒産させてしまったとしましょう。中小企業の場合、社長が個人保証するケースが多いですから、この社長は一文無しになってしまう。もしかしたら、父親の会長の家も担保に入れているかもしれない。こうなると、会社がなくなると同時に、この一家は住むところもなくしてしまう。45歳だと再就職もむずかしい。しかも社員も、みな迷惑する。こういうケースを私はいやになるほど見てきています。
―― どうやったら、そういう悲劇を起こさずにすむのでしょう。
分林 親から会社を継いだ人のほとんどは、真面目にこの会社をなんとかしたいと考えています。でも時代の変化もあり、いくら頑張っても思ったようにならないことはいくらでもある。ですから、できるだけ見極めを早くすることです。そのうえで、買ってくれるところがあればM&Aに応じればいいし、できるだけいい条件で会社を清算するという方法もある。真面目なのは日本人の美徳ですが、あまり頑張らないことです。
―― でも、ほとんどの経営者は、赤字に陥ったところで、いまをしのげばいずれ展望が開けるのではと考えているでしょう。たとえばいまなら、アベノミクス効果によっていずれ日本全体の経済がよくなる。それまでの我慢だ、といった具合です。
分林 その気持ちはわかりますが、人口が大きく減るわけですから、大きなトレンドでは、経済がシュリンクするのは仕方がない。その事実を認識し、自分の事業を客観的に見なければなりません。
―― それがいちばんむずかしい。
分林 ですから私たちは、一生懸命啓蒙活動を行っています。自ら主宰するセミナーも含め、年間300回ほど講演を行っていますし、聴講する人は年間、万単位でいらっしゃいます。みなさん、このままではどうなるか、不安を感じているんです。そこで私たちは客観的な状況を伝えるとともに、どういう選択肢があるか、説明しています。
―― 経営者の意識は変わってきましたか。
分林 そう思いますね。
たとえば最近のことですが、もともと買い手候補と考えて話をもちかけたところ、売り手になった事例がありました。横浜にある横浜テープ工業のケースです。衣料用テープメーカーで、売上高17億円、従業員は400人ほど。中国とバングラデシュに工場を持っていました。ここにある売却案件を持っていったら、逆に自分たちを売ってもいいと言う。そこで、伊藤忠商事グループで服飾資材の製造・販売を手がける三景がM&Aすることになりました。
この結果、伊藤忠の信用力、三景の販売力、横浜テープの生産力を組み合わせた企業が誕生したのです。横浜テープの経営者は、この会社にとって最善を考えた結果、買い手ではなく売り手になることを考えたのです。
―― 経営する者にしてみれば、M&Aで買われることはけっして受け身ではないということですね。
分林 少し前に、当社が仲介してワタミが買収した九州の宅配弁当のタクショクもそうしたケースです。5年ほど前のタクショクの売上高は80億円で、経常利益も5億円ほど出ていました。首都圏にも進出、上場準備も始めていました。
しかし首都圏で展開して気づいたのは、自らのブランド力のなさでした。そこで当社に、どこかブランド力のあるところと組むことはできないか、という相談があり、ワタミを紹介することにしたのです。その当時のワタミは企業買収はほとんどしてきませんでしたが、タクショクはお年寄り向け弁当も提供していました。ワタミが介護に力を入れていたこともあり、タクショクに関心を示し、M&Aが成立したのです。
いまタクショクがどうなっているかというと、売上高は500億円に拡大していますし、いずれ1000億円になると思います。すでにワタミは十分、元を取ることができました。タクショクのオーナーにしても、売却資金を元手に、九州の地元で事業を始め、うまくいっています
。
―― M&Aによってみんなが幸せになった好例ですね。ただし、経営者であれば誰しも自分の会社に愛着があるから、その決断はなかなか下せない。利益が出ているとなるとなおさらです。
分林 ですから、そこで必要になるのが先見力です。利益が出ている会社のほうが、結果的にはうまくいくものです。クライアントの社長が言った言葉ですが、「売りたくない時がいちばんの売り時、売りたくなった時には売れないもの」。これがM&Aをうまく運ぶコツです。また、「決断は心残りぐらいがちょうどいい」という言葉を残した経営者もいます。
そこで決断できるかどうかは経営者にかかっています。
―― 企業を売るにもタイミングが大切だということですね。売り時を逃したばかりに、高く売れるものが売れなくなってしまっては、元も子もありません。
分林 本当にタイミングは大切です。外部環境の変化によって、かつては高く売れたものが、いまでは値がつかないというケースも珍しくありません。
創業間もない頃に仲介した、70台の車両を保有していた北海道のタクシー会社は、17億円で売れました。これはタクシー1台につき1000万円、プラス純資産が10億円という計算です。ところがいまは、70台保有していても、純資産がなければ全部で1000万円にしかなりません。かつてタクシーは規制によって増車することが難しかった。だからこそ1台1000万円の値がついたのですが、規制緩和によって容易に増車ができるようになったものだから、会社の価値も暴落してしまいました。こういうケースは珍しくありません。
―― それも含めて経営者の先見力ということですね。あとひとつ気になるのは、社員のことです。会社を売って、経営者は買収資金を手にすることができても、社員が買収先から冷たい処遇を受けたりしたら、むしろ恨みを買ってしまいます。
分林 大企業のM&Aの場合、買収してリストラするという手法がよく取られますが、中小企業の場合はそうしたケースはまずありません。100%社員は残ります。というのも、中小企業の場合、社員あっての会社だからです。ですから場合によっては、買収後、社員が減ったら買収費を減額するという契約を結ぶケースもあるほどです。
―― 最後にうまくいくM&Aの条件を教えてください。
分林 絶対必要なのは相乗効果が出ることです。これがなかったらM&Aの意味はありません。たとえば技術屋社長のもと、技術屋集団の会社なら、技術系商社に買われたら面白い。技術に販売力や資本力が加わることで、売り上げはすぐに1.5倍くらいになりますよ。
企業カルチャーなどの相性も大切ですが、そういうことを考えマッチングするのが私ども仲介会社の役割です。相乗効果、相性などあらゆる条件を勘案し、最適の組み合わせを実現しますので、悩んでいる経営者はぜひ、相談してほしいですね。
(聴き手=本誌編集長・関 慎夫)
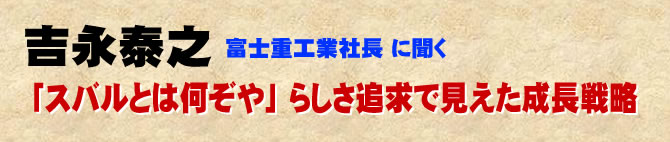

吉永泰之
富士重工業社長
よしなが・やすゆき 1954年生まれ。77年成蹊大学経済学部卒業後、富士重工に入社。99年国内営業本部営業企画部長、2002年スバル戦略本部スバル企画室長、03年経営企画部長を経て、05年執行役員。07年常務。09年専務。11年6月社長に就任。
昨年、円安で好調の自動車業界にあって、ひときわ注目を集めたのが富士重工だった。為替に頼ることなく販売台数、生産台数ともに過去最高を更新し、北米市場、国内市場では右肩上がりの成長を持続している。これに為替も追い風となり、14年3月期の決算見通しでは、売上高2兆3000億円(前年比20.2%増)、営業利益2780億円(前年比130.9%増)、純利益1780億円(前年比48.8%増)と、大幅な過去最高の決算となることが確実だ。なぜ富士重工は国内外で評価が高まっているのか。富士重工社長の吉永泰之氏に話を聞いた。
―― 販売台数から純利益まで、すべての項目が過去最高の数字になりそうですが、なぜスバルだけが伸びているのでしょうか。
吉永 スバルの場合、自動車会社の中では規模が小さいから、少し伸びると率が上がるという面もあるでしょう。アメリカを中心に台数が伸びて、非常にありがたいと思っていますが、やはり「スバルとは何ぞや」を議論してきた結果が出てきたのではないかと思っています。
自動車会社としては、我々は規模が小さいので、自分たちの特色を明確にして強みを伸ばしたほうがいいと4、5年前から言ってきました。経営資源が豊富な会社ではないですから、大手の会社に負けているところはいっぱいある。全方位的に勝とうというのではなく、強みは何かを議論してきたわけです。
我々がたどり着いた答えというのが「安全と愉しさ」なんです。スバルっぽくこだわって、「楽」ではなく「愉」。議論のなかで、我々は飛行機会社から始まっていることを、もっと大事にしたほうがいいと確認しました。企業はそれぞれ歴史があるわけで、歴史に根ざさないことを話せば言葉が浮ついてしまう。
例えばオートバイのメーカーから入ってこられた自動車メーカーは、モデルチェンジなどが早いんです。車名も変える。ウチはモデルチェンジは遅いし、ずっと「レガシィ」と言っている。悪く言えばいつまでも同じことをやっている。しかし、飛行機会社から始まり、いまも飛行機を作り、自動車も作っている唯一のメーカーです。飛行機をやってきたからこそ、車体の剛性など「安全」に対する考え方が非常に厳しい。突き詰めていくと、「アイサイト」などぶつからないクルマに発展してきたわけです。
―― それがアメリカはじめ市場に受け入れられてきたと。
吉永 昨年、アメリカで米国道路安全保険協会(IIHS)から、アイサイトが衝突回避性能評価で最高評価をいただきました。単純にクルマを米国向けに大きくしたからといって、ここまで伸びるものではない。つい最近も、モータートレンド誌でスバル車がベストSUVに選ばれています。5年、6年と本質的な価値の訴求をスバルもしているし、お客様も反応しているということでしょう。

東京モーターショーで紹介された日本専用車「レヴォーグ(LEVORG)」。
米国市場のお客様というのは、合理的な購買行動を起こされるのだなと感じています。新しいブランドだから不安というのではなく、客観的なデータを重要視する。かつてソニーが、まったく知名度がなかったにもかかわらず米国で成功したように、新しいブランドであっても安全だとわかれば一気に売れるわけです。これはただの偶然ではなく、我々としては非常にうまくいっている。
私はアメリカで売れている理由を3つ挙げているんですが、1つはお話ししてきた商品力、もう1つはマーケティングです。とにかく価格競争をやめました。スバルの価値を訴求していくようにしています。そして3つ目が、販売網の強化です。
いま北米で621のディーラーがスバルを売っているんですが、この5年間で25%が入れ替わっています。リーマン・ショックのあと、GMやフォードなどの破綻危機の時に、これらのメーカーがディーラーを切ったんですね。その時に、それまでスバルを扱ってもらえないような大きなディーラーがスバル車を売ってくれて、ディーラーが強くなることの効果を実感しました。いま売れていますから、スバル車を扱いたいというディーラーも増えてきましたので、現地のSOA(スバル・オブ・アメリカ)が戦略的にディーラーを入れ替えています。売れて儲かればまた宣伝してくれますから、販売網の強化が大きな成果に結びついています。
―― 日本国内の販売も、登録車では唯一、前年比増です。
吉永 国内の場合、一番効いているのはアイサイト。台数は少ないですが、「XVハイブリッド」も人気があります。実際は、11月からクルマが足りなくなってしまって前年割れになってきている。売れてないのではなく、アメリカでも足りずに国内に出荷できる数も限られてしまって、頭の痛い状況です。
―― 生産増はまだ時間がかかりそうですか。
吉永 14年の夏までに日本の本工場で2万台、アメリカで3万台、能力を増強するので、夏になれば落ち着くと思うんですが、しばらく足りないでしょうね。と言っても、能増をするたびに販売が上回ってくるので、何ともいえないのですが(笑)。
―― アメリカ以外の海外市場はいかがですか。数字的には北米や日本ほど伸びていないようですが。
吉永 北米、日本の次に伸ばしたいと思っているのは中国で、いま年間約5万台。10月1日から新しい販売合弁会社を立ち上げ、足元の台数は伸びてきて、我々のマーケティングをできる形が整ってきたので楽しみにしています。完成車を日本から輸出する形で、ブランドイメージを大切にしながら、富裕層を相手に日本製のクルマを買っていただき、10万台を目標に増やしたい。
ロシアはいま、年間1万5000台ほど。全需は300万台ですので、1%獲っても3万台。ですからいまの倍くらいにしたい。ディストリビューターはスバルの資本ではないですから、スバルの考え方を理解してもらえるように強化しています。
オーストラリアはいまシェアが4%と、スバルのなかでは結構高い。全需が100万台で、ウチが4万台。ここは少しずつ伸ばしていければいいかなと。
あとはASEANでも富裕層が増えてきているので、12年12月からマレーシアでノックダウン生産をXVで始めました。年間5000台計画で、予定通り進んでいる。タイ、インドネシア、マレーシアを相手に、現地生産5000台、日本から輸出で5000台くらい。これも伸ばしていきたい。
欧州はいま4万台くらいですが、ここは経済環境も厳しく、そもそも欧州に自動車メーカーがたくさんあるので、私としては4万台を減らされては困るんですが、無理に乱売合戦に突っ込んだりしなくてもいい。スバルには4輪駆動で水平対抗エンジンでバランスがいいという特徴がある。これをわかっていただけるお客様に4万台買っていただければいい。価値訴求でいまの規模を売っていければいいと思っています。
これらが小さめの柱に育てば、いい形になる。手は順番に打っていますから、あとは様子を見ながらやっていく。
―― 中国では、森郁夫前社長時代から現地生産の話が出ていましたが、実現には至っていない。
吉永 森社長の時に現地生産をやろうと決めて、私が社長になった時の中期経営計画で始めると発表したのですが、何の認可も下りないんです。なしのつぶて。いまになってみれば、認可が下りなくてよかった。

世界販売を牽引する「フォレスター」。
当社の場合、生産技術の人間がそんなに多くないですから、アメリカと中国、両方の工場で能力を増強するということができないんです。もし中国工場ができていたら、アメリカで売れているのに何の手も打てないところだった。中国が動かなかったぶん、出すはずの生産の人間が日本にいたので、SIA(スバル・インディアナ・オートモーティブ)の能力を増強できる。将来的には、政治が落ち着けば中国の現地生産は考えるべきですが、いまの状況だと焦る必要はないので、販売のほうの合弁会社をつくって輸出で売ることを優先します。
中国も15年くらいに供給過剰になるという話があって、それくらいの勢いで欧州勢、日本勢、現地資本が工場を建てています。いま欧州の自動車産業は1900万台くらいの供給能力がある。全需が下がって1200万台。それが結局中国等に流れて乱売の元になっているわけです。生産能力をつけてしまえば、インセンティブをつけてでも売っていくしかない。その意味では、スバルは恵まれている。在庫が少ないと言ってもフル稼働ですから、贅沢なことが言えるんです。もしもう1つ大きな工場を持っていたら、同じく乱売する状況になっていたかもしれない。自動車のビジネスは、在庫を抱えてしまえば捌かざるを得ない。供給が少し少ないくらいにしておきたいですね。
―― 資本関係にあるトヨタとの提携は今後どうなりますか。SIAでのトヨタ車の生産をやめるという話も出てきています。
吉永 トヨタさんからは、SIAでの「カムリ」の生産をやめる検討をしたいと言われています。私どもとしては、今まで通り作らせていただきたいというのが本音。ただ、トヨタさんも決定はしていない。トヨタさんにしてみれば、世界の生産体制を見直すうえでの、ごく一部のカムリの話ですので、メインテーマではないんですね。そこにウチが絡んでしまっている。仮に生産をやめるとしても、今年すぐにというわけではなく、少し先の話ですから、時間はあります。
スバル側の能力増強は進めていて、いま17万台なんですが、30万台にまで増やす。これは予定通り、計画は変わりません。誤解されている人がいるかもしれないですが、カムリの設備でスバルがつくれるわけではない。トヨタさんの設備ですから、トヨタさんが撤去されたあとに、スバルのラインを敷くのか、撤去されたままにしておくのか、販売の売れ行きを見ながら考えるということです。ただ、工場の固定費の半分くらいはカムリが負担してくれた面もあるので、経営の安定という意味では、作らせてもらえるほうがありがたい。当社からやめたいという気持ちはまったくない。
提携そのものについては、最初がカムリで、生産を中心とした提携関係でした。08年9月に「86」「BRZ」の共同開発を発表し、世の中に出し、いまは技術や商品のアライアンスになっています。これはいい流れです。スバルという会社の特徴から見ても、技術・商品を軸にした提携関係がいちばんよい。我々にとっては将来の環境技術、例えば燃料電池車の開発は我々の規模では無理ですから、トヨタさんとのアライアンスのなかで学んでいくということになる。生産との繋がりをなくしたいとは思わないですが、技術・商品の繋がりのほうがスバルっぽいですよね。
―― トヨタの豊田章男社長もスバルの技術力には一目置いているようですね。
吉永 親しくさせていただいていますが、すごいですね、あのクルマ好きは(笑)。自工会でSUGOサーキット(宮城県)に行ったときも、グルグルとスピンターンをやったり、本当に好きなんだなあと。「インプレッサはいいクルマだ。ただ、ダンパーをもう少しこうしてほしいんだ」とか。こういう社長がトヨタさんにいることは、スバルに悪いことではない(笑)。
いい意味で言っているんですが、よくトヨタさんに章男さんのような人が社長に出てきたなと。「もっといいクルマをつくろうよ」というメッセージを出した時に、いまはすっかり浸透していますが、トヨタの人たちが戸惑った顔をしていたのを覚えている。クルマの会社ですから、すばらしいメッセージだと思います。
ウチは、そんなことを言ったら大変なことになります(笑)。スバルは「利益も少しは考えようね」と言わないと、技術系の連中は、採算度外視で、どこまで作りこんでしまうかわからない。だから営業系の私が社長をやっているんでしょうけど、「給料を払わないといけないんだから」「事業性を考えろよ」と言わないと、会社に泊まりこんで作り始めてしまう(笑)。
共同開発では、提携を活かして、我々もできるコストダウンはしていこうと思っている。いちばん印象的だったのは、86、BRZの時の両社のテクニカルスタンダードの違いですね。いい悪いではなく。例えばマニュアルシフトの長さの技術基準が違うんですよ。スバルは短くて、カチッカチッと入る。トヨタさんは長くてフワリと抵抗なく入る。ステアリングもスバルは動かしたらピッとタイヤが動く。トヨタさんはあそびが大きい。同じクルマでも味付けが違うんですね。マニアの間ではその違いに対して話題沸騰だったようです。技術的にはお互い譲れないところがあるでしょう。こういう話をウチの技術系の人とすると、朝までやっている。こういう会社があってもいいでしょう(笑)。
―― 最後に、14年の抱負を。
吉永 13年は60周年、14年は61年目なので、次のスタートを切る大事な年です。いま気になっているのは、これだけスバル車が売れているということは、初めてスバルを買ってくださるお客様がたくさんいらっしゃるということ。そのお客様が、クルマはもちろんアフターサービスも含めて「スバルにしてよかった」と思っていただけるかが勝負だよ、と言っています。確かに売れていることはうれしいですが、次もスバルを買うよと言ってくださった時に、はじめてぼくらは本物になるのであって、いまが勝負です。それは絶対に忘れてはいけない。
(聞き手=本誌・児玉智浩)
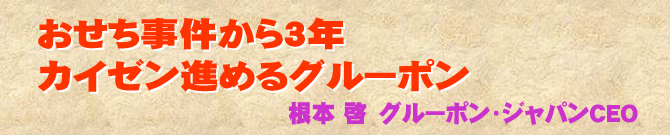

根本 啓 グルーポン・ジャパンCEO
ねもと・さとる 神奈川県出身。1989年慶應義塾大学経済学部卒業後、ソニー入社。2005年アマゾンジャパン入社。07年同社エレクトロニクス事業部長、10年7事業部門ディレクター兼統括事業本部長、12年アプリストア事業本部本部長を経て、13年5月グルーポン・ジャパン入社、8月に代表取締役CEOに就任。
3年前、正月のおせち料理で大騒動を起こしたグルーポン・ジャパン。時を経て、改めておせち事件と向き合い、再出発を誓った。グルーポン・ジャパンは何を改善し、どう変わろうとしているのか、昨年CEOに就任した根本啓氏に話を聞いた。
〔昨年11月21日、クーポンサイト大手のグルーポン・ジャパンが記者会見を行った。2011年1月に起こった「おせち事件」から約3年、同社がいかに改善をしてきたかを伝え、名誉挽回を図る場として、改めて事業説明会を行った。
「おせち事件」は、某レストランのおせち料理をグルーポンのクーポン券を利用して購入したユーザーに起こった悲劇のこと。ネット上の写真とはまったく別物の貧相なおせち料理が届けられたり、また配送の遅延で元旦に届かなかったりと、相次ぐ不手際にユーザーの怒りが爆発。非難が殺到し、社会問題にまで発展した。以降グルーポンでは、おせち料理を扱っていなかった。
この日の会見で、グルーポンは「夢のおせち」プレゼントキャンペーンの開催を発表。高級料理店の料理人・シェフの手による豪華なおせち料理をふるまうことで、新たなグルーポンをアピールする試みだった(取材日は12月25日)〕
グルーポン・ジャパンがサービスを始めたのは10年10月、わずか2カ月後の11年1月にあのような騒動が起き、それから多くの改善をしてきました。私がこの会社に入ってから7カ月程度ですが、この半年間でもいろいろと改善を進めています。ここでいま一度、我々のサービスについて、もっと多くのお客様に知っていただきたい。またクーポンを発行するパートナー様にも知っていただきたい。そこで我々の事業を説明させていただく場を設けたわけです。
今回、事業の説明をさせていただく際に、おせちに触れる必要はないのではないかという議論もありました。でも、おせちのプレゼントキャンペーンをしたからすべて信頼が回復する、事故が帳消しになるというわけではありません。我々が避けたとしても、社会で事件が風化しているわけではないですから、むしろ事故を受けて、我々がどう改善したかを紹介し、これからどのような取り組みをしていくのかを紹介したかったのです。
プレゼントという形であって、購入していただくのとは違いますが、いままでにないような夢のおせちを企画させていただき、間違いなく12月31日までにお届けするのがよいのではないかと。今回は31日までに配送可能なエリアということで、関東地方のお客様に限定させていただいたのですが、十数万件の応募があったことは、我々にご注目いただけたということで、素直に嬉しいことですね。
〔創業後、間もなかった11年当時、グルーポンは、おせち事件だけでなく、様々な不祥事を起こしていた。クーポンを発行する店舗との間で契約内容を変更したり、未契約のままクーポンを販売したり、契約数よりも多いクーポンを発行するなど、店側と訴訟に発展するケースも出てきていた〕
11年当時、どういったことがお客様のご迷惑になったのかを検証し、業務のあらゆるプロセスで改善を進めてきました。
例えば、営業の評価制度は、当初は売り上げこそが評価の一番の目標になっていました。それを、お客様の満足度を含めた評価制度へと仕組みを変えていきました。また、営業がとってきた契約の審査基準項目も30件から現在は200件以上にまで増えています。具体的には、パートナー様のメニューの内容は正しいのか、証明書は出していただいているのか、稼働率から見たクーポンの販売枚数は適切なのか、といったチェック項目があり、いまも増え続けています。
サイトのページをつくったあとの校正機能も、外注から内製に変え、責任を持ったチームをつくり、業種別の編集チームをつくって、正確にお客様に伝えられるような体制にしています。そしてパートナー様に、掲載前と後、内容に問題はないか、間違いはないかをお互いに確認するようにしています。契約をとる営業とは別に、パートナー様をフォローする部署をつくり、掲載直前には人員の手配などの確認、掲載後にはクーポンの使用状況や、我々から提供する管理画面の確認など、24時間ご連絡を受け付けられる体制にしています。
エンドユーザー様については、以前のお問い合わせはメールのみの受け付けで72時間以内の返信率が70%程度と、褒められた体制ではありませんでした。現在ではコールセンターでの対応を始め、24時間以内でのメール返信率は93.9%、受電率は97.9%にまで改善してきています。まだ数%でもご対応できていないお客様がいますので、不満に思われることは事実です。継続的に改善に取り組み、エラーを少なくして不満足度を少しでも減らすようにしていかなくてはいけません。
私が来てからの半年でも、別の切り口で、より多くの品揃えや多くのバリエーションを増やし、検索のしやすさや商品の選びやすさ、買いやすさなどの改善を進めているところです。
〔クーポンの利用自体は古くからあるものだが、ネットビジネスとして広く認知されるようになったのは、08年11月に米国でグルーポンが設立されてからだろう。ネットのマーケティングとECの普及から広まってきたものだ。そしてリーマン・ショック以降の世界的な景気後退が、クーポンサイトの利用を後押ししたと言えなくもない。節約志向にあったユーザーの「少しでも安く」というニーズに合ったからだ。しかし根本氏は、グルーポンは景気に左右されないビジネスモデルだという〕
本質的には、不景気でも好景気でも、いいものが少しでもリーズナブルな価格で手に入るほうがいい。コストとバリューの関係で、コストパフォーマンスが高いほうがいいというのは、景気がどちらでも同じではないかと思っています。
パートナー様にとっては、新しいお客様を含めて集客ができ、その際に少しアップセールがあって、一部のお客様にはリピートする。そのお客様はどこから、どの年齢層の方が来ているのかもわかりますし、再び集客する時にはまた私たちのプラットフォームを使っていただく。
エンドユーザーの方は、我々ができるだけ多くの、質のいいディールを揃え、ご紹介することで、安く簡単にすばらしいサービスを受けていただけます。
その意味では、我々が地道に質の高いディールを集めることの繰り返しが、結果的にお客様、パートナー様にご満足いただくことになる。不景気、好景気でもやることは変わらないかなと思いますね。
〔特に日本人は品質に敏感な文化をもっている。おせち事件でも発端は品質だった。質の高いディールへのこだわりはどのように実現させていくのか〕
お客様の満足度を測るために、利用後にアンケートを用意しています。その評価が一定の基準に達していないと、次からそのパートナー様のディールの販売を差し控えさせていただいています。もちろんそこで終わりではなく、お客様からの厳しい指摘を私どもとパートナー様で共有し、改善を助言させていただいています。改善すれば、再びよりよいサービスとして、お客様にご提供したい。
満足度が低いと、我々のサービス自体が使われなくなってしまいますので、一定の基準を設け、安かろう悪かろうというものが継続して掲載されないような仕組みにしています。
一方で、ディスカウントのメニューを組んだ時に、その価格でお客様が来店して、どのような採算になるのか、損をしないのか、どの程度儲かるのかを、パートナー様と事前にシミュレーションして共有したうえで契約していただく。集客だけの宣伝ではなく、採算に合って、ビジネスの拡大に繋がり、継続可能なモデルでなければ、パートナー様の再掲載のご意向に繋がりませんからね。もちろん、パートナー様に対しても、毎月定期的にアンケートをお願いしています。お答えによって、どの程度改善の余地があるのか、我々に対する満足度も測っています。
品揃えを増やす、バラエティを増やすというのは、言うのは簡単ですし、実際にやるのも簡単です。でもそれでサービスの質が落ちたら、何のためにやっているのかわからなくなる。質を高めながら、どう拡大していくのか、これは難しいですが、やらなくてはならないことです。
〔国内のクーポンサイトでは、リクルートの「ポンパレ」とグルーポンが大手として頭一つ抜けた存在だ。それを楽天の「RaCoupon」、ジャフコやKDDIが出資する「LUXA」、GMOの「くまポン」などが追う。競争が熾烈になっているなか、どう差別化を図っていくのか〕
我々は48カ国でサービスを行っていますので、パートナー様向けの管理画面やお客様とのインターフェースとして大事なアプリなどは、全世界共通でつくっています。日本だけでなく、米国や欧州からの要望も、全世界で汲み上げることができる。いろんな国で学んだことを、よりよいサービスとしてパートナー様にご提供できます。

サイトも日々改善が加えられているという。
お客様についても、例えば香港で流行ったレジャー案件など、新しいディールを全世界で共有できるようになっていまして、同じようなサービスを提供している施設を日本でも探してお客様にご紹介するということができます。また48カ国の宿泊施設がディールとしてあるわけですから、例えばシンガポールと連携して、日本のお客様にシンガポールのリゾート施設を提供しようという試みも少しずつ始めています。48カ国のネットワークを使って、より多くの選択肢をご紹介できるといいかなと思っています。
〔ひと言でクーポンといっても、いまや値引きだけにとどまらない。付加価値をつけたサービスも広まりつつあるという〕
「“WOW!”ディール」、つまりびっくりしてしまうようなディールも売られ始めています。例えばアメリカでは、ロッド・スチュアートさんのコンサートチケット+往復航空券+シーザーパレスで2泊+ご本人と楽屋で会えて一緒に写真撮影&サインというディールが2500ドルとか。お金を使えば買えるというものではなく、ふつうは買えないようなディールを紹介して日々の生活におどろきや楽しみを提供する。ブラジルだと、サッカーのネイマール選手とオンラインゲームで対戦できるクーポンも出ていました(笑)。
〔根本氏は昨年5月に社長に就任したが、前職はソニー、アマゾンといった経歴を持つ〕
ソニーでは、テレビのハードウェアのビジネスに携わっていることがほとんどでした。国内、北米、欧州で何かしらのテレビのビジネスに関わっていて、商品企画やマーケティングという業務にあたっていました。
アマゾンに転職したのは、2005年にアマゾンで働いている友人から紹介されたのがキッカケです。それまでは、インターネットを通じて電気製品を売るということにイメージがわかなかったんです。本当にそんなことができるのかと。ソニーでマーケティングをしている時は、数百というアイテム数を扱っていましたが、アマゾンはその桁数が3つか4つくらい違う。エンドユーザーも桁が5つか6つくらい違うような数を相手にしているわけです。ソニーの時は商品を通じて楽しさや便利さを届けられたらいいなと思っていましたが、今度はオンラインを通じて商品をお届けして、お客様の利便性が上がることに魅力を感じたんですね。
グルーポンも、キッカケは知人を通じた紹介でした。私の知人が違う国でグルーポンの仕事をしていて、他の国のマネジメントと話をしていくなかで、情熱を感じました。外から見てどういうサービスかは知っていましたが、数字的に業界が顕著に成長しているというわけではありませんでした。でも、品揃えやユーザーエクスペリエンス(ユーザが真にやりたいことを楽しく、心地よく実現できるかどうかを重視した概念)、価格付けなど、まだまだ改善できること、成長できる余地はあると感じたのです。お客様、パートナー様にもっと満足いただけるようなサービスができて、アマゾンとは違った形で楽しさやワクワク感、便利さが提供できるのではないかと。
お客様に、暇な時、何かの時に、まずはグルーポンを最初にチェックしてみようと思われるよう、志をもって取り組んでいきたいですね。
(構成=本誌・児玉智浩)
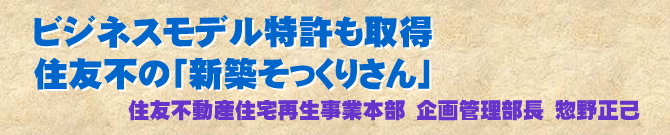
中古住宅の流通マーケット拡大に伴い、リフォームやリノベーション市場が盛り上がりを見せている。リフォーム産業新聞の独自調査によると、昨年のこの分野の売上高ランキングで、住友不動産は8年連続トップという強さを見せた。
その強さの代名詞にもなっているのが「新築そっくりさん」という、中古物件を丸ごと再生する商品である。一度聞けば覚えやすいことから、ヒット商品に成長した要因の1つにネーミングの妙があるといっていいだろう。ちなみに名付け親は、1994年から2007年まで社長を務めた高島準司氏である。
「新築そっくりさん」が商品化されたのは96年のこと。前年年初に起きた阪神・淡路大震災で全壊した住宅も多かったことから、「地震に強く、しかもできるだけ安価で、建て替えせずに住宅を再生させたい」との思いが起点になっている。
「もともと、この『新築そっくりさん』というのは、建て替えか部分リフォームしか選択肢がなかった頃、新しい住宅再生システムというコンセプトで立ち上げたのです。ですから、リフォームという概念とは少し違うところから始めている。そこがある意味、我々の強みともいえるでしょう。
外部の方からはリフォームとして括られるんですが、我々としてはずっと住宅再生というコンセプトを持ち続けています。ですから、チラシ広告を打つ時はリフォームという言葉は使いません。世間に浸透して認知度が上がるまでは、建て替えやリフォームに変わる、第3の選択肢みたいな文言を使っていました」
語るのは、住友不動産の住宅再生事業本部で企画管理部長を務める、惣野正己氏。同氏が「新築そっくりさん」のビジネスに携わったのは98年夏からで、すでに15年以上のキャリアがある。

住友不動産住宅再生事業本部の惣野正己氏。
確かに、かつての常識だと、リフォームの主力は部分的な工事、見積もりは積算方式で価格も不明瞭、不測の事態による追加請求は当たり前で、リフォームの際に耐震補強という発想もなかった。どちらかと言えば、建て替え費用を用意するほど資金的に余裕のない人たちが、ある意味必要に迫られてリフォームするイメージが強かったといってもいい。
それがいまでは、「高い新築住宅よりも割安な中古を買って好きにリフォームしたほうがお得」と考える人がかなり増えた。これは、核家族化や長引くデフレ不況、住宅すごろくの崩壊、住宅観の多様化など要因はさまざまだが、昔とは隔世の感さえある。
話を戻そう。他社との競合については、リフォーム会社より、どちらかと言えば建て替えを手がける企業との競争が多いという。となると、同じ住友グループで注文住宅を手がける住友林業も気になるが、より高価格帯が主力の住友林業とはほとんどバッティングしないようだ。
「新築そっくりさん」は文字通り、既存の住宅構造を活かした新築同様の住まいを、建て替えた場合の費用に比べて7割、うまくすれば5割にとどめることができる点が売りの1つ。それだけに、競合するのはむしろ、地場工務店が手がけた新築物件、あるいは割安価格を売りにしてきたタマホームあたりになる。
単なるリフォームのようにキッチンだけ、バスだけ、あるいはフローリングだけをバラバラに一新するとなると、相当割高になることは言うまでもない。それでなくても個人がリフォーム、ないしリノベーションをする場合は、ディベロッパーがまとまった戸数を発注する新築物件の設備コストに比べて、コストパフォーマンスが圧倒的に悪くなるからだ。住友不動産でも部分リフォームは請け負ってはいるが、主力はあくまで戸建てまるごと再生と、マンションをスケルトンにして全体をリフォームする商品群である。

高度成長期時代の団地では、上の写真のようなキッチンが一般的だった。
「新築そっくりさん」のセールスポイントはもう1つ、“完全定価制”にもある。ただ、最近は住宅の部位ごと、部屋の面積に応じてリフォーム価格が決まっている工事も多く、その点では他社との差異は見つけにくい。
問題は中古物件だけに、いざ工事に入ってみたら想定以上の毀損部分や劣化などが見つかり、追加工事が必要になった場合だ。その点、「新築そっくりさん」は、工事金額が契約時と変わらない、完全定価制の安心さを売りにしている。そこも大きな支持を得ている要因といえるだろう。
「追加工事が発生しても『完全定価制』が売りなので、そこは崩せません。商品コンセプトの前提として守っていかなければいけませんから。追加工事が発生した場合のコストアップ分は、(リフォーム売上高ランク首位であるがゆえ)大量発注できるという強みを発揮して、仕入れ部材のスケールメリットにより、原価を下げているわけです。工期短縮もやっていくべきものですが、マンションですとスケルトンにする解体工事で1週間程度、トータルの工期でだいたい、1カ月から1カ月半でしょうか」

「新築そっくりさん」が手がけるダイニングキッチン事例。
工事期間中の仮住まいは、たとえば住友不動産所有の、都心の高級マンションが敷金や礼金なしの月額10万円と、お得な価格で提供されている。また、完成後は定期的に無料点検を行い、24時間365日、アフターケアに関するサポートもある。
さらに、前述したように商品化の原点が震災だっただけに、標準仕様で耐震保険にも入っており、耐震補強工事には定評がある。ちなみに96年以降、全国でマグニチュード6以上の主な地震だけで10回以上あったが、すでに8万棟以上の実績がある「新築そっくりさん」の物件は、倒壊や全壊はもちろん、半壊もゼロという。
「加えて、営業、技術、工事とスタッフの分担をせず、技術的な知識もあるSE(セールス・エンジニア)が一環して担当させていただいています。つまりご商談から完成後にお引き渡しするまで、専任の担当者がついて進めていくのです。工事を請け負う棟梁も、当社のノウハウをよく知っている人たちによる、専属制ですしね」
ちなみに惣野氏も大学は理系で、都市工学を専攻している。
これまで述べてきた「新築そっくりさん」のいくつかの特徴は、すでにビジネスモデル特許として取得済みだが、気になるのはお値段だ。
「戸建てもマンションも含めた『新築そっくりさん』全体の平均単価は1300万円です。マンションだけで見れば1000万円ぐらい、部分リフォームで100万円ぐらいでしょうか」
同じ財閥系不動産会社と比べてみると、リフォームで括られる分野では住友不動産が圧倒している。

「マンション新築そっくりさん」の玄関ドア回りの事例モデル(奥)と、昔の住戸玄関の事例モデル。
中古売買の仲介分野では、「三井のリハウス」で知られる三井不動産リアルティがトップ、「STEP」の住友不動産販売が僅差で2位の展開だが、三井不動産リフォームはデザイン面で評価され、質感にも強いこだわりがあるので平均単価は高いものの、売上高ランクでいえば9位にとどまる。
さらに三菱地所にいたっては圏外で、同社は新築分譲マンション分野こそ藤和不動産買収の効果もあって上位だが、中古仲介やリフォーム分野では、やや存在感が薄い。
住友不動産は逆に、三井ホームや三菱地所ホームと違い、注文住宅ビジネスは外出しせず、住友不動産本体で手がけている。また、住友不動産リフォームという子会社もあるものの、同社は小規模工事を手がけるのみだという。リフォーム関連ビジネスもあくまで、「新築そっくりさん」を全面に打ち出した、住友不動産本体の事業として展開しているのだ。それぞれよし悪しはあるのだろうが、住友不動産本体で手がけることで、顧客への信頼度が一層増す効果はありそうだ。
さて、最後に惣野氏にこれからの課題を語ってもらうと――。

リフォームの売上高ランクで8年連続首位の原動力が、1996年からスタートした「新築そっくりさん」の商品だ。
「1つは、拡販に直結するかどうかはともかく、耐震診断というのは当社でもしっかりやっていこうと考えています。家のドクターではないですけど、いわば家の健康診断ですよね」
特に、見ず知らずの人が住んでいた中古物件を買ってリフォームする場合、買い主の不安を払拭するために、プロの目で建物の構造や設備にどんな欠陥があるのか調べる、「住宅インスペクション(診断)」が広がりを見せており、リフォームの見積もりも、それだけ明瞭化が進んでいきそうだ。
「もう1つはいま、スケルトンのマンションリフォームが注目を集め始めています。その要因に、89年から数年の間、つまりバブル期とその崩壊直後に数多くのマンションが建てられていて、そうした物件の“リフォーム適齢期”が来ているのです。その需要を取り込んで事業を伸ばしていく余地があるのかなと。
一般的には向こう5年間ぐらいで、そのリフォーム適齢期マンションが倍ぐらいになると言われているので、『マンション新築そっくりさん』のビジネスチャンスはさらに広がると思っています」
リフォーム戦国時代のいま、スケールメリットも利く住友不動産の首位は揺らぎそうにない。
(本誌編集委員・河野圭祐)
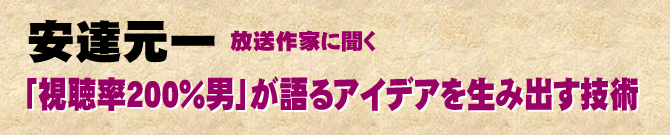

放送作家 安達元一
あだち・もといち 1965年群馬県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。在学中から放送作家としての活動を始め、「視聴率200%男」との異名を持つ。放送作家として担当した番組が第42回ギャラクシー大賞、2007国際平和映画祭特別賞などを受賞している。また『LOVE GAME』『痛妻』『ハイエナたちの25時』などの小説がある。
―― 安達さんは放送作家として、視聴率200%男との異名を取っています(『ダウンタウンのガキの使いじゃあらへんで!!』や『SMAP×SMAP』、『伊東家の食卓』など、テレビ全盛期に担当した番組の1週間の合計視聴率が200%を突破した)。
安達 高校時代から深夜放送への投稿を繰り返していました。自分のハガキが番組で読まれると、次の日は学校でヒーローです。それがきっかけで、放送作家への道に入っていきました。当時はバブル経済が上り詰めていくところで、番組制作にかける費用も余裕があった。ですからひとつの番組に多くの放送作家が携わっていました。私もすぐにいくつかの番組に関わるようになり、今日にいたっています。
―― 以来30年近くにわたり放送作家として第一線に立ち続けてきたわけですね。
安達 自分に特別な才能があったとは思っていません。それでもここまで続けることができたのは、真面目に仕事をしてきたから、としか言いようがない。締め切りはきちんと守る。相手が期待した以上のものをつくり続ける。「ま、いいんじゃないか」ということだけはやらないよう、日々、考える。これを自然にやってきただけのことです。
―― ただそうは言っても、視聴率を稼ぐアイデアを出し続けることは容易ではありません。アイデアを生むルーチンのようなものはあるんですか。
安達 机の前で考えているだけでもだめで、リラックスすることで発酵させることも必要です。僕の場合だと、朝、風呂に入っている時に思いつくことが多いですね。そういう時は、神様が与えてくれたようにも思いますが、何もしないで与えてくれるわけではありません。日々考え、努力することで、ようやく神様が与えてくれるのです。
―― 年明け早々、『ハイエナたちの25時』(中央公論新社)という小説を出しましたが、小説家としての活動も増えてきました。
安達 ほとんどの放送作家は、小説を書きたいと思っているはずです。僕も例外ではありませんでした。小説家というのは物書きの世界の頂点です。一方、放送作家は底辺です(笑)。放送作家はみな、小説家にあこがれています。
しかも、テレビ番組の場合、放送作家の僕の役割というのは、ほんの数%です。プロデューサーがいるし、タレントがいる。仕事として楽しくて面白い、大好きな世界ですが、所詮は巨艦の乗組員にすぎません。ところが小説の場合、その責任のほとんどすべてが自分にかかってくる。売れるのも売れないのも自分次第。いわば小船の船長です。どっちがいいというのではなく、それぞれが面白い。
―― ところで安達さんは昨年、『アイデアを脳に思いつかせる技術』(講談社+α新書)という本を出し、さらには「安達元一のアイデア工学Works」というサイトを開設、いかにしてアイデアを生むかを、多くの人に向けて発信していますね。
安達 もともとはアイデア発想法などというのは、一種の職人技のようなもので、人に教えることなどできないと思っていました。でも、いままでアイデアを生むためにやってきたことを体系としてまとめてみようと考え、大学院に入って学術的に研究したところ、科学的な技法によってアイデアを生み出すことができることがわかりました。
僕はいままで、先輩の放送作家など、多くの人たちからいろんなことを学んできました。ですから、その恩返しの意味でも、自分の学んできたことを後進の人たちに教えようと思っています。
これまでにも、放送作家を目指す人たちを集めてスクールのようなものを開いてきました。それを今度は放送業界の人だけでなく、もっと多くの人に知ってもらいたいと思って本を書き、サイトをオープンしたわけです。
―― 本を読むと、「しりとり法」「シックスハット法」など、アイデアを生むためのさまざまな方法が紹介されています。
安達 こうした技法は、僕がこれまで、特に意識しないでやってきた方法です。何がアイデアを阻害しているかというと、凝り固まった常識です。従来の延長線上で物事を考えても、新しいものはなかなか生まれない。裏を返せば、それを取っ払うだけで自然に脳は動き出す。そこで、たとえばしりとり法なら、テーマとなるキーワードからスタートして、しりとりで思いつく言葉をつなげていくだけです。これによって先入観を持たずに、思考を広げることが可能となります。
―― 中でも紙幅を割いているのが、「セレンディピティFA法」というアイデア発想法です。
安達 これは、僕と、大学院の指導教員であり共同研究者でもあった東洋大学総合情報学部の藤本貴之准教授と開発した発想法で、簡単に無理なく、機械的に発想力を引き出す手法です。セミナーなどでは参加者にこの技法を実践してもらっていますが、みなさん、ユニークなアイデアを出していますよ。
ニュートンはリンゴが落ちるのを見て万有引力を発見したと言いますが、そのチャンスは誰にでもあったはずです。でもニュートン以外は気づかなかった。セレンディピティFA法はそれと同じで、日常生活をちょっと意識するといったような、ちょっとした積み重ねによって発想力を引き出そうというものです。
―― 機械的にアイデアが生まれてくるなら、凡人には嬉しいですね。
安達 このようなトレーニングを積むことで、柔軟な発想法を身につけることができます。
ただ、そうした技法をさらに磨く方法があります。技法というのはいわばアプリです。つまりOSの上に乗っているわけです。アプリを最大限活用するためにも、OS自身が進化する必要がある。つまり、脳そのものの機能を進化させるのです。そのためには常に刺激を与え続けなければなりません。
―― 安達さん自身はどうやって脳を進化させてきたんですか。
安達 毎日、いろんなところに行きますよ。居酒屋で女を口説いている男のそばに座って、その会話を盗み聞く。海外に行ったら、最底辺の地区にも足を運ぶ。身の危険を感じて逃げて帰ったこともあるけれど、こうやって常に刺激を与えています。
僕の「超アイデア会議」というセミナーの最後は、街に繰り出し、経験をしたことのないようなディープな場所を紹介します。こういう経験をすることで、脳のリミッターを外すことができるのです。
―― 今後はどんな活動を考えていますか。
安達 最近、スクールを3つ立ち上げました。1つは、「コンテンツブレークスルーカレッジ」。いかにしてコンテンツを企画・作成し、それをどうやって世に送り出していくのか、というスクールです。もう1つが「日本ビジネスプロモーション協会」で、これは埋もれているコンテンツを発掘し、ムーブメントを起こしていくための協会です。
新しくつくるか、既存のコンテンツかの違いはありますが、いかにヒットとブームを生むかという意味では同じです。
そして、これから始めるのが、WiZ×Bizさんと一緒にやる経営者向けセミナーです。私と放送プロデューサー、雑誌編集長、テレビショッピングのプロデューサーが講師になって、ヒット商品やサービスの生み出し方を講義します。
僕の思いとしては、いままでのように自分でものをつくっていく仕事を半分、次の人たちに伝えていく仕事を半分という配分でやっていけたらいいと考えています。