




「ゴーン・ショック」――1999年、カルロス・ゴーン社長は「日産リバイバルプラン」として調達コスト見直しのために、系列の解体と、自動車生産に不可欠であるはずの鋼材調達先の絞り込みと大幅な値下げ要請を行った。これが引き金となって鉄鋼業界は大規模な再編に見舞われ、業界構造自体が再構築された。そしていま、ゴーン社長は外部ではなく、内部組織に対してゴーン・ショックを与えようとしている。志賀俊之COOの解任、エグゼクティブ・コミッティの再編は、日産自動車に何をもたらすのか。
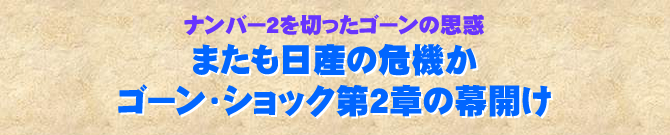
11月1日、日産自動車で電撃的な解任劇が起こった。
本来、日産の2013年3月期中間決算の発表は11月5日に行われるはずだった。その予定を繰り上げ、1日に発表会見を行うという連絡が入ったのが前日のこと。通常ならCOOである志賀俊之氏が発表する予定だったが、急遽CEOであるカルロス・ゴーン社長自らが会見を行うことになった。当然これは「重大発表がある」ことを示すものだ。

ナンバー2の志賀COOの電撃解任は衝撃を与えた。
会見に先立って報道陣に配られたニュースリリースには「役員体制の変更について」と記されていた。日産のナンバー2である志賀氏のCOO退任、最高意思決定機関であるエグゼクティブ・コミッティ(EC)のメンバー入れ替えが1日付で行われたのである。志賀氏解任の真意は何か、決算の数字はそっちのけで人事についての発言に注目が集まった。
もちろん、業績と人事が無関係であるはずはない。決算の数字は他の国内メーカーと比べて厳しいものになっていた。
日本メーカーを長らく苦しめていたのは、リーマン・ショック後に急激に進行した円高だった。いくら原価低減を進めても為替差損で消し飛んでしまう。トヨタですら単体決算の赤字を解消するのに5年を費やした。それがアベノミクス効果で年初から円安方向に進み、一時は1ドル=70円台まで進んだ為替は97~100円前後まで回復している。国内メーカー各社は1ドル=80円でも利益が出せる体質づくりを進めてきたおかげで、今年に入ってからの決算の数字は好調そのもの。為替差益の後押しもあって、この中間期の営業利益は、ホンダが前年同期比28.7%増の3564億円、トヨタに至っては同81%増の1兆2554億円まで数字を伸ばしている。
ところが、日産は1449億円の為替差益を得ながら、前年同期比7.8%減の2647億円にとどまった。営業利益率は6.3%から5.1%に悪化。中期経営計画「日産パワー88」では営業利益率8%を目標値に据えているだけに、大きな後退になったと言える。
今回の決算で、最大のトピックは、14年3月期の決算見通しを下方修正したことだろう。
日産の期初の通期見通しでは、為替レートを1ドル=95円としたうえで、営業利益7000億円を目標に掲げていた。営業利益率も6.3%と前期の5.4%を大きく上回るものだった。しかし、今回発表された見通しでは1ドル=97.9円で営業利益6000億円、営業利益率5.4%に修正された。国内メーカーの上方修正が相次ぐ中で、日産はひとり負けの様相を呈し、悪い意味で目立つ結果になってしまった。
もともと、今期の日産は上半期の苦戦が予想されていた。日産が他の国内メーカーに先駆けて注力していた新興国市場の停滞があったからだ。下半期の反攻を目論んでいただけに、想定以上の上半期のダメージが悔やまれる。
なかでも日産が期待していたのはブラジルだったが、12年から始まったメキシコからブラジルへの完成車の輸出制限により、メキシコ工場からの供給が制限されてしまっていた。14年初頭にブラジル工場が完成するまでは、売りたくても売れない状況がつづくことはわかっていたため、年が明けてからの反攻が期待されていた。しかし、レアルの通貨安の影響もあり、ダメージはより深刻なものになっている。
ロシアも生産計画が予定通り進んでおらず、インドも景気減速が著しい。頼みの中国市場も、尖閣問題以来の不振から、期待された伸びになっていないのが実情だ。新興国戦略に重きを置いてリーマン・ショックから回復してきただけに、市場拡大の見込みが甘すぎたのかもしれない。急拡大のツケが溜まってきているのではないか。
決算会見後、ある自動車記者は次のように漏らした。
「急拡大で兵站が伸びきってしまっている。どこかで見聞きしたような状況ですね」
販売台数を追って業績が急落したと言えば、リーマン・ショック前のトヨタがそうだった。世界一の座と販売台数1000万台を目指したトヨタは、利益を確保できる体質が伴わないまま拡大政策を続けた。リーマン・ショック前の04年、経営説明会に登場した当時の奥田碩会長は、拡大する生産・販売拠点に対し、「兵站が伸びきっている」とトヨタの弱点を語った。急拡大に追いつかない人材育成と、世界一は目の前という社員の驕りを戒めたものだった。奥田氏の不安は的中。世界一の販売台数を確保したその年にトヨタは上場以来初の赤字を記録することになってしまう。
環境が異なることから一概に当時のトヨタと日産を比較することはできないが、日産が中期経営計画「日産パワー88」で16年度までのグローバル市場占有率8%(750万台以上は必要と言われる)を掲げ、販売台数を追っている状況は同じだ。遠くを見すぎて足元をおろそかにすると、どんな結末になるのか、歴史が物語っている。
とはいえ、数字だけ見れば、日産はまだ営業利益率5%を誇る優良企業である。販売台数も下方修正したものの、過去最高の520万台を見込んでいる。何より純利益が3550億円確保できる見通しというのが大きい。赤字に転落してからでは再びリストラの嵐に飛び込むことになってしまうからだ。利益を出せているうちに、何らかの手を打つというのは正しい経営判断だと言えるだろう。そこはさすがゴーン氏だ。
ただ、問題はどんな手を打つか、である。
ゴーン氏は業績の下方修正と同時に、エグゼクティブ・コミッティの入れ替えという、いわば社内に対するショック療法という道を選んだ。

次期社長候補の呼び声も高いアンディ・パーマー副社長。
かつてゴーン氏の代名詞と言えば、「コミットメント経営」だった。必達目標を掲げ、それを達成できなければ責任を取るという、明快なスタイルで日産の改革を実行してきた。年度の業績目標という株主やステークホルダーに向けた目標値に対し、下方修正を行うことは裏切りに等しい。実は、この上半期の数字だけではない。前期の13年3月期決算でも、営業利益7000億円の見通しから下方修正、実績は5235億円の営業減益に終わった。
いつしか「必達目標」という言葉を使わなくなったゴーン氏だが、さすがに2年連続での下方修正では株主に対して申し訳立たない。
漏れ出てきた話によると、今回の決算見通しでは、下方修正をすべきか否か、意見が割れていたようだ。もともと後半に巻き返しの予定だっただけに、据え置くという意見が出ても不思議ではない。しかし、上半期の数字が悪すぎたために、志賀氏は下方修正をすべきとの意見だったとみられる。ゴーン氏は、下方修正を決断する代わりに、社員の意識を引き締める意味でも、懲罰人事は避けられなくなったようだ。
「通期の予想について、いろいろ議論しました。確かに痛みを伴います。当初の予測を達成できないと認めるのは難しかったのですが、下方修正を決めました」(ゴーン社長)
とはいえ、功労者で盟友でもある志賀氏に対し、懲罰人事という形にはしたくなかったのだろう。会見でのゴーン氏の言い分は次のようなものだった。
「今回の人事変更について、懲罰的だとは考えていません。現に志賀さんはこの場にいるでしょう? 懲罰ではありません。いまの体制でも、逆風の一部は吸収できる。しかし、拡大の取り組みに集中していくなかで問題が発生しているので体制を見直します。ECは平均年齢が高すぎる。ある時点で若返りを図らなくてはいけません。ただ若返りは徐々にやっていきたい。4月1日にも変更を発表します。将来的にも変更していく。しかしながら、業績が想定よりも低かったことで、実行を迅速化していきます」
志賀氏の退任、ECの入れ替えは、若返りの一環だとしたが、この人事で実質ナンバー2に就いたのは副社長の西川廣人氏である。志賀氏と西川氏は同学年であり、若返りとは言えない。また志賀氏とともにECから離れた副社長のコリン・ドッジ氏は、もともと年度末までに退任する意向を示していた。志賀氏の解任をカモフラージュするために、タイミングを合わせたとみるのが自然だろう。実質的にECをクビになったのは志賀氏だけだったのである。
実は13年8月29日、ゴーン氏がCEOを兼任している仏ルノーでもCOO解任劇が起こっていた。ルノーのナンバー2でCOOに就いていたのはカルロス・タバレス氏。ルノーの公式発表では「個人的プロジェクトの追求のため」としているが、真相はゴーン氏との感情的対立が原因だという。
タバレス氏と言えば、F1ファンの間では馴染みの名前でもある。現在チャンピオンチームのレッドブル・レーシングにエンジンを供給しているのがルノー。タバレス氏は大のモータースポーツファンであり、自身もテストドライバーからCOOに上り詰めた人物でもある。ルノーのF1活動に対する発言権もあり、タバレス氏の解任はルノーのモータースポーツ活動に少なからず影響を及ぼすと思われる。
そのタバレス氏解任のキッカケとなったのは、米ブルームバーグのインタビューだった。タバレス氏は「我が社では偉大なリーダーが君臨している。自動車産業に情熱を注ぐ者ならだれでも、ある時点でナンバー1を目指したくなるものだ」と語り、自らの権限拡大を求めていたという。
ゴーン氏は14年でルノーのCEOの任期が切れるが、再任されることも考えられる。仮にゴーン氏の引退が5年後ならば、タバレス氏は60歳を超えることになり、CEOを引き継ぐには遅すぎると考えていたようだ。他社でトップを目指すこともチラつかせていたようだが、この野心がゴーン氏の逆鱗に触れたらしい。ゴーン氏はルノーのCOO職を廃止し、職務は他の役員で分担させている。
8月にこんなことが起こった直後の日産である。ゴーン氏は日産の人事にあたり、ルノーの前例が頭にないはずはない。野心的なCOOは自らの存在を脅かすと認識したはずだ。
タバレス氏と志賀氏は状況が異なるが、ルノーのCOO職を廃止しながら日産のCOO職を残すのは違和感があったのだろう。日産もルノーと同じく、志賀氏の職務を西川氏、アンディ・パーマー氏、トレバー・マン氏の3人の副社長に分担させた。

実質的ナンバー2となった西川廣人副社長。
「組織体制は会社の戦略と目標に応じて適応していかなくてはいけません。COO職を設けたのは、私がルノーと日産の2社を経営することになった05年の時です。COOは、私がフルタイムで働いていた時には必要がなかった役職です。いまの日産は、05年の日産にくらべて、徐々に会社が大人になり、成熟し、経営層は重責を担うようになっています。いまの日産には、成熟したマネジメントが揃っている。ナンバー2として1人を置く必要はない。これからは複数のナンバー2にあたる人間を設けることが必要です。彼らが会社の責任の大部分を担う必要があります。ナンバー2(COO)が必要ないというのは、悪いサインではない。会社が大人になっているという証です。これはルノーもしかり日産も同様です」(ゴーン氏)
ものは言いようではあるが、ともかくナンバー2を置かず、権限を集中させないことを選んだのは間違いない。言い換えれば、ゴーンCEOに対する一極集中が進んだということだ。ちなみに、ゴーン氏は自身の責任と進退について次のように語っている。
「私次第ではなく、会社を持っている株主の方々次第だ」
株主が退任を迫れば、ゴーン氏は退かざるを得ないということらしいが、日産の株主を見てみよう。43.4%を持つ大株主は、言わずと知れたルノーである。ルノーの責任者はゴーン氏である。つまり、実質的にルノー以外のすべての株主が解任論をぶち上げるくらいでなければクビになることはない。すなわち、日産のCEOのヤメ時は、株主ルノーのCEOである自分が決めるということ。都合のいい話ではある。
それにしても日産は好調時を迎えると、なぜつまずくのか。未達に終わった中期経営計画「日産バリューアップ」の時もそうだった。トヨタが世界一を睨むなか、日産の販売は伸び悩んでいた。この時はリーマン・ショックでの危機感がバネとなって復活したが、何かしらの衝撃がなければ本気を出せない企業体質なのかもしれない。
ルノー、日産のCOO解任劇は、どこか来日当初のゴーン氏を思い出させる。
たとえ批判の声が上がろうとも、断固たる信念でミッションを遂行する「コストカッター」時代のゴーン氏である。当時の日本は、日本人にはないゴーン氏の圧倒的な改革力に畏れを抱いた。系列をぶっ壊し、鉄鋼業界の再編を招いた「ゴーン・ショック」は、日産社員にとって改革の本気度を認識させるに十分だった。ゴーン氏は再びゴーン・ショックで日産社員の目を覚まそうとしているのかもしれない。
電撃的な人事から始まったゴーン・ショックは成功するのか、日産の復活を検証したい。
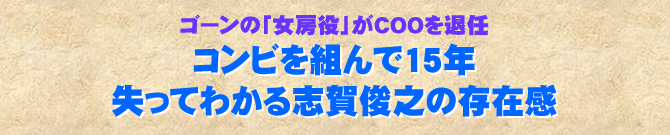
2013年11月1日付の人事で志賀俊之氏がCOOを外れ、副会長に就任することが発表された。志賀氏がCOOに就いたのは05年4月1日のこと。8年半の長きにわたりCEOのゴーン氏を支えてきた。60歳になり、退任が噂されていたのは事実だが、「女房役」の突然の解任に少なからず驚きの声も上がった。
志賀氏がゴーン氏と初めて会ったのは、ルノーと日産が資本業務提携の調印をする前年、1998年の秋だった。当時のルノー会長兼CEOだったシュバイツァー氏が、日産にゴーン氏を紹介するという形での面会だったという。当時のことをふり返り、志賀氏は本誌のインタビューで次のように語っていた。
「すごい迫力の人で、こういう人の下で働きたいと思いましたよ。その後、ルノーと日産のアライアンスの話が進んで、誰が日産にCOOとして来るかという時、当時の塙義一社長が三顧の礼でゴーンを迎えたと告白していますが、それは本当の話なんです。私は当時下っ端でしたから後ろのほうで見ていただけですけど、ゴーンには本当に圧倒されました」
99年に企画室長だった志賀氏は、ルノーとの提携後、アライアンス推進室長も兼務した。ルノーとのパイプ役として存在感を高め、まさにゴーン氏の“相棒”としてルノー・日産連合の礎を築いたと言っていい。
その後2000年に常務執行役員として海外市場を担当、中国東風汽車との合弁交渉などで実績を残し、05年にCOOに就いた。志賀氏が国内組の評価を高めたのは、「日産リバイバルプラン」以降、苦しむ系列や販社に対し、徹底的にフォローに回ったことだった。さらにゴーン氏の経営に対する考えを日産社員に浸透させる、文字通りパイプ役として、ルノーからの信頼も厚かった。いつしか、ゴーン氏と志賀氏の間には、言葉を交わさずとも互いを理解できる阿吽の呼吸のようなものが生まれていた。
「ゴーンの経営は不思議なワザを使っているのではなく、いわゆる王道、極めてオーソドックスな手法なわけです。王道だからこそ、こういう時にこう分析して、こう判断する、というのが理解できる。“天才の勘”だったら、こうはいかないでしょう。現にここ2週間ほど連絡を取ってないんですよ。でも日常的なことをいちいち相談しなくても、ゴーンならこう判断するということはわかる。私だけでなく、社員全体がわかれば、会社全体が同じ方向に進むことができる。私がCOOとしてやりたいのはそこです」(志賀氏・05年)
ゴーン氏が日産の経営トップに就いて以降、「日産リバイバルプラン」「日産180」と順調に中期経営計画を達成し、コミットメント経営の本領を発揮してきた。しかし、ゴーン氏にとって3度目の中計である「日産バリューアップ」で、初めて未達を経験した。
バリューアップでは、08年3月期のグローバル販売台数を420万台に設定していた。しかし販売台数は伸び悩み、07年3月期の決算は7年ぶりの営業減益、さらにバリューアップの達成時期を09年3月期まで1年先送りにする禁じ手まで使う危機を迎えた。
05年にCOOに就任した志賀氏にしてみれば、就任直後からの不振に、更迭論が上がってもおかしくない状況だったという。ゴーン氏にとっては、自分がルノーのCEOを引き受けたせいで日産が凋落したとは言えない。経営責任を問う声をかわす必要があった。
「時間が欲しい。未達成ではない」
ゴーン氏が初めて吐いた弱音ともとれる叫びだった。
しかし、時間の先延ばしはゴーン氏に有利に働いた。07年ごろから顕在化した米国のサブムライムローン問題が世界中に飛び火、08年9月15日にリーマン・ブラザーズが破綻したことで、世界的な金融危機に陥ってしまう。
世界中の自動車メーカーが赤字に転落し、悲鳴をあげた。もう誰も日産バリューアップの未達を責める者はいなくなっていた。経営責任ではなく、いかに危機を乗り越えるかに焦点が移っていった。
リーマン・ショックを受けて、09年2月、中期経営計画「日産GT2012」は破棄され、「日産リカバリープラン」が示された。労務費削減や企業スポーツ活動の休部など、痛みを伴う計画となった。売上高増を狙うよりも企業を存続させるべくフリーキャッシュフローを優先させる経営にシフトしたのである。
この間、志賀氏は国内販売店の再編や、電気自動車のインフラ整備に向けて神奈川県や横浜市との交渉なども行ってきた。表には見えない経営の裏方の仕事である。
どのメーカーも身を縮めて危機が去るのを待っていたような状況のなかで、日産は志賀氏が築いた中国市場の恩恵もあり、いち早く黒字を回復。11年3月期には418万台を販売、過去最高の販売台数を記録し、一気に上げ潮ムードになった。
その11年3月に、東日本大震災が起きる。
日産も例外ではなく、福島県いわき市のいわき工場は壊滅的な状況に陥っていた。当時、日産本社では対策本部が設置され、本部長を務めていたのが志賀氏だった。
いわき工場は「Z」や「GT-R」「フーガ」といった高級車のエンジンを生産している。震度6強の揺れによる被害も大きかったが、福島第一原発から57キロという距離にあったことで、屋内退避を強いられた時期もあった。志賀氏は、まだ屋内退避が解除されない3月21日にいわき市を訪れて、現地を視察、渡辺敬夫市長を訪問している。いわき工場の要望にもほぼ満額回答で応えた。工場の復旧に志賀氏の果たした役割は大きかった。

2005年のCOO就任会見。志賀氏の代わりは見つかるのか。
こうした現場との調整や、地方自治体との折衝など、志賀氏がいればこそ成し遂げられた交渉事は非常に多い。震災復興のために国内自動車メーカーが横の連携を取ることができたのも、10年から自工会会長を務めていた志賀氏の存在感があればこそだろう。渉外担当として志賀氏の役割を残したのも理解できる。
海外メーカーと日本メーカーのアライアンスは難しく、多くが訣別している。そんななか、ルノー・日産がここまで協調できたのは、ゴーン氏というより、志賀氏の存在抜きには語れないはずだ。
ルノーと日産の提携直後、ゴーン氏には「コストカッター」との異名がつけられていた。一切のしがらみを気にすることなくリストラに邁進した姿に、冷徹さを感じた日本人は多かったはずだ。ゴーン氏の冷たさとは対照的に、志賀氏は非常に柔和なやさしいイメージがある。それに引きずられてか、次第にゴーン氏も温和な表情を撮られることが多くなったように思える。志賀氏はゴーン氏に対し、何をすれば日本人の反感を買うか、どうすれば日本人に受け入れられるのかをアドバイスしていたようだ。
志賀氏のことをマスコミはゴーン氏の「女房役」「右腕」などと表現し、ゴーン氏と一対で捉えていた。ゴーン氏は今回の人事を「引責辞任ではない」と強調するが、志賀氏のこれまでの貢献は計り知れない。業績という数字に表れない大きなものを失ったのかもしれない。
(本誌・児玉智浩)
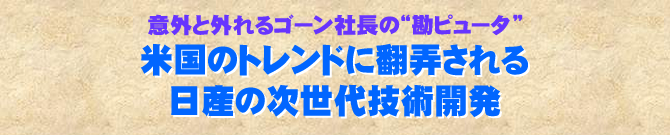
このところ、ドライバーが運転操作をせずとも車が自律的に走行する「自動運転技術」が脚光を浴びている。米グーグルが2007年に開発を開始し、アメリカ政府が強力に後押ししたことで開発熱に火がついた。それに負けじと安倍内閣が成長戦略の一つに組み入れたこの分野で、日産自動車が自社技術の先進性を強烈にアピールしている。
8月末、日産はアメリカで技術体験イベント「日産360」を開催し、日本からも大勢の新聞記者やジャーナリストたちを招待した。そのイベントのメインは自動運転であったという。参加したジャーナリストの1人は、
「自動運転といっても、まだ普通の車と完全に混走するには程遠いのは事実。ただ、日産がこの分野で先進性を見せつけて、技術力をアピールしたいという気持ちは痛いほど伝わってきた」
とその場の雰囲気を語る。
自動運転にこれだけ大胆に踏み出す決断をしたのは誰あろう、日産のカルロス・ゴーン社長だと明かすのは、ある日産OB。

EVではアテが外れたゴーン氏。
「自動運転はご想像のとおり、次世代の成長分野を作ることで大統領としての、また民主党としての実績をアピールしたいオバマ大統領が執着している技術です。ゴーンさんは多額の助成金が期待できる行政の紐付き技術が大好きなんです。オバマ氏が環境産業を成長させることで雇用増大を図るグリーンニューディールを大々的に打ち出したときも、ゴーンさんはEVでその話に乗った。自動運転もその流れでしょう」
ゴーン氏はこのところ、新しい“コミットメント”として、20年に自動運転技術の実現を目指すと言いだした。別の日産OBは、
「何か遠大なことを考えているわけではないと思いますよ。彼もまだ50代ですから、自動運転をコミットメントに掲げれば、あと7年は日産、ルノーの最高権力者として居座ることができると思っているんでしょう。もっとも、それは普通の車がきちんと売れて、シェアを伸ばすことができればの話。当面大丈夫だと思っていた販売が中国でダメになり、先進国でも調子が悪いとあらば、権力基盤が揺らぎかねない。そのこともあってか、最近は相当カリカリきているようですよ」
と、ゴーン氏が自動運転を権力基盤強化の道具に使っているのではないかという見方を示す。
20年に自動運転実用化という日産のスタンドプレーに、トヨタ、ホンダをはじめライバルメーカーの関係者たちは少なからず色めき立っている。
ホンダで先進安全技術を担当しているシニアエンジニアは言う。
「世界の上位メーカーはどこも運転支援の技術開発に全力で取り組んでいます。ウチもですし、トヨタさんやデンソーさんの熱意もすごい。トヨタさんは車だけでなく、道路側との連携のあり方も模索するために、専用のテストコースを東富士の研究所にわざわざ作ったくらいですからね。
自動運転の技術はその延長線上のもので、20年に自動運転のまね事らしきものをやるくらいなら、十分に実現できるんですよ。それを日産さんは、まるで自分たちが先駆者であるかのように宣伝している。ウチとトヨタさんがハイブリッドカーで火花を散らした時に、いきなりEVを持ち出して自分たちの技術レベルの高さをアピールした時と同じ手法だと思いますね」
トヨタは日産が自動運転を大々的にアピールした直後、首都高速道路で手放し運転を披露するというパフォーマンスを行った。当然のことながら行政サイドは「道路交通法違反だ」と気色ばんだが、それを押してでもどこだって自動運転の研究開発はやっているということを示して、日産を牽制しようという意図があったことは容易に想像できる。
もっとも、本当に20年に日産が自動運転技術で世界をリードできるのなら、今日の強弁も実るというもの。果たして日産の自動運転技術はモノになるのだろうか。
「日産の技術だけがコケるということはないと思います。そもそも20年に自動運転がエンドユーザー向けの商品に使える技術になるという可能性はほとんどありませんから」(前出のホンダ関係者)
先進技術に詳しい自動車ジャーナリストは、今後の展望を次のように語る。
「自動車の運転は認知、判断、操作の3段階からなるといわれます。周りの状況を見て、それがどうなるかを予測し、実際に運転行動を起こすというプロセスを、ドライバーは誰でもほとんど無意識のうちにこなしているんですね。そのうちアクセル、ブレーキ、ハンドルなどの操作については、実は現時点ですでにかなり機械化されているんですが、問題は前の2者。なかでも難物は2番めの“判断”なんですよ。
たとえば自転車が前にいるとします。ドライバーはその自転車に乗る人がチラッとこっちを見た時に、ああ、こっちに気づいているなとか、今にも飛び出してきそうだなといった予測を行います。しかし、少なくとも近未来の画像認識やレーダーシステムでは、そのような細かいコミュニケーションを取れるようになるメドはまったく立っていない。そのレベルの技術で自動運転車を公道に投入できると考えているエンジニアがいるとすれば、そのエンジニアは道路を走る資質のない人。少なくともトヨタ、ホンダ、ダイムラーなどは、完全自動運転は当分無理と考えていて、あくまで運転支援をメインに据えているようです」
ゴーン氏は、09年にEV戦略を大々的に打ち出し、11年には16年までに世界で150万台のEVを売ると豪語した。三菱自動車に次いで世界で2番めとなる量産EV『リーフ』を売り出しただけでなく、NECトーキンと共同でEV用の大型リチウムイオン電池製造会社、オートモーティブエナジーサプライを設立したりもした。

日本市場では受け入れられなかったタイ工場製「マーチ」。
しかし、フタを開けてみるとEV販売は伸び悩んだ。リチウムイオン電池は現時点では量産品として最も性能が良い蓄電装置なのだが、それでも重くて高価だ。リーフのようなコンパクトカーを、ある程度ユーザーに買ってもらえそうな価格に抑えるためには、どうしても性能を落とさざるを得なかったのだ。
加えて技術面でも、問題を抱えたままの見切り発車だったと指摘する声も多い。トヨタで蓄電装置の研究開発に携わっている幹部の一人は、リーフが発売になる前に技術情報を調べて、疑問を抱いたという。
「ウチでも日産さんのような成分の電池はさんざんテストをしていました。気温の低い状態で運用すると性能が落ちたり耐久性に問題が出たりと、あまり良い結果が得られませんでした。そのバッテリーを日産さんが積むと聞いた時、本当に大丈夫なのかと情報収集に走ったほどでした」
リース会社やバッテリーメーカーからも、それを裏付けるような話が漏れ聞こえる。日産はリーフを購入したユーザーに、バッテリーを保護するためには満充電の8割にとどめるよう推奨。さらに、一定期間内にバッテリー容量が基準値を超えて劣化したものについては、無料でバッテリーを交換する保証制度を追加するなどして信頼性をアピールしたが、リーフの販売は当初の日産の目論見どおりにはいかないまま今日に至っている。
EVばかりではない。ゴーン氏の“勘ピュータ”による見切り発車的な商品戦略は、決して打率が高いとはいえないのが実情だ。
10年、日産は主力コンパクトカーのマーチをフルモデルチェンジした際、国内産ではなく、タイ工場製のアジアンモデルに切り替えた。
導入当初は、信号待ちのときにエンジンを自動的に止めてガソリン消費を節約するアイドリングストップ機構を採用して燃費を向上させたことが話題となって、そこそこの人気を博していたが、長続きせずに販売は失速。13年10月には軽乗用車を除く販売ランキングで上位30位から転落するというありさまだ。
失策はそればかりではない。12年にはコンパクトセダンの「ラティオ」を同じくタイ製のアジア・中国市場向けモデルに切り替えたが、これも販売は低迷。北米ではある程度売れているが、それは「ヒュンダイの同クラスのモデルよりさらに安売りされている」(事情通)という販売支援策に支えられての好調だ。
「ゴーンさんはイメージさえ作れれば、低コストで作ったスペックの低い車でも売れると思い込んでいるフシがある。日産は、世界販売台数そのものは決して少なくない。しかし、車の販売価格は同クラスのライバルに比べて安いケースが多く、利幅は大きくないはず。マーチなど、ウチの車と比べてもスペックが低い。コストを安くしても販売価格まで安くなってしまっては、結局マイナス効果のほうが大きくなってしまう」(スズキ幹部)
なぜ日産は自社の車の付加価値を高めることができないでいるのか。それは技術開発の迷走と無縁ではない。
もともと日産は、90年代に経営危機に陥り、ルノーに救済される直前の数年間は、研究開発に投じる資金にも事欠くありさまで、技術開発競争の最先端から大きく後退した。
ルノー傘下に入った後、ゴーン氏はコストカットに大ナタを振るったが、その対象は過剰な生産設備の削減や人員整理、子会社株の売却だけでなく、研究開発のメニューにも及んでいた。
ちょうどその頃、日産は乏しい開発リソースを必死にやり繰りし、トヨタ、ホンダに続いて燃費性能に優れたハイブリッドカーの量産モデル『ティーノハイブリッド』の発売にこぎ着けようとしていた。しかし、ゴーン氏は当時、コスト高であったハイブリッドカーには未来がないと決めつけ、100台を限定的に売るだけでプロジェクトをやめてしまった。ハイブリッドカープロジェクトがなくなった後、エンジニアたちは市販とは無関係なモーターショー用のコンセプトカーの製作などに従事し、優秀な人材はほどなく散逸してしまった。
ゴーン氏はその後も次世代技術の開発には関心をあまり示さなかったが、上手かった部分もある。それは国内外の大学との産学連携。自動運転のベースとなるIT分野の先端研究で後れをとらずにすんだのは、とくにアメリカの大学の著名な研究室との連携を保てたからということに尽きる。
しかし、肝心要の商品開発はその後も混迷した。09年にEV戦略を打ち出したとき、「ハイブリッドカーはグローバル市場でのシェアがほんの数%でニッチ商品だ」と、さらにニッチなEVのことを棚に上げて言い放った。
移民でありながら、フランスのエリート養成校の一つである理系のエコール・ポリテクニークを卒業し、若くしてミシュランの経営の立て直しに貢献したりと、様々な実績をあげてきたが、その世渡りの中で自分の判断の誤りを絶対に認めないという処世術が身に染み付いてしまったのか、その後ハイブリッドカーの部品コストが急速に下がっても、その判断をなかなか修正できず、結果として持ち味であるはずの経営のスピード感を自ら殺してしまったのだ。
ゴーン氏がハイブリッドにようやく関心を示しはじめたのは、EV戦略の躓きが明白になってからのことだった。
頼みの綱は、先に述べたオバマ大統領のグリーンニューディールだが、オバマ大統領は実は科学技術にはあまり明るくなく、ブレインやシンクタンクの我田引水的な政策提言を鵜呑みにするところがある。グリーンニューディールの中にはEVを大量普及させるというメニューもあったのだが、技術的な裏付けがないままに提唱していたきらいが強く、今日ではほぼ頓挫している。

国内で展開する新型「スカイライン」はハイブリッドモデルのみ。
アテが外れ、EVの販売を急速に伸ばすことが難しくなった今日、問題となっているのは巨額の投資を行ったバッテリー製造子会社のオートモーティブエナジーサプライである。EVが売れなければ投資を回収することができるわけもなく、不良債権化するリスクすら浮上しているのだ。
「日産さんはハイブリッド戦略を唐突に打ち出した理由として、欧州での燃費規制への対応などを挙げていますが、もともと欧州市場における日産さんの存在感は薄く、たまたまヒットしたSUVで一見好調なだけ。その欧州市場への手当てというのも変な話です。おそらくオートモーティブエナジーサプライの稼働率を上げるには、大型バッテリーを使うハイブリッドをやるしかなかったのでは」(ライバルメーカー幹部)
日産はリーマン・ショック、東日本大震災といった厄災に見舞われながらも、一時はライバルに対して優位に戦いを進めることに成功していた。技術的には何を取っても2番手だが、技術や車のタイプなど、市場によって異なるユーザーの嗜好を敏感に察知し、ハイブリッドカー以外のものについては柔軟なクルマ作りをすることで技術力をカバーしてきた。そうやって時間稼ぎをしている間に、ライバルメーカーを技術開発でキャッチアップできれば、結果として技術格差はなかったことにできる可能性は十分にあった。
しかしゴーン氏が今取ろうとしている戦略は、日産の地力をコツコツと上げるのではなく、アメリカが仕掛ける自動運転のトレンドに乗るというスタンドプレー的なものだ。アメリカのシンクタンクは、オバマ政権におもねるように、自動運転の未来がすぐにでもひらけるようなレポートを連発している。グリーンニューディールのときと同じ光景が繰り広げられているのだ。
自動運転に必要な投資は、EVほどには大きくないため、日産のイメージの肥大化に上手く利用するのは、悪い手というわけではなかろう。しかし、イメージ戦略にかまけて、エネルギー効率の向上など、クルマの研究開発の王道でライバルに勝てるような取り組みをおろそかにしては、いつまでも2級勢力のままである。それが長引けば、いずれ技術力を蓄えた新興国のメーカーに食われることもあり得る。まさに今が正念場というところだろう。
(ジャーナリスト・杉田 稔)
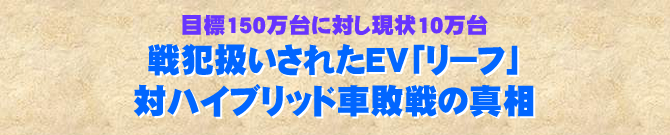
大手自動車で唯一、業績が悪化し事実上の更迭人事を実施した日産自動車。2014年3月期の通期業績見通しでも営業利益を下方修正したが、思うように業績が伸びない原因の一つに電気自動車(EV)の不振があるという指摘がある。果たして、日産のEV「リーフ」は売れていないのか。
「リーフの累計販売台数は、年明けのそう遠くはない時点で10万台を達成する見通しだ。少なくとも3月までには確実で、10年12月の発売から3年数カ月で10万台となる。同じ10万台達成に、プリウスの場合は(1997年12月の発売から2002年8月までの)4年9カ月を要した。プリウスの実績を上回ることに、大きな手応えを感じている」
日産のグローバルチーフマーケティングマネージャーオフィスEV&クロスカーラインマーケティング部長、トニー・ガーディナ氏は文法に忠実な英語で話す。 ガーディナ氏はフォード・モーター出身で日産に転じてからは、米国のインフィニティ部門、横浜本社のグローバルセールス部門を経て、今年8月から現職だ。
リーフの累計販売台数が3万台に達したのは、発売から1年6カ月が経過した12年5月。12年度の年間販売台数は3万445台だった。これが、今年度は10月までに2万8800台を販売した。
「11月には前年度の1年分を超えられる。13年度は5万台は突破できると考えている」とガーディナ氏。
累計10万台のうち、ほぼ半分は今年度の実績で占められる見込みだ。
なお、13年10月の世界販売台数は4559台。内訳は米国2002台、日本1257台、欧州を中心とするその他の地域が1300台。米国で最も売れている地域はジョージア州アトランタ市。また、人口約500万人のノルウェーでは10月、すべての車種の中でリーフがトップに立った。「(ノルウェーで)VWのゴルフにも勝った」(日産幹部)という。

ゴーン社長が2016年までに150万台売ると打ち上げた日産のEV「リーフ」。
一般に新車は発売直後に、バックオーダーをたくさん抱えて大きな販売台数を記録する。だが、時間の経過とともに、縮小していく。これに対し、EVのリーフは逆に「時間の経過とともに販売台数を増やしている。これには秘密がある。それはSNSやリアルの集会で“口コミ”により商品の魅力が広がったため」とガーディナ氏は話す。
リーフや三菱i-MiEVなどEVユーザーは、スマートフォンやネットを使いこなせる人が多く、フェイスブックなどに気軽に情報や感想を投稿する。また、後述するがユーザーによる集会も日米で開かれていて、日産の社員もボランティアで参加している。投稿やつぶやき、リアルな発言により、「客が客を呼ぶ構造」が13年夏以降に回り始めているともいえよう。
さて、こうした現象により販売数字だけを捉えれば、リーフの販売が急拡大を始めた、しかも、当時のハイブリッド車(HV)「プリウス」よりも速く普及している―と見ることができるかもしれない。
しかし、話はそれほど単純ではない。
日産は11年6月に発表した中期経営計画「日産パワー88」に、16年までに仏ルノーと合わせてEVを累計150万台販売すると盛り込んでいるのだ。まだ3年以上あるものの、前述の通りリーフはようやく累計10万台である。目標値と現実の数値との乖離は、あまりに大きい。「16年に150万台が達成できると信じる日産社員は、おそらく一人もいないだろう」(日産幹部)という声も聞こえる。これでは、ゴーン社長本来の「コミットメント」文化とも、相容れないのではないか。しかも、150万台に代わる修正計画は正式には出されていない。これでは、目標が見出せずに現場は混乱する。1990年代に、破滅へと疾走した、かつての日産と姿が重なってしまう。
ゴーン社長自身は、日産リバイバルプラン(NRP)の断行、中国市場の市域開拓、そしてEV開発と、短期間でゼロから1を生むのが得意な経営者だろう。逆に、長期的に1を10へと大きく育てなければならないとき、少しでも逆風が吹くと意外と脆い面を見せるタイプなのかもしれない。
それはともかく、今期の販売見込みの5万台は、リーフの発売当初に掲げた年間生産台数と一緒だ。もっと正確に言えば、発売の1年半前の2009年5月、リーマン・ショックによる08年度の赤字決算について発表していたゴーン社長が「追浜工場で年間5万台のEVを生産する」と明言したのが“5万台”という数字が歩き出した最初だった。
このとき、NECと共同開発していたラミネート型リチウムイオン電池を、突如掲げて「ゼロ・エミッション・カーのグローバルリーダーに日産はなる」と訴えた。
当初の年産5万台に見合う販売見通しが、実質3年目でようやく立てられた、というのがいまだろう。
が、リーフにはどうしてもスケール(規模)が求められる。
リーフのプロジェクトにはこれまで、約4800億円ともいわれる巨費が投じられたからだ。投資の対象は、主にバッテリー(電池)に向けられた。
日産が、本格的にEV開発をスタートさせたのは1991年1月。米カリフォルニア州が、前年にゼロ・エミッション・ビーグル(ZEV)規制を定めたためだった。大手自動車メーカーを対象に、排ガスを一切出さない自動車の販売を、98年以降に一定割合(2%)以上に義務づける規制だった。日産は電池の独自開発を目指すが途中で断念。リチウムイオン電池の開発メーカーであるソニーと96年に組み、同年に「プレイリージョイEV」、97年「アルトラEV」を発売する。少量生産のリース販売だったが、世界でZEVを商品化したのは日産だけだった。このため、98年に予定された規制自体はなし崩し的に緩和されていく。
パナソニックと組んだトヨタと、三洋電機(当時)と組んだホンダが、いずれも価格が安いニッケル水素電池から入りHVを商品化したのとは違う選択を、日産は行う。最初から技術レベルが高く、容量が大きい(電気をたくさん貯められる)リチウムイオン電池から入ったわけだが、パートナーのソニーがニッケル水素電池をやっていなかったことも選択の理由だろう。
だが、99年にソニーは採算性を主な理由に、日産と訣別する。一方、日産自体も大きな経営危機を迎えてしまう。ルノーが資本注入して、ゴーン氏が当初はCOO(最高執行責任者)で日産の舵を取りNRPが始まる。
実はこうした中、水面下で攻防があった。工場閉鎖をはじめ大リストラが断行され、金のかかるEV開発予算はゼロとなる。
その時、当時は技術開発担当の副社長だった大久保宣夫氏がゴーン氏に直談判。EVの重要性を訴えた。その結果、ゴーン氏の裁量で動かす特別な予算を獲得し、首の皮一枚でEVプロジェクトは継続されたのである。開発は終わっていた軽自動車のEV「ハイパーミニ」、「ティーノHV」を、経営再建真っ只中の2000年に相次ぎ実験的に発売する。いずれも、日立系の新神戸電機製リチウムイオン電池が搭載されていた。
ある政治家は「EVに消極的だったゴーンさんを、その気にさせたのは実は俺だ」と話すが、直談判によるプロジェクト継続が、ゴーン氏がEVと出会い、深く入っていくきっかけだった。
日産とNECが電池の合弁会社、オートモーティブエナジーサプライ(AESC、神奈川県座間市)を設立したのは、07年4月。このとき、電池の基本部分は既に開発されていた。日産は、ソニーと訣別した頃から、軽量なラミネート型を開発したNECを本命と決める。水面下でNEC製電池の実証実験も行った。
合弁から半年後の10月、リーフの車両開発は正式にスタート。プリウスやカローラ、ゴルフと同じCセグメントとすること、発売を10年末とすることなど、重要事項はすぐに決まった。AESC内の電池工場の大増強は、発売直前まで突貫工事が続いた。
リーフの販売は「13年度になってから、特に夏場から急拡大している」(ガーディナ氏)。
車両そのものが13年モデルとして12年12月、日本から順次世界に発売されていく。従来車と比べ80キロの軽量化、暖房にヒートポンプ導入、モータ改良などを行う。この結果、一充電走行距離(国土交通省審査値)を、200キロから228キロに向上させることができた。
米国で13年モデルは3月に発売されたが、8月までに前年同期比335%増と大きく伸びた。

まもなく始まる自動運転こそEVにうってつけ(カリフォルニアの実験施設にある自動運転対応リーフ)。
アトランタ以外にも、サンフランシスコ、シアトル、ロサンゼルスなど西海岸で販売が好調。米国の優遇税制に加え州による税制優遇が存在するが、これらの地域はEVへの優遇幅が大きい。
さらには、ガソリン車ならば複数人が乗車しなければ走行できないレーンでも、EVならば一人運転が許される。「環境に優しい車両EVを運転しているということを、周囲に見せつけることに喜びをもつ人は多い。リーフもテスラも、一目でわかる専用車。かつてシビックHVが売れなかったのは、専用車ではなくシビックとの区別がつきにくかったから。クールでなかった」(日米で仕事をする経営コンサルタント)。
環境意識が高い人、新しいモノをすぐに導入しようとする人が西海岸には多いのも、リーフ好調の理由だろう。
また、電気自動車そのものも、大きく伸び始めている。米EVベンチャーのテスラ・モーターズが昨年6月に売り出した、同社初の量販車「モデルS」も好調。累計販売台数は1万5000台を超え、「月1000台は超えてきている。富裕層に人気」(日産幹部)。価格は7万~10万ドル(約700万~約1000万円)で、1充電で500キロとガソリン車並みに走る。
ちなみにリーフの価格は約298万円から約384万円(日本で国の補助金を使うと、例えば約298万円が約220万円)。ステラよりはるかに安い。
ガーディナ氏は「一部の富裕層に絞るのではなく、まずはリーフをもって幅広い層に対しEVを普及させていくのが日産の戦略」と話す。
テスラは、ジャガーやBMWなどのユーザーがターゲットとなる。環境性能もさることながら、加速感などEV特有の上質な走りがセールスポイント。対するリーフの価格は3分の1であり、電池容量が小さい分、航続距離も短い。そのため、走りに加えて維持費の安さなどがリーフの“売り”となる。
売れ始めた13年夏から、日米で日産が始めているのが「オーナー・エンゲージメント・プログラム」という取り組みだ。ユーザー(オーナー)同士による情報交換のミーティング、リーフの愛着心を高めるためのある種のオフ会はそれなりに始まっていたが、ここに日産の技術者を含む社員を送り込んだのだ。もとはユーザーサイドから日産に要請があり応じたもので、日産の社員はボランティアで参加している。つまり、社員は会社から報酬をもらっていない。
「世界で働く日産の従業員は、日本人でも米国人でも熱いタイプが多い。日米とも幹部もけっこう参加している」(カーディア氏)そうだ。
会合は、フェイスブックなどのSNSを通じて始まったケースが多く、米国、日本とも集会場や公園などで開かれる。集会の規模や頻度などはマチマチだ。
群馬県の、とある道の駅にある休憩室(和室)で最近実施された集会には、子供連れを含めて約30人が参加した。雪道での走行、回生を生かすための運転の仕方、リーフに対応したスマホのアプリについて、お茶を飲みながら情報交換し同時に交流を楽しむ。「1000キロ走って、電気代は1200円という書き込みがあった」といった話題も出る。
日産の社員は会合で、求めに応じて質問に答えていくが、ユーザーと直接対話し生の声を聞くことで販売やマーケティング活動、開発などに生かせる知見の確保につながっている。
「これまでのガソリン車と異なり、リーフを売るためにはお客への啓蒙と説明は不可欠。ITと親和性が高いリーフの使い方は、日々進化していくから。リーフが急に売れ出した秘密は、口コミの力だが、日産社員の参加により口コミは加速した」(ガーディナ氏)
日産では近く欧州でも、同様のプログラムを始める。現地の社員をユーザーのコミュニティへと投入していく。また、日産は、新たなスマホアプリを来年の早い段階で配布する計画でもある。
自動運転にはEVが有利
日産は16年度中にリーフを含めて4車種のEV投入を計画している。新型リーフ、小型商用車、高級車のインフィニティ、最後の1車種に関する詳細は出されていないがスポーツタイプの公算が強い。
インフィニティはテスラと競合が必至であり、「電池の性能で勝敗は決まるのでは」(ライバルメーカー)とも見られる。もっとも、150万台という計画自体があやふやであるだけに、新車投入計画もどうなるのかわからないが、三菱自工との提携から軽自動車ベースのEVも共同開発していく計画が浮上している。ガソリンなど液体燃料に比べ、電池はエネルギー密度が小さいため「EVは軽自動車など小さな車両に向く」(益子修・三菱自工社長)特性があるという。
15年には、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の排出規制が、世界的に厳しくなっていく。環境保全に加え原油価格も高騰に向かい、自動車を電動化させていく必要に迫られる。とりわけ液体燃料は、航空機のために安定的に確保しておかなければならない。
近い将来は、EV、HV、PHV(プラグインハイブリッド車)、レンジエクステンダー、FCV(燃料電池車)といった電動車両、さらにクリーンディーゼル車や低燃費ガソリン車など内燃機車両が、混在していく形になっていくだろう。
競争はますます激しくなるが、EVは走行中に一切の排ガスも二酸化炭素も排出しない。軽自動車の大手、スズキのユーザー調査によれば、「1日の走行距離は20キロ未満が大半」(スズキ幹部)だった。つまり、一充電で200キロも走れば、軽自動車のような小さなクルマならば日常的なことには問題なく使えるはず。また、将来の自動運転には、HVなどよりEVやFCVは向く。エンジンを使う車よりも電気を制御するほうが反応が早いからだ。
リーフが達成する見込みの3年強で販売累計10万台は、日産にとって重要なのかどうなのか。「10万台というマイルストーンを通過する意味は、やはり大きい。リーフが着実に普及しているということを、示せるのだから」と、EVを担当する志賀俊之副会長は話す。
実質的に99年から続くゴーン体制の行方とともに、日産が環境時代にEVを社会にどう普及させていくのか、その本気度も実力も、これから本当に試されていく。
T型フォード以来、「100年以上続く内燃機関車の時代からEV時代に代わっていくのは、革命的なこと」(ガーディナ氏)なのは間違いないのだから。
(経済ジャーナリスト・永井隆)
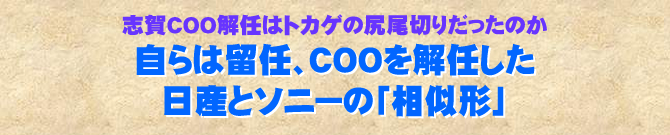
他稿にもあるので詳しくは触れないが、日産自動車は11月1日、中間決算を発表すると同時に、志賀俊之COOがCOO職を離れ副会長に就任すると同時に、コリン・ドッジ副社長兼CPO(チープ・パフォーマンス・オフィサー)がCPO職を離れると発表した。
志賀氏は2005年にCOOに就任。ルノーCEOを掛け持ちするゴーン氏をサポートしてきたが、ついにその座を解かれることになった。通常の人事であれば、後任のCOOを誰かが引き受けることになるが、今回、日産はCOO職を廃止、新たに西川廣人氏、アンディ・パーマー氏、トレバー・マン氏の3人が分担してCOO職を引き継ぐことになった。
この人事によって「ゴーンCEOの独裁色が強まった」と見るのが自然だろう。これまでは志賀氏がクッションの役割を果たしていたが、すべての業務が直接ゴーン氏とつながることになるからだ。
また、ゴーン氏は否定しているものの、今回、日産が通期営業利益見通しを、従来予想より1200億円下方修正しているため、志賀氏はその責任を取らされたとの見方は強い。
かつてゴーン氏は、日産リバイバルプランによる再建策を発表した時に、「これはコミットメントだ」と強調。達成できなかった時は退陣すると宣言した。この「コミットメント経営」は一種の流行語となり、日産を象徴する経営手法ともなった。
ところが今回、業績目標到達が不可能になった時にゴーン氏が選んだのは、自らの進退ではなく、COOの志賀氏の退任だった。「トカゲの尻尾切り」と言われてもしかたがない。
ゴーン氏にしてみれば、来期以降の業績回復によって、今回の人事の正当性を証明するしかない。逆に、ゴーン氏への「権力一極集中人事」が功を奏さなかった場合、ゴーン氏の威信は大きく傷つくことになる。
「ゴーンさんにしてみれば、瀕死の日産をここまで成長させたという自負もある。ただ、長期政権が続き、志賀さんのCOO任期も8年を超え、ややマンネリ化してきたことも事実。そこでゴーンさんは一種のショック療法として今回の人事を断行したのでは。決算発表の日程を前倒しし、出席しないはずのゴーンさんが壇上に立つ。これだけで社内には緊張が走ったでしょう。そしてCOO退任を発表する。そのインパクトは大きかったはずですよ。
問題はこれからです。結果が伴えば名人事となるけれど、うまくいかなかったら“ゴーンの限界”と言われることになる。実際、今回の日産と同じような人事をやっておきながら成果を出せず、最後は戦犯扱いされて会社を去った外国人経営者もいましたからね」
と語るのは、古くから財界を取材している年輩記者である。
この記者の言う、「会社を去った外国人経営者」とは、昨年、ソニーCEOを退任したハワード・ストリンガー氏のことである。
ストリンガー氏がソニーCEOに就任したのは2005年のことだった。
それ以前のソニーCEOは出井伸之氏。出井氏は1995年に社長に就任、2000年からは会長を務めていた。ソニートップとなった出井氏は、見た目のスマートさに加え、フランス映画の巨匠のルイ・マル監督と親交があるなど文化的な香りを漂わせていたこともあり、たちまち人気経営者となっていく。
ITバブルにも乗って業績も好調、株価も2000年に3万3900円の高値をつけた。出井氏はそれまでの歴代トップと違い、創業時の社名、東京通信工業時代を知らない第二世代の経営者だ。2000年頃までの出井氏の活躍を見ているかぎりでは、ソニーは無事、代替わりを果たした、と思われた。ところがITバブルの崩壊と同時にソニーにも暗雲が立ち込める。ブラウン管テレビにこだわり、液晶テレビに出遅れたこともあって業績は低迷、03年、業績の下方修正をきっかけにソニー株は急落する。世に言う「ソニー・ショック」である。
以来、出井氏の評価は一変、社内外から批判の声が出て、結局05年に安藤国威社長ともども退陣せざるを得なかった。代わって会長兼CEOに就任したのがストリンガー氏だった。
ソニーのトップには、他の電機メーカーのトップとは違う資質が求められる。というのも、ソニーはエレクトロニクス=ハードと、エンタテインメント=ソフトそれぞれの部門を持つ、世界で唯一の両輪経営を行っている。そのため、単にハードに明るいというだけでは通用しない。特にソフトについては、買収したアメリカのコロンビア映画(現ソニー・ピクチャーズエンタテインメント)で散々苦労したこともあり、これを御する能力を求められた。そこで白羽の矢が立ったのが、米三大ネットワーク、CBS社長を務めた経験があり、ソニーアメリカ会長だったストリンガー氏だった。ストリンガー氏はアメリカのエレキ事業を立て直した経験もあり、両輪経営を標榜するソニーのCEOにふさわしいように見えた。
当時、よく言われたのが「ストリンガーは第二のゴーンになれるか」ということだった。ゴーン氏はルノーから日産に派遣されたが、ルノーの前にはタイヤメーカー、ミシュランで実績を残している。2人に共通するのは他の業界を知っているプロの経営者であること。ゴーン氏の日産での成果が華々しかっただけに、ストリンガー氏にも同様の結果を期待した。

2009年、ソニーのストリンガー会長(右から3人目)は中鉢社長(同4人目)を解任し、権限を自らに集中させた。
出足はまずまずだった。前述のように、当時のソニーの最大の泣き所が、液晶テレビの出遅れだった。しかしストリンガー体制になって初めて迎えたクリスマス商戦。ソニーの液晶テレビ「ブラビア」は瞬間風速ながらも「液晶のシャープ」の「アクオス」を上回りシェアトップにも立った。株価も半年近くで5割も上昇した。「第二のゴーン」が現実のものになるかもしれない。期待はさらに膨らんだ。
その後曲折はあったものの、08年3月期決算では過去最高益を計上、ストリンガー体制は盤石かと思えた。そこをリーマン・ショックが襲った。それによって明らかになったのは、ソニーの過去最高益は資産の切り売りによってもたらされたものであって、高収益体質になってはいないことだった。そのためリーマン・ショックで世界同時不況が起きると同時に、ソニーの業績は水面下に沈んだ。同時にストリンガー氏がゴーン氏の再来だと言う人はどこにもいなくなった。
05年のストリンガー体制発足時から、ソニートップはストリンガー会長兼CEO、中鉢良治社長兼COOのコンビだった。ストリンガー氏はひと月のうち1週間から2週間しか日本に滞在しない。またエレクトロニクスにも明るくない。そこで、日ごろのオペレーションやエレキ部門については中鉢氏に任せていた。
リーマン・ショック後、エレキ部門が大赤字となり、ソニー本体も赤字転落すると同時に、経営陣の責任を問う声が強まった。そこでストリンガー氏は思い切った人事を断行する。
09年4月1日付で、中鉢社長は副会長となり、ストリンガー氏が社長を兼務することになったのだ。さらに40~50代の執行役員4人を抜擢し、COOの役割を分担させた。中鉢社長を副会長に棚上げした理由についてストリンガー氏は、「余計なレイヤー(階層)はいらない」と語っている。中鉢氏がいたことが、自分と事業責任者との距離を遠ざけていた、中鉢氏こそ、エレキ不振の根源だと言わんばかりだった。
「でも実際のところは、ハワードのハード音痴がソニーのエレキがおかしくなった最大の理由です。AIBO(犬型ロボット)のようなソニーならではの商品も、利益が出ないために製造を中止するなど、製品に対してほとんど興味を持たなかった。そのためエンジニアの間では、いずれハワードはエレキ部門を売却するつもりじゃないか、との噂まで出たほどです」(ソニーの中堅エンジニア)
ストリンガー氏はソニー時代「ソニー・ユナイテッド」という言葉を口にした。また「サイロを壊す」という言葉も、経営方針発表会などで繰り返し使っている。
しかし内情は、エンジニアたちはエレキに理解のないCEOに不満を抱き、ストリンガー氏はヒット商品を生まない現場にいらだちを募らせるという状況で、ソニー・ユナイテッドとは口当たりのいいスローガンにすぎなかった。
そのため、中鉢社長を中抜きする人事も効果を発揮することなく、結局、ソニーは赤字を積み重ねていくのだが、中鉢氏がいなくなった分だけ、ストリンガー氏への批判は強まっていき、12年2月に開かれたソニー指名委員会で、ストリンガー氏の4月1日付でのCEO退任が決まった。ストリンガー氏は最後まで会長職にとどまりたいとの意向を示していたが、指名委員会は株主総会までの留任しか認めなかったため、6月に取締役会議長となり、13年5月、取締役も退任した。
結局、自分に権限を集中させ、レイヤーを少なくして経営にスピード感を持たせようとの目論見は実らなかった。
今回、日産が発表した、志賀COOが副会長になり、その業務を3人の副社長が担当するというのは、09年のソニーの人事に瓜二つだ。強いて違いを挙げれば、ソニーの場合、四銃士はすべて日本人だったが、日産の三銃士は日本人1人に対して外国人2人というところだが、COOの処遇も、CEOに権限を集中させるやり方もまったく同じである。しかもゴーン氏はルノーCEOを兼務しているため、日本にいる時間も限られている。社長兼務後も、日本での勤務は限定的だったストリンガー氏と、これまた相似形だ。
もちろん企業の置かれている立場はソニーと日産ではまるで違う。ソニーは赤字転落がきっかけで人事を断行したが、日産は下方修正したとはいえ、営業利益率5%以上を誇る優良企業である。ただし、経営者の危機感という意味では同じなのかもしれない。ゴーン氏にしてみれば、いまのうちに手を打っておかなければ将来的に取り返しがつかなくなると感じたのかもしれない。

今度の人事の成果でゴーン氏の評価は定まる。
いち早く手を打ったのは、ゴーン氏ならではの慧眼と言えるのかもしれない。ただし、権限の集中が、必ずしもいい方向に働くとはかぎらない。志賀氏のような存在が、組織の上で果たす役割は意外と大きいからだ。
1999年にゴーン氏は来日。半年後に日産リバイバルプラン(NRP)を策定して聖域なき構造改革を行った結果、日産は劇的に立ち直った。これは、産業史に特筆されるほどの快挙である。この時ゴーン氏は、それまでのしがらみや慣習をことごとく破壊し、コスト削減と生産率向上と、社員のモチベーションアップを同時に成し遂げた。
しかし、従来の仕事のやり方を根本から否定するかのようなNRPにとまどう社員も多かった。そのとまどいが、ゴーン氏に対する恨み節に転じることもあった。
この時、バッファー役としてゴーン氏をサポートしたのがゴーン社長の前任者、塙義一氏だった。
塙氏は早いうちから日産のプリンスと目され、1996年に社長に就任した。当時の日産は、シェアは右肩下がりで低下、財務も毀損し、「明日をも知れない」という言葉が誇張でないほど惨憺たる状況だった。そのため社長になった塙氏の最大の仕事は、生き残るための提携先を見つけ出すことだった。
当初は独ダイムラーと提携を模索したが不調に終わり、最後に望みを託したのが仏ルノーだった。
幸いルノーとの提携交渉は上首尾に終わり、今日のルノー・日産連合が誕生する。言わば塙氏は、いまの日産の形をつくった立役者である。
ゴーン氏が赴任してからも2001年までの2年間は、塙氏が社長兼CEOだった。つまり最終責任者であるにもかかわらず、塙氏はゴーン氏のやりたいようにやらせた。その代わりになだめ役に回り、社内の不満を一手に引き受けた。塙氏の存在が一種のガス抜きとなったのだ。この功績はけっして小さくはない。
志賀氏の存在も同様だ。カミソリのように、触れれば切れるほど鋭いゴーン氏を志賀氏がソフトに包み込んでいたからこそ、ゴーン氏が誤解を恐れることなく経営手腕を発揮することができた。社員にしても、ゴーン氏に文句は言えないが、志賀氏に対してなら、具申することができる。志賀氏を通すことで、ゴーン氏と社員が多少なりとも意思疎通することが可能になっていた。
ところがこれからは違う。たとえは悪いが、抜身の刀を持ったまま、ゴーン氏は社内を練り歩くことになる。いままで鞘の役割を果たしてくれた女房役は自らの手で更迭してしまった。これがどんな結果を生むのか。意思決定が段違いに早まり、ゴーン氏の指示がダイレクトに末端まで届くのか、あるいはゴーン氏が雲上人になってしまうのか。こればかりは行く末を見守るほかはない。

ストリンガー氏はエンジニアの反発を買った。
少なくとも4年前に似たような人事を行ったソニーの場合、結果は吉とは出なかった。ソニーのエンジニアは、エンジニア出身の中鉢社長に対して、「自分たちの気持ちをわかってくれる人」という仲間意識を持っていた。それが更迭されたことで、エンジニアの気持ちは一気に萎えてしまった。そしてストリンガー氏には、しぼんでしまったエンジニアの士気を、再び燃え上がらせることはできなかった。
「ゴーンさんに必要なのは、NRPを行っていた時のように、自らの責任を明確にすることです。コミットメント経営で一世を風靡したゴーンさんですが、08年に『必達目標は社員を怖がらせ、不安にさせていると思った』と、その看板を下ろしています。確かに社員を必要以上に怖がらせる必要はないでしょうが、いま問われているのは、自らの責任をどうコミットメントしていくかということです。少なくとも、今度の人事を社員が“トカゲの尻尾切り”と考えているようでは、士気は上がりません」(前出の財界記者)
十数年前、日産自動車を蘇えらせたのは、ゴーン氏の不退転の決意だった。いま一度、その決意が必要なのかもしれない。


柴田 裕 キーコーヒー社長
しばた・ゆたか 1964年、神奈川県生まれ。87年慶応大学経済学部卒業後、木村コーヒー店(現・キーコーヒー)入社。第一営業部などを経て、2000年常務、01年専務、02年から現職。今年、同社のフラッグシップコーヒーの「トアルコトラジャ」(インドネシアの直営農園で育てている豆)発売から35周年の節目を迎えた。
コーヒー市場争奪戦が過熱してきた。遡ると、1996年にスターバックスコーヒーが日本に上陸した後、タリーズコーヒーなど外資系チェーンが増えてカフェ事情が一変し、「コーヒー戦争」と呼ばれた。近年でも、大手コンビニが淹れたての「100円コーヒー」で攻勢をかけ、競争は激しさを増している。
加えて、ネスレ日本では9月から“インスタントコーヒー”という呼称を“レギュラーソリュブルコーヒー”に変更、価格面のみならず品質競争にも拍車がかかる。そこで、東京五輪開催の2020年に創業100周年となる老舗キーコーヒーの創業家社長、柴田裕氏に、同社の差別化、勝ち残り策などを聞いた。
―― 一口にコーヒー市場といっても、外食、コンビニ、カフェ、缶コーヒー、家庭用など様々ですが、いずれにしても競争自体は激化してきています。老舗のキーコーヒーとしては、どう勝ち残りに挑みますか。
柴田 企業はヒト、モノ、カネと言いますが、プラス、情報とブランドだと思うんですね。で、当社がこれまで少し弱かったのは、ブランドのところだと思っています。
もちろん、老舗ということでご存じの方もたくさんいらっしゃるんですけど、若い時にキーコーヒーに出会わなかった人には、コーヒーと言えば、外資系のコーヒーチェーンで紙コップで買う商品というイメージも強いですから。
店の看板に、キーコーヒーのロゴを掲げている喫茶店なら馴染みもあると思いますが、喫茶形態のみならず、ほかの商品も含めてもっともっとブランドを認知していただくことが重要です。コーヒー会社がたくさんある中で、「ほかの企業も知っているけど、一番美味しいのはキーコーヒーだね」とか、「ギフトで一番喜ばれるのはキーコーヒーだろうな」と、お客様からそんなふうに評価される会社でありたいですね。
―― キーコーヒーには、昔からのファンというコアな人が多いのでは。
柴田 今年3月に増資をしまして、個人株主が3万人から3万5000人に増えたんですけど、確かにそういうコアな株主が増えたと思います。5000人増えたこともあって、今年の株主総会では初めて出席者が1000人を超え、1200人の方が総会に来られました。ありがたいことです。当社の株は100株から買っていただけますが、300株からは、“株主限定ブレンド”という優待品もご用意しています。
もう少し、そのコアなファンのボリュームを増やしたいですし、当社の認知度は、たとえば九州全域と沖縄では割と強いんですが、中国、四国、近畿エリアなどでやや弱い。これは、現地への進出のタイミングが遅かったか早かったかが大きいと思います。
―― 業績的には前期(13年3月期)から増益に転じました。
柴田 前々期(12年3月期)は純損失を出してしまいました。当時、コーヒー豆の相場が上がったため、商品の値上げをさせていただいたんですが、11年の3月初めに値上げを発表して、直後の11日に東日本大震災が起こってしまった。あの混乱のさなかでしたから、値上げ実施はしばらく先送りせざるを得ず、それで利益が増えなかったのです。
―― 現在はコーヒー豆の相場も落ち着いてきていると思いますが、最近は円安がやや逆風ですね。
柴田 円安は、コーヒー豆だけでなく輸送燃料の高騰などにも関わってきますから。
当社の売上構成は、業務用で4割、家庭用が3割、原料用で3割あって、原料用というのは、缶コーヒーの会社にコーヒー原料を買っていただくビジネスです(JTの「ルーツ」ほか、ビールメーカー系飲料会社など取引先は広範囲)。
事業構成比的には、これまでこの「4・3・3」できたのですが、最近はクロスオーバーしてきています。ですから、当社でもこれは業務用、あれは家庭用とか、あまりカテゴリーごとに考え過ぎてはいけない。たとえば、コンビニの店頭で淹れたてコーヒーを買うという行動は、外食、中食、家庭用のどれにもあてはまりますしね。
あまり安穏としていてはいけないですが、日本でコーヒー市場が伸びてきた過程では、これまでもいろんなトレンドがありました。1960年代から70年代は喫茶店ブームでしたし、80年代からファストフードが出てきて、90年代に外資系コーヒーチェーン、2000年代からはイタリアンブームがあって、さらにコーヒー市場が伸びています。そして最近はコンビニコーヒーと。
そういう積み重ねが、コーヒーの消費全体には貢献していると思いますし、コンビニコーヒーの影響も、我々以上にファストフードやコーヒーチェーンのほうが大きいでしょう。要は、お客様が利用シーンによって使い分けていくのではないかと。
―― コーヒーマーケット自体は、規模感的にはどのくらいですか。
柴田 何を基準にするかですけど、当社のシェアでだいたい15%ぐらいと言われています。売上規模で言えば500億円強ですから、残り85%が2500億~3000億円の間ぐらいというところですかね。
―― キーコーヒーとしては、中長期的に売上規模をどのくらいまで拡大する計画ですか。
柴田 ここのところ、当社は資本業務提携などが続き、いまもその手のお話はいろいろあります。ただ、しばらくはいまのガバナンスに注力していきたいですね。この規模で株式上場しているコーヒー会社はありませんので、なんとか勝ち抜いていきたいと思います。
―― 確かに、05年にイタリアントマトを子会社化し、昨年はアマンドを子会社化、さらに今年、銀座ルノアール(ジャスダック市場上場)と資本業務提携を結ぶなど、アライアンスが加速してきました。
柴田 イタリアントマトの時は当時、ナムコさんが(イタトマの)親会社だったんですが、ナムコさんがバンダイさんと経営統合するにあたって、イタトマを引き受けてほしいと言われましてね。
イタトマは当社が手を挙げないと、ある居酒屋チェーンに買われそうになっていました。それなら親和性がより高い、当社に任せたほうがいいというご判断も働いたようです。当社の子会社になって、イタトマ当時よりもライトな「カフェジュニア」という業態にしましたので、地方のショッピングセンターなどにも出店がしやすくなりましたね。いま、フランチャイズで300店舗ぐらいになっています。

新業態「キーズカフェ」の外観パース。
アマンドについては個人的にも昔からよく使っていて、お取引としてのお付き合いも、もう50年ぐらいになりますが、先方の経営者が、「会社が厳しくなって何かあったら、キーコーヒーに頼みなさい」とおっしゃっていたようです。店舗数も、一時期は相当多かったんですが、立ち行かない店も少なくなかったのでかなり閉めていただきました。まだその過程にあり、不採算のところを整備していく必要があります。
3つめの銀座ルノワールは優良投資先の1つで、何か一緒にやろうという話し合いを続けてきました。あちらも株式公開会社ですので、ある程度の規模感があって、組むのだったら大きな外食企業よりもキーコーヒーがいいとおっしゃっていただいた。で、「喫茶室ルノアール」は東京23区内に100店舗(自社物件店舗、賃借店舗といろいろだが、ほとんどが直営店)もありますから、そういうアドバンテージも利用していければ、と。
―― その3業態の海外展開はどうでしょう。
柴田 イタリアントマトでは、すでに少しずつ海外で出店し始めていますけど、ほかの業態も海外で引き合いがあります。特にアジアを中心に、日本の外食産業はとても人気があって、喫茶業態も結構、人気があるようです。こういった市場も狙っていきたいですね。新興国の大都市では、ちょっと価格が高めの商品でも、中流層の拡大でだいぶ消費が活発になってきていますから。
―― 同業のUCCがUCCホールディングスと持ち株会社形態にしていますが、アライアンスが活発になってきたキーコーヒーでも持ち株会社化は検討しているのでしょうか。
柴田 方向性の1つとして検討はしていますが、現段階ではどういう形がいいかわからないですね。
―― 買収や資本参加だけでなく、キーコーヒー自身も「キーズカフェ」という新業態を始めています。
柴田 とはいえ、これは別会社を作ってやっているものではありません。いま、デパ地下中心にコーヒー豆の挽き売りの売り場が72ヵ所あるんですが、これは直営店と言えなくもない。一方で、キーズカフェというのは、キーコーヒーのブランドを上手に活用したいという方に向けてご提案している小型店業態で、いまのところ、高速道路のサービスエリアとか病院などでの立地が多くなっています。もう1つ、キーズカフェの特徴は、フランチャイズと直営の中間業態とでもいうべきもので、お取引先サポートの傾向が強いこと。
―― サポートとは?
柴田 たとえばその土地で人気のパスタレストランのオーナーに、店近くの病院や公共施設にも何か出店してほしいという声が地元からあったとします。そこで、パスタレストランの業態のままではちょっと重たいので、もう少し軽いカフェ業態なら出せるという時に、我々のご提案が活きてくるんです。
―― 多面的な展開で売り上げを伸ばしていこうということですか。
柴田 もちろん、個々の事業のセールスで売り上げを作っていくことも大事ですが、売り上げ自体はどこかのPB(プライベート・ブランド)を受託するなど、作ろうと思えば作れるんです。あるいは破格の条件を出して、コーヒー飲料の原料を受注しても売り上げは伸びるんですけど、それだと利益が伸びませんし、何よりキーコーヒーという存在感が希薄化してしまいます。
ですから、そういう事業もやりつつ、そのボリュームはある程度のところでとどめないといけない。キーコーヒーのものだから買ってもらえるという商品、あるいはご来店いただける業態を開発し続けることが大事です。当社には、氷温熟成コーヒーという独自技術の商品もありますし。
―― 最後に今後の重点課題を。
柴田 ブランド磨きに尽きますね。昔は、コーヒー会社といえば当社かUCCさんかと言われていたんですが、いまは外資系チェーンを挙げる方もいますし、コーヒーで想起される企業として、もう少し憧れのブランドにしていきたいと思います。そのために、商品と業態の両方を磨いていく。
日本は今後、ますます人口減少と高齢社会が加速するわけですが、当社に関しては、成熟されたシニア層の方のほうに比較的認知度が高いので、あまり大きくは心配していません。ともあれ、コーヒーでちょっと贅沢をという時、キーコーヒーを選んでいただける、あるいはすぐに思い浮かべていただけるようにしたいですね。
(聞き手=本誌編集委員・河野圭祐)


中村康浩
東京ミッドタウンマネジメント社長
なかむら・やすひろ 1960年5月10日生まれ。福岡県出身。早稲田大学政治経済学部を卒業し、84年に三井不動産に入社。宅地事業部、広報部、横浜支店、ビルディング本部、関西支社などを経て、2004年より秘書部。07年から5年間秘書部長を務め、12年4月から現職。三井不動産東京ミッドタウン事業部長も兼務する。横浜支店時代の同支店課長が現在、三井不動産社長の菰田正信氏。
六本木ヒルズと並んで、同エリアのランドマークになったのが、2007年に開業した東京ミッドタウン。六本木ヒルズとは一味違う街作りでスタートしたミッドタウンは、さらにどう進化していくのだろうか。
〔2013年4月。森ビルが運営する六本木ヒルズが開業10周年イベントを開催したのと前後して、六本木エリアのもう1つのランドマークである、東京ミッドタウン(運営は三井不動産グループの東京ミッドタウンマネジメント)も動いた。開業6周年を迎え「ニューステージオープン」と称して、商業施設テナントの入れ替えで新たな展開を発表したのがそれだ〕
敢えて、呼称を「リニューアル」ではなく、ニューステージオープンとしました。リニューアルという言葉は、古くなったものを新しくするというイメージが強いのですが、ミッドタウンはまだ古くなったわけではないし、収益的に下がっているわけでもありません。いわば、よりミッドタウンらしくなるための店舗の入れ替えです。ですから10周年の節目に向けても、10年だから何かを変えるのではなく、ミッドタウンはミッドタウンらしくありたいですね。
〔では、ミッドタウンらしさ、ミッドタウンが掲げる街のコンセプトとはどんなものなのだろうか〕

東京ミッドタウンは「大人の街」をコンセプトにしている。
もともと、アベノミクスによる資産効果が出やすい店舗構成ではあったんです。つまり、少し高めの価格帯の商品というわけですが、資産効果の追い風に乗ることができました。それと、既存店舗の売り上げが意外に伸びているんです。新しく入っていただいた店への来店者数が増えるのは当然として、入れ替えなかった店舗にも買い回りしていただける店舗構成を考えましたので、いまのところその狙い通りに推移しています。
ミッドタウンでは、一貫して大人の街というイメージを作ってきました。そういう意味では、六本木ヒルズさんのほうが、より幅広い年齢層をイメージされているでしょう。我々は、もう少しイメージターゲットを絞っているのです。ただし、ターゲットといっても実年齢はあまり気にしていません。自分の生活にこだわりを持ち、少し上質なものを買い揃えたいという方にとってどんな店舗があったらいいか、そこにフォーカスしてきましたから。
一言で言えば、セレクトショップがあるように、ミッドタウンは「セレクトタウン」というイメージであり続けたいんです。たとえば、ベンツやBMWって、20年前のモデルと最新モデルを比べると全然違いますけど、フロントマスクを見ただけですぐにわかる、一貫したテイストがあるじゃないですか。
同じようにミッドタウンも将来、仮に商業施設の中身が全部変わったとしても、「いつ行ってもミッドタウンらしい店があるよね」と言われたいし、そういうブランドイメージを構築したいと思っています。また、ロケーション的にも東京の都心、あるいは港区のど真ん中という意味で、ブランド力が発揮できる場所なのですから。
〔三井不動産系の商業施設で代表的なのは、ショッピングセンターのららぽーとだが、ららぽーとでも過去、テナントの入れ替えは6年が1つの節目になっている〕
初めて入るテナント、特に飲食関連のテナントはかなり投資されますので、それを前提にすると2~3年での入れ替えは難しいですね。そうすると6年ぐらいでということになるのですが、6年経って次の更新時には皆さん、投資の償却もだいたい終えられてきますから。
もちろん、契約条件はお店によって変えていますので一概には言えませんが、次の6年で、また一気に入れ替えることはないようにしたいんです。外部からはあまりわからないうちに、ミッドタウンが常にミッドタウンらしく磨かれていくほうが相応しいし、また好ましいと思っていますから。
あと、昼ご飯を食べる場所が、以前はこのエリアにはそんなになかったんです。それでミッドタウンの中にカジュアルダイニングを入れたんですが、このエリア一帯にお勤めの方が1万5000人いますので、そのランチ需要は、ミッドタウンだけではとても吸収できません。
ですから当然、周辺のお店にも行かれます。そうなると、居酒屋だったところがランチも出すようになって、ミッドタウンの、いわば“ランチマネー”が周辺にどんどん落ちています。そうした状況を踏まえ、今回の商業テナントの入れ替えに際しては、カジュアルダイニングはやめてファッション関連分野のテナントに切り換えました。ミッドタウン周辺が変わることで、ミッドタウンの持つべき機能も、少しずつ変わってきていると思います。
〔テナント収入の額は非開示だが、ミッドタウンの大きな収益源は何といってもオフィステナントにあり、キーテナントは開業当初から入居している富士フイルムホールディングスやコナミ、さらにヤフー、ファーストリテイリング、シスコシステムズなどが本社を構えている〕
その5社で、テナント面積の8割ぐらいでしょうか。皆さんそれぞれミッドタウンを気に入ってくださっているので、ずっとここに本社を置いてほしいというのが我々の願いですね。テナント面積を増床されているところもありますので嬉しい悲鳴で、いまはほとんど満室状態です。
〔ミッドタウンにはホテルやレジデンス、商業施設やオフィスがあるという点で、三井不動産が得意な複合再開発における、ひとつの集大成といえる。同社は「不動産のデパート」といっていいほど守備範囲が広いわけだが、グループ各社とのシナジーはあるのだろうか〕
確かに(三井不動産は)多様な開発メニューを持っていて、それを一カ所に集めて大規模複合開発をし、あとは該当エリアをマネジメントすることによって、掛け算で相乗効果を出すのが強みです。ですので、当社でもいろいろな掛け合わせの仕掛けはどんどんやっていきたい。今年から(ミッドタウン内にある高級外資系ホテルの)リッツカールトンさんがカクテルアワードを開催したり、我々もこれまで、アートアワードやデザインアワードなど、デザインの街というブランドコンセプトのもと、いろいろな仕掛けをしてきました。
〔これまで日本はインバウンド、つまり海外からの旅行客という点で、アジアの中でも吸引力が弱く、台湾にも負けているのが実情だった。が、昨今の円安効果もあってようやく海外からの渡航者が増え、7年後の東京五輪もインバウンド強化へ追い風となる。
六本木エリア周辺では、住友不動産が手がける旧日本IBM本社や六本木プリンスホテル跡地の再開発(16年完成予定)も注目される。開発の核となるオフィス棟はミッドタウンと肩を並べる高さになり、六本木ヒルズやミッドタウンに次ぐ、3つ目のランドマークとなるからだ〕
五輪に関して言えば、国立競技場と湾岸エリアが2つの大きな拠点になると思いますが、六本木はそのちょうど中間地点なんですね。そうなると、都営大江戸線が結構、両エリアをつなぐキーになると思います。
湾岸エリアにもいろいろな施設ができるでしょうから、六本木もうかうかしていると、通過するだけのスルー・エリアになってしまいかねません。そこで、ショッピングやエンタテインメントだけではなく、美術館も豊富にあるスマートな街として六本木がさらに変貌していけば、いろいろな方に寄っていただける街になるのではと。
〔中村氏が、東京ミッドタウンマネジメント社長(三井不動産本体では東京ミッドタウン事業部長を兼務)に就いたのは12年4月のこと。それまで8年間は秘書部(07年から5年間秘書部長)勤務だった。その時仕えたのが、98年から13年間社長を務めた岩沙弘道氏(現在は会長)で、ミッドタウンはその岩沙氏が決断したビッグプロジェクトだ〕
岩沙の社長秘書を3年やりましたが、確かに、ミッドタウンはある意味「岩沙プロジェクト」でした。(ミッドタウンの敷地である)防衛庁跡地で入札したのが、驚天動地の出来事だった9・11(米国の同時多発テロ)の1週間後なんです。そもそも、98年に岩沙が社長に就いた時は金融ビッグバンもありましたし、何か前向きなことを手がけて、次世代につなぐ夢を追っていかないと、会社としても活性化しないという思いが強かったわけです。
〔結果、三井不動産が落札した価格は1800億円。2番札の企業よりも約500億円高かっただけに当時、高値掴みではとも言われ、同社の役員会では異論や反対もあった。が、最後は岩沙氏の熱い思いに圧倒されたようだ〕

「グループシナジーも最大限に」と中村氏。
落札した時は、岩沙から全社員に「心配することはない」とメールが来ましてね。何しろ、落札した瞬間に(三井不動産の)株価が下がりましたから。周囲から高値買いに見られ、マーケットでもそう受け止められたので、岩沙は怒っていました。ただ、当時は小泉政権下の規制緩和や民活がありましたので、我々の知恵でどんな街にして何を作るかを、フリーハンドでできたのは幸いでした。
それと本来、防衛庁跡地のような土地は三井、三菱、住友などが組んでオール日本的にやらないといけないような場所で、3社でスクラムを組めばリスクも分散できるという議論もあったようです。でも、岩沙は「いや、あくまで1社でやるべきだ」と。船頭を多くせず、どこかが責任をもって街作りをするべきだという考えからです。ミッドタウンのプロジェクトを推進できたのはまずトップの強い意志、次いで民活という、当時の環境が大きかったと思いますね。
それからもう1つ、防衛庁跡地は都心に残された最後の、いわば千載一遇の開発チャンスだったんです。三井不動産では汐留エリアも開発してきましたが、結果的にこのエリアは「切り売り」です。汐留も広大な敷地ですが、大手の地主企業さんが一緒に街作りをしようという感じではありませんでしたから。
それもあって、自分たちだけで街を作れる防衛庁跡地というのは、ディベロッパーとしてこれ以上ないチャンスという思いが強かったのです。開発に関わる許認可手続きも、民活の中で官も一緒になってやっていただいた。なので、計画と実際にプロジェクトが完成するまでのタイムラグも、そんなにありませんでした。
〔前述の土地取得額もさることながら、ミッドタウンの総工費は3700億円というビッグプロジェクトだけに、初期の減価償却も当然、大きかった。営業損益ではこれまでも黒字を出していたのだが、機関投資家に配当を出していくには累損をゼロにしないといけない。その配当も、12年度からようやく始まった〕
ミッドタウンがオープンして、1年半が経過した時期にリーマン・ショックがありましたからね。そして11年は東日本大震災。特にリーマン・ショックでは、(株式の大暴落などで)逆資産効果が働きました。
先ほど言いましたように、ミッドタウンは商業施設も住宅もオフィスもちょっと上質な、というコンセプトですから、従来の六本木のマーケットを超えるような家賃設定をしていました。それだけに、当時は厳しかったと思います。
〔六本木ヒルズでは、近隣エリアで「第2六本木ヒルズ」ともいうべき開発構想があるが、ミッドタウンでは今後、周辺に拡張余地はあるのだろうか〕
当社にも、周辺エリアでのマンションの再開発とか、いろいろな情報は入ってきますが、いわば網をかけるような形で大きな再開発をするというのは、ちょっと難しいかもしれません。
(構成=本誌編集委員・河野圭祐)

2013年、ヤマハ発動機の電動アシスト自転車「PAS」が発売20周年を迎えた。「世界新商品」として1993年に誕生、その発売以来、同社の累計総出荷台数は225万台(12年末時点)を超え、年間10万台以上を販売するヒット商品となっている。

商品には絶対の自信を持つ森本氏。
「PAS」の名前の由来は、Power Assist Systemの頭文字を取ったもの。文字通り、電動モーターの助けで、急な坂道や重い荷物を載せた状態でもスイスイとペダルを漕ぐことができる。シニア世代だけでなく、自転車の前後に小さな子供を乗せたママさんユーザーも急増していることから、いまや街で見かけない日はないほど。電動アシスト自転車は生活の足として定着しつつあると言っていい。
そのヤマハが、PASシリーズで初めてBtoB向けに専用設計モデルを発売した。11月1日に発表された「PAS GEAR CARGO(パス ギア カーゴ)」がそれで、三輪の電動アシスト自転車と脱着可能なリヤカーを組み合わせた配送業務専用モデルとなっている。リヤキャリア20キログラム、専用リヤカー100キログラム、フロントバスケット3キログラムで、合計123キログラムの荷物の積載が可能。宅配便をはじめとした配送業務に特化したつくりになっている。
これまでもビジネスモデルのPASは発売されていたが、営業業務の訪問・巡回用車という位置づけで、ここまで用途を限定した法人向けモデルはなかった。ヤマト運輸での採用がすでに決まっており、ヤマハの積極的な仕掛けが感じ取れる商品だと言えるだろう。
しかし、ヤマハは、本来は世界第二位のモーターサイクルメーカー。20年前に世界で初めて誕生した電動アシスト自転車は、どのような発想から生まれたのだろうか。
「自転車への着眼は、実はかなり古くからヤマハのなかにありました。低炭素化社会で地球にやさしく、大量の人数で移動するのではなく、個人が移動するために使うパーソナル・コミューター。その究極の乗り物は自転車でした。自転車の弱点はというと、急な坂道や向かい風です。ここに人力を補助する動力があればどうだろう。どんな商品が提供できるのか、といった着想は70~80年代から始まっていました。当時は小さなガソリンエンジンを搭載したものから始まり、さまざまな形の技術開発に取り組んだのです」
こう語るのはヤマハ発動機事業開発本部SPV事業部事業部長の森本実氏。国際A級ライセンスを持ち、鈴鹿8時間耐久レースにも参戦したライダーでもある。後述するが、PASの開発にはモーターサイクルの経験者が大きな役割を果たしているのだという。
話を戻すと、ヤマハは73年に25cc小型ガソリンエンジンを積んだ自転車を、82年には35ccの小型エンジン付マウンテンバイクを試作していた。それらが商品化に至らなかったのは、エンジン付は技術的な問題もあり、ヘルメットも運転免許も不要な、手軽な乗り物でなければならなかったからだ。つまり自走してはいけない。あくまで人力の補助を求めていた。
「80年代後半には電動モーターでアシストするという新しい発想で研究がはじまりました。背景にはバッテリーやコンピュータの小型高性能化など、急激な技術革新があったからです。
しかし、製品化に至るまでは、商品とは別に大きな問題もありました。日本には20年前、電動アシスト自転車に関するレギュレーションがなかったのです。
道路運送車両法と道路交通法の兼ね合いで、当時の運輸省や警察庁に対して、さまざまな働きかけを行いました。電動アシスト自転車はあくまで自転車の延長戦上にあり、省エネや排出ガスの削減にも繋がる公益性の高い乗り物であることを訴えたのです」
社会性が認められ、自転車として認可が下りたのが93年。その年にPASは発表され、11月1日に神奈川、静岡、兵庫で地域限定発売、翌94年4月1日に全国発売されている。96年にはパナソニックも電動アシスト自転車の販売を開始し、市場が広がりを見せるようになっていった。
「当初は特許をがんじがらめにして、ヤマハ単独で事業をスタートすることもできたはずなんですが、私たちの諸先輩は、それをしませんでした。他社が参入してくることで、業界が大きくなる。一社では力が足りないことはわかっている。みんなで業界をつくろう、強くしようと始めた事業です。結果として20年間で国内に40万台の市場ができた。我々はパイオニアとして、さらに一歩、新しい技術、提案をしていこうと考えています」
現在の市場シェアを見ると、三洋電機を取り込んだパナソニックが約50%を占め、それをヤマハが約30%で追う展開。国内3番目のメーカーはブリヂストンだが、ヤマハとブリヂストンは車体と電動アシストユニットを相互供給する関係にあり、実質的にはパナソニックvsヤマハ・ブリヂストン連合軍の争いになっている。国内市場は3社で約9割を占める。ちなみに、国内で販売された自転車の約15%が電動アシスト自転車になっているという。
普及の追い風になったのが販売価格の低下と電池性能の向上が挙げられる。93年当時に発売されたPASは価格が14万9000円と原付バイク並みの価格だったが、現在では最廉価モデルは8万9800円まで低下。販売店によってはさらに安い価格で販売されている。

「PAS GEAR CARGO」は、ヤマト運輸が機能検証の協力をしている。
走行距離も93年の20キロメートルだったものが、現在は50キロメートルを超えるものも珍しくなく、モデルや用途によっては70キロメートルを上回るものまで登場している。低価格化と高性能化を後押ししたのは、電池の分野での技術革新が大きい。
「どんなにいいエンジンをつくっても、ガソリンがなければ動かないのと同じで、電動アシスト自転車もバッテリーがカギになります。この20年間で鉛バッテリーから始まり、ニカド、ニッケル水素、リチウムイオンと進化を続けています。バッテリーに関しては、まだまだ技術開発が進む過程段階だと思っています。それぞれの時代によって、一貫しているのは軽量・コンパクト・高性能というキーワードです。いかにバッテリーを小さく、長く使い続けられるか。さらにバッテリーは、危険もはらんでいる。ですからヤマハ発は、安全性に関することすべてにアンテナを立てて、その時代にベストと思われるマテリアルを使って取り組んできたのが、この20年です」
バッテリー以外にも、モーターサイクルで培ったヤマハの技術が自転車に注がれるようになってきている。一つが前述の「PAS GEAR CARGO」に採用されたスイング機構。二輪車の場合、カーブを曲がるのはハンドルを切るのではなく、リーン(傾けること)を行う。リーンは体重と遠心力のバランスにより安定性を増すことができるが、自転車をリヤカーに固定しただけだと、自転車本体を傾けることができないためにリーンによるバランスが取れなくなってしまう。スイング機構をつけることにより、リーンが可能となり、重い荷物を載せていても、カーブを曲がる際の安定感が増す。
「PASはモーターサイクルの経験者が、走る・曲がる・止まるをチェックしていますので、運転のしやすさ、快適さには、かなりこだわりがあります。私も今回の商品を試乗した際に、リーン感覚が嬉しくて、『わぁ!』と声を出してしまいました。電動アシスト自転車にも運転するワクワク感というのをお客様に伝えたいですね」
PASが20周年を迎えるに伴い、2013年モデルからヤマハは様々な新技術を採用してきている。見た目にもわかりやすいのが、バッテリー残量表示。初期モデルではパイロットランプの点滅の仕方で充電状態を知らせていたが、11年モデルからバッテリー残量がパーセント表示でわかるようになり、13年モデルに至っては、走行モードによってあと何キロメートル走れるかの目安をデジタルで表示する機能までついた。
電動アシスト自転車の心臓部にあたるドライブユニットにも新技術が投入された。従来にはなかった「クランク回転センサー」を搭載し、センサーが3つとなるトリプルセンサーシステムを開発。これはヤマハだけの技術となっている。
「日本のレギュレーションでは、自走することは許されませんから、人間が『前に進むぞ』という気持ちがなければ前に進んではいけないんです。従来はペダルの踏む力を感知するトルクセンサーと、走行中の車速を感知するスピードセンサーで、アシストをするかしないかを判断していました。
しかしながら、ペダルを漕ぐというのは、いわゆる2気筒なんですが、上死点と下死点があって、本人が前に進みたくても力が抜けてしまう死点が存在しています。他社さんもダブルセンサーは投入していますが、我々は一歩上に行かなくてはいけませんから、より自然な乗り心地を実現するために、死点をなくすことを考えたわけです。
漕いでいる時というのは、クランクシャフトは回っているわけですから、回転センサーをつけて察知することで、本人が前に行きたいという意思が伝わる。上死点と下死点でアシストが途切れることがなくなり、より安定してアシストを受けることができます。乗り比べれば違いがはっきりとわかりますよ」
電動アシスト自転車は、国内は40万台の市場だが、欧州では100万台に達する市場になっている。半面、アメリカやオーストラリア、アジアの国々は、電動アシストのレギュレーションがなく、本格普及には至っていない。
「レギュレーションや認定技術があって、商品として成り立っているのは日本と欧州だけです。90年代にヤマハも欧州にチャレンジしたんですが、当時は『健康のために自転車に乗るのだからアシストはいらない』と相手にされませんでした。我々が撤収したあとに、欧州メーカーが我々の商品を研究し、市場を席巻してしまいました。ドイツの電動工具メーカーのボッシュが電動アシストシステムではかなりシェアを獲っています。
欧州では各自転車メーカーごとに電動アシスト自転車が発売されていて、モーターなどのシステムだけを買って自社製品に載せています。現在ヤマハでは、世界一の自転車メーカーである台湾のジャイアントと提携し、ドライブユニットを供給している。今後も採用メーカーが増えるように交渉を展開しているところです」
日本国内においても、まだまだ普及させる余地は大きいという。市場を牽引したシニア層、子育て層に加え、10代の学生をターゲットにしたモデルも投入された。ビジネス需要も含め、さらに市場が拡大する見込みだ。
「日本で試乗会を開いても、7~8割のお客様は『初めて乗りました』という。購入していただいたお客様にアンケートを取ると、7~8割は『初めて買いました』という。まだまだ電動アシスト自転車に乗ったことがない人が多いということです。私たちは乗り物メーカーですから、排出ガスが出るものも作ってきましたが、次世代のためにきれいな地球を引き継ぎたいという信念のもと、低炭素化社会に貢献しようというビジョンがあります。その意味では、電動アシスト自転車の普及は貢献に繋がる。日本、欧州以外の地域でもレギュレーションが整えば、世界中どこでも飛んでいく準備はできています。
世界中の人々にヤマハの電動アシスト自転車を知って乗ってもらいたい。生活を豊かにしてもらいたい。笑顔を創造したいというのがテーマですね」
(本誌・児玉智浩)


ネオモデルタレントスクール社長
長縄将太
ながなわ・しょうた 1977年生まれ。制作会社やレストラン経営などを経て7年前からネオモデルタレントスクール社長。ギャラクシーオーシャン取締役を兼務する。
ネオモデルタレントスクール取締役
長縄未歩
ながなわ・みほ 1972年生まれ。父の仕事の手伝いを経て、カメラマンとして独立。現在はネオモデルタレントスクール取締役、ギャラクシーオーシャンの社長を務めている。
―― おふたりは、姉弟でネオモデルタレントスクールを運営されていて、弟の長縄将太さんが社長、姉の未歩さんが取締役を務めています。どういう経緯で姉弟経営を行うことになったのですか。
未歩 会社の名前こそ違いますが、もともと私たちの父が、モデル事務所と養成所を経営していました。父としては、私たちに後を継いでもらいたいという気持ちはあったようですが、私自身は父とは違う道を進みたくて、プロフィール写真のカメラマンとして独立。ところが、7年前、父が突然亡くなってしまった。
将太 私は曲折あって、父が亡くなる1年前から会社を手伝っていましたが、後を継ぐ気持ちはそれほど強くなかった。
未歩 生徒さんたちのこともあるため、簡単に会社を閉めてしまうわけにはいけません。それで姉弟力を合わせて運営していくことになったのです。
―― それではさぞかし苦労したのではないですか。
未歩 最初は大変でした。営業の仕方から何からまるでわかりませんでしたから。周りの方々に助けられてここまできたようなものです。
でも父のやり方をそのまま踏襲したわけではありません。父の時代は、たくさん生徒さんを集めて、少人数の講師で教えるという、ある意味で利益追求型の部分もありました。でも私たちは、そうではなく、通った生徒さんたちが、満足してくれるレッスン内容にしようと考えました。そこで、講師方は全員、現役の俳優やモデル、スタイリスト、映画監督にお願いしています。テレビで活躍されている坂上忍さんも講師です。OBの講師でも優れた方はたくさんいらっしゃいますが、いまの現場に即していないこともあります。ここでレッスンを受けた生徒さんたちには、全員、現場に出てほしいですから、その時に役立つことを教えるようにしています。
―― 具体的にどのようなカリキュラムになっているのですか。
将太 3カ月でひと通りのことを教えるのがベースとしてあって、ここではポージングやウォーキング、発声、演技指導から、業界のルールやマナー、オーディション戦略などが必修科目です。さらに、モデル、タレント、俳優・女優、声優といった志望ごとの選択レッスンがあります。また3カ月のレッスン後も、希望者には引き続きレッスンを行っていきます。
―― 生徒数はどのくらいですか。
将太 だいたい、3カ月のカリキュラムを常時50~60人が受講しています。
―― ところで、このようなタレント養成スクールというのは都内にどのくらいあるものなんでしょう。
将太 100社はありますね。それ以外にもプロダクションがスクールを併設しているところもあります。芸能プロダクションとなると、都内に1000以上と言われています。
―― それだけ競争が激しい中で、生徒を確保するのは大変ですね。
未歩 ですから私たちは大手のプロダクションと提携して、そこに所属するタレントさんたちにレッスンするというケースが多いです。フジテレビの『めざまし土曜日』のレポーター役で人気の鈴木ちなみちゃんも、売れる前にはここでポージングなどのレッスンを受けていました。
でも最近では、独力での募集にも力を入れ始めていますし、徐々に実績も上がっています。
―― どういう人がレッスンにくるんですか。やはり子役希望の子供たちですか。
将太 ここでは子役志望の生徒さんは受け入れていません。10代以上の方に限っています。年齢層や目的などはさまざまですが、最近多いのは30歳以上の主婦の方たちですね。もともと芸能界に興味はあったけれど、一度はあきらめた。でも子供から手が離れたので、自分の夢を叶えたい。お母さん役でテレビに出たい、チラシモデルや和服モデルになりたいという生徒さんたちが増えています。
―― 経営的には順調ですか。
未歩 養成所は、父から引き継いで2年目には黒字が出るようになりました。ところが同時にギャラクシーオーシャン(こちらは未歩氏が社長、将太氏が取締役)というプロダクションも引き継いだのですが、こちらは赤字続き。ネオの利益でギャラクシーの赤字を補填していました。利益がでるようになったのはここ2年ぐらいのものです。
将太 とにかく最初の1年間は、仕事を依頼するFAXが一度も受信しなかったですからね。当時は何も知らなくて、テレビ局などに行って挨拶すれば、資料を置いてくれば、それで仕事がくるものだと思っていました。でも現実はそんなものではありません。毎日のようにテレビ局などに通ってもまだ足りない。資料の作り方にも工夫が必要だし私の営業トークも足りないところがいっぱいありました。
未歩 オーディションの連絡くらい絶対くるはずだと思っていたのに、それさえこない。それだけ考え方が甘かったんです。24時間365日体制で営業しなければならないのに、そこまでやる覚悟がありませんでした。
将太 結局最初に来たのはエキストラの仕事でした。
―― やめようと思うことはなかったですか。
将太 やっぱりありました。でも姉がいたので、話し合って、続けていこうとここまできました。
―― ふたりの役割分担はどうなっているのでしょう。
将太 姉が戦略を考え、私が営業と、レッスンも一部担当しています。
未歩 実は私も、カメラマンとして独立する前は、父の仕事を手伝っていました。その時はけっこう、経営について厳しく言われていました。それがあったから、父と一緒に仕事をするのをやめたということもあるのですが、その経験と、自分でも会社を経営したことがいまでは役にたっています。
―― 喧嘩はよくします?
未歩 しょっちゅう(笑)。といっても弟は私に頭は上がりませんが。喧嘩になるのは意思疎通がはかれない時ですね。ふたりとも、向いている方向は同じです。でも、やはりそれでも方法論などでぶつかる時があります。ですからできるだけ、弟とは話をするようにしています。
―― 今後の夢はなんですか。
未歩 夢を持った生徒さんたちをたくさん集めたいと思います。そしてこのスクールに入った人たちには、全員、テレビなどに出演させたい。現実的にはとてもむずかしいと思います。でもそれが私たちの使命だと考えています。

生徒の夢はテレビなどへの出演。その夢を叶えるためのレッスンが続く。
生徒さんたちがなぜここに通ってくるかというと、芸能界の仕事をしたいからです。その期待に応えたい。その仕事というのは、小さな仕事でもかまわない。とにかく関わっていたいというのが生徒さんたちの希望です。
そこを昔は少し勘違いしていたことがあって、生徒さんたちは主役級の仕事が欲しいに違いないし、その期待に応えることが自分たちの仕事だと考えていました。
ですので、ギャラクシーでも最初の頃は、エキストラの仕事などは断っていたことがあります。ギャラも安く、営業費用さえ出ないケースもありますから。でもそれはとんでもないことで、生徒さんたちにしてみれば、なんでもいいから仕事をしたい。一方、仕事の発注側にしてみれば、せっかく仕事を回してやったのに、という気持ちになります。何より、私たちのような新参者がこの世界で生きていくには、相手がいちばん困っていることからやってあげる必要があるのに、それを忘れていました。
―― 大きく方向転換をしたわけですね。
未歩 3~4年前にすべての仕事を断らないことに決めました。最近では、以前なら大手経由でしかこなかったオーデションなどの誘いが直接入ってくるケースも増えています。
―― 出演実績が増えれば、生徒募集にもはずみがつきますしね。さらにその先の夢はありますか。
未歩 出演機会を増やすという目的も兼ねて、映画製作に携わりたいと考えています。これまでにも舞台公演などは何度か手がけたことがあります。その時は生徒さんに全員出演してもらいましたが、それを映画でやりたいですね。
ただし映画となると、資金調達にしても小屋にかけるにしても舞台よりハードルははるかに高いです。でも5年から10年の間には実現したいと考えています。
将太 僕は昔から映画やドラマが好きで、その制作をしたいとずっと思っていましたし、社会に出てからはそういう仕事に就き、自分でも一時制作会社を立ち上げたこともあります。芸能界の仕事をしたいというよりは、制作がしたいというのが僕の夢でした。
―― だったらその夢が叶うかもしれませんね。
将太 ところが、スクールを運営しているうちに、制作したいという夢よりも、このスクールから、そしてギャラクシーから売れっ子を出したいという思いのほうが強くなってきました。1人でもそういうタレントが育つと、環境は大きく変わるのではないかと思います。
未歩 私はいまでは、生徒さんや所属している人たちの出演が増えることを考えて動いています。そこで最近、WizBizさんと組んで、モデルの派遣ビジネスを始めたばかりです。
―― モデルの派遣は昔からありますが、それとは違うのですか。
未歩 料金体系がまったく違います。
パンフレットやチラシやホームページを作成する時に、モデルを使いたいと考えている会社は多いと思います。ところがモデルを使うと高くつく、と多くの方がそう思っています。
でもこのプランの場合、モデル1人を派遣するだけなら3万円で引き受けています。また、カメラやヘアメークをつけても9万8000円から可能です。
この値段なら、ほとんど負担なくモデルを使うことができますし、私の知り合いの会社でモデルを使ったパンフレットを作ったら、売り上げが大きく伸びたという実績もあります。そして利用する会社が増えれば増えるほど、私たちの生徒さんたちの活躍する場も増えることになります。
これまで、モデル利用は高過ぎると思い込み、二の足を踏んでいた方は、このプランをぜひ検討していただきたいですね。