




5年前、米国に端を発したリーマン・ショックは、日本の電機業界を直撃した。ほとんどの企業が赤字に転落。前3月期の決算も芳しいものではなかった。しかしこの試練に直面して、企業は否応なく自己改革を断行せざるを得なくなった。その結果、業界地図は5年前とはまったく違う姿となった。横並びは影を潜め、得意分野を最大限に追求する姿勢へと変化したのだ。反撃の準備は整った。
今年も10月1日から5日間、千葉市の幕張メッセで日本最大のエレクトロニクス見本市、CEATEC(シーテック)が開かれ、多くの電機メーカーや部品メーカーが、最先端の技術や製品を展示、会場は多くのエレクトロニクス関係者でにぎわった。
開幕当日には、多くの主要メーカー首脳も顔を見せたが、昨年までと比べると、なんとなく明るい表情をしているのが印象的だった。それは、日本の電機業界が置かれた状態と無縁ではない。
5年前の2008年10月に起きたリーマン・ショックは、世界の産業構造を激変させたが、日の丸電機メーカーに与えた影響も深刻だった。それを証明するのが、次の数字である。
08年度 ▲2兆1312億円
09年度 ▲943億円
10年度 3775億円
11年度 ▲1兆1394億円
12年度 ▲9757億円
5年間分すべて合算すると、3兆9641億円のマイナスとなる。
この数字は、本特集でも個別に取り上げている電機メーカー大手8社の、年度別最終損益の合計(黒字額から赤字額のを引いたもの)である。黒字になったのは10年度だけ。全メーカー合わせると、5年間で4兆円もの赤字を出したことになる。
日本の電機メーカーはこのまま没落してしまうのではないか。大手メーカーの中にも経営破綻するところが出るのではないか。昨年の今頃は、そうした論調の報道ばかりだった。
終戦から50年間、日本の電機メーカーは世界を牽引してきた。メイド・イン・ジャパンの家電製品は世界中で消費者の心を捉えていき、その結果としてアメリカではテレビメーカーが“絶滅”した。家電の日本一極集中状態がしばらく続いた。
1990年代半ばともなると、バブル経済の崩壊、円高の進行、そして韓国や台湾など新興国の台頭によって、徐々にその地位は低下していくが、それでも世界の中心は日本だった。
ブラウン管テレビに代わる薄型テレビの量産化にいち早く取り組んだのも日本メーカーだったし、DVDやそれに続くブルーレイといった記録メディアの規格も、日本メーカー主導でつくられていった。技術力にしても製造能力にしても、90年代までは日本優位が続いていた。
しかし90年代末から2000年代に入る頃になると、次第にほころびが目立つようになる。
かつては超優良企業と言われ、「石橋を叩いても渡らない」というほど堅実経営で知られた日立製作所が1999年3月期に創業以来初の赤字を計上したのはその象徴だった。
2001年度には松下電器産業(現パナソニック)が赤字となり、さらにはITバブル破裂の影響もあり、ソニー・ショックと呼ばれる株価暴落も起きる。世界の電機業界をリードしてきたビッグカンパニーの足元が、徐々におかしくなってきた。
日本企業がここまで追い込まれたのはAV機器におけるデジタル化の進展で、極端にいうと、電機メーカーはただのアッセンブルメーカーになってしまったためだ。デジタル部品を組み立てさえすれば、それなりの品質のデジタル家電ができてしまう。日本企業は新興国のメーカーに歯が立たなくなった。
それでもこれまでは生産拠点を海外に移転したり、AV以外の分野で補ったりしながら持ちこたえていた。苦しいながらも、市場全体は新興国の生活レベルの向上もあって確実に大きくなっている。ここを乗り切り、さらに生産性を上げることができれば、再び覇権を手にすることができるかもしれない。その思いで必死に耐えていた。
この一縷の望みを、完全に断ち切ったのが、リーマン・ショックだった。
リーマン・ショックによって、世界経済は一気にしぼんだ。同時にデジタル機器の価格は暴落、電子部品の市況も悪化した。それまで市場の膨張を前提にに生産計画を立て、設備投資を行ってきた企業は、一気にピンチに立たされた。
その結果が、冒頭に記した最終損益の合計である。
中でも悲惨だったのがテレビメーカーで、パナソニック、ソニー、シャープ3社はいずれも巨額な赤字に転落、シャープにいたっては企業の存続さえ危ぶまれる事態となった。
かつてテレビは茶の間の中心にあった。時代は変わり、いまでは1室に1台が当たり前となったが、それでもテレビが家電の王様であることには違いない。だからこそ、多くのメーカーがテレビ事業を維持し続けたし、キヤノンのような“部外者”さえも、参入を目指したのだ。
しかしもはやテレビ事業は、そんな安易な気持ちで維持できるようなものではなくなった。各社とも、テレビ事業の大幅な見直しに着手せざるを得なくなった。日立はいち早く国内生産から撤退したし、東芝も最近海外生産への移行が明らかになった。
ほんの10年前までは、10社に迫る日本メーカーが国内でテレビを生産していたが、いまでは半減。しかもパナソニックやソニーでさえも、赤字が続く場合の撤退の可能性を否定しない。「テレビをつくってこそ電機メーカーは一人前」との常識は、まったく通用しない時代となった。価値観がまるで違ってしまった。
問題は、これをどう捉えるかだ。「電機業界の動向をずっと見ていると、リーマン・ショック直後はどう対応していいかわからず、リストラなど後ろ向きのことをやって、どうにかしてコストを抑えようとしていたものが、しばらくすると、これを企業が生まれ変わるためのひとつのきっかけにしようという動きが始まった」(IT業界ウォッチャー)
日本企業を批判する時によくつかわれる言葉が「横並び主義」だ。競合相手がつくっているから自分たちもつくる。テレビなどその代表例だった。しかしこの数年の電機業界の状況は、それを許さないほど厳しいものだった。だとしたら、いま一度自分たちの強みを確認し、それを最大限に活かしていく。同時に、不必要な事業は大胆に切り捨て、経営資源を強い事業に振り分けるしかない。否が応でも、そう考えざるを得なくなった。いわゆる「集中と選択」の徹底である。
電機メーカーの多くは、米ゼネラル・エレクトロニック(GE)にならって、1990年代から「集中と選択」を口にしていた。しかし現時点から振り返れば、それは極めて甘いものでしかなかった。事業構造を根本から覆すような変革は行ってこなかった。ところがここにきて、過去にない企業構造の変化が起き始めた。いちばんわかりやすいのがパナソニックだろう。
言うまでもなく、パナソニックは家電業界の覇者である。旧松下電工と旧三洋電機を本体に吸収したことにより、電化製品のみならず、配線や太陽電池にいたるまで、家の中の電気に関係するものは、ほとんどすべてを取り扱う会社となった。
ところがそのパナソニックが、「家電依存を改め、B2Bビジネスで成長していく」(津賀一宏社長)というのである。いままで消費者に向いていた企業が、企業を対象にしたビジネスに比重を置こうとしている。ある意味180度の方針転換だ。

これから開発競争が激化するウェアラブル情報機器。日本企業の得意とするところだ。
パナソニックは5年後に創業100周年を迎える。その直前の大きな決断だった。悪く言えば、それだけ追い込まれているということであり、よく言えば、新しい可能性を見出したということだ。とにかく生き残り、さらなる成長を遂げるためにはなりふり構っていられないという必死さが見てとれる。
同じように、事業構造を大きく変えて、すでに成果を出しているのが日立である。
パナソニックが家電の覇者なら、日立は電機の覇者である。売り上げがいちばん大きいというだけでなく、重電、コンピュータ、通信、AV機器、白物家電と、およそすべてのジャンルの商品を手がけてきた。しかも昔から「自前主義」を貫いていたため、膨大な商品ラインナップをすべて自分たちでつくってきた会社だった。
ところがリーマン・ショックとほぼ同時期に、日立は自分たちの本業を定義し直し、それに基づき事業を選別していった。
すると、「イギリスで鉄道事業を受注」等々、大型案件を次々とモノにしていくようになる。本業に経営資源を絞り、全社挙げての取り組みが、功を奏したのだ。その結果、日立はリーマン・ショックの2年後にはV字回復を果たした。
残念ながら前3月期決算までは、依然として大赤字を垂れ流している企業もいくつかあった。しかしそうした企業であっても、体質は確実に改善されており、今期第1四半期決算では、いずれも黒字を計上している。間もなく発表される中間決算でも、好決算が相次ぐはずで、少なくとも最悪期は脱したといえる。重要なのは、これからどうやって成長路線に乗せていくか、である。
少なくとも外部環境は、日本の電機メーカーにとって悪くない。これは別に為替が円安に進んだとか、アベノミクス効果のことを言っているわけではない。いま世界が進もうとしている方向が、日本企業が得意とする分野と一致しているという意味である。
たとえば最近、話題になっているウェアラブル情報機器。これはポストスマホとも言うべきもので、メガネや時計のようにして身につけるものだ。この分野に関してはグーグルやサムスンが先行しているように見えるが、ソニーもすでに時計型スマホを出すなど、「かなり前から議論している」(平井一夫社長)

CEATECで話題になった日産の自動操縦車。このクルマの中には電機メーカーの技術とノウハウが満載だ。
このような、技術を組み合わせ凝縮した商品というのは、日本企業がもっとも得意とするところだ。しかもこうした製品は素材の力を最大限活用しなければならず、日本にはすぐれた素材が揃っている。それらをきちんと組み合わせ、コーディネートする能力さえあれば、日本ほど、ウェアラブル製品をつくりやすい環境をもった国はほかにない。
あるいは冒頭に紹介したCEATECでも話題になっていた自動操縦車。ドライバーが何もしなくても、クルマが目的地にまで運んでくれるという優れものだ。
CEATECに出展していたのは、電機メーカーではなく、自動車メーカーの日産だが、クルマ自体は走る電気機器だ。その内部のほとんどを、電機メーカーに依存している。
また実際に自動操縦車が道路を走るには、街全体のインフラとして、自動操縦を可能にする情報システムを構築する必要がある。これなど、社会インフラや情報通信分野を手がける日の丸電機メーカーのもっとも得意とするところだ。
社会のIT化は、間違いなく、今以上に進んでいく。地球環境やエネルギー資源のことを考えれば、スマートハウス、スマートシティもどんどん増えてくる。これは誰にでも容易に想像がつく世界である。最初は先進国から始まって、やがては新興国にも及んでいく。ビジネスチャンスは無限といっていい。
つまり、電機メーカーの果たす社会的役割は、今後ますます重要になってくる。しかもハード単体ではなく、社会インフラを組み合わせた世界である。これこそ、日本企業の独壇場になってもおかしくない。
リーマン・ショックによって、電機メーカーの多くが危急存亡に陥った。しかしこれを奇貨として、他社にはない独自の強みを認識することができたのだ。そしてそれが活用できる社会がすぐそこに迫っている。日の丸電機が復権する条件は揃った。
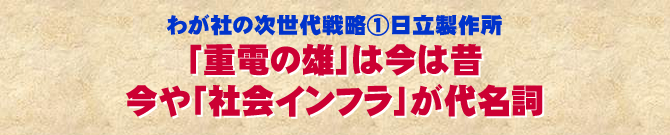
日立製作所はこの夏、東京・京橋に新しいショールーム「日立コラボレーションスクエア京橋」をオープンした。この施設は、「エネルギー」「交通」「水環境」を中心とした日立の社会インフラ事業への取り組みや技術を紹介するものだ。
ショールームの中には、日立の社会インフラ事業の軌跡を紹介するコーナーがあるほか、大型スクリーンを活用して、社会インフラ事業をインタラクティブに紹介するコーナーがあるなど、ここに来れば、日立の社会インフラの概要がわかるようになっている。
このショールームを開設したことからもわかるように、日立にとって社会インフラ事業は、屋台骨そのものといっていいほど重要な事業となっている。
テレビなどを見ると、いまでも日立は人気アイドルグループの嵐を起用した白物家電のコマーシャルが放映されている。しかし日立の白物家電の販売額は2500億円程度。日立全売上高9兆円に占める比率は3%にも満たない。ここに薄型テレビなどの民生品を加えても、5000億円には届かない。つまり日立の膨大な製品のうち、直接、消費者に届くのは5%程度しかないということになる。
それに対して、発電、鉄道、ITシステムなど、広義の社会インフラ事業は5割を優に超す。この特集の中でも取り上げているが、日立以外の電機メーカーも、最近では社会インフラへの注力を口にする。しかし、この路線を真っ先に表明したのは日立であり、その分だけ、他社を大きくリードしている。
日立が新聞などで大きく報じられるのも、ほとんど社会インフラ関連ばかりである。
たとえば今年4月に『GE日立連合、米で原発採用内定 三菱重を逆転』という見出しが日経新聞を飾った。米バージニア州の原子力発電所に新設する原子炉として、米GEと日立の合弁会社の沸騰水型軽水炉の採用が決まった。これは、内定していた三菱重工の加圧水型軽水炉を逆転したものという記事だ。
あるいは、2011年には日立と三菱が企業統合を行うという記事が日経新聞1面を飾った。これは企業規模で劣る三菱側の反発が強く、実現しなかったが、今年4月には両社の火力発電所のインフラ事業を統合するというパーシャル連合へと結びついた。
以上2つとも社会インフラに関する動きである。
日立といえば、昔から発電所などで高いシェアを維持してきた会社である。また電電ファミリーとして、日本の通信業界のインフラを支えてきた企業でもある。その意味で、日立が社会インフラを事業の主軸とするのは、保守本流にすぎないと見ることもできる。
しかし、わずか10年前の日立は、自分たちの本流が何なのかわからず右往左往するばかりだった。バブル崩壊後は業績も長期低落し、1999年3月期には、創業以来初の赤字という屈辱を味わう。
「日立の落日」といったタイトルの記事が散見されたほか、「大砲巨艦主義の失敗」「巨体すぎて絶滅した恐竜」等、日立を形容する言葉はかんばしくないものばかりだった。
2000年の頃の日立は、絶滅を避けるために自ら変わろうと必死にもがいていた。このままではダメになる、というのは日立の全社員が共有する思いだった。ところが、もがけばもがくほど、身動きがとれなくなるというのもよくある話で、日立の業績は一向に改善しなかった。
つまりは変わろうとしている方向が間違っていたのだ。
当時の日立が志向していたのは、「重電の雄」からの脱却だった。重電という言葉は、日立の重くて動けない体質を象徴しているかのようだった。そこで日立は、IT分野に大きく舵を切った。社長も非重電分野の人材が続く一方で、IBMからHDD事業を買収するなど、重電の日立ではなくITの日立になろうと考えたのだ。
しかし、これは日立最大の強みをないがしろにするものだった。結果として、この改革は失敗。日立は2009年3月期に最終赤字7873億円という日本製造業史上最悪の赤字を計上することになった。しかも、赤字の原因となっていたのはIT分野。この分野は価格下落のスピードが速く、少し油断すると巨額の赤字を計上してしまう。日立もその陥穽に墜ちていた。
そこで再び日立は大きく舵を切る。就任からわずか3年しかたっていないコンピュータ部門出身社長を更迭。すでに社外に去っていた重電出身者を呼び戻し社長に据えたのだ。
こうして09年に就任した川村隆社長のもと、日立は自らを社会インフラの会社と位置づけ、本流に回帰していく。ただし、過去の重電偏重時代は「工場プロフィットセンター制」と言われる、工場単位で利益を生み出す体制にあったが、社会インフラの場合、各事業部の強みを持ち寄り、そこにITを絡めることで、システムソリューションを提供することを目指した。強みを最大限に活かしつつ、そこに新しい付加価値をつけていった。
リリーフ登板だった川村氏は、わずか1年で社長の座を中西宏明氏に譲るが、中西氏はさらにその路線を進めていった。その結果日立は、8000億円弱の赤字を出した2年後の11年3月期、2388億円の最終利益を出してV字回復を遂げる。当時の電機業界は、まだリーマン・ショックの悪夢から抜け出せておらず、大半の企業が赤字を計上していた。その中で日立だけがいち早く、立ち直ったのだ。

いち早くリーマン・ショック禍から立ち直った日立の中西宏明社長。
日立の場合、幸いだったのは、リーマン・ショックが起こる前から問題が表面化したことで、翌年の大赤字をきっかけにすばやく舵を切ることができたことだ。
中西社長は昨年4月、組織を5つの領域に再編した(インフラシステム、電力システム、情報・通信システム、建設・機械システム、高機能材料システムの5グループ)。
「ITプラス社会インフラの融合、スマートシティ事業のグローバル展開、ビッグデータを用いた蓄積、検索・分析予測するニーズへの対応、これらを重点的にやっていく」(中西社長)狙いがこめられている。
前3月期決算は福島第一原発事故の影響で国内原子力事業が不振に陥ったこともあり、売上高は前々期から6000億円以上減って9兆410億円、営業段階では増益を確保したものの(97億円プラスの4220億円)、経常段階(2132億円マイナスの3445億円)、最終段階(1718億円マイナスの1753億円)では減益となった。
今年第1四半期も、国内原子力に加え中国など新興国での需要が落ち込んでいることもあって、減益が続いている。しかしそれでも、当初の計画よりは上振れしていると言い、中間決算での営業利益も、当初見込みの1300億円から1450億円に上積みした。また今後はアベノミクス効果も期待できる。
ただ、日立の営業利益率は4.7%(前3月期)にすぎない。これは国内電機メーカーとしては相当高い水準ではあるものの、GEやドイツのシーメンスの10%前後などと比べると、まだまだ見劣りする。
今年、発表した中期経営計画によると、15年度の売上高目標は10兆円、営業利益率は7%以上を目指す。海外売上高比率も現状の40%から50%に伸ばす計画だ。
この計画どおりに構造改革が進んだ時、日立はグローバルカンパニーとしての位置を確立することになる。
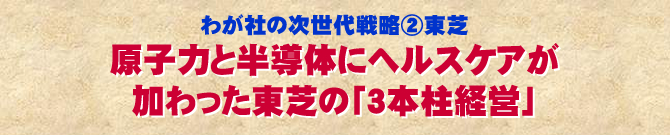
東芝が子会社の原子力発電メーカー、ウェスチングハウスを通じて、イギリスの原子力発電所運営会社を買収する方針であることが明らかになった。買収額は100億円超と伝えられている。
東芝がウェスチングハウスを50億ドル以上の巨費で買収したのは2006年のこと。当時の社長、西田厚聰現会長の決断で、将来にわたり原子力発電事業を東芝の中核事業と位置付けてのことだった。この価格に対し、当時は高値つかみとの批判も出たが、その後、地球温暖化対策としてCO2を出さない原発に注目が集まり、アメリカで立て続けに6基を受注するなど、買収の評価は一気に逆転した。
この流れは、日本でも同じように起こるはずだった。09年、当時の鳩山由紀夫首相は、国連本部でスピーチし、「20年までに温室効果ガスを1990年比25%削減する」と国際公約した。これを実現するためには風力や太陽光発電など、再生可能エネルギーだけで賄うことなど到底不可能であり、必然的に原子力発電依存を高めなければならない。そのことを、首相が世界に対して公約したわけだ。東芝の原子力事業は前途洋々に見えた。
事実、この頃の東芝は、「原子力の東芝」とのキャッチコピーの入った企業広告を、新聞や雑誌に数多く掲載していた。これは東芝の決意表明でもあった。
ところが、2011年3月の東日本大震災に起因する福島第一原子力発電所の事故により、日本での原子力発電所の新設は事実上不可能になってしまった。国内だけでなく、世界の原子力事業に暗雲が立ち込めた。
震災後、12年3月期、13年3月期の2期連続で、東芝は減収減益(営業段階)となった。その要因のひとつは、やはり原子力事業の不振だった。
いまでは経営用語として一般化した「集中と選択」を、日本でいち早く導入したのは1990年代の東芝だった。生き残れるのは業界1位か2位の事業だけ。3位以下の事業からは撤退する。この方針に基づき東芝は、小型モーター事業や音響機器部門を売却していく。それを突き詰めていった結果、西田社長時代に到達した結論は、原子力発電と半導体の2本柱戦略だった。
福島の原発事故によって、その2本柱戦略は大幅な見直しを迫られる。前述のように業績も低迷。株価も11年2月には553円をつけていたものが、昨年9月には234円と半分以下となった。
「原発事故によって、東芝の『集中と選択』路線そのものが間違っていたのではないか、とさえ言われたものです。何かあった時にあまりにも脆すぎますから」(ライバルメーカー幹部)
それでも東芝は、原子力発電を事業の柱から外そうとはしなかった。冒頭に記したM&Aは、今後の東芝の方向性を何より雄弁に物語っている。今後とも原子力発電事業は、東芝の最重要部門であり続けるということだ。
東芝にとって幸いだったのは、原子力の前途が見えない一方で、半導体部門が好調だったことだ。
東芝の半導体事業のメイン製品は、NAND型フラッシュメモリと呼ばれるもので、スマートフォンやタブレット端末などに使われている。この需要がスマホブーム、タブレットブームのおかげで急増している。東芝のフラッシュメモリ主力工場は四日市工場だが、この春からフル稼働が続いているという。それでも需給は逼迫している。そのため東芝では、来年夏稼働を目指し、300億円をかけて新しいラインを建設中だ。
7月に発表された東芝の第1四半期決算は、売上高が前年同期比10%増の1兆3906億円、営業利益が同112%増の243億円と、利益が倍増した。その最大の要因は半導体事業の大幅増益で、この部門だけで前年同時期より385億円多い479億円の利益を上げている。つまり半導体の利益で他部門の赤字を補っているという構図だ。
東芝が西田社長時代に、原子力発電と半導体を2大柱と定めた時から「短期的には半導体で。長期的には原子力発電で」と考えてきた。ところがその後のリーマン・ショックの影響で、世界的に半導体市況が悪化、東芝の半導体事業も大赤字に陥っている。しかしスマホやタブレット端末が普及したことで状況は激変、大きな利益を出せるようになった。これが半導体事業の面白さであり、怖さでもある。市況一つで収益は大きく変わってくる。それほどまでに不安定なビジネスだ。
そこで東芝は、この夏、「ヘルスケアを第3の柱に据える」(田中久雄社長)と宣言した。「医療費の増大が先進国と新興国のいずれでも大きな課題となっていることに加え、今後は画像診断に限定されない新しい診断・治療技術が確立される見通しで、ここに大きな商機がある」と田中社長は説明する。

ヘルスケアを3本目の柱にすると宣言した田中久雄社長。
すでに東芝は、X線CTT装置で世界3位、MRI装置で世界4位など、画像診断装置を中心に高いシェアを誇っている。今後、これらヘルスケア事業をさらに伸ばしていき、現在2770億円の同分野の売り上げを、15年度には6000億円へと倍増させるというのだ。
当然、既存のヘルスケア事業を拡大するだけではこれだけの短期間に倍増などできるはずもないため、M&Aも選択肢だ。結果的に失敗に終わったが、パナソニックのヘルスケア事業売却に手を挙げたのもその一つだ。
その一方で、大きくメスを入れたのがパソコンとテレビ分野だ。これまでパソコンとテレビはデジタルプロダクツ事業としてくくられていたが、これと白物家電などの家庭電器事業と合わせてコンシューマ&ライフスタイル事業グループが新設された(10月1日付)。
パソコンとテレビはともに赤字事業である。かつて東芝はダイナブックで米国市場を席巻。ノートパソコン分野では高いシェアを誇った。またテレビでは「レグザ」が福山雅治のテレビCMのおかげもあって大ヒット。国内テレビの勝ち組と言われたものだが、それもいまは昔。そこで東芝は、事業グループを再編するだけでなく、事業スケールの削減に踏み切った。
具体的には、海外に3カ所ある工場を一カ所に集約、従業員2000人を削減する。自社生産の比率を6割から3割へと半減させるだけでなく、120ある機種も70種ほどに削減するという。またパソコン事業でも設計や開発・営業・間接部門の人材を、社会インフラ部門へ振り分けている。
つまり、これまで東芝の顔であった事業分野にも大胆なメスを入れたということだ。これはとりもなおさず、集中と選択に聖域が存在しないことを意味する。
リーマン・ショックからこれまで、東芝はひたすら守りに徹していた。しかし、今年6月に田中社長が就任したのをきっかけに、再び攻めの姿勢を取り戻した。集中と選択により事業領域を絞り込むことは、時として大きなリスクを背負いこむ。赤字部門を黒字部門で補うという総合電機ならではの強みを発揮できないケースもある。それでも東芝は、集中と選択経営を掲げ続ける。
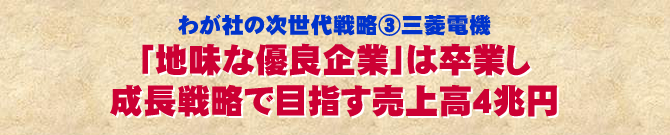
「地味な優良企業」。三菱電機をひと言で表すならこの言葉しかないだろう。
日立、東芝と並ぶ総合電機(この言葉もすでに死語となりつつある)の一角を占めてきただけに、商品分野は幅広く、社会インフラやエレベーターなどから、白物家電、AV機器などまで手掛けている。しかし、こと民生品にかぎれば、シェアトップの製品はなく、エアコンの「霧ヶ峰」など、一部を除けば知名度もそれほど高くない。しかし、その地味さとは裏腹に、業績は手堅い。何しろリーマン・ショック後の2009年3月期と翌10年3月期において、ともに黒字を確保した、唯一の大手電機メーカーである。
本特集の日立の稿で、日立が他社に先駆けV字回復を果たせたのは、リーマン・ショック前に危機に陥っていたことが逆に功を奏した、とある。三菱についても同じことが言える。ただし、三菱の場合は、その危機が訪れたのは、はるか昔、1990年代のことだった。
80年代まで、世界の半導体の覇権は日本メーカーにあった。日立や東芝、NECは、世界最先端のDRAM(メモリ)を市場に投入、大きな利益をあげてきた。三菱もそれに負けじと、半導体事業に入れ込んだ。90年代半ばには、半導体に明るい北岡隆社長が誕生したことで、それがさらに加速、1000億円を超える設備投資を決断している。
結果からすればこれが大失敗。大型投資の直後から半導体市況は暴落。三菱の半導体部門は96年度、97年度の2年間で1500億円の赤字を計上、98年3月期の同社決算は1000億円を超える赤字に陥り、有利子負債も1兆7700億円にまで膨らんだ。
しかしこの事態が三菱が生まれ変わるきっかけとなった。大赤字を出した98年、北岡社長が辞任するが、これは三菱グループが結集して退任に追い込んだといっていいほどの政変劇だった。

成長戦略に乗せることが使命の山西健一郎・三菱電機社長
後継の谷口一郎、野間口有、下村節宏の3代の社長は、ひたすら堅実に、企業の立て直しに専念していく。北岡氏はメディア露出も多い「派手な」社長だった。しかし以降の社長は、ITバブル崩壊後の2001年度、02年度と2期にわたって最終赤字に陥ったこともあり、ほとんどメディアに出ることなく、不採算事業からの撤退など、内向きの仕事に精を出していく。
まず1999年にパソコン生産から撤退。2003年には、かつてあれほど熱を上げたDRAM事業をエルピーダメモリに売却、さらにはシステムLSI事業をルネサステクノロジーに移譲した。エルピーダもルネサスも、ここ数年、業績悪化で話題になった企業である。もし三菱がそのまま持ち続けていたら、その傷がさらに大きくなったことは容易に想像がつく。
08年には携帯電話事業から撤退。ここ数年、携帯から撤退するメーカーが相次いでいるが、皮切りは三菱だった。
こうしたリストラ策と、それによって浮いた経営資産を、ファクトリーオートメーションやエレベーターなど産業用機器や社会インフラなど、もともと強かった部門に振り分けた結果、三菱の業績は回復を果たしていく。リーマン・ショックで赤字転落しなかったのは前述のとおりだし、時価総額においても、一時、日立、東芝を抜いて総合電機トップの座についている(現在は日立に次いで2位)。
その一方で三菱には、過去10年の売り上げがほとんど変わっていないというジレンマがある。かつてのように「売り上げはすべてを癒す」という時代ではないが、やはり企業規模が成長しないことには、社内のモチベーションも上がらない。
前3月期の業績は、売上高3兆5672億円、営業利益1521億円、最終利益695億円となっているが、売り上げ、利益ともに2年連続で減少している。07年3月期には、瞬間的に売上高4兆円を達成しているが、いまはそこから4000億円近く減ってしまっている。
現社長の山西健一郎氏は、10年に就任した際、13年度に売上高4兆円の目標を掲げている。その直近の売上高は3兆6651億円だから、毎年1000億円ずつ伸ばしていけば余裕で到達する、それほどハードルの高くない目標だった。ところが現実には、売上高はむしろ減少、どう考えても今年度での目標達成は不可能になった。
今年5月に経営戦略発表会で山西社長が明らかにしたところによると、今期の売上高は3兆8100億円にとどまる見通しだ。しかし山西社長はその発表の席で、売上高4兆円は14年度で達成すると明言した。当初の計画よりも1年遅れになるが、それでも山西社長は成長路線に意欲を見せる。というより、過去10年間以上にわたって堅実路線を歩んできた三菱を、再び成長路線に乗せることこそ自らの仕事だと考えているフシがある。
そのための方策が、「強い事業をグローバルでより強く」(山西社長)というものだ。
三菱の「強い事業」とは、(1)電力システム(2)交通システム(3)ビルシステム(4)FAシステム(5)自動車機器(6)パワーデバイス(7)⑦空調システム(8)宇宙システム――の8分野。これをそれぞれ世界市場で大きく伸ばすことによって、成長エンジンにする考えだ。
それに伴い海外売上高比率も、現在の35%から40%へと伸ばしていく方針だが、中でも新興国での展開が急ピッチで進んでいる。例えばトルコには、昨年12月に現地法人を設立、本格的参入を始める準備をしたと思えば、今年3月には、FA機器販売やシステムインテグレーションを手がけるGTSという会社を買収した。インドでは、昨年8月にエレベーター事業の新会社を設立したほか、今年3月にはFA開発センターの業務開始に漕ぎつけた。インドネシアには昨年11月に総合販売会社を設立し、空調システムや白物家電、FA機器の販売を本格化させている。
メキシコでは今年4月、FAセンターを開設したほか、来年には自動車機器製造販売会社を立ち上げ、北米向けの製造・販売を開始する予定だ。さらにブラジルでは、昨年7月に新会社を立ち上げ、NC装置の販売サービスを開始する一方で、FA機器や電力システムのアフターサービスを行う総合販売会社を設立した。このような動きが世界各地で始まっている。
また三菱が国内シェア8割を誇る重量子線治療装置(がん治療装置)の輸出にも乗り出す。経営戦略発表会で山西社長が明かしたところによると、すでにフランス、中国、シンガポール、サウジアラビア、ロシアから購入の打診があったという。同装置はそれほど台数が出るものではないが、1台100億円前後と高額なうえ、周辺装置を含めると200億円の取引となる。また、この装置とは違うタイプの陽子線治療装置などのがん治療装置の輸出も目指していく。
もっとも、既存事業の伸長だけでは、14年度1年間で、売り上げを2000億円以上伸ばすことは容易ではない。そこで可能性が指摘されているのはM&Aによる事業規模の拡大である。
三菱は10年にドイツの半導体メーカーを買収している。これが20年ぶりのM&Aだった。しかし買収金額は数十億円にすぎないから、M&Aによって4兆円を目指すのであれば、これよりはるかに大型の企業買収を目指さなければならない。山西社長が一部報道機関に語ったところによると、複数の案件が頭の中にあるという。これが具体化すれば、待望の4兆円が現実のものとなる。三菱電機の成長戦略が軌道にのるかどうかは、M&Aの成否にかかっている。
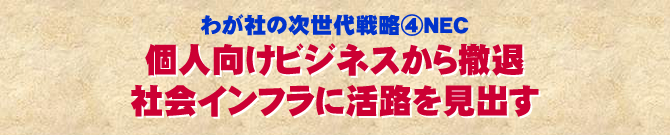
本誌発売日(2013年10月22日)のわずか10日ほど前、「NECがビッグローブを売却」というニュースが日本中を駆け巡った。
ビッグローブはNECが株式の78%を握る国内有数のインターネットサービスプロバイダ(ISP)。その歴史は古く、1996年にNECのパソコン通信サービスPC-VANなどが統合して誕生した。いわば日本のISPの草分けで、会員数は300万人以上を誇る。
そのビッグローブをなぜNECが手放すかというと、ビッグローブ単体では大きな成長が見込めないことと、売却によって得た資金を、社会インフラ分野などに集中投資するためだという。
ビッグローブ単体では黒字を維持していること、ISPの中でも富士通傘下のニフティと並んで高い知名度を誇っていることなどを考えると、この売却はもったいないようにも思えるが、ここ数年、NECが行ってきた「個人向けビジネスから社会インフラビジネスへ」という動きを考えると、ある意味で自然な流れということができる。
下の写真は、2011年1月のもの。右はNECの遠藤信博社長。左は中国レノボのヤン・ユアンチンCEOだ。この日、NECとレノボは日本国内のパソコン事業で提携、合弁会社を設立すると発表した。設立された新会社、NECレノボ・ジャパングループの出資比率は、NEC49%に対してレノボ51%。このことからもわかるように主導権はレノボにある。
NECといえば、1990年代までは日本パソコン界の巨人だった。中でもPC98シリーズは、累計で2000万台を売る史上空前のヒットとなり、NECのパソコン市場におけるシェアは、コンスタントに6割を超えていた。
マイクロソフトのOS、ウィンドウズの誕生でその天下は終わりを告げるのだが、その後も長らく、NECはシェア1位の座を守り続ける。日本のユーザーにとって、パソコンとNECは同義だった。
そのNECの顔ともいうべきパソコンで、レノボに主導権を渡したことは衝撃だった。NECの遠藤社長はこの提携の狙いについて、(1)製品力の強化(2)スケールメリットによるコスト競争力の強化(3)NECのビジネスパソコンの海外展開拡大――をあげている。
国内のパソコン市場は人口減少もあり大きな伸びは期待できない。しかも若い世代の中には、スマホがあればパソコンは要らないという人も増えている。だとしたら、個人向けには見切りをつけ、ビジネス用途で付加価値の高いパソコンをつくるほうが、NECとしてのメリットは大きいと判断したのだ。
さらにNECは今年の夏に、個人向けスマホからの撤退も発表している。NECはかつて、携帯端末市場シェアで、断トツの実績を誇っていた。日本におけるスタンダードになった2つ折りケータイも、最初に世に送り出したのはNECだった。
ところがスマホの出現がすべてを変えた。
iPhoneが日本に登場したのは2007年。しかしNECを含め日本のメーカーは静観の構えを崩さなかった。当時はまだ、その後のスマホ革命を、どこも予見できなかった。そのため、開発でも後手を踏んだ結果、iPhoneとサムスンにスマホ市場を牛耳られることになった。日本メーカーも遅ればせながら参入したが、今ではソニーを除けば存在感はないに等しい。NECもその中の1社である。
決定的だったのは、ドコモがこの夏に行った「ツートップ戦略」だ。ソニーの「エクスぺリア」とサムスンの「ギャラクシー」のみを格安で販売するこの戦略は、他のメーカーを直撃。NECのスマホもまったくと言っていいほど売れなくなった。
苦境から脱するために、NECはスマホ事業でもレノボとの提携を模索した。しかし結局条件が合わずに断念。残された道はスマホからの撤退だった。
このように撤退の歴史を羅列していくと、NECは縮小均衡に陥っているかのように見える。事実、NECの売上高は、2002年3月期には5兆円を超えていたが、前3月期には3兆716億円にまで落ち込んでいる。約10年で6割の規模にまで縮んでしまったのだ。
そして今度のスマホ撤退、ビッグローブ売却である。縮小均衡路線はまだまだ続く、と思われてもしかたがない。
ただ、過去10年の戦線縮小と、最近の撤退には大きな違いがある。過去が出血を抑えるためのやむなき縮小=リストラだったのに対し、最近の縮小は、経営資源を重点投資するための戦略的構造改革と見ることができるからだ。

レノボと提携するなど事業構造の見直しを進めてきた。右が遠藤信博社長、左はレノボのヤン・ユアンチン代表。
今年4月、中期経営計画を策定したが、その冒頭につぎのような一文がある。
《人が豊かに生きるための安全・安心・効率的・公平な社会の実現に向け、ICTを活用した高度な社会インフラを提供する「社会ソリューション事業」に注力し、社会の様々な課題解決に貢献するとともに、中長期的な事業規模の拡大と収益性の向上を目指します》
そのうえで遠藤信博社長は次のように語った。
「社会ソリューション事業を推進するため、常に市場と顧客を意識したスピード感のある組織体制に再編した」
この再編は4月1日付で行われており、この時以降、NECは社会インフラ提供会社へと、経営の舵を大きく切った。また借り入れによって1300億円を調達、そのうち1000億円を社会ソリューション事業へ投じるという。当然、それ以外の事業のプライオリティは低くならざるを得ない。
個人向けスマホの撤退や、ビッグローブの売却も、この延長線上にある。個人向け事業で将来性が見えないのであれば、そこにこだわる理由は何もない。その経営資源を、社会インフラに振り分けたほうが企業の目的とも合致するし成功の可能性も大きい、というわけだ。
もともとNECは、電電ファミリーの1社として、日本の通信を支えてきた。つまり、そのルーツは社会インフラ提供会社である。中興の祖、小林宏治氏が唱えたC&Cも、コンピュータと通信を融合して、世界中の人たちがつながる社会インフラのことを意味していた。
その意味からすれば、いまのNECは、先祖返りをしようとしていることになる。
バブル経済以降、身についてしまった贅肉を、過去10年間にわたって削ぎ落し、昔の姿に戻り、再び成長路線に転じようとしているかのように見える。
ただし、中期経営計画の目標は、前期3兆716億円の売り上げを、15年度で3兆2000億円、1146億円の営業利益を1500億円という、極めて歩みのスピードがのろいものになっている。これは成長よりも体質強化を優先させた結果である。
「今後100年間の礎を築く」と遠藤社長。次の飛躍のための3年が始まった。
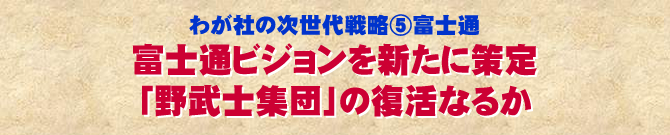
本特集で個別に取り上げた8社の中で、前3月期で最終赤字を計上した3社のうちの1社が富士通だ。
赤字額は729億円だが、営業、経常両段階では黒字が出ていたにもかかわらず最終段階で赤字に転落したのは、構造改革に伴い多額の特別損失を計上したためだ。
具体的にはシステムLSIを生産する三重工場の設備を減損処理したほか、ヨーロッパのパソコン販売など不採算事業のリストラ費用も盛り込み、総額で1500億円に達している。これにより赤字に転落したというわけだ。
今期に入っても苦戦は続いている。第1四半期決算をみると、営業段階で228億円、経常段階で187億円、最終段階で219億円の赤字となった。それぞれ、前年同期に比べれば39億円、80億円、35億円改善しているのだが、赤字脱却はできなかった。まもなく発表される中間決算でも赤字となる見通しで(通期では黒字を予定)、本特集の8社の中では、唯一の赤字企業となる可能性がある。
苦戦の理由として、パソコンや携帯電話の不振が挙げられる。パソコンに関しては、タブレット端末の普及の影響で、市場全体が縮小している。富士通のパソコンも、金額ベースで10%減少した。また携帯電話に関しては、富士通のスマホは、最大の販売先であるドコモの「ツートップ戦略」から外れてしまった影響が大きく、前年比30%減と激減した。
このほか、システムプラットフォーム事業でも赤字が続く。
富士通の過去10年の歴史は、赤字と構造改革の繰り返しに費やされてきた。
もともと天下のIBMを相手に、国内コンピュータ市場でシェアトップを維持してきた会社である。富士通と理化学研究所が共同開発したスーパーコンピュータ「京」が世界最速に輝くなど、技術力には圧倒的な自信を持つ。その技術力を武器に、1980年代までは快進撃が続いていた。ところが90年代に入ると、オープン化とダウインサイジングの波がコンピュータ業界に押し寄せた。
それに対応するために、IBMはコンピュータメーカーからソリューションメーカーへと変身する。顧客が求めているのはコンピュータではなく問題解決であり、ハードにこだわる意味はないことに気づいたのだ。そのためIBMは、プリンタ、HDD、パソコンなどの部門を売却していった。
富士通にとっても状況は同じだった。そこで90年代半ばには、IBM同様、ソリューションカンパニーへの変身を宣言する。しかし、よくも悪くも富士通はメーカーでありすぎた。汎用機からパソコンまで自ら製造することに誇りを持ちすぎていた。それだけではない。携帯電話、半導体、プラズマディスプレイ、液晶、さらにはエアコンなどの白物家電まで、富士通はすべて自ら製造し、市場に投入することの「誘惑」から逃れることができなかった。そのため、口では「ソリューション」と言いながらも、その体質は根っからのメーカーだった。その結果、IT業界の変化のスピードについていけなくなってしまった。
その結果として業績が悪化するたびに、富士通は構造改革を唱え、リストラを断行した。しかし本質的な体質改革ができずに終わるため、同じことが繰り返されるばかりだった。
だとすると、昨年、赤字転落と引き換えに行った構造改革も、過去と同じことになる可能性もある。
それでも2010年に就任した富士通の山本正己社長は、富士通は今度こそ生まれ変われると自信を見せる。4月の決算発表の席でも、特損計上によって赤字決算にはなったものの、「1500億円を投資し、課題事業への対応と体質強化に向けた構造改革にも着手してきた」と、けっして後ろ向きのリストラばかりではなきことを強調している。
富士通が収益拡大のエンジンとして力を注いでいるのが、クラウド・コンピューティングだ。「クラウドビジネスは、2012年度に売上高1500億円という計画は達成した。来年度は、これに、かけ算できるような形で伸ばしていきたい」と山本社長も期待を寄せる。このほか、マイコンと半導体の開発設計を米国企業に売却するなど、経営資源のシフトも引き続き行っていくという。昨年から続く構造改革で、これから進むべき道への対応は最終段階に入っている。
それだけではない。決算発表から半月後の5月16、17日の2日間、東京・有楽町の東京国際フォーラムで「富士通フォーラム2013」が開かれた。このフォーラムはICT(情報通信技術)を活用することで、社会や地域がかかえる問題を解決するための富士通の取り組みや、最先端のプロダクトやサービス、テクノロジーを紹介するというもの。

富士通の新たなビジョンを策定した山本正己社長。
このフォーラムの冒頭、挨拶に立った山本社長は、「このほどFujitsu Technology and Service Vision(以下、富士通ビジョン)をまとめた」と語っている。
富士通ビジョンは、ICTによってどうやって社会に貢献するかについて、富士通の考え方をまとめたものだ。いわば、今後の富士通の指針と言っていい。これを定めたことによって、富士通のモノづくりの手法そのものが変わってくるという。
「これまでは製品をつくってからそれを体系にまとめていたが、これからは富士通ビジョンをベースに開発を進める。富士通は生まれ変わる」(山本社長)
富士通ビジョンの中には、「ヒューマンセントリック」という言葉が出てくる。
《コンピューティングは、その黎明期のメインフレームに始まるコンピュータセントリックな時代、クライアント・サーバのモデルに代表されるネットワークセントリックな時代へと変遷してきました。スマートデバイスを1人ひとりが手にし、クラウドを通じて知見を得ることができるようになった今、コンピューティングは人を中心としたヒューマンセントリックな時代に進化していきます。コンピューティングの力は、生活・企業活動・社会基盤の中に埋め込まれ、人にやさしく寄り添って人と人との協働や最適な判断をサポートし、創造的な活動を支援します。そして、これまで個別のコンピューティングシステムに分断されて管理されていた多様な情報が、人の判断の役に立つように最適な形で整理・統合され(中略)、人々が情報を高度に利活用できるインテリジェントな社会が実現されていきます》
簡単にいえば、人が使いやすく利用しやすいようにという思想のもと、ICTを組み立てていくということだ。これまでの、技術力に頼った富士通からは出てこない思想である。この思想が根付けば、富士通はメーカー発想から抜け出し、クライアント・オリエンテッドな製品・サービスを生むことができるはずだ。
かつて富士通の社員は「野武士軍団」と呼ばれ、より高性能なコンピュータづくりに邁進、ライバルを蹴散らしてきた。しかしITの世界がハードからソリューションへと変化しても、野武士軍団は考えを変えることができず、迷走を続けてきた。
このほど策定された富士通ビジョンは、「より高性能なコンピュータ」に代わる新しい旗頭だ。この旗頭の下、野武士軍団が結束することができれば、富士通復活も見えてくる。
今期富士通は、4兆5500億円の売り上げと、1400億円の営業利益を見込む。この営業利益は、過去10年でもっとも大きな数字である。これが達成できるかどうかが、富士通が生まれ変われたかどうかの指針となる。
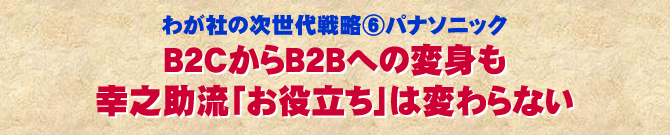
パナソニックがプラズマディスプレイから完全撤退する。すでに昨年にはプラズマテレビからの撤退を表明、神戸に2つあった工場のうち最新鋭の1つを閉鎖した。残る1つの工場で産業用ディスプレイなどへの活用を模索したが、それもうまくいかず、来年3月までにここも工場を閉鎖し、売却すると見られている。
このニュースが流れた時、多くのメディアが、「パナソニックのプラズマテレビが液晶テレビとの戦いに完全敗北した」といった論調で報じていた。確かにそれはそのとおりなのだが、プラズマ対液晶の戦いという意味では、7年ほど前にとっくに勝負はついていた。
2000年代初めまでは、大型テレビはプラズマ、中小型は液晶という棲み分けができていたが、技術進化により液晶が欠点をどんどん克服。40インチ以上の大型画面でも十分プラズマと勝負できるようになった瞬間から、液晶に凱歌があがるのは見えていた。パナソニックはそれまで注ぎ込んできた経営資源が無駄になってしまうことを恐れて、その現実から目を背けた結果、傷を大きくしてしまった。
ただ、この失敗を教訓に、パナソニックは新たな道を歩み始めた。
ひとつは、垂直統合モデルからの訣別だ。
「これまで我々は自分たちで部品をつくるなど、内部の活動に多くの時間とお金を使ってきました。でも、テレビを買うお客さんにとってみれば、中の部品をどこが作っていようが関係ない。そういう目で見ると、労力のかけ方、コストのかけ方がお客さんにわかりにくいというのがありました。そのやり方を変える必要があると考えています」(津賀一宏・パナソニック社長)
そしてもうひとつが、B2Cビジネスにこだわらない姿勢である。
パナソニックの創業者・松下幸之助の水道哲学はあまりに有名だ。家電製品を大量生産することによって、水道のように安く、誰にでも使ってもらえるようにする、というものだが、津賀社長は、それが普遍の考えではないという。

ついにプラズマディスプレイからの完全撤退を決めた津賀一宏・パナソニック社長。
「創業者の普遍の考えというのは、お客さんのお役立ちを考えるということです。求められることは時代時代によって変わっていきます」というのである。
日本が貧しかった時代は、家電製品を隅々まで行き渡らせ、少しでも生活を豊かにすることが社会の役に立つということだった。ところが、今や日本は十分に豊かになった。となると、お役立ちの意味も違ってくる。しかも物が足りない時代は、大量に作ってシェアを取れば、利益はあとからついてきた。しかし今ではシェアを目指せば目指すほど赤字になりかねない時代である。
そこで津賀社長の打ち出したのが、「家電製品への依存脱却」だった。毎年1月に、米ラスベガスで世界最大のエレクロトニクス見本市「CES」が開かれる。今年のCESでは津賀社長が基調講演を行ったが、その冒頭に語ったのが、「みなさんが知っているパナソニックとは異なるパナソニック」の姿であり、B2Cではなく、B2Bビジネスにかける思いだった。
3月末にパナソニックは2015年度を最終年度とする中期経営計画を発表したが、その内容のベースには、CESでの基調講演があった。
経営計画でもB2Bビジネスを拡大していくことが盛り込まれ、中でも自動車産業向けビジネスと住宅用ビジネスを、それぞれ18年度には2兆円規模にまで拡大すると宣言した。
自動車産業向けビジネスも住宅用ビジネスも、ともに現在の実力は1兆円前後。これをM&Aという手段を使いながら、5年間で倍増するというのである。
3月にこの話を聞いた人の多くが、大風呂敷を広げたと思ったものだが、ここに来て可能性を感じさせる事例も出てきている。
アメリカにテスラモーターズという、シリコンバレーに拠点を置く電気自動車(EV)メーカーがある。これまではスポーツカータイプのEVを生産していたこともあり、販売台数も限られていた。ところが昨年発売した4ドアセダン「タイプS」が大ヒット。今では月間1500台以上を販売するまでになった。
大人7人が乗れて、家庭用電源(200V)2時間でフル充電ができ、走行距離は500キロ、しかも価格が600万円前後なのだから、売れないほうがどうかしている。タイプSのヒットによって、テスラはついに黒字化を果たした。来年には日本でもタイプSの発売に踏み切る予定で、さらにその先には、クロスオーバータイプの「タイプX」の発売も控えている。
また日産自動車のEV「リーフ」も、日本国内ではいまだ販売が伸び悩んでいるが、アメリカでは今年になってから火が付き、今は月販2000台ほどとなっている。今や西海岸を中心に(電気料金が安いことに加え、気温が氷点下に下がることがないためバッテリーが劣化しにくい)、完全に普及期に入っている。
このムーブメントは、やがて世界中に伝播するだろうし、日本でも遅かれ早かれ、数年の違いでEVブームが起きることだろう。テスラの大ヒットは、世の中の流れを大きく変えようとしている。
そのテスラになくてはならないバッテリーは、そのすべてが、パナソニック製リチウム・イオン電池である(リーフは日産とNECの合弁会社製リチウム・イオン電池)。EV用リチウム・イオン電池は、容量が大きいだけに発熱する可能性があり、高水準な技術が求められるため、そう簡単に参入できる分野ではない。
それゆえこの市場を最初に抑えておけば、EVが普及すればするほど、パナソニック製電池の販売先が増えることにつながる。
加えて、EVそのものが走るコンピュータのようなもの。テスラの本社がシリコンバレーにあるのもそれが理由で、そうであるなら、普及すればするほど、電機メーカーが活躍する場面は増えてくる。パナソニックだけではないが、大きな市場がそこには広がっている。
住宅部門もそうだ。
この9月、神奈川県藤沢市の「Fujisawa サスティナブル・スマートシティ(以下FSST)」において、住宅建設が始まった。来年4月までに100戸の住宅が誕生する見込みで、まもなく人の住む街として動き始める。
FSSTは、もともとパナソニックの工場があった跡地に、住宅1000戸(集合住宅400戸、戸建600戸)、商業施設、健康・福祉・教育施設を建てようという再開発プロジェクトだ。ただし通常の再開発とは違い、徹底してエコにこだわっている。住宅からのCO2発生はゼロに抑え、街全体でも1990年比でCO2排出量70%削減、生活用水30%削減、再生エネルギー率30%以上の目標を掲げている。ここにパナソニックの持つ、HEMS(家庭内エネルギー管理システム)の技術のすべてを注ぎ込み、今後、日本全国で建設が進むと予想されるスマートタウンのモデルケースにしようと考えている。
これも、いままでパナソニックが目指してきたものが具現化した例である。
B2CからB2Bへと、パナソニックは大きく舵を切った。家電王国の復活はもしかするとないかもしれないが、しかし生活の様々な場で、パナソニックはユーザーとかかわり続けることになる。それが津賀社長の考える、お役立ちの形ということなのだろう。
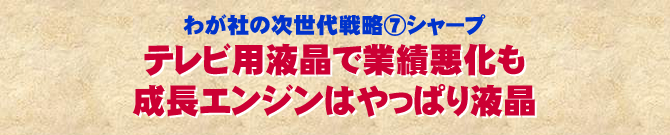
NTTドコモは10月に入り、今年の携帯秋冬モデルを発表したが、春夏商戦で見せた「ツートップ戦略」は終了、それに代わってソニー、富士通、シャープの3機種のスマホの値引きを他機より優遇するとした。事実上のスリートップである。
この決定をどこよりも喜んでいたのがシャープだろう。シャープの携帯端末は、春夏商戦でツートップに選ばれなかったため、販売台数を落としていた。9月からはドコモもiPhoneを売り出したため、シャープのスマホもそのあおりを食う可能性は高いが、それでもソニーのエクスペリアと同じ土俵に立てたことで、今後の展望が明るくなった。
シャープにとって、スマホ販売が拡大するのは、他のメーカーとは異なる意味を持つ。言うまでもなくシャープは、稀有となった、液晶までも自社生産する垂直統合モデルを持つ会社だからだ。
昨年、シャープが経営危機に陥り、台湾の鴻海集団との間で出資を巡るやり取りがあったことは記憶に新しい。シャープの株価が下落したことで、予定していた増資を引き受けてもらえず、資金調達に苦しみ、一時は倒産必至とまで語られたものだった。
経営危機に陥った理由は、リーマン・ショック後に明らかになったテレビ事業の不振である。価格競争で韓国勢に歯が立たず、シャープの液晶テレビは販売台数を落としていく。それが液晶パネル価格の下落を招き、ひいては増強を重ねてきた液晶工場の稼働率の低下につながった。業績もつるべ落としに悪化していった。
つまりシャープの場合、最終商品の売り上げの増減が液晶販売の増減に直結するため、悪い時はダブルで効いてくる。その悪い面が出た結果の経営危機だった。
前3月決算では、最終赤字が5453億円。その前年にも3760億円の赤字だったから、2年で9000億円を超える赤字を垂れ流したことになる。おかげで自己資本比率は6%にまで低下したのだから、存続を危ぶまれるのも当然だった。
シャープが液晶テレビしか生産しないと決めたのは1990年末のこと。当時はまだブラウン管テレビ全盛で、画質も液晶を上回っていた。それでもシャープが液晶テレビへと大きく舵を切ったのは、液晶メーカーとして生きていくことを決めたからだ。以前にもシャープは、ビデオカメラ「液晶ビューカム」で、液晶の新しい使い方を提案し、以後のビデオには、ほぼ100%液晶が組み込まれていくのだが、液晶テレビもそれと同じで、液晶の薄さ、省電力を自らのテレビで広めていくことがシャープの戦略だった。
この作戦はまんまと成功。それまでのシャープは三洋電機とほぼ同規模の大阪のローカル電機メーカーとしか認識されてこなかったが、液晶テレビの成功によって、国内ではパナソニック、ソニーをもしのぐテレビメーカーへと成長を遂げた。「世界の亀山モデル」のステッカーが貼られたシャープのテレビは、ライバルメーカーより高くても売れるという神話も生みだした。
しかしその神話はもう通用しない。テレビに代わる新たなビジネスモデルを構築しなければならない。ただ、そのベースになるのは、やはり液晶だ。
シャープの液晶工場の稼働率は、一部を鴻海グループに売却したことに加え、円安によって競争力を増したことで、国内外の携帯メーカー向けに販売を伸ばしている。かつては3割ほどしかなかった稼働率が、最近では7割を超えたともいう。
第1四半期で、シャープは営業利益30億円と黒字転換を果たした。四半期ベースでの黒字の確保はこれで3四半期連続。続く第2四半期もこの黒字は続いており、9月には、中間決算の営業利益が従来予想の倍の300億円になると上方修正。その最大の要因は、液晶部門の赤字が大幅に縮小したことだ。第1四半期でも液晶部門は95億円の営業赤字だったが、それでも11年前と比べると539億円も改善されている。
しかしいまのままでは、シャープは安心できない。再び市況が悪化したり、万が一、再び円高に振れることがあれば、以前と同じ状況に戻ってしまう。
それを防ぐ切り札としてシャープが期待しているのが、「IGZO」という省電力、高精細な液晶だ。スマホの最大の弱点は、すぐに電池がなくなることだが、IGZO搭載スマホなら、従来の約3倍の時間、使い続けることができる。

一時の経営危機を乗り越え、反撃に転じるシャープの高橋興三社長。
スマホはいまでもiPhoneとアンドロイド勢との間で熾烈な覇権争いが続いているが、機能面に限ってみれば、そろそろそれも限界に近づきつつある。それぞれの機能が似てくれば似てくるほど、最後は使いやすさといった、マシンとしての機能が重視されるようになる。となると、これからIGZO搭載スマホの出番である。
ところが現段階では、IGZOパネルは従来型液晶パネルより高いため、ほとんど外販できていない。そこで必要になってくるのが、かつての液晶テレビと同様に、シャープが自らの商品を通じて、IGZOの魅力をユーザーに伝えることだ。ただし高精細であることは店頭で確かめることも可能だが、電池の持ちについては、実際に使ってみなければわからない。
だからこそ、冒頭に記した、ドコモのスリートップに選ばれたことは大きな意味を持つ。auやソフトバンクに追い上げられているとはいえ、いまだドコモは45%のシェアを持つ携帯キャリアの巨人である。その「推奨銘柄」に入るか入らないかは販売実績に大きく響く。
現にシャープ自身、夏のツートップに入れなかったことで販売台数を落としたし、パナソニックとNECは、今度のスリートップに入れないことがわかったこともあり、スマホからの撤退を決意した。逆にソニーはツートップに入ったことで独り勝ちと言っていいほど販売台数を伸ばし、スリートップに留まることにも成功した。
シャープはスリートップに入ったことで、拡販のチャンスを得た。あとは電池の持ちの良さなどが、ユーザーレビューなどで広がっていけば、IGZOに対する興味と関心は一段と大きくなるし、それによって他社も搭載に踏み切る可能性が高まる。シャープとしてもここはぜひとも、IGZO搭載スマホの販売台数を伸ばし、反攻の狼煙としたいところである。
9月の取締役会で、約1500億円の第三者割当増資を決議した。これによって自己資本比率は6%から10%へと上昇。ここで得た資金を中小画面液晶の高精細化のための設備投資に充てるとしているという。
このことからもわかるように、シャープは自分たちの未来を、IGZOを中心とした高精細液晶に託している。
幸い、液晶以外の事業も、最悪期を脱した。テレビ事業も赤字は続いているが、販売台数を追わずに構造改革を進めたことで、収益は大きく改善した。テレビと携帯電話を合わせたデジタル情報家電部門は、昨年の第1四半期は202億円の営業赤字だったのに対し、今期の第1四半期では13億円の赤字まで改善、通期では50億円の黒字を見込む。太陽電池事業も、前年は69億円の赤字だったものが今期は68億円の黒字へと転換を果たした。またエアコンや空気清浄器を中心に、白物家電も堅調だった。
あとは成長エンジンとして、液晶が再び輝きを取り戻せるかどうかにかかっている。
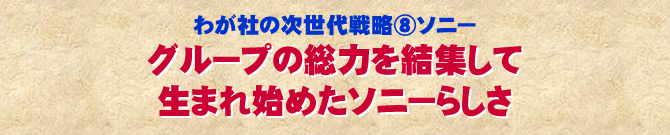
ソニーの社長兼CEOに平井一夫氏が就任して早くも1年半が経過した。
就任にあたり、平井社長はひとつのコミットメントを発表した。それは、ソニーの本業であるエレクトロニクス事業の復活であり、それをはっきりした形で示すために、2013年3月期でのエレクトロニクス事業の黒字化を明言した。
しかし結果は1344億円の営業赤字。前年の1702億円よりは改善しているとはいうものの、まだまだ巨額の赤字が残っている。公約は破られた。その責任を取って、平井社長以下全役員は、役員賞与を返上してけじめをつけざるを得なかった。
それだけに、今期は何が何でも黒字転換しなければならないが、幸いにもこれまでのところ、目標が達成できそうな趨勢だ。8月に発表した第1四半期決算では、エレクトロニクス事業の営業損益は、前年の131億円の赤字から134億円の黒字へと大きく改善した。これまで、エレキ部門最大の赤字要因だったテレビ事業も、前年の66億円の赤字が52億円の黒字へと黒字化を果たした。テレビ事業の黒字化は、10年度第1四半期決算以来12四半期ぶりのことだ。
平井社長によれば、第2四半期以降についても、「これまでのところ、予定どおりに進んでいる」。
ただしソニーの場合、単に黒字を出しただけでは誰も納得しないところがある。ソニーは創業以来、商品やサービスを通じて世の中を動かしてきた。決算数字よりも、むしろ商品によってソニーの復活を実感したいというファンは多い。平井社長はこれについても自信ありげだ。
「昨年来、会社をこうしたい、特にエレクトロニクスをこう持っていきたいという話をしているが、ここにきてそうした商品を市場に投入することができてきた。手ごたえを感じている」
次頁からの平井社長のインタビューにも出てくるが、昨年発売され、話題になったカメラに、ソニーの「RX1」がある。話題のミラーレス1眼ではない。部類としてはコンパクトカメラの仲間と言えるだろう。ズーム機能もついていない。それでいて実勢価格は25万円と超高価なカメラだ。こんな価格設定では売れるはずがないと思いがちだが、実際には人気を集めている。最大の特徴は、色再現性の素晴らしさ。昔のカメラのフィルムに当たるイメージセンサーを、従来のものよりはるかに大きい35ミリフィルムサイズにまで大きくすることで、画質を向上させたのだ。
ソニーはイメージセンサーにおいて、絶対の自信を持っている。その威信をかけてつくったカメラが、真のカメラ好きから高く評価された。購入した人からは、「こういうソニーらしいカメラを待っていた」という声も寄せられている。
もうひとつ、平井社長がソニーらしい商品として胸を張るのが、スマホの「エクスペリアZ」およびその後継の「Z1」だ。Z1はドコモの「スリートップ」にも入っているが、その最大の特徴はカメラ機能にある。ソニーがデジカメで培った最先端技術を、スマホの中に詰め込んだのがZシリーズだ。
デジカメやウォークマンは、スマホがその機能を兼ね備えるため、スマホ普及とともに販売台数が減少している。そういう状況ならば、スマホにデジカメの最先端技術を供与するのは、デジカメ部門の人間が抵抗するはずだ。「せめて1年前の技術を搭載してほしい」。こういう要請がデジカメ部門から出ることは容易に想像がつく。
ところがソニーのスマホには、最先端のデジカメ技術が提供されている。
平井社長は就任以来、「ワンソニー」という言葉を好んで使っている。ソニーグループがひとつになり、総力を結集してソニーらしい商品、サービスを提供していこうという意味が、そこには込められている。エクスペリアZシリーズは、まさにワンソニーを体現する商品と言えるだろう。
残念ながら、まだ今の状況では、ソニーが復活を果たしたと言うことはできない。しかし少しずつながら、その兆しが出てきていることは間違いない。
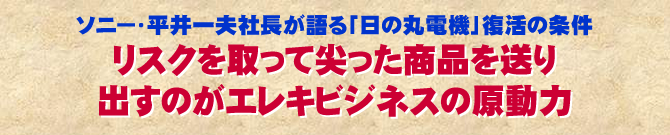
〔ソニーの平井一夫社長は、10月11日、本誌などのインタビューに応じた。インタビューは、最初、平井社長による状況報告から始まった〕

平井一夫氏がソニーの社長に就任してから1年半がたった。
平井 昨年4月に社長に就任して以来、自分の使命はソニーを変革すること、特にエレクトロニクス事業を再生させ、エンターテイメント事業と金融事業をさらに成長させることであり、この3事業をソニーグループのコアのビジネスとして積極的に関わっていくことだと思っている。(昨年、株主から上場を提案された)エンターテインメント事業については、ソニーグループにとっては戦略上必要不可欠なビジネスと考えているので、今後も100%保有していく。
エレクトロニクスビジネスの、コアビジネスはモバイルビジネス(スマホ等)、ゲームおよびネットワークサービス、デジタルイメージング(デジカメ等)だが、これから年末に向け、あるいは来年に向けいろんな商品を発表していく。モバイルではソニーの総合力を結集したエクスぺリアZおよびその後継のZ1、デジタルイメージングでは昨年大ヒットしたRX1と後継のRX1R、あるいは新しいスタイルのレンズ型カメラも発表した。ゲームではプレイステーション4の発売が控えている。加えてテレビ事業では4Kを中心にいろんな展開をしている。
昨年来、会社をこうしたい、特にエレクトロニクスをこう持って行きたいという話をしているが、ここにきてそうした商品を市場に投入することができてきた。手応えを感じている。ただし、エレキを取り巻く事業環境というのは、まだまだ厳しいし、解決すべき課題もあるので、マネジメントチームとしては、引き続き、気を引き締めていく。
―― エレクトロニクス再生の牽引役のひとつがモバイル分野だが、世界のスマホ市場でどういうポジションを目指していくのか。競争が激化する中、何が勝敗を分けるのか。
平井 モバイル市場におけるポジションということでは、ナンバー3ポジションには確実に入っていかなければならない。すでにナンバー3になっているところもけっこうあるので、そこでは、それを守っていく。あるいはナンバー2を目指す。
差異化ということについては、ひとつはハードウエアとしての魅力があるかということ。これに関してはエクスぺリアのシリーズ、とくにZ、Z1は、デザインや持った時の感触において、非常に高い評価をいただいている。デザイン力は昔からソニーのお家芸。これは徹底追求してきたし、これからもしていく。さらに「ワンソニー」として、ソニーの様々な事業部が持っている技術を投入していく。エクスぺリアでいえば、デジタルイメージングの技術に注目して投入した結果、撮像・撮影の部分が最大の差異化になっている。今後ともソニーグループが持つ最新の技術を投入し、商品に組み込んでいくのがソニーらしいスマートフォンの戦い方だと思う。
―― スマホに関して、米国市場、中国市場をどうやって開拓していくのか。
平井 スマホのいちばんのプライオリティは日本でのシェアを確実に守る、あるいはさらに伸ばしていくことにある。次にヨーロッパ。ヨーロッパ市場においてもソニーのシェアは高いので、これをさらに上げていくことが最重要課題だと考えている。そのため日本、ヨーロッパにはかなりの経営資源を投入している。逆に、米国、中国の市場に入っていくとなると、かなりの経営資源を投入してマーケティングからオペレーションまでやらなければならない。これを全部一度にやるのは現実的ではない。段階を踏んでひとつずつ確実にやっていく。
―― グローバルなテレビ市場において、ソニーはどのようなポジションを目指すのか。
平井 世界各地でシェア何位を目指すと言うより、いまどういうステージにあるか話したほうがいいと思う。副社長になってコンシューマーエレクトロニクスの責任者になったのが3年前のこと。そこでテレビビジネスを見ることになったが、その時は、まずは出血を止めなければならなかったため、シェアは追わないと言った。赤字を減らすために、モデル数を絞り出荷台数も絞り込むなどして、マーケットシェアを意図的に落とした。しかしその一方で、ディフェンスもあればオフェンスもある。オフェンスとしては商品の強化をやってきた。その結果、4Kなどいいものが出てきたという認識だ。だからいまは、マーケットシェアを取っていくんだというスタンスで、世界で同じようにビジネスをしている。

ソニー製スマホ、「エクスペリア」はソニー再生の原動力
―― 4Kが本格的普及期に入るのはいつ頃か。そのためにはコンテンツが必要なのか、あるいは価格が下がらなければならないのか。
平井 価格もですが、お客さんのいちばんの関心は、映像はきれいだけど何を見るんですかというもの。ソニーの4Kテレビは、アップコン機能(現行放送をより高精細に映す機能)がついていて高い評価を受けているが、やはり、総務省の次世代放送推進フォーラムで、4K放送をどう立ち上げるかが重要になってくる。
2020年に東京オリンピックがあるが、その前にも、来年はソチ冬季五輪とサッカーのブラジルW杯があり、3年後にはリオ五輪と、スポーツイベントがあるのだから、そこで4Kコンテンツを提供できるよう、ソニーとしてはハードもコンテンツも両面から、意見を述べさせていただく。
―― エレクトロニクスとエンターテインメントの融合の状況は。
平井 最近の例でいちばん手応えのあるのが、アメリカでスタートした4Kのサービスだ。4Kの場合、テレビは買ったもののコンテンツをどうするという話をよく聞く。その点、ソニーには、ソニー・ピクチャーズエンタテインメントがある。彼らに4Kの映画コンテンツをつくってもらい、映画が10本入っているハードディスクボックスを提供するサービスを始めている。このボックスを購入すれば、すぐに4Kの映画を観ることができる。9月1日にはダウンロードサービスも開始した。
他社ができないこうしたサービスをソニーができるのは、スタジオを持っているから。これがエレクトロニクスとエンターテインメントの融合の直近の例だと思う。
―― 日本におけるサービス開始の時期は。
平井 アメリカでダウンロードサービスを始めたばかりだが、4Kのコンテンツなので、ダウンロードに時間がかかる。これをどういうように提供するのがいいのかトライアルしている段階だ。たとえばヒットタイトルは先にダウンロードしておいて、見たい場合、キーだけダウンロードする。そうすれば、すぐに映画を再生できる。このようにいろんなアイデアがあるが、アメリカでトライアルして、お客さんの反応をいただき、それを踏まえて日本やヨーロッパで展開する時はグレードアップしたサービスを提供していこうと考えている。
エレキの黒字化は予定どおり
―― (ソニーの株主の)サードポイントから、エンターテインメント部門を上場すべきとの提案があったが、ソニーは100%保有し続けるとの結論を出した。その一方で、エレクトロニクス、エンターテインメントと並ぶコアビジネスである金融部門、ソニーファイナンス株は60%しか持っていない。なぜ完全子会社にしないのか。
平井 金融部門にいろんな見方があるのは承知しているが、いまの段階で発表するものは何もない。
同じコア事業でありながら、なぜ金融は6割にとどめているのかという話をよく聞くが、金融ビジネスというのは様々な規制があるために、仮に100%保有していても、60%保有と同じぐらいしかコントロールが及ばない。

CEATECでは世界最大の有機EL4Kテレビも出品した。
それに比べてエンターテインメント部門は、少数株主の方々が入ってくると経営スピードが格段に落ちてしまう。もしくはワンソニーという観点からいうと、少数株主に対してはいい判断かもしれないが、ワンソニーとして違う方向に向かってしまう可能性がある。
具体的に言うと、先ほど4Kのボックスの話をしたが、あれは音源や映画コンテンツについて100%コントロールできるから、大号令をかけてグループで一気にできた。少数株主がいた場合、もしコンテンツをもっといい条件でほしいというところがあって、自社でボックスをつくるより、他社に提供したほうが株主にとってメリットがあるとしたら、他社にライセンスせざるを得ないかもしれない。でもそれではエンターテインメントがエレクトロニクスビジネスを支えることにはならない。ワンソニーを実現するためには、100%保有している必要がある。
―― エレクトロニクス部門の健全化の進捗状況はどうか。
平井 エレクトロニクスビジネスの黒字化については、現在のところ、当初の計画どおり行っている。
―― 事業環境は厳しいというが、どういう状況か。
平井 よく、円安に振れるといいと言うが、ソニーの場合、対ユーロに関しては確かにプラスαある。しかし対ドルでは、円安によってマイナスになる場合もある。またあまり注目されていないがソニーの中で新興国ビジネスの比率が上がっている中で、新興国通貨のバランスがちょっと崩れてきていて、そこが利益に影響してくる。
―― そのような環境下で、ソニーとして何を目指していくのか。
平井 環境が悪いからと言って、手をこまねいていていいということではない。構造改革については、昨年社長に就任して以来、様々なことをやっているし、コスト削減についても各事業部で優先的にやっている。厳しい環境だからこそ、お客さんにこれってソニーらしい商品だよね、これって面白いねという商品を開発して市場に出していく。
―― 就任時に、ソニーを改革すると言ったが、1年半たって、その改革はどこまで進んだのか。
平井 改革については、これでいいいうものではなく、常にやっていかなければならない。最近は、ソニーらしい商品だねと言われることが増えてきたが、もっとソニーらしい商品、面白い商品を、各事業部がタイムリーに出してほしいし、もっとスピードアップできると思っている。
―― リーマン・ショック以降、日本の電機業界はソニーも含め大打撃を受けたが、復活できるのか。
平井 エレクトロニクスビジネスというのは、いかにお客さんに面白い、楽しいと言ってもらえる商品を市場に送り出すことかだと思う。これは、クリエイティビティとかイマジネーション、もしくはイノベーションという領域に入ってくる。そうしたものがソニーだけではなく、いままでの日本のエレキビジネスを支えてきた大きな原動力だと思っている。
そういったモノづくりのスピリット、考え方を推し進めていくと、リスクを取らないといけない。もしかしたらこの商品は売れないかもしれないという場合でも、果敢にリスクを取っていく。賛否両論あるような商品、それこそ、尖った商品を研究して開発しマーケティングしていく。こういうスピリットというのは必要だと思うし。それがあれば、日本のエレキビジネスは、価格競争に巻き込まれてコストで勝ち負けという軸とは違う軸のモノづくりができるのではないかと思っている。
(※)この記事は2013年10月19日のインタビューを再構成したものです。


柴田 裕 キーコーヒー社長
しばた・ゆたか 1964年、神奈川県生まれ。87年慶応大学経済学部卒業後、木村コーヒー店(現・キーコーヒー)入社。第一営業部などを経て、2000年常務、01年専務、02年から現職。今年、同社のフラッグシップコーヒーの「トアルコトラジャ」(インドネシアの直営農園で育てている豆)発売から35周年の節目を迎えた。
コーヒー市場争奪戦が過熱してきた。遡ると、1996年にスターバックスコーヒーが日本に上陸した後、タリーズコーヒーなど外資系チェーンが増えてカフェ事情が一変し、「コーヒー戦争」と呼ばれた。近年でも、大手コンビニが淹れたての「100円コーヒー」で攻勢をかけ、競争は激しさを増している。
加えて、ネスレ日本では9月から“インスタントコーヒー”という呼称を“レギュラーソリュブルコーヒー”に変更、価格面のみならず品質競争にも拍車がかかる。そこで、東京五輪開催の2020年に創業100周年となる老舗キーコーヒーの創業家社長、柴田裕氏に、同社の差別化、勝ち残り策などを聞いた。
―― 一口にコーヒー市場といっても、外食、コンビニ、カフェ、缶コーヒー、家庭用など様々ですが、いずれにしても競争自体は激化してきています。老舗のキーコーヒーとしては、どう勝ち残りに挑みますか。
柴田 企業はヒト、モノ、カネと言いますが、プラス、情報とブランドだと思うんですね。で、当社がこれまで少し弱かったのは、ブランドのところだと思っています。
もちろん、老舗ということでご存じの方もたくさんいらっしゃるんですけど、若い時にキーコーヒーに出会わなかった人には、コーヒーと言えば、外資系のコーヒーチェーンで紙コップで買う商品というイメージも強いですから。
店の看板に、キーコーヒーのロゴを掲げている喫茶店なら馴染みもあると思いますが、喫茶形態のみならず、ほかの商品も含めてもっともっとブランドを認知していただくことが重要です。コーヒー会社がたくさんある中で、「ほかの企業も知っているけど、一番美味しいのはキーコーヒーだね」とか、「ギフトで一番喜ばれるのはキーコーヒーだろうな」と、お客様からそんなふうに評価される会社でありたいですね。
―― キーコーヒーには、昔からのファンというコアな人が多いのでは。
柴田 今年3月に増資をしまして、個人株主が3万人から3万5000人に増えたんですけど、確かにそういうコアな株主が増えたと思います。5000人増えたこともあって、今年の株主総会では初めて出席者が1000人を超え、1200人の方が総会に来られました。ありがたいことです。当社の株は100株から買っていただけますが、300株からは、“株主限定ブレンド”という優待品もご用意しています。
もう少し、そのコアなファンのボリュームを増やしたいですし、当社の認知度は、たとえば九州全域と沖縄では割と強いんですが、中国、四国、近畿エリアなどでやや弱い。これは、現地への進出のタイミングが遅かったか早かったかが大きいと思います。
―― 業績的には前期(13年3月期)から増益に転じました。
柴田 前々期(12年3月期)は純損失を出してしまいました。当時、コーヒー豆の相場が上がったため、商品の値上げをさせていただいたんですが、11年の3月初めに値上げを発表して、直後の11日に東日本大震災が起こってしまった。あの混乱のさなかでしたから、値上げ実施はしばらく先送りせざるを得ず、それで利益が増えなかったのです。
―― 現在はコーヒー豆の相場も落ち着いてきていると思いますが、最近は円安がやや逆風ですね。
柴田 円安は、コーヒー豆だけでなく輸送燃料の高騰などにも関わってきますから。
当社の売上構成は、業務用で4割、家庭用が3割、原料用で3割あって、原料用というのは、缶コーヒーの会社にコーヒー原料を買っていただくビジネスです(JTの「ルーツ」ほか、ビールメーカー系飲料会社など取引先は広範囲)。
事業構成比的には、これまでこの「4・3・3」できたのですが、最近はクロスオーバーしてきています。ですから、当社でもこれは業務用、あれは家庭用とか、あまりカテゴリーごとに考え過ぎてはいけない。たとえば、コンビニの店頭で淹れたてコーヒーを買うという行動は、外食、中食、家庭用のどれにもあてはまりますしね。
あまり安穏としていてはいけないですが、日本でコーヒー市場が伸びてきた過程では、これまでもいろんなトレンドがありました。1960年代から70年代は喫茶店ブームでしたし、80年代からファストフードが出てきて、90年代に外資系コーヒーチェーン、2000年代からはイタリアンブームがあって、さらにコーヒー市場が伸びています。そして最近はコンビニコーヒーと。
そういう積み重ねが、コーヒーの消費全体には貢献していると思いますし、コンビニコーヒーの影響も、我々以上にファストフードやコーヒーチェーンのほうが大きいでしょう。要は、お客様が利用シーンによって使い分けていくのではないかと。
―― コーヒーマーケット自体は、規模感的にはどのくらいですか。
柴田 何を基準にするかですけど、当社のシェアでだいたい15%ぐらいと言われています。売上規模で言えば500億円強ですから、残り85%が2500億~3000億円の間ぐらいというところですかね。
―― キーコーヒーとしては、中長期的に売上規模をどのくらいまで拡大する計画ですか。
柴田 ここのところ、当社は資本業務提携などが続き、いまもその手のお話はいろいろあります。ただ、しばらくはいまのガバナンスに注力していきたいですね。この規模で株式上場しているコーヒー会社はありませんので、なんとか勝ち抜いていきたいと思います。
―― 確かに、05年にイタリアントマトを子会社化し、昨年はアマンドを子会社化、さらに今年、銀座ルノアール(ジャスダック市場上場)と資本業務提携を結ぶなど、アライアンスが加速してきました。
柴田 イタリアントマトの時は当時、ナムコさんが(イタトマの)親会社だったんですが、ナムコさんがバンダイさんと経営統合するにあたって、イタトマを引き受けてほしいと言われましてね。
イタトマは当社が手を挙げないと、ある居酒屋チェーンに買われそうになっていました。それなら親和性がより高い、当社に任せたほうがいいというご判断も働いたようです。当社の子会社になって、イタトマ当時よりもライトな「カフェジュニア」という業態にしましたので、地方のショッピングセンターなどにも出店がしやすくなりましたね。いま、フランチャイズで300店舗ぐらいになっています。

新業態「キーズカフェ」の外観パース。
アマンドについては個人的にも昔からよく使っていて、お取引としてのお付き合いも、もう50年ぐらいになりますが、先方の経営者が、「会社が厳しくなって何かあったら、キーコーヒーに頼みなさい」とおっしゃっていたようです。店舗数も、一時期は相当多かったんですが、立ち行かない店も少なくなかったのでかなり閉めていただきました。まだその過程にあり、不採算のところを整備していく必要があります。
3つめの銀座ルノワールは優良投資先の1つで、何か一緒にやろうという話し合いを続けてきました。あちらも株式公開会社ですので、ある程度の規模感があって、組むのだったら大きな外食企業よりもキーコーヒーがいいとおっしゃっていただいた。で、「喫茶室ルノアール」は東京23区内に100店舗(自社物件店舗、賃借店舗といろいろだが、ほとんどが直営店)もありますから、そういうアドバンテージも利用していければ、と。
―― その3業態の海外展開はどうでしょう。
柴田 イタリアントマトでは、すでに少しずつ海外で出店し始めていますけど、ほかの業態も海外で引き合いがあります。特にアジアを中心に、日本の外食産業はとても人気があって、喫茶業態も結構、人気があるようです。こういった市場も狙っていきたいですね。新興国の大都市では、ちょっと価格が高めの商品でも、中流層の拡大でだいぶ消費が活発になってきていますから。
―― 同業のUCCがUCCホールディングスと持ち株会社形態にしていますが、アライアンスが活発になってきたキーコーヒーでも持ち株会社化は検討しているのでしょうか。
柴田 方向性の1つとして検討はしていますが、現段階ではどういう形がいいかわからないですね。
―― 買収や資本参加だけでなく、キーコーヒー自身も「キーズカフェ」という新業態を始めています。
柴田 とはいえ、これは別会社を作ってやっているものではありません。いま、デパ地下中心にコーヒー豆の挽き売りの売り場が72ヵ所あるんですが、これは直営店と言えなくもない。一方で、キーズカフェというのは、キーコーヒーのブランドを上手に活用したいという方に向けてご提案している小型店業態で、いまのところ、高速道路のサービスエリアとか病院などでの立地が多くなっています。もう1つ、キーズカフェの特徴は、フランチャイズと直営の中間業態とでもいうべきもので、お取引先サポートの傾向が強いこと。
―― サポートとは?
柴田 たとえばその土地で人気のパスタレストランのオーナーに、店近くの病院や公共施設にも何か出店してほしいという声が地元からあったとします。そこで、パスタレストランの業態のままではちょっと重たいので、もう少し軽いカフェ業態なら出せるという時に、我々のご提案が活きてくるんです。
―― 多面的な展開で売り上げを伸ばしていこうということですか。
柴田 もちろん、個々の事業のセールスで売り上げを作っていくことも大事ですが、売り上げ自体はどこかのPB(プライベート・ブランド)を受託するなど、作ろうと思えば作れるんです。あるいは破格の条件を出して、コーヒー飲料の原料を受注しても売り上げは伸びるんですけど、それだと利益が伸びませんし、何よりキーコーヒーという存在感が希薄化してしまいます。
ですから、そういう事業もやりつつ、そのボリュームはある程度のところでとどめないといけない。キーコーヒーのものだから買ってもらえるという商品、あるいはご来店いただける業態を開発し続けることが大事です。当社には、氷温熟成コーヒーという独自技術の商品もありますし。
―― 最後に今後の重点課題を。
柴田 ブランド磨きに尽きますね。昔は、コーヒー会社といえば当社かUCCさんかと言われていたんですが、いまは外資系チェーンを挙げる方もいますし、コーヒーで想起される企業として、もう少し憧れのブランドにしていきたいと思います。そのために、商品と業態の両方を磨いていく。
日本は今後、ますます人口減少と高齢社会が加速するわけですが、当社に関しては、成熟されたシニア層の方のほうに比較的認知度が高いので、あまり大きくは心配していません。ともあれ、コーヒーでちょっと贅沢をという時、キーコーヒーを選んでいただける、あるいはすぐに思い浮かべていただけるようにしたいですね。
(聞き手=本誌編集委員・河野圭祐)
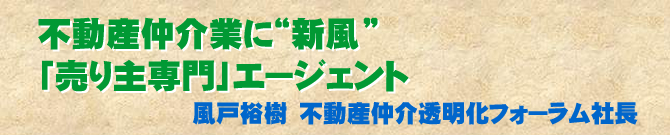

風戸裕樹 不動産仲介透明化フォーラム社長
かざと・ひろき 1981年10月24日生まれ。東京都出身。私立攻玉社高校を経て、2004年早稲田大学商学部卒業。同年オークラヤ住宅に入社。その後、06年にクリード、さらに08年ダヴィンチ・アドバイザーズに転じ、この間、起業構想を温める。09年にアーブル・パートナーズを創業、10年不動産仲介透明化フォーラムを設立、社長に就任。座右の銘は「他山の石を以て玉を攻むべし」。モータースポーツ好きでF1に詳しい。
不動産業界に対して、いまだ「騙され感」や「胡散臭さ」を抱く人は少なくない。そこを、中古マンション売買の事業を通して払拭しようとしているのが、不動産仲介透明化フォーラムの風戸裕樹社長だ。この若き起業家の目指すもの、そして起業経緯は――。
〔中古マンションの売買が活況だ。その売買を仲介する企業は、売り主と買い主の両方を仲介する「両手取引」が一般的。だが、できるだけ高く売りたい売り主と可能な限り安く買いたい買い主の両方から手数料(成約価格の3%)を取る慣習については、以前からこんな指摘もあった。「たとえば、原告と被告で同じ弁護士がつくはずがないでしょう。それと、他社に取られないよう、自社でお客さんを囲い込もうとするから、必然的に潜在顧客へのリーチが足りないんですよ」(業界関係者)
米国では売り買いのどちらか一方を専門にするエージェントが一般的だが、日本ではなぜか「両手取引」が普通になっている。そこに風穴を開けたのが、売却専門のエージェントサービス(サイト名は「売却のミカタ」)を手がける、不動産仲介透明化フォーラム(以下FCT。2009年にアーブル・パートナーズを創業し、翌年FCT設立)の風戸裕樹社長(31)である。同氏は今年、『マンションを相場より高く売る方法』(ファーストプレス)という著書も上梓し、売り主の支持を得て注目されている〕
普通、仲介会社で“できる営業マン”というのは、売却を依頼された際の査定価格が低いんです。低くても契約が取ってこれる人が、買い手にも売りやすく、両方から手数料が取れるからです。
であるならば、売り主専門に特化すれば、もちろん我々のコスト削減努力、営業努力もありますが、これまでの売却価格よりも高くなることは明らかです。
ただし、立地や眺望に難があればその限りではありませんし、売り主の中には、高く売るためにリフォームする方もいますが、我々としてはリフォームしてない物件のほうが売りやすい。個人でリフォームを依頼すると、だいたい平均で400万~500万円の先行投資がかかりますが、その分が売却価格に乗るわけではありません。リフォームは、あくまで買い手側に任せたほうがいいのです。
おかげさまで、この半年ぐらいで月に100件以上のお問い合わせをいただけるようになって、その中で実際に売却のご依頼を受けて成約するのが15から20件ぐらいですね。当社のウェブサイトを通じて、北は北海道から南は沖縄までいろいろなお問い合わせを受けるので、東京を中心とした首都圏以外でも、今年5月の名古屋を皮切りに、大阪や神戸、岡山など、西日本にも展開を広げています。
〔広域展開といっても、FCTが自分たちで店舗展開をするわけではない〕
地方都市でも、当社のように売却専門のやり方で少しでも高く売れることがわかったので、我々の事業理念と売るノウハウに賛同していただける不動産仲介会社が増えています。完全なFC(フランチャイズ)のように、店の看板ごと変えてもらうわけではないですけど、売却専門の部門として、「売却のミカタ」と同じやり方でやっていただくと。
〔さらに2013年9月27日からは、間取りタイプや階数、面積などに照らして分譲マンションの査定価格を公開した、「マンションプライス」というウェブサイトサービスもスタートさせている〕
現状、我々は仲介マーケットの1%から2%ぐらいのシェアを取れている感じなんですが、これを10%まで広げていくことを、向こう5年で達成させる計画でやっています。この業界は、最大手でもシェアが20%いってませんから、10%取れたら大手に伍すことができます。要は、消費者がマンションの売却を考えた時、その選択肢の中に必ず当社が入るようなところまでもっていきたいということ。ある程度のシェアを取っていくことで、売ろうとしている方が誰でも知る存在になりたいのです。
国交省でも、流通活性化フォーラムの中で、レインズ(不動産流通機構。売り主から依頼された不動産仲介会社は、依頼後7日間は同機構のサイトに他社も見る売却情報を出さなくて済む)に代わるシステム、さらに全方位的な売買情報開示を促していますから、いずれは、実際に法律的な面から変わっていくと思います。
〔風戸氏が起業した当初は、同じ不動産でも仲介手数料不要の賃貸マンション検索サイトの事業から始めている。賃貸でもこれまで、半ば不動産業界の“慣習”化しているものがある。仲介手数料は家賃1カ月分が普通だが、キャンペーンで半額、あるいは無料としている物件もあるし、礼金や敷金も各2カ月ずつの物件もあれば、礼金がない物件、敷引きや更新料の有無など様々だ〕

不動産業界のこれまでの常識を、消費者目線で変えている風戸裕樹・不動産仲介透明化フォーラム社長。
いまは「売却のミカタ」のサイトに特化していますが、そもそも当初は賃貸と売却両方のビジネスでやろうと思っていて、どちらが先かという時に、ウェブサイトを先に作り始めたほうが賃貸だったということです。いずれにしろ、起業のポイントは仲介の透明化だけに焦点を絞っていくということでした。何か新しいマーケットを作るというより、不動産業界に長らくはびこった慣習を変えていくことで、消費者から「不動産業って意外と透明なんだね、胡散臭くないんだね」と思っていただけるようにしたいと。
ただ賃貸のサイトは、ほとんどが同業者とウェブの中での戦いになってしまうので、検索の上位に来るかどうかで勝敗が分かれやすいんですね。その点、売却のビジネスは、より高く売るというサービス面での差別化がしやすい。なのでウェブでの競争に巻き込まれにくいということと、他社がやってない事業ですから、賃貸の時に比べてかなりのびしろがあるなと。それで売却の事業にフォーカスしたわけです。
〔ここからは、風戸氏のこれまでのキャリアから起業に至る経緯、などについて触れていこう。同氏が早稲田大学を卒業したのは2004年のこと。その前の02年から03年にかけては就職氷河期と言われて、採用が底だった時期でもある〕
入社試験は、不動産と金融しか受けていません。金融のほうは特に深い理由はありませんでしたが、たとえば銀行なら対面業界が広いので、ビジネス全体を見渡すことができ、起業意欲は学生の頃からあったので、そういう意味でもいろいろ勉強できるのではないかと。
不動産は単純に面白いと思っていて、私は文系の人間なので何かを作り出すというのは簡単ではないんですね。でも不動産なら、たとえば再開発プロジェクトにも、かなり文系の人間も関わっていくんです。だから面白みがある。ということで、不動産・ディベロッパー、それに付随して仲介会社を受けていました。
でも就活はうまくいかなくて(笑)。それまであまり挫折なくストレートで来ていたので、甘い考えで、いわゆるいい会社に入れるんだろうなと思っていたんですね。
学生時から起業を意識していたのは、世の中で若手起業家が注目されるようになったからというより、父親の影響が大きいですね。父は理系のエンジニアで、いわゆる大企業にずっと勤めていたんですけど、私が高校1年の時に病気になり、会社を辞めざるを得なくなったんです。
そこで、定年まで勤め上げるというのがあまり魅力的には思えなくなって、自分で何かビジネスを興す立場に立ちたくなりました。また立たないと、どんなに健康に気を使っていても何が起こるかわかりません。父は酒も煙草もやらない人間でしたし、大企業に入っただけでは安心できないと思いました。
〔とはいえ、起業する前に一度社会で揉まれる経験はしておかねばいけない。苦労の連続だった就活で、やっと辿り着いたのが、中古マンションの買取再販や仲介業を手がけるオークラヤ住宅だった〕
もう1社、野村不動産アーバンネットからも内定をいただいてましたが、どちらも学歴に関係ない仕事で、就職氷河期という環境のせいにしない力をつけていこうと考えました。発想を転換して、入社した会社でトップ営業マンを目指そうと。どちらの会社に行くかは最後まで悩みましたが、当時の野村不動産アーバンネットだと、仲介業務しかなかったんです。
一方で、オークラヤ住宅なら物件を買い取ることもできる。仲介だけだとどこか他人事に感じるので、自分たちが当事者にもなれるというポイントが大きかったですね。
〔2年後の06年、風戸氏は不動産ファンド会社のクリードに転職する。トップ営業マンを目指せば目指すほど、消費者利益とは乖離していくことを実感するようになったという。が、リーマン・ショック前という時期で、不動産ファンドは破竹の勢いを見せていた頃でもあり、クリードで腕を磨くうち、営業成績が良かった風戸氏にヘッドハンティングの話が舞い込む。スカウト先は、「稼ぐが勝ち」を地でいくような、同じファンドでも最大手のダヴィンチ・アドバイザーズである。08年のことだった〕
ダヴィンチでの1年半ぐらいは、本当に死ぬような思いで仕事をしましたね。不動産の評価も投資家とのやりとりもかなり強引でしたし、そういう意味では、クリードはまだまだゆるいファンド会社だったんだなと思いました。
ダヴィンチでは給料もすごく高かったですけど、お金をたくさんもらって嬉しいという気持ちは段々薄れてしまいました。そんなにお金を使う機会もないし、貯金するのが楽しいわけでもない。そうこうしているうちに、リーマン・ショックでファンドバブル崩壊です。当時は結婚したばかりの頃でしたが、以前から起業の話は彼女にしていましたし、両親も、起業について特に何も言いませんでした。
私自身、クリードとダヴィンチの2社の経験で、かなり自分に自信がついたんです。賃貸も売買の世界も見ることができ、不動産1棟の投資キャッシュフローの書き方、あるいは土地を仕入れて建物を建てること、既存の古いオフィスビルや住宅をリノベーションすることも、20代半ばぐらいでやらせてもらえましたから、経験も人的ネットワークも、同世代の人たちよりかなりあるという自負はありましたね。
起業に際しては、海外に6年ぐらい赴任している友人がいたので、彼らに「米国では不動産はどういう仕組みになっていて、どうやって家を借りたり売ったりしているのか」と聞きながら、その情報を組み合わせてサイトを作る準備をしていきました。
〔風戸氏の著書は、FCTで会長を務める吉川克弥氏との共著となっているが、吉川氏は「不動産マーケットの歪みを解消する」という志を共有する創業メンバーで、経営パートナーでもある〕

著書の帯にある「相場より500万円以上高く売れる会社」が目を引く。
当初は資本金100万円で会社を作り、賃貸サイトの時はあまりブランド力も必要でなく、ある意味、集客さえすればお金にはなったんです。
で、そうこうしているうち、「売却のミカタ」の構想を練っていた時に吉川と知り合いました。彼は私がクリードにいた時に、クリードに対して仲介をして取引があったんです。
その後、吉川も独立して不動産コンサルティング会社を興しましたが、リーマン・ショック後、「これから新しいものを作らなければいけないだろう」と。
私が「消費者のために米国型の仲介をやりたい」と言ったところ、非常に興味を持ってくれまして、彼も、昔いた野村不動産でマンションを売っていた頃を思い出し、「それなら一緒にやろう」ということで共同出資に至っています。
〔さて、賃貸のサイトから「売却のミカタ」に全面シフトしたFCTだが、風戸氏は会社を拡大させていく上で、次なる成長分野を視野に入れているのだろうか〕
1つやりたいのは、投資家向けのサービスです。リノベーションといったビジネスも確かに華があっていいんですが、この分野を手がける会社はすでにたくさんあるので、いまから打って出ても中途半端になってしまいます。
むしろ、投資用に不動産を買っている方、あるいはこれから買う予定のある方に向けたサービスがいい。いまよりも賃料を上げる、あるいは物件のバリューアップをする方法とか、価値を高めて高く売るためにしておくべきノウハウは私も吉川も強いので、それはやっていきたいなと。あまり大きく広げる気はないので、ぶれることはありませんね。
(構成=本誌編集委員・河野圭祐)
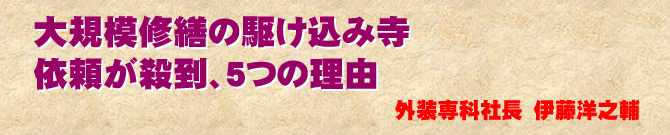
中古マンション売買やリフォームなど、最近の住宅を巡る事情やビジネスは今回の「経営戦記」をご参照いただくとして、まだまだ多くの人にとって家は一生に一度の買い物で、“終の棲家”というのが実情。となると、マンションの経年変化とともに避けては通れないのが大規模修繕だ。
そこで問題になりがちなのが、ある意味利益相反する、マンションの管理会社と管理組合の関係である。管理会社側からすれば、経年ごとに予め計画されている修繕を促すのもサービスの一環であり、そのために修繕費を積み立ててもらっている。一方の管理組合は、修繕費をできるだけ抑えたいが、専門知識の不足が悩みだ。

伊藤洋之輔・外装専科社長とダイヤモンド社から出版された同氏の著書。
その、弱い立場の管理組合にとって、いわば“お助けマン”的な存在といえるのが本稿の「外装専科」である。社名だけ聞くと一見、お洒落なアパレル企業と勘違いしそうだが、創業社長の伊藤洋之輔氏(1945年生まれ)は、こう語る。
「かつて工事で使っていたシーリング材に“外壁専科”という変わった社名を見つけて、そこからヒントを得ました」
印象に残る、社名を商標登録してあるだけでなく、同社のホームページや伊藤氏の名刺にも刷りこんである、“マンション大規模修繕かけこみ寺”というキャッチフレーズも商標登録済みだ。これだけみても、同氏は商才あるアイデアマンといっていいだろう。
そして社名の〝専科〟のとおり、いたずらに手を広げない。戸建ては手がけずマンション修繕だけに特化し、給水管の交換やリフォーム、リノベーション分野にも進出していない。あくまで屋上の防水工事や外壁、廊下工事など、文字通りマンションの外回り工事に集中しているのが特徴だ。
「外装専科で再出発して今年でちょうど10年。3年前の9月に『ガイアの夜明け』(テレビ東京のドキュメンタリー番組)で取り上げられて以降、依頼が殺到するようにはなりましたが、その1年ぐらい前から、すでに見積もり依頼が目に見えて増えるようになりました。後で考えると、ホームページ上に載せた『大規模修繕のかけこみ寺』という文言に惹かれた方が多かったんでしょうね」
とはいえ、当事者がいくら駆け込み寺を自認しても、看板に偽りない、丁寧で良心的な工事実績を積み上げなければ、インターネット上で口コミ評価がたちまち広がってしまうこの時代、定評を獲得し続けていくことはたやすくない。
外装専科を頼ってくるマンションの管理組合は、まさに切実そのものなようだ。その事例として、こんなケースがあるという。
「権限を持つ管理組合の理事長が1年で代わるとか、あるいは何もわからない素人の方が理事長に就く一方で、管理会社はなるべく工事を請け負いたいし、かつ規模も大きくやりたいんですね。だから、先延ばしにしていいような工事もひっくるめて提示してくることがある。たとえば、当社では1500万円ぐらいで請け負った工事が、管理会社の見積もりではその3倍ぐらいの額を提示されたという例があります。
一方で、修繕積立金は2400万円ぐらいしかないという。それでびっくりされ、お困りになって当社にお声をかけていただいたわけです。当社なら、工事後も1000万円近い積立金が残るわけですが、管理会社の言うがままだったら大きな借金をしなければいけなかったのです。管理会社、あるいはコンサルタントもそうですが、そういうところが見積もると、1所帯あたり100万円といった相場があるようで、修繕費がかなり大きな金額になってしまうんですよ」
管理組合側からすれば、当然のように高い見積もりを出す管理会社に怒りを覚える一方で、当初は「なぜ、外装専科ではそんなに安くできるのか」という思いも錯綜したのではないか。前述したような、3倍もの開きが出る工事価格は、どこがどう違うのだろう。

コストのかかる組立足場でなく、ビルの窓ふき清掃にヒントを得て、ブランコやゴンドラを使った吊り足場でコストを軽減。
その要因はいくつかある。たとえばマンション屋上の防水工事など、まだ先延ばしできる工事については次回での修繕を促すことが1つ。管理会社側の主張する、単純に10年、15年刻みで計画されたような修繕工事は、必ずしも必要でないケースが少なくないからだ。そういう仕分けをしただけでもずいぶん費用総額に違いが生じる。要は、管理組合側に修繕知識や現状認識がしっかりなければ、管理会社に押し切られてしまうことになるのだ。
2つめは、外壁工事では組立足場を組むのが一般的だが、この組立足場が工事コストを大きく膨らませるため、外装専科ではビルの窓ふき清掃にヒントを得て、下の写真にあるようなロープを使ったゴンドラ足場などでコスト軽減に成功している。
3つめが、これも商標登録している「ワンコート塗装」(=1回塗りで仕上げることができる塗装工法)で、他社にない特徴だという。
さらに4つめ。同社では80人近い職人を専属で抱え、元請け工事以外の、いわゆる下請け、孫請け、曾孫請けなどは基本的にしない。しないから、職人に対しても業界平均を大幅に上回る待遇が用意できる。また、職人たちも優遇によって誇りを持ち、丁寧で心のこもった仕事をする。いわば、ダイレクトに請け負って中間マージンのコストを削り、消費者に安く提供し、働く人にも報いていくというわけだ。しかも、この好循環に口コミ力が効き、広告宣伝費や営業費用をほとんどかけずとも、管理組合のほうから自然と依頼が来るというわけだ。
5つめが工事後のフォローの真摯さ。受注額が500万円以上の工事についてはナンバリングしてファイルに収め、何の工事で、住所はどこ、受注が紹介なのかリピートなのか持ち込み依頼なのかといった要因まで、細かく工事経歴書を作成している(今年7月末時点で延べ527件)ことにある。
本来、工事経歴書の施工実績は多ければ多いほどいいはずだが、大抵は都合のいい“抜粋工事”の実績のみで、すべてを開示しているわけではない。その点、外装専科では過去の工事実績が削除できないよう、ナンバリングをして開示しているのである。
「これまで未収入金は数十万円しかありませんし、裁判で訴えられたことは1件もありません。工事経歴書のみならず保証書も、たとえば工事した外壁塗膜に万一、膨れ剥がれ、あるいは極端な変褪色が発生した場合、5年間無償で修理しますし、塗装工事を実施した外壁面からの雨漏りも5年間保証しています。そして、もし実際に発生した場合は必ず無償修理する。この積み上げが信用そのものですから。
修繕工事は数千万円単位になるので、消費税増税を気にされる方も結構、いらっしゃいますが、(管理会社に煽られて)1年か2年早く工事させられてしまうだけです。それよりも、きちんと大規模修繕のサイクルを考えていくことが大事ですね」
ひと口に大規模修繕といっても、立地や規模、躯体などマンションによって工事の条件が異なってくるが、伊藤氏から見て、大規模修繕をやりやすい物件、やりにくい物件はどこが違うのだろう。
「我々の得意とする、ブランコ足場やゴンドラ足場などの吊り足場でやる場合、やりやすいのは普通の箱型ですが、特に関西では、屋上が屋根型をしたマンションも多いので、ちょっと危険を伴います。ですから、斜め屋根の物件では、当社の特徴がなくなっても安全性第一を考え、組立足場にするよう指示することもありますね」
気になるのは最近、大都市圏で増えているタワーマンションだ。高層で、特に上階からの眺望を売りにし、その分価格も破格だが、こうしたタワーマンションが将来、軒並み大規模修繕期を迎えたら、果たして外装専科式の修繕は可能なのか。
「まず、タワーマンションを手がける修繕業者自体がまだ少ないです。だから工事価格も相当、高止まりしていますし、どうしても管理会社依存になってしまうでしょうね。タワーマンションは、買った後の維持費、修繕が大変だと思います。
でも、私も長年やってきましたからアイデアは持っています。バルコニーがぐるっと建物の四方を囲っているようなマンションであれば、10階とか15階、20階といった節目のフロアの方に、3カ月から5カ月ぐらい、ほかのマンションで暮らしていただくんです。で、その期間、フロアごとお借りして、各部屋の中を通ってバルコニーに出て工事をする。そういうことができれば相当、工事費も安くできるんじゃないかと」
伊藤氏は、1人のプロの職人であると同時に、創業経営者でもあるのだが、今後についてはこう語る。
「私も来年2月で69歳になりますし、いつまでも社長をしていてはいけない。そろそろ当社の良き社風を見守る、会長にならねばいけません。
過去、私は自己破産という苦い経験もしています。かつて『時代劇の父』と言われた、伊藤大輔という映画監督がいましたが、彼は私の叔父で、この立派な叔父を目標にし、お客さんに喜ばれることを大きな励みに頑張ってきました」
ここで、伊藤氏のキャリアを簡単に振り返っておこう。19歳で父親が営むビルの塗装・防水工事業に従事し、24歳で独立、伊藤工業所を興した。主に雨漏り修理を手がけ、独力で「ノンクラックコート」を開発、塗装業に移行する。こうして1980年にアズマ工業(後に株式会社アズマ)を設立するのだがその後、急成長の反動か、管理体制の甘さもあって大幅赤字に転落。同じ頃に始まった銀行の貸し渋りも追い打ちをかけ、98年に会社、個人とも破産してしまう。
それでも不屈の精神を発揮して、破産直後から個人で塗装業を再開し、10年前の2003年に有限会社外装専科を設立、2年後の05年に株式会社化して今日に至っている。
最後に、伊藤氏はこう結んだ。
「我々の工事スキル、工程管理ノウハウなどをいままで以上に磨いて、会社としてはそんなに大きくならなくてもいいから、少なくとも私の目の黒いうちは、お客さんのほうから自然と発注が来るという社風は絶対に守りたい。そこが壊れたら、ただの会社になってしまいます」
(本誌編集委員・河野圭祐)
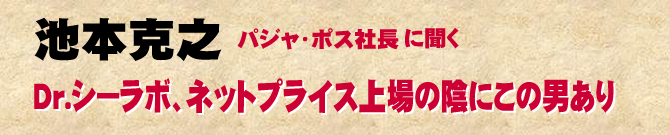

池本克之 パジャ・ポス社長
いけもと・かつゆき 1965年神戸市生まれ。88年日本大学生物資源科学部卒業。ノンバンク、生保を経て、コンサルタントとして独立するが、2001年、請われてドクターシーラボ社長に就任。同社は03年に上場を果たす。04年にはネットプライス執行役員となり、4カ月後に同社は上場。その後、パジャ・ポスを設立。コンサルタントとして活躍するほか、NPO法人「Are You Happy? Japan」代表を務める。
―― 池本さんは過去にドクターシーラボ、ネットプライスの上場に貢献し、現在はコンサルタントとして多くの企業の経営に関与しています。もともとコンサルタントという仕事に興味があったのですか。
池本 そんなことはありません。大学時代は、とにかく海外で仕事をしたかった。卒業してノンバンクに就職したのも、海外要員を探していると聞いたからです。
―― 就職したのが1988年。バブルのピークに向かって、日本中がイケイケドンドンだった時代です。
池本 本当にそうでしたね。就職の心配をすることもなかった。私の場合、もともと鉄鋼会社の内定をもらっていましたが、3月になってから、ノンバンクへの就職を決めています。そういうことが許される時代でした。
ただし、就職したあと、業績は急速に悪化していきます。入社時には2700億円だった借入金が、7年後に退職する時には9800億円にまで膨れ上がっていましたから。
―― 海外で働くことはできたのですか。
池本 投資先のひとつに、ハワイのホテルがありました。ここに入社3年後から3年間、出向しています。マウイ島にあったこのホテルは、稼働率が30%台と経営不振に陥っていた。私に与えられたミッションは、このホテルを再生させたうえで売却し、資金を回収するというものでした。
幸いだったのが、このホテルの上司が、もと日本ペプシコーラの役員だった人で、この人のもとでアメリカン・マーケティングや、事業経営のやり方を覚えることができたことです。実際、この経験は、いまも非常に役に立っています。
このホテルは無事、外国の投資家に売ることができました。売却後は、ノンバンクに戻り不良債権の回収などにもあたりましたが、その一方で、中小企業の事業再生も担当していました。中小企業の場合、ただ「返せ」と言っても意味がない。ほとんどの経営者は真面目な人で、お金があったら返したいと考えている。でも資金的にそれがむずかしい企業ばかりです。そこで、一緒になって事業計画をつくり、毎月100万円返さなければならないところを30万円に減免するなどして、その企業をいかにして再生させるか、という仕事をできるかぎりやるようにしていました。
―― 一種のコンサルですね。
池本 ええ。でも片方で何百億の不良債権があるわけですから、あまり会社では認められる仕事ではありませんでした。そこで退職して、生命保険会社に入ります。配属されたのは代理店営業で、代理店を開拓して、生命保険の売り方を教えるというものです。ここでも上司に恵まれ、私はその上司から、セールスと教育を学ぶことができた。この2人との出会いが、いまの私を支えています。
―― その後、コンサルタントとして独立しますが、ドクターシーラボに入社していますね。
池本 独立後、友人の紹介でドクターシーラボ創業者の城野親徳さん(現会長)と出会います。当時は社員数15人ほどの小さな会社でした。でも私が手伝うようになって、1カ月で売り上げが大きく伸びた。それを見て、城野さんが社長になってほしいと言ったのです。
―― そんな短期間で成果が出るものですか。どんなマジックを使ったんですか。
池本 できていないことをリストアップして解決するという、極めて単純なことです。一例を挙げれば、広告を打てば注文の電話がかかってきます。ところが当時は、そのすべての電話を受けることができませんでした。これを解決するために、臨時で人を雇ったり、一部、外部に出したり、残業してもらったり、1件あたりの通話時間を短くしたり、様々なことをやってすべての電話を受けられるようにした。それだけで売り上げは大きく伸ばせるのです。
社長になってからも同じことです。宣伝を打つ。その効果を分析する。受注体制や物流体制を整え、リピート率を高めるための仕掛けをつくる。そしてそうした一連の流れをシステム化し、効率的なインフラをつくる。そうしたことを飽きずに精密に組み合わせていく。ただそれだけなんですが、わかっていてもなかなかできないことでもあるのです。
―― その結果、社長就任から3年もたたずに、ドクターシーラボは上場を果たします。
池本 もともと入社する時に、城野さんにどこを目指すかと聞いたら、上場を目指したいと言うから、そこに向かって進んでいきました。でも、この間は本当によく働きました。先ほど挙げた仕事をほとんど1人でやっていましたから。ほとんど家にも帰らず、会社に置いたソファーベッドの肘掛部分が、私の頭の形になったほどです。
―― ドクターシーラボを上場した1年4カ月後には、ネットプライスの上場に携わったそうですね。
池本 ドクターシーラボを辞めたあと、4カ月ほど遊んでいたんですよ。まとまったお金もありましたし。でも面白くない。やっぱり働こうと決めたのですが、どうせなら、ネットベンチャーで気の合う経営者と一緒に仕事をしたいと考えていたところに紹介されたのが、ネットプライスの佐藤輝英社長でした。佐藤さんとは初対面で意気投合し、即座に入社を決めました。
ネットベンチャーですから、みなITやデジタルには強い。でもその一方で、物流部門やコールセンターなどが遅れていた。ドクターシーラボでの経験がありますから、こうしたアナログ部分を引き受けて、入社4カ月で上場に漕ぎつけることができました。
―― 立て続けに2つの会社の上場に関わったわけですから、その後も、上場を目指す企業からスカウトされたりしませんでしたか。
池本 きましたよ。でも、少人数で自分の好きな仕事をやろうと考え、コンサルタントとしていまに至っています。
―― コンサルタントとしての立場から見て、いまの日本企業の問題点はどこにあると感じていますか。
池本 ひとつには、投資することに対するマインドが問題だと思います。どういうわけか、投資に対して恐怖や不安を持ち、躊躇してしまう。設備投資にしても、人を雇うにしても、リスクを取らない会社は成長しません。そこを避けていながら売り上げが伸びないと言っている経営者もいますが、考え方が間違っています。長期的に見ると、例えば毎年新卒を採用するといったように、コンスタントに投資している会社のほうがうまくいっています。
もうひとつ、うまくいっている経営者に共通するのは、自分の中にきちんとしたルールを持っている点です。ルールがあると、利益が出ている時でも深追いせずにすむ。あるいは上手に損切りができる。みんながやっているからという理由で他社と同じような行動を取ることもない。そうしたルールをきちんと持ち、守ることができるかどうかです。
―― これから先の目標はなんですか。
池本 私は今年48歳になりますが、コンサルタントは57歳までと決めています。つまりあと9年です。
実は、コンサルタント会社であるパジャ・ポスとは別に、NPO法人「Are You Happy? Japan」を5年前に設立しました。上場によって大金を手にしたのですが、それを独り占めするのではなく、世の中の役に立たなければならないと考えたのです。いまコンサルタントをやっているのも、稼いだお金をNPO法人につぎ込むためです。この部分をもっともっと大きくしたい。200億円のファンドをつくれば、永続的に事業を継続できる。それを集めるのが当面の目標です。