




いまや国内販売の4割を占める軽自動車。その存在感は自動車業界の競争の枠を越え、政治、外交問題にまで影響を及ぼし始めている。
日本国内でしか売られない軽自動車は、ガラパゴス携帯ならぬ「ガラパゴス軽自動車(ガラ軽)」と揶揄されることが増えてきたが、その理由は軽自動車の規格が日本独自のものであるからにほかならない。改めて軽自動車の規格を見てみると、
・全長3400mm以下
・全幅1480mm以下
・全高2000mm以下
・排気量660cc以下
・定員4名以下
・貨物積載量350kg以下
これらのうち1つでもオーバーすれば、「登録車」の扱いになる。
日本国内で軽自動車がこれほど人気を呼ぶ理由は、自動車税や保険料の安さだ。
なかでも自動車税は、軽の場合、自家用乗用で年7200円。1000cc以下の登録車の2万9500円と比較しても、その差は歴然としている。自賠責保険についても、登録車2万4950円に対し、軽自動車は2万1970円だ。
そのほか、購入時に車庫証明が不要なこと(自治体による)、高速道路料金も割安に設定されている等々、かなり優遇されていることは間違いない。
この優遇について、海外メーカーが非難の声を上げているのだ。
国内市場の4割を占めるとはいえ、ざっくりと言えば約200万台にしかすぎない市場に、わざわざコストをかけて軽自動車を開発する欧米メーカーはない。TPP交渉のなかでも“参入障壁”としてアメリカ側からヤリ玉に挙げられ、軽自動車の規格を変えるか、優遇税制を変えるか、もしくは両方を変えるのか、政府としても何らかの対応に迫られているのが現状だ。
しかしながら、軽自動車の優遇はいまに始まったことではなく、排気量が360ccから660ccに規格改定されたのは1990年と、20年以上も前の話だ。98年に普通車と同様の安全規格を採用したことから車体の大型化が進んだが、それ以降は大きな規格変更が行われていない。なぜいま、軽自動車に矛先が向いているのか。
答えは日本市場での圧倒的な伸び率にある。
全国軽自動車協会連合会の集計によると、2013年3月末現在の世帯当たり軽四輪車の保有台数は、100世帯に51.8台となっている。2世帯に1台以上軽自動車が保有されていることになるが、実は、保有台数は1977年以降、37年連続で右肩上がりを続けている。
75年3月末の100世帯当たり保有台数は18.0台にすぎなかったが、88年に31.9台、2000年に40.8台に達し、11年には50.3台と、大台を突破した。
地域別に見ると、世帯当たり普及率が高いのは、第1位が佐賀県の100.2台で、第2位に鳥取県が100.1台でつづく。この両県については、1世帯に1台以上の軽自動車が保有されていることになる。ちなみに、佐賀県が首位に立ったのは、史上初。昨年まで27年連続で鳥取県が首位を守ってきたのだが、今年ついに、入れ替わった。
表を見ていただければわかるとおり、上位は軒並み地方部であり、都市部ほど保有率は低くなっている。全国平均の51.8台より下回っているのは東京都、神奈川県など9都道府県しかない。

「地方での軽自動車の使用状況を分析すると、1日当たりの走行距離は約10 kmほどでした。これはつまり、遠距離の移動としてではなく、生活のなかでの足として、日常的に使われていることを表しています」(ダイハツ関係者)
実際、地方ではメインに登録車を据え、セカンドカーとして軽自動車を保有するケースが多い。2世代、3世代が同居する大家族にあっては、3台目、4台目の保有も珍しい話ではなく、維持費を抑えるために、軽自動車を選択することは大いにあり得る。
都市部と違い、鉄道やバスなどの公共交通機関が発達しておらず、むしろ廃線や廃路線が増えつつあるなかで、軽自動車の存在価値は非常に高いことがうかがえる。
世帯当たり台数だけみれば、都市部の軽自動車人気が低いように思われがちだが、近年は、都市部でも軽自動車への乗り換え需要は高まっているという。
商品力も向上
都市部での人気上昇のキッカケとなったのが、11年11月にホンダが発売した「N BOX」だ。
「従来の軽自動車のマーケットは、やはり地方が中心でした。スズキ、ダイハツといったメーカーも、地方の顧客を見てクルマづくりをしてきたように思います。ところが、ホンダは従来の軽自動車づくりとは異なる視点から開発したわけです。登録車と遜色ない乗り心地と、走りを持ち込んだ。これが、従来のミニバンやコンパクトカーのユーザーの軽自動車への乗り換えに促した。地方ではいまだにスズキ、ダイハツが強く、ホンダはそこが不満のようですが、都市部でも売れる軽自動車という、かつてない商品の存在が、軽自動車業界に刺激を与えました」(自動車ジャーナリスト)
さらに、11年はダイハツが「ミライース」を発売し、軽自動車業界における燃費競争に火をつけた年でもある。9月に発売された同車は、JC08モードで30km/Lを達成した初の軽自動車。ハイブリッド技術を使わずに「軽量化・低燃費・低価格」を目指して「第3のエコカー」をコンセプトに発売されたクルマだ。
それまでの軽自動車と言えば、登録車に比べれば低燃費だが、安全性能を重視した半面、車体重量が重くなり、燃費効率という意味では1000ccクラスの登録車より劣るクルマになっていた。ハイブリッドカーの登場で、低燃費という軽自動車の個性が失われるのを危惧したダイハツ陣営が「第3のエコカー」と銘打ち、燃費性能の改善に着手、燃費競争の先鞭をつけた。
これに呼応したのが、かつての軽の盟主スズキで、「アルトエコ」をはじめダイハツに対抗する形でモデルチェンジを繰り返し、燃費競争では常に肩を並べる存在になっている。遅れてやってきた日産・三菱自動車連合の軽自動車「デイズ」「ekワゴン」も発売するや軽トールワゴンクラストップ(当時)の29.2km/Lで追撃をかけてきた。
「価格や税金といった軽自動車の従来の利点に加え、競争の激化で商品力自体が急速に上がってきています。以前は『軽なんて…』というドライバーも多かったですが、排気量の違いがあるとはいえ、性能や使い勝手が登録車と遜色ないレベルに近づいている。乗り心地や使い勝手に差がなければ、維持費の安い軽自動車に消費者が流れるのも、自然な流れだと言えます」(自動車ジャーナリスト)
この商品力向上こそが、「ガラ軽」といわれる所以だ。
日本市場でのみ通用する高性能かつ至れり尽くせりの商品開発は、グローバル基準の小型車からはかけ離れていく一方。他国メーカーからの参入がない代わりに、自分たちもグローバル展開できないという、携帯電話市場と同様のジレンマに陥っている。
最近、話題になってきたのが、軽自動車を海外展開できないかというもの。そのためには規格改正が必要で、TPPなどをからめて規格についての議論も取りざたされるようになってきている。
このまま、わずか200万台しかない軽自動車市場を国内メーカーだけで奪い合うのか、それともグローバルカーとして飛躍を遂げる展開になるのか。次頁から、「ガラ軽」の動向を検証していきたい。
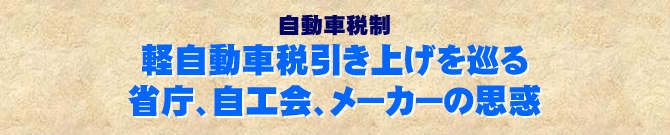
かねてから「優遇」と一部で批判の声が上がっていた軽自動車税の大幅引き上げに、総務省が本腰を入れ始めた。5月に自動車税制改正に関する有識者会議を発足させ、国交省、経産省、環境省など関係省庁の担当者を招いて議論を行っているが、一番の槍玉に上がっているのは軽自動車である。
軽自動車の自家用・乗用の税額は年間7200円だ。それに対して小型車は1000cc以下の最も安いクラスでも2万9500円と、いきなり4倍以上に跳ね上がる。それをトリガーに軽自動車の税額を上げたいというのが総務省の思惑だ。
その包囲網は綿密だ。早くから「アメリカが、税金の安い軽自動車は非関税障壁だと言っている」「地方税である自動車取得税が廃止されると税収が減るから、地方自治体が軽自動車税の引き上げを要望している」などと盛んに情報を流し、記者クラブを通じて世の中に喧伝してきた。
一方で、軽自動車ユーザーの反発をかわすために、2人乗りで、高速道路の走行はできないが税額は安いという「超小型車」を創設するという懐柔策も打ち出している。
省庁の事情に詳しいある新聞記者は、
「総務省は自動車税制全体のバランスを取りながらと言っているが、本命は軽自動車増税で、一点集中突破を狙っている」
と、内幕を説明する。
「たとえばアメリカの軽自動車批判。あれは完全に“霞が関文学”の類です。アメリカが言っているのは軽自動車に対して他の車の税金が高すぎる、軽自動車並みにしろということ。ところが役人のフィルターを通すと、軽を普通車の税金に合わせて同水準にしろというふうにすり替わる。
もちろんアメリカの自動車業界関係者は、軽自動車がなくなれば日本でアメリカ車が売れるようになるなどとは微塵も思っていない。そんな見え透いた論理のすり替えを平然とやってくるあたりに、総務省の本気度が垣間見える」
地方自治体の要望にしても、実際に確認すると、軽自動車の増税を要望しているところはほとんどない。そもそも自治体、なかでも第一級へき地を多く抱えるところは、車を保有するコストが上がれば住民の生活が破壊されることは最初から認識している。
総務省に対して求めているのは、都道府県税ではあるが6割以上が市町村に分配される自動車取得税の廃止による税収減を回避してくれということだけだが、それも軽自動車増税の根拠に利用されている。もはや増税は既定路線になっているのである。
軽自動車税の引き上げは、消費税増税にともなって段階的に廃止される自動車取得税(車を買うときに車両価格にかけられる税金)の穴埋めという名目で行われる。その取得税廃止を訴えていたのは、完成車メーカーで構成される日本自動車工業会だ。
自工会の現会長はトヨタ自動車社長の豊田章男氏。豊田氏は「消費税増税によって自動車ユーザーの負担がこれ以上大きくならないよう、車体課税の廃止を求める」と要求。それが実現するなら消費税増税を容認する、というスタンスを示したという経緯がある。
消費税は最終的に5%増えて10%となっても、税率が5ポイントの取得税を廃止することで、実質的には税額が変わらないというのが皮算用だった。
消費税アップが決まってから、消費税増税分を無視して、地方税が減るからという理由で保有にかかる税金の引き上げを突き付けてくるのは、モラルを欠いた横紙破りとも言える行為だ。しかし、自工会は軽自動車税の引き上げについて、明確な反対コメントはほとんど出していない。
「自工会は官庁以上にお役所的な組織で、自分たちが闘いの矢面に立つようなことは絶対にしません。自動車関連の税金が高いと普段から主張していますが、ただ言うだけで具体的な行動はユーザーに対してゴミみたいなパンフレットを配るようなことばかり。幹部がヘラヘラ笑って『減税要求はほぼ百戦百敗ですよ』などと話す緊張感のなさです。反対声明は正式に税制改正の骨子が発表されてからという言い訳なのでしょうが、せいぜい声明を出して終わりですよ」
自動車メーカー関係者の一人はこのように、自工会は、こと税制に関しては、もはや行政に対する有効な圧力団体とはなり得ないとあきらめ気味だ。
軽自動車主体のメーカーにとって、軽自動車税の大幅引き上げは死活問題だ。現在、軽自動車は新車販売の4割を占める人気商品となっているが、それはひとえに税金の安さによるものだ。
車体が小さくて運転しやすい、燃費が良いといった商品性におけるメリットもあるが、もし普通車の1000cc車と税額が大差ないものになれば、何のために4人乗りでパワーも小さい車に我慢して乗らなければならないのかと考えるユーザーは劇的に増えるだろう。

「軽自動車増税はいじめ」発言で物議を醸した鈴木修会長。
軽離れが起きれば、致命的な打撃を被るのは軽を主力とするスズキとダイハツである。また、グローバル販売における軽の比率はそれほど高くなくとも、最近になって軽の新戦略を打ち出し、投資を重ねてきた三菱自動車=日産自動車連合や、ホンダも被害は免れない。
「税額の引き上げ幅が大きければ、ユーザーは軽から離れるでしょうが、その全部が普通車を買うわけでもない。国内市場全体でみても販売台数は大幅に減るでしょう」(前出の自動車メーカー関係者)
国内市場での販売台数で激減が避けられない軽自動車メーカーが活路を見出せるのは、海外比率を伸ばすことだ。が、そこにも問題がある。軽自動車は全幅1480ミリ、全長3400ミリと、世界的にも相当小さく、そのまま海外で売るのは難しい。スズキはインドで軽自動車サイズの車を売っているが、そのモデルは日本では何世代も前のもので、価格も劇的に安い。ある程度の付加価値をつけて売る場合、ボディを拡大し、排気量の大きなエンジンを積むなど、国内向けモデルとは別物に仕立てる必要がある。
今の軽自動車メーカーにとって、国内向けと海外向けに車を作り分けるのは難しい。世界でも特殊な“ガラパゴス規格”と言われる軽自動車のホームグラウンドである国内での販売が減れば、軽自動車のコストは上がり、下手をすると絶滅に向かいかねない。
その最悪の事態を回避するための策として、業界内から声が聞こえはじめているのが、軽規格の拡大である。車体や排気量を海外向け商品として成立する大きさまで拡大し、右ハンドルと左ハンドルを作り分けるくらいですむようにすれば、国内需要が減っても海外での販売増で穴埋めできるというものだ。
車の開発を行うエンジニアに聞くと、おしなべて軽規格が拡大するのは悪くない話という答えが返ってくる。トヨタ傘下のダイハツ工業で商品開発に関わるスタッフは言う。
「軽自動車の規格が最後に改定されたのは98年。このとき、軽自動車にも普通車と同レベルの衝突安全性確保が義務付けられ、車体は重くなった。にもかかわらず、排気量は660ccのままでした。実は660ccというスケールだと、今の軽の重さに対して排気量が小さすぎるんです。排気量は小さいほうが燃費がいいと思われがちだが、実は度を超えて小さい排気量だと、エンジンが常に無理をして燃費はかえって悪くなる。800ccくらいになれば、設計はずっと楽になるし、海外向け商品としても良い性能が出せる。軽の税額を大きく引き上げるなら、それを認めさせるように働きかけるべきです」
スズキ関係者も言う。
「今の軽自動車は、小さいボディで衝突安全性を確保するために、サイズのわりに重くできている。ボディ形状にもよりますが、たとえば全幅を1600ミリくらいにしても、重量はそうそう増えない。一方で車幅を広げれば、海外向け商品ではとくに重要なデザイン性を格段に高めることができます」
普通に考えれば、コンパクトカーの寸法を詰めてもミニマムサイズのグローバルカーは作れそうだ。が、軽自動車の寸法や排気量を拡大するほうが、日本車の優位性を前面に出しやすいという。軽自動車と普通車は同じ四輪車ではあるが、設計のノウハウはほぼ別物だからだ。
「軽自動車メーカーはユーザーの厳しい要求に応えるため、限られた寸法の中にどれだけ効率よく車の部品を置いて機能を充実させられるか必死に工夫してきました。その結果、今の軽自動車は室内の横幅こそ狭いですが、たった全長3400ミリしかないのに室内は普通車と変わらないくらい広々としている。その寸法を拡大すれば、小さい車は狭いと思い込んでいる海外のユーザーをびっくりさせられるような商品を作れる。社長の鈴木が『軽自動車は芸術品』と言っていますが、実際そうだと自分たちも思います」(前出のスズキ関係者)
増税に揺れる軽自動車メーカーにとって、最後の砦となりそうなのは、ベーシックカーとしてグローバルに受け入れられるよう、規格を拡大することだろう。
しかし、自工会がそういった要望をきちんと取りまとめ、政府に働きかけていけるかどうかということになると、自動車業界関係者は一様に悲観的な見方を示す。当時の経緯を知る自動車メーカーOBはこう語る。

豊田章男・自工会会長(トヨタ社長)はどう決着をつけるのか。
「実は98年の軽規格改定のときも、衝突安全性の確保のために車体が大きく、重くなったことに対応して排気量を800cc程度まで広げようという話があったんです。が、普通車主体のメーカーにとっては、税金の安い軽自動車の商品力が上がりすぎると普通車のコンパクトカーがますます売れなくなる。トヨタ、日産などが反対し、結局車体だけが拡大されることになったんです。
その状況は今も変わっていないでしょう。結局メーカー間で利害が完全に一致することはないので、自工会としては折衷案を取らざるをえない。普通車メーカーは軽自動車の車体が大きくなり、排気量が800ccになると、軽自動車税制がなくなって税額が同じにならない限り、自社の販売が相当の打撃を受けると考えている。そうなるくらいなら軽自動車の枠を今のままにして、増税額を抑えるという方向に行くはず」
自工会の改革をうたって会長に就任した豊田氏も、最近は無難な発言に終始している。
「最初はずいぶん張り切っていたようですが、長年培われてきたお役人体質が簡単に変わることなんかありえない。今秋の東京モーターショーの成功を勲章に、来年春までの任期を無難にこなすのがせいぜいでしょう」(業界関係者)
今や、業界団体としての存在意義も薄れつつあるとも言われる自工会。軽自動車の税制、規格について、有効な解決策を世間に提示できるのか、まさしく叡智が試されている。
(ジャーナリスト・杉田 稔)
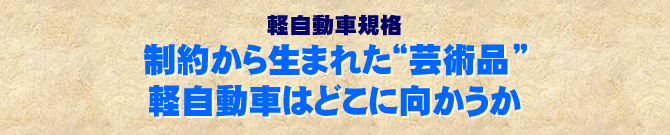
「国内にとどめておいてはもったいない」
三菱自動車の益子修社長は6月の軽自動車「ek」の発表会見で、このように話していた。ここまでの特集で語られている通り、軽自動車は日本国内だけの独自規格。生産も販売も国内に絞って行われている。この小型車開発の技術は、新興国戦略車等に活かされているものの、軽自動車そのものを海外で展開することはできていない。
現在、新興国などで見られるエントリーカーとしての小型車は、概ね800~1000ccクラスのエンジンが用いられている。日本の軽自動車は660ccしかなく、そのままでは明らかなパワー不足で敬遠されてしまうだろう。先進国ならまだしも、新興国は本来想定された乗車人数や積載量を無視して利用されることが多く、4人乗り、積載量350kgを前提にした軽自動車では受け入れられないと思われる。
また、近年の軽自動車は、キーフリーシステムやUVカットガラス、衝突回避支援ブレーキが装備されることも珍しくなくなったが、このようなハイテク技術は、海外、特に新興国ではさほど求められてはいない。至れり尽くせりのクルマは日本人が好むだけで、新興国のエントリーカーとして考えた時には不要の
装備があまりにも多くなっている。「ガラ軽」と呼ばれる理由の一つだ。
しかしながら、前述したように、軽自動車を生産する技術は、新興国向けの小型車に活用することは十分可能だ。スズキの鈴木修会長が「一定の制約の下で挑戦したからこそ、技術力は向上した。技術屋から見たら、軽自動車は芸術品だ」と語るように、軽量かつコンパクト、低燃費のクルマを低価格でつくりあげる技術は、欧米メーカーにマネのできる芸当ではない。
では、せっかくの高い技術力を、どうグローバル戦略に活かせばよいのだろうか。そこでいま議論を呼んでいるのが、軽自動車規格の改定だ。増税による軽自動車離れの救済処置として、より柔軟性の高い規格を取り入れ、海外展開をしやすくしようというものだ。実現するかはともかく、日本メーカーの可能性を開くという意味でも興味深い話ではある。
ここで少し軽自動車の規格の変遷についてふり返ってみよう。
もともと「軽自動車」という名称が生まれたのは戦後、1949年のことだ。この当時、規格としては存在していたものの対象となるクルマはほとんどなく、オート三輪などがあった程度。毎年のように規格が変わるなど、法整備も安定せず、普及にはほど遠い状況だった。
軽自動車が具体的な形となって現れたのは、55年に起こった「国民車構想」をめぐる論議からだった。

国民車の代名詞となった「スバル360」。
その前年、道路交通取締法の改正で軽自動車の規格が全長3000mm、全幅1300mm、全高2000mm、排気量360cc以下に統一され、この規格に沿って、55年10月に鈴木自動車工業(現スズキ)が「スズライトSF」を発売したのが日本初の本格的軽自動車だとされている。国民車構想そのものは具体化しなかったが、58年3月に富士重工業から発売された「スバル・360」がこの構想を満足させるものとして、その後の軽自動車に大きな影響を与えている。
59年にスズキが「スズライトTL」、60年東洋工業(現マツダ)が「R360クーペ」、62年三菱重工が「ミニカ」、66年ダイハツが「フェロー」、67年ホンダが「N360」を、といった具合に各メーカーが軽自動車のヒット車を連発するようになったことで、一気にその地位が確立されていった。
大きな規格改定が行われたのは、76年のことだ。75年、76年と排出ガス規制が成立し、これに伴い全長が3200mmに、全幅が1400mmに、エンジンの排気量が550ccに引き上げられている。この規格下で発売されたのが、79年スズキ「アルト」、80年ダイハツ「ミラ」で、現在までその名を残している。
その後、軽貨物車を中心に幾度かの排出ガス規制を経て90年に全長3300mm、排気量は660ccに改定された。この規格の下では、スズキ「ワゴンR」、ダイハツ「ムーヴ」といった、室内空間が広いデザインへと変貌を始めた。
最後に規格改定が行われたのは98年のこと。普通車と同じ安全基準を軽自動車にも採用するために、全長3400mm、全幅1480mmへと大型化された。この改定以後、マツダ、富士重工が軽の自社生産から撤退、日産、トヨタがOEM供給により参入するなど、目まぐるしく業界が動いていく。現在、軽自動車を発売しているのは、トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱自、富士重工、スズキ、ダイハツの8社だが、実際に生産しているのはスズキ、ダイハツ、ホンダ、三菱自の4社のみとなっている。
近年、新たな枠組みで道路運送車両法に加えられそうなのが、「超小型車」の存在だ。超小型モビリティとも呼ばれるが、言ってみれば軽自動車と二輪車の中間的な存在。東京モーターショーなどで各メーカーからお披露目されている2人乗りの小さなモビリティのことだ。イメージとしては、ピザ屋の屋根付き配達用バイクが4輪になったと思えばわかりやすいかもしれない。
実際、今年1月に国土交通省から超小型モビリティの認定制度について発表され、車両の詳しい規格などが公表されている。すでに発表された各メーカーのモビリティを見ると、多くが電気自動車(EV)として開発が進められている。トヨタ「コムス」、日産「ニューモビリティコンセプト」、ホンダ「マイクロコミュータープロトタイプ」は、いずれもEVだ。

93年に発売された初代「ワゴンR」。
超小型モビリティが市場として成り立つのはしばらく先になりそうだが、本格化すれば期待が大きい市場なだけに、四輪だけでなく二輪メーカーも含めて参入を検討している企業は多い。
しかし、ここで問題になってくるのが、その規格だ。国土交通省のガイドラインによると、超小型モビリティは軽自動車の規格に組み込まれている。排気量が「定格出力8kW以下」「内燃機関の場合は125cc以下」、乗車定員も「2人」となっているところが軽自動車とは異なるが、サイズなどは軽自動車の規格内、ナンバープレートも「黄色」の扱いになるという。これには各メーカーも落胆の色を隠せない。
というのも、軽自動車自体がガラパゴス化しているにもかかわらず、世界の超小型モビリティ市場を一切無視した車両区分に当てはめようとしているからだ。
「軽自動車の税制見直しに大きく絡んでいると思われます。現行の軽自動車を増税する一方で、超小型モビリティを現在の軽自動車と同じ税額にすることで、自動車メーカーのガス抜きをしようとしているのかもしれません」(自動車ジャーナリスト)
日産・ルノー連合のように欧州規格の「L7」に合わせた超小型モビリティの開発を同時に進めているケースもあるが、日本の規格とグローバル規格にズレが生じた場合、それぞれにクルマを開発しなければならず、この超小型モビリティさえガラパゴス化する可能性もある。国土交通省が規格の正式決定をするのは16年の予定だが、世界に目を向けた判断を望みたいところだ。
競争が優れた商品を生む
話を軽自動車のグローバル化に戻すと、新興国向けのエントリーカーとして考えた時に、大きな課題となるのが排気量だろう。実際、スズキはインドで、アルトに800ccのエンジンを積み、ワゴンRに1000ccのエンジンを積んでヒットさせている。

超小型モビリティは新たな市場をつくりだせるか。日産「PIVO3」とゴーン社長。
軽自動車は大型化が進み、ワゴンRで重量が約800kg、N BOXに至っては約1000kgに達する。この重量をわずか660ccのエンジンが動かすのだから、燃費は悪くなって当然、加速も悪くて当たり前の話だ。こんな状況で25~30km/Lという燃費なのだから、軽自動車の技術者には恐れ入る。
逆に言えば、800ccのエンジンを積むことで燃費性能は向上し、加速に対する不満が解消され、坂道の快適さも実現される。特に暑いASEAN地域などはクーラーが必須。グローバルで快適な走りを求めるためにも、排気量アップは最低限の課題だろう。
加えて全幅の拡大も求められる。少子化、核家族化が進みきった日本とは違い、新興国は多人数でクルマに乗るケースが多いことから、国内的には4人乗りの規格を残すとしても、快適に5人乗りができる広さは欲しい。
問題は、国内でこの規格にした場合、1000ccクラスの小型車との差がなくなってしまうことだが、軽自動車メーカーの関係者はこう指摘する。
「過去の歴史を見ても、軽自動車の人気が高まったあとは、登録車が盛り返して販売台数を伸ばしてきたものです。波線のようにお互いにいい時と悪い時を繰り返してきた。それが、これだけ軽自動車に偏って売れ続けることは、いまだかつてなかったことです。収束が起きないということは、リッターカーの商品力が上がってきていないということではないでしょうか。1000ccに乗りたいクルマがあれば、ユーザーは軽自動車なんて見向きもせずにそれを買うと思いますよ」
軽自動車メーカーの開発者たちは、厳しい制約の中で技術を磨き、商品力の向上を図ってきた。一方で、かつてはコンパクトカーブームという時期があっただけに、小型車の開発陣に甘えはなかったか。
軽の規格を変更し、小型車に近づけることで、互いの商品力が高まるのであれば、消費者にとってはありがたい話だ。
自工会会長でもあるトヨタの豊田章男社長が口癖のように言う「ワクワクするようなクルマづくり」のために、あえて軽自動車と小型車を競争させることを提案したい。
(本誌・児玉智浩)
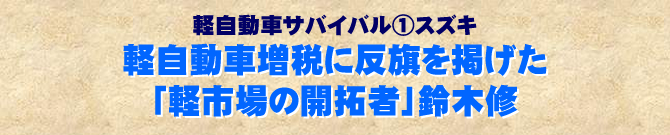
「これは弱いものいじめ。弱者救済ではない」「九州や四国では道は狭く、通勤や商売、運搬とあらゆるところで、軽自動車は使われています。軽は住む人たちにとって、なくてはならない存在なのです」「軽のユーザーに年収1500万円以上の人はほとんどいません。所得の少ない方々が、生活や仕事のために利用しているのです」

軽自動車増税論に強く反発する鈴木修・スズキ社長。
スズキの鈴木修会長兼社長は、訴え続けていた。強烈に。
軽自動車の増税論が総務省から浮上していることに対し、断固とした態度で批判を繰り返した。鈴木修自身がインドから帰国した翌日の8月29日、都内で開かれた軽トラック「キャリイ」の発表会場での出来事だった。
これまでも、繰り返されてきたシーンである。
軽自動車が否定されたとき、軽自動車を守ろうと鈴木修は軽自動車の魅力、そして存在意義をとことん説いていくのだ。
ある時には厳しく、ある時にはユーモアいっぱいに。
今年4月、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)交渉に絡み「普通車の自動車税よりも低い軽自動車税は不公平」と米国が言っているという指摘があった。このときにはすかさず、「軽自動車をやりたいのなら、自分でつくればいい。つくるなとは、誰も言っていません。不公平でも何でもない。もし、つくれないのなら、スズキはいつでもOEM(相手先ブランドの生産)でつくってさし上げます」とやり返した。最後の行では、会見会場には笑いがあふれた。
今回の軽自動車増税論は、5月末から総務省で始まった「自動車関係税制のあり方に関する検討会」(会長は神野直彦・東大名誉教授)で浮上したもの。同会では今、自動車税と軽自動車税の格差をどうするかなど、自動車関係の地方税のあり方を包括的に議論している最中である。
今年1月にまとまった今年度の与党税制大綱において、消費税が10%となった段階で自動車取得税の廃止が盛り込まれている。確定ではないものの、消費税10%は2015年10月となる見通しである。
自動車取得税とは普通車や軽自動車の取得時にかかる税だ。
総務省サイドにとってややアンラッキーだったのは、廃止される自動車取得税の「穴埋め(代替財源)」として軽自動車税が大幅増税されると、8月下旬から大きく報じられたことだろう。つまり、最初から自動車取得税の廃止と軽自動車税の増税がワンセットであると広く認知されてしまった点だ。基本的には「あり方」に関する検討だったのが、「穴埋め」のための検討のように思われてしまった。
しかも「(軽自動車税に関して)まだ、何も決まっていない」(総務省幹部)状況なのに、インドから帰国したばかりで新聞報道だけを見た鈴木修をいきなり刺激してしまったのである。“巨人”は動き出し、キャリイ発表当日の反撃となった。
8月の国内新車販売全体に占める軽自動車の比率は約41%。
鈴木修は「41%が標的にされた。弱いのはユーザーだけではなく、41%を占める軽自動車の部品メーカーも同じ。普通車のサプライヤー(納入業者)と比べ軽自動車の部品メーカーは中小企業が多いから。増税されると大きな影響を被るのです」「消費税増税は日本の将来を考えればやむなし。しかし、自動車取得税の廃止に伴い、財源を軽自動車税の増税で穴埋めしようなど仕組みがなってない。残念というより本当に悲しい」と続ける。
ちなみに、所得税や酒税など国税は財務省が所管するが、自動車税など地方税は総務省が所管する。
自動車取得税は都道府県税だが、納付額の66・5%は市町村に交付されるのが特徴だ。13年度の税収見通しは1900億円。
軽自動車税は同じ地方税でも市町村税。税収見通しは1852億円。計算上は、2倍にすると失われる分をほぼ補填できる。
なお、排気量が1000ccを超え1500cc以下の普通車の自動車税は年間3万4500円(月に直すと2875円)。自動車税は都道府県税。
軽自動車の排気量は660cc以下であり、軽自動車税は年7200円(月600円)。都道府県に登録する普通車のナンバープレートは白色。市区町村に届け出する軽自動車のそれは、黄色である。
軽自動車はエンジンの大きさだけではない。サイズは全長3400ミリ以下、全幅1480ミリ以下、高さ2000ミリ以下であり、定員は4人以下、最大積載量は350キロ以下と規格が決まっている。これらを一つでも超えると、普通車(登録車)となる。
軽自動車は日本だけの規格だ。現在、軽を生産・販売しているのは、スズキ、ダイハツ工業、ホンダ、三菱自動車工業の4社。
トヨタはダイハツから、日産は三菱自工とスズキから、マツダはスズキから、富士重工業はダイハツから、それぞれOEMで供給を受けて、いまや8社すべてが軽自動車を販売している。また、日産と三菱自工は軽自動車の開発で協業関係にある。
軽自動車の増税議論について、ホンダ首脳は言う。
「軽自動車の税率は国際的にみて平均的な水準。軽が安いのではなく、登録車にかかる税金が高すぎる」
これが、8社すべてが軽自動車を扱っている自動車業界においての、標準的な考え方である。
鈴木修は1930年1月生まれ。世界の自動車メーカーのなかでは、最高齢の経営者だ。冬は雪深い岐阜県下呂町(現在は下呂市)の出身。
「農家の四男坊でして、私の旧姓は松田」(鈴木修)と、講演冒頭の自己紹介でよくこう話し聴衆から笑いをとる。子供時代は、腕白のガキ大将だったそうだが、いまも基本部分は変わらない。
旧制中学の途中で宝塚市の海軍航空隊に志願して入隊する。文武両道に通じていたため甲種飛行予科練習生となる。ちなみに、甲飛は予科練の最上位だったが、海軍特別攻撃隊(特攻隊)への道を選択し、一度は国防に身を捧げる決意をする。あるとき、淡路島への移動を命じられ、修少年は無事に渡れたが、仲間が乗ったもう1艘が魚雷で撃沈されてしまう。「本当は私が乗るかもしなかったんだよ。志をもっていたのに、みんな海の藻屑になってしまった」と、ずいぶん前に筆者に話してくれたことがあった。
戦後は大学の教育学部を卒業し、東京世田谷区で小学校の教員となる。教壇に立ちながら、当時は神田にあった中央大学法学部に学ぶ。中大卒業後は中央相互銀行に入行。銀行員時代、スズキ第2代社長の鈴木俊三に見出され婿養子となる。
スズキに入社したのは58年だった。実は58年は、軽自動車税が創設された年である。54年に自転車税と荷車税が統合してできた自転車荷車税が、軽自動車税となった。さらに、経済産業省(当時は通産省)がもっていた「国民車構想」に合致する最初の国民車となる軽自動車「スバル360」が、富士重工から発売されたのも58年だった。
入社した鈴木修は当初、企画室に配属された。ところが、地に足がついていないスタッフの仕事を嫌い「現場に行かせてくれ」と社長に願い出て、工程管理課に異動する。
本社の中枢である企画室と対立する関係となった鈴木修は、入社3年目の61年1月に新工場の建設責任者となる。責任者に仕立てたのは企画室のトップである専務。鈴木修の失脚を狙っていたとも見られる。
その新工場は豊川工場(愛知県)。無茶な工期だったが、鈴木修は現場に張り付き、61年9月に予定通り完成させる。予算は3億円だったが、2億7000万円で建設し3000万円を企画室に突っ返したそうだ。
「豊川工場建設で、修は自信をつけた。経営者、鈴木修の原点とは工場にある」
同期入社であり元社長だった戸田昌夫(故人)は、生前このように話していた。
豊川工場で生産したのが軽トラックの「スズライトキャリイ」(2サイクル360cc)。これが初代キャリイであり、今年8月に発表したキャリイは11代目を数える。つまり、鈴木修は軽自動車の発展とともに、歩んできた経営者なのだ。
鈴木修が第4代社長に就任したのは78年。48歳だった。このときは、第3代社長が病気で倒れたため、専務から緊急登板する。ただし、75年からの国の排ガス規制により、スズキの経営は厳しさを増していたから。“ノーアウト満塁”のような波乱の登板だった。
他社がみな4サイクルエンジンを搭載していたのに、スズキはずっと2サイクルエンジン車の専業メーカーだった。このため、HC(炭化水素)で国の排ガス規制への対応ができなかったのだ。しかも、規制をクリアーする新エンジンの開発に失敗してしまう。社長になっていなかった鈴木修は当時の豊田英二トヨタ自工社長に頭を下げて、トヨタからダイハツ製4サイクルの軽自動車エンジンを供与してもらう。「潰れるんじゃ、しかたない」と豊田英二は言ったそうだ。
この一方、排ガス規制や第2次オイルショックが発生していく時期、監督官庁である通産省(現在の経済産業省)や運輸省(現在の国土交通省)など霞が関、さらに永田町を鈴木修は積極的に動く。ここで人脈を得て、「若い経営者が孤軍奮闘してるから」と鈴木修の応援団が増えていったのだ。
79年5月には軽自動車「アルト」を発売する。当時の軽自動車は60万円台が中心だったなか、アルトは全国統一価格の47万円としてヒットさせる。第2次オイルショックを受けた後のこの頃、通産省は都市内交通に適した「コミュニティーカー構想」を打ち出していた。これは「小さい車で低燃費」なコミュニティーカーを想定していて、まさにアルトがピッタリだった。通産省の考え方と連動してアルトをタイミングよく出せたことで、スズキも軽自動車そのものも飛躍していく。
アルトはその後、インドに導入される。800ccのエンジンを積み、「マルチ800」という名前で売り出され、実質的なインドの国民車に成長していった。
軽自動車の反対派には「そもそも軽はガラパゴス。日本市場にしかない規格」という指摘がある。
この点を、鈴木修はキャリイの会見会場で次のように話した。

インドで生産する「マルチ」は国民車となった。
「スズキはインドで毎月8万台の自動車を販売しているが、うち3万台は軽自動車と同じ部品、車体を使っている。例えばワゴンRのボディーに1000ccのエンジンを積んでいるのです。インドは暑い国であり、ユーザーはみな冷房を強力に使っているため、エンジンは大きい。日本の軽自動車で培った技術は、インドで生かされていますが、これからはインドネシアやタイ、ベトナムでも、軽のボディーを使った新車の開発も考えている。軽はアジアのエコカーになりつつあるのですよ」
昨年夏に筆者が単独インタビューしたときにも、鈴木修は力説していた。
「身体の大きい欧米人とは違い、小さな身体のアジアの人たちには、日本の軽自動車が向いています。軽は経済が発展して自動車の需要が急拡大するアジアの新興市場で通用する、究極のエコカーなのです。日本のワゴンRに投入した環境技術のエネチャージも、インドなどアジアにいずれ広げていきます」
もう一つ加えるなら、「軽自動車はEV(電気自動車)に向いています。長距離走行の必要はなく、ボディも軽くて小さいから」(日産首脳)。石油が枯渇していくなかで、少ない電力で走行できるEVを開発していくのに、軽自動車を維持しておくのは必須である。
軽自動車税(乗用・自家用)の標準税率の推移をみると、58年が年間1500円で始まり、61年に3000円、65年に4500円へと増税された。
その後は76年に5900円、79年6500円、84年に現在の7200円となる。つまり、昭和50年代に3度ばかり増税されたが、76年だけが排ガス規制への対応からエンジンやボディーが大きくなる規格改定に伴う増税だった。
そもそも自動車税は「財産税」(財産の所有に対して担保力を認めて課す租税)であるため、「道路損傷負担金」として増税された面はあった。昭和50年代は景気も上向いて自動車および軽自動車が急速に普及し、道路などインフラ整備を推進する必要にも迫られていた。
そして、ほぼ30年前の84年を最後に軽自動車税は、変わっていないのだ。ちなみに、自動車税も2000cc以下の普通車に限れば、やはり84年から変わっていない。
軽をもたなかった日産やトヨタは、かつて軽不要論を主張していた。軽の最後の規格改定は98年だったが、特にトヨタからの圧力は強かった。安全面からボディーは大きくなったものの、排気量は660ccのまま従前と変わらなかったため、トヨタ「ヴィッツ」や日産「マーチ」などと比べて、軽は燃費性能で劣ってしまったのだ。
「ガソリンをたくさん使う車が、なぜ税金が安いのか」「諸外国と同じに排気量に応じた税制にすべきでは」などと、反対派から批判が続出した。
しかし、それからほぼ15年が経過したいま、技術革新が進み当時と同じ規格でありながらリッター30キロを超える軽自動車が、ダイハツやスズキから相次いで誕生してきた。
「軽は規格が決められているため、逆に開発力はアップできる。技術者は妥協を許されない分、創意工夫していくためです」(軽メーカーの技術者)。創意工夫で生まれた新技術は、やがては海を渡っていく形である。
さて、総務省から浮上している30年ぶりの増税議論だが、検討会は10月までには意見をとりまとめるという。
これにもとづき総務省は自民党税制調査会(野田毅会長)に、軽自動車増税要求を提出していくだろう。自民党税調の幹部会は野田会長のほか、高村正彦、町村信孝、額賀福志郎、宮沢洋一がメンバー。
この5人が各省庁や自民党の部会などが提出する要求項目に、〇(受け入れ)、×(却下)、△(検討して後日報告)、〇政(政策的課題として検討)など印をつける。こうして“電話帳”と呼ばれる分厚い冊子が作成され与党間で合意して(税制改正大綱)、年末までには税制改正作業を終える。
総務省は今回、“〇政狙い”と見られる。軽自動車の税制改正は実現すれば30年ぶりであり、時代が違いすぎて前例は役には立たない。
ビール類は頻繁に増税されてきたが、「増税により消費が落ち込み、税収が減るケースが多い」(ビール会社幹部)。責任は、政治家が選挙により問われることとなる。
かつて自民党税調会長を務めた相沢英之は、筆者に次のように語ったことがある。
「選挙に落ちても仕方ないんだ。国のために、税制改正は誰かがやらなければならないから」
自民党税調の5人の幹部には、旧自治省出身者はいない。また、来年と再来年に迫っている消費税引き上げ自体がこれからどうなっていくのかが、自動車取得税廃止と絡んでいくことになる。
一方、軽自動車税増税を阻止しようとする鈴木修は、徹底して世論を味方につけていくことだろう。戦う相手は以前のトヨタや日産ではなく、今度は国となる。が、本来は消費者であり有権者の支持をどこまで得られるかがポイントだ。
仮に増税となれば、最も影響を受けるのは軽の比率が高いダイハツ、すなわちトヨタだ。また、全国にある自動車整備などの業販店も厳しい状況となろう。
鈴木修は再び訴える。
「地方によっては、軽自動車がなければ、生活できないし働けない」「東北の復興にも、軽は活躍しているのですよ」
(文中敬称略 ジャーナリスト・永井隆)
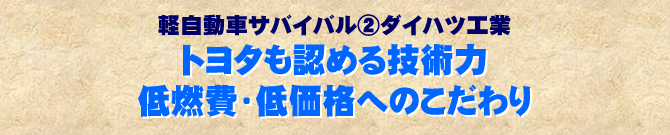
いま国内の自動車業界で、もっとも熱い戦いが繰り広げられているのが軽自動車。8月の新車販売ランキングを見ても、ベスト10のうち、実に7車種を占めている。うち3車種がダイハツ車だ。
軽自動車市場で7年連続シェアトップに君臨しているダイハツだが、近年はライバル・スズキに加え、ホンダが本腰を入れて軽自動車に参入、日産・三菱自連合も初の共同開発という肝いりの新車を投入したことで、かつてないほど競争が激化している。
今年1~8月の軽自動車販売のシェアをみると、トップがダイハツ(31.4%)、2位がスズキ(29.6%)、3位がホンダ(19.5%)と、ダイハツは首位を堅持しているものの、12年度の33.1%、11年度の35.7%と比較するとかなりシェアを落としていることがわかる。しかし、ダイハツ自体は販売台数を右肩上がりで伸ばし続けており、軽自動車総体が登録車から顧客を奪っていると言えるだろう。
軽自動車業界の競争は、他の業界で多く見られる単なる値下げ競争ではなく、他社との差別化、商品力強化によって行われている部分が大きい。それ故、総体として競争力が高まり、登録車の小型車と比較しても遜色ない、もしくは車種によっては上回るレベルにまで達している。登録車からの乗り換えが進んでいるというのもうなずける話だ。
こうした軽自動車業界の商品力競争の引き金を引いたのが、ダイハツだった。
2004年から08年にかけて、原油価格が大幅に高騰した。リーマン・ショックによる景気減速もあって、世の中のクルマへの関心はもっぱら燃費に絞られるようになる。必然的に燃費を売りにしたハイブリッド車(HV)が脚光を浴び、トヨタ「プリウス」、ホンダ「インサイト」などHV専用車が台頭。政府のエコカー減税や補助金の効果もあって、ラインナップにHVを加えなければ見向きもされない時代に突入する。
このような風潮に危機感を抱いたのがダイハツだった。低燃費が売り文句の一つだった軽自動車が、HVの台頭によってストロングポイントを消されてしまった。いかに競争力を高めるかが喫緊の課題として浮上したのである。
09年の東京モーターショーでダイハツが出品したのが「イース」だった。10・15モードで30km/L(JC08モードなら約27km/L)と、当時、ノーマルエンジンで世界最高の燃費を達成させた。ただ、軽自動車でHV並みの燃費を実現させたことで注目はされたものの、そのままで市販すると価格が130万円ほどになってしまう。HVの低価格化が進んでいたこともあり、これでは勝負にならない。
そこでダイハツが打ち出したのが、JC08モードでの30km/Lを達成しつつ、価格はHVの半分以下、80万円程度に抑えたクルマづくりを目指すことだった。しかも通常の新車開発なら3年かかるところを1年半に短縮させ、11年秋には発売させるという挑戦だった。
ダイハツはこの「ミライース」の開発にあたり、従来とはまったく異なる開発チームを結成。部署間の壁を取り払い、指揮系統を一本化させてスピードアップを図る。単純に燃費性能と言うと、エンジンを思い浮かべがちだが、その達成には車体の軽量化や空力など総合的に取り組まなければならず、部署間の連絡に手間取れば作業は進まない。チームとして一体となって取り組むことで、従来にはなかったクルマづくりが可能になった。
11年9月に行われた「ミライース」の新車発表会では「30km/L、79.5万円」と、低燃費、低価格を実現して見せた。このクルマに使われた低燃費技術は「e:sテクノロジー」として、「ムーヴ」をはじめ他の車種にも展開し、「第3のエコカー」としての軽自動車の存在を決定づけた。
ミライースはその後も改良を重ね、今年8月には33.4km/Lまで燃費を伸ばし、さらに廉価グレードでは74.5万円と低価格化も一段と押し進めている。
6月に就任した三井正則社長は「いまや低燃費・低価格はお客様にとって当たり前。この流れを作ったダイハツが、『第3のエコカー』を定着させたと自負している。今後も燃費技術を磨いて先頭を走る」と、さらなる燃費性能の向上を宣言している。
ミライースの開発効果は、軽自動車だけにとどまらない。
ダイハツは昨年10月にインドネシア新工場カラワンアッセンブリー プラントを稼働させている。この工場では9月9日に発売した小型車トヨタ「アギア」、ダイハツ「アイラ」を生産する。ダイハツがトヨタに対してアギアをOEM供給することになるが、ベースとなるアイラは軽自動車に採用してきた「e:sテクノロジー」を活用したクルマだ。

「今後も燃費技術を磨いて先頭を走る」と三井正則社長。
インドネシア政府が発表した低価格・環境対応車(ローコスト・グリーンカー=LCGC)政策に対応するため、トヨタがダイハツの持つ低価格・低燃費技術をインドネシア向け小型車に活用させたわけだが、これがダイハツにとって新境地を開くことになった。
アイラは1000ccのエンジンを搭載した小型車で、価格は7610万~9750万ルピア(約66万~85万円)。LCGC政策はその名のとおり低燃費だけでなく低価格でなければならず、トヨタの進めてきたHV戦略では高額になってしまう。そこでダイハツの培ってきた低価格のノウハウが活かされることになった。軽自動車の技術が小型車にも通用することが、このクルマの開発で証明されたわけだ。
「値段を上げずに燃費を向上させるには、細かい積み重ねが必要になります。アイラはインドネシアでつくった、インドネシアのためのクルマですが、日本の軽のモノづくりがつまっている」(ダイハツ関係者)
こうなってくると、軽自動車そのものを規格変更し、アジア等新興国に展開できるクルマにすれば、高い競争力を発揮できそうなものだ。しかし、ダイハツはあえて規格変更を肯定しない。
「軽自動車は、国内市場向けですから、多くの部品も国内で作られたものを使用しています。そのぶん部品のクオリティも高いわけです。その意味では、軽自動車業界は国内のモノづくりに大きく貢献していると言えるでしょう。軽自動車は国内工場だから現在のクオリティで作れるのであって、海外の工場ではつくれません。モノづくりの総合力は国内工場を上回ることはできません。
仮に規格がグローバル対応した時に、現在のモノづくりが維持できるでしょうか。国内から輸出すると、必然的に価格が上がり、勝負できませんから、現地調達・現地生産を進めることになります。
なかには海外で軽自動車を生産して日本にも持ち込むメーカーも出てくると思います。そのようなクルマが現在と同等の商品力を保てるのか。他メーカーのコンパクトカーには、グローバル戦略車としてアジアでつくり低価格化を進めて逆輸入しているクルマもありますが、明らかに商品力が落ちているから売れていません」(ダイハツ関係者)
技術的なノウハウは海外に移せても、高いレベルを求められる日本基準を移転することは難しい。軽自動車はガラパゴス化しているからこそ、日本市場で売れているという一面もあるのだろう。ただこれはトヨタグループの一員として、海外戦略はトヨタと連携しながら進めるというダイハツならではの意見でもある。経営資源を一本化できるに越したことはないというメーカーも多いはずだ。ダイハツは業界の盟主だけに、どのような対応を採るのか興味深い。
(本誌・児玉智浩)
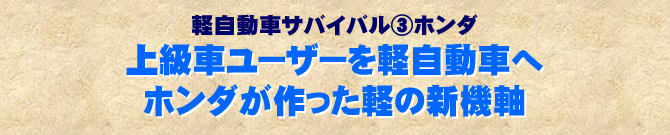
スズキ、ダイハツの2強がシェアを分けあっていた軽自動車市場は今日、ふたたび群雄割拠の時代に突入した。その風を巻き起こしたのは、ホンダである。
2011年、普通車の大型セダンも顔負けの広い後席を持つミニバン「N BOX(エヌボックス)」を発売するや、それがスマッシュヒットとなり、月間販売台数で軽トップを取る月が続いた。12年には背高型のセダンモデル「N ONE」を発売。これも可愛いスタイリングや居住性の良さ、快適性の高さなどが人気を呼び、月販1万台前後というヒット作となった。
ホンダが軽に本腰を入れた理由は、国内市場において大型車から小型車への乗り換え、すなわちダウンサイジングのニーズが高まっていることへの対応だ。
大きな車から小さな車に乗り換えるといえば、経済的に逼迫しているようなイメージがあるが、近年ではさにあらず。快適性やパワー、そして所有する満足感を得られるような演出のある車なら、小さいほうが運転も楽で燃料消費も少なくてすむという、きわめて合理的な理由で乗り換えるユーザーが増えているのだ。これは欧州市場にもみられる傾向で、中高年層を中心に、経済力がありながらミドルクラスからコンパクトに乗り換えるダウンサイズユーザーが急増しているという。
ホンダが四輪車に参入したのは今からちょうど50年前の1963年だが、市販車第1号車は軽トラックの「T360」。その次に発売したのは普通車のオープンカー「S500」だったが、これも本来は軽自動車として設計されたもの。しかし、「軽でスポーツというのは好ましくない」と考える行政の壁に阻まれ、やむなく当時の軽自動車枠である360ccをオーバーする500ccエンジンを積んだモデルになったという逸話がある。
その後もホンダはハッチバックモデルの「N360」、若者向けの「ホンダZ」、ボンネットにスペアタイヤをつけたユニークなスタイリングの「バモス」、またバブル期にはエンジンをボンネットではなく運転席の後ろに置いたオープンスポーツ「ビート」など、個性的な軽モデルを次々に送り出した。ホンダにとって軽自動車は、F1に並ぶ技術・商品の源流のようなものなのだ。
その軽自動車にホンダは新しい役割を与えた。それがダウンサイジングユーザーの受け皿だ。利便性や合理性を求めて小さい車を求めるユーザーを、コンパクトカーを飛び越えて軽自動車に引き入れることも、車の作り次第では十分可能ではないかと考えたのだ。
先に述べたN BOX、N ONEの2モデルは、従来の軽モデルのような“庶民の足”とは、やや違ったカラーを持っている。
たとえばN ONEの外観や内装。ボンネットにこれまでの軽自動車にはあまりなかった豊かな抑揚がつけられ、また往年の名車N360をモチーフにしたという丸目の前照灯や角型の尾灯の中は、高級車や輸入車で最近流行っている、イルミネーションによるデザインの遊びが盛り込まれた。
インテリアも、普通の軽自動車のような機能一点張りではなく、昔懐かしい切り立ったダッシュボードの形状とされるなど、これまた輸入車のようなお洒落な演出が加えられている。その遊び感覚は、ホンダの上級モデルでもあまり見られないもので、N ONEを、より個性的なものにしている。
N BOXのほうは、広大で静かな空間という快適性が最大の売りだ。車内に乗り込むと、とくに後席の足下空間の広さが際立っていることがわかる。背もたれを少し倒し、足を組んでくつろいだ姿勢を取っても、前席との間にはなお広々としたスペースが残る。しかも静粛性はきわめて高い。居住感だけを比べれば、コンパクトカーはおろか、ミドルクラスセダンも負けるほどである。
自動車に詳しいジャーナリストの井元康一郎氏は、夏にN ONEで東京と鹿児島の間を、一般道主体で往復した。総走行距離はなんと3200キロほどに達したが、その性能の高さに驚かされたという。
「最初は軽自動車で超ロングドライブというのは無謀かなとも思ったのですが、実際に乗ってみると、5時間休みなしで運転しても腰が痛くなったりといった身体的ストレスがほとんどなかった。大型車も含め、日本車では珍しいことです。もちろん軽自動車ですから車幅が狭く、サスペンションの能力の限界も低い。普通ならそれが軽自動車と見切って作るところですが、ホンダはその軽自動車の限界による大小の揺れを、シートで巧みに吸収するという手法でクリアしたんですね。ダウンサイジングユーザーの多くは内外装のデザインに引きつけられて買うのでしょうが、使ってみて、大型車と同じように長距離を旅することができることに気づくでしょう。ホンダの技術イメージを上げる格好の材料といえます」
N BOXとN ONEは、ライバルに比べてかなり高めの値付けがなされており、グレードによってはホンダのコンパクトカーと比べてもむしろ高価という“下剋上”が起こっている。にもかかわらず、個性的なキャラクターと高い機能性によってダウンサイジングユーザーを取り込むことに成功した。
上級車のユーザーを軽へという、軽自動車メーカーがこれまであまり考えなかったニッチ戦略は、今のところ成功していると言っていい。
もっとも、ホンダの軽戦略が今後もパワフルなものでいられるかどうかは未知数だ。前出の井元氏は、
「N BOX、N ONEとも、きわめてキャラクター性の強いモデルですが、そういう乾坤一擲のクルマづくりを続けることは簡単ではありませんし、販売数をさらに増やすには、従来からの軽自動車ユーザーが買う低価格モデルなども必要です。ホンダの関係者はそのモデルも年内に発売すると言っていますが、それらはN BOX、N ONEと違って、スズキやダイハツが絶対的な強さを持っている領域で、これまでもホンダはその壁に散々跳ね返されてきた。新型車でどういう戦いをするかで、軽市場におけるホンダの立ち位置が固まるでしょう」
と、軽市場におけるホンダの攻勢の成否はまだ確定していないと語る。

軌道に乗りつつある軽戦略だが、伊東孝紳社長は早くも見直しを迫られるかもしれない。
ホンダの懸念材料はそれだけではない。他メーカーと同様、軽自動車の増税論議が本格化していることにはやきもきさせられている。大幅増税となれば、せっかく上手くいきはじめたホンダの軽戦略に、いきなり水をさされる格好となりかねないからだ。
「ホンダにとって幸運なのは、N BOX、N ONEというプレミアム系のモデルを攻めの起点に持ってきたこと。もちろん税金が安いということはこの2モデルにとって大事なことですが、他の軽自動車に比べると増税されても買う理由が残りやすい」(井元氏)
とはいえ、ホンダは新世代の軽モデルのためのエンジンやボディなど、開発費のかかる基本部分を新造したばかりで、増税で失速するようなことになれば多大な影響を被ることは避けられない。今の軽自動車を基本に、新興国向けに幅を広げたモデルを開発するなど、開発費や設備投資を吸収するための対策が早急に求められるところだ。
ホンダにとって国内販売の救世主となった軽自動車が、ホンダをこれからも躍進させるのか、それとも足かせになるのか。経営判断によってどっちにも転がりかねない、まさに今が分水嶺と言えるだろう。
(ジャーナリスト・杉田 稔)
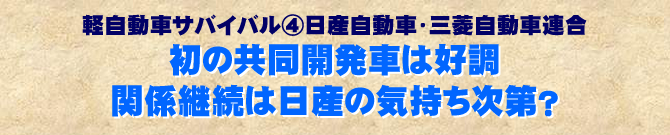
今年6月に発売された日産「デイズ」、三菱自「ek」は、両社が折半出資した軽自動車の企画・開発会社NMKVで企画が進められたクルマだ。自動車メーカーが国内でジョイントベンチャーを組むのは初めての試み。どんなクルマが飛び出してくるのか、大いに期待されていた。
実際に6月に登場したクルマは、いかにも軽自動車らしい軽自動車という印象。ホンダが「N BOX」を出した時のような斬新さはなく、その意味では期待倒れだったと言えなくもない。ただ、燃費性能には重きを置いており、発表当時はクラストップの29.2km/L(1カ月後にスズキが「ワゴンR」で30.0m/Lにモデルチェンジ)を達成。軽自動車の王道のクルマだけに、日産・三菱の販売力をもってすれば大外れはないとの見方が有力だった。
8月末までの販売台数を見ると、両社とも販売前に1万2000台もの受注を抱えていたこともあり、好調な滑り出しをみせている。デイズは3万5788台、ekも3万1598台(旧型含)を販売し、両社で7万台近い成果を挙げた。合算すればN BOXやダイハツ「ムーヴ」に匹敵するヒット車種になっている。
特にデイズは月別ランキングでも上位に入る健闘を見せ、月販目標の8000台を大きく上回るペースで推移。日産は月別の軽自動車市場でのシェアが10%前後にまで上昇してきている。ここまでの動きを見る限り、両社の共同開発は成功だったと言えるのではないだろうか。
一方で、9月2日、三菱自動車が軽商用車の開発生産から年度内に撤退すると報じられた。これによって三菱自は軽について日産との共同開発に一本化することになり、単独での開発を打ち切ることになる。軽商用車については、日産は三菱自からOEM供給を受けていたが、これによって、日産、三菱自ともにスズキから軽商用車のOEMを受けることになった。
ここで気になるのは、NMKVに対する両社の温度差だ。

三菱自が軽自動車の開発をNMKVに一本化するのに対し、日産はスズキからのOEM車「モコ」を存続させ、「デイズ」と共存させる方針を示している。軽商用車の調達も三菱自からスズキに移ったことで、日産とスズキの関係もより深まることは確実だ。
14年初頭に共同開発車第2弾となるスーパーハイトワゴン(日産「ルークス」、三菱「トッポ」の後継車)が発売されることは決まっているものの、それ以後の発売計画は明らかになっていない。一部報道では第3弾として三菱「パジェロミニ」の後継車が企画されているとあったが、日産側からは具体的な明言がないのが現状だ。
日産にしてみれば、一極集中によるリスク回避も視野に入れつつ、軽自動車の戦略を組み立てているのだろうが、三菱自はNMKVへの依存を高めているように見える。
日産と三菱自の大きな違いは、その企業文化にある。現在の日産の強みは、現場と経営陣の意思疎通のスピードが極めて高いことにある。何か議題があれば、クロスファンクショナルチームが各部門を横断して課題解決に取り組み、その声はエグゼクティブコミッティに届けられる。CEO、COOの決断を仰ぐまでに階層は少ない。
対して三菱自は、現場の状況が経営トップに伝わるまでに時間がかかる、もしくは伝わらない可能性すらある。過去のリコール問題が大型車の三菱ふそうトラックバス、昨年末の軽自動車、今年のSUVなど、異なる開発部門で起きていることからも、横軸の連携が取れていないことがわかる。三菱自の意思決定の遅さ、横軸の連携の不備は致命的。日産にとって組みやすい相手ではないのは明らかだ。
デイズの滑り出しが順調だったことで、当面の協力関係は続くだろうが、仮に軽の規格改定などが行われれば、決して安泰とは言えない。日産にとってグローバルカーをわざわざ共同開発する理由もないからだ。
三菱自は、組むメリットを日産にアピールするしかなく、今後のプロジェクトはすべて失敗が許されない状況がつづきそうだ。


柴田 裕 キーコーヒー社長
しばた・ゆたか 1964年、神奈川県生まれ。87年慶応大学経済学部卒業後、木村コーヒー店(現・キーコーヒー)入社。第一営業部などを経て、2000年常務、01年専務、02年から現職。今年、同社のフラッグシップコーヒーの「トアルコトラジャ」(インドネシアの直営農園で育てている豆)発売から35周年の節目を迎えた。
コーヒー市場争奪戦が過熱してきた。遡ると、1996年にスターバックスコーヒーが日本に上陸した後、タリーズコーヒーなど外資系チェーンが増えてカフェ事情が一変し、「コーヒー戦争」と呼ばれた。近年でも、大手コンビニが淹れたての「100円コーヒー」で攻勢をかけ、競争は激しさを増している。
加えて、ネスレ日本では9月から“インスタントコーヒー”という呼称を“レギュラーソリュブルコーヒー”に変更、価格面のみならず品質競争にも拍車がかかる。そこで、東京五輪開催の2020年に創業100周年となる老舗キーコーヒーの創業家社長、柴田裕氏に、同社の差別化、勝ち残り策などを聞いた。
―― 一口にコーヒー市場といっても、外食、コンビニ、カフェ、缶コーヒー、家庭用など様々ですが、いずれにしても競争自体は激化してきています。老舗のキーコーヒーとしては、どう勝ち残りに挑みますか。
柴田 企業はヒト、モノ、カネと言いますが、プラス、情報とブランドだと思うんですね。で、当社がこれまで少し弱かったのは、ブランドのところだと思っています。
もちろん、老舗ということでご存じの方もたくさんいらっしゃるんですけど、若い時にキーコーヒーに出会わなかった人には、コーヒーと言えば、外資系のコーヒーチェーンで紙コップで買う商品というイメージも強いですから。
店の看板に、キーコーヒーのロゴを掲げている喫茶店なら馴染みもあると思いますが、喫茶形態のみならず、ほかの商品も含めてもっともっとブランドを認知していただくことが重要です。コーヒー会社がたくさんある中で、「ほかの企業も知っているけど、一番美味しいのはキーコーヒーだね」とか、「ギフトで一番喜ばれるのはキーコーヒーだろうな」と、お客様からそんなふうに評価される会社でありたいですね。
―― キーコーヒーには、昔からのファンというコアな人が多いのでは。
柴田 今年3月に増資をしまして、個人株主が3万人から3万5000人に増えたんですけど、確かにそういうコアな株主が増えたと思います。5000人増えたこともあって、今年の株主総会では初めて出席者が1000人を超え、1200人の方が総会に来られました。ありがたいことです。当社の株は100株から買っていただけますが、300株からは、“株主限定ブレンド”という優待品もご用意しています。
もう少し、そのコアなファンのボリュームを増やしたいですし、当社の認知度は、たとえば九州全域と沖縄では割と強いんですが、中国、四国、近畿エリアなどでやや弱い。これは、現地への進出のタイミングが遅かったか早かったかが大きいと思います。
―― 業績的には前期(13年3月期)から増益に転じました。
柴田 前々期(12年3月期)は純損失を出してしまいました。当時、コーヒー豆の相場が上がったため、商品の値上げをさせていただいたんですが、11年の3月初めに値上げを発表して、直後の11日に東日本大震災が起こってしまった。あの混乱のさなかでしたから、値上げ実施はしばらく先送りせざるを得ず、それで利益が増えなかったのです。
―― 現在はコーヒー豆の相場も落ち着いてきていると思いますが、最近は円安がやや逆風ですね。
柴田 円安は、コーヒー豆だけでなく輸送燃料の高騰などにも関わってきますから。
当社の売上構成は、業務用で4割、家庭用が3割、原料用で3割あって、原料用というのは、缶コーヒーの会社にコーヒー原料を買っていただくビジネスです(JTの「ルーツ」ほか、ビールメーカー系飲料会社など取引先は広範囲)。
事業構成比的には、これまでこの「4・3・3」できたのですが、最近はクロスオーバーしてきています。ですから、当社でもこれは業務用、あれは家庭用とか、あまりカテゴリーごとに考え過ぎてはいけない。たとえば、コンビニの店頭で淹れたてコーヒーを買うという行動は、外食、中食、家庭用のどれにもあてはまりますしね。
あまり安穏としていてはいけないですが、日本でコーヒー市場が伸びてきた過程では、これまでもいろんなトレンドがありました。1960年代から70年代は喫茶店ブームでしたし、80年代からファストフードが出てきて、90年代に外資系コーヒーチェーン、2000年代からはイタリアンブームがあって、さらにコーヒー市場が伸びています。そして最近はコンビニコーヒーと。
そういう積み重ねが、コーヒーの消費全体には貢献していると思いますし、コンビニコーヒーの影響も、我々以上にファストフードやコーヒーチェーンのほうが大きいでしょう。要は、お客様が利用シーンによって使い分けていくのではないかと。
―― コーヒーマーケット自体は、規模感的にはどのくらいですか。
柴田 何を基準にするかですけど、当社のシェアでだいたい15%ぐらいと言われています。売上規模で言えば500億円強ですから、残り85%が2500億~3000億円の間ぐらいというところですかね。
―― キーコーヒーとしては、中長期的に売上規模をどのくらいまで拡大する計画ですか。
柴田 ここのところ、当社は資本業務提携などが続き、いまもその手のお話はいろいろあります。ただ、しばらくはいまのガバナンスに注力していきたいですね。この規模で株式上場しているコーヒー会社はありませんので、なんとか勝ち抜いていきたいと思います。
―― 確かに、05年にイタリアントマトを子会社化し、昨年はアマンドを子会社化、さらに今年、銀座ルノアール(ジャスダック市場上場)と資本業務提携を結ぶなど、アライアンスが加速してきました。
柴田 イタリアントマトの時は当時、ナムコさんが(イタトマの)親会社だったんですが、ナムコさんがバンダイさんと経営統合するにあたって、イタトマを引き受けてほしいと言われましてね。
イタトマは当社が手を挙げないと、ある居酒屋チェーンに買われそうになっていました。それなら親和性がより高い、当社に任せたほうがいいというご判断も働いたようです。当社の子会社になって、イタトマ当時よりもライトな「カフェジュニア」という業態にしましたので、地方のショッピングセンターなどにも出店がしやすくなりましたね。いま、フランチャイズで300店舗ぐらいになっています。

新業態「キーズカフェ」の外観パース。
アマンドについては個人的にも昔からよく使っていて、お取引としてのお付き合いも、もう50年ぐらいになりますが、先方の経営者が、「会社が厳しくなって何かあったら、キーコーヒーに頼みなさい」とおっしゃっていたようです。店舗数も、一時期は相当多かったんですが、立ち行かない店も少なくなかったのでかなり閉めていただきました。まだその過程にあり、不採算のところを整備していく必要があります。
3つめの銀座ルノワールは優良投資先の1つで、何か一緒にやろうという話し合いを続けてきました。あちらも株式公開会社ですので、ある程度の規模感があって、組むのだったら大きな外食企業よりもキーコーヒーがいいとおっしゃっていただいた。で、「喫茶室ルノアール」は東京23区内に100店舗(自社物件店舗、賃借店舗といろいろだが、ほとんどが直営店)もありますから、そういうアドバンテージも利用していければ、と。
―― その3業態の海外展開はどうでしょう。
柴田 イタリアントマトでは、すでに少しずつ海外で出店し始めていますけど、ほかの業態も海外で引き合いがあります。特にアジアを中心に、日本の外食産業はとても人気があって、喫茶業態も結構、人気があるようです。こういった市場も狙っていきたいですね。新興国の大都市では、ちょっと価格が高めの商品でも、中流層の拡大でだいぶ消費が活発になってきていますから。
―― 同業のUCCがUCCホールディングスと持ち株会社形態にしていますが、アライアンスが活発になってきたキーコーヒーでも持ち株会社化は検討しているのでしょうか。
柴田 方向性の1つとして検討はしていますが、現段階ではどういう形がいいかわからないですね。
―― 買収や資本参加だけでなく、キーコーヒー自身も「キーズカフェ」という新業態を始めています。
柴田 とはいえ、これは別会社を作ってやっているものではありません。いま、デパ地下中心にコーヒー豆の挽き売りの売り場が72ヵ所あるんですが、これは直営店と言えなくもない。一方で、キーズカフェというのは、キーコーヒーのブランドを上手に活用したいという方に向けてご提案している小型店業態で、いまのところ、高速道路のサービスエリアとか病院などでの立地が多くなっています。もう1つ、キーズカフェの特徴は、フランチャイズと直営の中間業態とでもいうべきもので、お取引先サポートの傾向が強いこと。
―― サポートとは?
柴田 たとえばその土地で人気のパスタレストランのオーナーに、店近くの病院や公共施設にも何か出店してほしいという声が地元からあったとします。そこで、パスタレストランの業態のままではちょっと重たいので、もう少し軽いカフェ業態なら出せるという時に、我々のご提案が活きてくるんです。
―― 多面的な展開で売り上げを伸ばしていこうということですか。
柴田 もちろん、個々の事業のセールスで売り上げを作っていくことも大事ですが、売り上げ自体はどこかのPB(プライベート・ブランド)を受託するなど、作ろうと思えば作れるんです。あるいは破格の条件を出して、コーヒー飲料の原料を受注しても売り上げは伸びるんですけど、それだと利益が伸びませんし、何よりキーコーヒーという存在感が希薄化してしまいます。
ですから、そういう事業もやりつつ、そのボリュームはある程度のところでとどめないといけない。キーコーヒーのものだから買ってもらえるという商品、あるいはご来店いただける業態を開発し続けることが大事です。当社には、氷温熟成コーヒーという独自技術の商品もありますし。
―― 最後に今後の重点課題を。
柴田 ブランド磨きに尽きますね。昔は、コーヒー会社といえば当社かUCCさんかと言われていたんですが、いまは外資系チェーンを挙げる方もいますし、コーヒーで想起される企業として、もう少し憧れのブランドにしていきたいと思います。そのために、商品と業態の両方を磨いていく。
日本は今後、ますます人口減少と高齢社会が加速するわけですが、当社に関しては、成熟されたシニア層の方のほうに比較的認知度が高いので、あまり大きくは心配していません。ともあれ、コーヒーでちょっと贅沢をという時、キーコーヒーを選んでいただける、あるいはすぐに思い浮かべていただけるようにしたいですね。
(聞き手=本誌編集委員・河野圭祐)


松田佳紀 ヤマダ・エスバイエルホーム社長
まつだ・よしのり 1960年11月9日生まれ。和歌山県出身。79年和歌山北高校卒業。同年上新電機入社。2004年営業本部販売促進部長に就任。06年同社退社。07年ぷれっそHD社長のほか、マツヤデンキ、サトームセン、星電社の社長に就任。12年ヤマダ電機に入社し、取締役兼執行役員副社長。今年3月エス・バイ・エルに転じ社長代行、5月28日から現職。趣味はスポーツ観戦。
日本で100以上のゴルフ場を保有するのは、アコーディア・ゴルフとPGMホールディングスの2社のみだ。このうちの1社、PGM社長の神田有宏氏は、かつてアコーディアの取締役を務めていていたばかりか、その古巣にTOBをかけたため、業界は大騒ぎに。その真意はどこにあったのか。
〔全国で125のゴルフ場を運営するPGMホールディングスは、8月8日、2013年度6月中間決算を発表した。それによると、売上高は前年同期比101.4%増の361億円、営業利益は同47.8%増の42億円となった。一昨年の東日本大震災で落ち込んだ来場者数が伸びたことが増収増益の要因となっている。
PGMを牽引するのが神田有宏社長で、昨年1月に就任した。PGMは、もともと米ファンドのローンスターによって設立されたが、昨年、ローンスターは持ち株をパチンコ機器メーカーの平和に売却。それに伴い社長として送り込まれたのが神田有宏氏だ。その前職が、PGM最大のライバルであるアコーディア・ゴルフ取締役とあって、移籍当初は、業界内で大きな話題となった。それから1年8カ月――〕
社長に就任して以来、あまりお客様の目に触れない部分の改革を進めてきました。新しい予約システムや基幹システムの導入を終え、新会計システムも今年中に導入を終えます。このシステムによって収集・分析したデータを活かすことで、次のステップに進むことができる。その前段階まで来ています。ゴルフ場の価値というとまず思い浮かぶのが不動産としての価値ですが、これからは顧客をどう活かすかが、ゴルフ場の価値となる。システムを変えたことでそれができるようになったし、その効果はこれから出てきます。
こうした部分においては、就任して以来、思ったように進んでいますが、その一方で、不満なところもあります。一例を挙げれば、所属するゴルフ場に対する本社のサポートがまだまだ不十分です。
年々メンバーの高齢化が進んでいます。彼らは暑い夏や寒い冬にはプレーをしなくなる。そのことがわかっていながら現場ではどうしたらいいかわからない。だとしたら、高齢者に優しいゴルフ場の運営を本社が教えてあげなければいけません。たとえば、これまでは禁止していたカートのフェアウエーへの乗り入れを認めるとか、ヤーデージの表示をわかりやすくするとか、さまざまなことが考えられます。メンバーが1年でも長くゴルフをやってもらうために何ができるか、会社ぐるみでサポートする。そういう点ではまだまだ物足りない。
〔ゴルフ場にとって頭の痛いのが、プレー料金が下げ止まらないことだ。そのため、多少来場者が伸びたとしても、売り上げはなかなか伸びないというジレンマに陥っている〕
この夏のことですが、平日ランチ付き、しかもゴルフボール1ダースがついて4000円という料金を設定したゴルフ場もあります。これはゴルフ場としての料金はないに等しい価格です。ここまで極端でなくても、関東のゴルフ場では平日ランチ付きで5000円台が珍しくありません。
〔PGMは中間決算発表と同時に16年度を最終年度とする中期経営計画も発表した。そこでも、プレー料金の上昇が見込めないことを前提にしており、その中で業績を維持・向上できる体制を目指す〕
単価が下がるぶん、それをどうやってコストを削減してまかなっていくかが勝負です。ただそれだけでは企業として成長することはできません。そこで年間10コースのM&Aを行っていこうと考えています。条件は、キャッシュフローが出ていて今後も集客が見込めるコースです。となると、どうしても首都圏のコースが中心にならざるを得ません。
〔このM&Aを支えるのは、資金調達力だ。PGMの場合、平和が筆頭株主のため、その信用をバックに資金調達をすることが可能だ。一方、ライバルのアコーディアはというと、11年まで筆頭株主だったゴールドマン・サックス(GS)がエグジットしたため、強力なスポンサーがいない。しかも9割配当を行っているため、内部留保もままならず、新規M&Aは容易ではない。現状では、アコーディアの運営ゴルフ場のほうがPGMより若干多いが、早晩逆転するのは確実だ〕
M&Aだけではありません。コースを磨くにも、ローコストオペレーションを導入するにも、お金はかかります。クラブハウスひとつとってもそう。多くのゴルフ場のクラブハウスが老朽化しています。その大半が、預託金をあてにして建てられた、豪華だけれど効率の悪いものです。これを建て替えて、光熱費を下げ、動線を考えたレイアウトにすると、著しく効率を上げることができます。ところがそうするにはキャッシュが必要です。それが調達できないために、多くのゴルフ場がだましだましクラブハウスを使っている。でもそういうところが、将来、大きな差となって表れるのです。
〔PGMの中計には、「3年間で圧倒的優位性を保つ盤石な基盤を築く」との一文が盛り込まれている。ゴルフ場経営はどこも苦しい。でもここを乗り切れば、次の展望が開けると神田氏は考えている〕
いまの単価では、死のゲームを行っているようなものですから、この3年の間に淘汰が進み、いずれ需給バランスが取れるようになる。そこを生き残ることができれば、M&A物件も出てくるようになる。つまり新しいステージが見えてくるのです。ですから16年を迎えた時の当社の姿をぜひ見てほしいですね。
〔神田氏は1963年生まれの50歳。慶応大学商学部を卒業し、最初に就職したのは東海銀行(現三菱東京UFJ銀行)。転機となったのが91年にロサンゼルス支店への異動だった。神田氏はここで6年以上も勤務する〕

ハンディは7、ベストスコアは69の腕前だ。
91年というと日本でバブルが崩壊した年ですが、アメリカでは日本より一足早く不況が訪れていました。私は不動産案件のプロジェクトファイナンスに従事したのですが、実際に行ったのは不良資産の回収です。いまドラマの『半沢直樹』が人気を集めていますが、あれと似たようなことを私はたくさんやってきています。しかも1ロットあたり10億円と非常に大きいものばかりで、処理するのは大変でした。
アメリカの場合、州によって法律が違いますから、回収方法も州によって異なっている。そういうことに習熟している人材はなかなかいません。一種の職人のようなものです。そのために長く勤めることになったのかもしれません。
〔このあと97年に東海銀行を去り、メリルリンチ証券に入社、さらには99年にゴールドマン・サックスへと転じる〕
東海銀行では不良資産の処分を担当していましたが、その売り先のひとつがメリルリンチでした。メリルリンチにしてみれば、私は日本の銀行の悩みを知っている。そこでスカウトされたようです。当初はニューヨークで債権を買う業務に携わるはずだったのですが、その頃、日本で不良債権処理が加速していました。そこで帰国して、不良資産、不動産購入を手がけたのですが、いいトレードが何件かできた。それで業界内で名前が売れて、今度はGSに引っ張られ、移籍しました。
〔ここで神田氏は企業再生ビジネスに携わる。その一環としてゴルフ場の再生を手がけ、経営破綻に陥った日東興業を買収、それを中心としたアコーディア・ゴルフの創業メンバーとなった。以降アコーディア・ゴルフはPGMとともに日本のゴルフ場再生ビジネスをリードしていく。神田氏はその功績が認められてGSのマネージングディレクターという経営層への昇格を果たした。しかし2008年、神田氏はGSを退社する〕
ゴルフ場は、日本の不良債権処理の最後の案件でした。日東興業は当初、和議申請をし、のちに民事再生法を申請してGSがスポンサーになったのですが、当初から、これはビジネスになると考えました。実際アコーディア・ゴルフはいくつものゴルフ場を買収・再生し、日本一のコースを所有する会社となり、06年には上場を果たしています。
08年にGSを退社したのは、そろそろ10年になろうとしたからです。それを一区切りとして、もう一度自分を見つめなおそうと考えました。GSを辞めると同時に、アコーディアも辞めるつもりでした。ところが当時、アコーディアの株価が冴えない。その原因に、IRを知っている人が社内にいないことがあった。市場とどう対話していいかわからない。そこでしばらくの間、私がIR担当役員を務めることになったのです。
GSは11年1月、所有していたアコーディア株を売却します。私はそもそもGSから派遣されていた役員ですから、GSとの縁がなくなったあとも役員に残るのは筋が通らない。そこでアコーディア取締役を退任することに決めました。昨年5月のことです。
〔それから半年後、神田氏はPGMの社長交代会見の壇上にいた。この経緯を神田氏が語る前に、少し、状況を説明しておく必要がある。前述のようにPGMの社長交代は、ローンスターの所有するPGM株を、平和が取得したことに伴うものだ。その一方、アコーディアの大株主にオリンピアというパチスロメーカーがある。オリンピアは形の上では平和の子会社だが、オリンピアの創業者である石原昌幸氏は平和の筆頭株主でもある。つまり石原氏は、アコーディアの大株主であると同時に、PGMの筆頭株主という構図である。当然、石原氏と神田氏は面識があった〕
アコーディアを辞めたあとは、しばらくプータローとして過ごすつもりでした。ぶらぶらしながら、自分が本当に何をしたいのか自分自身に聞きたかった。自由の身になって、おそらくあと20年近くある自分の人生を見直すいい機会だと考えたのです。毎日ジョギングをしたり、1人でハワイへ行ったり、自由気ままな毎日を送っていました。
そんな生活を送っている時に、オリンピアのオーナーから電話がありました。内容は、PGMを買うことになりそうだ。ついては社長を引き受けてほしいというものでした。私は、もしそんなことを知ったら世間が騒ぐと伝えたのですが、適任者は神田しかいない、買収決定後、可及的すみやかに発表するから真面目に考えろと言われ、決断しました。
オーナーからは、日本一のゴルフ場にしたいと。アコーディアに比べると数字のうえでは劣るところがあるけれど、これをもっと磨いてくれと言われました。その段階で、統合というプロセスがあるならサポートするとも言っていただきました。
〔その言葉どおり、神田氏は今年1月、アコーディアに対しTOBを仕掛けて大きな話題になった。冒頭から何度も記しているように、ゴルフ場ビジネスの最大の問題は単価の下落なのだが、それを招いたのは、PGM、アコーディア両ライバルの値引き合戦にある。お互い競い合うことで単価を下げ、自分たちの首を絞めている。それを解決するには両社が統合するのがいちばんだと神田氏は考えた〕
私はアコーディアのこともよく知っているから、友好的に統合できるものだと考えていました。お互い歴史も似たようなものだし、メリットも共通している。このまま価格競争を繰り広げていたのでは、ゴルフ場業界全体を苦しめてしまう。コースにお金をかけることができないため、極端な話、フェアウェイでなく目土でプレーすることになりかねない。業界全体のためにも統合すべきだと考えたのです。でもアコーディアは、なぜか経営統合を嫌がった。
〔結局このTOBは、途中で村上ファンドの流れを汲むファンド「レノ」が参入したこともあって、買い付け下限の20%に達せず失敗に終わってしまう。しかしゴルフビジネスを巡る環境は当時となんら変わっていない。それだけに神田氏はいまでも、経営統合が必要だと考えている〕
いまでも統合を申し入れた時と同じ気持ちです。ただ、自分たちから何かをしようとは、いまのところは考えていません。というのも、TOBの最中にアコーディアはレノに対して、「PGMとの経営統合交渉の場につく用意がある」との書簡を送っています。つまりボールは我々にではなく、アコーディアの側にある。彼らの考え方次第でどうにでもなるわけです。
先ほど言ったように、中期経営計画が終わる頃には、我々は頭一つ抜けた存在になっているはずです。ですから、向こうが嫌だと言っているのに、こちらから頭を下げるつもりはありません。
〔もしアコーディアが経営統合を呑んだ場合、両社合わせたゴルフ場の数は260コースを超える。これは日本にあるすべてのゴルフ場の1割以上となる。ゴルフ業界のガリバーが誕生するかどうかは、ここ3年にかかっているといっていい。
最後に、神田氏のゴルフの腕前について紹介しよう。始めたのは大学時代、ゴルフサークルに入ったのがきっかけだった〕
本格的に始めたのは社会人になってからです。特にロサンゼルス勤務時代は年に100ラウンドほどプレーしていました。現在のハンディは7。生涯ベストはアメリカのゴルフ場で出した69ですが、直近では73が最高です。
(構成=本誌編集長・関慎夫)
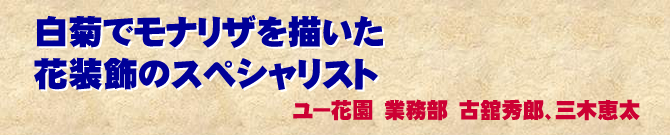
東京・世田谷区桜新町に本社を持つ花屋「ユー花園」。創業者の山田祐也会長が世田谷区下北沢に最初の店をかまえてから、すでに54年を数える老舗の花屋である。
店頭での生花販売だけではなく、葬儀用装花、ブライダル・ホテル用飾花なども手掛けている。
都内にある日航ホテル東京(お台場)、ザ・ペニンシュラ東京(日比谷)、コンラッド(東京)内に飾られている花は、すべてユー花園の手によるものだ。
しかしそれ以上に大きなボリュームを占めているのが葬儀用装花で、これを手がけることでユー花園は大きく成長した。
とはいえ最初は苦労の連続だった。葬儀社に花を提供しようと思っても、葬儀社ごとにつきあいのある花屋がいて、容易に入っていくことはできなかった。そこで創業者は、毎日のように斎場に出かけて行っては、葬儀社の人の祭壇づくりをだまって手伝っていた。そうやって顔見知りになったうえで、もう一度営業をかけることで、徐々に取引先を増やしていく。
後発だからこその工夫も欠かせなかった。従来の花屋は、斎場でジャンパーに長靴で仕事をしていた。水に濡れた花を扱うのだから当然といえば当然なのだが、ユー花園では社員にスーツとネクタイを義務付けている。葬儀社の人たちは必ずスーツ姿なのだから、花屋もスーツで仕事をするのが当然、との考えに基づくものだ。
仕事のやりかたも、従来の花屋は祭壇ができるとそこに花を運び込んで終わりだったものを、葬儀社の人と一緒に、祭壇の飾りつけから後片付けまでずっと一緒にするようにした。花のプロであるユー花園の社員が飾りつけをやったほうがきれいにできるのは当たり前。葬儀社が喜ぶだけでなく、遺族も参列者も喜ぶ。それがユー花園の仕事のやり方だった。
さらには、飾りつけにも工夫をこらし、いまでは当たり前になった青竹に生花を挿すなどの新趣向を次々と生み出していった。こうした努力によって、ユー花園を指名する葬儀社がどんどん増えていき、現在、葬儀用装花の分野において、ユー花園は日本一の売り上げを誇っている。
創意工夫は日本一になったいまでも日常的に行われている。ユー花園では、葬儀用の花の装飾においては、「元気だったあの人が微笑みかけてくれるようなステージプランニング」を心がけている。厳粛な儀式である葬儀会場を、時にはしめやかに、時には華やかに飾り上げる。ゴルフ好きだった人の葬儀には祭壇をグリーンのように装飾するなど、遺族の思いに応えるために多彩なプランニングを用意をしているのがユー花園の特徴で、少しでも故人、遺族に喜んでもらおうと、日々、新しい提案を行っている。
今年8月、東京・お台場のホテル日航東京で、ユー花園の葬儀用装花の内覧会が開かれた。この内覧会では、ユー花園が提案する新しい演出を見ることができたが、ひときわ目を引いたのが、白菊でつくられた「モナリザ」だった。

祭壇用の装花をつくる古舘秀郎氏(左)と三木恵太氏。
このモナリザをつくったのが、業務部第4課係長の古舘秀郎氏と、業務部第1課主任の三木恵太氏。古舘氏は入社13年目の32歳、三木氏は8年目の30歳だ。
2人ともユー花園に入る前は、それほど花と親しんでいたわけではない。しかし「デスクワークがいやで、現場で汗を流したい。体を動かしたかった」(三木氏)、「ものをつくることに興味があった」(古舘氏)ことから、入社以来、祭壇用装飾にたずさわり、2人とも、「生花祭壇検定S級フラワーデザイナー」の資格を持つ。
これは、ユー花園の社内検定なのだが、いちばん下のD級を取るのに3年間、以降、C、B、Aと上りつめていった最上級の資格がS級だ。
各自が、ほぼ毎日、1つの現場を担当するなど、多忙な毎日を送っている。2人とも「遺族の方に喜んでもらった時に、この仕事をやってよかったと思います」と口を揃えるが、その日々の仕事の中でも、「こうすればもっと喜んでもらえるのではないか」と考えているという。モナリザのアイデアも、そうした中から生まれてきた。
ユー花園では以前から、「文字祭壇」を提案してきた。これは2.7メートル四方(四畳半)の枠の中に、花で「愛」「響」など、故人を偲ぶのにいちばんふさわしい文字を表したもの。そして今度は人の顔を花で描こうというわけだ。
「モナリザを選んだのは、誰もがその顔を知っているため」(三木氏)というが、これまで生花によって人の顔を描くのは不可能と言われてきた。それにチャレンジしたのだ。
ホテル日航東京での内覧会で2人は、招待客の目の前でモナリザを描いた。その様子はユーチューブでも見ることができるが、所要時間3時間半という大作だった。
当日を迎えるまでの前1週間、2人は練習を重ねた。

8月に日航ホテル東京で行った白菊によるモナリザの実演。
「最初の作品はどう見てもモナリザとは似ていなかった」(三木氏)
最初は、上から何センチ、左から何センチのところに目頭、というように、細かい位置を決めたうえで描き始めたがうまくいかない。結局、ポイントだけを決めておき、あとは現場で全体を見ながら微調整したほうがうまくいくことに気づいた。1本1本の花は、同じように見えて微妙に違う。その微妙な違いによって、全体の雰囲気も違ってくる。それを現場で最適な花を選びながら置いていく。言葉にするのは簡単だが、実際には相当な苦労があったはずだ。
なかでもむずかしかったのが、目と口だ。目の印象は強烈なため、ここが違うとまるで似ない。また、「謎の微笑」の異名を取ることからもわかるように、微笑む口元が、モナリザをモナリザたらしめている。
「視線の方向や左右の大きさなどに気を使いましたね」と言うのは、目を担当した古舘氏。一方、口を担当した三木氏は「最初は、口の形を決めておいて、それに合わせて花を置こうとしたのですがうまくいかない。そこで、最初に口の部分を花で埋めておいてから、ポイントの花を抜くようにしたところ、うまくいきました」と振り返る。
最初は似ても似つかなかったモナリザだが、練習を重ねるうちにだんだん形になっていき、最後にはカメラを向けると顔認証するまでになったという。「その時はうれしかったですね」(三木氏)
内覧会の会場でも、モナリザは好評を博した。生花によって人の顔を描くという試みは大成功に終わった。
「最初はできるかどうか半信半疑でしたから、できた時には本当にうれしかったですね」(古舘氏)
「不可能といわれたものがここまでできたわけですから、むずかしいことでもやればできるという自信を持つことができました」(三木氏)
2人が語るには、モナリザを描くからといって特別な技術が必要なわけではないと言う。いつも現場で行っていることの延長線上にモナリザはある。
葬儀用の装花は、通夜の当日の午前中に本社内の作業場でつくられる。午後にはそれをいったん分解してトラックで運搬、葬儀会場でもう一度組み立てるという手順を踏む。しかし現場では、すべて予定どおりにいくわけではない。遺族から「こうしてほしい」という要望が寄せられるなど、その場で対応が求められることも多い。
「遺族の方、葬儀社の方などの要望を聞きながら、少しでもきれいになるよう心掛けています。それには現場での臨機応変な対応が必要です」(古舘氏)
前述したように、ユー花園ではフラワーディレクターをD級からS級にランク分けしている。ランクが違えば、技術、スピードなどが違うのは当然だが、現場対応力も大きく差が開くという。
モナリザを描けたのも、花の個性を考えて、最適の1本を選び、より正確にきれいに飾る技術があってこそだった。
そして、さらに技術を高めていけば、故人の肖像を花でつくれるようになるだろう。愛する人を花の肖像で送ることが、当たり前になる時代が来るかもしれない。
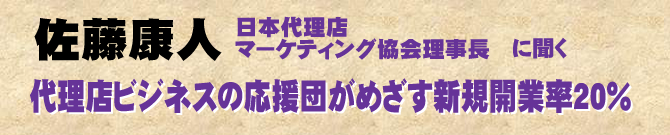

佐藤康人 日本代理店マーケティング協会理事長
さとう・やすひと 1972年生まれ、東京出身。中央大学商学部を卒業し、建設会社、営業アウトソーシング会社、外資系生命保険を経て2005年4月に独立し、プライスレス設立。当初は営業代行を行っていたが、代理店ビジネスの魅力に気づき、日本で唯一の代理店構築コンサルタントの地位を確立した。昨年1月、一般社団法人日本代理店マーケティング協会を設立、理事長に就任した。
―― 日本代理店マーケティング協会という名称は、あまり聞いたことがないのですが。
佐藤 2012年1月にできたばかりの一般社団法人です。代理店マーケティングを普及させることで、すべての事業従事者に収益向上の機会を提供し、社会に貢献しようという目的で設立しました。
―― 設立にいたる経緯を教えてください。
佐藤 それにはまず、私の経歴をお話ししたほうがいいと思います。
私は大学を卒業したあと、建設会社に就職し、総務部門で6年ほど働いたところで転職、営業アウトソーシング会社や外資系生保で営業を学び、05年4月に独立して、プライスレスという会社を立ち上げました。
当初、行っていたのは営業代行です。いろんな会社の名刺を持って、そこの営業部長として働くようになりました。ところがある日、電話があって、POSレジの代理店の開拓を行ってほしいとの依頼があったのです。そこで初めて代理店の仕組みを勉強して、こんな画期的なシステムはないと思ったのです。
いい商品をつくっても、販路がない、営業力がないがためにそれを売ることができない会社がたくさんあります。代理店を活用すれば、小さな会社でもその商品を津々浦々まで届けることができる。それでこのシステムの構築を自分のビジネスにしようと考え、日本で唯一の代理店構築コンサルタントとしての活動を始めました。
―― 代理店ビジネスというのは大昔からあります。それでも日本で唯一、だったのですか。
佐藤 ええ。それまでは代理店を募集する媒体はありました。でも私の場合、代理店募集サイトを運営するだけでなく、企業の代理店制度の構築や、営業ツールの開発、事業説明会、初期導入研修、勉強会など、代理店制度のすべてを支援することができます。おかげさまでこれまで500社以上の代理店募集や代理店制度構築を支援してきました。
―― それだけのニーズがあるということは、代理店システムの構築に苦労しているところが多いということですね。
佐藤 代理店というのは、契約さえすればすぐに営業を委託することができます。そして代理店を使う会社の経営者は、代理店契約すれば、自社商品をどんどん売ってくれると思っています。でもそこに誤解があります。
代理店を活用するには、事業説明会を開き、参加者と面接、勧誘を行い、そして契約を結びます。それぞれの段階で、ノウハウと手間が必要です。ところが、代理店を担当する社員というのは、せいぜい1人か2人ぐらいのもの。しかも、契約すればそれで終わりというわけではなく、教育もきちんとしなければなりません。
代理店をやろうという人・企業は営業力に自信がある。でも、その商品の特性や、売り方を知らないとうまく機能しない。それなのに担当者が少ないために、メーカー側はなかなかそこまで手が回らない。結局、代理店はたくさんできたけれど、売り上げは全然伸びないということになってしまいます。
―― どうやったらそれを防ぐことができるのですか。
佐藤 たとえば事業説明会で、とおりいっぺんに商品の説明をするだけでなく、売り方についても説明する。すでに代理店を使っているのであれば、その代理店ではどういうふうにして売っているのか。あるいは直販部隊があるなら、どうやっているかを説明する。もちろん契約を結んだあとの教育も大切です。そういうことに気をつければ、代理店を活用して売り上げを大きく伸ばすことが可能です。
―― プライスレスが軌道に乗ったことはわかりましたが、それがどうして協会設立へとつながるのですか。
佐藤 代理店ビジネスの素晴らしさを、できるだけ多くの人に知ってほしいと思ったからです。繰り返しになりますが、代理店を活用することで、販路がなくても、人脈がなくても、営業力がなくても、販売を伸ばしていくことができます。その一方で、代理店をつくったけれどうまくいかなかったという例もたくさんあるため、二の足を踏んでしまうところもある。その意識を変えていきたい。そのためには啓蒙していくことが必要です。
プライスレスとしても、代理店構築塾というのをつくったことがあります。ただ、こういうのを一企業でやったとしても、自らの営業活動として見られてしまうところがありました。私としては、代理店ビジネスの市場そのものを大きくしたいという思いがあります。すぐれた商品・サービスがあれば、代理店をつくれない業種はありません。そのことをまず知ってほしかった。
そこで、同じ意見を持つ仲間とともに、昨年、日本代理店マーケティング協会を設立したのです。
ここでは、すでに代理店展開を行っている企業や、これから行いたい企業に対して、セミナーやコンサルティングを行っています。さらには代理店として活躍したい企業や個人に対してもサポートしています。
これらはすでにプライスレス時代にやっていたことですが、協会をつくったことで、1社でやっていたときよりも広がるスピードが速まりました。まだ2年に満たないですが、すでに会員は500社近くにのぼっています。でも、まだまだ足りません。すべての業種で代理店ビジネスは可能なのですから、会員予備軍はいくらでもいる。できるだけ多くの力を結集して、影響力を持つようになりたいですね。
―― 会員を色分けした場合、メーカーと代理店の比率はどうなっていますか。
佐藤 いまのところ、ほとんどがメーカーです。でも最近は代理店に応募したい人や、独立を考えている人も増えています。
当協会は一つの目標を掲げています。それは「日本経済発展のために新規開業率を20%に!」というものです。
日本の新規開業率は、最近では5%を下回っています。他の先進国が10%程度であることを考えると非常に低い数字です。その結果、廃業率が開業率を上回る状態が続いていて、日本では企業の数が毎年減っています。日本経済が今後も発展していくには、新規開業企業を増やしていかなくてはなりません。
その点、代理店というのは、独立したい人にとってはいいビジネスだと思います。開業する一つの方法として、フランチャイズチェーンに加盟する方法があります。しかしFCの場合、加盟の条件も厳しく、加盟料も高い場合が多い。これではベンチャーの芽をつぶしかねない。その点、代理店の場合、そこまで条件が厳しくない。とくに営業力に自信がある人にとっては、メーカーの代理店になることで、簡単に独立・開業ができる。
ただし、そこで必要になってくるのが、どのメーカーの代理店になったらいいかということです。最初に言ったように、メーカーの中には教育まで手が回らず、まるで売り上げが伸びないということも少なくありません。これは代理店にとっても悲劇です。
私自身、そういう思いをしたことがあります。独立後、あるメーカーの代理店になり、加盟料70万円を支払ったにもかかわらず何も教えてくれずに苦労した。そんな思いをしなくてすむよう、当協会では、メーカーの見極め方についても教えています。
日本代理店マーケティング協会は走り始めたばかりです。より多くの会員を集め、いい商品・サービスを世の中に広めるお手伝いをしたいと考えています。それによって日本経済が元気になれば、設立した甲斐があったというものです。