




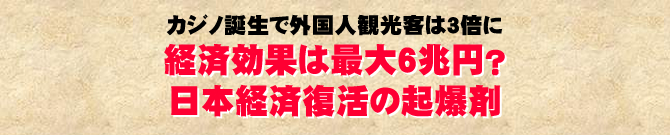
「シンガポール、あるいはマカオがカジノによって世界からたくさんの人たちを呼び込むことに成功している。私自身は(カジノ解禁は)かなりメリットもあると思っている」
3月8日の衆院予算委員会における安倍首相の答弁からもわかるように、カジノ解禁に向けての動きが加速している。
日本におけるカジノ解禁運動の歴史は1990年代半ばにまで遡る。96年、ジャーナリストの室伏哲郎氏(故人)が中心になり、カジノ合法化を目的に「カジノ学会」を設立、さまざまな啓発活動を行っていった。そのメンバーでもあった石原慎太郎氏は、99年の東京都知事選に勝利を収めると、お台場カジノ構想を発表する。
2000年代に入ると、国会議員の間でもカジノ解禁を本格的に議論しようという動きが起こり始め、02年、超党派の国会議員による「国際観光産業としてのカジノを考える議員連盟」通称カジノ議連が誕生した。
このカジノ議連は、民主党政権下の10年、「国際観光産業振興議連」として再スタートする。カジノ解禁の動きが活発になったのは、この議連誕生がきっかけだ。
ちなみに、現在はカジノ議連ではなく、IR議連という通称を使っている。IRとは、統合型リゾートの略で、カジノだけでなく、ホテル、国際会議場、商業施設などが一体になった複合リゾート施設の意味である。

世界120カ国以上で認められているカジノが、間もなく日本にも誕生する。
IR議連誕生の翌年には、IR推進法案が出来上がり、この秋にも国会に提出する運びとなっている。IR推進法は、IRの基本理念および基本方針を定めたもので、国内に最大10カ所、IR建設を認めるものとなっている。1ヵ所につき、カジノは1つという想定で、ラスベガスのような街まるごとカジノを目指すのではなく、シンガポールにある、船の形をした「マリーナ・ベイ・サンズ」(この中にカジノ、ホテルなど複合施設がすべて揃っている)を思い浮かべるとわかりやすい。
IR推進法に対しては、共産党と社民党を除くすべての党が賛意を示しており、成立への障害は少ない。そして推進法成立後2年以内にIR実施法を制定することになっており、この法案成立をもって、カジノ解禁は具体的に動き始めることになる。
なぜここにきてカジノ解禁の機運が高まったのかというと、カジノによって日本経済復活の起爆剤にしたいという思いがあるためだ。バブル崩壊後、日本経済は低迷を続けている。この間、国家財政は急速に悪化したため、財政出動による経済振興はむずかしい。そこでカジノである。
以前から、日本経済成長の1つの柱として、外国人旅行客の誘致が挙げられている。昨年、日本を訪れた外国人(インバウンド)は835万人。海外に出かけた日本人1699万人の半分以下である。インバウンドを増やし、外国人が日本でお金を落とせば、それが日本の経済成長につながるというわけだ。
もともと日本に対する外国人の関心は根強いものがある。それは今年、円安になって一気に欧米からのインバウンドが増えたことでも裏付けられる。もしここにカジノがあれば、さらに多くの外国人を呼び込むことができるのではないか、というわけだ。
この動きを、アベノミクスが加速させた。
言うまでもなく、アベノミクスは(1)大胆な金融政策(2)機動的な財政政策(3)成長戦略の3本の矢からなる。(1)と(2)に関してはすでに進行中だが、インバウンドの増加は、(3)の柱の1つに位置づけられる。今年6月には「本年に訪日外国人旅行者数1000万人を達成し、さらに2000万人の高みを目指すとともに、2030年には3000万人を超えることを目指す」という内容の、インバウンド目標を閣議決定した。
年内1000万人の目標は、円安のおかげで達成できそうな勢いだが、これを17年後に3倍にするのは容易なことではない。そこでカジノによって外国人客を誘致しようというわけだ。
身近なところにある成功例がシンガポールだ。シンガポールは日本同様、カジノを認めてこなかった国だが、2008年にカジノ解禁を決断、10年に2つのカジノがオープンした。その結果、09年に968万人だった海外からの観光客数は、10年には1160万人と一挙に20%伸び、以降11年1320万人、12年1440万人と右肩上がりで伸びている。
シンガポールではカジノ建設に先駆け、15年にインバウンド1500万人の目標を立てていたが、このままいけば、2年早く今年達成する見通しだ。
観光収入も09年には126億シンガポールドル(1シンガポールドル=76円)だったものが、昨年230億シンガポールドルと倍増した。昨年のシンガポールのGDPが約3000億シンガポールドルだから、およそ8%を観光収入で稼いでいる計算だ。ちなみに日本の昨年の国際観光収入は1400億円にすぎない。シンガポールの例にならえば、これを倍増することも夢ではない。
もちろん、観光客がカジノに落とすお金も魅力である。いま世界一のカジノタウンはマカオだが、マカオのカジノの売り上げは、年間3兆5000億円に迫ろうとしている。これはラスベガスの約5倍。しかも売り上げといっても実際には粗利、つまりお客が費やした金額からカジノ側が支払った金額を引いたものだからカジノで実際に動く金額ははるかに大きい。そしてカジノ施設の上げる利益に対してはカジノ税や法人税をかけ、勝った客に対しても税金を課すことが可能となる。税率をいくらにするかは、制度設計上の問題になるが、いずれにせよ、国や自治体の収入になることは間違いない。
海外のカジノに詳しいグローバルミックス代表の勝見博光氏によると、「どのように税金をかけるか、あるいは入場料をどのくらい取るかというのはカジノによってまちまちですが、カナダ・ケベック州のカジノなどは施設の利益の半分を税金で持って行き、それを教育や医療に充てている」という。このように、カジノにかける税金を目的税化することも可能である。
カジノ(=IR)のいいところは、国や地方自治体が関与するのは規制や周辺環境の整備のみであり、他は純粋民間資本によって行われることになりそうなことだ。
公営ギャンブルと比較してみればよくわかる。中央競馬の場合なら、農水省が管轄する特殊法人、日本中央競馬会(JRA)が主催する、いわば国営競馬である。東京競馬場や中山競馬場などの施設もJRAが建設・所有している。これが公営競馬であれば、主催は地方自治体であり、施設所有権も競馬から上がる利益もすべて自治体に入る仕組みだ。
ただしこの仕組みは両刃の剣だ。利益が上がっているうちは、その利益を独占できるが、ひとたび赤字になったら、その負担はすべてJRAや自治体にのしかかってくる。バブル崩壊後、公営ギャンブルの苦戦が続いており赤字に転落、維持できなくなって閉鎖に追い込まれた地方の競馬場は少なくない。その結果、その地域の雇用は失われる。
ところが現在、解禁に向け動き始めているカジノ=IRの場合、開発から運営まで、すべて民間に委ねられる予定だ。つまり、公共投資のように国や地方のお金を必要としない。それでいて、一時的にはIR建設でゼネコンが潤い、カジノ開業後は観光客がお金を落としていく。雇用も生まれる。しかもカジノの売り上げや利益に応じて税収を得ることもできる。国家財政や地方財政が逼迫している日本にとって、これほどありがたい話はない。

シンガポールはカジノ誕生で観光収入が倍になった。日本の目指す姿でもある。
現にシンガポールの場合は、1兆円かけてカジノを建設したものの、カジノを含むIR全体で3万5000人の直接雇用を生み、その経済効果は年間1000億円にも迫るという。
これを日本にそのままあてはめることはできないが、周辺人口の多さを勘案すると、もし東京・台場にIRができた場合、経済効果はシンガポールの2倍か3倍、あるいは5倍とも言われている。また大阪に誕生したとしても、シンガポール以上の経済効果を生むという。
経団連の試算では、IR1カ所で、需要創出効果が年間3000億円、波及効果まで含めた経済効果は6000億円にまで達するという結果が出ている。これが10カ所なら6兆円だ。ちなみに東京五輪誘致が決定した場合の経済効果は3兆円と言われているが、これは一過性のもの。IRの場合、運営を間違わなければ継続的に経済効果を発揮し続けることになる。
これだけの経済効果があるのだから、安倍首相やIR議連の人たちが、日本経済復活の起爆剤として期待するのも無理はない。
このように、カジノ解禁はいいことばかりのように思えるが、もちろんそんなに甘い話ではない。IR=統合型リゾートと名前を変えたところで、カジノがギャンブルであることに違いはない。ギャンブルであれば、当然そこには負の側面がある。
本特集では、日本の刑法で賭博を禁じておきながら(一八五条、一八六条)、カジノを設置することの是非は問わないことにする。すでに公営ギャンブルによってその条文は骨抜きにされている。カジノだけを害悪視しても始まらない。ただし、ギャンブルであるなら、そのための配慮をしなければならないのは当然のことだろう。そうでなければ、カジノ=風紀の乱れとして解禁に難色を示す人たちを納得させることはむずかしい。
冒頭から何度も述べているように、カジノ解禁の目的は、インバウンドを増やし、日本経済を活性化することにある。しかしいざ解禁してみたら、インバウンドは増えず、ギャンブル依存症になる国民が増えたというのでは本末転倒だ。
原則、自国民にカジノを開放していない韓国だが、1カ所(江原ランド)だけ、自国民でも遊べるカジノがある。しかし、そこには朝早くから「カジノホームレス」と呼ばれる人たちが開場を待ち、借金がかさんで自ら命を絶つ人も少なくないという。
カジノ解禁に際しては、そうしたギャンブル依存症の人たちをどうやってケアするかも大きな問題だ。
シンガポールの場合ではカジノを開設するにあたり、ギャンブル依存症の人たちのためのリハビリセンターがパッケージになっている。また、シンガポール人がカジノに入場するには7000円必要だ(外国人は無料)。このように自国民にはカジノの敷居を高くし、海外からの客を誘致するなど、工夫を凝らしている。
青少年対策も必要だ。「曖昧さ」を好む日本では、大人と子供の境もこれまで曖昧にしてきた。たとえば馬券を買えるのは20歳以上だが、競馬場に行けば未成年の大学生が普通に馬券を買っている。「大学生になれば大人同然」ということなのだろうが、時によっては高校生が馬券を買うのを目にすることもある。
カジノにおいてはこれは許されない。厳密な身分審査をすると同時に、もし未成年者に遊興させた場合、カジノ側に厳罰を処すなどの対策が必要になってくる。
もうひとつ、徹底しなければならないのは、反社会勢力を根絶することだ。
ラスベガスでは、マフィアが入場できないのはもちろんのこと、マフィアの親族であってもブラックリストに載せられるという。ラスベガスの歴史そのものが、マフィア排除の歴史だと言っても過言ではない。日本でもそこまで徹底して、はじめてカジノは、大人が楽しむ非日常空間になる。それができなければ、日本のカジノは失敗に終わる公算が強いだろう。
忘れてはならないのは、IRをつくれば、それでインバウンドが増えるという単純なものではないということだ。
現に、世界中のカジノには、経営不振に陥っているところも珍しくはない。隣国、韓国には17カ所のカジノがあるが、赤字経営のところも多い。東・東南アジアには、韓国、シンガポール、マカオだけでなく、ベトナムにもカンボジアにもあるし、フィリピンにも間もなく誕生する。日本のIRは、そこと競争していかなければならない。
「IRの魅力というのは、カジノの魅力だけではありません。周辺のホテルやレストラン、会議場を含め、トータルでのサービスが重要になってきます。しかもその施設だけでなく、その地区周辺の資産を最大限活用することが、必要です」(前出・勝見氏)
規模のうえではどうやってもマカオに勝てるはずがない。そうした中、マカオではなく日本のカジノで遊びたいと思わせるには、日本らしい“おもてなし”や、世界をリードする「クールジャパン」をうまく取り入れたIRの運営が不可欠だ。
IR議連では、次の国会でIR推進法案を成立させ、2020年、東京五輪(誘致に成功すればだが)に合わせる形で日本初のIRを誕生させることで、起爆剤としての効果を一層高めることを狙っている。つまりあと7年しか時間がない。
その限られた時間の中で、カジノのマイナス部分への対策と、世界から人を呼び込むだけの魅力あるIRを、どうつくっていくかが問われている。カジノ解禁は目前なのだ。
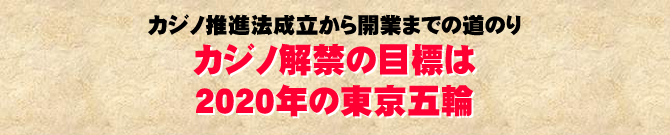
前稿でも触れたように、超党派議員連盟がまとめたカジノ推進法案が、間もなく国会に提出される予定だ。その時期は、いまのところ秋の臨時国会が有力視されている。
現在のところ、法案に反対姿勢を打ち出しているのは共産党と社民党のみ。それ以外の党は原則賛成なのだから、早ければ臨時国会中、遅くとも継続審議としたうえで次期通常国会で可決・成立する見通しだ。
いまやカジノにおいても、グローバルで客の奪い合いをしている。特にアジアの場合は、日に日に豊かになっていく中国人をどう取り込むかで、収益は大きく変わる。どうせカジノを解禁するのなら、中国はもちろん世界から人を集めないことには面白くない。そのためには、できるかぎり早くカジノ解禁に道筋をつける必要がある。
推進法の提出と成立は、日本が観光立国のスタートラインに着くことを意味する。

カジノを擬似体験する超党派の議員たち(中央は野田聖子衆議院議員)。
もちろん推進法の成立で、いきなりカジノ解禁というほど単純ではない。推進法はあくまで大枠の方向性を示すものでしかなく、2年以内にカジノ実施法を成立させる必要がある。実施法は内閣法となる見通しで、関係省庁が詳細を詰めて作成し提出するという流れとなるのだが、推進法と違って、実施法がすんなり国会を通る保証はどこにもない。
「推進法というのはいわば総論のようなものです。インバウンドを増やすためにカジノを解禁する。これに対して反対する人はほとんどいません。でも実施法は各論です。各論となると、省庁間の利害がぶつかりあう。政治的に決着をつけたとしても、国会でまた蒸し返される可能性もある。いわばTPPと一緒ですよ、日本が国際社会で生きていくためにTPPの必要性はわかっても、自分に不利益が見込まれるところは聖域を主張するようなものです」(IR議員連盟関係者)
また実施法では、実際のカジノ経営を想定して、多くのことを決めておく必要がある。ギャンブル依存症対策をどうするか。反社会的勢力とどうやって絶縁するか。未成年がカジノに入れないようにするにはどうするか。またそれを破った時にはどのような罰則を科するのか。
カジノ解禁反対の人たちは、そういったところの不備をついて反対運動を展開してくるはずだ。国会議員の間ではカジノ解禁は多数派だが、世論は必ずしもそうではない。新聞社が行っている世論調査でカジノ解禁の是非を問うと、賛成、反対は拮抗している。昨年「週刊東洋経済」が行った調査では、賛成40%、反対47%と反対が上回っている。
とくに女性の間では、ギャンブルに対する拒絶感が強く、この対応を一歩間違えると、実施法成立に支障が出る可能性もある。また、一部のマスコミがカジノ反対のキャンペーンを展開してもおかしくない。
そのため、実施法の成立が、カジノ解禁に向けての最大の山場となるはずだ。
無事にこの山を乗り越えることができても、まだまだ関門は多い。まず、どこにカジノを建設するかを決めなければならない。これもまたひと苦労だ。
詳しくは次稿に譲るが、「わが地元にカジノを誘致したい」と手を挙げている自治体は10カ所を優に超える。カジノが解禁されたとしても国内にできるカジノの数は、最初、2、3カ所でスタートして最大でも10カ所までと想定される。当然、手を挙げても選定されない自治体も出てくる。
自治体にとってカジノは打ち出の小槌だ。自分たちで資金負担をしなくても、民間業者が大規模設備投資を行ってくれる。それでいてカジノの粗利から、一定率を納付金として徴収できる。もちろんカジノができれば雇用も増える。世界から観光客がやってきて、お金を落としていく。喉から手が出るほど欲しいに違いない。
それだけに誘致に名乗りを上げる地区選出の国会議員は必死になってカジノを引っ張ってこようとするだろう。しかしここで圧力に負けたら、日本のカジノはスタートからゆがんだものとなる。インバウンドを増やし経済を活性化させるのが最大目的なのだから、どこにカジノを置いたらその目的を実現できるのか、公平・公正に選考作業を行うべきだ。しかし言うは易く行うは難しで、実際に情実を排除しようとすると様々な抵抗にあうはずだ。それでも初志貫徹できるかどうか。
この立地は、実施法成立から1年後、おそらく15年から16年の間に決まることになる。
指定を受けた地方自治体は、次に事業者の選定に入る。アメリカやアジアのカジノのほとんどは、ホテル内にカジノを併設する形をとっている。つまりホテル=カジノである。そしてカジノの運営ノウハウを日本企業は持っていない。そのため必然的に、IRのホテルはラスベガスなどで経験を積んだアメリカ資本が担うことになる。
そうなると、外国人観光客が落とした金は、アメリカ資本に持っていかれ、日本にとってのメリットは小さくなる。
最初の段階ではそれもやむを得ないが、カジノ開発認可が第2次、第3次と続く場合は、いずれは日本企業を事業者として選定すべきだろう。そのためにはノウハウの蓄積が重要で、すでに海外のカジノに参加している日本企業もあるが、エンターテインメントや会議場の運営など、学ぶことはいくらでもある。そこで、民間事業者を選定する際には、日本企業が何らかの形で最初から参加するような縛りをかける必要もあるだろう。
ここでカジノ運営ノウハウを身につけることができたら、次は海外にそのノウハウを持って出ていくことも可能になる。だからこそ、多くの企業がカジノのインサイダーになりたがっている。
事業者が決まったら、今度はその事業者がカジノの免許を申請、取得する。すでに選定段階で審査を受けているわけだから問題はない。そして免許が下りた段階で、いよいよカジノ建設に取り掛かることになる。
しかし、いま見てきた段取りをひとつずつこなしていった場合、この段階ですでに2020年頃になってしまう。これでは東京五輪に合わせてカジノ開業などできるはずもない。どんなに早くても25年というのが正直なところだろう。
間に合わせるには、実施法成立後、すべての段階を同時並行的に進めるしかない。シンガポールのIRは、わずか34カ月で完成したというが、それは地震のない国だからできたこと。地震大国日本では、このような急ピッチの建設工事は許されない。工事に4年かかるとして、20年に間に合わせようとすると、16年には工事を始めなければならない。ということは実施法制定から1年間で、立地選定、事業者選定、免許交付まで一気に行うというスケジュールとなる。拙速と言われかねない。
「ですから現実問題としては東京五輪に間に合わせるのはむずかしいと思いますよ。でも20年カジノオープンを掲げているから、目標に向かっていろんなものが動き始めた。もしそれがなかったら、いまだ推進法上程さえ先送りされていたかもしれない」(前出・IR議連関係者)
刑法で賭博を明確に禁じている日本でカジノを解禁しようというのだから、国民的議論が必要なのは言うまでもない。しかしここでもたもたしていては、カジノがオープンする頃には、すべて市場が押さえられてしまう可能性もある。さじ加減はむずかしい。
そのバランスをいかに取るかによって、日本のカジノの未来が決まる。ともかく、間もなく、カジノ推進法案は国会に上程される。本格的カジノの到来は目の前だ。
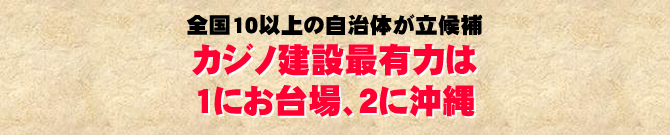
カジノ解禁が現実味を帯びるにつれ、日本各地でカジノ誘致の動きが加速している。
経済効果だけを考えれば、カジノ誘致ほど「おいしい」話はない。何しろ、IR(統合型リゾート)施設を建設するだけで、1000億円単位の投資が行われることになる。しかも開業後は1万人以上の雇用が生まれ、世界から、そして日本各地からカジノを楽しみたいという観光客がやってくる。その落とす金も1000億円単位である。自治体に入ってくるのは税金としてだが、それでも疲弊している地方経済にとってみれば、干天の慈雨以上の恵みといっていい。

夏休み、多くの人を集めるお台場。カジノができればさらに多くの人で賑わうことに。
何より大事なのが、周辺の道路整備などは別として、カジノ建設や運営に、自治体は一切お金を出さなくていいということだ。財政難の自治体にしてみれば、是が非でも誘致したいところだろう。
他稿でも触れたが、日本で最初にカジノ誘致に手を挙げたのは東京都だ。石原慎太郎氏が都知事に初当選した1999年にお台場誘致構想を発表している。その後、いったん石原氏はこの構想を取り下げるのだが、カジノ解禁の機運とともにお台場構想は復活。猪瀬直樹都知事もカジノ誘致に意欲を見せている。
東京都とほぼ同時に手を挙げたのが沖縄県だ。99年、沖縄県議会は伊良部郡下地島にカジノを誘致することを決議した。下地島は宮古島から5キロほど離れた小さな島だが、空港がある。ここに誘致しようというのである。しかしここに多くの施設を建設することはむずかしいため、沖縄本島内に変更されると予想される。基地が返還されたら、その跡地をカジノにする構想もあるようだ。
東京、沖縄がカジノに手を挙げたあとは、2002年から03年にかけて、熱海市(静岡県)、珠洲市(石川県)、鳥羽市(三重県)、堺市(大阪府)などがカジノ誘致を表明した。小泉政権下のこの時期、地域ごとに規制改革を行う目的で「構造改革特区」構想が浮上する。これに応じる形で各自治体は「カジノ特区」を申請したのだ。
熱海市は、社員旅行などのニーズが減少した結果、ピーク時の半分以下に観光客数が落ち込んでいる。これを挽回する手段として、カジノに目をつけた。カジノ計画とは別に、熱海にはF1を誘致しようという動きもあり、もし共に実現すれば、熱海は日本のモナコのような存在になる。かつて日本中から人が集まった熱海に、世界中から人が集まることになる。
鳥羽市ももともと観光で成り立ってきた都市だ。しかし人口は1970年代以降、一貫して減り続けている。また観光客数も伸び悩む。そこでカジノを誘致することで、海洋リゾート+カジノを前面に押し出していこうというわけだ。
結局、特区としてカジノが認められることはなかったが、この時に手を挙げた各都市は、いまでもカジノ誘致を諦めておらず、誘致活動を続けている。
このように特区としてカジノを申請する都市が出現した頃から、日本全国でカジノ導入を目指す地方自治体が増え始めた。03年には、「地方自治体カジノ研究会」が設立され、日本におけるカジノのあり方などが検討された。同研究会は翌年には「地方自治体カジノ協議会」に受け継がれ、また03年には珠洲市で「日本カジノ創設サミット」が開催されてもいる。
長引く不況の影響を、もっとも受けているのが地方都市だ。駅前商店街がシャッターストリートになったという話は普通のこととなった。仕事もないため若者たちは地方を棄て都会に出ていく。残されるのは高齢者ばかりで、都市はさらに疲弊していく。この悪循環を断つには、劇薬が必要だ。それがカジノだった。現在、カジノ誘致を表明、あるいは検討している自治体は、北は北海道から南は沖縄まで全国に散見される。
北海道は、情報交換会を発足させ、カジノ誘致を検討している。現在出ているプランだと、札幌駅の隣接地に、カジノホテルを建設するという。交通アクセスのよさが最大の魅力である。
05年に第3回カジノサミットを開いた秋田県からは、秋田市と合併した雄和町(現秋田市雄和)が、合併前から積極的に活動してきた。雄和は、秋田空港がある地区で、カジノを誘致することで、秋田空港を最大限有効活用することも可能になる。この地区を流れる雄物川は明治期まで水運が盛んだった。その水路を利用したカジノ建設を検討中だ。
千葉県も、森田健作知事を筆頭に、カジノ誘致に力を入れている。成田空港は日本でいちばん多く外国人観光客を迎えている空港だ。この隣接地にカジノを建設することで、来日時や離日時に遊んで行ってもらおうということだ。羽田空港の国際化が進み、成田空港は存在感が薄くなりつつあるだけに、カジノによって、再浮上したいところだ。
空港立地ということでは、中部国際空港のある愛知県常滑市も同様だ。空港は沖合の人工島にあるが、その対岸部分にカジノを誘致したいとする。
中部国際空港が開港したのは05年。当時、名古屋経済が絶好調だったこともあり、多くの利用者で賑わうと思われていたが、実際には見込みほどには伸びていない。昨年から今年にかけて、ガルーダ・インドネシア航空、チャイナエアライン、エバー航空、揚子江快運航空、ジェットスター・ジャパンなどが、中部国際空港発着便の一部もしくはすべてから撤退している。また開業以来赤字が続いているため、カジノ開業に期待するところは大きい。

長崎県では佐世保市が熱心だ。佐世保市にはハウステンボスがあり、園内には3つの直営ホテルがある。これを活用し、カジノを併設することで、それほど投資することなく、しかも短期間でIRをつくることが可能になる。しかも大村空港からも至近で交通の便もよく、世界最大のカジノ愛好国、中国に近いのもセールスポイントだ。
九州ではもう1つ、宮崎県が誘致に名乗りをあげている。かつて「新婚旅行のメッカ」とも言われ、多くの観光客を集めた宮崎だが、海外旅行が一般化するに伴い、観光産業はじり貧になった。これをカジノを誘致することで救おうというのだ。しかも宮崎シーガイアを、カジノ経営に興味津々のセガサミーホールディングスが買収(次稿参照)したことで、機運はさらに盛り上がっている。
このほか、和歌山県白浜町や徳島市もカジノに関心を示している。
カジノ誘致への取り組みで忘れてはならないのが大阪府だ。
大阪府がカジノ誘致に力を入れるようになったのは、現大阪市長の橋下徹氏が大阪府知事の時代。開業が間近に迫ったシンガポールのカジノを視察した橋下氏は、帰国後、IR構想を打ち出した。
関西国際空港の対岸に位置する大阪ベイエリア。この地区の開発が大阪府・市にとって長年の課題になっている。ここにカジノを誘致すれば、その課題は一挙に解決する。橋下氏はそれを狙ったのだ。橋下氏は2010年に今度はマカオのカジノを視察、カジノの必要性をさらに強く認識するようになったようだ。
橋下氏は最近でも、維新の会代表として、「(外国人観光客を増やすには)カジノの解禁。それしかない」と語っているほどだ。
橋下氏とともに維新の会代表を務める石原氏も、冒頭に記したように熱心なカジノ解禁派。橋下氏と石原氏の関係は必ずしもうまくいっていないと言われるが、カジノ解禁に関しては一枚岩のようだ。
もう1カ所。カジノ誘致を目指しているのが宮城県だ。ただ、宮城県の誘致の仕方は、他の自治体とは少し違う。というのも、自治体が主体的に手を挙げる前に、国会議員の間でカジノ建設の動きが始まったからだ。
一昨年の東日本大震災以来、東北では復興への取り組みが続いているが、思うようには進んでいない。いまは公共工事が行われているため、この地区に大量のお金が落ちているが、真の意味での復興は、産業が回復し、それが雇用を生んでこそだ。ところが、まだまだそういう状況には至っていない。
その解決策として国会議員の間で「宮城県にカジノ誘致」が語られたのは、震災からそれほど時間がたっていない時期である。この国会議員の声に呼応する形で、県議会の議員が超党派で誘致議員連盟を結成したという経緯である。
以上見てきたように、日本全国で誘致合戦が起こっている。いまのところ、カジノ解禁になっても認可されるのは2カ所程度だろうと言われている。その椅子を、10以上の自治体が競うことになる。
「でも実際には、ほとんど決まっているんですよ」
と打ち明けるのは、IR議連関係者だ。「東京・お台場がまず確定。もう1カ所となると沖縄が最有力」だというのである。
「カジノ解禁の目的は外国人旅行客を増やすことです。その目的を念頭におけば、どこにカジノを置けばいちばん効果的かは自明の理。東京ならば、シンガポール以上に人を集めることも不可能ではない。
沖縄というのは、政治的な理由によるものです。基地問題で揺れる沖縄の人たちの気持ちを考えると、基地以外の産業を育てることが必要です。その点、カジノは、IRのような大型施設ができれば1万人以上の雇用が生まれるし、財政的にも潤いますからね」
確かにお台場なら、羽田空港もすぐ近くであり、これ以上の立地条件はない。またホテルも十分にあるため、カジノホテルに泊まらなくてもカジノを楽しみたいという人を収容できる。さらには東京には日本中の人が集まるため、その人たちがカジノに来て落とすお金もバカにならない。
「お台場にカジノをつくれば成功は約束されている」と言われる所以である。
こうした見方に対して地方で誘致をしている自治体からは「カジノ解禁の目的には地域の活性化もあるはず。何もかも東京一極集中しているのに、カジノまでも持っていこうというのか」という反発の声も上がっている。
果たして結末はどうなるか。カジノ推進法成立後、誘致レースは最終コーナーを迎える。

―― カジノが解禁された場合、いちばん影響を受けると思われているのがパチンコ業界です。かつてパチンコは30兆円産業と言われましたが、いまではそれが20兆円にまで減り、淘汰の時代に入っています。そこにカジノがオープンすれば、さらに客が減るのではないかというわけです。
庄司 カジノ解禁を、パチンコ業界が反対しているというのは風評でしかありません。私の知る限り、パチンコ店の経営者がカジノに反対しているという話は聞いたことがありません。
というのも、パチンコというのは日常的な大衆のエンターテインメントです。一方、これから解禁しようとしているIRは、広汎なエンターテインメントですし、その目的は観光産業の振興にあります。ですからドメインがまったく違います。何より、カジノが解禁になったところで、日本全国で数ヵ所につくるといった話です。経営的に影響はほとんどありません。
―― カジノとパチンコを対立軸で捉えてはいけないわけですね。
庄司 ええ。むしろ私は、カジノ解禁への動きを歓迎しています。
これまで日本ではギャンブルというとネガティブなイメージが強かった。賭博であり、健全な勤労意欲を削ぐという、日本独特の概念が先行して、ギャンブルの効用がいままで議論のテーブルに乗ることさえありませんでした。でもカジノ法案の審議を通じて、さまざまな議論がなされるはずです。その中には、ギャンブルのネガティブな部分だけでなく、効能も含まれます。その意味は非常に大きい。

カジノとパチンコは競合しないと庄司正英・ピーアーク社長。
―― ギャンブルの効能とはなんですか。
庄司 2年前の東日本大震災の時、ピーアークの店舗はほとんど被害を受けずにすみましたが、それでも自主的に1週間、店を閉めました。安全を点検するという意味もありましたし、非常時に店を開けてもいいのかという思いもありました。でも1週間後に店を開けた時、多くのお客さまが本当に喜んでくれました。
「開けてくれたよかった。家の中でじっとしているとノイローゼになりそうだった」という方もいらっしゃいました。こういう方にとって、パチンコはもっとも身近な娯楽です。生活にビルトインされているのです。私たちはそれを糧として、この仕事をしているわけです。そういう効能についても、カジノ法案を通じて議論してほしいですね。
あるいはギャンブル依存症への対応もそうです。私たちは、パチンコ依存症の方のための、リカバリーサポートを行ってきました。でもいままでは各社、個別にやっています。カジノ法案の議論の中でも、ギャンブル依存症の問題は取り上げられるはずですし、解禁するにあたってはオフィシャルにこの対策に取り組むことになるでしょう。そのやり方は、私たちにとっても参考になるはずです。
―― パチンコ業者の中には、現在、グレーゾーンとも言われている三店方式による換金方法が、カジノ解禁によってとばっちりを食うのではと心配する人もいます。
庄司 確かに三店方式はグレーゾーンと言われています。その原因は都道府県ごとにルールがバラバラだったりすることにあります。ですから、これをグレーでなくせばいい。統一のルールをつくるなど、この問題にもしっかりと向き合っていく。カジノ解禁はそのいいチャンスだと思います。これをリスクと考えるか、パチンコが産業としての基盤を固めるためのチャンスと見るか。私は後者だと考えています。
―― ピーアークとして、カジノに参加する意思はありますか。
庄司 直接的に関与することはないと思います。でもファンドのような形で参加することはあるかもしれませんし、何より同じエンターテインメントサービスですから、人材の派遣など、得意分野を活かす方法はあるかもしれませんね。
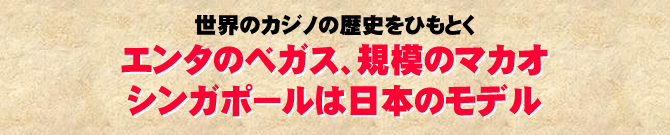
日本はカジノ後進国。世界120カ国にカジノはあるのに、日本ではこれまで認められてこなかった。しかしこれは日本に限ったことではない。現在カジノのある国でも、過去にはギャンブルが禁止されていた歴史がある。それがいかにして解禁されていったのか。参考のためにもその歴史を少し振り返ってみたい。
カジノはヨーロッパで誕生した。ドイツでは14世紀にはすでにあったともいうし、イタリアには17世紀にあったという。誕生当時から、カジノは貴族の社交場として発達した。しかしその一方で労働者階級の賭博場も出現していく。為政者はこうした賭博場を取り締まるが、いたちごっこのようなもので、根絶することはできなかった。
これは日本でも同じことで、江戸時代、幕府は賭博を禁じていたが、大名の下屋敷などで夜毎に賭場が開帳されていたことは時代劇でもおなじみのシーンである。
ヨーロッパで、カジノが公認されるのは19世紀以降のことだ。
そのきっかけがフランス革命だったという。
ブルボン王朝時代、フランス政府はギャンブルを禁じていた。しかし革命がなるや、それまでの反動もあって革命家たちはギャンブルを黙認した。これによってフランスにはカジノがあちらこちらに誕生する。そして為政者は、カジノを禁止するよりも、税金をかけたほうが財政的にもうま味があることに気づいたという。
その後、フランスを支配したナポレオンはカジノ禁止令を出す。ブルボン王朝を模倣したわけだ。しかしその結果、税収が激減、そこでさまざまな例外規定を設けて、事実上、カジノ禁止を骨抜きにした。そしてこの動きはヨーロッパ全土に広がる。
代表的な特例が、保養地のような、都会とは距離のある場所だった。いまでもヨーロッパのカジノの多くが保養所=観光地にあるのは、そういう理由による。また当時、保養所を利用できるのは上流階級に限られていたため、カジノはますます社交場としての色彩を強めていった。
現在、ヨーロッパには500を超えるカジノがあると言われている。旧社会主義国にもカジノがあり、カジノのない国を探すほうがむずかしい。それほどまでにカジノ文化が根付いている。
ただし、ヨーロッパの社交場型カジノの多くが、経営状態がよくないという。古いカジノより、ラスベガス型のエンターテインメントを前面に押し出したカジノが人気を集めているためだ。古いカジノは、歴史と伝統があるだけに、変わりたくても変われない。しかも、もともと税金徴収のために認められたこともあり、税率が異常に高く(ドイツでは粗利の90%)、新たな投資ができないという事情もあるようだ。
ヨーロッパに代わってカジノ大国となったのがアメリカだ。アメリカのカジノといえば誰しもラスベガス(ネバダ州)を思い浮かべるだろうが、全米ではネバダも含め10州でカジノが認められている。またこれとは別にインディアンカジノと言われる、先住民の居住区に建設されたカジノが20以上の州に存在する。しかし、米国のカジノといえばやはりラスベガスに止めをさす。
ラスベガスはゴールドラッシュの時に、西海岸を目指す人たちの宿泊地として発達した街だ。大恐慌から間もない1931年、ネバダ州は税収不足を補うためにギャンブルを合法化した。ただしその頃のラスベガスは砂漠の中の都市であり、水も電力も不足していたため大きく発展することはむずかしかった。ところがニューディール政策の一環で36年にフーバーダムが誕生。水と電力の不足は解消される。ここからラスベガスは大発展を遂げていく。
当初はダウンタウン地区にカジノは集中していたが、80年代に入ると、ストリップ地区に超巨大カジノが続々と誕生して今日のラスベガスが形づくられた。ピラミッド型のカジノ、エッフェル塔のあるカジノ。水路があってゴンドラで行き来をするカジノ等、施設そのものがテーマパークとなっている。またシルク・ド・ソレイユなどの公演が夜毎に行われている。その結果として、ラスベガスはギャンブルをしない人でも、家族連れでも十分に楽しめる街となった。実際、ラスベガスでは、カジノ以外の収入がカジノからの収入を上回っている。これは世界のカジノのうち、ラスベガスだけの特徴だ。
そのラスベガスを抜いて、カジノ売り上げ世界一を誇るのが、マカオのカジノである。
マカオのカジノには160年を超える歴史がある。始まったのはポルトガルが統治していた時代である。しかし1999年に中国に返還されるまでのマカオのカジノは、カジノというより「鉄火場」と言ったほうがいいような雰囲気を漂わせていたし、マフィアの抗争の舞台となることも珍しくはなかった。
それが大きく変わったのは返還後の2002年に、外国資本にカジノ経営を開放してからだ。それまでは地場資本だけにしかカジノ経営を認めなかったものが、大きく方針転換したのである。これによってまずは香港系とアメリカ系資本が進出、これをきっかけに10年も経ずして20以上の巨大カジノが誕生することになった。その結果、観光客が急増。2000年には年間800万人だったものが、5年後には1900万人と2倍以上に増えた。そして昨年は2800万人に達している。10年で3倍以上である。
カジノ収入も06年には70億ドルと、ラスベガスの65億ドルを抜いて世界一となり、昨年は380億ドルにまで伸ばしている。6年で5倍以上に増えたことになる。
マカオのカジノを支えているのが、経済成長著しい中国人だ。中国人は賭博好きとして知られるが、共産党政権下では賭博は禁止されている。それもあって、中国人はマカオに出かけるとカジノに入り浸る。それがマカオのカジノの収益につながる。
ちなみに、ラスベガスを1年間に訪れる観光客は約4000万人。それでいてカジノの収入は70億ドル程度にすぎない。かたやマカオは2800万人で380億ドルだ。もちろんラスベガスの場合、前述のように家族連れも多い。また国際見本市や国際会議も数多く開催されているため、カジノを目的としないビジネス客も多い。
そうした人たちが4000万人のうち半分を占めるとしても、カジノ客1人あたりのカジノ収入は350ドルに過ぎない。ところがマカオは1350ドルに達する。ラスベガスのざっと4倍。いかに中国人が賭博好きかがわかろうというものだ。
マカオがここまで発展する前、日本人にとってもっとも身近なカジノといえば韓国だった。
韓国初のカジノは、1967年仁川に誕生した。翌年には日本人にも馴染みの深い、ウォーカーヒルカジノが誕生した。韓国がカジノを解禁したのは、観光客を呼び込むため。自国民がカジノにお金を落としても意味がないため、外国人専用だった。
いまでも全土に17あるカジノのうち、16カ所では韓国民が入ることはできないようになっている。もっとも、だからこそ開放されている1カ所(江原ランド)にギャンブラーが集まり、社会問題化しているのも事実である。
韓国でカジノがいちばん集中しているのが済州島だ。1975年に最初のカジノができたのを皮切りに、現在までに8つのカジノが誕生している。
ただし、済州島を訪れる外国人観光客の数は年間150万人程度。この数に対して8つのカジノというのは過剰であり、実際、経営不振に苦しむところもあるという。この150万人の観光客のうち、6割前後が中国人が占める。
特に今年に入ってから日本人観光客が激減しているため、余計、中国人の比率が高まった。また、次で触れるが、シンガポールのカジノの最大の顧客も中国人である。結局、中国東北部の人は韓国へ、それ以外の人はマカオへ、そして富裕層はシンガポールへという棲み分けができているようだ。
さて、最後はシンガポールである。日本と同じでカジノに慎重だったシンガポールが解禁した経緯は、既述のレポートでも触れているため、ここでは現在の様子だけを述べる。
シンガポールのカジノは2カ所にある。1つはセントーサ島にあるリゾート・ワールド・セントーサ。この島全体がリゾートになっていて、その中の施設の1つとしてカジノがある。カジノの隣にはユニバーサル・スタジオがあり、島全体がカジノを含むエンターテインメントリゾートになっている。

もう1つのカジノが、マリーナ・ベイ・サンズ。ソフトバンクのCMの舞台となったところで、3本のビルの上に巨大な船が乗っているといえばわかるだろう(上写真参照)。屋上のプールは世界一高いところにあるプールとして知られており、このプールに入りたいがためにこのホテルを予約する人も多いという。この建物の中には会議場や美術館も併設されており、IRとしてのあらゆる機能を備えている。日本で建設しようとしているIRのモデルと考えていい。
このほかアジアには、共産党国家のベトナムにも、カンボジアにもカジノがある。
さて、日本では、カジノ推進法が超党派の議員によって秋にも国会に提出され、成立する見通しである。しかし中にはギャンブルに対して嫌悪感を持ち、カジノ解禁もってのほか、と考えている人もいるはずだ。そういう人こそ、ぜひ海外のカジノを覗いてみるべきだ。そしてできれば少額でもいいからカジノで遊んでほしい。
そうすれば、カジノの魅力が少しは理解できるだろう。もちろんカジノ解禁賛成の人も同様で、頭で考える前に体験してみることをお勧めする。

日本でカジノができるのは、最短でも2020年。少し先の話である。その前に、海外のカジノで遊んでおきたいという人も多いはずだ。海外のカジノに慣れておけば、日本で解禁になった時に「通」ぶることもできる。
というわけでもないだろうが、海外のカジノに遊びに行く人は増えている。各旅行会社は、ラスベガスやマカオのツアーを用意しており、利用者も年々増加傾向にある。
ただし、そうは言ってもギャンブルといえば競馬かパチンコ、あるいは仲間内のポーカーぐらいしかしたことのない一般の人にとっては、カジノは少し、敷居が高い。
スロットやルーレットなら、遊び方もわかるが、ブラックジャックだバカラだとなると、ルールは知っていても、お洒落に楽しむにはどうすればいいかわからない、という人がほとんどだろう。
ゲームのルールだけではなく、どんな恰好でいくべきなのか。たとえばヨーロッパのカジノは社交場として発展してきたから、ドレスコードもあるかもしれない。それがシンガポールならどうなのか、マカオならどうか。経験しなければわからないことだらけである。
そういう「カジノ素人」にとって強い味方になるのが、「リゾカジ.com」というウェブサイトだ。リゾカジとはリゾートカジノのことで、いま日本で解禁しようとしているIRと同義語だ。
世界中のカジノについても詳しく紹介している「リゾカジ.com」
このサイトでは、各地のカジノの特徴や、ゲームの遊び方を詳しく紹介している。
参考になるのが、海外のカジノに実際に行ってきた人の体験記で、勝った話、負けた話、恫喝された話など、実にさまざまな体験が語られている。これを読むだけで、地域ごとのカジノの特性や、実際の雰囲気が伝わってくるから、カジノに行こうと考えている人にとって参考になるはずだ。
また、閲覧者からの質問も受け付けているので、カジノに関するさまざまな疑問にも答えてくれる。
たとえば、先に述べたドレスコードの問題でも、「普段着でも大丈夫だが、ポロシャツ、短パンは避けたほうがいい」といった具合に具体的に回答してくれる。
何より、初心者にとって心強いのは、「オフ会」を年に何回か主催していることだ。ここのオフ会は、実際に海外のカジノへのツアーなのだが、初心者には遊び方から楽しみ方まですべて教えてくれるし、何より、ウェルカム・パーティも含め、カジノ側がVIP待遇してくれる。まさに至れり尽くせりだ。
ただし問題は、このオフ会に参加するには、ツアー料金のほかに、カジノに預けるお金として100万円ほどが必要になる。
「100万円というのは、VIP待遇を受けるための最低限の金額だと思ってください。でもカジノですから、全額なくなるわけではありません。何の待遇も受けずに、5万円や10万円負けるより、VIP待遇を受けて、それで100万円のうち20万円負けたとしても、楽しさはまったく違います。もちろん、負けると決まっているわけではありません。勝って帰って高級車を買ったという方もいらっしゃいます」(リゾカジ.comを運営するグローバルミックスの勝見博光代表)
勝見代表によると、このサイトの前身を立ち上げたのが15年前。8年前から現在のスタイルにしたが、ここ数年、カジノに対する関心が高まってきたことで、このサイトの閲覧数や会員登録する人も増えているという。またオフ会参加者も確実に増えてきて、カジノの場所によっては家族で参加する人が半分を占めることもあるという。
日本でカジノが解禁されると、海外へ出かける人が減る可能性もあるのだが、「カジノは非日常を楽しむものだから、行くなら海外という人も多いですよ」(勝見代表)。
カジノ解禁はリゾカジ.comにとってもプラスとなりそうだ。

―― 今年春先までは静かだったマクドナルドが6月以降、季節限定や期間限定商品を矢継ぎ早に投入し、怒涛のキャンペーンラッシュで注目されました。
1日限りで数量限定の1000円バーガーがその最たるものでしたが、振り返ると昨年11月、第3四半期決算(同社は12月期決算)の発表の席上で、それまで8年連続で続いてきた既存店売上高アップが途切れることを明らかにしています。それ以降、社内の議論、あるいは原田さんの社内での指示はどんなものだったのでしょうか。
原田 以前から、ずっと私が言っていたのが「成功した時が危機の始まり」「成功すればするほどハードルが高くなる」といったことです。私がここへ来た2004年以降、8年間連続して成功すると、社内の空気が目の前の数字を作ることにやっぱり慣れてしまい、ある意味では緊張感が足りなくなった。いまだから言えますけど、そう感じることもありました。そこで、私が社内でよく聞いて回ったのが、「それは売れた数字か、それとも売った数字か」ということです。
―― 待ちのビジネスではなく、主体的、積極的に売り上げを取りに行ったかどうかということですか。
原田 そう、売れた売れなかったではなく、売ったか売っていなかったかの議論ができないと、継続的な成長になっていかないわけです。

話題になった「BITE!」キャンペーン。
また売った数字も、利益の伴った、継続的な成長につながる売り上げなのか、一過性のもので終わるものなのかを検証していかなくてはいけない。言い換えれば、一過性の売り上げを追求するあまり、継続的な成長を犠牲にしているものはないか。そういう検証をしたわけです。
04年から始めた改革は、改革ですから、私の強烈なリーダーシップで引っ張っていかざるを得ませんでした。その改革はまだ終わっていません。でも、終わった改革の延長線上にある成長戦略については、私が全部リーダーシップを取っていたのではいかんのです。人材を育て、リーダーシップ育成もやらないといけませんから。これからやるべきことを言うのは簡単で、戦略とは、やめるべきことを言うことだと思ってますから、何をやめなければいけないかという議論は、かなりしました。
―― そういう意味では、昨年11月、あるいは今年2月の本決算発表時点では、いたずらにメニューを増やさないということで当初、今年のマクドナルドは地味な1年になりそうだという印象を持ちました。
原田 いろいろ議論した結果、いくつか機会点(=課題)が見えました。1つは、新商品の乱発をやめること。新商品の売り上げが上がっても、利益が伴うかというと、広告宣伝費がかさみますし、目算が狂って商品廃棄が出ても利益を圧迫します。つまり、継続的に右肩上がりになる成長戦略ではないんです。
それよりも、長い間売ってきた定番メニューに注力するのが、本当はあるべき姿なのです。そこに軸足を移すべきじゃないかという議論がありました。新商品の乱発、特に季節限定メニューの再考ですね。
それと、ディスカウントで目の前の売り上げを取ることもやめる。ディスカウントをやめるとその分、売り上げは下がります。だから、またディスカウントして売り上げを上げる。これを、単純に繰り返していてはダメです。
たとえば、炭酸飲料をオールサイズ100円にする。これはいい。ところが、ビッグマックのような商品を、ディスカウントして200円で売るということを年に数回、1週間ずつやっていくと、一時的にはお得感が上がります。
でも、繰り返してやっていると、お得感がだんだん下がってきます。これはたぶん、牛丼チェーンがやってきたことと同じなんですよ。そこに1つの発見があったので、それはやめようと。
―― 定番メニュー回帰とディスカウントもしない論理はわかりますが、その次の一手が、春先までは見えにくい感じでした。
原田 メディアは「マクドナルド業績不振」と、こう書かれてましたけど、業績が不振に終わったんじゃなくて、業績を一旦下げるという、明確な意図と意思をもってやってきたわけです。ですから、我々は業績不振という感覚は持っていません。敢えて、今後のために痛みを伴うビジネスモデルの体質改善をしようとしたわけですから。
―― 矢継ぎ早のキャンペーンは、その考え方に変化が生じたと。
原田 大きかったのは、今年の1月、2月の既存店の売上高が、マイナス17%とマイナス12%だったことです。もちろん、マイナスになるとは思っていました。

マクドナルド入り後、10年目に入った原田泳幸氏。
でも正直、2桁も下がるとは誰も思っていなかった。そこで猛烈に戦略を見直してみたわけです。でも、やっぱり季節限定の乱発はやってはいけない。そこは選択と集中で、季節限定商品の数は少なくていいから、よりインパクトのある強烈なものをやらないと。
お客さんはやはり、新しい価値やサプライズを求めています。乱発抑制と新商品投入の、バランスを取ることが大事だということがわかったので、そこから猛烈に企画を立て始めて、6月からのキャンペーン(サッカーの本田圭佑選手をイメージキャラクターにした大がかりな販促戦略)に至ったわけです。
一方で、いまだにディスカウントはやめています。もっと言えば、1月、2月のあの落ち込みがあったからこそ、いろいろと学べたのです。あの時期、そこそこのマイナスで終わっていたらたぶん、ここまで強烈な発想は出てこなかったと思いますね。社内の空気としては決して路頭に迷っているわけではない。今回のキャンペーンは、いわば学びから出てきた新しいアイデアですから。これは大きな財産として、今後に生かしていきます。
―― その1、2月の大幅な落ち込みですが、昨年末以降、アベノミクスで日経平均株価がグッと上がり、ファミレスやファストフードに行っていた客が、財布の紐を緩めてワンランク上の食事に出かけるようになったということはないですか。
原田 そういうデータはないですね。アベノミクスで外食産業の消費構造がそんなに変わったとは思えません。それよりも、大きな流れの変化はありますよ。たとえばデリバリー市場が右肩上がり、あるいはテイクアウトが伸びているとか。依然デフレで、外食マーケットが右肩下がりでありながら、競争は逆に厳しくなってきて、お店の数もプレーヤーも増えています。

負けず嫌いで絶対に弱音を吐かないのが原田氏の身上でもある。
ということは、消費者はお店もメニューもものすごく選択肢が広がっているわけで、我々にしたらこれは強烈な競争要因です。なので、一番大事なことはマーケットシェアをしっかりと捉えるということ。外食産業はまだまだ右肩下がりということは意識しておかないといけないですから。テイクアウトやデリバリーが増えているほか、スーパーマーケットでも積極的に弁当を売っていますから、我々のようなレストランビジネスは、まだまだ厳しいものがあると思います。
その中で一連のキャンペーンは大成功。1000円バーガーなど、数量限定メニューも予定より早く売り切れましたし、特に好評だった「クォーターパウンダー ハバネロトマト」が相当早く売り切れて、次に準備していたスパイシーな「サルサバーガー」投入を、前倒しするくらい売れましたから。
でも、これですごく売り上げが上がって安泰かといえば、そういうレベルではないです。やはり、客数を取っていくというところがまだまだ厳しいですね。当社に限らず、外食マーケットは当分、客数ではダウントレンドだと思います。したがって、今後は当社もデリバリーには力を入れていく。これは投資上、大事なポイントです。
―― 「BLT」「ハバネロトマト」ともに、従来のクォーターパウンダー商品よりも高価格帯であったうえ、「クォーターパウンダー ジュエリー」という1000円バーガーでサプライズを見せ、従来よりも高価格帯に客を誘導しつつ、新デザート商品で客数を取っていくという見方もあります。
原田 一連の商品は決して客単価政策ではありません。あくまで、来店されたお客様にマクドナルドの勢いを感じてもらうためのプロモーション、お祭りであって、ビジネスモデルではありません。マクドナルドは、ウィークデーの客単価、ウィークエンドの客単価、カウンターの客単価、ドライブスルーの客単価と、もうほとんど決まっているんですよ。これは普遍的なものです。ですので、一連のキャンペーン商品は客単価を上げるものではなく、客数を上げていくためのキャンペーンで、話題作りなのです。
それに、高額商品で獲得する客数というのはそんなに大したことはないですから。むしろ、新デザート商品のほうで客数を増やさないといけない。でも、まだ予定よりも客数が下回っているというのが正直なところです。
年間の業績も、今年1月、2月のマイナス幅が1年間、重くのしかかってきますから、今年は大変、勉強の年だったということでしょうね。ともあれ、客数がまだ予定通りにいってないので、そこが今後の一番のチャレンジになります。
―― 本田選手を起用した「BITE!」のキャンペーンでは、相当な販促費になったのでは。
原田 いや、販促費は年間予算の枠が決まっていて何も変わらないです。同じ予算の中で配分を変えただけで、例年よりも予算をたくさん使ったということではない。それでいて、外部の方には販促費を相当使っているなと感じさせるのが、いいマーケティングなのです。
今回のキャンペーンの企画立案では、相当久しぶりに私も入り込みました。広告宣伝やマーケティング、コピーまで入り込んだのは、前回のクォーターパウンダー以来でしょう。要は、マーケティングも選択と集中なんですよ。これは社員もずいぶん勉強したんじゃないですか。
―― 足元と、12月期の決算に向けたこれからの課題は、どのあたりにありますか。
原田 さきほど言いましたように、1月、2月の数字は決算発表上、重くのしかかってきますから、年初の業績見通しをこう変えますとは、この場では言えません。年初に発表した年間数字を達成するのは、厳しいことは厳しいですね。
去年と今年の経験が、来年以降のさらなる成長のために、かなり貢献してくるでしょう。8年連続成長の後、2年間学びがあったと。毎年、永遠にマイナスが続くわけじゃないですから。この厳しいデフレの中で、通らなければいけない、不可欠の経験だったんでしょうね。ただ、迷走は絶対にしていませんから。戦略も変わっていないし、やるべきことは見えていると思います。低迷している時こそ、社員やステークホルダーに対して希望を見せるのが経営者の役割ですし。
―― 後半戦の中で、消費税増税が来年以降本当に引き上げになるのか、不透明な部分もあります。
原田 消費税率引き上げが予定通り来年4月からでも、あるいはその予定が先に伸びても、いずれにしてもどこかでは上がるんです。その時どうするのかという準備はしておかなくてはいけないんですけど、それ以上に、そんなことにエネルギーを使っていても業績は上がりません。

選択と集中の重要性を説く原田氏。
大事なのは、どうやって売るかという議論がしっかりできているかどうかです。消費税が上がった場合、どういうキャンペーンをやったらいいとかまずいとか、そういう議論に終始している経営者だったらもう、ダメでしょうね。
消費税増税なら、家やクルマなどの大型商品には駆け込み需要やリバウンドがあるでしょう。でも、コモディティや日常の食生活の商品の場合は、駆け込みってないわけですよ。税率が上がった瞬間はストーンと落ちます。でもスッとまた元に戻るんです。その現象は成長戦略とは関係ないもので、どちらかと言えば戦略でなく戦術の話です。
それ以上に、日本は人口が減っていくわけですから、顧客獲得率を上げていく以上に、来店頻度を上げる。そこではメニューの数を増やすのではなく、来店動機を増やすことが重要なのです。
―― ところで、店舗のフランチャイズ化比率や自社物件店舗の多寡では、米国本社とかなり差があり、この水準の差を埋めていくこともずいぶん前から言われてきました。
原田 04年からやってきたことはたくさんありますけど、その中の1つがグローバリゼーションです。マクドナルドはグローバルなレストランのビジネスモデルでありながら、それまでは日本の独自性に偏り過ぎていた。
そういう意味では、米国本社との連動を図るというのは相当、こちらから積極的にやってきました。店舗開発から厨房設備、オペレーションシステム、サプライチェーン、メニューの改廃と、すべてにおいてです。「BITE!」のキャンペーン商品も、米国からのアイデアもあるし、日本が開発した部分もある。そのインテグレーションから生まれた商品ですからね。
そういうことをやってきた中で、日本マクドナルドHDはジャスダック市場の上場企業ですから、上場企業としてガバナンスも守らなければいけないので、経営戦略に関しての自立性は大事。
でも、ビジネモデルに関してはグローバルな強みを出さないといけない。ここは、かなりけじめをもって議論しています。あくまで戦略の決定権は日本側ですから。それに、積極的に日本人のニーズを反映した商品開発をしなかったら、企業として存続できません。
―― この夏以降の課題はどうですか。
原田 「BITE!」のキャンペーンは終わりましたし、次のメニューをどうするか、この夏に学んだことや、1月、2月の失敗から学んだことを、どう秋冬シーズンの商戦につなげていくか、まさにいま一生懸命議論しています。これまでと同じことをやっても、過去の成功以上の成功は望めないのですから。
(聞き手・本誌編集委員・河野圭祐)
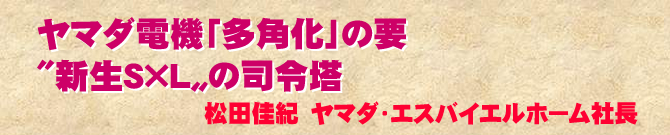

松田佳紀 ヤマダ・エスバイエルホーム社長
まつだ・よしのり 1960年11月9日生まれ。和歌山県出身。79年和歌山北高校卒業。同年上新電機入社。2004年営業本部販売促進部長に就任。06年同社退社。07年ぷれっそHD社長のほか、マツヤデンキ、サトームセン、星電社の社長に就任。12年ヤマダ電機に入社し、取締役兼執行役員副社長。今年3月エス・バイ・エルに転じ社長代行、5月28日から現職。趣味はスポーツ観戦。
ヤマダ電機が、ハウスメーカーの中でも老舗のエス・バイ・エルを買収して、住宅事業を拡大している。その中核を担うのが、生まれ変わったヤマダ・エスバイエルホームだ。今年5月末、同社の社長に就いたヤマダ出身の松田佳紀氏は、どう再浮上に挑むのか。
〔家電量販店最大手のヤマダ電機が、木質プレハブ中堅の住宅メーカー、エス・バイ・エルを買収、子会社化(現ヤマダ・エスバイエルホーム。以下ヤマダS×L。東証1部上場)すると発表したのは2年前の2011年8月のこと。地上デジタル放送への移行後、家電量販店はどこも薄型テレビの売り上げが急減したことから次の収益源を模索している。ヤマダが期待をかけるのがスマートハウスを核とした住宅事業で、省エネ性能の高いエアコンやテレビなどの家電製品、家庭向けの発電・蓄電装置などを組み合わせた住宅を提案し始めている〕
液晶テレビもさることながら、パソコンもタブレットに取って代わられてきています。ヤマダ電機のパソコン販売シェアは非常に高いですから、この分野の売り上げ減少も効いてくる(その対策として去る7月に、ヤマダはレノボ・ジャパンと組んだ独自のミニタブレット「エブリパッド」を発表、発売)。
一方で住宅、特に戸建て住宅というのは、地場の工務店需要が高いため、圧倒的なトップメーカーは存在しません。そこで、ヤマダ電機のさまざまなインフラを使って将来、戸建て住宅業界でナンバーワンになれないかなと考えています。
〔確かに、昨年の戸建て住宅の国内シェア(日経新聞社による推定値)はトップの積水ハウスでも3.7%、以下、僅差で旭化成ホームズ、積水化学工業、ミサワホーム、大和ハウス工業と続く。ほかにも、住宅との関連性が高いためか、トヨタ自動車が「トヨタホーム」を、パナソニックも「パナホーム」を擁している。トヨタ、パナソニックは巨大メーカーだけに、グループ会社も入れると社員数が膨大で、それだけでも住宅の売り先は一定量が見込める。その点、ヤマダ電機のような流通小売業からの住宅市場参入は珍しい〕
トヨタホームさんは鉄骨系の住宅で、従来は木質系の住宅がありませんでした。そこでミサワホームさんをグループ化して、木造と鉄骨の2枚看板にされた。パナホームさんも鉄骨系だけですが、パナソニック電工さんという、システムキッチンやシステムバス、トイレ設備なども作っているグループ会社を持つ強みがあります。で、ヤマダ電機も昨年、ハウステック(元は日立化成系のキッチン、バス、給湯設備を手がける企業)という会社を買収していまして、競争力はあると思っています。プラス、家電量販店最大手(ヤマダ電機の2年前の売り上げは2兆1532億円。今年3月期は1兆7014億円)のスケールとインフラ(全国に約600店)も武器になりますね。
〔具体的なヤマダシナジーとしては、3500万枚ものヤマダ電機の新聞折り込みや店頭でのチラシと、店舗駐車場スペースの住宅展示場への利用などが挙げられ、この10月頃までに、住宅展示場を10カ所ぐらい設置する予定だ〕
住宅は30年とか50年とか、買い替えサイクルが長いでしょう。家電なら、たとえばパソコンで5年から8年、冷蔵庫でも10年から15年、エアコンやテレビも10年ぐらいです。日本は5000万世帯で、テレビが一家に2台平均で1億台のマーケット。それが10年に1回の買い替えなら、計算上は1年で1000万台という需要になります。冷蔵庫や洗濯機も700万台から800万台の間で、買い替えサイクルでほぼ、年間マーケットが決まってしまうわけです。
一方、住宅は当社製の家で過去、9万5000世帯ぐらいに売っていますから、そこに、我々からリフォームなどの情報発信、提案ができます。その点でも、ヤマダ電機の店舗でリフォームコーナーが拡充できるのは大きい。昨年、ヤマダ電機の店内に初めて30坪のリフォームコーナーを作りました。山田昇(=ヤマダ電機社長)がすごいのは、30坪で一亘投資したところを、まだ効果が物足りないと判断したら、さらに80坪、100坪と拡大再投資して作り変えることです。リフォームコーナーも、成功パターンができれば大きな効果をもたらすでしょう。
〔ヤマダS×Lホームは、創業から通算63年目の老舗。創業者の小堀林衛は竹中工務店の出身で、独立して三成建築工業(後に小堀住建興業となり1990年からエス・バイ・エル)を興した。デザイン性や耐久性に優れた商品力に定評があったが、低価格帯の戸建て住宅に参入後、安価なイメージが先行したこともあって、業績低迷期が続いていく。
そこで、ヤマダ電機出身の松田氏が社長に就いた直後の今年6月、ヤマダS×Lホームでは、中高級商品とコストパフォーマンスに優れた商品の2路線を打ち出した。前者の高級路線では往年の「小堀ファン」層を取り込むべく、「小堀の住まい設計工房」の設計、デザイン、提案力を最大限に活用していくという〕
いわば、オンリーワンの家作りですね。我々は、基本的なデザインは自分たちで手がけています。もともと関西では評価が高かったのですが、シンプル&モダンというコンセプトで一時期、関東でもエス・バイ・エルの家がブームになって、ほかのハウスメーカーが追随したほどです。
ですが、デザイン重視は高コストにもなり、経営権が主力銀行やファンドの手に渡った時期は、その良さがどんどん縮小されていきました。そこで、これからは原点に戻って本質を極めていこうと。それがまた、強力な差別化にもなっていくからです。当社の創立記念日は6月14日ですが、それまでこの日は会社が休みになっていました。でも、そうじゃないだろうと。全員が出社して、全員で原点を確認する日、戻る日だと訴えました。
創業家の小堀家の社員が子会社も入れると2人いまして、その人たちにも創立記念日に、小堀林衛という人の思いについてスピーチしてもらいました。小堀は生前、「心の住まない家を住まいとは言いたくない」と言っていましたが、社名は折々で変わっても、基本は「小堀の住まい」というコンセプトにあるのです。そこをしっかり確認しようと社員に伝えました。
もちろん、小堀の良き文化は継承しつつ、一方でスケールメリットも追求します。実際にかつて、「ハウス55計画」(75年に実施された、5年間で一戸建て住宅を500万円で供給できるようにしようという国を挙げてのプロジェクト。唯一、エス・バイ・エルを中心としたグループがこの価格帯の住宅を実現できた)で、ミサワホームさんと一緒に、お得感のあるデザインで、いい家を大量供給できた時代もありましたし。
〔比較的安価な住宅で過去、一世を風靡した感もあったわけだが、そのお株は近年、タマホームやファースト住建といった新興の上場ハウスメーカーに取って代わられていた。名実ともにヤマダ電機グループとなったいま、これからがリベンジの時期になるのかもしれない。
ヤマダ電機のカリスマ、山田昇社長はいまも月曜、火曜は朝7時前に出社。他社も含めた新聞の折り込みチラシもこまめにチェックし、対抗値下げの指示も多いらしい。人一倍負けず嫌いの山田氏のこと、新規参入した住宅市場でも、シェア獲りの野望は大きいだろう〕
ただ、住宅メーカーは家電量販店と違って、プレーヤーの数が非常に多いんですね。家電量販店はずいぶん店舗数も減りまして、昔は、大小入れると電器店が全国で4万店ぐらいあったのが、いまは2万店ぐらいです。一方で、戸建て住宅市場は、親子2人で工務店を経営しているようなところが無数にあります。将来、どこかで合従連衡の局面も出てくるかもしれませんが、この業界ではまだ、少し先のことかなと思いますね。
〔新生のヤマダS×Lホームとなって、松田氏が重点的に取り組むのが人材育成と社内の活性化だ。業績低迷で沈滞した士気を再び盛り上げることが、何より大きな課題と考えているからである〕
ここ1、2年でベテランも辞めたりしましたが、幸いなことに、ピーク時で1806億円売った時代の工場インフラがいまでもあります。このインフラで売り上げ1000億円までは対応できる(2013年2月期は398億円。今期見通しは540億円)。技術の継承という点では、中堅社員を中途採用していくことも大事なことです。でないと、1000億円という事業目標は絵に描いた餅になってしまう。
あとは、ファンドの資本が入った頃、社員の給料が圧縮されて、優秀な社員が去っていった面も否定できませんから、利益は社員にも還元していく。そういう意味でも、工場インフラに投資しなくて済むことは大きい。業績が少し良くなれば、給与アップやボーナスアップの原資に回せるからです。同業他社の大手とは経常利益率がまったく違うので、業界平均より上の給与水準というのはかなり大変ですが、決して恥ずかしくない給与ベースにもっていくのも、私の大きな仕事の1つだと考えています。
〔松田氏のヤマダ電機時代の役職は、取締役兼執行役員副社長で、営業本部長兼商品事業部長という重要なポストを担っていた。山田昇氏からの指示で、エス・バイ・エル社内を初めて視察したのが昨年11月のことである〕
視察から戻ってきて「営業現場で人が辞めており、ちょっと大変です。モチベーションが下がっています」と報告したら、「2、3カ月行ってこい」と。また戻って「いや、これは本当に大変です」と言ったら年明けに、「人心掌握しろ」、さらに2月に入ると「3月1日からこの会社の責任者になりなさい」と言われました。それでまず社長代行となり、5月28日の株主総会をもって正式に社長になったという経緯です。
〔年齢的にも52歳と比較的若い松田氏。出身は和歌山県で、地元の高校を卒業後、大学進学を断念して社会人生活をスタートさせている。最初に入社したのは、大阪が地盤の上新電機だった〕
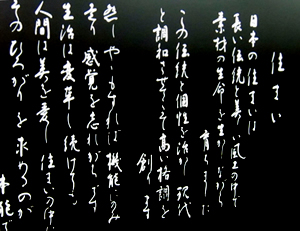
創業者の小堀林衛が遺した「住まい」の言葉。
ある大学に受かりはしたんですが、もう少しいい大学を目指して1年浪人しようと。その合間に上新電機の試験があって、往復の電車代を出してくれたんですよ。高校の先生には「大学を受け直すから会社には行かない、浪人します」と言ってたんですが、「学校推薦で来た求人なんだ。半年でもいいから行ってくれ。でないと来年から求人案内が来なくなる」と言われましてね。
それで、半年のつもりで上新電機に入ったんです。大学受験は捨てがたいので一定期間経過後、辞表を出したんですが、年末商戦の忙しい時期の直前でしたから店長に辞表をビリビリと破られてしまって(笑)。そうこうするうちに辞められなくなって、バイヤーの仕事に移りました。
その後、名古屋で店長をしていた頃に、上新電機で過去に経営者をしていた人たちの間でゴタゴタが起きましてね。嫌気がさして、私も辞めようかと気持ちが揺らぎました。結局、行きませんでしたが当時、三井ホームさんとエス・バイ・エルの中途採用試験を受けたことがあるんです。もう20年も前のことですが、いま、こうして私がここにいるのも何かの縁かもしれません。
〔辞めずに勤め続けた上新電機で、松田氏は04年に営業本部販売促進部長となり、2年後の06年に同社を退社した。本人は「ヘッドハンティングでなく、いわば“ボディハンティングですよ”」と苦笑するが、スカウトされた先が東証1部に上場していたマツヤデンキである。マツヤデンキは民事再生法を申請して破綻。その再生役として松田氏に白羽の矢が立ったのだ。06年4月のことである〕
その06年秋に、神戸にあった星電社、東京にあったサトームセンの代表取締役にもなりまして、マツヤデンキを含む3社を統合した持ち株会社、ぷれっそホールディングスの社長に、翌年の07年に就任しました。そのぷれっそHDをヤマダ電機が買収したわけです。

松田氏の座右の銘は「とにかく何かを始めよう!」。
当初はまだ、マツヤデンキの再建で頭が一杯で、実際駆けずり回っていましたね。マツヤデンキも、一時期は経常利益率で5%ぐらい出していたんですが、店舗規模が小さくて、100坪とか150坪ぐらいだった。つまり、ヤマダ電機やコジマといった、1000坪以上ある店舗を擁するところと競争しても、効率性で負けちゃうわけです。
上新電機は小さい店を大きくして残ったんですが、マツヤデンキは小さいままでした。で、何とかその小さい規模のままで勝ち残る方法を考え出さないといけない。それでリフォームサービスをしたり、旅行パンフレットを置いて販売したりしました。店を電器屋レベルのプラットフォームに縮小して、保険代理販売や住宅リフォームを含め、地域密着型でいろいろトライしたのです。
そうこうするうち、親会社となったヤマダ電機を含め、家電量販店も厳しい状況になりました。11年7月にアナログ停波となり、ピーク時は2500万台まで伸びたテレビの需要が急減したわけです。前年度までの、家電メーカーの業績悪化は周知の通りです。
電機メーカーの苦境の波は、1周遅れで必ず家電量販店にやって来ます。家電量販店がまだ、何とかなっていたのは、メーカーのように生産設備を持ってないから。でも、販売戦線を拡大した後の需要急減の影響は、規模が大きいヤマダ電機ほど効いてきます。
そこで、さきほど言いましたように、エス・バイ・エルやハウステックといった会社を買収したと。テレビの売り上げ減少分は、6兆円のマーケットがあるというリフォーム市場、10兆円近くあるといわれる住宅マーケット、この両ジャンルで賭けることになりました。
エス・バイ・エルがつらかったのは、ファンド傘下の時は、何よりも毎期の損益が最重要ですから、優良な遊休不動産物件をどんどん売却していったわけです。5年10年先の経営を考えたら残すべき物件も売ってしまった。一方で、短期利益ではマイナスになる、簿価割れ物件は売らないんです。
ファンドは目先1年1年の収益が勝負で、雇われた経営者は単年度収益で自分のボーナス、もしくはインセンティブが支払われますから、長期的なことは考えていません。優良物件を売って、規模を縮小していくしかないというのが、過去のエス・バイ・エルでしたが、いま、やっとそこから脱却して攻めの展開ができるようになってきたのです。
家と家電製品はもともと親和性が高いわけですから、ヤマダS×Lホームでの仕事もこれからが本番、気合を入れていきますよ。
(構成=本誌編集委員・河野圭祐)

9月14日から東京・渋谷シネクイントで開催される「ぴあフィルムフェスティバル(PFF)」。今年で35回目を迎える自主制作映画の映画祭だ。作品を公募して審査会を開き、優秀な作品を上映・表彰するこのイベントは、いまやプロ監督への登竜門として定着。PFFはこれまでに『失楽園』『黒い家』の森田芳光監督(1977年入選)や、『ウォーターボーイズ』『スウィングガールズ』の矢口史靖監督(90年入選)、『フラガール』『許されざる者』の李相日監督(2000年入選)、『舟を編む』の石井裕也監督(07年入選)等々、現在も活躍する監督が100人以上も輩出している。

PFFが初めて開催されたのは1977年のこと。情報誌「ぴあ」の創刊5年目で、企業としても設立3年目、草創期からスタートしたことになる。矢内廣社長をはじめ、ぴあの創業メンバーが中央大学の映画研究会出身ということもあり、雑誌に掲載する映画情報もメジャー、マイナーの差をつけずに掲載する編集方針を採っていた。
当時、有料入場者数が激減していた映画業界は、社員としての映画監督候補の採用をやめたことから、映画監督を目指す若者は自主製作映画に打ち込んでいたのだという。しかし、その作品を発表する場がほとんどなかったのが実情だった。PFFはそんな若い感性と個性に日の目を当てるべく、「自主製作映画展」としてスタートしている。
1992年からPFFのディレクターを務める荒木啓子氏に話を聞いた。
「昔の、例えば黒澤明監督の時代は、映画監督になりたければ映画会社に就職すればよかったわけです。大島渚監督や山田洋次監督の時代もそう。ところが、いまや映画会社は映画監督を1人も雇っていません。映画監督として生きていきたいと思う若者は大勢いますが、どうしていいかわからない時代になっています。70年代当時、8ミリを使って自主製作映画を始めた人が、中学・高校・大学の映研と言われているところから、自然発生的に出てきました。そういう人たちの作品を、映画を作る力のある人、いわゆるプロデューサーや映画会社の人たちに見せていこうとしたのが、PFFの始まりです。
社長の矢内も映研出身ですので、たぶん監督をやりたかったのではないでしょうか。その時の思いを忘れないでこれまで続けていることが貴重な存在だと思います。そもそも映画祭をプライベート企業が運営しているケースはほとんどありません。スポンサーとしてお金は出しても、運営まで行っているのは世界で唯一かもしれません」
実際、PFFは直接ぴあの利益に結びつく事業ではないという。矢内社長自身、証券マンから「利益を生まないことに使うお金があるなら、それは株主に配当しなさい、ということになる」と言われ、一度はぴあの上場を見送った経緯があることをメディアで語っている。PFFは、ぴあの企業理念である「若くて新しいチャレンジをしている人を応援する」を具現化したイベントであることから、企業の経済性よりも「趣旨性」にこだわった事業だ。
「PFFには、将来がわからない若者たちに希望を与えるということに対する責任があります。PFFで賞を獲らなかったら、ぜんぜん違う人生を送った人もいるかもしれないわけです。本人の問題かもしれませんが、応援すると同時に希望を与えているわけですので、そのことに対する責任は感じていなければいけない。だからこそ、どのような映画祭にするのか、常に考えています」
PFFには毎回500~600本の作品が応募されてくる。今年のPFFで上映される入賞作品は、そのうちの16本と狭き門になっている。
「そのなかから実際にプロになれるのは何人出てくるのか、という世界ですから、すべて狭き門です。将来、名監督になれるような人は、やはりオーラのようなものをある程度感じますが、本当になれるかというと、簡単ではありません。PFFに入選しても、実はそこから監督として食べられるようになるまでは非常に長い。時々、シンデレラボーイのように李監督や石井監督のように、すぐ大型の映画を撮るような人が出てくるので、成功しているように見えるかもしれませんが、ほとんどの人は長い下積みがある。

園子温監督(87年入選)はいまでこそもてはやされていますけど、食べられるようになったのはここ数年。矢口監督もグランプリを獲ってから10年間は食べられていないと思う。結局、全員フリーランスですから、やっていける人は限られています。辞めない人しか残っていけない。
映画って、別の世界を切り開くんだというビジョンを持った人しか残らないんですよ。残っている人たちは、別の価値観を世界に導入したいと思っている人たち。おのずと、生まれた時から世界観のある人たちしかクリエイターになれないと思う。自分のことしか考えてない人は、無理だと思う。それがある種の才能だと思いますね。人間の可能性、人ってすごいことができるんだという感じを、観た人が感じてくれればいいなと思うんですよね」
積み重ねた回数35回、100人を超えるプロ映画監督を世に送り出してきたPFFだが、一貫してぶれずに示しているのが、荒木氏の言う「人間の可能性」だ。
「自主映画の根本的なスピリットは『個人の力が、はじまりの第一歩だ』『個人のものづくりの意欲が、すべてのはじまりだ』ということです。人間というのは、常に何かを生み出す力があるということを、若い世代に示し続け、具体的な形である自主映画を見せる場所として、PFFは常に変わらずそこにある。時代の変遷とともに作品も変わり、上映場所も方法も変わりますが、根本的に変わることがないのは、人の表現したい意欲、何かを作りたい意欲です。個人でできることを超えて、大きく展開できる場所として、PFFは一種のメディアであるとも言えるかもしれませんね」
PFF入賞者には、PFFスカラシップへの挑戦権も与えられる。次回作の企画書を提出し、そのなかから毎年1人のオリジナル作品をPFFが企画、脚本、撮影、公開、DVD発売までトータルプロデュースし、プロ監督としてのデビューを支援する。また、早稲田大学とも提携し、最新デジタル設備を備えた早稲田大学大学院国際情報通信研究科へ、PFFアワード入選監督を推薦入学させるプログラムも、2005年から用意されている。こうしたスカラシップ制度を設けている映画祭は世界的に数少ない。
「本来なら、映画で商売している人たちがやるべきことを、肩代わりしている部分がある(笑)。ものをつくるということは、志がないとできない。商売では無理なんです」
PFFは92年、企業メセナ大賞特別賞も受賞している。矢内社長が02年にぴあの上場を決断したのも、企業メセナ活動や文化振興といった事業が、企業のあるべき姿として認められたからだと言える。
日本映画製作者連盟の統計データによると、12年の映画館への観客動員数は1億5516万人。国民1人が1回以上、映画館へ足を運んだことになる。しかし、荒木氏は若者の「映画館離れ」を指摘する。
「少なくとも私は1年に何十回と映画館に行っていますし、1年に300回くらい行く人もいるわけです。均した数字なんて、まったく意味がない。この1年間に映画館に行った人は、100人中1人か2人くらいではないでしょうか。
いまの人は映画館に行かない。むしろ映画館が嫌いという人もいます。まったく知らない人と隣同士で見たくない。見知らぬ人とシェアする訓練がまったくできていないんですね。いま地方に行くと、映画館は県庁所在地くらいにしかないところが増えています。映画が好きで、映画館に行こうと志した人以外は一生行かない。生まれてから一度も映画館に行かずに亡くなる人は、これから増えると思います。若い人たちは、映画の既存のシステムを捨てようとしており、映画館に行くことは、もう映画の前提ではないんです」
いまやDVDやブルーレイなどをレンタルして映画を観るという人も多いだろう。なかにはヘッドフォンをしてスマートフォンで映画を観るという人もいるくらいだ。

「人間は、常に何かを生み出す力がある」と荒木氏。
「私たちとしては、作る人がどういうサイズをイメージして作るかというのがすごく大事ですから、大きいスクリーンをイメージしてほしいんですけど。映画を観る、音楽を聴くというのは、本来は教養です。映画を観ることによって、何かを考え、何かを知ろうとする。映画をフックに何かが起きることが大事です。それが、単なる娯楽として、何も考えなくてもいいという映画ばかりが喧伝されている。これは何も考えるなという社会的な洗脳に乗っかっているとしか思えない」
それは作り手の側にも表れてきているという。映画に関する大学の学科や専門学校も増えているが、逆にPFFに応募する作品にも個性あるものが減っているのが現状だ。
「高い意識を持つということに対しての訓練がされていない。大きなイメージを描く人が潰されるという社会に急速になっている気がするんですよ。応募作を観ても、すごくセルフコントロールされている。審査員は過激な作品を期待していたりもするんです。そういう作品を入選させていないように言われることもありますが、そうではなく、応募がないんですよ。何かのきっかけで、何をやってもいいんだということを感じたら、もっとおもしろいものが出てくると思うんですけど、自己規制がすごく激しい世の中になっていると思います。
いまは情報社会で、変に情報だけは知っている。どういうことをやったら受けるかとか、どういうことをやったら効率が高いかとか、どうやれば商売に繋がるとか、小賢しいことばかり知っている。手堅くまとめてしまうんですね。予備審査員を1回やると、いまの日本の状況がすごくよくわかる。本当に怖いですよ」
とはいえ、そんななかでもPFFでは、個性と若い才能にあふれた自主製作映画が上映される。なかには、すでに海外の映画祭から招待を受けている作品もある。
「自主映画は生々しくて苦手という人もいるかもしれません。自主映画=暗いというイメージの人も多いでしょう。ところが、ぜんぜん暗くない。すごくエンタテインメントな映画が多いんです。こんなにエンタテインメントを志向して成功している映画があるということを多くの人に知ってほしい。去年の入選作品『賢い犬は吠えずに笑う』は、完全に女子高生のエンタテインメント映画。入選した時からダントツに注目されていたんですが、今年渋谷で自主公開したら、連日立ち見。ふつうの商業映画が、いま1000人のお客さんを集めるのが難しいなか、それを軽く超えて何千人も来てしまう。そういう映画があることを知ってほしいですね」(本誌・児玉智浩)
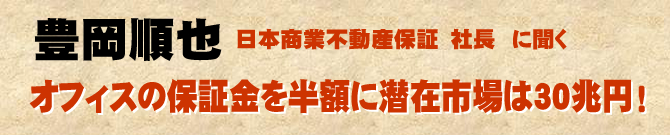

豊岡順也 日本商業不動産保証 社長
とよおか・まさや 1973年東京生まれ。大学卒業後、国際証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)に入社するが7カ月後に父が倒れたため家業の物販会社を経営。その2年後、HIS協立証券に入社し、株式公開引受業務に従事。その後企業内起業でコンサルティング会社を立ち上げ、社長に就任。同社をMBOで取得独立したあと、2011年フィナンシャルギャランティを設立、今年現社名に変更した。
―― 日本商業不動産保証という社名は非常に堅苦しいですが、提供するサービスは「保証金半額くん」で、オフィスを移転する際の敷金・保証金を半額にするという、非常にわかりやすいものですね。
豊岡 ええ。通常ですと新しいオフィスを構えるには、ビルのオーナーに家賃の10~12カ月分の保証金を預けなければいけません。家賃が仮に100万円なら、10カ月分で1000万円です。店子にしてみれば、これだけの資金が寝てしまっています。中小企業にとっては、この負担はバカになりません。そこで、その半分を当社が保証しようというのが「保証金半額くん」です。
ですから店子にしてみれば、移転に際してのコストを低減することができるし、本来納めなければならない半分の保証金をほかに投資することも可能になります。さらには、ビルオーナーに何があっても、預託金の未返還リスクを半減することができるわけです。その代わり、当社は手数料として、年間に家賃の0.15~0.3カ月分の年間保証委託料をいただくというビジネスモデルです。
―― 半分を保証するということは、日本商業不動産保証が店子に代わって半額を納めるということですか。
豊岡 いいえ違います。もし店子に何かあって、家賃が未納だったり原状回復費が支払えなくなった時に、保証金の半分以内であれば当社が代わって支払うということです。ですから、最初の段階で当社が保証金を支払うわけではありません。
―― ということは、店子にとってはいいことづくめですが、オーナーにとっては必ずしもそうではないですね。本来入ってくる保証金が入らないことには、運用益を上げることもできません。
豊岡 経済状況がよく、空室率が低い状況ならそうかもしれません。でも、いまビルオーナーの最大の関心事は、いかにして部屋を埋めるかです。同じような物件なら、「保証金半額くん」が利用できる物件のほうが店子の負担は減りますから、それが差別化になる。あるいは、保証金を半額にすることで、月々の家賃を増やすことができるかもしれない。あるいはフリーレント期間を短縮できるかもしれない。
それにこのサービスを利用しようという店子に対しては、我々が与信審査を行いますから、オーナーにしてみれば、そのぶん負担が減ることになります。それだけ、オーナーにとってもメリットは大きいんです。オーナーの中には、本来、店子が負担すべき保証委託料を自分で負担してもいいというところもあるぐらいですから。
とはいえ、2年前に会社を立ち上げ、サービスを開始したのですが、オーナーに理解してもらうまでが大変でした。専門紙や損保会社と組んでセミナーを開き、説明して納得してもらう。そうやっているうちに実績もついてくる。そうすると、その実績をもとに大手のオーナーもこのサービス受け入れてくれる。おかげさまで、利用するケースはどんどん増えていますし、いまでは保証金が1000万円単位の物件も扱うことになりました。
―― それにしても、どうしてこうしたサービスがいままで存在しなかったのかが不思議です。豊岡さんはなぜこれを思いついたんですか。
豊岡 なぜこれまでなかったかというと、1つには時代背景もあると思います。先ほど言ったように、以前は貸し手市場でオーナーのほうが強気だった。それがいまでは完全に借り手市場です。オーナーの側が選ばれるための努力をしなければならなくなった。そしてもう1つが低金利です。金利が高ければ、保証金から得られる金利収入もバカになりませんが、いまではそれは微々たるものです。そうした条件が組み合わさってということがあると思います。
それに、このビジネスモデルは、単に保証金の半分を当社が保証するというだけではありません。店子に対して与信審査をしなければなりませんし、損害保険会社と再保険の契約もしなければなりません。そんな簡単なスキームではありません。
ではなぜ、このビジネスを思いついたかというと、この会社を設立する前、コンサルタント会社を経営していました。その時に、ある企業の財務内容を見ていたら、2000億円以上ある資産のうち、3分の1が保証金で眠っていることに気づいたのです。これを半減することができれば、数百億円を投資に回すことができる。それで、何かできないかと考えたのが最初のきっかけです。
それとは別に、あるビルのオーナーから、すでに2度、店子に逃げられたことがあり、与信業務のアウトソーシングができないかという相談を受けたこともありました。つまり、店子もオーナーも、保証金の問題ではそれぞれ困っている。それを解決するスキームがないかと考えた結果、このビジネスモデルが生まれたのです。
―― ところで、豊岡さんは大学卒業後、最初に入ったのが国際証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)です。そこから起業までの道のりを教えてください。
豊岡 もともと高校の頃から、いつかは独立したいという思いは持っていました。司馬遼太郎の『竜馬がゆく』を読んで、自分のためではなく世の中のために何かしないと存在意義がないのではと思うようになりました。
大学では国際政治を学んだのですが、その中に経済的安全保障というものがあることを知りました。だとしたら、この分野で何かできないだろうか。そう考えて、まず金融の道を選んだわけです。
ところが国際証券に入社して7カ月後に父が倒れ、家業を手伝うため退社せざるを得ませんでした。でも父が元気になったこともあり、HIS協立証券(現HS証券)に入り直し、株式公開引受業務に携わります。当時のHS証券は、できて間もないこともあり、なかなか幹事証券になることが難しかった。そこで企業にさまざまな提案をしながら、徐々に実績を残すようになり、主幹事も何社か務めています。
その主幹事を務めた1社とHS証券が合弁でコンサルティング会社を立ち上げることになり、社長に就任。その後、この会社はMBOによってHS証券から独立、現在にいたっています。この会社で、「保証金半額くん」のスキームを考えたのですが、ビジネス展開するには別会社でやるべきだと考え、2年前にフィナンシャルギャランティを設立しています。だけど、この社名だと何をする会社かわからない。下手をすると貸金業と間違えられてしまう。そこで、わかりやすいように、今年になってから日本商業不動産保証に社名変更しました。
―― 今後の目標は何ですか。
豊岡 会社としては、数年のうちに株式公開したいと考えています。しかしそれよりも、できるだけ多くの方に、眠っている保証金を活きたお金に変えていただきたい。
日本全体では預り金となっている保証金の総額は30兆円に達します。これが半減されれば、15兆円が新たな投資や雇用の確保につながります。このインパクトは大きい。
これまでは我々の営業活動は、ビルオーナーが中心でした。でもこれからは、店子にも積極的に働きかけます。移転やオフィスを拡大する時に相談してもらえれば、ビルオーナーと交渉して、このスキームを承諾してもらうことも可能です。
特に成長期のベンチャー企業は、すぐにオフィスを拡大する必要に迫られます。もしその時に保証金を半減できれば、そのぶん、人を雇うことができるし、それによって成長のスピードを上げることもできます。そういう企業にこそ、このサービスを利用してほしいですね。