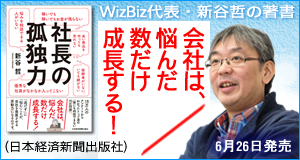製造業、サービスを問わず、企業には「◯△の生みの親」、「△◯の達人」と呼ばれる人がいる。
そうした、いわば「匠の技」の数々がこれまで日本経済の強さを支えてきたのだ。日本の競争力低下とともに、そこがいま揺らいでいるという指摘が多いからこそ、各界の匠にスポットを当ててみたいー。
2013年10月号より

ぴあが運営する映画祭
9月14日から東京・渋谷シネクイントで開催される「ぴあフィルムフェスティバル(PFF)」。今年で35回目を迎える自主制作映画の映画祭だ。作品を公募して審査会を開き、優秀な作品を上映・表彰するこのイベントは、いまやプロ監督への登竜門として定着。PFFはこれまでに『失楽園』『黒い家』の森田芳光監督(1977年入選)や、『ウォーターボーイズ』『スウィングガールズ』の矢口史靖監督(90年入選)、『フラガール』『許されざる者』の李相日監督(2000年入選)、『舟を編む』の石井裕也監督(07年入選)等々、現在も活躍する監督が100人以上も輩出している。

PFFが初めて開催されたのは1977年のこと。情報誌「ぴあ」の創刊5年目で、企業としても設立3年目、草創期からスタートしたことになる。矢内廣社長をはじめ、ぴあの創業メンバーが中央大学の映画研究会出身ということもあり、雑誌に掲載する映画情報もメジャー、マイナーの差をつけずに掲載する編集方針を採っていた。
当時、有料入場者数が激減していた映画業界は、社員としての映画監督候補の採用をやめたことから、映画監督を目指す若者は自主製作映画に打ち込んでいたのだという。しかし、その作品を発表する場がほとんどなかったのが実情だった。PFFはそんな若い感性と個性に日の目を当てるべく、「自主製作映画展」としてスタートしている。
1992年からPFFのディレクターを務める荒木啓子氏に話を聞いた。
「昔の、例えば黒澤明監督の時代は、映画監督になりたければ映画会社に就職すればよかったわけです。大島渚監督や山田洋次監督の時代もそう。ところが、いまや映画会社は映画監督を1人も雇っていません。映画監督として生きていきたいと思う若者は大勢いますが、どうしていいかわからない時代になっています。70年代当時、8ミリを使って自主製作映画を始めた人が、中学・高校・大学の映研と言われているところから、自然発生的に出てきました。そういう人たちの作品を、映画を作る力のある人、いわゆるプロデューサーや映画会社の人たちに見せていこうとしたのが、PFFの始まりです。
社長の矢内も映研出身ですので、たぶん監督をやりたかったのではないでしょうか。その時の思いを忘れないでこれまで続けていることが貴重な存在だと思います。そもそも映画祭をプライベート企業が運営しているケースはほとんどありません。スポンサーとしてお金は出しても、運営まで行っているのは世界で唯一かもしれません」
実際、PFFは直接ぴあの利益に結びつく事業ではないという。矢内社長自身、証券マンから「利益を生まないことに使うお金があるなら、それは株主に配当しなさい、ということになる」と言われ、一度はぴあの上場を見送った経緯があることをメディアで語っている。PFFは、ぴあの企業理念である「若くて新しいチャレンジをしている人を応援する」を具現化したイベントであることから、企業の経済性よりも「趣旨性」にこだわった事業だ。
「PFFには、将来がわからない若者たちに希望を与えるということに対する責任があります。PFFで賞を獲らなかったら、ぜんぜん違う人生を送った人もいるかもしれないわけです。本人の問題かもしれませんが、応援すると同時に希望を与えているわけですので、そのことに対する責任は感じていなければいけない。だからこそ、どのような映画祭にするのか、常に考えています」
人間の可能性
PFFには毎回500~600本の作品が応募されてくる。今年のPFFで上映される入賞作品は、そのうちの16本と狭き門になっている。
「そのなかから実際にプロになれるのは何人出てくるのか、という世界ですから、すべて狭き門です。将来、名監督になれるような人は、やはりオーラのようなものをある程度感じますが、本当になれるかというと、簡単ではありません。PFFに入選しても、実はそこから監督として食べられるようになるまでは非常に長い。時々、シンデレラボーイのように李監督や石井監督のように、すぐ大型の映画を撮るような人が出てくるので、成功しているように見えるかもしれませんが、ほとんどの人は長い下積みがある。
 ぴあが運営までも行う自主製作映画の祭典PFF。
ぴあが運営までも行う自主製作映画の祭典PFF。園子温監督(87年入選)はいまでこそもてはやされていますけど、食べられるようになったのはここ数年。矢口監督もグランプリを獲ってから10年間は食べられていないと思う。結局、全員フリーランスですから、やっていける人は限られています。辞めない人しか残っていけない。
映画って、別の世界を切り開くんだというビジョンを持った人しか残らないんですよ。残っている人たちは、別の価値観を世界に導入したいと思っている人たち。おのずと、生まれた時から世界観のある人たちしかクリエイターになれないと思う。自分のことしか考えてない人は、無理だと思う。それがある種の才能だと思いますね。人間の可能性、人ってすごいことができるんだという感じを、観た人が感じてくれればいいなと思うんですよね」
積み重ねた回数35回、100人を超えるプロ映画監督を世に送り出してきたPFFだが、一貫してぶれずに示しているのが、荒木氏の言う「人間の可能性」だ。
「自主映画の根本的なスピリットは『個人の力が、はじまりの第一歩だ』『個人のものづくりの意欲が、すべてのはじまりだ』ということです。人間というのは、常に何かを生み出す力があるということを、若い世代に示し続け、具体的な形である自主映画を見せる場所として、PFFは常に変わらずそこにある。時代の変遷とともに作品も変わり、上映場所も方法も変わりますが、根本的に変わることがないのは、人の表現したい意欲、何かを作りたい意欲です。個人でできることを超えて、大きく展開できる場所として、PFFは一種のメディアであるとも言えるかもしれませんね」
PFF入賞者には、PFFスカラシップへの挑戦権も与えられる。次回作の企画書を提出し、そのなかから毎年1人のオリジナル作品をPFFが企画、脚本、撮影、公開、DVD発売までトータルプロデュースし、プロ監督としてのデビューを支援する。また、早稲田大学とも提携し、最新デジタル設備を備えた早稲田大学大学院国際情報通信研究科へ、PFFアワード入選監督を推薦入学させるプログラムも、2005年から用意されている。こうしたスカラシップ制度を設けている映画祭は世界的に数少ない。
「本来なら、映画で商売している人たちがやるべきことを、肩代わりしている部分がある(笑)。ものをつくるということは、志がないとできない。商売では無理なんです」
PFFは92年、企業メセナ大賞特別賞も受賞している。矢内社長が02年にぴあの上場を決断したのも、企業メセナ活動や文化振興といった事業が、企業のあるべき姿として認められたからだと言える。
進む若者の映画館離れ
日本映画製作者連盟の統計データによると、12年の映画館への観客動員数は1億5516万人。国民1人が1回以上、映画館へ足を運んだことになる。しかし、荒木氏は若者の「映画館離れ」を指摘する。
「少なくとも私は1年に何十回と映画館に行っていますし、1年に300回くらい行く人もいるわけです。均した数字なんて、まったく意味がない。この1年間に映画館に行った人は、100人中1人か2人くらいではないでしょうか。
いまの人は映画館に行かない。むしろ映画館が嫌いという人もいます。まったく知らない人と隣同士で見たくない。見知らぬ人とシェアする訓練がまったくできていないんですね。いま地方に行くと、映画館は県庁所在地くらいにしかないところが増えています。映画が好きで、映画館に行こうと志した人以外は一生行かない。生まれてから一度も映画館に行かずに亡くなる人は、これから増えると思います。若い人たちは、映画の既存のシステムを捨てようとしており、映画館に行くことは、もう映画の前提ではないんです」
いまやDVDやブルーレイなどをレンタルして映画を観るという人も多いだろう。なかにはヘッドフォンをしてスマートフォンで映画を観るという人もいるくらいだ。
 「人間は、常に何かを生み出す力がある」と荒木氏。
「人間は、常に何かを生み出す力がある」と荒木氏。「私たちとしては、作る人がどういうサイズをイメージして作るかというのがすごく大事ですから、大きいスクリーンをイメージしてほしいんですけど。映画を観る、音楽を聴くというのは、本来は教養です。映画を観ることによって、何かを考え、何かを知ろうとする。映画をフックに何かが起きることが大事です。それが、単なる娯楽として、何も考えなくてもいいという映画ばかりが喧伝されている。これは何も考えるなという社会的な洗脳に乗っかっているとしか思えない」
それは作り手の側にも表れてきているという。映画に関する大学の学科や専門学校も増えているが、逆にPFFに応募する作品にも個性あるものが減っているのが現状だ。
「高い意識を持つということに対しての訓練がされていない。大きなイメージを描く人が潰されるという社会に急速になっている気がするんですよ。応募作を観ても、すごくセルフコントロールされている。審査員は過激な作品を期待していたりもするんです。そういう作品を入選させていないように言われることもありますが、そうではなく、応募がないんですよ。何かのきっかけで、何をやってもいいんだということを感じたら、もっとおもしろいものが出てくると思うんですけど、自己規制がすごく激しい世の中になっていると思います。
いまは情報社会で、変に情報だけは知っている。どういうことをやったら受けるかとか、どういうことをやったら効率が高いかとか、どうやれば商売に繋がるとか、小賢しいことばかり知っている。手堅くまとめてしまうんですね。予備審査員を1回やると、いまの日本の状況がすごくよくわかる。本当に怖いですよ」
とはいえ、そんななかでもPFFでは、個性と若い才能にあふれた自主製作映画が上映される。なかには、すでに海外の映画祭から招待を受けている作品もある。
「自主映画は生々しくて苦手という人もいるかもしれません。自主映画=暗いというイメージの人も多いでしょう。ところが、ぜんぜん暗くない。すごくエンタテインメントな映画が多いんです。こんなにエンタテインメントを志向して成功している映画があるということを多くの人に知ってほしい。去年の入選作品『賢い犬は吠えずに笑う』は、完全に女子高生のエンタテインメント映画。入選した時からダントツに注目されていたんですが、今年渋谷で自主公開したら、連日立ち見。ふつうの商業映画が、いま1000人のお客さんを集めるのが難しいなか、それを軽く超えて何千人も来てしまう。そういう映画があることを知ってほしいですね」(本誌・児玉智浩)